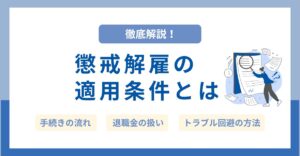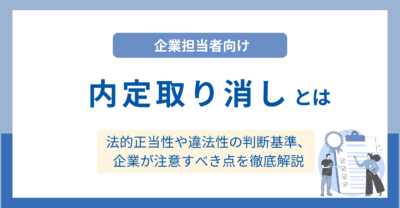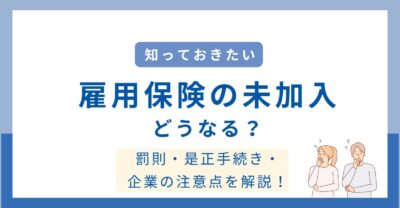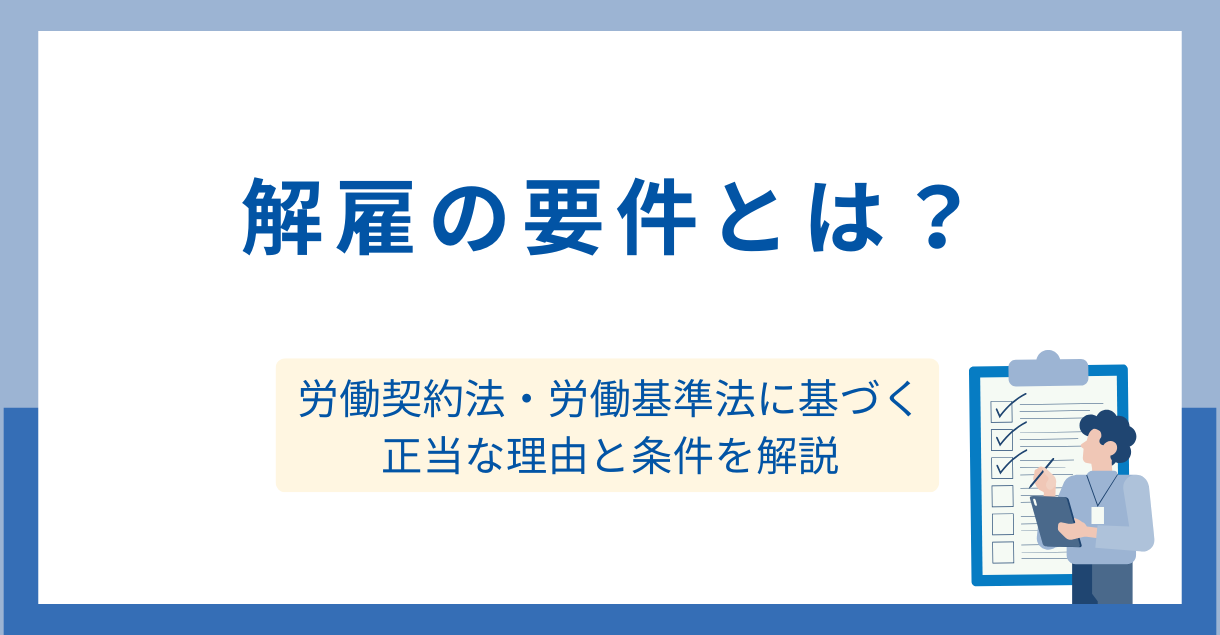
解雇の要件とは?労働契約法・労働基準法に基づく正当な理由と条件を解説
従業員を解雇することは、企業にとって極めて重い判断です。特に中小企業では、一度の対応ミスが大きなトラブルへと発展し、経営や職場環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、労働契約法・労働基準法に基づく解雇の要件や種類、企業が取るべき実務対応をわかりやすく解説しています。解雇に伴うリスクを正しく理解し、適法かつ円滑な対応に役立ててください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
解雇の基本を理解する

従業員を解雇する場合、企業は法律上の厳格なルールを守らなければなりません。
この章では、以下の3つのポイントに絞って解説します。
- 「解雇」と「退職」の違い
- 労働契約法で定められた正当な理由の必要性
- 会社都合と自己都合退職の違いについて
1 解雇とは?雇用契約終了との違い
解雇とは、使用者の一方的な意思表示によって労働契約を終了させることを指します。労働者が自ら契約を終える「退職」とは異なり、労働者の意思に反して雇用が打ち切られる点が特徴です。
労働基準法や労働契約法は、企業が恣意的に解雇を行うことを防ぐため、手続きや理由について厳格な規制を設けています。解雇は労働者の生活基盤を左右する重大な処分であり、慎重に行わなければ不当解雇とみなされる恐れがあります。
2 解雇には「正当な理由」が必要(労働契約法第16条)
日本の労働法制において、解雇は企業が自由に行えるものではありません。労働契約法第16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、かつ、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」とあります。
「解雇権濫用法理」と呼ばれる考え方で、もともとは数多くの裁判例を通じて形成され、2007年に労働契約法の制定によって条文化されました。
ここで重要なのは、解雇には 「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」 の二つが求められる点です。
例えば、
- 能力不足や勤務態度の不良が一時的で、改善の機会も与えられていない
- 経営上の必要性が乏しいにもかかわらず人員整理を強行した
といったケースでは、裁判で「解雇は無効」と判断される可能性が高まります。逆に、継続的な無断欠勤や著しい勤務成績不良、横領などの重大な背信行為など、客観的に認められる理由があり、さらに適切な手続きや説明を尽くしていれば、解雇が有効とされます。
感情的な対立や一時的な不満を根拠に解雇を行うことはできず、証拠に基づき合理的に説明できるかどうかが最も重要です。
参照元:厚生労働省「法第16条において権利濫用に該当する解雇」
3 会社都合退職と自己都合退職の違い
労働契約が終了する際には、「会社都合退職」「自己都合退職」という区分があり、この違いは従業員の雇用保険や失業給付に大きな影響を与えます。
企業はこの区分を正しく理解し、適切に説明することが求められます。
〇会社都合退職とは
会社都合退職とは、企業側の事情によって雇用契約が終了する場合を指します。典型的な例としては、解雇・倒産・経営悪化に伴う人員整理などがあります。雇用保険上は「会社都合」と扱われ、失業給付(基本手当)の給付制限期間がなくなり、所定給付日数が長くなるなど、従業員にとって有利な取り扱いがなされます。
〇自己都合退職とは
自己都合退職は、労働者本人の意思に基づいて退職するケースです。転職・家庭の事情・キャリア変更など、本人の事情による契約終了が該当します。雇用保険では「自己都合」として扱われ、失業給付(基本手当)の給付制限期間があり、給付日数も会社都合退職より短くなることが多いため、従業員にとって不利になりやすい点が特徴です。
会社都合退職か自己都合退職かの区別は、従業員の生活設計に直結する重要な要素です。企業が退職理由をあいまいにしたまま処理すると、不信感やトラブルにつながる恐れがあります。
退職の際には正しい区分を明示し、丁寧に説明を行うことで、従業員の納得感を高め、後の紛争を防ぐことができます。
参照元:雇用・労働雇用保険制度
解雇の種類とそれぞれの要件

解雇と一口に言っても、その背景や理由によっていくつかの種類に分けられます。一般的には、以下の3つがあります。
- 普通解雇
- 懲戒解雇
- 整理解雇
種類ごとに必要とされる要件や注意点が異なります。企業はそれぞれの特徴を正しく理解し、対応する必要があるので、くわしく解説します。
1 普通解雇の要件
普通解雇とは、労働者の勤務態度や能力、健康上の問題などにより雇用を継続することが難しい場合に行う解雇です。
厚生労働省が公表しているモデル就業規則には、「勤務成績が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないとき」とあり、典型例が挙げられています。
ただし、単に成績が悪い、上司との関係が良くないといった主観的な理由では足りません。労働契約法第16条が定める「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」を満たす必要があります。
さらに、労働基準法第20条に基づき「少なくとも30日前の解雇予告」または「30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払い」といった手続きを経なければなりません。
2 懲戒解雇の要件
懲戒解雇は、労働者が企業秩序を著しく乱した場合に科される最も重い処分です。懲戒解雇を行うためには、就業規則に事由を明記していることが前提とされています。
具体例
- 横領や窃盗などの重大な背信行為
- 長期の無断欠勤
- 経歴詐称
- 機密情報の漏洩
- 悪質なハラスメント行為
以上が典型的な例です。
懲戒解雇は制裁的性格が強いため、普通解雇以上に厳格な基準が適用され、手続きの公正さも強く求められます。
参照元:しっかりマスター 解雇編
3 整理解雇の要件
整理解雇とは、企業が不況や経営不振などの理由から、やむを得ず人員削減を目的に行う解雇のことを指します。
これは労働者側ではなく、あくまで使用者側の事情による解雇であるため、その有効性については厳しく判断されています。
判例上は「整理解雇の四要件」と呼ばれる判断基準が確立され、以下の点を総合的に満たしているかどうかが問われます。
- 人員削減の必要性
人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること - 解雇回避の努力
配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと - 人選の合理性
整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること - 解雇手続の妥当性
労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと
これらを満たさない整理解雇は、不当解雇として無効になるリスクが高いといえます。
引用元:労働契約の終了に関するルール
諭旨解雇・即時解雇の扱い
諭旨解雇
懲戒解雇に相当する重大な非違行為があるものの、本人に自ら退職を選ばせる形で行われる処分です。法令に明文はありませんが、多くの企業が就業規則に規定を設けています。
即時解雇(予告なしの解雇)
労働基準法第20条が原則として少なくとも30日前の解雇予告を義務付けており、例外的に労働基準監督署の「解雇予告除外認定」を受けた場合のみ有効です。
認定がなければ、解雇予告手当を支払わずに即時解雇することはできません。
参照元:労働契約の終了に関するルール
労働基準法に定められた解雇に関するルール

労働契約法は「解雇には正当な理由が必要」と定めていますが、それだけではありません。労働基準法にも、解雇に関して守らなければならない手続きや、制限が細かく定められています。
解雇が労働者の生活に直結する重大な処分であるため、企業による恣意的な対応を防ぐための仕組みです。
以下、3つのポイントを解説します。
- 解雇予告と解雇予告手当
- 就業規則に解雇事由を明記する義務
- 解雇制限
1 解雇予告と解雇予告手当(労基法20条)
労働基準法第20条には、労働者を解雇する場合は 少なくとも30日前に予告しなければならないと定めています。
もし30日前に通知できない場合は、その不足日数分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う義務があります。
例えば、10日前に解雇を通知するなら、残り20日分の平均賃金を支払う必要があります。ただし例外もあります。
労働者の重大な規律違反があった場合や、天災などで事業継続が不可能になった場合には、労働基準監督署長の認定を受けることで予告や手当が免除されることがあります。
いわゆる解雇予告除外認定です。ただし認定は厳格に判断されるため、企業が独断で即日解雇を行えば、不当解雇とされるリスクが高い点に注意が必要です。
2 就業規則に解雇事由を明記する義務(労基法89条)
労働基準法第89条には、常時10人以上の従業員がいる会社に就業規則の作成・届出を義務付けています。
その際、解雇の事由を必ず記載することが求められています。
厚生労働省の労働契約の終了に関するルールでも、解雇事由を明確に記しておくことが紛争防止に不可欠だとされています。
例えば「業務命令に繰り返し違反した場合」「勤務成績が著しく不良で改善の見込みがない場合」といった具体的な記載が必要です。
逆に「勤務態度が悪い者」といった曖昧な表現では、後に裁判で無効とされる可能性があります。
3 解雇制限(労基法19条)
労働基準法第19条は、一定の状況にある労働者を原則として解雇できないと定めています。具体的には次のケースです。
- 業務上のケガや病気で休業している間と、その後30日間
- 産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間の休業(産前産後休業)中と、その後30日間
これらの期間に解雇を行った場合、原則として無効になります。労働者の健康や母性を守るための強力な保護規定です。
ただし例外もあり、使用者が労基法第81条に定める「打切補償」を支払った場合や、事業そのものが存続できなくなった場合(天災地変など)には解雇が認められることもあります。
なお、後者の場合は労働基準監督署による解雇制限の除外認定を受ける必要があり、企業が自由に適用できるものではありません。
これらは労働者を保護すると同時に、企業にとっても解雇を適法に行うためのガイドラインです。一つ一つ確認することが、トラブルを未然に防ぐ最善策といえるでしょう。
解雇が有効とされる条件(解雇権濫用法理)

労働基準法のルールを守って予告や手続きを行っても、それだけで解雇が有効になるわけではありません。
上述しましたが、「解雇権濫用法理」という考え方があり、解雇に客観的合理性と社会通念上の相当性がなければ無効とされます。この原則は裁判例を通じて確立し、現在は労働契約法第16条に明記されています。
「客観的に合理的な理由」とは
合理的理由とは、解雇を正当化できる事実が客観的に存在することを指します。典型的な例としては以下のような場合です。
- 業務を続けられないほどの長期療養や傷病
- 能力不足・成績不良が改善されず業務に支障がある場合
- 度重なる規律違反や職務命令違反
- 経営悪化による人員削減(整理解雇)
厚生労働省の判例紹介でも、こうした事実が合理的理由の代表例として示されています。ただし「事実がある」だけでは不十分で、社会常識に照らして妥当かどうかも判断されます。
参照元:厚生労働省「確かめよう労働条件」
「社会通念上相当」と判断される基準
「社会通念上相当」とは、社会常識に照らして妥当と考えられるかどうかです。判断の基準には、
- 行為の重大性や頻度
- 指導や注意を受けた経緯
- 勤続年数や職務内容
- 他の従業員との公平性
- 異動や軽い処分など解雇以外の方法の有無
などが含まれます。例えば一度だけの軽微な違反であれば解雇は重すぎると判断される可能性があります。
参照元:労働契約の終了に関するルール
裁判例に見る有効・無効の分かれ目
解雇の有効性は、理由の合理性と社会常識に照らした妥当性の両方から判断されます。裁判例の中から、3つの事例を見てみましょう。
- 能力不足を理由とした解雇(無効)
営業成績の低さを理由に解雇した事案(セガ・エンタープライゼス事件)では、会社が十分な教育や指導を行っていなかったことが問題とされました。裁判所は「十分な改善の機会を与えずに解雇するのは合理的理由を欠く」と判断し、解雇は無効とされました。 - 規律違反を理由とした解雇(有効)
取引先の労働者に暴言を吐き、器物を損壊し、取引先の管理職にも誹謗する発言をし、また、休職処分に従わなかった労働者を企業が解雇した事案(大通事件)では、裁判所は解雇の妥当性を肯定しました。 - 日本食塩製造事件(最高裁判所判決)
最高裁(昭和50年4月25日判決)は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、かつ社会通念上相当として是認できない場合には権利濫用として無効」と明示しました。
以後、この考え方が「解雇権濫用法理」とて確立し、解雇判断の基本的な枠組みとなっています。
この3つの事例から分かることは、企業がどれだけ改善努力や公平な対応を尽くしたか、また行為が信頼関係を破壊するほど重大かどうかが、有効・無効の大きな分かれ目になるということです。
参照元:解雇|裁判例 – 確かめよう労働条件 – 厚生労働省
職場規律違反・職務懈怠による解雇|愛知県雇用労働相談センター
具体的な解雇理由の例

解雇には、実務上はどのような理由が認められるのでしょうか。この章では、代表的な5つの具体例を解説します。
1 勤務態度を理由とする解雇
勤務態度の不良は典型的な解雇理由のひとつです。厚生労働省の労働契約の終了に関するルールでは、業務命令違反や服務規律違反が、労働者側の落ち度にあたると説明されています。
ただし、一度の行為で直ちに解雇が有効になるわけではなく、通常は注意や指導を繰り返しても改善されない場合に限られます。
実際の裁判例でも、商品の欠品を生じさせたり書類の提出の遅延等を繰り返し、顧客や会社内の他部門の労働者からの苦情が続き、会社が本人にその都度指導・注意を行い報告書の提出を求めたにも係わらず従わなかったケースで解雇が有効とされました。一方、軽微な違反を理由に直ちに解雇した場合には無効とされることがあります。
企業は、指導の記録を残し、改善の機会を与えたうえで解雇に至る必要があります。
2 能力不足を理由とする解雇
「成績不良」「能力不足」もよく問題となる解雇理由です。厚生労働省の中央労働委員会「勤務成績不良者に対する解雇問題」では、勤務成績の低下が一時的または軽微であれば解雇は認められず、雇用契約の継続が困難なほど重大な場合に限られると明記されています。
また、厚生労働省のモデル就業規則では「勤務成績又は業務能率が著しく不良で向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない場合」と、例示されています。
以上のことから分かるように、能力不足を理由とする解雇では、教育・指導・配置転換といった改善措置を経ても、なお勤務継続が困難な状況であることが必要です。
3 健康上の理由による解雇
病気やケガによって業務遂行が難しくなるケースもあります。ただし、労働基準法第19条は「業務上の負傷や疾病による療養のために休業中の期間と、その後30日間」は解雇できないと定めています。また、産前産後休業中とその後30日間の解雇も原則禁止です。
したがって、健康上の理由による解雇を検討する場合は、休職制度や療養期間を就業規則に定め、その期間を経ても回復が見込めないときに、初めて解雇の可能性が生じます。
軽微な病気を理由に解雇することは許されず、社会通念上も不当と判断されるリスクが高い点に注意が必要です。
4 経営悪化による整理解雇
上述したように、経営上の理由で人員整理を行う「整理解雇」は、労働者に責任がないため、最も厳しい基準で判断されます。整理解雇が有効とされるには、「四要件」を満たす必要があります。
これらを欠いた整理解雇は、判例上も無効とされやすい傾向にあります。経営悪化を理由にする場合でも、代替策や説明責任を果たさなければ正当性は認められません。
5 懲戒解雇の典型例
懲戒解雇は、従業員にとって最も重い処分です。厚生労働省や労働局の指導でも、懲戒解雇を行うには就業規則に具体的な事由を明記しておく必要があるとされています。
典型的な事由としては以下のものが挙げられます。
- 横領・窃盗などの刑事罰に該当する行為
- 度重なる無断欠勤
- 職務命令への著しい違反
- 機密情報の漏洩や背信行為
ただし、懲戒解雇は「企業秩序を根本から破壊する重大な非違行為」でなければ有効とはされません。
軽微な非違行為を理由に懲戒解雇を行った場合、裁判で無効とされるリスクが高い点に注意が必要です。
企業は「正当な理由」を示せるように証拠を整え、社会通念に照らしても妥当といえるかを慎重に確認する必要があります。
参照元:厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」
不当解雇と判断されるケース

解雇は、正当な理由と適切な手続きを欠くと「不当解雇」とされ無効になります。この章では、注意すべき3つの典型例をご紹介します。
1 解雇理由が客観的に存在しない場合
「勤務態度が悪い」「成績が低い」といった曖昧な評価だけでの解雇は無効とされやすいです。厚生労働省の判例紹介でも、勤務態度や能力を理由に解雇する場合は、出勤記録・評価表・注意指導の履歴など客観的な証拠が必要だとされています。
裏付けのない主観的判断だけでは、合理的理由とは認められません。
2 解雇理由の後付け
解雇通知をした後で、新しい理由を追加して正当化しようとすることは「後付け」と呼ばれます。普通解雇では一定程度認められる余地もありますが、裁判所は「その時点で会社が本当に重視していた理由か」を厳しくチェックします。
特に懲戒解雇では、後から持ち出した理由はほとんど通用せず、無効と判断されるのが一般的です。
3 差別的・報復的な解雇
労働基準法第3条では、国籍・信条・社会的身分を理由とする差別的扱いを禁止しています。これに基づき、差別的な動機での解雇はすべて無効です。
また、労働組合活動や労働基準監督署への通報を理由とする「報復的解雇」も、無効とされます。例えば、均等法関連の相談や通報をした従業員を解雇することは、裁判で厳しく否定されています。
企業は、事実に基づいた合理的理由を示すとともに、差別や報復と誤解される行為を避けることが不可欠です。
参照元:解雇|裁判例 – 確かめよう労働条件 – 厚生労働省
解雇理由の通知義務と手続き

解雇を行う際には「なぜその従業員を解雇するのか」を明確に示すことが不可欠です。理由が曖昧なままでは、労働者の納得を得られないだけでなく、不当解雇と判断されてしまうリスクも高まります。
この章では、法律で定められた通知義務と、実務上の注意点を解説します。
解雇理由証明書とは(労基法22条)
労働基準法第22条は、労働者が請求したときに「解雇理由証明書」を交付する義務を使用者に課しています。
これは、解雇の理由や日付を記録した公式文書で、労働者が納得できるように説明責任を果たすためのものです。
- 労働者が請求した事項のみを記載する(勝手に別の理由を追加しない)
- 記載は具体的かつ事実に基づくこと
- 曖昧な表現や虚偽は、後の紛争で会社に不利に働く
この証明書は、労働審判や裁判での重要な証拠になるため、正確かつ誠実に作成することが大前提です。
参照元:厚生労働省「解雇理由証明書」
解雇通知書の書き方と記載内容
実務では、会社から従業員へ「解雇通知書」を交付するのが一般的です。ここで重要なのは、誰が読んでも理解できるように、具体的に書くことです。
- 解雇日を明記する
- 解雇理由を具体的に記載する
(例:「就業規則第〇条に基づき、無断欠勤〇日間」) - 根拠となる就業規則の条文を引用する
「勤務態度不良」「能力不足」といった抽象的な表現だけでは、後に争いになった際に「合理的理由が示されていない」と判断される危険があります。
後付けの理由は無効となるリスク
上述しましたが、解雇通知後に「実は別の理由もあった」と追加することは、原則として認められません。
普通解雇では、一定の補足主張が許される場合もありますが、当時会社が実際に重視していたかどうかが厳しく審査されます。懲戒解雇では、後付け理由はほぼ通用せず、無効とされるリスクが高いです。
また、解雇理由証明書や通知書に記載していない事由を後から主張すると、書面の信頼性が疑われ、企業側に不利な判断が下されやすくなります。解雇の正当性を裏付けるのは「事実に基づいた明確な理由」「法律に則った正しい手続き」です。
労働者への説明責任を果たし、後に争いになった際に不利とならないよう、解雇理由証明書や解雇通知書は具体的かつ誠実に作成することが不可欠です。
企業が解雇を進める際の実務対応

解雇は企業にとって避けがたい最終手段ですが、その対応を誤ると「不当解雇」と判断され、裁判や労働審判に発展して多大なコストを負うことになります。
解雇を検討する際には、2つに分けて考えることが大切です。
- 解雇前の事前準備(社内対応)
- トラブルが発生した時の外部対応
以下、実務上の重要なポイントを整理します。
1 解雇前の事前準備(社内対応)
①勤務態度・成績の記録を残す
「勤務態度が悪い」「成績が振るわない」といった漠然とした評価では、裁判所に正当性を認めてもらうことは困難です。遅刻・欠勤の回数、目標未達成の状況、改善指導の履歴などを客観的に記録しておくことが不可欠です。
これらの記録は、万一トラブルに発展した場合に、解雇の合理性を示す決定的な証拠となります。
②従業員への説明・改善機会の提供
解雇の前には、必ず従業員に説明を行い、改善のチャンスを与えることが求められます。口頭での注意にとどまらず、文書での指導や配置転換、教育研修といった代替措置を講じることで、「会社として最大限努力した」という姿勢を示すことができます。
これらのプロセスを経て初めて解雇に「合理的な理由」があり、「社会的に相当」と判断されやすくなります。
③社労士の活用(リスク評価と証拠整備)
社会保険労務士は、企業の労務管理をサポートする専門家です。解雇に関しては、以下のような支援が可能です。
- リスク評価:就業規則や雇用契約に照らし、解雇事由が法的に有効かどうかを事前に診断
- 証拠整理:注意指導書・勤務記録・面談記録など、証拠として有効な書類の作り方を助言
- 面談同席:従業員面談に立ち会い、第三者の視点から説明を補助
- 書面整備支援:解雇通知書や解雇理由証明書の文面について、法的に適切かどうかを確認
さらに、労働局の「あっせん制度」などを利用して問題解決を図りたい際に、特定社労士であれば代理人となることも可能です。
解雇に至る前段階から社労士を関与してもらうことで、トラブルの芽を摘み、企業のリスクを大幅に減らせます。
2 トラブルが発生した時の外部対応
①労働局のあっせん制度の活用
従業員が解雇に不服を申し立てた場合、労働局が提供する「あっせん制度」を利用できます。中立的な紛争調整委員(弁護士や社労士)が間に入り、短期間・非公開で紛争解決を図るため、訴訟に比べて企業の負担が軽減されます。
費用がかからないのもメリットですが、合意には双方の同意が必要で強制力はない点には注意が必要です。
②弁護士への相談と法的対応
さらに、労働審判や裁判に発展した場合は、弁護士の対応が不可欠です。解雇無効の主張や未払い賃金の請求に備え、通知書の文面や証拠資料を事前に弁護士に確認してもらうことが望まれます。
社労士と弁護士が連携して関与することで、紛争対応のスピードと確実性が高まります。
上記のように、二段階を意識して進めることが重要です。
社労士に早期に関与してもらうことで「予防的なリスク管理」と「実務対応の円滑化」を同時に実現でき、企業は不当解雇リスクを最小限に抑えることができます。
解雇後に想定されるリスクと対応

解雇を実行したあと、企業にはさまざまなリスクが待っています。対応を誤れば裁判に発展し、金銭的・社会的な負担が大きくなることもあります。
この章では、代表的なリスクと注意点を解説します。
労働審判・裁判に発展する場合
解雇を不服とする従業員は、裁判所の「労働審判」を申し立てることができます。労働審判は、原則3回以内の期日で迅速に解決を目指す制度で、多くの場合は解決金の支払いによる和解で終わります。
ただし、ここで決着がつかないと通常の裁判に移り、長期化・公開化によって企業の評判や社会的信用に影響が出るリスクがあります。
参照元:裁判所「労働審判手続」
解雇無効時の企業側義務(復職・賃金支払い)
裁判所が解雇を無効と判断すれば、企業は従業員を復職させなければなりません。さらに、解雇から復職までの間に支払うべきだった賃金(バックペイ)をまとめて支払う必要があります。
数か月から数年分に及ぶこともあり、企業にとって大きな負担です。実際には、復職よりも解決金を支払って雇用関係を終了させる合意に至るケースが多く見られます。
参照元:JILPT:解雇等無効判決後における復職状況等に関する調査
助成金や企業評価への影響
不当解雇が問題化すると、行政からの助成金申請で不利に扱われる場合があります。さらに、労働審判や裁判の情報は、取引先や求職者に知られることで「労務管理が不十分な会社」と評価されかねません。
採用の難化や企業イメージの低下といった副次的なダメージにも注意が必要です。
解雇後に企業が直面する主なリスクは、以下の通りです。
- 労働審判・裁判での紛争長期化
- 解雇無効時の復職・バックペイ義務
- 助成金や企業評価への悪影響
上述したように、事前に手続きを整え、専門家に相談しながら対応を進めることが、リスクを最小限に抑える鍵となります。
まとめ
解雇は、企業にとって避けられない選択となる場合もありますが、その実行には厳格な要件と手続きが求められます。
労働契約法第16条に定められた「合理的理由」と「社会通念上の相当性」を欠けば、不当解雇と判断され、企業側は復職や賃金支払いなど大きな負担を負う可能性があります。
そのため、解雇を検討する際は、勤務態度や成績などの記録を残し、従業員に改善の機会を与え、解雇理由を明確に説明することが不可欠です。
さらに、労働局のあっせん制度をはじめとした公的手続きや、社労士・弁護士といった専門家の助言を活用することで、リスクを最小限に抑えることができます。
解雇は労使双方にとって大きな影響をもたらすものです。企業は「やむを得ない事情」を正しく示せるよう準備を整え、透明性と公正さを持った対応を心がけることが、信頼できる職場づくりにつながります。
解雇の要件について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。