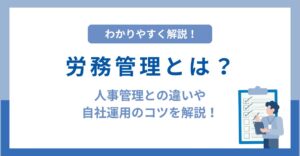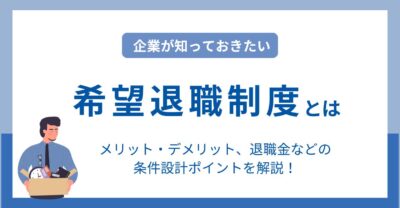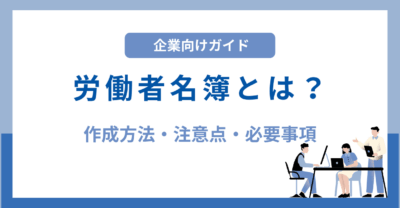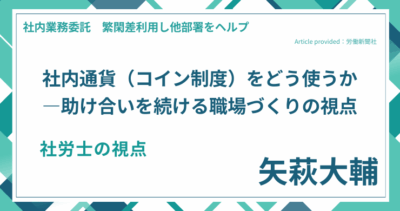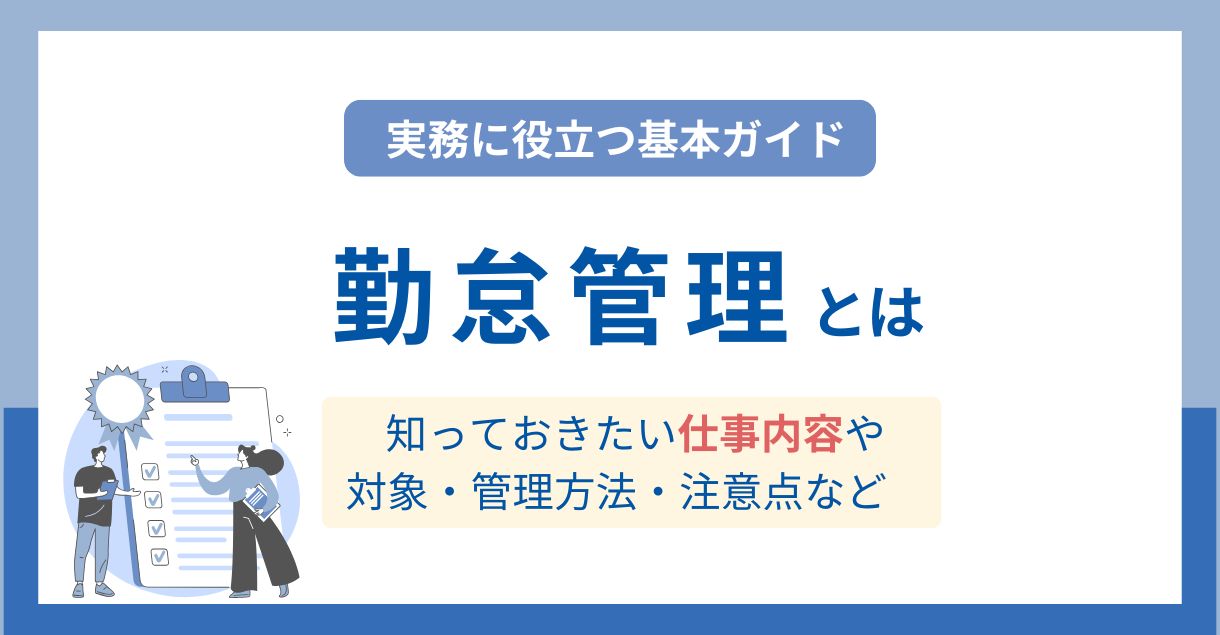
【実務に役立つ】勤怠管理とは?仕事内容から対象・管理方法まで徹底解説!
正確な勤怠管理は、労働基準法を守るうえで必須であり、給与計算や残業代の支払い、有給休暇の取得管理など、あらゆる労務管理の土台となる重要な業務です。
近年ではコンプライアンス意識の高まりや働き方改革の影響もあり、企業にとって勤怠管理の在り方が経営課題のひとつとして注目されています。
本記事では、勤怠管理の基本的な意義から仕事内容、管理対象、具体的な管理方法や注意点までを解説します。
実務担当者が知っておくべき内容をわかりやすく整理していますので、ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
勤怠管理とは?

「勤怠管理」とは、企業が労働者の出退勤時刻、労働時間、休憩、休日、有給休暇などを正確に把握・記録し、労働基準法などに基づいて適切に管理することを指します。
企業は、雇用する労働者の勤怠状況をデータとして記録し、賃金台帳などの関連書類を最低3年間(将来的に5年に延長されることが決まっています。ただし、実施時期は未定です)保存する義務があります(労働基準法第109条)。
勤怠管理の目的
勤怠管理は、単に給与計算のための労働時間の記録にとどまりません。
労働者の健康を守るための法令遵守や、働き方改革に伴うテレワークやフレックスタイム制度など多様な働き方への対応といった観点からも、企業にとって極めて重要な業務といえます。
以下、企業における勤怠管理の目的をそれぞれ解説します。
労働者の健康と安全を確保するため
適切な勤怠管理は、労働者が安心して働ける環境をつくるためにも大切な役割を果たします。
過重労働が常態化すると、心身への負荷が蓄積し、健康障害やメンタル不調、さらには過労死といった深刻な問題に発展しかねません。
出勤・退勤時間や休憩・休日をきちんと記録して管理することで、労働者の「働きすぎ」を防ぎ、安全な職場環境を維持することにつながります。
労働時間の適正な把握の義務
労働基準法では、企業に対して労働時間や休日、深夜労働などの管理と賃金台帳への記録を義務付けています。
「使用者は、労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。」
賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に虚偽の記録を行った場合は、30万円以下の罰金が科されることもあります。(労働基準法第120条)
そのため、正しい勤怠管理は企業のリスク回避にも直結します。
働き方改革による多様な働き方に対応するため
働き方改革関連法の施行により、企業には「長時間労働の是正」「柔軟な勤務制度の整備」「同一労働同一賃金の実現」など、多様な働き方に対応することが求められています。
特に、テレワークやフレックスタイム制など、働き方の選択肢が増える中で、企業は労働時間を正確に把握し、柔軟に対応しなければなりません。
仮に勤怠管理が不十分で、意図せず法令違反と判断されてしまうと、企業の信頼性やブランドイメージに大きな影響を及ぼす恐れがあります。
日々の勤怠管理を通じてコンプライアンスを強化し、労働者とのトラブルを未然に防ぐことは、今後ますます重要な企業の責務といえるでしょう。
勤怠管理で管理する主な項目

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働者ごとに労働時間を適正に把握し、以下の事項を賃金台帳に適正に記入しておくよう定められています。
- 労働日数
- 労働時間数
- 休日労働時間数
- 時間外労働時間数
- 深夜労働時間数
また、上記の労働時間数に加え、以下の記録も労働者の健康を管理するうえで重要です。
- 休憩時間の取得状況
- 年次有給休暇の取得状況・残日数
- 出勤日・欠勤日・休日出勤日
これらの情報は、正確な給与計算だけでなく、労働時間の上限規制や年5日の年次有給休暇の取得など法的義務に対応するためにも不可欠です。(参考:働き方改革|厚生労働省)
記録する項目が漏れていたり不正確だったりすると、違法な長時間労働や未払い残業などのリスクを招くため、勤怠管理には高い正確性と継続的なチェック体制が求められます。
勤怠管理の具体的な仕事内容

勤怠管理を担当する人事・労務担当者の業務は多岐にわたります。勤怠管理の具体的な仕事内容は以下のとおりです。
- 勤怠データの収集・確認
- 労働時間の集計と残業時間の把握
- シフト・勤務形態に応じた出勤記録の調整
- 有給休暇の取得状況の確認と管理
- 休暇申請や遅刻・早退などの承認フロー管理
- 集計データの作成と給与システムとの連携
- 就業規則・36協定・労働基準法などとの整合性確認
日々の業務では、収集した勤怠データに異常がないかを確認し、必要に応じて労働者や上司と連携して修正を行います。また、勤怠データが社内規定や労使協定、労働基準法に適合しているかを定期的にチェックする業務も重要です。
企業規模が大きくなるほど業務負担も増える傾向にあり、特に手作業中心の運用では、人的ミスや作業負担の増加が懸念されます。
こうした課題に対応するためには、業務プロセスを標準化し、勤怠管理システムなどのITツールを活用することが有効です。これにより、正確性を保ちながら効率的な勤怠管理体制を整えられます。
勤怠管理の対象
勤怠管理は、労働基準法によりすべての企業とすべての労働者が対象となる、基本的かつ大切な管理業務です。
ここでは、勤怠管理が必要となる企業の条件と、対象となる労働者の範囲を具体的に解説します。
対象となる企業
厚生労働省のガイドラインには、対象となる企業は「労働基準法のうち労働時間に係る規定(労働基準法第4章)が適用される全ての事業場」と明記されています。
つまり、原則として1人以上の労働者を雇用する企業すべてに、労働時間の管理義務があります。法人・個人事業主を問わず、パートやアルバイトだけを雇っている事業者も対象です。
たとえば以下のような企業も該当します。
- 小規模事業者(労働者1~5人)
- 店舗・フランチャイズ経営企業
- リモートワーク中心の企業
対象となる労働者
勤怠管理の対象となるのは、正社員だけではありません。パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など、すべての雇用形態の労働者が含まれます。
- 短時間勤務のパート・アルバイト
- 日雇いやシフト制の労働者
- フレックスタイム・裁量労働制の適用者
- テレワーク・在宅勤務の労働者
いずれも、就業実態に応じた正確な勤怠記録が求められます。
ただし、厚生労働省のガイドラインにも規定されているように、「労働基準法第41条に定める者」と「みなし労働時間制が適用される労働者」は労働時間の把握については対象外です。
たとえば以下の労働者は対象外となります。
- 管理監督者(部長・工場長など)
- 機密の事務を取り扱う者(機密文書等に従事する事務職)
- 事業場外みなし労働時間制(営業職や出張中心の職種) など
営業職などで一部に事業場外の業務が含まれる場合は、その該当時間の労働時間を把握することが困難な場合は労働時間の把握の対象外となります。
オフィス勤務など労働時間の把握が可能な部分については、通常どおりの勤怠管理が必要です。
なお、上記のような労働時間の把握義務の対象外とされている労働者であっても、働き方改革関連法により改正された労働安全衛生法により、企業には健康管理の観点から労働時間の状況を把握する義務があります。
勤怠管理に関する法令

企業が適正な勤怠管理を行ううえで、労働基準法をはじめとする関連法令の理解は欠かせません。
勤怠管理に関する法令には、以下のようなものがあります。
- 労働時間の上限(労働基準法 第32条)
原則として、1日8時間・1週40時間を超えて労働させてはいけません。 - 時間外労働の管理と36協定の締結(労働基準法 第36条)
上記の労働時間の上限を超える残業や法定休日労働をさせるには、労使協定(36協定)の締結と労働基準監督署への届出が必要です。 - 休憩時間の確保(労働基準法 第34条)
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を与えることが義務です。 - 年次有給休暇の管理(労働基準法 第39条)
年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、年5日分を確実に取得させる義務があります。
とくに人事・労務担当者は、これらの基本ルールを正しく理解し、日々の勤怠管理に反映させることが求められます。
勤怠管理の方法とは?紙・タイムカード・Excel・システム

勤怠管理はさまざまな方法で行われています。
勤怠管理には主に「紙」「Excel」「勤怠管理システム」の3つの方法があります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを理解し、自社に合った手法を選ぶことが重要です。
■紙ベースの管理:
導入コストが低く、すぐに始められる点が利点です。しかし、集計作業が手間であり、記録ミスや改ざんのリスクもあるため、人数が増えると管理が煩雑になります。また、保管スペースが必要なこと、検索が不便なこともデメリットです。
■タイムカード:
タイムレコーダーさえあればすぐに導入でき、一定の環境下では安定した管理が可能です。
一方で、打刻忘れや修正時の手続きの煩雑さ、記録の保管・検索に手間がかかるなど、紙ベースの管理と同様に管理上の負担が大きいのが課題です。
■Excelによる管理:
自由度が高く、多くの企業で利用されています。関数を使えばある程度の自動化が可能ですが、ファイルの共有・管理に限界があり、属人化やヒューマンエラーが起こりやすいのが難点です。
■勤怠管理システム:
収集した勤怠データをグラフや一覧で可視化でき、労働者ごとの労働傾向や残業状況を分析できます。リアルタイムでの打刻状況を把握できるため、過重労働の早期発見にもつながります。
また、膨大なデータの中から必要な情報をすぐに検索できる点も、紙やExcelにはない大きなメリットです。
最近は、法改正やリモートワークに対応しやすいクラウド型勤怠管理システムが注目されています。
最適な勤怠管理の方法を見直す際には、自社の勤務形態や労働者数、将来的な拡張性、他システムとの連携性などを考慮して検討しましょう。
勤怠管理の注意点

近年では、企業が雇用する労働者の働き方が多様化しており、それに伴って勤怠管理も働き方に合った対応が求められます。以下のようなケースに注意が必要です。
扶養控除内で働く労働者の場合
年収が一定額を超えると、扶養から外れてしまい、配偶者控除が受けられなくなるなどの税制上のデメリットが生じます。そのため、扶養控除内で働くことを希望する労働者に対しては、労働時間や給与の月ごとのバランスを把握・管理する必要があります。
アルバイト・パートの場合
シフト制や変則勤務が多いアルバイトやパート労働者の勤怠管理では、急なシフト変更や勤務日数のばらつきに対応する柔軟性が必要です。また、短時間勤務であっても、休憩の付与や残業手当の対象になる場合があります。管理ルールを明確にし、日々の運用で徹底することがトラブル防止につながります。
テレワーク・フレックスタイム制の場合
場所や時間にとらわれない働き方では、始業・終業の打刻や業務報告のルールが曖昧になりがちです。
システム上での打刻やログイン履歴を活用することで、客観的な労働時間の把握が可能になります。
企業は労働者と合意したルールを明文化し、社内制度として定着させることが求められます。
まとめ|勤怠管理は企業と労働者を守る重要な業務です
本記事では、勤怠管理の基本的な意義から仕事内容、対象となる企業や労働者、具体的な管理項目や方法、注意点、関連法令まで、実務に必要なポイントを整理して解説しました。
勤怠管理の整備は、正確な給与計算や労働時間管理を可能にし、コンプライアンスや労働者の健康確保にも直結します。
しかし、法改正や勤務形態の多様化に伴い、制度や運用の複雑さが増している今、企業が独自にすべてを正確に対応することは簡単ではありません。
そのため、勤怠管理の見直しや制度設計を進める際には、労務管理の専門家である社労士との連携が安心です。
勤怠管理について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めたうえで依頼しましょう。