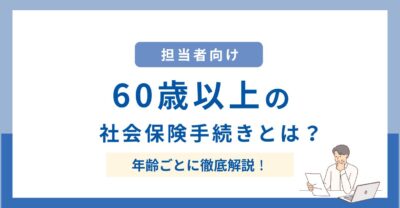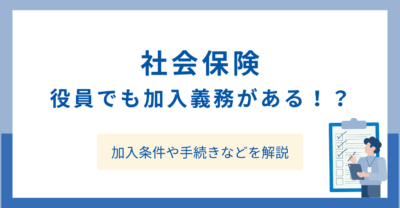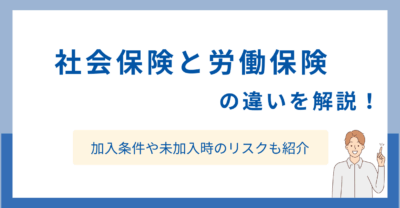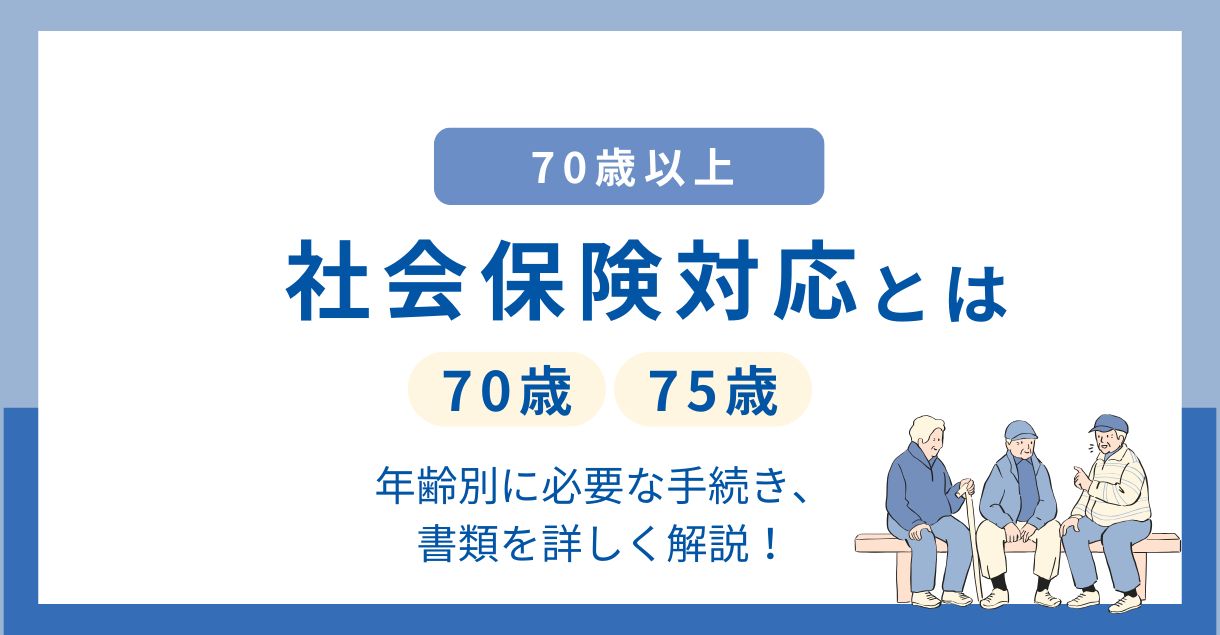
【年齢別】70歳以上の社会保険対応とは?必要な手続き・書類を詳しく解説!
少子高齢化が進むなか、政府は企業に対して「70歳までの就業機会確保」を努力義務とし、高年齢者が活躍できる環境づくりを後押ししてきました。
実際に、70歳を超えても働く意欲を持つ人は増えており、現場で活躍する高年齢者の姿も珍しくありません。
こうした背景を踏まえ、企業には高年齢従業員を受け入れる体制整備だけでなく、70歳以上の社会保険制度についても正しく理解し、適切に対応することが求められます。
本記事では、70歳以上の従業員を雇用する際に必要な社会保険、手続きの流れ、75歳到達時の対応、企業が押さえておくべき実務ポイントまでをわかりやすく解説します。
年齢によって適用が変わる社会保険制度を正しく理解することは、企業の法令遵守に加え、高年齢従業員が安心して働ける環境づくりにも重要な要素です。
ぜひ本記事を最後までご覧いただき、実務にご活用ください。
※本記事では社会保険のうち、健康保険、厚生年金保険、介護保険について解説しております。
※従業員を新たに雇用する際のみならず、継続して雇用する従業員が70歳を超える場合や、常勤の取締役等として働く場合にも同様の考え方となりますので、ご参照ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
社会保険の加入対象となる年齢は?

社会保険制度は、それぞれ対象年齢の上限が異なります。企業が高年齢従業員を雇用する際には、各制度の対象年齢を正しく理解しておくことが重要です。
以下、健康保険・厚生年金保険・介護保険の適用事業所における、それぞれの対象年齢について解説します。
健康保険:75歳未満
健康保険は、一定の要件に該当する75歳未満の方が対象です。75歳になると後期高齢者医療制度へ移行し、健康保険の被保険者資格は喪失します。
厚生年金保険:70歳未満
厚生年金保険は、一定の要件に該当する70歳未満が被保険者の対象です。企業に勤めていても、70歳に達した時点で資格を喪失し、それ以降は保険料の納付も不要になります。
介護保険:40歳以上
介護保険は、40歳以上の被保険者が、一定の要介護状態や要支援状態になった場合に、介護サービスを受けられる制度です。40歳以上65歳未満は第2号被保険者となり、会社が保険料を徴収します。65歳以上になると第1号被保険者となり、市町村が保険料を徴収します。
70歳以上の従業員に必要な社会保険の手続き

70歳以上の社会保険手続きは、在籍中の従業員が70歳を迎える場合、新たに70歳以上の方を雇用する場合、または退職する場合で異なる手続きが発生します。
以下、それぞれの場面ごとに必要な手続きを解説します。
1.従業員が70歳に到達した場合
従業員が70歳を迎えると、厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。これに伴い、70歳以降の報酬状況に応じて「70歳到達届」の提出が必要となる場合があります。
| 「70歳到達届」とは: 「厚生年金保険の被保険者資格喪失届」と「70歳以上被用者該当届」が一体となった様式です。(以下、「70歳到達届」と総称して解説します。) |
【70歳到達届の提出が必要な場合】
70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる場合、管轄の事務センターまたは年金事務所へ70歳到達届の提出が必要です。

出典:70歳到達届 記入例|日本年金機構
提出期限は、70歳到達日(誕生日の前日)から5日以内とされており、遅延すると保険料計算に影響が出る可能性があります。
70歳到達届の届出用紙は、被保険者が70歳に到達する月の前月に、日本年金機構から該当事業所の事業主宛に事前送付されます。
万が一、紛失などで届出用紙が手元にない場合は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。
【届出が不要な場合】
70歳到達日時点の標準報酬月額相当額とそれまでの標準報酬月額に変更がなければ、事業主からの届出は不要です。
報酬月額については、日本年金機構の70歳到達時の被保険者等における届出に関するページからご参考いただけます。
2.新たに70歳以上の従業員を雇い入れる場合
70歳以上の方を新たに採用する場合、健康保険や厚生年金に関する次の届出が必要です。
- 健康保険被保険者資格取得届
- 厚生年金保険70歳以上被用者該当届
通常の資格取得届と同様の書式ですが、⑩備考欄の1の「70歳以上被用者該当」に〇をつけるのことが記載上の注意点です。
(参考:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届|日本年金機構)

出典:従業員を採用したとき|日本年金機構
75歳未満は健康保険の適用対象となるため、健康保険への加入手続きが必要です。原則として被保険者資格の取得日は、雇入日と同日になります。
記入方法は、日本年金機構の記入例をご参考ください。
70歳以上の常勤役員・被用者は厚生年金の被保険者にはなりませんが、在職老齢年金の調整の対象となるため届出が必要です。
| 在職老齢年金とは: 老齢厚生年金を受給できる60歳以上の方が厚生年金の適用事業所で働き、一定以上の賃金を受け取っている場合に適用される制度です。年金と給与・賞与の合計額(総報酬月額相当額)に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となることがあります。(参考:在職老齢年金の計算方法|日本年金機構) |
3.70歳以上の従業員が退職した場合
70歳以上の従業員が退職する際には、以下の手続きが必要となります。
- 「70歳以上被用者不該当届」の提出
この届出は、一般の従業員が退職時に提出する「被保険者資格喪失届」と同じ様式を使用します。通常の記入内容に加えて、様式内の下部にある「70歳以上被用者不該当」の項目にチェックを入れ、「不該当年月日」には退職日当日を記入します。 - 健康保険証・高齢受給者証などの返却
退職に伴い、すでに交付されているものに限り回収・返却が必要です。
【回収が必要なもの】
高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額 適用・標準負担額減額認定証
届出の提出は、退職日の翌日から起算して5日以内と定められています。
75歳以上の社会保険の手続き
従業員が75歳以上になると、保険者が切り替わるため、注意が必要です。ここでは、75歳以上の従業員に必要な社会保険の手続きを解説します。
健康保険被保険者資格喪失届の提出
すべての国民は75歳に達した時点で、それまで加入していた健康保険等の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ移行します。
後期高齢者医療制度への移行は自動的に行われますが、企業側は、従業員が75歳になった際に「健康保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。
喪失年月日は誕生日当日です。
提出期限は75歳の誕生日から5日以内です。健康保険証・高齢受給者証の回収と返却を行いましょう。
被扶養者がいる場合の手続き
従業員が75歳に達して健康保険の被保険者資格を喪失すると、その方に扶養されていた被扶養者も、健康保険の被扶養者資格を失います。
被扶養者が75歳未満である場合には、以下のいずれかの対応が必要です。
- 他の家族の扶養に入る
- 国民健康保険などへ自身で加入する
被扶養者が国民健康保険に加入する場合には、手続きの際に「資格喪失証明書」が求められます。
企業側が注意すべきポイント

70歳以上の従業員に関する社会保険の手続きを扱う際は、以下のポイントを意識することで、実務トラブルを回避できます。
年齢ごとの制度切替を正確に把握すること
社会保険制度は、健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満といったように、制度ごとに適用年齢が異なります。
適用対象の見誤りは、保険料の誤徴収や未加入トラブルを招く可能性があります。
対象年齢の基準と適用の有無を正確に把握し、従業員ごとに適切な保険制度を適用しましょう。
各種届出の提出期限を厳守する
「70歳到達届」や「70歳以上被用者不該当届」などの提出期限は、原則として5日以内とされています。
提出が遅れると、厚生年金保険料が継続して徴収されるケースや、年金の支給額に影響するケースなどもあります。
期限を守って正確に届出を行いましょう。
まとめ|70歳以上の社会保険の手続きに備えよう
本記事では、70歳以上の従業員に対する社会保険制度の取り扱いや、企業が対応すべき手続きについて解説しました。
各制度には年齢に応じた適用範囲があり、70歳・75歳を境に健康保険や厚生年金の資格が変わるほか、それに伴う届出義務も多岐にわたります。
従業員の高齢化が進むなか、こうした制度の正しい理解と実務への反映は、法令遵守はもちろん、従業員との信頼関係を築くうえでも不可欠です。
ただし、手続き方法は複雑かつ更新される可能性もあるため、必要に応じて専門家のサポートを受けることも検討してみてはいかがでしょうか。
社会保険制度や労務対応について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。