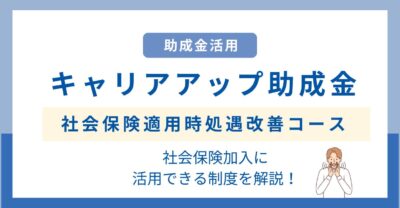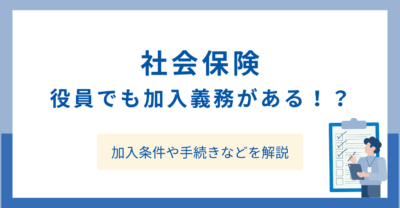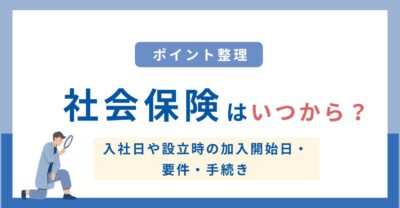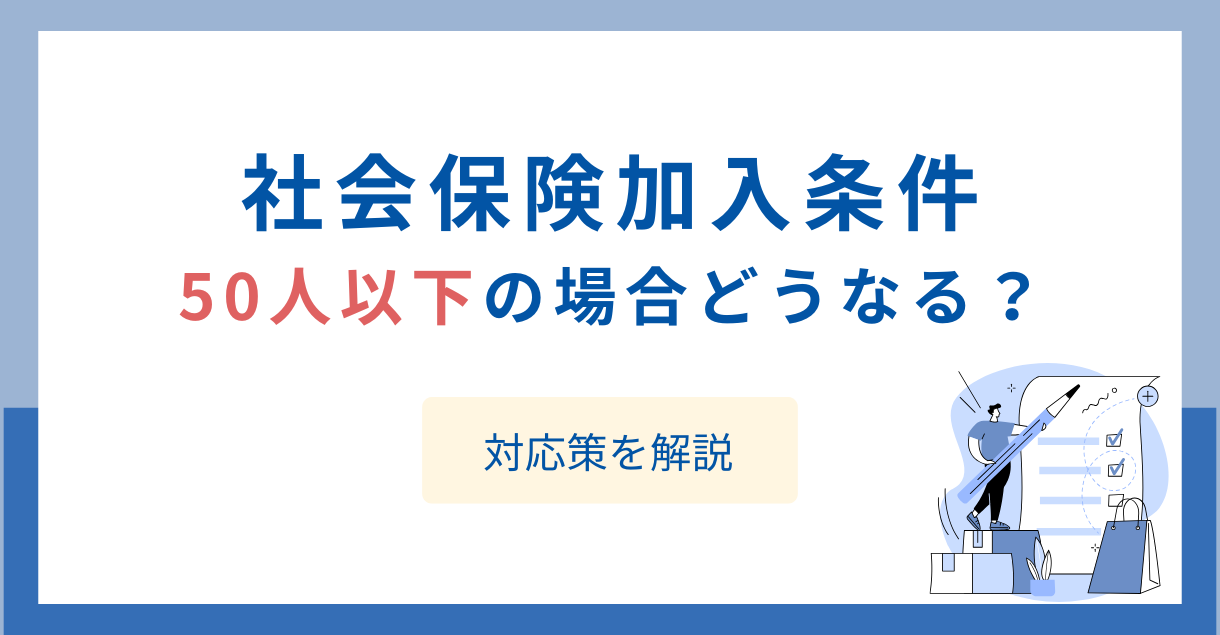
社会保険加入条件は50人以下の場合どうなる?対応策を解説
2024年10月から、社会保険の適用範囲が拡大され、従業員51人以上の企業において、一定の条件を満たす短時間労働者も新たに社会保険の加入対象となりました。しかし、従業員50人以下の企業はこの適用拡大の対象外です。ただし、法人であれば従業員数にかかわらず社会保険への加入義務があるため、注意が必要です。さらに、個人事業主であっても、業種によって従業員が5人以上いれば加入義務があります。
2025年6月に成立した改正年金法により、2027年10月以降、従業員50人以下の企業にも段階的に適用拡大を進めていくことが確定しており、今後の制度変更の動向に注目が集まっています。将来的な制度変更も踏まえ、最新の情報を確認しながら、自社に必要な対応を検討しておくと安心です。本記事では、従業員50人以下の中小企業が押さえておくべき社会保険の加入条件や、2024年の適用拡大のポイント、今後の対応策について詳しく解説します。
社会保険については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:社会保険とは?概要から保険料の計算方法まで徹底解説!)
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
社会保険の加入条件
企業に社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務が発生するかどうかは、企業の形態や業種、従業員数などによって異なります。また、従業員側も一定の条件を満たすことで、社会保険の加入対象となります。ここでは、企業と従業員の社会保険の加入条件について、それぞれ見ていきましょう。
企業における社会保険の加入条件
企業における社会保険の加入条件は以下です。
社会保険の加入条件
- すべての法人事業所(事業主のみの場合を含む)
- 常時、従業員を5人以上雇用している個人事業所(一部業種を除く)
まず、すべての法人事業所は、従業員の人数にかかわらず、社会保険への加入義務があります。これは、事業主のみの企業(従業員がいない企業)も例外ではありません。
一方、個人事業所については、常時5人以上の従業員を雇用している場合に加入義務が発生します。ただし、対象となるのは製造業や建設業などの業種であり、農業や林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業、政治・経済・文化団体、宗教団体など、一部業種は法令で適用除外とされています。
従業員の社会保険の加入条件
従業員の社会保険の加入条件は以下のとおりです。
社会保険の加入条件
- 正社員などフルタイムの従業員
- 週の所定労働時間および月の所定労働日数がフルタイムの従業員の4分の3以上の従業員
正社員やそれに相当するフルタイムの従業員は、社会保険の加入対象です。さらに、フルタイムには満たないものの、週の所定労働時間および月の所定労働日数が「正社員の4分の3以上」あるパート・アルバイト従業員も、同様に加入対象となります。
出典:日本年金機構「厚生年金保険・健康保険制度のご案内」
2024年10月からの社会保険の適用拡大とは?
社会保険の適用拡大とは、フルタイムの従業員や、所定労働時間・日数がフルタイムの4分の3以上のパート・アルバイトが対象だった社会保険の加入範囲を、より短時間で働くパート・アルバイトにも広げる取り組みです。これにより、従業員51人以上の企業において一定の条件を満たす短時間労働者は、正社員の4分の3未満の勤務時間であっても、社会保険への加入が必要となります。
これは、以前から段階的に進められてきた制度改革の一環であり、企業規模に応じて適用対象が拡大されてきました。具体的には、2016年に従業員数501人以上の企業、2022年に101人以上の企業が適用対象となり、2024年10月からは従業員数51人以上の企業も新たに対象に加わりました。
企業の従業員規模に応じた適用拡大の流れ
- 2016年10月~ 従業員501人以上の企業
- 2022年10月~ 従業員101人以上の企業
- 2024年10月~ 従業員51人以上の企業
ここからは、従業員数のカウントの仕方やタイミング、短時間労働者が社会保険に加入する具体的な条件について解説します。
従業員数のカウントの仕方とタイミング
社会保険の適用拡大における「従業員数」は、企業に在籍している社員数ではなく、「厚生年金保険の被保険者数」です。被保険者数としてカウントされるのは、フルタイムの従業員と、所定労働時間・日数が正社員の4分の3以上のパート・アルバイトです。例えば、正社員30人と週30時間勤務のパート・アルバイト25人なら、合計55人となり、適用拡大の対象になります。
また、カウントのタイミングにも注意が必要です。一時的に51人を超えても即対象とはならず、「直近12ヶ月のうち6ヶ月以上で被保険者が51人以上」であることが条件です。近年は人材が流動的な企業も増えているため、企業の人事・労務担当者は、従業員の就業実態を正しく把握することが大切です。
短時間労働者の社会保険の加入条件
先述したとおり、2024年10月から、従業員数51人以上の企業に勤務する短時間労働者も、一定の条件を満たす場合には、社会保険への加入が義務付けられます。具体的には、以下4つの条件をすべて満たすことが必要です。
社会保険の加入条件
- 週の所定労働時間が20時間以上ある
- 月額の賃金が8.8万円以上ある
- 雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれる
- 学生ではない(夜間学生や通信制学生は除く)
まず、週の所定労働時間が20時間以上あることが求められます。ここでの「所定労働時間」とは、雇用契約上の勤務時間を指し、臨時の残業や休日出勤などは含まれません。
次に、月額賃金が8.8万円以上であることが条件です。例えば、時給1,200円で1日5時間・週5日勤務している場合、この基準を満たす計算になります。
さらに、雇用期間が2ヵ月を超えると見込まれることも条件のひとつです。たとえ2ヵ月以内の契約であっても、当初から更新が予定されている場合や、実際に長期的な勤務が見込まれる場合には、加入対象となります。最後に、学生でないことも条件ですが、夜間学生や通信制の学生などは、加入対象となります。
従業員数51人以上の企業の場合、これら4つの条件をすべて満たす短時間労働者は、正社員の4分の3未満の勤務時間であっても、社会保険への加入が必要です。
出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
社会保険の加入条件や適用拡大については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:社会保険の加入義務とは?パートの適用拡大と企業の対応ポイントを解説)
従業員50人以下の企業の社会保険加入条件はどうなる?
2024年10月の社会保険適用拡大では、従業員数51人以上の企業が新たに対象となりましたが、従業員数が50人以下の企業は、今回の拡大の対象外です。ここでは、現在の従業員50人以下の企業における社会保険の適用条件について解説します。
現行の社会保険の加入条件が適用される
従業員50人以下の企業については、2024年10月からの社会保険の適用拡大の対象ではないため、これまでと同じ加入ルールが適用されます。したがって、従業員50人以下の企業の短時間労働者が社会保険に加入するかは、引き続き「正社員の4分の3以上の勤務かどうか」で判断されます。例えば、正社員の週の所定労働時間が40時間であれば、週30時間以上勤務していれば加入対象です。
なお、正社員の所定労働時間は企業ごとに異なるため、自社の基準をもとに判断することが大切です。また、契約上の労働時間が短くても、実態として基準を超えていれば加入義務が生じる可能性があるため注意しましょう。
労使合意のもと短時間労働者が社会保険に加入できることがある
従業員数50人以下の企業でも、労使合意のもと日本年金機構へ申し出て「任意特定適用事業所」として承認されれば、一定の短時間労働者を社会保険に加入させることが可能です。
この制度を活用するには、厚生年金保険の被保険者の過半数で組織された労働組合の同意が求められます。労働組合がない場合は、被保険者の過半数によって選出された従業員代表の同意、または被保険者全員の過半数の同意が必要です。
複数の事業所がある場合は注意する
複数の事業所がある場合、事業主が同一であれば従業員数は合算して判断されます。例えば、本社に40人、2つの支社に10人ずついれば合計60人です。このようなケースでは、従業員51人以上の企業とみなされ、先に紹介した条件にあてはまれば、短時間労働者の社会保険加入が必要になる可能性があります。判断基準は、各拠点ではなく、企業全体の厚生年金保険の被保険者数となるため注意が必要です。
将来的には従業員50人以下の企業にも適用拡大される可能性がある
現在、短時間労働者への社会保険の適用拡大の対象は「従業員51人以上の企業」とされていますが、2025年6月に成立した改正年金法により、2027年10月以降、段階的に拡大適用が進み、2035年10月には、企業規模にかかわらず、すべての労働者が加入できる制度が実現します。
具体的には、2027年10月に従業員36人以上の企業を対象とし、2029年には従業員21人以上、2032年には従業員11人以上へと段階的に拡大され、2035年10月には企業規模による制限は完全に撤廃されることとなります。
制度改正が進むことにより、保険料の負担や人員体制への影響も考えられるため、従業員50人以下の企業でも、今後の動向を踏まえつつ、必要に応じて準備を進めておくとよいでしょう。
税制・社会保険の制度改正については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:【2025年最新】“パート扶養がなくなる”は誤解?年収の壁一覧とポイント整理)
社会保険の加入について社労士に相談する
日本最大級の社労士検索サイト「社労士ナビ」は地域、得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
企業と従業員が社会保険に加入するメリット
社会保険は企業・従業員の双方にとって多くの利点がある制度です。ここでは、それぞれの立場から見た具体的なメリットについて解説します。
企業のメリット
企業にとって、社会保険への加入は、法令遵守の姿勢を示し、社会的信用を高める上で不可欠です。企業の信頼性を支える基盤ともいえるでしょう。
また、社会保険が整備されている企業は、求職者から「安心して働ける職場」として選ばれやすく、人材の確保・定着につながります。さらに、将来への備えがあり働きやすい環境が整うことで、従業員のモチベーションや生産性の向上も期待できます。
従業員のメリット
社会保険に加入することは、従業員にとって将来の生活保障を得られるという点で、重要なメリットがあります。健康保険では、医療費の自己負担が軽減されるほか、病気やケガで働けない場合の傷病手当金や出産時の給付などが受けられ、国民健康保険に比べて保障が手厚いことが特長です。また、厚生年金保険では、老後の年金額が増えるだけでなく、心身に障害が生じた場合などにも公的保障が用意されています。
社会保険に加入するメリットについては、以下の記事をご覧ください。
(関連記事:社会保険に加入するメリットとデメリットを解説!加入対象や条件も紹介 )
企業が社会保険に加入しない場合のリスク
企業が法令にもとづき社会保険の加入義務を果たさない場合、経営上さまざまなリスクを負うことになります。
例えば、社会保険の加入義務があるにもかかわらず未加入の状態が続くと、年金事務所の調査・指導対象となり、過去2年分の保険料を請求されることもあります。また、採用や人材定着にも悪影響を及ぼし、「福利厚生が不十分な企業」と見なされるリスクもあります。優秀な人材の確保が難しくなるだけでなく、在籍中の従業員が安心して働き続けられない環境になる恐れもあるでしょう。
企業の信頼と健全な成長を守るためにも、制度にもとづき社会保険の加入義務を果たすことは重要です。
社会保険の適用拡大に備えて従業員50人以下の企業ができる準備
現時点では、従業員50人以下の企業が適用拡大の対象となることは確定していません。しかし政府は今後、段階的に対象を広げていく方針を示しています。対象外の企業も、早めに備えることがリスク回避につながるでしょう。
まず検討すべきは、保険料負担に備えたコストシミュレーションです。加入対象者が増えた場合の人件費の見通しを立てておくことで、財務への影響を事前に把握できます。また、「106万円の壁」や「130万円の壁」といった収入基準にも注意が必要です。制度変更に備えた給与体系の見直しも検討すると望ましいでしょう。その上で、制度の詳細が発表された際にスムーズに対応できるよう、雇用状況や人件費などの現状を整理しておくことが重要です。
社会保険の加入に関する疑問は社労士に相談を
社会保険制度は、法的義務にとどまらず、企業の人材戦略や職場環境づくりにも影響を与える重要な仕組みです。特に今後、従業員50人以下の企業にも適用が広がる可能性が議論されているため、自社への影響を見据えて、情報収集や検討を進めておくと安心です。その際は、制度に詳しい社労士への相談も視野に入れておくことで、より的確な対応が可能となるでしょう。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この日本最大級の社労士検索サイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。