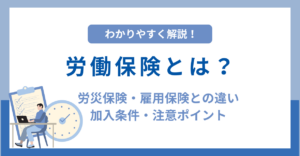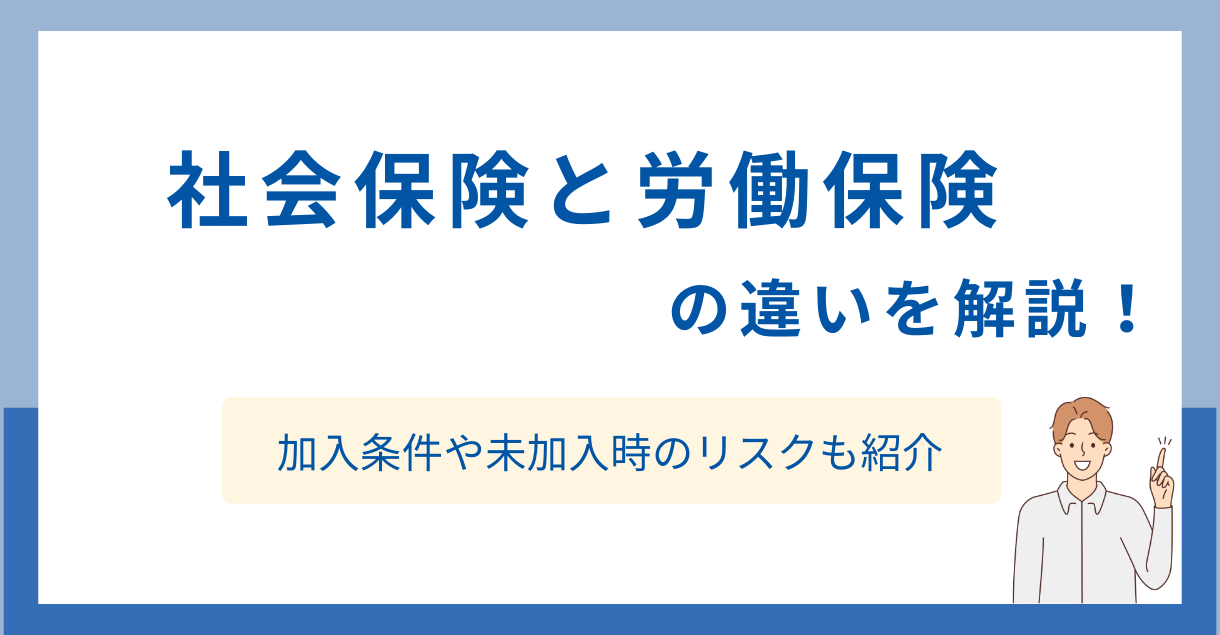
社会保険と労働保険の違いを解説!加入条件や未加入時のリスクも紹介
企業および従業員が加入する社会保険は、以下の5つの制度で構成されています。
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 労災保険
- 雇用保険
このうち、狭義の意味で、健康保険・介護保険・厚生年金保険の3つを「社会保険」、雇用保険・労災保険を「労働保険」と区別します。
社会保険は主に「医療・年金」などを保障する制度であり、労働保険は「労働災害」や「失業」など、労働に起因するリスクをカバーする制度です。
本記事では、社会保険と労働保険の違いについて解説するとともに、保険の内容や加入条件についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
社会保険と労働保険の違い
「社会保険」と「労働保険」はいずれも欠かすことのできない重要な保険制度ですが、それぞれの目的や適用範囲には明確な違いがあります。
ここでは、社会保険と労働保険それぞれの概要を整理し、その違いについて解説します。
社会保険とは
社会保険とは、健康保険、介護保険、厚生年金保険の3つを合わせた総称です。
健康保険は、業務外の病気やケガ、出産、死亡の際に、必要な医療や給付を受けられる制度です。
介護保険は、65歳以上の方が、要介護状態または要支援状態になり、訪問介護などの介護サービスを利用した場合に、サービスにかかった費用の一部が保障される制度です。40~64歳の方は、がんや関節リウマチなど、一定の特定疾病にかかった場合に保障されます。
厚生年金保険は、老後の年金以外にも、ケガや病気で障害が残ったときの障害年金、遺族に支給される遺族年金などの種類があります。
社会保険制度について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
社会保険とは?概要から保険料の計算方法まで徹底解説!
労働保険とは
労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを合わせた総称です。
労災保険は、従業員が仕事中や通勤中にケガをしたときなどに治療費や休業補償などを受けられる制度です。雇用保険は、失業中や育児・介護で休職する際などに給付を受けられる制度で、再就職支援なども含まれます。
労働保険については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
労働保険とは?労災保険・雇用保険との違いから加入条件をわかりやすく解説!
社会保険と労働保険の各制度の内容
企業で加入する社会保険と労働保険について、それぞれ保険の種類ごとに解説します。
- 健康保険
- 介護保険
- 厚生年金保険
- 労働者災害補償保険(労災保険)
- 雇用保険
保険制度の内容に加えて、事業主が保険料を支払う期日についても紹介します。
健康保険
健康保険は、業務外での病気やケガ、出産、死亡時に医療費や手当金などの給付を行う制度です。通院のみで済むような療養以外に、出産や亡くなったときも所定の保険給付が行われます。
健康保険の保険料は、被保険者と企業が折半しますが、企業がまとめて支払います。
なお、当月分の健康保険料の支払期日は翌月末までとなるため、支払いが滞ることのないよう注意が必要です。被保険者が負担する健康保険料は、原則翌月の給与から差し引きます。
介護保険
介護保険は、40歳以上の方が対象となる保険制度です。疾病やケガなどにより介助が必要となった際に、介護サービスを受けるための保険となります。
企業で社会保険に加入する従業員の場合、40歳になると同時に給与から天引きします。原則として40歳未満の方は介護保険の被保険者ではないため、介護保険料の支払い義務はありません。
介護保険料の徴収は、健康保険と同じく原則として翌月の給与から差し引きます。保険料は、健康保険と同じく企業と折半です。また、企業が保険料を支払う期日も健康保険と同じく、当月分を翌月末までとされています。
厚生年金保険
厚生年金保険は、報酬に応じて計算された保険料を納めた期間に応じて、将来的に受け取れる年金を、国民年金に上乗せして受け取れる公的年金制度のひとつです。
被保険者である従業員が一定の年齢に達したときに、老齢厚生年金が給付されます。また、障がい者になったときには障害厚生年金、亡くなったときには遺族が遺族厚生年金として、給付を受けられます。健康保険や介護保険と同じく、当月分を翌月末までに支払い、給与から控除しましょう。
労働者災害補償保険(労災保険)
労災保険は、従業員が業務中や通勤中にケガをした場合などに補償を受けられる制度です。治療費や休業中の所得補償、障害を負った際の年金・一時金、死亡時の遺族補償などが給付されます。
労災保険の保険料は、全額を企業が負担し、従業員の給与から控除することはできません。なお、労災保険率は業種により異なるため、厚生労働省の「労災保険率表」をご確認ください。保険料は、年度ごとに概算・確定申告で納付します。また、保険料が一定額を超える場合などには、分割納付制度が利用できるケースもあります。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合などに一定の給付を受けられる制度です。他にも、教育訓練を受講した場合や高年齢者が雇用を継続される場合、育児休業をする場合、介護休業をする場合にも給付が受けられます。
各種助成金の原資としても使用されています。
雇用保険料は、企業と従業員で負担します。なお、雇用保険料率は業種により異なるため、厚生労働省「雇用保険料率について」をご確認ください。
また、雇用保険を含む労働保険の保険料は、6月1日~7月10日の間に概算で納付し、翌年度の6月1日~7月10日の間に確定申告した上で精算するため、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告しなければなりません。
企業の社会保険と労働保険の加入条件
企業が社会保険や労働保険に加入するかどうかは、事業の形態(法人・個人)、業種、雇用している人数や労働者の有無によって異なります。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働者を1人でも雇用していれば、法人・個人問わず原則として加入が必要です。ただし、雇用保険の加入要件に該当する従業員がいない場合(1週間の所定労働時間が20時間未満のパート・アルバイトしかいない場合など)や、役員のみで構成されている法人、労働者を雇っていない個人事業主は対象外となります。
一方、社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人であれば従業員数にかかわらず原則すべての企業に加入義務があります。個人事業主の場合は、従業員数や業種によって取り扱いがわかれます。
例えば、製造業や卸売業などの「適用業種」に該当し、常時5人以上の従業員を雇用している場合は強制加入となります。ただし、飲食業、理美容業、農林漁業などの「非適用業種」では、同じ条件でも加入義務はありません。
制度の詳細や最新の加入条件については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:労働保険とは?労災保険・雇用保険との違いから加入条件をわかりやすく解説!)
(関連記事:社会保険とは?概要から保険料の計算方法まで徹底解説!)
社会保険と労働保険に未加入の場合のリスク
強制適用事業所にもかかわらず、社会保険や労働保険に加入していない場合は、法令違反のリスクがあります。未加入が発覚した際は、企業(事業主)に以下のような罰則や問題が生じる可能性があります。
- 6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金
- 過去2年間分の保険料徴収
- 延滞金の追加徴収
- 従業員負担分の保険料支払い
強制適用事業所に該当する場合は、法令遵守のためにも、該当する従業員を社会保険や労働保険に加入させ、漏れのないよう注意しなければなりません。
リスクを回避するためには、社会保険と労働保険の専門家である社労士への依頼がおすすめです。社労士に加入要件の確認や、各保険の加入手続き・資格喪失手続きを任せることで、適用漏れや誤りを未然に防げます。
社会保険の加入義務については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:社会保険の加入義務とは?パートの適用拡大と企業の対応ポイントを解説)
社会保険と労働保険の手続きが困難なときは
社会保険と労働保険の手続きが困難なときは、社労士に依頼しましょう。社会保険や労働保険は、従業員の雇用や退職、一定の年齢に達したときなど、さまざまなタイミングで手続きが必要です。
従業員への説明や給与計算システムの変更、給与明細への反映など、事務的な手続きも多いため、ミスをしやすい手続きでもあります。
専門家の社労士に一括して手続きを任せることで、必要なタイミングでの手続き漏れを防ぎやすくなります。ほかにも任せられる業務がいくつもあるので、まずは社労士に相談してみましょう。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。