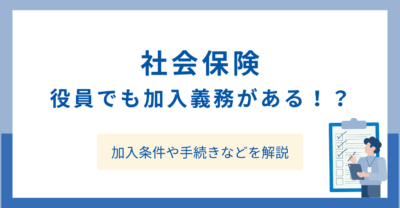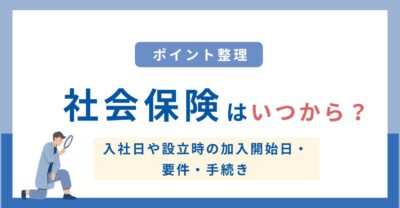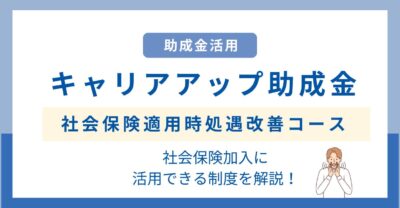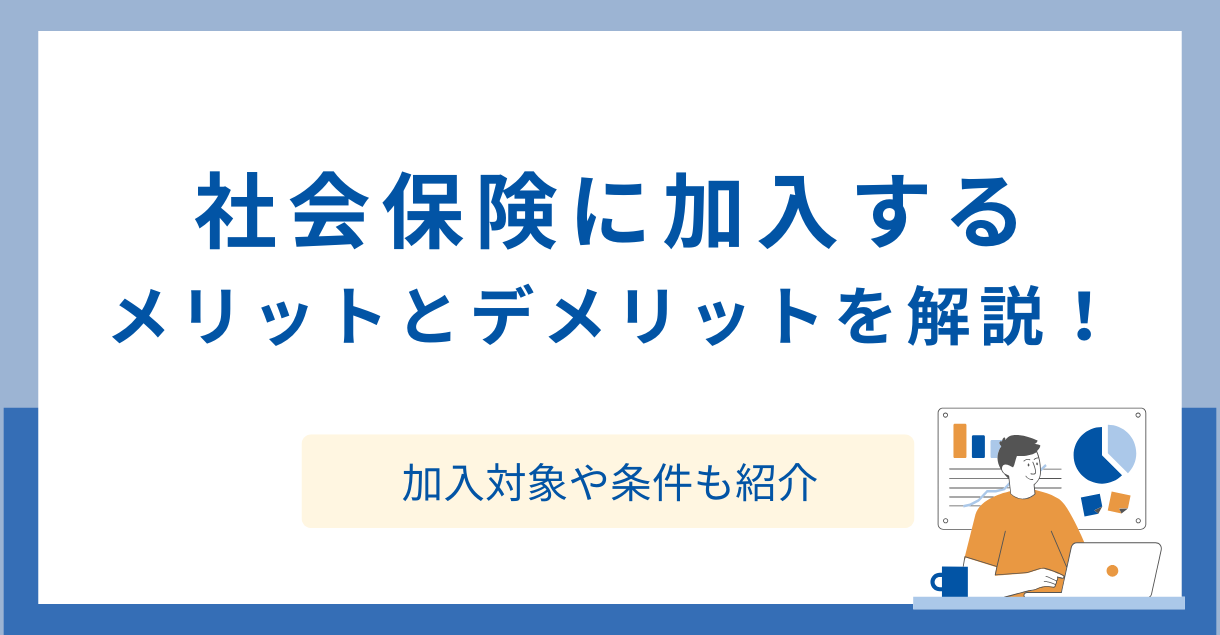
社会保険に加入するメリットとデメリットを解説!加入対象や条件も紹介
パートやアルバイトとして働く中で、勤務先から「社会保険に加入しませんか」と声をかけられた方も多いのではないでしょうか。社会保険に加入すると保険料が差し引かれ、手取り収入が減ってしまうという印象から、加入をためらう方も少なくないようです。
しかし、社会保険には、健康保険の給付が充実することや、将来的に受け取る年金額が増えるといったメリットがあります。本記事では、パート・アルバイトの方向けに、社会保険に加入することのメリットとデメリットについて整理します。
社会保険には、労災保険・雇用保険・介護保険など複数の制度が含まれますが、この記事では、パート・アルバイトの方に特に影響が大きく、手取り額や将来受け取る年金額に直結しやすい「健康保険」と「厚生年金保険」にフォーカスして解説します。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
社会保険に加入するメリット
社会保険とは、病気やケガ、老後など、生活に関わるさまざまなリスクに備えるための公的保険制度です。ここでは、パート・アルバイトの方が社会保険に加入することで得られる主なメリットを整理します。
- 将来の年金受給額が増える
- 健康保険(医療保険)の給付も充実する
- 会社が保険料を半分負担してくれる
将来の年金受給額が増える
厚生年金保険に加入することで、将来受け取れる年金額が増加します。これは、国民年金(基礎年金)の上乗せとして支給される「報酬比例部分」が追加されるためです。
具体的な金額の目安は以下のとおりです(※月収8万8,000円の場合)
| 加入期間 | 月額保険料(本人負担) | 増える年金額(月額) | 増える年金額(年額) |
|---|---|---|---|
| 20年間 | 約8,100円 | 約8,800円 | 約10万6,700円 |
| 10年間 | 約8,100円 | 約4,400円 | 約5万3,300円 |
| 1年間 | 約8,100円 | 約400円 | 約5,300円 |
※厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
老齢厚生年金は終身で支給されるため、長生きするほどメリットは大きくなります。加えて、将来的な遺族年金や障害年金の保障も充実しており、万が一の備えとしても有効です。
健康保険(医療保険)の給付も充実する
健康保険に加入すると、医療費の自己負担割合が軽減されるだけでなく、病気やケガで働けない場合に「傷病手当金」が、出産時には「出産手当金」が支給される場合があります。
例えば、連続して3日以上仕事を休み、4日目以降も就労できない状態が続いた場合、欠勤期間中の生活保障という趣旨で、傷病手当金として給与の約3分の2に相当する額が支給されます。これは自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険にはない給付です。
会社が保険料を半分負担してくれる
社会保険は、保険料を事業主と被保険者で折半します。例えば、前述した月額8,100円という保険料は、実際には総額1万6,200円の半分に相当します。
一方、国民健康保険や国民年金の場合は、保険料を全額自己負担しなければなりません。これらを踏まえると、充実した保障を受けながらも自己負担が軽減される点がメリットです。
社会保険に加入するデメリット
社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料が給与から天引きされ、手取りが減る場合があります。また、配偶者の扶養から外れて、自分で保険料を支払う必要が出てくることもあります。
ただし、これらの支出は、将来の安心への投資です。前述のとおり、老後に受け取る公的年金が増えるほか、病気やケガの際には医療費が大幅に軽減され、出産時には出産一時金などの給付も受けられます。
社会保険制度は、個人の生活を支えると同時に、誰もが安心して暮らせる社会を築くための土台でもあります。加入による負担は、単なるコストではなく、社会全体の安定と連帯を支える大切な役割を果たしていると言えるでしょう。
社会保険の加入対象
社会保険への加入は、すべての労働者に義務づけられているわけではありません。パート・アルバイトといった非正規雇用の方が社会保険に加入するかどうかは、一定の条件を満たしているかどうかにより判断されます。
具体的には、次のような要件をすべて満たす場合、原則として社会保険の加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8,000円以上(年収106万円の目安)
- 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
- 学生ではないこと(夜間・定時制・通信制を除く)
- 勤務先の従業員数が常時50~100人以上(2024年10月から適用拡大)
※厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
これらはいわゆる「短時間労働者への適用拡大」の対象となる条件であり、条件をすべて満たした場合には、正社員と同様に健康保険および厚生年金保険の加入義務が生じます。
勤務先がこれらの条件に該当するかどうか、まずは就業規則や労働契約書などで確認してみるとよいでしょう。
国民健康保険・国民年金保険との違い
パート・アルバイトとして働く方の中には、「社会保険に加入せず、今のまま国民健康保険や国民年金に加入していた方がよいのでは?」と考える方もいるかもしれません。ここでは、それぞれの保険制度の違いについて、健康保険と年金保険に分けて見ていきます。
健康保険と国民健康保険の違い
健康保険と国民健康保険はいずれも、医療機関でかかった診察料や薬剤費などの自己負担を原則3割に抑える公的医療保険制度です。ただし、保険料の算定方法や傷病手当金などの付帯給付には違いがあります。
ここでは、勤務先で加入する「健康保険」と、自営業者などが加入する「国民健康保険」のしくみを3つの観点で比べてみましょう。
| 比較項目 | 健康保険 (会社員・パート等) |
国民健康保険 (自営業・フリーランス等) |
| 保険料の計算方法 | 標準報酬月額 × 保険料率 | 所得割+均等割+平等割など、自治体が定める方式 |
| 保険料の負担 | 会社と本人で折半 | 全額自己負担(世帯主が世帯全体分を納付) |
| 主な付帯給付 | ・出産育児一時金 ・出産手当金 ・傷病手当金 |
・出産育児一時金 ・傷病手当金・出産手当金は原則なし |
上表のとおり、健康保険は会社が保険料を半分負担してくれる上、働けなくなった期間の所得補償(傷病手当金・出産手当金)が付く点がメリットです。
一方、国民健康保険は保険料をすべて自分で負担しますが、加入と脱退が比較的自由で、自営業やフリーランスの人でも加入できるという柔軟性があります。
厚生年金保険と国民年金保険の違い
年金制度には、すべての人が対象となる「国民年金(基礎年金)」と、会社員などが加入する「厚生年金」があります。パート・アルバイトとして働く方が社会保険に加入するかどうかを判断する上で、この違いを正しく理解しておくことは重要です。
以下は、両制度の主な違いを比較した表です。
| 項目 | 国民年金保険 | 厚生年金保険 |
|---|---|---|
| 対象者 | 20歳以上60歳未満の全国民 | 会社などに雇用される従業員 |
| 保険料 | 月額1万7,510円(2025年度) | 報酬に応じて決定(会社と本人が折半) |
| 保険料の負担方法 | 全額自己負担 | 会社と本人が半分ずつ負担 |
| 最低加入期間 | 原則10年 | 原則10年(国民年金と通算可能) |
| 将来の受給額(目安) | 年額約83万円 (満額・2025年度) |
基礎年金+報酬比例の上乗せあり |
| 遺族年金・ 障害年金の保障 |
限定的 | 基礎年金に加え、上乗せ保障あり |
| 配偶者の扶養の取り扱い | なし | 年収130万円未満で扶養の対象になる |
厚生年金保険は、報酬に応じた保険料であるため、国民年金に比べて保険料は高くなる傾向があります。しかし、その分、将来の受給額や保障内容も手厚くなっています。
扶養から外れたくないときは?
家庭の事情や家計のバランスを考慮し、「できれば扶養の範囲内で働きたい」と希望する方もいます。こうしたケースでは、社会保険の加入義務が生じない範囲で働くという選択肢もあります。
その場合、制度上の加入要件を正しく理解し、以下のように勤務条件を調整することが必要です。
社会保険の加入要件を満たさない範囲で働く
パート・アルバイトが社会保険の加入義務を負うのは、下記5要件をすべて満たしたときです。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 所定内賃金が月額8万8,000円以上であること
- 学生ではないこと
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
- 勤務先の被保険者数が常時51人以上
※厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト|パート・アルバイトのみなさま」
※厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト|人事・労務管理者のみなさま」
ただし、勤務先が希望どおりにシフトを調整できるとは限りません。業務の状況によっては、条件を超える時間数の勤務を依頼されることも想定しておきましょう。
短期のアルバイトをこなす
社会保険の適用対象は、原則として常用的に雇用される従業員です。したがって、雇用契約が2ヶ月以内とはっきり決まっており、かつ更新の見込みがなければ適用除外になります。
繁忙期限定のアルバイトや期間限定の業務など、柔軟な働き方を選ぶことで扶養内を維持しやすくなります。
従業員を社会保険に加入させる会社側のメリット
社会保険への加入は従業員のための制度と思われやすいですが、企業側にも多くのメリットがあります。
まず挙げられるのは、従業員の安心感が高まり、定着率の向上につながるという点です。社会保険に加入していれば、病気やケガ、出産、老後といったライフイベントに備えることができるため、働く上での不安が軽減されます。こうした安心感は職場への信頼にもつながり、離職の抑制効果が期待できます。
次に、企業の信頼性や社会的信用が高まるというメリットもあります。求人応募者や取引先に対して、「適切な労務管理を行っている企業」としての印象を与えることができ、採用活動や営業活動において有利に働く可能性があります。
また、一定規模以上の企業には社会保険の適用義務があります。仮に未加入のまま運用を続けた場合、後から保険料の遡及徴収や行政指導を受けるリスクもあるため、早めの整備が必要です。
社会保険のメリットを理解して自分にあった選択をしよう
社会保険に加入することで得られる保障は、将来の年金受給額の増加や医療・出産時の所得補償など、多岐にわたります。
とくにパート・アルバイトとして働く方の中には、制度の詳細がわかりづらい状況のまま、「損をするのでは」と不安に思っているケースも見受けられます。しかし、正しい知識をもって制度を理解すれば、自分にとってどのような選択が適しているかを判断しやすくなります。
例えば、扶養内にとどまりながら働くことも可能ですが、長期的に見れば社会保険への加入で得られる保障のほうが生活の安定につながる場合もあります。短期的な手取り収入だけでなく、将来の年金や医療給付の視点も含めて、全体的なバランスを考えることが大切です。
また、自分でうまく制度を説明できない、あるいは勤務先との調整に不安があるといった場合には、社会保険の専門家である社労士に相談するのもひとつの方法です。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。