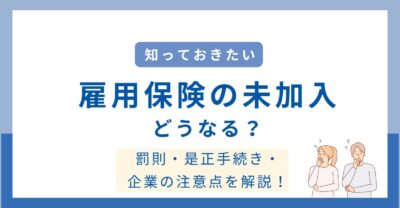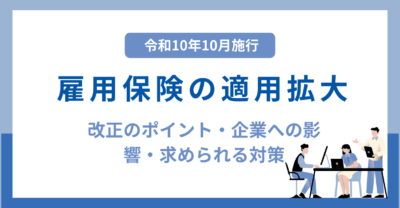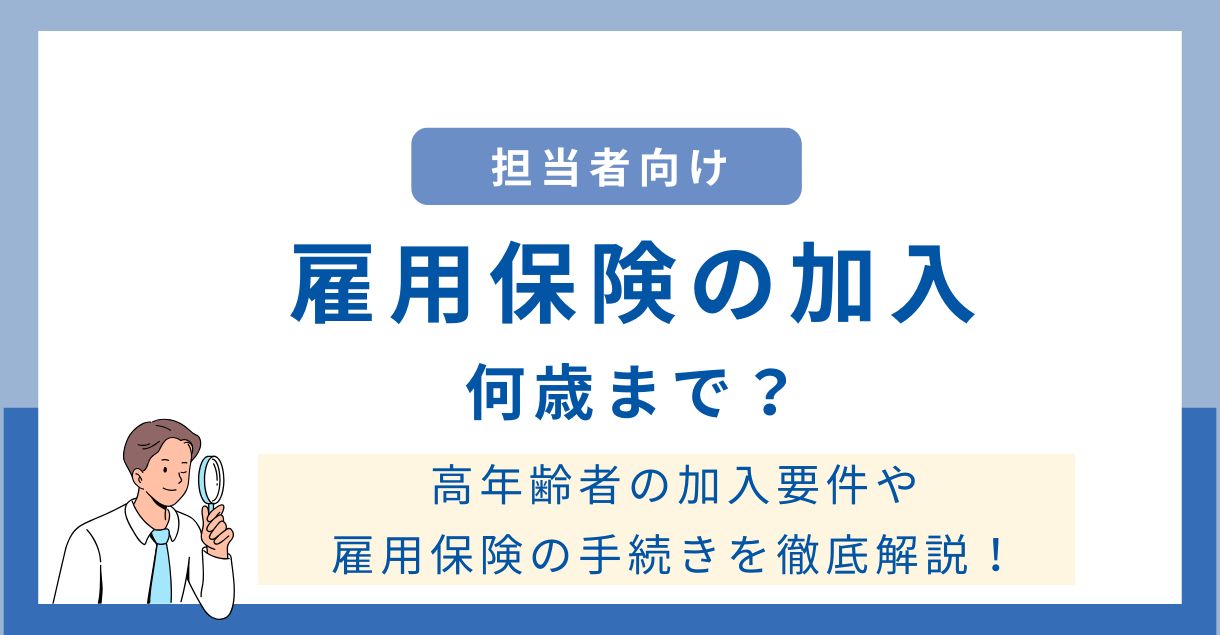
雇用保険の加入は何歳まで?65歳以上の加入要件や再雇用時の手続きを徹底解説!
高年齢の労働者を雇用する企業にとって、「定年の65歳以上でも雇用保険の対象になるのか?」「どんな手続きが必要なのか?」といった疑問は実務上つきものです。
特に再雇用や勤務延長といった継続雇用の形態によって、必要な届出や加入要件が変わるため、企業担当者は制度を正しく理解したうえで対応することが求められます。
さらに、内閣府の報告によれば、労働力人口に占める65歳以上の割合は13.4%と年々増加しており、定年後の雇用対応は今後ますます重要になるでしょう。
本記事では65歳以上の労働者に関する雇用保険の仕組みや加入条件、継続雇用制度(勤務延長・再雇用)における手続きや必要書類をわかりやすく解説します。
「自社の高年齢労働者は雇用保険の対象になるのか?」「再雇用時に必要な手続きは?」といった疑問を持つ実務担当者にとって、現場で役立つ知識が身につく内容です。
ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
雇用保険は何歳まで加入できる?―「65歳以上」も対象に

これまで雇用保険は、原則として「65歳未満の労働者」が加入対象とされてきました。
しかし、現在は年齢を問わず、一定の加入要件を満たす労働者は雇用保険に加入させる必要があります。
これは、2017年(平成29年)の法改正により、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の対象に加わったためです。
この改正により、定年後に再雇用される労働者や、嘱託契約で働く高年齢の労働者についても、企業として適切な対応が求められるようになりました。
雇用保険の対象となるかどうかは、労働時間や契約内容により判断されます。
次章では、雇用保険の加入要件を具体的に確認していきましょう。
雇用保険の加入要件とは

雇用保険に加入するためには、年齢を問わず次の2つの要件を満たす必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
したがって、65歳以上の継続雇用(勤務延長や再雇用)の際も、加入要件を満たす場合は雇用保険の加入手続きが必要です。
なお、「31日以上の雇用見込み」は契約書に基づいて判断されます。契約更新の予定がない短期雇用などは、要件を満たさない可能性もあるため、契約内容の確認が欠かせません。
要件を満たしているか判断に迷う場合は、雇用保険加入の手続きをおこなう管轄のハローワークや社労士に相談すると安心です。
企業としては、高年齢の労働者を雇用する際も、これらの条件を丁寧に確認し、適切に雇用保険の手続きを進める姿勢が求められます。
65歳以上の労働者の雇用保険の手続き

65歳以上の労働者において、雇用保険の手続きが発生する主な場面は以下の3つです。
- 65歳以上の労働者を新たに雇用した場合
- 勤務延長制度を利用して雇用を継続する場合
- 再雇用制度を利用して新たな契約を結ぶ場合
それぞれのケースについて、必要な手続きや書類を以下で詳しく解説します。
1.65歳以上の労働者を新たに雇用した場合
新たに65歳以上の労働者を雇用し、週20時間以上の勤務かつ31日以上の雇用見込みがある場合には、「高年齢被保険者」として雇用保険に加入させる必要があります。
この場合、「雇用保険被保険者資格取得届」を、雇用開始日の属する月の翌月10日までにハローワークへ提出します。
2.勤務延長制度を利用して雇用を継続する場合
勤務延長制度とは、定年後も現在の雇用契約をそのまま延長し、雇用を継続する制度です。
この場合、雇用形態や役職、賃金、業務内容などの条件は基本的に変更せず、勤務期間のみを延長するのが一般的です。
勤務延長により契約内容が大きく変わらない場合は、雇用保険の資格は継続されるため、特別な手続きは不要です。
ただし、勤務時間が週20時間未満になるなど、加入要件を満たさなくなった場合には「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。
契約内容が変更された場合は、必ず加入要件を再確認しましょう。
3.再雇用制度を利用して新たな雇用契約を結ぶ場合
再雇用制度は、一度定年退職した後に新たな雇用契約を結び直す制度です。
定年前まで正規雇用されていた労働者を、契約社員・嘱託社員・パート社員などの雇用形態で再雇用する仕組みです。
定年を迎えた労働者と再雇用契約を結んだ場合、企業には次の手続きが発生します。
【再雇用時に必要な手続きとスケジュール】
- 雇用保険被保険者資格喪失届の提出(退職日の翌々日から10日以内)
- 雇用契約書の再締結(再雇用初日に有効となるよう調整)
※①は、再雇用により雇用保険の加入要件を満たさなくなった場合に所轄のハローワークへ提出します(電子申請も対応可)。
また、資格喪失日と再取得日の間に1年を超えた空白があると、雇用保険の被保険者期間の通算に影響を及ぼします。
次の章では、再雇用時に必要な雇用保険に関する提出書類について詳しく解説します。
再雇用時に必要な雇用保険の提出書類(資格喪失届)

再雇用の場合も、雇用保険の資格は基本的には継続しますが、再雇用の労働条件が雇用保険の加入要件を満たさなくなる場合には、資格喪失の手続きを行う必要があります。
【資格喪失届の提出と必要事項】
提出期限は退職日の翌々日から10日以内で、所轄のハローワークへ提出します。
提出に必要な書類は以下の通りです。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用保険被保険者離職証明書
- 確認資料(賃金台帳、出勤簿、労働者名簿など)
これらの書類に基づき、ハローワークでは失業給付を受けるための資格の有無、期間や給付額の判断が行われます。
記載内容に不備があると手続きが差し戻されることもあるため、賃金支払状況や離職理由の正確な記載を心がけましょう。
複数事業所で働く高齢者のための雇用保険マルチジョブホルダー制度

週20時間未満の勤務でも、65歳以上の労働者が複数の事業所で働いている場合には、雇用保険に加入できるケースがあります。
このような場合に利用できるのが「雇用保険マルチジョブホルダー制度」です。
65歳以上の労働者が、複数の企業にまたがって雇用されているケースでは、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」という特別な雇用保険制度を利用できます。
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、勤務する複数の事業所のうち2つの事業所の所定労働時間を合算して、一定の要件を満たす場合に雇用保険の被保険者になれる制度です。
申請は労働者本人の意思で行い、受理されると「マルチ高年齢被保険者」として雇用保険の対象になります。
ただし、書類の作成や確認には企業側の協力が必要です。
企業担当者は、制度への加入要件や必要書類について事前に理解を深めておきましょう。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の加入要件
制度への加入には、以下の要件すべてを満たす必要があります。
| ①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること ※雇用保険に加入できるのは最大2事業所。いずれも異なる事業主であること。②2つの事業所(いずれも週5時間以上20時間未満の勤務であるものに限る)の所定労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。 |
引用:厚生省|Q&A雇用保険マルチジョブホルダー制度、雇用保険の加入条件
たとえば、A社「10時間/週」、B社「12時間/週」の場合、1事業所のみでは週20時間の所定労働時間を下回ってしまいます。しかし、2営業所を合算(10時間+12時間=22時間/週)することで、労働者は「マルチ高年齢被保険者」として雇用保険に加入することが可能です。
企業側の手続きと注意点
制度の利用には、労働者本人がハローワークへ必要書類を提出することが前提です。
申出が受理されると、通常の被保険者と同様に任意脱退はできないため、本人の意見をしっかり確認しておきましょう。
企業が行う手続きは以下の通りです。
【企業が行う対応フロー】
- 労働者から依頼された「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得(マルチ雇入届)」に必要事項を記入する
- 労働条件通知書・賃金台帳・出勤簿などの確認資料を用意する
- 書類一式を労働者へ返却(※本人がハローワークに提出)
- 後日、ハローワークから「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」が企業に届く
- 通知書に記載された資格取得年月日以降、雇用保険料の納付義務が発生する
制度を円滑に運用するためにも、書類対応を含めた準備が求められます。
まとめ|65歳以上の労働者の雇用保険対応も必要です
本記事では、65歳以上の高年齢労働者に対する雇用保険の加入要件や手続きの流れ、勤務延長・再雇用それぞれに必要な手続き対応について、制度と実務の両面から解説しました。
高年齢者の雇用は、経験や専門性を活かした戦力確保になる一方で、手続きの遅れや誤りは、企業が法令違反に問われる可能性や、労働者が必要な給付を受ける権利を損なうリスクにつながる可能性があります。
こうした対応を確実に行うためには、社内でのチェック体制の整備とあわせて、社労士など専門家のサポートを受けながら、法令に即した運用を行うと安心です。
65歳以上の雇用保険対応について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。