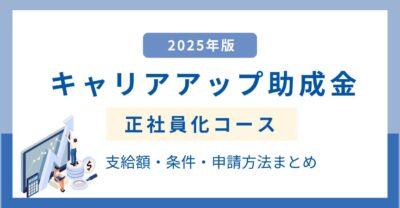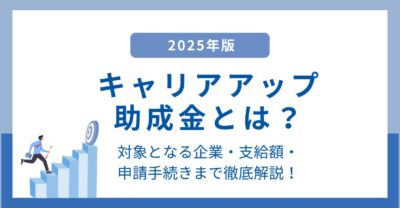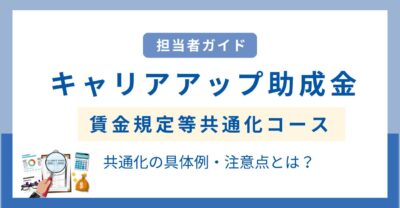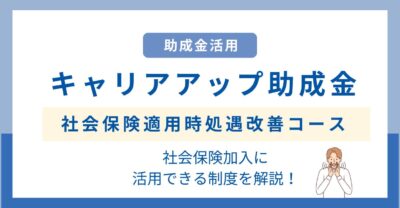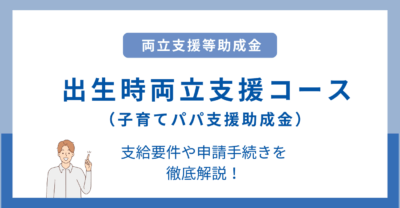【一覧表あり】両立支援等助成金とは?中小企業が知っておきたい6つのコースと申請方法
両立支援等助成金とは、労働者の仕事と育児・介護などの両立を支援するために、職場の環境整備に取り組む事業主に対して助成される公的な制度です。
2025年には「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」が新設され、出産・育児・介護に加え、不妊治療や女性特有の健康課題にも対応した支援が拡充されました。
現在は、労働者が抱えるさまざまな事情に対応できるよう、6つのコースが用意されています。
両立支援等助成金の活用は、金銭的支援だけでなく、労働者の定着率向上や採用活動での企業イメージ向上にもつながるため、人材確保に悩む企業にとって有効な施策のひとつです。
本記事では、中小企業が利用できる両立支援等助成金の制度概要をわかりやすく整理し、6つのコースの条件や助成額を一覧でご紹介します。また、申請の流れや注意すべきポイントも詳しく解説しています。
ぜひ最後までご覧いただき、自社に合った両立支援等助成金制度の導入・活用にお役立てください。
※本記事は令和7(2025)年度の制度内容を元に作成しています。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
両立支援等助成金とは

厚生労働省が実施する「両立支援等助成金」は、仕事と家庭の両立を支える職場環境の整備に取り組む企業を支援する制度です。
出産・育児・介護・不妊治療・女性の健康課題など、多様なライフイベントに対応した支援を行うことで、労働者の離職防止や人材の安定確保につなげることを目的としています。
両立支援等助成金は「中小企業のみ」

両立支援等助成金は、「中小企業」のみを支給対象としています。
本制度における「中小企業」とは、以下のいずれかの要件を満たす企業です。
▼両立支援等助成金における「中小企業」の範囲
| 業種 | 資本金または出資金 | 常時雇用する労働者数※ | |
|---|---|---|---|
| 小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
| その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
出典:厚生労働省|両立支援等助成金 支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)(P.195)
ただし、「育休中等業務代替支援コース」のうち、「手当支給等(育児休業)」と「手当支給等(短時間勤務)」は業種を問わず、常時雇用する労働者数が300人以下であれば支給対象です。
▼育休中等業務代替支援コース(手当支給等)のみ下表範囲
| 業種 | 資本金または出資金 | 常時雇用する労働者数※ | |
|---|---|---|---|
| 小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 | または | 300人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 300人以下 | |
| 卸売業 | 1億円以下 | 300人以下 | |
| その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
出典:厚生労働省|両立支援等助成金 支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)(P.195)
常時雇用する労働者とは、以下の2つの条件を満たす者を指します。
- 2か月を超えて連続雇用される者(期間の定めがなく雇用される者、2か月を超える契約期間で雇用される者を含む)
- 週の所定労働時間が当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同じである者
申請を検討する前に、自社が中小企業に該当するかを確認しておきましょう。
両立支援等助成金の6つのコースと助成額【一覧表あり】

両立支援等助成金には、目的や支援内容に応じた6つのコースが用意されています。
それぞれ対象となる取り組みや支給額が異なるため、まずは全体像を一覧表で確認しましょう。
【各コースの内容と助成額一覧表】
| コース名 | 内容 | 助成額 |
|---|---|---|
| 1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) | 男性労働者の育児休業取得を促進 | 第1種(育休取得): 1人目 20万円 2・3人目 10万円第2種(育休取得率上昇): 60万円 |
| 2.介護離職防止支援コース | 介護休業の取得や復帰、両立支援制度の利用を支える企業への支援 | 介護休業取得と復帰: 40万円 介護両立支援制度導入と利用: 20万円~25万円 業務代替支援: 3万円~20万円 |
| 3.育児休業等支援コース | 円滑な育児休業の取得を支援 | 育休取得時:30万円 職場復帰時:30万円 |
| 4.育休中等業務代替支援コース | 育児休業取得者や短時間勤務者の代替体制づくりを支援 | 手当支給等(育児休業): 最大140万円 手当支給等(短時間勤務): 最大128万円 新規雇用(育児休業): 最大67.5万円 |
| 5.柔軟な働き方選択制度等支援コース | 対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を利用した際の支援 | 導入制度2つ:20万円 導入制度3つ以上:25万円 |
| 6.不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース | 不妊治療や女性の健康課題と仕事の両立に取り組む企業を支援する助成金 | 不妊治療:30万円 女性健康課題(月経): 30万円 女性健康課題(更年期): 30万円 |
※支給額は取り組み内容や回数・単位により異なる場合があります。
ここからは、各コースの詳細についてそれぞれ解説します。
1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は、男性労働者の育児休業取得を支援する、中小企業を対象とした助成制度です。
本コースは、「第1種」と「第2種」で区分されており、2つのケースを対象に助成金が支給されます。区分ごとの内容・おもな支給要件・受給額は以下のとおりです。
【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】
| 区分 | ケース | 支給額 | 上限回数 |
|---|---|---|---|
| 第1種
男性労働者の育児休業取得 |
企業が男性の育児休暇取得を促進させるために環境整備を行った後、子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上の育児休業を取得した男性労働者が出た場合 | 1人目:20万円 雇用環境整備措置※2を4つ以上実施した場合、30万円 |
同一事業主につき3人まで申請可能 |
| 2人目・3人目:10万円 | |||
| 第2種
男性の育児休業取得率の上昇等 |
男性労働者の育児休業取得率※1が、1事業年度で以下のいずれかを達成した場合 ・30ポイント以上上昇し、50%を越えた ・2年連続で70%以上となった |
60万円 申請時にプラチナくるみん認定事業主であれば15万円加算 |
1回限り |
| 育児休業等に関する情報公表加算※:2万円
※自社の育児休業制度や取得状況を厚労省指定サイトで公表した場合に支給 |
第1種(1~3人目のいずれか)または第2種のいずれか1回限り | ||
出典:厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)|出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
※1:「育児休業取得率」は以下の計算式で求められます。
育児休業取得率(%:小数第1位以下切捨)=
一事業年度中に育児休業を取得した男性労働者数/一事業年度中に配偶者が出産した男性労働者数
30ポイント以上上昇とは、もともと40%であれば、70%以上に上昇した場合のことを指します。
※2:「雇用環境整備の措置」とは、次の5項目を指します。
「育児休業取得率」
- 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
- 育児休業に関する相談体制の整備
- 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
- 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
- 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
出典:厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)|P.5
出生時両立支援コースの申請は、以下の点に注意が必要です。
- 第1種は、同一労働者の同一の育児休業について「育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)」との併給はできません。
- 第2種は、第1種の受給の有無に関わらず申請可能です。ただし、第2種の受給後に、第1種の申請はできません。
- 同じ年度内に、第1種・第2種の両方を申請することはできません。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の支給要件などの詳しい内容は、こちらの記事で解説しています。
>出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは?支給要件や申請手続きを徹底解説|両立支援等助成金
2.介護離職防止支援コース
介護離職防止支援コースは、「介護支援プラン※」を策定したうえで、介護休業の取得支援介護や代替体制の整備など、仕事の両立を支える取り組みを行った中小企業を対象とした助成制度です。
※介護支援プランとは
介護休業の取得や職場復帰を円滑に進めるために、事業主が労働者ごとに作成する、業務の整理や引き継ぎ方法などを具体的に盛り込んだ計画のこと
介護離職防止支援コースは「介護休業」・「介護両立支援制度」・「業務代替支援」の3つの区分に分かれており、それぞれの内容・支給額・上限回数は以下のとおりです。
【介護離職防止支援コース】
| 区分 | 内容 | 支給額(1人あたり) | 上限回数 |
|---|---|---|---|
| (1)介護休業 | 介護支援プランを作成し、プランに基づいて対象労働者が介護休業を取得・職場復帰した場合 | 40万円 (連続15日以上の休業:60万円) |
1事業主あたり5人まで |
| (2)介護両立支援制度 | 介護支援プランを作成し、介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度など、仕事と介護の両立支援制度※1を利用した場合 | 制度を1つ導入し、 対象労働者が利用した場合:20万円 (合計60日以上の制度利用:30万円) 制度を2つ以上導入し、 対象労働者が1つ以上利用した場合:25万円 (合計60日以上の制度利用:40万円) |
1事業主あたり5人まで |
| (3)業務代替支援 | 対象労働者(介護休業取得者または短時間勤務制度利用者)について、代替要員の新規雇用(派遣含む)、または業務を代替する労働者へ手当の支給を行った場合 | 新規雇用:20万円 (連続15日以上の休業の場合:30万円) |
1事業主あたり5人まで |
| 手当支給等(介護休業):5万円 (連続15日以上の休業の場合:10万円) |
|||
| 手当支給等(短時間勤務):3万円 | |||
| 環境整備加算※:10万円 ※定められた4つの「仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組」すべてを行った場合に支給 |
1事業主あたり1回限り | ||
出典:厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)|介護離職防止支援コース
※1:「介護両立支援制度」とは、以下の8つの制度を指します。
- 所定外労働の制限制度
- 時差出勤制度
- 深夜業の制限制度
- 短時間勤務制度
- 在宅勤務制度
- フレックスタイム制度
- 法を上回る介護休暇制度
- 介護サービス費用補助制度
同じ労働者が介護離職防止支援コースで複数回申請する場合は、以下の点にご注意ください。
- (1)介護休業:同じ家族に対する休業での申請は1回限りです(ただし、異なる家族の介護であれば、別途申請可能)。
- (2)介護両立支援制度:同一労働者の同じ家族に対する制度利用による申請は、1制度あたり1回まで、異なる制度を利用した場合は最大2回まで申請できます。
- (3)業務代替支援:同一労働者につき、「新規雇用」と「手当支給(短時間勤務)」、「手当支給(介護休業)」と「手当支給(短時間勤務)」で、1回ずつ支給可能です。ただし「新規雇用」と「手当支給等(介護休業)」の併用はできません。
介護離職防止支援コースの支給要件や申請手順などの詳しい内容は、こちらの記事をご覧下さい。
>両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の助成額や申請方法をわかりやすく解説!
3.育児休業等支援コース
育児休業等支援コースは、「育休復帰支援プラン※」を策定し、育児休業の取得や職場復帰を支援する取り組みを実施した、中小企業を対象とした助成制度です。
※育休復帰支援プランとは
労働者の育児休業の取得や職場復帰を円滑に進めるために、事業主が育児休業者ごとに作成する実施計画。業務の整理や引き継ぎ方法、休業中の職場情報などの共有を具体的に盛り込んだ計画のこと
本コースでは、「育休取得時」と「職場復帰時」の2つの区分があります。それぞれの内容・支給額・上限回数は以下のとおりです。
【育児休業等支援コース】
| 区分 | 内容 | 支給額 | 上限回数 |
|---|---|---|---|
| (1)育休取得時 | 育休復帰プランを作成し、プランに基づいて労働者に育児休業を取得させた場合 | 30万円 | 1事業主2回まで※ |
| (2)職場復帰時 | 「(1)育休取得時」の対象労働者を、育児休業取得後に職場復帰させた場合 | 30万円 | 1事業主2回まで※ |
| 育児休業等に関する情報公表加算※:2万円 ※企業の育児休業制度や取得状況を厚労省指定サイトで公表した場合に支給 |
1事業主につき1回限り | ||
※1事業主2回までとは、無期雇用・有期雇用労働者の各1回を指します。
出典:厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)|育児休業等支援コース
育児休業等支援コースを申請する際は、以下のポイントに注意が必要です。
- 対象労働者の同一の育児休業については、「出生時両立支援コース(第1種)」との併給はできません。
- (2)職場復帰時の助成金は、(1)育休取得時の助成金を受給している同じ労働者・同じ育児休業に対して申請する場合のみが対象です。
育児休業等支援コースの詳しい支給要件や申請手順は、こちらの記事をご確認ください。
>育児休業等支援コースとは?支給要件や申請手続きをわかりやすく解説!|両立支援等助成金
4.育休中等業務代替支援コース
育休中等業務代替支援コースは、育児休業や短時間勤務制度を利用する労働者の業務に対し、代替要員の確保や業務代替者へ手当支給を行った企業を対象とした助成制度です。
6つの両立支援等助成金の中で、本コースのみ、対象企業規模が「中小企業」と「全産業一律で労働者数が300人以下の事業」の2種類に分かれている特長があります。
助成金は「手当支給等(育児休業)」・「手当支給等(短時間勤務)」・「新規雇用(育児休業)」の3つの区分に分かれており、それぞれの内容・支給額・上限回数は以下のとおりです。
【育休中等業務代替支援コース】
| 区分 | 内容 | 支給額(1名あたり) | 上限回数 |
|---|---|---|---|
| (1)手当支給等(育児休業) | 育児休業取得者の業務代替労働者に対して、手当の支給を行った場合 | 最大140万円(A+B) A:業務体制整備経費:最大20万円 B:業務代替者への手当(総支給額の3/4): 最大120万円 ※月額10万円が上限、代替期間12か月分までが対象 |
1事業主1年度につき、(1)~(3)の合計で10人まで ※初回の対象者が出てから5年間 ※くるみん認定事業主は令和11年度まで延べ50人が限度 |
| (2)手当支給等(短時間勤務) | 育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務代替労働者に対して、手当の支給を行った場合 | 最大128万円(A+B) A:業務体制整備経費:最大20万円 B:業務代替者への手当(総支給額の3/4): 最大108万円 ※月額3万円が上限、子が3歳になるまでの期間が対象 |
|
| (3)新規雇用(育児休業) | 育児休業取得者の業務代替要員を、新規雇用(派遣含む)で確保した場合 | 最大67.5万円 育児休業期間中の代替期間に応じて支給 ・最短(7日以上14日未満):9万円(11万円) ・最長(6か月以上):67.5万円(82.5万円) ※():プラチナくるみん認定事業主への割増支給額 |
|
| 有期雇用労働者加算※:10万円 ※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象で、対象育児休業取得者もしくは短時間勤務制度利用者が、有期雇用労働者の場合に支給 |
1事業主につき1回限り | ||
| 育児休業等に関する情報公表加算※:2万円 ※自社の育児休業制度や取得状況を厚労省指定サイトで公表した場合に支給 |
1事業主につき1回限り | ||
(1)・(2):全産業一律で労働者数が300人以下の事業主が対象
(3):中小企業が対象
出典:厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)|育休中等業務代替支援コース
育休中等業務代替支援コースの申請ポイントは、以下のとおりです。
- (1)の手当支給等(育児休業)について、同じ子に対する育児休業の申請は1回限りです。
- (3)の新規雇用(育児休業)について、同じ子に対する育児休業の申請は1回限りです。
- (1)と(3)は併用できず、いずれか一方のみとなります。
育休中等業務代替支援コースの支給要件の詳細や申請方法は、厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)もご確認ください。
5.柔軟な働き方選択制度等支援コース
柔軟な働き方選択制度等支援コースは、テレワークや短時間勤務など、厚生労働省が定める育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を導入する中小企業を支援するコースです。
制度を2つ以上整備し、労働者が実際に利用できるよう支援した場合に助成金が支給されます。
これらの取り組みは、3歳すぎから小学校就学前までの子を育てる労働者が利用できる制度として設ける必要があります。
本コースの支給額は、制度の導入数によって異なります。
【柔軟な働き方選択制度等支援コース】
| 区分 | 支給額(1名あたり) | 利用回数 |
|---|---|---|
| 制度を2つ導入し、労働者が制度を利用した場合 | 20万円 | 1事業主1年度(4月1日~翌年3月31日)につき5人まで |
| 制度を3つ以上導入し、労働者が制度を利用した場合 | 25万円 | 1事業主1年度(4月1日~翌年3月31日)につき5人まで |
| 育児休業等に関する情報公表加算※:2万円 ※企業の育児休業制度や取得状況を厚労省指定サイトで公表した場合に支給 |
1事業主あたり1回限り | |
出典:厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)|柔軟な働き方選択制度等支援コース
導入した制度は、対象労働者が利用開始から6か月以内に、制度ごとに定められた実績(例:20日以上の利用、一定額以上の補助など)を満たしていることが条件となります。
柔軟な働き方制度の一覧と、支給に必要な利用実績の基準は以下のとおりです。
| 制度名 | 利用実績の基準 |
|---|---|
| (1-ⅰ)フレックスタイム制度 | 合計20日間以上 |
| (1-ⅱ)時差出勤制度 | 合計20日間以上 |
| (2)育児のためのテレワーク等 | 合計20日間以上 |
| (3)短時間勤務制度 | 合計20日間以上 |
| (4)保育サービスの手配及び費用補助 | 次のいずれかの補助を実施 (1)労働者負担額が料金の5割以上かつ事業主負担が3万円以上(2)事業主負担が10万円以上 |
| (5-ⅰ)子の養育を容易にするための休暇制度 | 合計20時間以上 |
| (5-ⅱ)法を上回る子の看護等休暇制度 | 合計20時間以上 |
※(1-ⅰ)フレックスタイム制度と(1-ⅱ)時差出勤制度の2つ、または(5-ⅰ)子の養育を容易にするための休暇制度と(5-ⅱ)法を上回る子の看護等休暇制度の2つを導入した場合は、1つの制度を導入したものと扱います。
※異なる制度を同一期間で利用しても利用実績は合算できません。
柔軟な働き方選択制度等支援コースの詳しい内容は、厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)をご覧下さい。
6.【2025年新設】不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースは、2025(令和7)年度より新設された助成制度です。
不妊治療や、女性特有の健康課題である月経(PMS(月経前症候群)含む)・更年期に対応した両立支援制度※を整備した中小企業が対象です。
※両立支援制度は、以下の6つを指します。(1つ以上の制度を導入すること)
- 休暇制度
- 所定外労働制限制度
- 時差出勤制度
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制度
- 在宅勤務等
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースは、「不妊治療」・「女性の健康課題対応(月経)」・「女性の健康課題対応(更年期)」の3つの区分があり、それぞれの内容・支給額は以下のとおりです。
【不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース】
| 区分 | 内容 | 支給額 | 利用回数 |
|---|---|---|---|
| 不妊治療 | 性別を問わず不妊治療と仕事の両立を支援する制度を導入し、対象労働者が5日(回)以上利用した場合※過去に不妊治療両立支援コースを受給した場合は受給できません | 30万円 | 1事業主あたり1回限り |
| 女性の健康課題対応(月経) | 月経に伴う不調などへの対応制度を整備し、対象労働者が5日(回)以上利用した場合 | 30万円 | 1事業主あたり1回限り |
| 女性の健康課題対応(更年期) | 更年期の心身の不調に対応する制度を整備し、対象労働者が5日(回)以上利用した場合 | 30万円 | 1事業主あたり1回限り |
出典:厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)|不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
また、支給要件の1つには、「両立支援担当者」の選任が定められています。
「両立支援担当者」は、不妊治療や女性の健康課題(月経・更年期)と、仕事の両立を支援するため、労働者からの相談に応じて制度利用をサポートするのが役割です。
事業主・労働者・外部専門家(社労士・産業医・保健師など)から選出可能で、制度利用開始日前までに決める必要があります。
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースの詳しい支給要件や申請方法については、厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)をご確認ください。
両立支援等助成金を申請する企業のメリット

仕事と育児・介護・健康課題の両立支援に取り組む企業にとって、助成金を得られるだけでなく、経営面・組織面・採用面で大きな効果があります。
ここでは、両立支援等助成金を申請する企業のメリットを3つご紹介します。
1|助成額が大きい
両立支援等助成金は、コースや制度の組み合わせによっては100万円以上の助成金が支給されるケースもあります。
【具体例】
- 介護離職防止支援コース:143万円(介護休業連続15日以上+両立支援制度2つ以上導入&制度60日以上利用+業務代替要員新規雇用&手当支給(短時間勤務)+環境整備加算)
- 育休中等業務代替支援コース:152万円(手当支給等(育児休業)+有期雇用労働者加算+情報公表加算)
- 育児休業等支援コース:62万円(育休取得時+職場復帰時+情報公表加算)
助成金は、事業主が職場環境の整備や向上に際し支出した費用を助成するもので返済不要です。
企業の課題に応じて、業務の効率化や職場環境の改善、設備投資、人件費補填など、多様な場面で活用することが可能です。
2|離職防止と雇用確保につながる
両立支援制度が整った職場では、育児・介護・不妊治療・更年期などのライフイベントに直面しても、柔軟な働き方により仕事を続けやすくなります。
一方で、制度が整っていない職場では、育児・介護・通院などのたび重なる早退や休暇に気をつかい、「迷惑をかけるくらいなら」と、自ら退職を選ぶケースも少なくありません。
時短勤務やテレワーク、休業取得といった働き方の選択肢は、労働者の離職を防ぎ、経験値の高い人材を長期的に確保しやすくなります。
また、社内でライフイベントと仕事の両立支援の前例ができることで、他の労働者にとっても制度利用のハードルが下がり、結果として組織全体の定着率向上にもつながるでしょう。
3|採用時のアピール材料になる
両立支援に取り組んでいる企業は、従業員からの信頼感が高まり、企業イメージの向上にも効果的です。
さらに、柔軟な働き方ができる職場は求職者にとっても魅力的であり、採用時のアピールポイントにもなります。実際に、制度導入を通じて応募数や入社後の定着率が向上した事例も多くあります。
- 株式会社共立アイコム(製造業):環境整備により女性活躍を推進
- 株式会社読売エージェンシー(専門サービス業):えるぼし認定を機に女性応募者が増加
ワークライフバランスを重視する労働者が増えているため、両立支援制度の充実は採用活動の強力なアピールポイントになります。
両立支援等助成金の申請の流れ

助成金を受けるには、事前の準備と労働局への届け出が必要です。
事前準備と基本的な申請の流れを理解して、スムーズに申請を進めましょう。
申請に向けた準備
申請するための事前準備は、以下のとおりです。
- 対象となる労働者や職場の抱える問題点に応じて、該当するコースを選択する
- コースに応じた制度を就業規則や労働協約等に策定し、社内周知する
- 対象者が制度を一定期間利用する
- 利用実績(出勤簿・賃金台帳・面談シートなど)を記録・保管する
コースによっては、介護支援や育休復帰支援プランの作成、両立支援担当者の選任、一般事業主行動計画策定と労働局への届け出が必要です。該当年度の両立支援等助成金支給申請の手引きを必ず確認しましょう。
制度利用後の申請手続き
制度を一定期間利用したあと、申請までの基本的な流れは以下のとおりです。
- 制度利用が要件を満たしているか確認する
- 支給申請書類(支給申請書・添付書類一式)を準備する
- 管轄の都道府県労働局または労働基準監督署に期限内に提出する
- 審査を経て、支給決定後に助成金が振り込まれる
コースによって、支給申請書の様式や提出期限が異なります。
また、消印の日付が申請期限内であっても、労働局への到着日が申請期限を過ぎていると申請が認められない可能性があります。申請期限を確認し、余裕をもって提出するようにしましょう。
申請に必要な書類や記入方法、提出期限については、厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)をご確認ください。
両立支援等助成金の申請回数|上限一覧

両立支援等助成金は、コースごとに申請できる回数や条件が決まっています。
以下、コース別の申請回数の上限と条件を一覧にまとめました。
| コース名 | 申請回数の上限・条件 |
|---|---|
| 1.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) | 第1種:1事業主につき最大3人まで 第2種:1事業主につき1回限り |
| 2.介護離職防止支援コース | 各支援内容ごとに、1事業主につき最大5人まで |
| 3.育児休業等支援コース | 1事業主あたり2回まで (無期・有期労働者それぞれ1回ずつ) |
| 4.育休中等業務代替支援コース | 1事業主1年度あたり延べ10人まで(3つの区分の合計) ※申請期限は初回から5年間 |
| 5.柔軟な働き方選択制度等支援コース | 1事業主1年度につき延べ5人まで |
| 6.不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース | 各支援内容ごとに、1事業主につき1回限り |
※1年度:4月1日~翌年3月31日
申請できる回数や条件をしっかり押さえておくことで、助成金をムダなく活用できます。
特に複数のコースを検討している場合は、年度ごとの申請上限にも注意しながら、早めにスケジュールを組んでおくと安心です。
両立支援等助成金の注意点

両立支援労助成金を活用するには、制度の正確な理解と適切な手続きが欠かせません。
申請内容が不正と判断された場合には、助成金の返還だけでなく、企業名の公表や将来の申請制限といった深刻なリスクが伴います。
ここでは、申請前に押さえておきたい重要な注意点について解説します。
事業主単位で支給される
両立支援等助成金は、雇用保険の適用事業主である「法人または個人事業主」単位で支給されます。
そのため、同一企業内に複数の事業所や事業がある場合でも一事業主とされ、申請の上限人数・回数が事業所・事業ごと個別に上限が設けられる訳ではありません。
不正受給は5年間の支給停止
虚偽申請や不正な証明、受給額の水増しなどが判明した場合は、以下のような厳しい措置が取られます。
- 助成金の一部、または全額返還
- 5年間の助成金受給停止
- (悪質な場合)社名・関与社労士名の公表
不正に関与した社労士や代理人も連帯責任を負い、事業主と同じく5年間は申請が受理されないため注意が必要です。
申請期間の末日までに労働局に到達必須
郵送申請の場合、申請期間までに都道府県労働局に到達していることが必要です。消印有効ではないため、早めの準備・発送が必要です。
なお、郵便事故を防ぐために、簡易書留など配達記録が残る方法で送付すると安心です。
令和5年4月1日前の制度利用は電子申請できない
両立支援等助成金の電子申請は、令和5年度以降の支給要件が適用される場合のみ対応しています。つまり、令和5年4月1日前から育児休業を取得しているなど、令和4年度以前の制度が適用される申請には電子申請が利用できません。
電子申請用の申請様式についての詳細は、厚生労働省HP|両立支援等助成金(電子申請用の様式)をご確認ください。
まとめ|両立支援等助成金の活用は社労士との連携が安心です
本記事では、両立支援等助成金の制度概要や対象となる中小企業の要件、申請手続き、コース別の特徴や注意点について詳しく解説しました。
両立支援等助成金は、中小企業が労働者の仕事と育児や介護の両立を支援する制度を整える際に活用できる公的助成金です。
制度をうまく活用すれば、最大数百万円の助成を受けられるだけでなく、労働者の定着率向上や採用活動における企業アピールにもつながります。優秀な人材確保に悩む企業にとって、大きなメリットのある支援策といえるでしょう。
一方で、各コースで異なる要件や申請上の注意点が多く、申請書類の不備や期限の遅れによる不支給を防ぐには、制度の正しい理解と計画的な運用が欠かせません。
申請手続きをスムーズに進め、制度の効果を最大限に活かすには、制度に精通した経験豊富な社労士との連携が安心です。
両立支援等助成金について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。