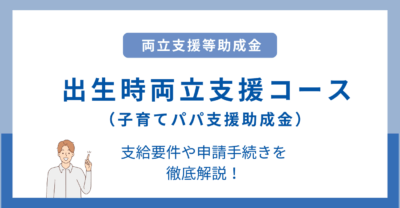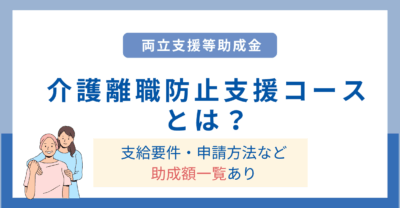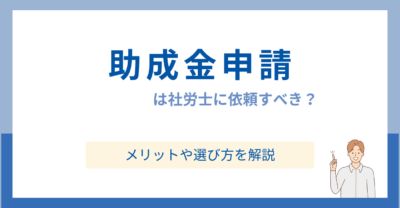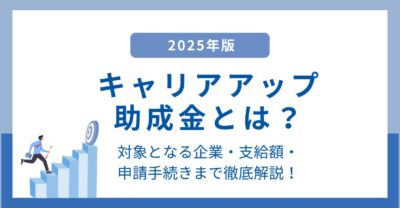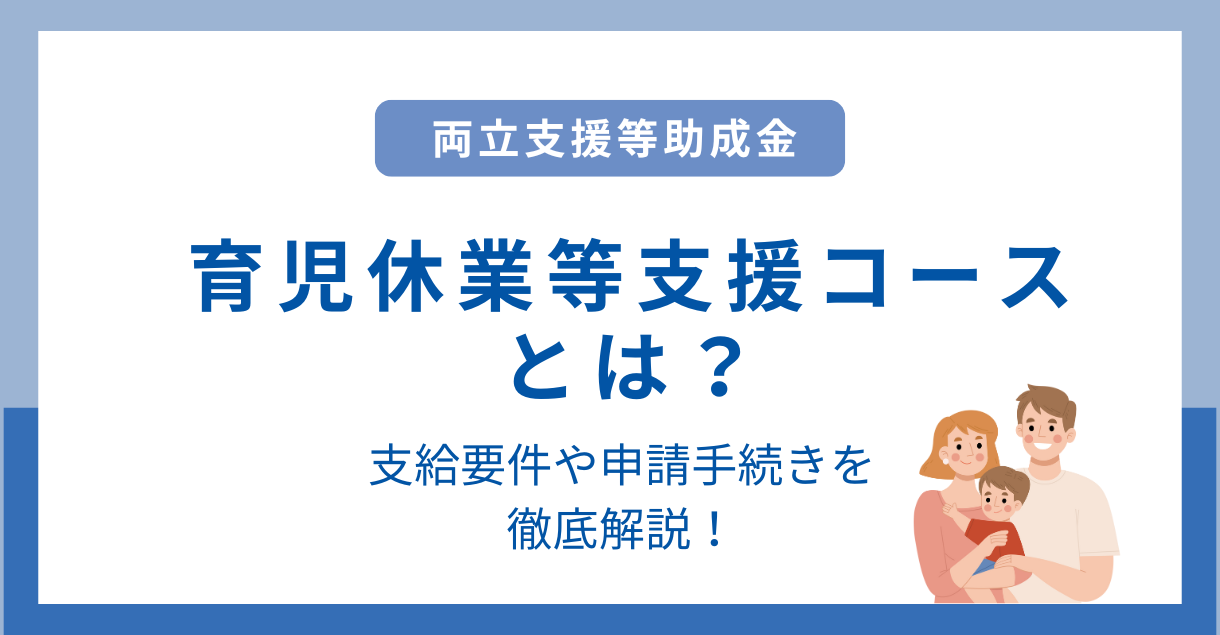
育児休業等支援コースとは?支給要件や申請手続きをわかりやすく解説!|両立支援等助成金
育児休業の取得や職場復帰を円滑に進めるには、企業側の支援体制の整備が欠かせません。
特に中小企業にとっては、労働者の育児と仕事の両立を支える制度として、「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」の活用が大きなメリットとなります。
ただし、この制度を活用するためには、支給要件や手続きの流れ、申請期限などを正しく把握しておくことが不可欠です。
本記事では、企業担当者の方が制度をスムーズに理解できるよう、制度の概要から支給要件、必要書類、手続きの流れや注意点を1記事にまとめてご紹介します。
「どのタイミングで、どう申請すればよいのか」が明確になる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
※本記事は令和7(2025)年度の制度内容を元に作成しています。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)とは

この章では、「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」がどのような制度で、どのような目的で設けられているのかを解説します。あわせて、対象となる企業の範囲についても確認していきましょう。
育児休業等支援コースの制度概要
両立支援等助成金は、企業が労働者の仕事と育児・介護の両立を支援する取り組みを行った際に、一定の条件を満たすことで支給される厚生労働省所管の助成制度です。
そのなかでも「育児休業等支援コース」とは、企業が『育休復帰支援プラン※』を策定し、育児休業の取得や職場復帰を円滑に進めるための体制を整えた場合に助成される制度です。
具体的には、企業が実際に育児休業取得の支援策を講じ、それに伴い労働者が育休を取得・復帰することで、育休取得時・職場復帰時の各段階で助成金が支給される仕組みになっています。
※育休復帰支援プランとは:
労働者の育児休業の取得や職場復帰を円滑に進めるために、育児休業者ごとに企業が作成する実施計画のことです。業務の整理や引き継ぎ方法、休業中の職場情報などの共有を具体的に盛り込みます。育休復帰支援プランの作成例については、厚生労働省の「育休復帰支援プラン策定マニュアル」からご覧いただけます。
この制度は、特に育児期の労働者が安心して休業・復職できる環境を整えるとともに、企業の人材定着にも寄与する仕組みとして活用が期待されています。
両立支援等助成金の全体像や各コースの概要については、こちらの記事で詳しく解説しています。
>【一覧表あり】両立支援等助成金とは?中小企業が知っておきたい6つのコースと申請方法
対象となるのは中小企業のみ
育児休業等支援コースの対象は、「中小企業」に限られています。
両立支援等助成金における「中小企業」とは、業種ごとに定められた「資本金(または出資金)」または「常時雇用する労働者数」のいずれかが基準以下である企業を指します。
| 業種 | 資本金または出資金 | 常時雇用する労働者数※ | |
|---|---|---|---|
| 小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
| その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
出典:厚生労働省|2025(令和7)年度両立支援等助成金のご案内(P.4)
※常時雇用する労働者とは、以下の両方を満たす者を指します。
- 2か月を超えて連続雇用される者(期間の定めがなく雇用される者、2か月を超える契約期間で雇用される者を含む)
- 週の所定労働時間が当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同じである者
申請を進める前に、まずは自社が中小企業の定義に該当するかどうかを確認しておきましょう。
育児休業等支援コースの種類と助成金額一覧
| 区分 | 内容 | 支給額 | 上限回数 |
|---|---|---|---|
| (1)育休取得時 | 育休復帰プランを作成し、プランに基づいて労働者に育児休業を取得させた場合 | 30万円 | 1事業主2回まで※ |
| (2)職場復帰時 | 「(1)育休取得時」の対象労働者を、育児休業取得後に職場復帰させた場合 | 30万円 | 1事業主2回まで※ |
| 育児休業等に関する情報公表加算[1] ※:2万円 ※企業の育児休業制度や取得状況を厚労省指定サイトで公表した場合に支給 |
1事業主につき1回限り | ||
※1事業主2回までとは、無期雇用労働者・有期雇用労働者の各1回の計2回を指します。
出典:厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)|育児休業等支援コース
育児休業等支援コースには、(1)育休取得時と(2)職場復帰時の助成金に加えて、「育児休業等に関する情報公表加算」が設けられています。
職場復帰時の助成金を申請するには、同じ労働者の同じ育児休業について「育休取得時」の助成金をすでに受給していることが条件となります。したがって、育休取得時の助成金を申請・受給していない労働者については、職場復帰時の申請はできないため注意が必要です。
つまり申請上限の2回とは、無期雇用労働者から1名、有期雇用労働者から1名の計2名ということになります。
また、「育児休業等に関する情報公表加算」については、(1)(2)のいずれかの助成金に1事業主につき1回限り加算されます。加算のみを単独で申請することはできない点も、あわせて押さえておきましょう。
育児休業等支援コースの支給要件

助成金を受給するには、ただ育休を取らせて復帰させるだけでは支給対象にはなりません。
企業としてどのような体制を整え、どのような実績を積む必要があるのかを知っておくことが重要です。以下、それぞれのおもな支給要件を整理します。
(1)育休取得時
育休取得時の支給要件は以下のとおりです。
- 育休復帰支援プランにより労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援する方針を周知していること
当該労働者ごとに育休復帰支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する方針の周知が必要です。 - 育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録したうえで、育休復帰支援プランを作成すること
育休復帰支援プラン:
以下の内容のいずれも盛り込む必要があります。
• 育児休業取得予定者の業務の整理、引き継ぎに関する事項
• 育児休業中の職務や業務内容に関する情報及び資料の提供に関する事項
育休復帰支援プランの作成例については、厚生労働省の「育休復帰支援プラン策定マニュアル」にてご確認いただけます。 - 育休復帰支援プランに基づき、業務の引き継ぎを実施していること
育休復帰プランの内容に沿わない方法で引き継ぎを行った場合は、支給対象外となります。 - 対象の労働者が連続3か月以上の育児休業を取得したこと
産後休業から引き続いて育児休業を取得する場合は、産後休業を含めて連続3か月以上となっていれば支給対象です。
育児休業期間中に一定日数または一定の時間を超えて就業した場合は、労使合意であったとしても助成金対象となりません。育休開始日を起算として全ての月において就業日数が10日(10日を超えている場合は80時間)以下の場合のみ助成金対象となります。 - 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
以下の制度すべてを育児休業開始前に労働協約または就業規則に定めている必要があります。
・育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業
※育児・介護休業法第9条の2に規定する出生時育児休業(産後パパ育休)を含む。
・育児・介護休業法第23条に定める育児のための所定労働時間の短縮措置 - 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
一般事業主行動計画は、申請時点において有効である(申請日が行動計画の期間内であること)必要があります。 - 対象労働者を育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること、産後休業から継続して育児休業を取得する場合は産後休業の開始日において雇用保険被保険者であることが必要です。
《実施期限》
①~③は、対象労働者の休業開始日の前日までに実施している必要があります。
【産前休業から連続して産後休業・育児休業を取得する場合】
産前休業開始日の前日まで
【産後休業から連続して育児休業を取得する場合】
産後休業開始日の前日まで
【それ以外の場合】
育児休業開始日の前日まで
※厚労省の「両立支援等助成金のご案内」ページにある『手引き』にてより細かい要件をご確認いただけます。実際に育児休業等支援コースに申請する際は、取組が該当する年度の支給要件を必ずご確認ください。
(2)職場復帰時
同じ対象労働者が、同じ育児休業の職場復帰時に助成金の支給を受けるには、育休取得時の助成金を受給していることが前提条件となります。
そのうえで、以下の要件を満たす必要があります。
- 育休復帰支援プランに基づき、対象の労働者の復帰までに職務や業務内容に関する情報及び資料※の提供を行ったこと
※原職または復帰後の職務に関連する情報(業務データ、月報、業務マニュアル、企画書、業界紙 など)のことを指します。 - 職場復帰前に育児休業取得者と面談等を行い、「面談シート」に記録すること
面談は、職場復帰の約2か月前に実施することが望ましいです。 - 育児休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること
「原職」とは、育児休業前に従事していた同じ部署かつ同じ職務内容を指します。原職への復帰でなくても、「原職相当職」への復帰であれば、支給対象となります。
本人の希望により原職等以外で復帰する場合は、当該希望が面談により確認できる必要があります。 - 対象労働者を職場復帰した日から6か月以上、かつ支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
対象の6か月間の間に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行っている場合は、支給対象外です。 - 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
一般事業主行動計画は、申請時点において有効である(申請日が行動計画の期間内であること)必要があります。
※厚労省の「両立支援等助成金のご案内」ページにある『手引き』にてより細かい要件をご確認いただけます。実際に育児休業等支援コースに申請する際は、取組が該当する年度の支給要件を必ずご確認ください。
育児休業等に関する情報公表加算
(1)育休取得時、または(2)職場復帰時のいずれかの申請時に、一定の要件を満たしていれば「育児休業等に関する情報公表加算」の申請が可能です。
・支給申請日までに、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば|一般事業主行動計画公表サイト」で以下の①~③の情報をすべて公表していること
- 雇用する男性労働者の育児休業等の取得割合
- 雇用する女性労働者の育児休業の取得割合
- 雇用する労働者(男女別)の育児休業の平均取得日数
※自社サイトでの公表など、「一般事業主行動計画公表サイト」以外の場で公表した場合は、加算の対象外となりますので注意が必要です。
※厚労省の「両立支援等助成金のご案内」ページにある『手引き』にてより細かい要件をご確認いただけます。実際に育児休業等支援コースに申請する際は、取組が該当する年度の支給要件を必ずご確認ください。
育児休業等支援コースの申請の必要書類と申請期限

育児休業等支援コースを申請するには、各タイミングに応じた必要書類を適切に準備・提出しなければなりません。
ここでは、「育休取得時」「職場復帰時」「育児休業等に関する情報公表加算」の申請で必要となる主な書類や申請期限を整理しています。
(1)育休取得時
【必要書類】
- 支給申請書
両立支援等助成金(育児休業等支援コース(育休取得時))支給申請書 - 支給要件確認申立書
共通要領様式 - 面談シート
※対象労働者の休業開始日の前日までに作成する必要があります - 育休復帰支援プラン
※対象労働者の休業開始日の前日までに作成する必要があります - 支援方針の周知を証明する書類
社内報、イントラネット掲示、就業規則、実施要領など(周知日が確認できるもの) - 育児関連制度の整備状況を示す書類
労働協約、就業規則、関連労使協定(育児休業制度・短時間勤務制度が確認できるもの)
※改定している場合は改定後のものも提出 - 対象労働者の雇用契約書・労働条件通知書など
プラン策定日時点での雇用期間が確認できるもの - 育児休業申出書
支給申請書に記載された育児休業期間が確認できる内容
※育休期間に変更がある場合は、変更申出書も提出 - 出勤簿及び賃金台帳
出勤簿(またはタイムカード)と賃金台帳
・休業前1か月分の勤務実績
・育児休業(または産休含む連続休業)3か月分の休業状況を確認できるもの - 母子手帳(出生欄)、住民票など
対象の労働者に育児休業に係る子がいることや子の出生日が確認できる書類 - 次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届
プラチナくるみん認定企業は提出不要
【過去に本コースの申請を行ったことがある事業主】 - 提出を省略する書類についての確認書
【育】様式第6号(2人目以降で内容変更がない場合に、5・6・11を省略可)
【初めて雇用関係助成金を申請する事業主】 - 支払方法・受取人住所届 及び 支払口座が確認できる通帳等の写し
情報公表加算を申請する場合の必要書類は後述の「育児休業等に関する情報公表加算」をご覧ください。
申請書類は、厚生労働省の「両立支援等助成金のご案内」ページにて必ず確認し、最新版をダウンロードしてください。
【申請期限】
申請期限は、以下の「起算日」から3か月を経過した日の翌日から2か月以内です。
- 産後休業から連続して育児休業を取得する場合
起算日:産後休業の開始日 - それ以外の場合
起算日:育児休業の開始日

育児休業の終了を待たずに申請期限が先に到来する場合があります。そのため、休業期間中であっても、早めに申請準備を進め、期限内に提出することが重要です。
(2)職場復帰時
【必要書類】
- 支給申請書
両立支援等助成金(育児休業等支援コース(職場復帰時))支給申請書2.支給要件確認申立書
共通要領様式3.面談シート
※職場復帰前に面談を行い育休取得時に用いた面談シートに記録します - 支給要件確認申立書
共通要領様式 - 面談シート
※職場復帰前に面談を行い育休取得時に用いた面談シートに記録します - 休業中に提供した業務関連資料
育児休業中に対象労働者へ業務情報を提供したことが確認できる資料
例:業務内容に関する社内資料、イントラネット画面の印刷物(日付入り) - 出勤簿(またはタイムカード)及び賃金台帳
以下の2つの期間が確認できる書類必要
・育児休業終了前3か月分の休業状況
・職場復帰後6か月分の勤務実績
※在宅勤務の場合は業務日報なども添付 - 労働協約・就業規則・労使協定など
育児休業制度や育児のための短時間勤務制度が確認できる部分
※原則は育休開始時点のものを提出。改訂がある場合はその最新版も提出
※労働者が10人未満で就業規則がない場合は、制度の周知状況が分かる書類を添付 - 次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届
プラチナくるみん認定企業は提出不要
【復職後に短時間勤務を利用している場合は、次の8・9も必要】 - 育児短時間勤務の申出書
- 賃金計算方法が確認できる書類(申立書など)
【過去に申請を行ったことのある事業主は必要に応じて10.を添付】 - 提出を省略する書類についての確認書
【育】様式第6号
※「育休取得時」の申請時から内容に変更がなければ、上記6・7の提出は省略可能
申請書類は、厚生労働省の「両立支援等助成金のご案内」ページにて必ず確認し、最新版をダウンロードしてください。
【申請期限】
申請期限は、育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内です。申請先は事業主の本社等の所在地にある労働局雇用環境・均等部(室)です。
郵送の場合は期限内必着である点に注意しましょう。期限を過ぎると申請できなくなるため、余裕をもって早めに準備を進めることが大切です。
育児休業等に関する情報公表加算
【必要書類】
- 育児休業等に関する情報公表加算の支給申請書
両立支援等助成金(育児休業等支援コース(育児休業等に関する情報公表加算))支給申請書 - 一般事業主行動計画公表サイトの企業情報の公表画面等
対象となる育児休業等の利用状況に係る情報をすべて公表していることが分かるよう、公表ページを印刷して提出する
育児休業等に関する情報公表加算は、1事業主につき1回限り申請が可能です。
申請する際は、「育休取得時」または「職場復帰時」のいずれかと併せて申請を行いましょう。
育児休業等支援コースの手続きの流れ

育児休業等支援コースにおける、育休取得時から職場復帰時の申請までの手続きの流れは、以下のとおりです。
- 就業規則を整備・周知し、育休復帰支援プラン作成のための面談を実施する
- 育休復帰支援プランを作成する
- プランに基づき業務の引き継ぎを行う
- 労働者が育児休業を3か月以上取得する
- 【育休取得時】の助成金を申請する
- 復職前に対象労働者へ業務情報や資料を提供する
- 労働者が職場に復帰し、6か月以上継続して就業する
- 【職場復帰時】の助成金を申請する
育児休業等支援コースは、育休の取得時から職場復帰時まで、各段階で申請手続きが必要となる制度です。支給を受けるには、それぞれのステップに応じた書類の準備や、申請期限の管理が不可欠となります。
必要な手続きや書類の確認や進行に不安がある場合は、社労士などの専門家に相談しながら進めることで、より確実に対応できます。
よくある質問

以下、育児休業等支援コースを活用するうえでよくある質問をまとめています。
Q1| 同じ男性労働者について、「育児休業等支援コース」と「子育てパパ支援助成金」の両方を申請できますか?
いいえ、同一の労働者が取得した同一の育児休業に対して、「育児休業等支援コース」と「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」の併給はできません。
育休の取得日数や申請上限を考慮して、いずれか一方の助成金を選んで申請する必要があります。
Q2.|助成金は事業所ごとに申請できますか?
助成金は事業主単位で支給される制度です。事業所ごと(支店や営業所ごと)ではなく、法人や団体全体としての申請となります。複数の事業所がある場合も、同一の事業主であればまとめて管理・申請する必要があります。
また、育児休業等支援コースは1事業主2回まで (無期雇用労働者・有期雇用労働者 各1回)が支給回数の上限となっていることに注意が必要です。
Q3| 育児休業中に次の子どもの産前・産後休業が重なった場合、職場復帰時の助成金申請期限はどうなりますか?
育児休業中に次子の産前・産後休業が開始する場合は、次子の産前・産後休業開始日を起算日としてカウントします。その日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内が申請期限となりますので、通常の期限とは異なります。
スケジュールの見直しが必要になるため、早めに確認しておくことが大切です。
まとめ|育児休業等支援コースの活用は社労士との連携が安心です
本記事では、両立支援等助成金の1つである「育児休業等支援コース」について、制度の種類、支給要件、申請の流れや注意点を詳しく解説しました。
育児休業等支援コースは、育児休業の取得と職場復帰の両方を段階的に支援することで、労働者の両立支援と企業の人材定着を後押しする制度です。
ただし、申請には細かい要件の確認や期日管理、書類準備などが求められ、企業単独での対応が難しい場合もあります。
育児休業等支援コースの申請に向けて、自社での対応が難しいと感じた場合は、社労士などの専門家と連携することも一つの選択肢です。
育児休業等支援コースについて社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めたうえで依頼しましょう。