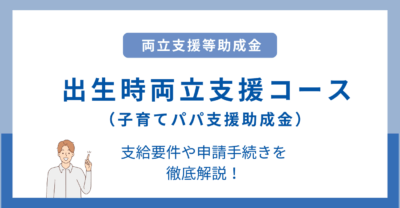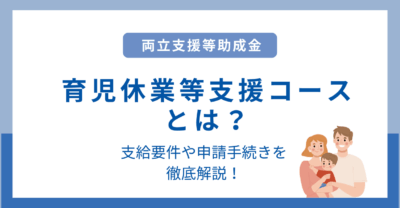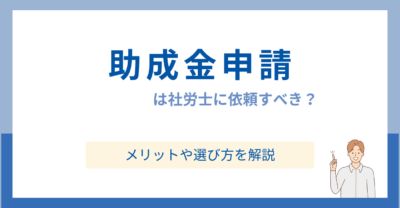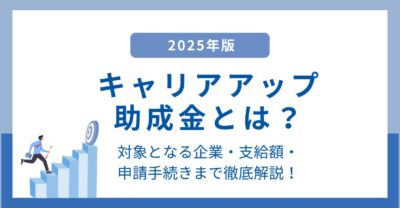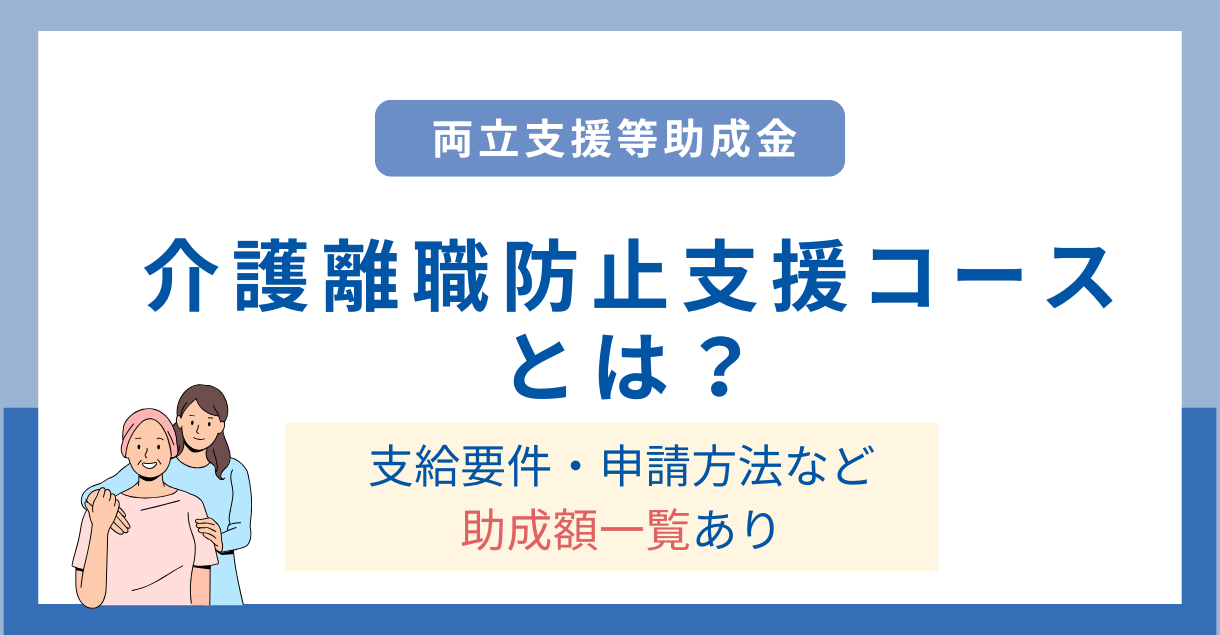
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の助成額や申請方法をわかりやすく解説!
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)は、労働者の介護離職を防ぐために、介護支援制度の導入や職場環境の整備を行った中小企業の事業主に対して、国から助成金が支給される制度です。
直近の調査では、毎年およそ10万人、過去5年間では47万人以上が介護を理由に離職しています(令和4年就業構造基本調査|総務省)。この制度を活用すれば、介護に直面した労働者の生活を守ると同時に、企業にとっても人材の定着や安定経営、さらには企業イメージ向上につながるメリットがあります。
一方で、助成金の活用には、就業規則の改訂や介護支援プランの作成、面談記録や代替要員の確保など、実務担当者にとって悩ましい準備が数多くあります。申請に不備があれば受給できない可能性もあるため、正確な理解と対応が欠かせません。
本記事では、介護離職防止支援コースの概要・助成額・支給要件・必要書類・申請の流れをわかりやすく整理しました。ぜひ最後までお読みいただき、自社の制度活用や助成金申請の円滑な実施にお役立てください。
※本記事は令和7(2025)年度の制度内容を元に作成しています。介護休業等の開始日により適用年度が異なる点にご注意ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
介護離職防止支援コースとは?|両立支援等助成金
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」(以下、介護離職防止支援コース)は、仕事と家族の介護を両立しやすい職場環境づくりを支援する、中小企業向けの助成金制度です。
申請にあたっては、対象労働者と面談を行い、個別に作成した「介護支援プラン※」に基づいて制度を実行する必要があります。
※介護支援プランとは
介護休業の取得や職場復帰を円滑に進めるために、事業主が労働者ごとに作成する、業務の整理や引き継ぎ方法などを具体的に盛り込んだ計画のことです。
なお、この制度は、厚生労働省が実施する「両立支援等助成金」の1つです。両立支援等助成金の全体像や各コースの概要については、こちらの記事をご覧下さい。
>【一覧表あり】両立支援等助成金とは?中小企業が知っておきたい6つのコースと申請方法
対象となる中小企業の規模
介護離職防止支援コースは、2025(令和7)年度時点で、中小企業のみが対象の助成制度です。
両立支援等助成金制度における「中小企業」とは、業種ごとに資本金(出資金)または常時雇用する労働者のいずれかが、下記基準以下である企業を指します。
| 業種 | 資本金または出資金 | 常時雇用する労働者数※ | |
|---|---|---|---|
| 小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
| その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
出典:厚生労働省|2025(令和7)年度両立支援等助成金のご案内(P.4)
※常時雇用する労働者とは、以下の両方を満たす者を指します。
- 2か月を超えて連続雇用される者(期間の定めがなく雇用される者、2か月を超える契約期間で雇用される者を含む)
- 週の所定労働時間が当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同じである者
申請を検討する際には、まず自社がこの中小企業の定義に該当するかを確認しておきましょう。
介護離職防止支援コースの助成額一覧

介護離職防止支援コースは、「介護休業」・「介護両立支援制度」・「業務代替支援」の3つの区分と「環境整備加算(加算措置)」に分かれており、それぞれ助成金の額が異なります。
3つの区分と加算措置の内容・支給額・上限回数の一覧は以下のとおりです。
【介護離職防止支援コース】
| 区分 | 内容 | 支給額(1人あたり) | 上限回数 |
|---|---|---|---|
| (1)介護休業 | 介護支援プランを作成し、プランに基づいて対象労働者が介護休業を取得・職場復帰した場合 | 40万円 (連続15日以上の休業:60万円) |
1事業主あたり5人まで |
| (2)介護両立支援制度 | 介護支援プランを作成し、介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度など、仕事と介護の両立支援制度を利用した場合 | 制度を1つ導入し、対象労働者が利用した場合: 20万円(合計60日以上の制度利用:30万円) 制度を2つ以上導入し、対象労働者が1つ以上利用した場合: 25万円(合計60日以上の制度利用:40万円) |
1事業主あたり5人まで |
| (3)業務代替支援 | 対象労働者(介護休業取得者または短時間勤務制度利用者)について、代替要員の新規雇用(派遣含む)、または業務を代替する労働者へ手当の支給を行った場合 | 新規雇用:20万円 (連続15日以上の休業の場合:30万円) |
1事業主あたり5人まで |
| 手当支給等(介護休業): 5万円(連続15日以上の休業の場合:10万円) |
|||
| 手当支給等(短時間勤務): 3万円 |
|||
| 環境整備加算※:10万円 ※定められた4つの「仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組」すべてを行った場合に支給 |
1事業主あたり1回限り | ||
出典:厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)|介護離職防止支援コース
最新の介護離職防止支援コースの助成額や注意点については、厚生労働省の「両立支援等助成金のご案内」ページにてご確認いただけます。
介護離職防止支援コースの3区分と加算措置の支給要件

介護離職防止支援コースの3区分(介護休業・介護両立支援制度・業務代替支援)と加算措置の支給要件は、それぞれ以下のとおりです。
介護離職防止支援コースを申請する際は、厚生労働省の「両立支援等助成金のご案内」ページにて、該当する年度の支給要件をご確認ください。
1.介護休業
「介護休業」は、介護支援プランを作成し、プランに基づいて対象労働者が介護休業を取得・職場復帰した場合に助成金が支給されます。
【介護休業の支給要件】
- 労働者の介護休業の取得や職場復帰を支援する方針を定め、その内容を社内に周知していること。
- 対象労働者と面談などを行い、その内容を「面談シート兼介護支援プラン」に記録したうえで、介護支援プランを作成していること。
- 作成した介護支援プランに基づいて、業務の整理や引き継ぎを実施していること。
- 対象労働者が、連続して5日以上の介護休業を取得していること。
- 介護休業制度および所定労働時間の短縮などの措置を、労働協約または就業規則に明記していること。
- 労働者の職場復帰後にフォロー面談を実施し、その内容を記録していること。
- 介護休業取得者を原職またはこれに準ずる職務に復帰させる旨を、労働協約または就業規則に規定していること。
- 介護休業が終了した後、原則として対象労働者を原職等に復帰させ、その後3か月以上継続して雇用していること。
- 介護休業開始日から支給申請日までの間、対象労働者を雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
なお、介護休業が2025(令和7)年3月31日以前に開始している場合は令和6年以前の支給要件が適用されますので令和6年以前のパンフレットをご確認ください。
2.介護両立支援制度
「介護両立支援制度」は、介護支援プランを作成し、企業が介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などを導入し、対象労働者がそれらの介護両立支援制度を利用した場合に助成金が支給されます。
【介護両立支援制度の支給要件】
- 介護支援プランに基づき、労働者の仕事と介護の両立を支援するという企業の方針を社内に周知していること。
- 対象労働者と面談等を実施し、その内容を「面談シート兼介護支援プラン」に記録したうえで、介護支援プランを作成していること。
- 介護両立支援制度に関する内容を、労働協約または就業規則に明記していること。
- 対象労働者が、就業規則等に基づく介護両立支援制度を実際に利用したこと。
- 対象労働者が、介護両立支援制度の利用終了後も1か月以上継続して雇用されていること。
- 対象労働者を、介護両立支援制度の利用開始日から支給申請日までの間、雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
なお、支給対象となる「介護両立支援制度」とは、以下の8つの制度を指します。
- 所定外労働の制限制度
- 時差出勤制度
- 深夜業の制限制度
- 短時間勤務制度
- 介護のための在宅勤務制度
- (法を上回る)介護休暇制度
- 介護のためのフレックスタイム制度
- 介護サービス費用補助制度
制度別に利用要件や対象となる労働者が定められています。導入の際には厚生労働省の「両立支援等助成金のご案内」ページで詳細をご確認ください。
なお、介護両立支援制度の利用が2025(令和7)年3月31日以前に開始している場合は令和6年以前の支給要件が適用されますので令和6年以前のパンフレットをご確認ください。
3.業務代替支援
「業務代替支援」の助成金は以下の3つに分けられ、それぞれ支給要件が異なります。
業務代替支援(新規雇用)
- 対象労働者(介護休業を取得した者)の業務代替要員を、新たに雇い入れるか、または新たに派遣を受け入れることで確保していること。
- 対象労働者に、連続して5日以上の介護休業を取得させていること。
- 対象労働者を、介護休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
- 介護休業制度および所定労働時間の短縮等の措置を、労働協約または就業規則に明記していること。
業務代替支援(手当支給等:介護休業)
- 対象労働者の業務を、事業主が雇用する別の労働者(業務代替者)に引き継ぎ、代替させていること。
- 業務の見直しや効率化のための取組を、対象労働者の介護休業開始日の前日までに実施していること。
- 代替業務に対応した賃金制度を、労働協約または就業規則に定め、その制度に基づき、業務代替期間中の業務代替者の賃金を増額していること。
- 対象労働者が、連続して5日以上の介護休業を取得していること。
- 対象労働者を、介護休業開始日から支給申請日までの間、雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
- 介護休業制度および所定労働時間の短縮等の措置を、労働協約または就業規則に明記していること。
業務代替支援(手当支給等:短時間勤務)
- 対象労働者の業務を、事業主が雇用する別の労働者(業務代替者)に引き継ぎ、代替させていること。
- 業務の見直しや効率化のための取組を、対象労働者の短時間勤務開始日の前日までに実施していること。
- 代替業務に対応する賃金制度を労働協約または就業規則に定め、その制度に基づき、業務代替期間中の業務代替者の賃金を増額していること。
- 対象労働者が、合計で15日以上の介護のための短時間勤務制度を利用していること。
- 対象労働者を、短時間勤務制度の利用開始日から支給申請日までの間、雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
- 介護休業制度および所定労働時間の短縮等の措置を、労働協約または就業規則に明記していること。
4.雇用環境整備加算(加算措置)
「環境整備加算」とは、1から3のいずれかの支給要件を満たしたうえで、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取り組みを行った場合に加算される支給金です。
仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取り組みとは、以下の4つです。
- 雇用する労働者に対する介護休業および介護両立支援制度に係る研修の実施
- 介護休業及び介護両立支援制度に関する相談体制の整備
- 介護休業および介護両立支援制度の取得・利用に関する事例の収集および提供
- 雇用する労働者に対する介護休業および介護両立支援制度に関する制度、介護休業等の取得・利用の促進に関する方針の周知
雇用環境整備加算を支給するには、4つすべてを実施する必要があります。
介護離職防止支援コースの申請に必要な書類

介護離職防止支援コースの助成金申請に必要な書類は、申請する3つの区分(介護休業・介護両立支援制度・業務代替支援)と雇用環境整備加算で異なります。
それぞれの助成金で用意する申請書類は、以下のとおりです。
申請に必要な書類の詳細は、厚生労働省の「両立支援等助成金のご案内」ページ内にある該当年度の『両立支援等助成金支給申請の手引き』でご確認ください。
なお、助成金を申請する際に必要な様式も上記ご案内ぺージからダウンロード可能です。必ず該当年度版であるかを確認してから使用しましょう。
1.介護休業
- 介護離職防止支援コース(介護休業)支給申請書 (【介】様式第1号①②)
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 面談シート兼介護支援プラン(【介】様式第5号)
- 介護支援プランに基づく介護休業・復帰支援方針を、事前に周知した事実と日付が確認できる書類
- 労働協約または就業規則、関連する労使協定
- 対象労働者の雇用契約書、労働条件通知書など
- 対象労働者の介護休業申出書
- 介護休業前1か月分及び職場復帰後3か月分の就業実績、及び介護休業期間における休業状況が確認できる書類(出勤簿・タイムカード・賃金台帳など)
- 介護休業期間及び職場復帰後3か月分の所定労働日が確認できる書類(就業規則・労働条件通知書・企業カレンダー・勤務シフト表など)
- 対象労働者の家族が要介護状態であることが確認できる書類(介護保険被保険者証・師等が交付する証明書類など)
<職場復帰後に、介護短時間勤務を利用する場合> - 介護短時間勤務の申出書
- 賃金計算方法が確認できる書類(申立書など)
<過去に申請を行ったことのある事業主> - 提出を省略する書類についての確認書(【介】様式第4号)
<初めて雇用関係助成金を申請する事業主> - 支払方法・受取人住所届及び支払口座が確認できる通帳等の写し
2.介護両立支援制度
- 介護離職防止支援コース(介護両立支援制度)支給申請書 (【介】様式第2号①②)
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 面談シート兼介護支援プラン(【介】様式第5号)
- 介護支援プランに基づく介護休業・復帰支援方針を、事前に周知した事実と日付が確認できる書類
- 労働協約または就業規則、関連する労使協定
- 対象となる労働者の雇用形態、所定労働日数及び所定労働時間が確認できる書類(雇用契約書・労働条件通知書・会社カレンダー・勤務シフト表など)
- 対象労働者の介護両立支援制度利用申出書
- 制度利用開始前1か月分(所定外労働の制限制度または深夜業の制限制度の利用者にあっては制度利用前3か月分)及び制度利用要件を満たす日の翌日から1か月分の就業実績が確認できる書類。(出勤簿・タイムカード・賃金台帳など)
- 対象労働者の家族が要介護状態であることが確認できる書類(介護保険被保険者証・師等が交付する証明書類など)
<利用した介護両立支援制度に応じて> - 介護のための短時間勤務制度:短時間制度利用開始前の1か月分及び制度利用20日分の賃金台帳、賃金の取扱を定めた制度
- 介護のための在宅勤務制度:在宅勤務申出書及び実施報告書(実施報告書がない場合はそれに準じた書類)
- (法を上回る)介護休暇制度:介護休暇制度の取得申出に係る書類及びその取得実績が確認できる書類
- 介護サービス費用補助制度:介護サービス利用者に対して事業所が費用の一部または全部を補助したことが分かる書類(介護サービス利用時の領収書など)
<初めて雇用関係助成金を申請する事業主> - 支払方法・受取人住所届及び支払口座が確認できる通帳等の写し
3.業務代替支援
①業務代替支援(新規雇用)
- 介護離職防止支援コース(業務代替支援:新規雇用)支給申請書(【介】様式第3号①②)
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 労働協約または就業規則、関連する労使協定
- 対象となる労働者の雇用形態が確認できる書類(雇用契約書・労働条件通知書など)
- 対象労働者の介護休業申出書
- 対象労働者の家族が要介護状態であることが確認できる書類(介護保険被保険者証・医師等が交付する証明書類など)
- 介護休業取得者および代替要員の部署・職務所定労働時間・所定労働日または所定労働日数が確認できる書類(組織図・労働条件通知書・企業カレンダーなど)
- 代替要員の雇い入れ日から介護休業終了日までの分の勤務状況が確認できる書類(代替要員の出勤簿・賃金台帳など)
- 代替要員が新たに雇い入れられた時期または新たに派遣された時期が確認できる書類(代替要員の労働条件通知書・辞令など)
<過去に申請を行ったことのある事業主> - 提出を省略する書類についての確認書(【介】様式第4号)
②業務代替支援(手当支給等:介護休業)
- 介護離職防止支援コース(業務代替支援:手当支給等(介護休業))支給申請書(【介】様式第3号①③)
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 労働協約または就業規則、関連する労使協定
- 対象労働者の家族が要介護状態であることが確認できる書類(介護保険被保険者証・医師等が交付する証明書類など)
- 対象となる労働者の雇用形態が確認できる書類(雇用契約書・労働条件通知書など)
- 対象労働者の介護休業申出書
- 介護休業期間の所定労働日が確認できる書類(就業規則・企業カレンダーなど)
- 対象介護休業取得者及び業務代替者が所属する部署全体または事業所全体の業務分担が確認できる書類(事務分担表など)
- 業務代替前1か月分および業務代替期間5日間分の業務代替者の賃金台帳
- 業務代替者の所定労働時間、所定労働日または所定労働日数が確認できる書類(業務代替者の労働条件通知書)
- 業務代替期間5日間を含む業務代替者のタイムカード、賃金台帳など
<過去に申請を行ったことのある事業主> - 提出を省略する書類についての確認書(【介】様式第4号)
③業務代替支援(手当支給等:短時間勤務)
- 介護離職防止支援コース(業務代替支援:手当支給等(短時間勤務)支給申請書(【介】様式第3号①④)
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 労働協約または就業規則、関連する労使協定
- 対象労働者の家族が要介護状態であることが確認できる書類(介護保険被保険者証・医師等が交付する証明書類など)
- 対象となる労働者の雇用形態が確認できる書類(雇用契約書・労働条件通知書など)
- 対象労働者の短時間勤務申出書
- 短時間勤務期間の所定労働日が確認できる書類(就業規則・企業カレンダーなど)
- 対象短時間勤務者及び業務代替者が所属する部署全体または事業所全体の業務分担が確認できる書類(事務分担表など)
- 業務代替前1か月分及び業務代替期間15日間分の業務代替者の賃金台帳
- 業務代替者の所定労働時間、所定労働日または所定労働日数が確認できる書類(業務代替者の労働条件通知書)
- 業務代替期間15日間を含む業務代替者のタイムカード、賃金台帳など
<過去に申請を行ったことのある事業主> - 提出を省略する書類についての確認書(【介】様式第4号)
4.雇用環境整備加算(加算措置)
介護離職防止支援コースで雇用環境整備加算を申請する際は、加算を申請する助成金(介護休業・介護両立支援制度・業務代替支援のいずれか)と同時に提出します。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 介護離職防止支援コース(環境整備加算)支給申請書(【介】様式第6号)
- 雇用環境整備の措置を4つすべて実施していることが確認できる書類
介護離職防止支援コースの申請の流れ

介護離職防止支援コース(介護休暇・介護両立支援制度・業務代替支援)の支給申請までの流れは、以下のとおりです。区分ごとにステップが異なるので確認しておきましょう。
【ステップ1】就業規則等への明文化・労働者への周知
介護休業制度や短時間勤務制度など、制度の内容を就業規則等に明記し、労働者へ周知します。育児介護休業法への委任規定(「育児介護休業法第●条に定めるところによる」というような規定の仕方)は認められていませんので注意しましょう。
なお、周知は原則として、対象労働者の介護休業開始日の前日までに行っている必要がありますが、介護休暇開始と同時進行で作成も可能です。
【ステップ2】労働者との面談・介護支援プランの作成 ※介護休業と介護両立支援制度のみ
対象となる労働者と面談を行い、「面談シート兼介護支援プラン」を作成します。これにより、介護休業の取得や職場復帰に向けた支援方針を具体化します。
介護支援プランは原則として介護休業開始前に作成します。介護休業終了後にプラン作成や面談を行った場合は支給対象外となります。
【ステップ3】区分(介護休暇・介護両立支援制度・業務代替支援)ごとの取り組み
<介護休暇の場合>
- 介護支援プランに基づき、業務の整理や引き継ぎを実施する
- 対象労働者が連続5日以上の介護休業・職場復帰を取得する
- 職場復帰後、3か月以上かつ申請日までの雇用継続を確認する
<介護両立支援制度の場合>
- 介護支援プランに基づき、業務体制の見直しを実施する
- 介護両立支援制度(8制度のうち1つ以上)の導入する
- 対象労働者が導入した制度を利用し、制度利用終了日後1か月以上かつ申請日までの雇用継続を確認する
<業務代替支援の場合>
- 介護休業や短時間勤務を取得する労働者の業務を代替する体制を整備する
(新規雇用・派遣、または既存労働者への代替業務+手当支給) - 代替要員の就労状況を確認する
【ステップ4】支給申請
- 事業主の人事労務管理の機能を有する部署の所在地を管轄する、労働局雇用環境・均等部(室)へ、必要書類を揃えて申請を行う
申請期限は、介護離職防止支援コースの区分や、介護両立支援制度の内容によって異なります。
詳しい申請手続きの期限については、必ず厚生労働省の「両立支援等助成金のご案内」ページ内にある、該当年度の『両立支援等助成金支給申請の手引き』で内容をご確認ください。
まとめ|介護離職防止支援コースの制度を理解し、確実に申請を進めましょう
本記事では、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の制度概要、助成額、支給要件、申請に必要な書類、さらに申請の流れについて詳しく解説しました。
介護離職防止支援コースは、労働者が仕事と介護を両立できるよう支援することで、介護を理由とした離職を防止し、人材の定着や企業の安定経営につなげることを目的とした制度です。企業にとっても、優秀な人材の確保や働きやすい職場づくりを内外に示せる大きなメリットがあります。
一方で、就業規則の改訂や介護支援プランの作成、面談記録や代替要員確保の証明など、申請には多くの要件を満たす必要があります。特に、書類不備や申請期限の遅れは支給不可につながるため、実務担当者の負担は少なくありません。
申請の手間や不安を軽減し、確実に助成金を受給するためには、社労士に早めに相談することをおすすめします。
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。