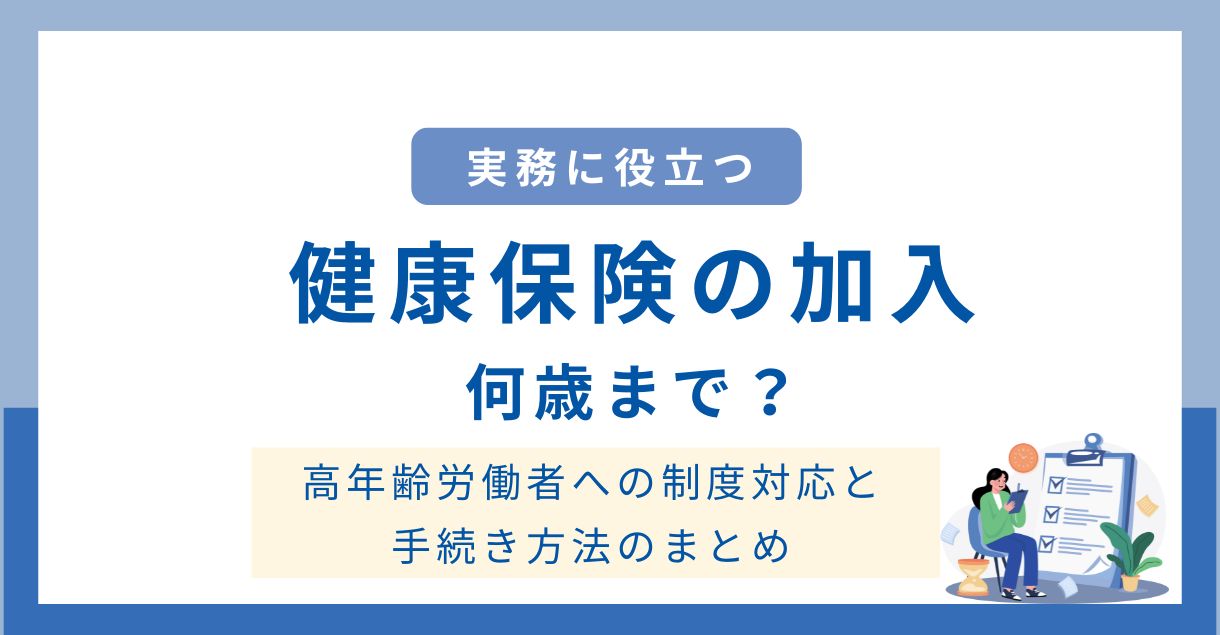
健康保険は何歳まで?高年齢労働者への手続き対応と実務ポイントをわかりやすく解説!
近年、高年齢者の就業機会が増えるなか、「健康保険は何歳まで加入できるのか」「65歳以降の高年齢労働者の健康保険はどうなるのか」と疑問に思う企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
特に65歳以上の労働者を雇用・再雇用する企業では、制度の正しい理解とトラブル防止に向けた実務対応が欠かせません。
本記事では、「健康保険は何歳まで対象になるのか」という基本から、75歳到達時の後期高齢者医療制度への移行、さらに加入・資格喪失・再雇用時の手続きまで、企業が押さえておきたいポイントをわかりやすくまとめています。
高年齢者の健康保険の手続きや資格喪失・再雇用時の手続きに不安がある人事・労務ご担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
内容
健康保険の対象は何歳まで?|基本制度と加入条件

健康保険は、企業に雇用される労働者とその労働者に扶養される家族(被扶養者)が医療給付を受けられる公的制度で、加入できる年齢に上限があります。
ここでは、健康保険に加入できる年齢の上限と、75歳以降に移行する「後期高齢者医療制度」について、被保険者・被扶養者のケースに分けて解説します。
被保険者の対象年齢は75歳未満まで
健康保険は、一定の要件に該当する75歳未満の方が対象です。75歳の誕生日を迎えると、後期高齢者医療制度へ移行し、健康保険の被保険者資格は喪失します。
75歳で後期高齢者医療制度に移行
被保険者は75歳の誕生日に健康保険の資格を喪失し、誕生日の翌日から後期高齢者医療制度の被保険者へ切り替わります。
被保険者本人の申請は不要ですが、企業には「被保険者資格喪失届」の提出義務があるため、対象者の誕生日を事前に把握しておく必要があります。
「被扶養者」の年齢制限と認定要件
被扶養者も、原則として75歳未満の方が健康保険の加入対象です。
被保険者と同様に、75歳に到達すると健康保険の資格を喪失し、個人で後期高齢者医療制度へ移行します。
その際、企業は「被扶養者(異動)届」を提出する必要があるため、労働者本人だけでなくその家族の年齢も把握しておくことが求められます。
なお、健康保険の被扶養者として認定されるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
【収入条件】 年間収入※130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ
※年間収入は、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の1年間に見込まれる収入額を指します。収入には、雇用保険の失業等給付・公的年金・健康保険の各種手当金も含むため、計算には注意が必要です。 要件を満たす具体的な金額は下記の通りです。
【同世帯の条件】 (ア)被保険者と同居していなくても認められる方:
(イ)被保険者と同居していることが必要な方:
|
参考:日本年金機構|従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|1.手続き内容
被保険者・被扶養者ともに、健康保険の加入は原則として75歳未満までとなり、以降は後期高齢者医療制度に移行します。
次章では、75歳以降に切り替わる「後期高齢者医療制度」の概要と、企業が行うべき実務対応について詳しく見ていきましょう。
75歳以降の健康保険「後期高齢者医療制度」

健康保険の被保険者や被扶養者は、75歳の誕生日を迎えると、健康保険の資格を喪失し「後期高齢者医療制度」へ移行します。
この制度への移行にあたっては、企業側でも「資格喪失届の提出」や被扶養者が75歳に到達した場合「被扶養者異動届の提出」といった具体的な対応が求められます。
以下に、その制度概要と企業が行うべき手続きを解説します。
「後期高齢者医療制度」とは
「後期高齢者医療制度」の対象は、75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方です。
75歳の誕生日に到達した時点で、それまでの健康保険資格を喪失し、居住地の都道府県が加入する後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療制度に加入します。
人事・総務担当者が押さえるべき実務ポイントは、以下のとおりです。
|
詳細は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
資格喪失にともなう企業の手続き
75歳の誕生日を迎えた労働者やその被扶養者が健康保険の資格を喪失した際には、それぞれ以下の手続きが必要となります。
-
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」の提出
労働者が75歳になり資格喪失した場合、届出には通常の退職時と同じ「被保険者資格喪失届」の様式を使用します。
基本的な記入事項に加えて、喪失原因では「75歳到達」を選択します。
※70歳以上の方で退職による資格喪失の場合は、様式下部の「70歳以上被用者不該当」にチェックを入れ、「不該当年月日」欄には退職日を記載します。
-
「健康保険被扶養者(異動)届」の提出
被扶養者が75歳になり資格喪失した場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を使用します。
様式内の「非該当」の欄にチェックを入れ、異動の理由は「75歳到達」、異動日は誕生日の当日とします。
また、被保険者が資格を喪失すると、扶養に入っていた家族は自動的に健康保険の被扶養者資格を失います。その場合、75歳未満の被扶養者であった方は、国民健康保険に加入することとなるため居住地の市区町村で手続きをする必要があります。

出典:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
-
健康保険被保険者証・高齢受給者証などの返却
退職後の手続きにあたっては、すでに交付されている証類(資格確認書および健康保険被保険者証・高齢受給者証など)がある場合には、届出に添付して返却する必要があります。
もし紛失などで回収できない場合は、届出の際に「回収不能届」の添付が必要です。
なお、いずれの届出の提出も、資格喪失日の翌日から5日以内と定められています。
健康保険の「任意継続被保険者制度」は75歳未満まで利用可能

労働者が退職後も在職中と同じ健康保険に引き続き加入したい場合は、「任意継続被保険者制度」を利用できます。
この制度は、75歳未満の労働者を対象とし、退職前に加入していた健康保険を本人の希望により最大2年間継続して加入できる仕組みです。なお、この制度は労働者本人が申請する制度であるため、企業が手続きをする必要はありません。
ただし、退職日が確認できる書類が申請に必要であるため、資格喪失届のコピーなど資格喪失の事実が確認できる書類を退職する労働者へ速やかに渡さなければなりません。
加入中でも、75歳の誕生日を迎えると「後期高齢者医療制度」に自動移行するため、任意継続被保険者の資格は喪失します。
任意継続被保険者になるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
|
※保険者:協会けんぽまたは健康保険組合
任意継続被保険者になると、労働者は在職中に被保険者であったときとほぼ変わらない条件で保険給付および健康診断などを受けられます。
退職した労働者が負担する健康保険料は、以下のとおりになります。
| 退職時の標準報酬月額(上限あり)× 都道府県ごとの保険料額 |
なお、任意継続期間が終了した時点で75歳未満である場合には、国民健康保険に切り替える必要があります。
企業担当者は、任意継続被保険者制度について理解し、制度利用を希望する退職者へ手続きについて伝えられるようにしておきましょう。
健康保険手続き方法―加入・資格喪失・再雇用時

健康保険は「70歳以上」「75歳到達」などの節目ごとに適用範囲や必要手続きが変わります。
高年齢の労働者を雇用または再雇用する企業には、年齢ごとの制度の違いを正確に把握して対応することが求められます。
以下では、状況別に企業が行うべき手続きを整理します。
労働者の健康保険の加入手続き
健康保険は、加入条件を満たしていれば75歳の誕生日まで継続して加入できます。
また、75歳未満の高年齢の労働者を新たに雇用する場合も、健康保険の手続きが必要です。
以下は、健康保険の加入手続きに関する実務対応の概要です。
- 必要書類:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 提出先:企業が加入している協会けんぽや健康保険組合
- 提出期限:雇用開始日(=資格取得日)から5日以内
- 提出方法:電子申請・窓口・郵送のいずれか

なお、70歳以上75歳未満の被保険者には、「健康保険証」と「高齢受給者証」の2種類が交付されます。2024年12月2日以降は、どちらも原則マイナ保険証と一体化されているので、事前に本人へ説明しておくとスムーズです。
健康保険を資格喪失する際の手続き
労働者が75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に移行した場合や、退職した場合には、健康保険の資格が喪失します。
資格喪失年月日は喪失原因によって異なるため、以下を参考にしてください。
| 喪失の原因 | 喪失年月日 |
| 退職等による資格喪失 | 退職日の翌日、転勤の当日、雇用契約変更の当日 |
| 死亡による資格喪失 | 死亡日の翌日 |
| 75歳到達による健康保険の資格喪失
(後期高齢者医療制度への移行) |
誕生日の当日 |
| 障害認定による健康保険の資格喪失 | 認定日の当日 |
| 社会保障協定による健康保険の資格喪失 | 社会保障協定発効の当日、相手国法令の適用となった日の翌日 |
参考:日本年金機構|従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き
資格喪失の手続き概要は、以下の通りです。
- 必要書類:健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
- 提出先:企業が加入している協会けんぽや健康保険組合
- 提出期限:被保険者資格を喪失した日から5日以内
- 提出方法:電子申請・窓口・郵送のいずれか

喪失届提出の際は、発行済みの健康保険被保険者証(本人・被扶養者分)や各種受給者証の添付が必要です。企業は速やかな回収を進めましょう。
再雇用契約時の手続き
60歳以上の労働者を定年後に再雇用する場合は、「退職」と「再雇用」という2つの手続きをそれぞれ行う必要があります。これは、再雇用が新たな雇用契約とみなされるためです。
なお、同じ企業で1日も空けずに再雇用する「継続雇用」のケースでは、退職日と再雇用日を記載した事業主の証明書(様式自由)を添付すると、2つの届出を同一日付で処理できます(同日得喪)。再雇用時に同日得喪を行うと、すぐに給与に見合った社会保険料になるというメリットもあります。
再雇用時の健康保険手続きは、資格の切れ目を防ぐうえでも重要です。提出期限の管理や社内での情報共有を徹底し、漏れのない対応を心がけましょう。
70歳以上の社会保険については、こちらの記事をご覧ください。
(関連記事:【年齢別】70歳以上の社会保険対応とは?必要な手続き・書類を詳しく解説!)
退職時の健康保険の対応ポイント

退職時は、資格喪失手続きとあわせて企業の案内対応が問われる重要な場面です。
ここからは、退職時の健康保険に関する実務ポイントを整理します。
ポイント①|退職者が選べる「健康保険の3つの選択肢」を正しく案内する
公的医療保険制度への加入は、すべての国民に求められている義務です。
退職後の健康保険は、退職者の状況に応じて、次の3つの選択肢から選ぶ必要があります。
1、任意継続被保険者制度を利用する
任意継続被保険者制度は、在職中と同じ健康保険に、退職後も継続して加入できる制度です。
任意継続の利用期間は最長2年ですが、75歳の誕生日を迎えた時点で、たとえ2年未満でも資格は自動的に喪失するため注意が必要です。
任意継続被保険者制度に関しては、ページ内「健康保険の任意継続被保険者制度は75歳未満まで利用可能」で詳しく解説しています。
2、国民健康保険に加入する
他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入していない方は、市区町村が運営する国民健康保険に加入できます。
保険料は所得や世帯構成に応じて決まり、原則として加入者本人が全額自己負担する仕組みです。
加入手続きは本人が行い、退職後14日以内に住民票のある市町村や国民健康保険組合の窓口へ、資格喪失証明書などの関係書類を提出します。
3、家族(被保険者)の扶養に入る
退職後、一定の条件(年収・同居など)を満たせば、家族の健康保険の被扶養者として加入できます。この場合、保険料の自己負担はありません。
手続きは被保険者の事業主を通じて、退職後5日以内に、家族が加入している保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)へ申請を行います。
労働者より、「家族が退職したため扶養に入れたい」と申出があった場合の必要書類は「健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届」で、添付書類の内容は、被扶養者の年齢・同居・収入状況などにより異なります。
退職者の年齢や収入、家族状況に応じて適切な制度を案内し、円滑な移行支援を行いましょう。
被扶養者と認められる条件はページ内「「被扶養者」の年齢制限と認定要件」をご確認下さい。
ポイント②|資格喪失届の提出期限と提出方法に注意
退職によって被保険者資格が喪失されるため、その確認と届出は企業にとって重要な対応業務の一つです。
手続きが遅れると、医療機関での負担増加や退職前の基準による保険料の過徴収など、実務上のトラブルを招くおそれがあります。
退職日を正確に把握し、スケジュールに沿って早めに準備を進めましょう。
具体的な手続きについては、ページ内「健康保険を資格喪失する際の手続き」をご確認下さい。
まとめ|75歳までの健康保険の対応に備えましょう
高年齢の労働者に関する健康保険制度は、75歳を境に大きく切り替わるため、企業には計画的な対応が求められます。
一部の手続きは制度上自動で進みますが、資格喪失の届出や交付済みの保険証の回収、再雇用時の再手続きなど、企業が担うべき実務も多く存在します。
とくに被扶養者の資格管理や任意継続被保険者制度の案内などは見落としやすく、スケジュールを正確に把握し、社内での情報共有を徹底することが重要です。
対応を後回しにすれば、保険料の誤徴収や医療機関での負担増など、思わぬトラブルを招くおそれもあります。
制度の正確な理解とスムーズな運用のためには、社会保険労務士など専門家との連携を図ることも有効な選択肢です。
75歳までの健康保険について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。














