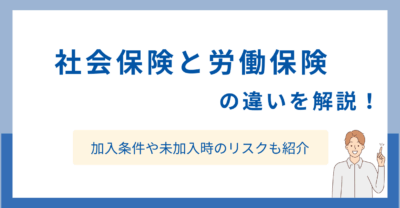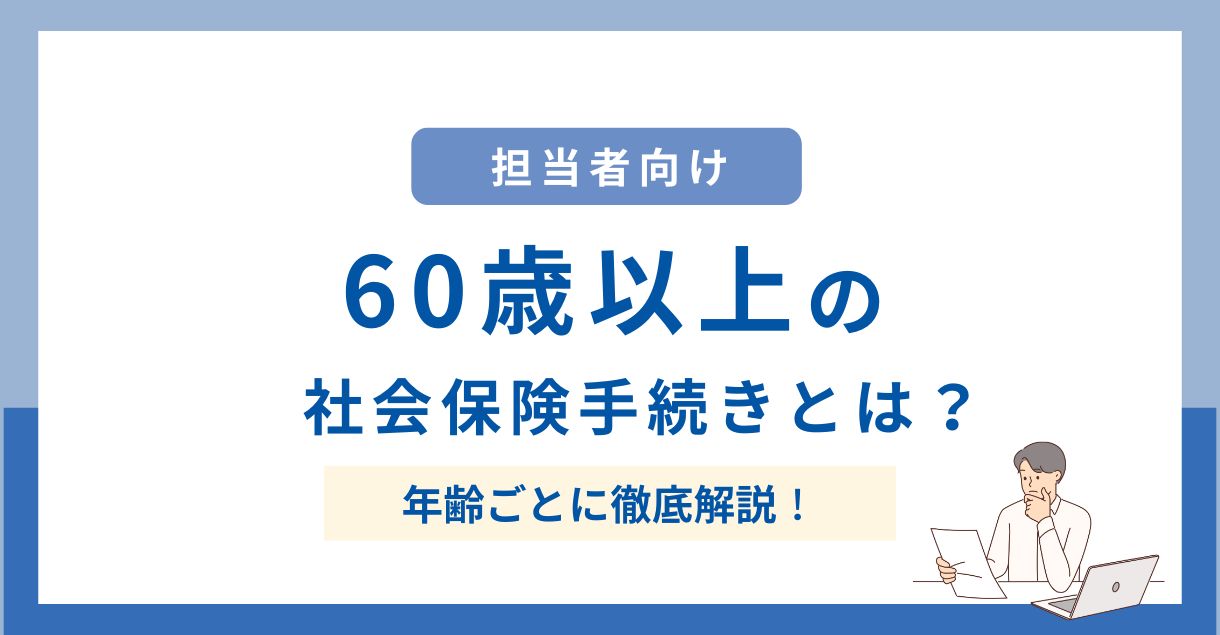
【担当者向け】60歳以上の労働者に必要な社会保険手続きとは?年齢別で徹底解説!
企業の定年延長や年金支給開始年齢の引き上げにより、60歳以降も働き続ける労働者が年々増加しています。
こうした状況において、企業側も高年齢労働者に対する社会保険手続きへの理解と対応が求められます。
しかし、社会保険の制度は「60歳」「65歳」「70歳」「75歳」の年齢ごとに適用内容が異なり、雇用形態によっても必要な手続きが変わるため、実務は非常に複雑です。
そのなかでも本記事では、企業の人事・労務担当者向けに、60歳以上の労働者に必要な社会保険手続きを年齢別で整理しています。
「いつ・何を・どのように対応するか」が明確になる記事になっていますので、実務対応の参考としてぜひご活用ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
| ※本記事では、主に60歳~70歳未満の社会保険について解説しています。
70歳以上の社会保険手続き(健康保険、厚生年金保険、介護保険)につきましては、以下の記事からご参考いただけます。あわせてご活用ください。 |
社会保険の加入対象年齢をおさらい

社会保険の加入対象年齢は、制度ごとに上限が異なります。
特に、企業が60歳以上の高年齢労働者を雇用・継続雇用する際には、それぞれの制度で「何歳まで加入できるのか」を正しく理解しておく必要があります。
以下、各社会保険制度ごとに、適用事業所で雇用された労働者の加入対象年齢の上限を整理しましょう。
健康保険:75歳未満
健康保険は、一定の要件を満たす75歳未満の労働者が対象です。
75歳に達すると、後期高齢者医療制度の対象となり、健康保険の被保険者資格は喪失します。
75歳までの健康保険については、この記事でくわしく説明しています。
(関連記事:健康保険は何歳まで?高年齢労働者への手続き対応と実務ポイントをわかりやすく解説!)
厚生年金保険:70歳未満
厚生年金保険は、一定の要件を満たす70歳未満の労働者が対象です。
企業に雇用されていても、70歳に達した時点で厚生年金の被保険者資格は喪失し、それ以降は保険料納付も不要となります。
介護保険:40歳以上
介護保険は、40歳以上の方が対象です。
40歳以上65歳未満は、健康保険の被保険者である労働者が「第2号被保険者」となり、企業が給与から介護保険料を徴収・納付します。
(会社の健康保険ではなく、国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料と合わせて市区町村に納付します。)
65歳以上になると、雇用の有無にかかわらずすべての方が「第1号被保険者」となり、市区町村が介護保険料を徴収します。
雇用保険:年齢上限なし(一定の要件を満たす労働者)
雇用保険は、年齢に関係なく、一定の要件を満たす労働者が対象です。
【適用要件】1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること。 |
65歳以上の労働者も上記の加入要件を満たす場合は、「高年齢被保険者」として加入対象となります。また、失業時に受給要件を満たしている場合は65歳未満と異なる「高年齢求職者給付金」が支給されます。
65歳以上の雇用保険については、こちらで詳しく解説しています。
(関連記事:雇用保険の加入は何歳まで?65歳以上の加入要件や再雇用時の手続きを徹底解説!)
労災保険:年齢上限なし(すべての労働者)
労災保険は、労働者を1人でも雇用している事業所であれば必ず適用され、年齢や雇用形態に関係なくすべての労働者が対象です。
60歳以上の定年退職時の社会保険手続き

60歳以上70歳未満の労働者に必要な社会保険の手続きについて、状況別に解説します。
| ※本記事では、全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)および日本年金機構に加入している企業を前提として解説しています。
健康保険組合に加入している企業の場合、日本年金機構への提出に加え、該当する組合にも書類の届出が必要です。詳細な提出書類や方法については、各組合に直接ご確認ください。 |
健康保険・厚生年金の手続き
退職により、健康保険および厚生年金の被保険者資格を喪失します。
企業は以下の書類を用意する必要があります。
【提出書類】
【添付書類(協会けんぽの場合)】
- 健康保険被保険者証(本人および被扶養者分)
- 高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
いずれも現在交付されている場合のみ、企業が労働者から回収し、返却を行います。また、届出の提出と同時に返却できない場合は、「回収不能届」をすみやかに提出する必要があります。
【提出先】
日本年金機構が設置する地域ごとの事務センター、または事業所の地域を管轄する年金事務所
【提出期限】
退職日の翌日(=資格喪失日)から5日以内
退職後の健康保険には、次の3つの選択肢があります。
- 任意継続被保険者として、在職中と同じ健康保険に継続加入する。
- 国民健康保険に加入する。
- 家族の健康保険の被扶養者になる。
企業が行う手続きはありませんが、制度の概要や申請期限(任意継続被保険者となる手続きは、退職日の翌日から20日以内)を事前に案内しておくと親切です。
雇用保険の手続き
定年退職時の雇用保険手続きでは、企業が被保険者資格喪失届を、所轄のハローワークへ提出します。
被保険者が雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の給付を希望する場合は、離職証明書も併せて提出します。
必要な書類は以下のとおりです。
【提出書類】
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- (離職票が必要な場合)雇用保険被保険者離職証明書
※複写式のため、ハローワーク窓口もしくは郵送で取得
【添付書類】
- 雇用時の賃金支払状況がわかる書類(賃金台帳・労働者名簿・出勤簿など)
- 有期雇用期間の満了により離職したことがわかる書類(就業規則など)
【提出先】
所轄のハローワーク
【提出期限】
被保険者でなくなった日(=退職日)の翌日から10日以内
離職証明書を提出すると、ハローワークから企業宛に「雇用保険被保険者離職票-1(資格喪失確認通知書)」「雇用保険被保険者離職票-2」が交付されます。
企業は受領後、記載内容(離職理由や賃金額)に誤りがないか確認し、速やかに退職者本人へ交付しましょう。
60歳以上の再雇用時の社会保険手続き

再雇用後に給与が下がる場合(※)は、定年退職時に「資格喪失届」と「資格取得届」を同じ日に提出することで、社会保険料の負担を軽くすることができます。
※定年を迎え、就業規則等に基づく定年後の継続雇用により賃金額が低下し、標準報酬の等級が1等級以上低下する場合。
この手続きのことを「同日得喪(どうじつとくそう)」といいます。
| 同日得喪の手続きとは:
使用関係が一旦中断したものとみなし、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できる任意の手続きです。 企業は「資格喪失届」と「資格取得届」を同じ日に提出し、資格取得届の備考欄にある「退職後の継続再雇用者の取得」に〇をする必要があります。 |
企業にとっても、社会保険料を見直し、負担を適正化するタイミングとして重要な手続きです。
健康保険・厚生年金の扱い
定年退職後に同じ会社で再雇用する場合、退職と再雇用の間に空白期間があるかどうかによって、社会保険の手続きが異なります。
空白期間がない場合
資格喪失届と資格取得届を同日に提出します。
数日以上の空白期間がある場合
資格喪失届は退職日付・資格取得届は再雇用日付で、それぞれ別日で提出します。再雇用開始日までの間、労働者本人は「任意継続被保険者」または「国民健康保険」への加入が必要です。
いずれの場合も、必要な書類は以下のとおりです。
【提出書類】
【提出書類】
- 喪失届
- 交付済みの健康保険被保険者証、各種受給者証
- 取得届
同日得喪の場合は、継続性の証明のため、以下の書類を添付します。
■同日得喪時の添付書類(いずれか)
| (ア)退職日が確認できる書類(就業規則や退職辞令の写しなど)と、継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書の写し
(イ)上記を用意できない場合は、退職日と再雇用日が記載された事業主の証明書 |
【提出先】
日本年金機構が設置する地域ごとの事務センター、または事業所の地域を管轄する年金事務所
【提出期限】
- 喪失届:被保険者資格を喪失した日(=退職日)から5日以内
- 取得届:被保険者資格を取得した日(=雇用開始日)から5日以内
再雇用後に給与・労働条件の変更がある場合は、標準報酬月額の見直し(随時改定)が必要になる場合もあります。
適正な保険料負担のため、企業は速やかに確認を行いましょう。
高年齢雇用継続給付の手続き

出典:ハローワーク|高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
雇用保険の給付制度には、60歳~65歳未満の一般被保険者を対象に、再雇用後に賃金が下がった場合に支給される「高年齢雇用継続給付」があります。
この給付は、雇用保険から補助的な支援として設けられており、以下の2種類があります。
- 高年齢雇用継続基本給付金
基本手当(いわゆる失業手当)を受給していない方が対象。
- 高年齢再就職給付金
基本手当を受給したあと、再就職した方が対象。
受給資格があるのは、以下の要件を満たす方です。
※②被保険者期間について:一度離職しても、次の加入までが1年以内かつ失業給付などを受けていなければ、過去の加入期間を合算可能です。 |
申請は基本的に企業が行います。ここでは、高齢者雇用継続基本給付金の支給を受けるための手続きを解説します。
【提出書類(初回)】
【添付書類(初回)】
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(複写式)
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票(あらかじめハローワークに受給資格紹介を行っていた場合)
- 記載内容確認書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)
- 被保険者確認書類(運転免許証・住民票の写しなど、マイナンバー届出済の場合は省略可)
2回目以降は、ハローワークより交付される高年齢雇用継続給付支給申請書に、申請書に記載した内容が確認できる書類(賃金台帳・出勤簿など)を添えて申請します。
【提出先】
所轄のハローワーク、もしくは電子申請
【提出期限】
①初回申請
支給対象月の初日から起算して4か月以内
②2回目以降
管轄のハローワークが指定
※ハローワークから交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に記載あり
高齢者雇用継続基本給付金申請の詳細や、高年齢再就職給付金の手続き手順については、厚生労働省のパンフレットやハローワークのホームページでご確認ください。
高年齢雇用継続給付の手続きは、初回の書類準備や添付書類の確認に時間を要することもあるため、早めの準備と申請スケジュールの管理をしましょう。
60歳以上の新規雇用時の社会保険手続き

60歳以上の方を新規で採用する場合も、労働条件に応じて社会保険の加入義務が発生します。
健康保険・厚生年金の適用可否の確認
60歳以上の方を新規雇用・再雇用する場合、以下のいずれかに当てはまると、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が必要です。
| ①正社員(フルタイム雇用)
②週の所定労働時間・月の労働日数が正社員の4分の3以上の方(雇用形態は問わない) ③ 短時間労働者(パート・アルバイト等)で、以下のすべてを満たす方
|
※健康保険は75歳未満、厚生年金は70歳未満であること。
加入対象となった場合、以下の書類を提出する必要があります。
【提出書類】
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(雇用日から5日以内)
- 基礎年金番号通知書・年金手帳またはマイナンバーカード
【提出場所】
日本年金機構が設置する地域ごとの事務センター、または事業所の地域を管轄する年金事務所、もしくは電子申請・郵送
雇用保険の加入要件と手続き
雇用保険は、雇用形態を問わず、以下の両方を満たす場合に加入対象となります。
|
雇用保険加入に関する手続きは以下のとおりです。
【提出書類】
- 雇用保険被保険者資格取得届(雇用日の翌月10日まで)
- 記載内容が確認できる書類(賃金台帳・労働者名簿など)
※本人が高年齢再就職給付金の支給を希望している場合は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」も必要です。
【提出場所】
所轄のハローワーク窓口、もしくは電子申請
高齢者を新規で雇用する場合は、労働条件と年齢に応じた保険適用可否を適切に判断し、制度上の上限年齢も考慮して必要な手続きを確実に進めましょう。
70歳以上の労働者に必要な社会保険手続き

70歳以上の労働者を雇用する場合、年齢に応じて社会保険の取り扱いが変わります。
実務で迷いやすい以下の4つのケースに分けて、必要な手続きを確認しておくと安心です。
1|労働者が70歳に到達した場合
労働者が70歳になると厚生年金の被保険者資格を喪失します。資格喪失処理は日本年金機構が行うため、基本的に企業からの届出は不要です。
ただし、70歳到達日時点の標準報酬月額相当額がそれまでと異なる場合には、70歳到達届の提出が必要となります。
【事務センターまたは年金事務所へ】
- 70歳到達届(70歳の誕生日の前日から5日以内)
2|新たに70歳以上の労働者を雇い入れる場合
70歳以上でも、健康保険や雇用保険の加入対象になる場合があります。新たに採用した労働者が加入要件を満たす場合は、それぞれの制度ごとに所定の届出が必要です。
【事務センターまたは年金事務所へ】
- 健康保険被保険者資格取得届(雇用日から5日以内)
- (過去に厚生年金加入歴がある場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当届(同上)
【ハローワークへ】
- 雇用保険被保険者資格取得届(雇用日の属する月の翌月10日まで)
3|70歳以上の労働者が退職した場合
70歳以上の労働者が退職した際には、健康保険と雇用保険の喪失手続きが必要です。それぞれの保険制度で、喪失に伴う届出を忘れずに行いましょう。
【事務センターまたは年金事務所へ】
- 健康保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届(退職日の翌日から5日以内)
※健康保険被保険者証や各種受給証も同時に返却
【ハローワークへ】
- 雇用保険被保険者資格喪失届(退職日の翌日から10日以内)
- (離職票が必要な場合)雇用保険被保険者離職証明書(同上)
4|労働者が75歳に到達した場合
健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ自動移行します。企業は、健康保険の資格喪失届の提出と、健康保険証・高齢受給者証の回収と返却が必要です。
【事務センターまたは年金事務所へ】
- 健康保険被保険者資格喪失届(75歳の誕生日から5日以内)
※健康保険被保険者証や各種受給証も同時に返却
労働者が被保険者資格を喪失すると、その方の被扶養者も、健康保険の被扶養者資格を喪失します。
被扶養者が75歳未満で、喪失後に国民健康保険へ加入する場合には、「資格喪失等確認通知書」が必要となることがあるため、必要に応じて早めに準備・交付の手続きを確認しておきましょう。
詳細な手続きや対象範囲については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
(関連記事:【年齢別】70歳以上の社会保険対応とは?必要な手続き・書類を詳しく解説!)
このように、70歳以上の労働者に関する社会保険の手続きは、年齢によって必要な対応が細かく分かれています。
実務で手続きに迷わず、提出期限を厳守するためにも、節目ごとのルール整理は大切です。
まとめ|60歳以上の社会保険の手続きは年齢別対応で正確に
60歳以上の労働者を雇用・再雇用する際には、健康保険・厚生年金・雇用保険など、それぞれの社会保険制度で年齢に応じた手続きが求められます。
また、定年後の再雇用時に労働者の給与が下がる場合でも、「同日得喪」の手続きを行うことで、適切な社会保険料をすぐに反映できます。
法令を守りつつ労働者に適切に対応するには、制度を正しく理解し、社内で情報を共有することが重要です。
不安な点がある場合は、社労士など専門家のサポートを活用することで、手続きを確実かつスムーズに進められるでしょう。
60歳以上の社会保険手続きについて社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。