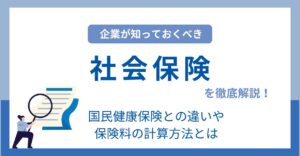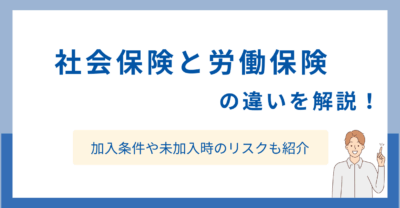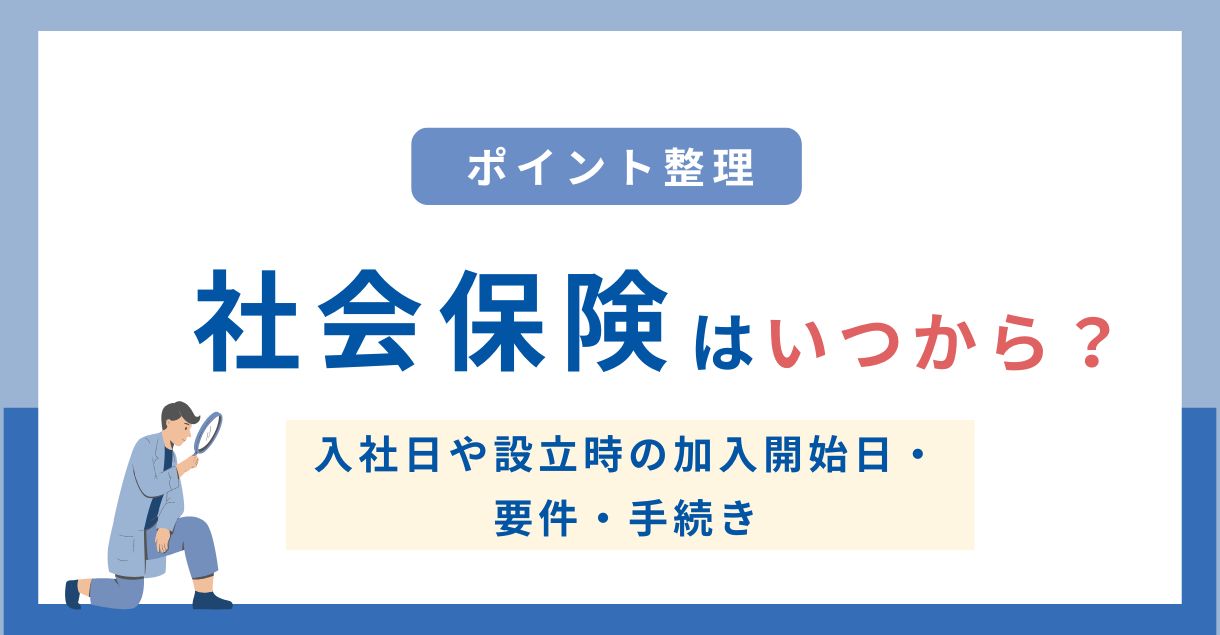
社会保険はいつから?入社日や設立時の加入開始日・要件・手続きまとめ
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入時期は、企業の担当者が迷いやすいポイントの一つです。
特に、法人設立時や有期雇用契約、短時間労働者の雇用など、「社会保険はいつから加入義務が発生するのか」「いつから適用されるのか」を正しく理解しておくことは、加入漏れやトラブルの防止に直結します。
本記事では、入社時や法人設立時の適用開始日をはじめ、有期契約・パート・アルバイト・派遣社員などの適用開始基準、加入手続き、未加入時のリスクまでを幅広く整理します。
ぜひ最後までご覧いただき、実務にお役立てください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
| ※なお、本記事での社会保険とは、厚生年金保険と健康保険からなる「狭義の社会保険」のことを指し、本記事内でも厚生年金と健康保険に焦点を当てて解説します。 |
入社時の社会保険の適用開始はいつから?

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、加入要件を満たす労働者が適用事業所に雇用された日、すなわち「入社日」から適用が開始されます。
本章では、入社時の社会保険の適用開始日を基本から整理し、試用期間の取り扱いや、社会保険料が発生するタイミングについても解説します。
入社時の適用開始日(資格取得日)はいつ?
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入について、被保険者資格取得日は「適用事業所に使用されるようになった日」と定められています。
| ⑦取得(該当)年月日:適用事業所に使用されるに至った日(事実上の使用関係が発生した日)をご記入ください。 |
この「使用されるに至った日」とは、形式的な契約日を指すのではありません。
実際に労働者が勤務を開始し、給与が発生する日、すなわち「入社日」を指します。
つまり、実務上は入社した日がそのまま社会保険の適用開始日となり、その日から社会保険料が発生します。
企業は、この被保険者資格取得日に基づき、入社日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を事務センターまたは所轄の年金事務所に提出しなければいけません。
試用期間の適用開始日(資格取得日)はいつ?
試用期間中であっても社会保険の一定の加入要件を満たす場合は、給与が支給される限り、試用期間の初日(入社日)が社会保険の適用開始日となります。
試用期間であっても給与が月単位で支給される場合は、試用が開始された日に被保険者資格を取得することになります。
社会保険料の発生はいつから?
社会保険料は、入社した月の分から1か月単位で発生します。
たとえ月の途中に入社しても、保険料は日割りされず1か月分の社会保険料が必要です。
たとえば、4月15日入社の場合でも、4月分の保険料が発生し、翌月(5月)支給の給与から控除されます。
企業はその保険料を、労働者負担分と自社負担分を合わせて、翌月末までに国へ納付します。
有期労働者(2か月以内の雇用契約)の適用開始はいつから?

健康保険法および厚生年金保険法では、雇用契約期間が2か月以内である場合は、原則として社会保険の適用対象外とされています。
しかし、一定の条件を満たす場合には、たとえ最初の契約期間が2か月以内であっても、「雇用契約が更新される見込みがある」と判断されることがあります。
その場合は、最初の雇用契約の初日から被保険者資格の取得が必要です。
以下のいずれかに該当する場合は、「更新される見込みがある」とみなされます。
- 就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が明示されていること
- 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること
上記の条件に該当する場合は、たとえ2か月以内の短期契約であっても、最初の契約開始日から社会保険に加入させる必要があるため注意が必要です。
また、契約当初は2か月以内の雇用期間とされていた場合でも、契約更新などで2カ月を超えて雇用されることになった場合は、契約更新日から社会保険への加入が必要です。
法人設立時の社会保険の適用はいつから?

企業が法人を設立した場合、設立日が社会保険の適用開始日となります。
ここでは、法人設立時における社会保険(健康保険・厚生年金保険)の取り扱いや注意点を解説します。
法人設立日に加入義務が発生
社会保険は、法人設立の登記が完了した設立日から加入義務が発生します。これは労働者がいなくても、たとえ事業主1名だけであっても同様です。
設立後は速やかに、事務センターまたは所轄の年金事務所に対し、「新規適用届」と「被保険者資格取得届」等を提出しなければなりません。
必要な提出書類は、後半部分の「社会保険の手続きの流れと必要な提出書類」で解説しています。
新規適用届は設立から5日以内が必須
法人設立後は、健康保険および厚生年金保険の「新規適用届」を設立日から5日以内に提出する必要があります。
法人設立後に社会保険の手続きを怠ると、保険料の遡及徴収や延滞金の発生、年金事務所による加入指導・立入検査の対象になる可能性があります。
設立と同時に社会保険への加入義務が発生するため、速やかな手続きが重要です。
必要であれば、社労士などの専門家の支援を受けることも検討しましょう。
企業における社会保険の加入要件

企業が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務は、事業形態や労働者数に応じて法律で定められています。
(1)法人事業所(株式会社・合同会社など)
法人は、事業規模や労働者数にかかわらず、すべての法人事業所に社会保険の加入義務が発生します。
たとえば、代表者1名のみで設立した法人であっても、給与(役員報酬)を支払っている場合には、社会保険の加入が義務付けられます。
(2)個人事業所(自営業など)
個人事業主が運営する事業所は、常時5人以上の労働者を使用している場合には、社会保険への加入が義務付けられます。
ただし、飲食業や理美容業、農林水産業、旅館業などの一部サービス業については「非適用業種」とされており、これらの業種に該当する個人事業所は、従業員が5人以上であっても社会保険の加入義務は発生しません。
労働者における社会保険の加入条件

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象かどうかは、雇用形態や労働時間・賃金などの基準によって判断されます。
フルタイム労働者(正社員・常勤契約社員など)
フルタイム労働者と、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、その事業所におけるフルタイム労働者の4分の3以上である労働者は、社会保険への加入が義務付けられています。
パート・アルバイトなどの短時間労働者
特定適用事業所(被保険者数51人以上の企業)の短時間労働者(1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数がフルタイム労働者の4分の3未満の労働者)のうち、以下のすべての条件を満たす短時間労働者には、社会保険の加入が義務付けられています。
1.週の所定労働時間が20時間以上契約書や就業規則で定めた「所定労働時間」が基準です。臨時的な残業は含まれません。 ※契約上は週20時間未満でも、実労働が2か月連続で週20時間を超え、今後も継続が見込まれる場合は、3か月目から対象となります。 2.月額賃金が88,000円以上(所定内賃金)基本給および各種手当(時間外手当・通勤手当・賞与などは除く)の「所定内賃金」が月額88,000円以上であることが条件です。 3.2か月を超える雇用の見込みがある
|
このように、雇用形態にかかわらず、労働者が一定の要件を満たす場合には、社会保険の加入義務が発生します。
特にパートタイム労働者については、近年適用が拡大しており、雇用時や勤務条件の変更時には注意が必要です。
企業担当者には、最新の制度改正や適用要件を確認し、適切に対応することが望まれます。
最新の法制度や今後の法改正の予定については、以下の記事をご参考ください。
(関連記事:社会保険の加入義務とは?パートの適用拡大と企業の対応ポイントを解説)
派遣社員や短期アルバイトの社会保険加入条件
派遣社員については、社会保険の加入手続きは派遣先ではなく派遣元企業が行う義務があります。
前述のとおり、特定適用事業所の短時間労働者で週20時間以上働き、契約期間が2か月を超える見込みがある場合等は、初日から社会保険の加入対象となります。
短期アルバイトは、契約期間が2か月以内であれば原則として適用対象外ですが、以下の場合には初日から加入義務が発生する可能性があります。
- 雇用契約書に「更新の可能性がある」旨が記載されている場合
- 同様の契約で繰り返し雇用されている実態がある場合
このように、契約の更新が見込まれるかどうかや過去の雇用実績が社会保険の適用判断に影響するため、短期雇用であっても内容の確認が重要です。
判断が難しい場合は、社労士などの専門家に相談すると安心です。
社会保険の手続きの流れと必要な提出書類

社会保険の加入に関する手続きは、企業の規模や加入対象者の状況によって若干異なるものの、基本的には次のような流れで進みます。
1. 新規適用事業所の手続き(法人設立時など)
事業所が厚生年金保険および健康保険に加入すべき要件を満たした場合、事業主は以下の書類を日本年金機構へ提出しなければいけません。
【提出書類】
※上記に加えて、それぞれの事業形態に応じて添付すべき書類が異なります。 日本年金機構の公式ホームページより、必要な添付書類をご確認いただけます。 |
社会保険の新規適用手続きは、加入義務が発生した日から5日以内に行う必要があります。
この手続きは、事務センターまたは所轄の年金事務所に対して行い、電子申請、郵送、または窓口への持参のいずれかの方法で提出できます。
2. 労働者の加入手続き
一定の要件を満たす労働者が入社した日、または労働者が社会保険の加入要件を新たに満たした日から5日以内に、事業主は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を事務センターまたは所轄の年金事務所へ提出する必要があります。
なお、被保険者に被扶養者(扶養親族等)がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」の提出も必要です。
提出方法は以下の3通りです。
- 電子申請(「GビズID」を取得のうえ、e-Govから申請可能)
- 郵送
- 窓口への持参
保険料の納付期限は、原則として納付対象月の「翌月末日」です。
納付が期限内に行われない場合、日本年金機構から督促状が送付され、指定された期限までに納付するよう求められます。
延滞によるリスクを避けるためにも、保険料は期限内に納めるようご注意ください。
加入漏れがあった場合の罰則とは

社会保険への加入が義務付けられているにもかかわらず、企業が手続きを怠った場合、さまざまなリスクが発生します。
社会保険料の遡及徴収と延滞金
社会保険に未加入だったことが判明した場合、過去2年分まで遡って保険料を支払う必要があります。
この場合、企業側が労働者・事業主双方の保険料を立て替える形となり、労働者分は後日給与から控除します。
また、納付遅延分には延滞金が加算されるため、企業にとっては財務的負担が大きくなる可能性があります。
行政指導・立ち入り調査の可能性
社会保険への加入義務を怠ると、年金事務所による加入指導の対象になることがあります。
改善が見られない場合は、職員による立ち入り検査や認定による加入手続きが実施される可能性もあります。
なお、健康保険法・厚生年金保険法では、事業者に立ち入り検査の受忍義務が課されており、調査の拒否や虚偽の回答を行った場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性もあるため注意が必要です。
労働者トラブル・信用失墜
社会保険に加入していないことが発覚すると、労働者から「権利が守られていない」と不満や不信を招き、トラブルに発展するおそれがあります。
また、未加入の状態は企業の法令遵守意識の低さを疑われる要因にもなり、取引先や金融機関、求職者など、社会からの信用にも悪影響を及ぼしかねません。
結果として、採用や契約面で不利になったり、企業価値が損なわれたりするリスクがあるため、社会保険の適正な対応は非常に重要です。
まとめ|社会保険の加入は社労士と連携した早期対応が安心
本記事では、、社会保険の適用開始時期や加入条件、対象労働者の範囲、法人設立時の手続き、さらには未加入によるリスクまでを包括的に解説しました。
社会保険への適切な対応は、企業の法令遵守だけでなく、労働者の安心にもつながります。
未加入のままでいると、保険料の遡及徴収や延滞金、行政指導・立入検査の対象になるだけでなく、労働者とのトラブルや社会的信用の低下にもつながりかねません。
ただし、適用要件や手続きは複雑であるため、企業だけで社会保険について理解し対応するには限界もあります。
社会保険の導入や見直しに不安がある場合には、社労士との連携が安心です。
社会保険の加入について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。