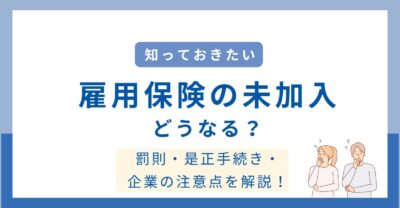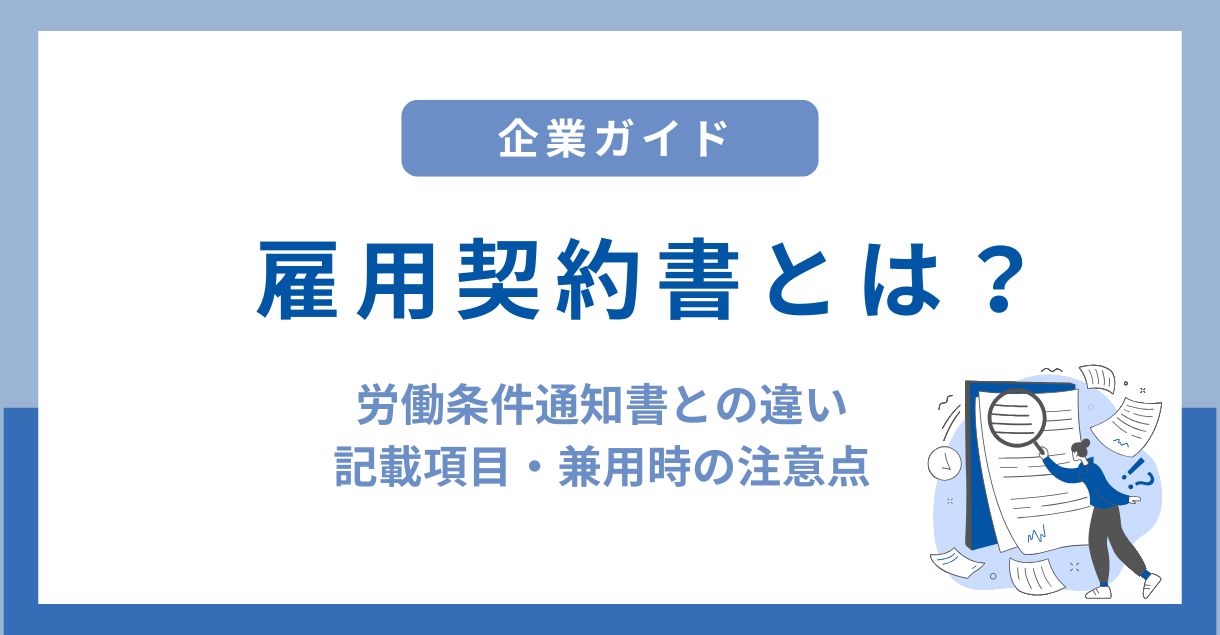
雇用契約書とは?労働条件通知書との違いと記載項目・兼用時の注意点を徹底解説
雇用契約書は、企業と労働者の間で労働条件を明確にして双方の合意を確認するための重要な書類です。
2024年4月には労働基準法施行規則の改正により労働条件明示のルールが強化され、雇用契約書の整備は一層重要になっています。
労働条件通知書との違いや、記載すべき内容・交付の方法についての理解があいまいなままだと、思わぬ法令違反や労使間のトラブルを引き起こすおそれがあります。
本記事では、雇用契約書の法的性質や記載項目、交付方法、内容変更時の注意点まで、企業の実務担当者が押さえるべきポイントを網羅的に解説しました。
法令遵守と企業の信頼性確保のためにも、ぜひ最後までご覧いただき、最新制度に対応した雇用契約書の整備にお役立てください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
雇用契約書とは

雇用契約書とは、企業が労働者を雇用する際に交わす労働契約の内容を、明文化して双方が確認・保存するための契約書です。企業にとって、労務管理の土台となる重要な書類といえます。
この記事では、雇用契約書の定義や法的な位置づけ、実務上の注意点をわかりやすく解説します。
雇用契約書の定義と役割
雇用契約書は、業務内容・賃金・就業場所・労働時間・契約期間などの労働条件に関する重要事項を記載した書類です。一般的には、企業と労働者の双方が署名捺印または記名押印を行い、契約を締結します。
契約内容を文書化することで、認識の相違による労使トラブルを防ぐことはもちろん、万が一の紛争や行政対応時には労働条件を裏付ける証拠資料としても機能します。
また、企業が誠実に契約書を交付する姿勢は、労働者からの信頼にもつながり、長期的な労務リスクの軽減にも貢献します。
雇用契約書に法律上の作成義務はあるのか?
雇用契約書の作成は、法律上の義務ではありません。労働条件に企業と労働者の双方が同意すれば、書面がなくても契約は成立します(労働契約法第6条)。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 労働条件には明示義務がある(労働基準法第15条)
通常、この明示義務は「労働条件通知書」の交付で対応しますが、雇用契約書に法定項目をすべて記載することで、通知書との兼用が可能です。 - 書面作成の重要性(労働基準法第15条第2項)
口頭契約では労働条件の認識のズレが生じやすく、労使トラブルの原因になります。明示された労働条件と実際の内容に相違がある場合、労働者は契約を即時解除できるとされています。
このため、雇用契約書の作成は法的義務ではなくても、労働条件を明確にし、トラブルを防ぐためには書面で契約内容を残すことが実務上不可欠です。
雇用契約書の署名・押印と法的効力
雇用契約は、企業と労働者の合意によって成立します。そのため、契約の成立自体には契約書の有無や署名・押印がなくても法律上は有効です(労働契約法第6条)。
実際、内閣府・法務省・経済産業省が2020年6月に発表した「押印に関するQ&A」にも、「私法上、契約は当事者の意思の合致により成立し、押印の有無は契約の効力に影響を与えない」と明記されています。
なお、雇用契約書を締結した場合、その内容には企業・労働者双方が拘束されることになります。しかし、その記載が労働基準法に違反している場合、その部分は無効です(労働基準法第13条)。同様に、就業規則に定めた労働条件を下回る契約内容も無効となります(労働契約法第12条)。
雇用契約書と労働条件通知書の違い

雇用契約書と混同されやすいのが「労働条件通知書」です。どちらも労働契約に関する書類ですが、法的な位置づけ・記載内容・手続きの性質が大きく異なります。
両者の違いを実務上重要な2つの視点から解説します。
それぞれの作成目的と交付義務の違い
雇用契約書と労働条件通知書の違いは以下のとおりです。
| 項目 | 雇用契約書 | 労働条件通知書 |
|---|---|---|
| 作成目的 | 労働契約の合意内容を明確にし、文書で確認・保管するため | 労働条件を法律に基づき、労働者に労働条件を明示するため |
| 法的義務 | 作成義務なし(任意) | 労働基準法第15条に基づく交付義務あり |
| 位置づけ | 双方の合意による契約書類 | 企業から労働者への一方的な通知書類 |
| 記載事項 | 任意(法的な定めなし) | 法定記載事項あり(労働基準法第15条・労働基準法施行規則第5条) |
雇用契約書には法令上の作成義務こそありませんが、契約内容を明確にし、労使トラブルを防ぐうえでは実務上欠かせない書類です。
一方、労働条件通知書は、労働基準法第15条により企業に交付が義務付けられた法定書類のため、作成は必須です。
混同によるリスクと実務上の注意点
「雇用契約書」と「労働条件通知書」は、それぞれ法的な位置づけや目的が異なるため、性質を正しく理解したうえで運用することが大切です。
もし区別せずに扱ってしまうと、労働条件の明示義務を果たしていないと判断され、労働基準法上の指摘を受ける可能性もあります。
特に注意したいのが、「雇用契約書を作成しているから、労働条件通知書は不要」と誤解するケースです。
たとえ雇用契約書を交わしていても、以下のいずれかに該当する場合は労働条件通知義務を満たしたことにはなりません。
- 法定記載事項がすべて盛り込まれていない
- 法令に沿った交付方法(書面または電子交付)が実施されていない
法定項目を正確に記載し、労働者にきちんと交付されているかを確認することが、法令遵守とトラブル回避につながります。
雇用契約書を作成するメリット

雇用契約書は法令上の作成義務こそありませんが、作成することで企業と労働者双方に大きなメリットがあります。
ここでは、雇用契約書を取り交わすことで得られる企業側の代表的なメリットを、3つに整理して解説します。
メリット①|労働条件の明確化
雇用契約書を作成すると、賃金や勤務時間、業務内容、勤務地などの労働条件が明確になり、企業と労働者双方が「労働者がどのような条件で働くのか」を文書で確認できます。
条件が透明化されることで、労働者の安心感や納得感につながると同時に、企業への信頼感の向上にもつながります。
メリット②|トラブル予防
雇用契約書で労働条件や業務範囲を明文化しておけば、「言った・言わない」の水掛け論を防止できます。
企業と労働者の間で認識のズレが生じにくくなり、トラブル予防につながるため、企業にとっても安定した労務関係を築くうえで有効です。
文書化された契約は、日常業務において双方の認識合わせの基準となるため、実務上のストレスや誤解の発生を防げます。
メリット③|法令遵守とリスク管理
雇用契約書は、企業側にとって法令遵守と適正な契約手続きの裏付けとなる重要な書類でもあります。
契約内容を明文化し、適切に交わしておくことで、企業が労働基準法などの法令を遵守している証拠となります。
万が一、労働基準監督署の調査や労使トラブルが発生した際も、雇用契約書は契約手続きや条件明示が適正だったことを証明できる証拠資料として活用可能です。
これにより、企業のリスク回避やトラブル対応の負担軽減にもつながります。
雇用契約書は「労働条件通知書」と兼用が可能

雇用契約書と労働条件通知書は、本来それぞれ目的の異なる書類ですが、実務上は1つの書式で兼用可能です。
実際、多くの企業では、情報の重複を避けるため、労働条件通知書と雇用契約書をひとつにまとめた書類を運用しています。
この書類は一般的に「労働条件通知書 兼 雇用契約書」と題され、以下の2つの機能を兼ね備えています。
- 労働条件の法定明示義務を果たす「労働条件通知書」としての機能
- 契約内容の合意を証明する「雇用契約書」としての機能
ただし、兼用する場合は、労働基準法に基づく法定記載事項が漏れなく記載されていることが前提です。
これらの記載事項については、次章で詳しく解説します。
「労働条件通知書 兼 雇用契約書」に記載すべき事項

「労働条件通知書 兼 雇用契約書」を作成する際は、労働基準法第15条および労働基準法施行規則第5条に基づく法定記載事項を正しく盛り込む必要があります。
これらの記載事項は、通知の必須度合いに応じて以下の2つに分類されます。
それぞれの具体的な内容について、以下で詳しく解説します。
絶対的記載事項
絶対的記載事項は、すべての労働契約で、書面明示が義務付けられている項目です。アンダーラインの部分は法改正により2024年4月から追加された項目です。
- 労働契約の期間(有期・無期の別、契約期間の長さなど)
- 【有期契約の場合】契約更新の有無と、その判断基準、(ある場合)更新回数の上限
- 就業場所と担当業務の内容、就業場所と担当業務の変更範囲
- 勤務時間・時間外労働の有無、休憩・休日・交代制勤務の有無など
- 賃金の決定・計算方法、締日・支給日・支払い方法(退職手当・臨時賃金を除く)、昇給に関する事項
- 退職に関する取り決め(解雇の事由を含む)
さらに、有期契約労働者の場合には、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングで以下の項目を明示する必要があります。
無期転換申込権が発生する有期契約労働者へ明示が必要な事項
- 無期転換の申込機会
- 無期転換後の労働条件
これらの項目に記載漏れがあると、労働基準法上の問題につながる可能性があります。2024年4月以前の書式を使用している場合は、現在の法令に適合しているかを確認し、必要に応じて最新の様式で作成するようにしましょう。
なお、2024年4月から適用されている労働条件明示ルールの詳細については、厚生労働省のパンフレットからご参照いただけます。
相対的記載事項
相対的記載事項は、企業が就業規則や労働契約で以下の条件を定めている場合に限り、書面で明示する必要がある項目です。
- 退職手当の対象者、計算方法、支払い時期など
- 賞与・臨時手当・最低賃金に関する内容
- 食費・作業用品などの労働者負担に関する事項
- 安全衛生管理に関する方針や体制
- 職業訓練の実施内容や対象者
- 業務災害補償・私傷病への支援制度
- 表彰制度・懲戒処分のルール
- 休職制度の内容や手続き
自社の制度を見直し、該当項目がないか、確認しておきましょう。
雇用契約書を「兼用」で作成する際の5つの注意点

「労働条件通知書 兼 雇用契約書」は、法令の要件を満たすことに加え、労使間の認識違いを防ぐためにも、適切に作成・管理することが重要です。
明示義務に違反した場合は、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科される可能性があり、労働基準監督署の是正指導対象となることもあります。
こうしたリスクを回避するために、作成時に特に注意したいポイントを以下に整理します。
1.必要な記載事項をもれなく整理する
「労働条件通知書 兼 雇用契約書」を作成する場合、労働基準法第15条および労働基準法施行規則第5条に定められた絶対的記載事項をすべて書面で明示することが義務づけられています。
さらに、就業規則や制度上該当する項目がある場合は、相対的記載事項もあわせて明示する必要があります。ただし、相対的記載事項については、書面での明示は求められていません。
記載漏れは明示義務違反とされる可能性があるため、契約締結前に社内規程や運用実態との整合性を十分に確認しておきましょう。
2.労働時間制を適切に明示する
「始業・終業の時刻」や「所定外労働の有無」など、労働時間に関する項目はすべての労働契約で明示が義務づけられています。
変形労働時間制やフレックスタイム制、裁量労働制など特殊な制度を導入している場合は、その内容や適用範囲まで具体的に記載する必要があります。
また、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働を予定している場合には、36協定の締結と労働基準監督署への届出も忘れずに行いましょう。
36協定についての詳しい内容は、以下の記事で解説しています。
>企業が知るべき「36協定」とは?特別条項・届出方法・違反リスクまで徹底解説
3.勤務地・職種・転勤の有無を明記する
将来的な転勤・職種変更・人事異動などの可能性がある場合は、その旨を契約書に明示しておくことで、後のトラブルを防止できます。
就業規則に規定があっても雇用契約書に明記していない場合、労働者の同意がないと見なされ、異動命令が無効と判断されるリスクがあります。
リスク軽減のためにも、転勤や配置転換の可能性は契約書上で明確に示しておくことが重要です。
4.試用期間を設定する場合は条件を明記する
試用期間中も労働契約は成立しているため、試用期間の長さや条件は契約書に明記する必要があります。
特に、就業規則に反して長期間の試用期間を設定や、就業規則にない取扱いを一方的に適用した場合は、労働契約自体が無効と判断される可能性があります。
記載内容は就業規則と必ず一致させましょう。
5.パート・有期雇用労働者への追加項目を明示する
パートタイム労働者や有期契約労働者などの非正規雇用労働者に対しては、パートタイム・有期雇用労働法第6条に基づき、次の事項の明示も義務付けられています。
- 昇給の有無
- 退職手当(退職金)の有無
- 賞与(ボーナス)の有無
- 雇用管理に関する相談窓口(部署名・担当者名など)
これらは、労働条件通知書または兼用契約書に必ず記載しておく必要があります。特に非正規雇用者への説明は不十分になりやすいため注意が必要です。
雇用契約書の交付方法

雇用契約書の交付方法は、その書類が労働条件通知書を兼ねているかどうかによって異なります。
企業側は、それぞれの書類の性質に応じて、適切な交付方法を選ぶことが求められます。
通常の雇用契約書(契約書単体)の場合
通常の雇用契約書(契約書単体)には、労働契約成立の合意内容を文書で確認するものですが、交付自体に法的義務はありません。
そのため、以下のような手段で自由に交付できます。
- 紙(書面)
- 電子ファイル(PDFなど)
- メール、FAX、LINEなどのSNS等による送信
ただし、電子的手段で交付した場合は電子帳簿保存法に基づく「電子取引」として扱われ、7年間の保存義務が発生します。保存データは改ざん防止措置や検索機能の確保など、法令に沿った管理が必要です。
「労働条件通知書 兼 雇用契約書」の場合
「労働条件通知書 兼 雇用契約書」は、労働条件の明示を目的とした法定書類です。
労働基準法第15条および施行規則第5条に基づき、交付方法は以下のとおり定められています。
- 紙(書面)
- メール、FAX、SNS等による送信(電子交付)
電子交付の場合、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 労働者本人が希望していること
- PDFなど、出力して書面作成が可能な形式であること
なお、企業の都合で一方的に電子交付をすることは認められていません。
電子交付は、労働基準法施行規則第5条の4に定められた方法で行う必要があり、適切に対応しない場合は、法令違反として30万円以下の罰⾦となるおそれがあります。
このように、雇用契約書の交付方法は書類の法的性質に応じた対応が求められます。
電子交付を行う際には「保存義務」や「労働者の同意」など、関連法令を十分に理解し、適切に運用することが重要です。
雇用契約書の内容を変更する際の手続き

雇用契約書に記載された労働条件を変更するには、原則として労働者との合意が必要です(労働契約法第8条)。
ただし労働条件の変更に伴い就業規則を変更する場合には、個別合意が不要となる場合があります。また、この場合変更内容が労働者にとって「有利」か「不利益」かにより、手続きが異なります。
ここでは、有利な変更・不利益な変更それぞれの場合の考え方を整理します。
労働者にとって「有利」な労働条件の変更
賃金の引き上げや休暇制度新設など、労働者にとって有利な内容の就業規則の変更であれば、例外的に労働者の個別合意は不要です。
ただし、有利な変更であっても従業員代表の意見の聴取と変更後の周知は必要です。
労働者にとって「不利益」な労働条件の変更
一方で、賃金の減額や勤務地の変更など、労働者にとって不利益な条件変更は、下記の観点から合理性を説明できるものでなければなりません。
- 労働者の受ける不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- (あれば)労働組合等との交渉の状況
上記の条件を満たしたうえで、労働者へ十分な説明を行い、変更後の就業規則を周知した場合は、例外として個別の合意がなくても変更が認められる場合があります。
ただし、契約時に「この条件は就業規則変更があっても変えない」と合意している項目については変更できません(例外として、労働基準法第12条(平均賃金)に該当する場合を除く)。
これらの判断には法的知識が必要なため、社労士などの専門家と連携しながら対応することが、法令遵守とトラブル防止のうえで重要なポイントです。
まとめ|雇用契約書の整備は、企業経営と労務管理の土台です
本記事では、雇用契約書の基本から記載項目、交付方法、変更時の注意点まで、実務担当者が押さえるべきポイントを整理して解説しました。
雇用契約書そのものに法的な作成義務はありませんが、労働条件通知書の要件を満たせば、明示義務を果たす書類としても機能します。
一方で、記載内容の不足や誤った交付方法は、法令違反や労使トラブルの原因となるリスクもあるため、制度の正確な理解と適切な運用が重要です。
雇用契約書の整備は、法令遵守の徹底だけでなく、労働者との信頼関係の土台でもあります。
雇用契約書の整備に不安がある場合は、社労士などの専門家のサポートを受けることで、法令遵守と実務対応の両面においても安心です。
雇用契約書について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。