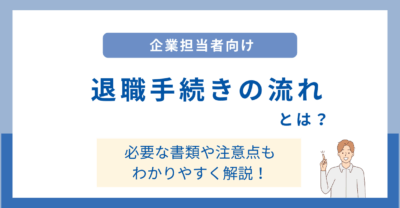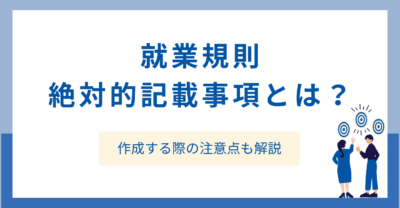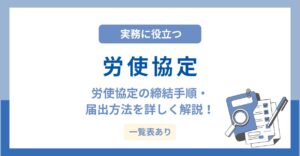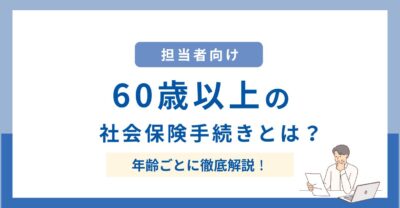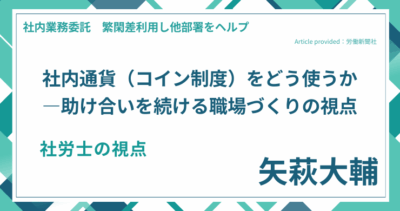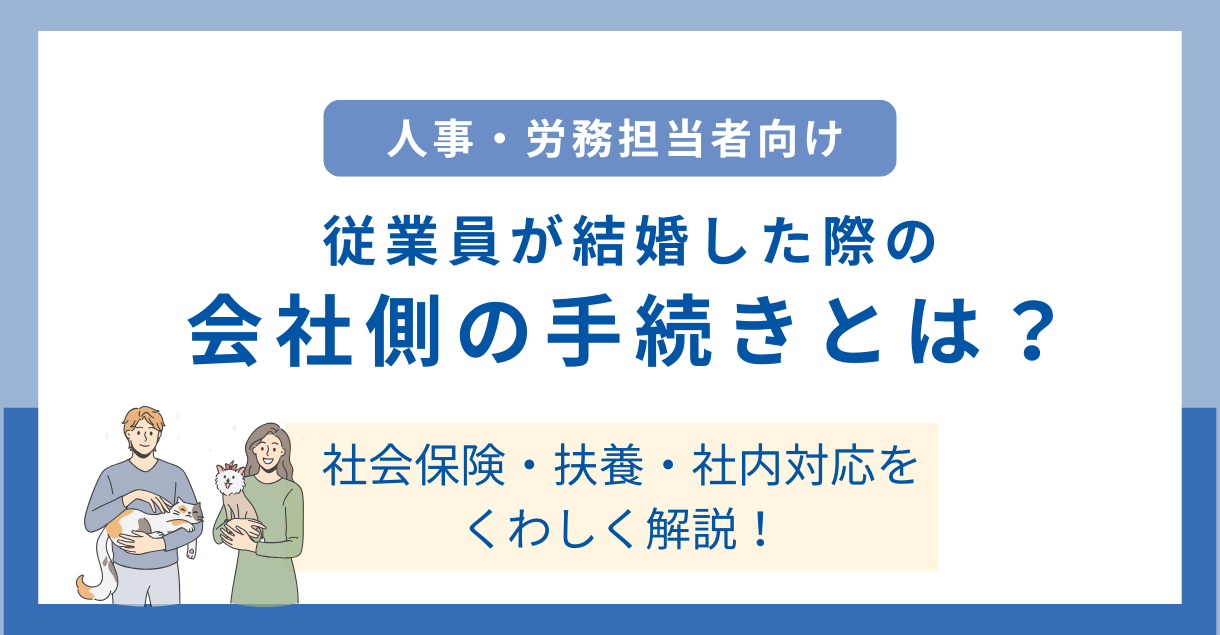
従業員が結婚した際の会社側の手続き一覧|社会保険・扶養・社内対応までくわしく解説!
従業員が結婚した際、企業の人事・労務担当者には、法令に基づく申請から結婚休暇や慶弔見舞金の支給などの社内制度適用の対応まで、幅広い手続き対応が求められます。
対応漏れや手続きの遅れがあると、社会保険料や所得税の計算、給与の支給額に影響が出るだけでなく、従業員に不利益や混乱が生じるおそれもあります。信頼関係の維持のためにも、正確かつ迅速な対応が欠かせません。
本記事では、従業員が結婚した際の会社が対応すべき手続き一覧をまとめました。また、社会保険や雇用保険の変更、配偶者を被扶養者にするための申請手順、税務上の扶養控除や年末調整の対応、社内制度の整備ポイントまでくわしく解説します。
実務対応にお役立ていただけるよう、必要な書類や注意点についてもわかりやすく紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
従業員が結婚した際に会社が行う手続きとは?

従業員が結婚した場合、会社は法令に基づく各種手続きと社内制度への対応が求められます。
まずは手続きの全体像を把握し、従業員に確認しておくべき情報や必要書類を整理しておきましょう。
必要な手続き一覧
結婚に伴い、会社が対応すべき主な手続きは、大きく分けて法令に基づくものと社内制度に基づくものがあります。
【法令に基づく手続き】
- 健康保険および厚生年金保険に関する氏名・住所変更の届出
- 雇用保険の氏名変更届け出
- 配偶者を被扶養者とする場合の手続き
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出(年末調整対応)
【会社独自の社内制度に基づく対応】
- 家族手当・通勤手当など社内手当の見直し
- 結婚休暇・慶弔見舞金の支給(福利厚生)
結婚に関連する手続きの多くは速やかな対応が求められます。社会保険や税務上の申告には期限が設けられているものもあるため、確認と準備を早めに行うことが大切です。
従業員に確認しておくべき事項
会社が従業員からの報告を受けた時点で、確認しておくべき事項は、以下のとおりです。
- 入籍日(婚姻届を提出した日)
- 姓の変更はあるか
- 住所の変更はあるか
- 配偶者が被扶養者となるか
- 通勤手当の追加など、給与の変更はあるか
これらは、結婚後に提出してもらう書類や各種手続きに直結するため、最初に押さえておくことが重要です。
確認が曖昧なまま処理を進めると、書類の差し戻しや再提出が発生するため、従業員・会社双方の負担にならないためにも正確に把握しておきましょう。
従業員に提出してもらう書類
書類は、確認した内容を裏付け、会社が適切に手続きを進めるために必要です。健康保険や税務関連の届出に添付を求められる場合もあるため、漏れのない準備が求められます。
入籍後に従業員から提出してもらう主な書類は以下のとおりです。
【法令に基づく手続き用(配偶者を被扶養者とする場合)】
- 被扶養者の戸籍謄(抄)本
- 住民票の写し※(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
- 配偶者の収入証明書類(給与明細・源泉徴収票など)
- (配偶者が退職した場合)退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
- (被保険者の住所に変更がある場合)健康保険被保険者証
【社内手続き用】
- 結婚報告書(社内書式または結婚届受理証明書・婚姻届のコピー)
- 氏名・住所変更届
- 家族手当申請書、結婚休暇届、緊急連絡先の更新届など
なお、必要な書類は従業員の状況によって異なります。提出漏れを防ぐために、チェックリストを用意しておくと安心です。
従業員が結婚した際に社会保険で必要な変更手続き

社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の資格情報は、氏名や住所などの個人情報をもとに管理されています。
正しく届出を行うことで過去の加入履歴が引き継がれ、保険給付を受ける際の不利益を防ぐことが可能です。
ここでは、結婚に伴い会社が対応すべき主な変更手続きを整理します。
健康保険・厚生年金保険の手続き(協会けんぽの場合)
協会けんぽに加入している従業員の場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、原則として氏名・住所変更の届出は不要です。
ただし、次のいずれかに該当する従業員の方は手続きが必要なため、書類や提出先を確認しておきましょう。
【手続きが必要になるケース】
- マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
- 健康保険(全国健康保険協会管掌)のみに加入している方
- マイナンバーを有していない海外居住者
- 短期在留外国人
- (住所変更時のみ)住民票住所以外の居所を登録する方
【必要書類】
- 氏名変更:健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届
※添付書類:資格確認書および健康保険被保険者証が必要です。
なお、健康保険被保険者証は令和7年12月2日以降、原則廃止となるため使用できなくなります。必要添付書類については、日本年金機構の最新の情報をご確認ください。 - 住所変更:健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届(国民年金第3号被保険者住所変更届)
※添付書類なし
【手続き方法(氏名変更・住所変更ともに)】
- 時期:氏名・住所が変更になったらすみやかに
- 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
※電子申請(氏名変更のみ)・郵送・窓口可
協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合は、必要な届出や手続きが異なる可能性があるため、加入先の健康保険組合へ直接お問い合わせください。
雇用保険の手続き
雇用保険については、従業員の氏名が変更になった場合のみ、所轄のハローワークで手続きが必要です。
従来は「雇用保険被保険者氏名変更届」による届出が必要でしたが、2020(令和2)年1月に廃止されました。
そのため、現在は、以下の届出を提出する際に、あわせて氏名変更手続きを行います。
※氏名変更記載欄がそれぞれの申請書内にあります。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用継続交流採用終了届
- 雇用保険被保険者転勤届
- 個人番号登録・変更届
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
- 高年齢再就職給付金の支給申請
- 育児休業給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
- 介護休業給付金の支給申請
なお、雇用保険では住所情報を登録していないため、住所変更に関する手続きは発生しません。
従業員が結婚した際に配偶者が被扶養者になる場合の手続き

配偶者が健康保険や厚生年金保険の被扶養者になるには、従業員から必要書類を提出してもらい、会社が認定要件を確認したうえで届出を行います。
認定されるかどうかは収入や同居状況などで判断されるため、誤解や漏れがあると従業員に不利益が生じます。
正しく対応するために、被扶養者の認定要件と手続きの流れを確認しておきましょう。
配偶者が被扶養者として認定されるための要件
配偶者が被扶養者として認定されるには、以下のすべてに該当する必要があります。
【配偶者が被扶養者として認定されるための要件】
- 日本国内に住所(住民票)があること
- 被保険者の収入で主に生計を維持していること
- 年間収入が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)であること
配偶者の場合、同居・別居の有無は問わず同一世帯と認められます。
ただし、同居している場合は、被扶養者の年間収入が被保険者の収入の2分の1未満であることが要件です。別居している場合は、被扶養者の年間収入が仕送り額未満であることが必要です。
申請に必要な書類と手続きの流れ
申請に必要な書類や添付資料、手続きの流れは以下のとおりです。
【提出書類】
- 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
協会けんぽ以外の健康保険組合等の被保険者を配偶者として被扶養者認定する場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」のみを提出。(健康保険組合等の資格喪失手続きは別途健康保険組合等で行う必要があります。) - 続柄を確認する書類(被扶養者の戸籍謄本や住民票の写しなど)
- 収入要件を満たしているか確認する書類
※所得税法の規定による控除対象配偶者であれば事業主の証明可 - 年金収入や非課税収入がある場合は、その金額がわかる通知書等のコピー
- 別居の場合は、仕送り額を確認できる書類
【提出時期】
- 事実発生(入籍した日)から5日以内
【提出先】
- 事務センターまたは管轄の年金事務所
【提出方法】
- 電子申請・郵送・窓口
配偶者を被扶養者にするには、申請で完了するのではなく、収入状況や仕送り実態などの審査を受けてはじめて認定されます。書類を提出しても、要件を満たさない場合は認定されないこともあるため、事前に確認を徹底しましょう。
従業員の結婚に伴う給与・手当の変更と税務手続き

結婚をきっかけに、家族手当や通勤手当の額が変わったり、配偶者を扶養に入れることで税務上の控除が発生したりすることがあります。
対応を誤ると税金や社会保険料にズレが生じるため、正しく押さえておくことが大切です。
ここでは、手当や扶養家族の有無によって給与・税金にどのような影響があるかを整理し、必要な税務手続きを解説します。
家族手当や通勤手当が変わる場合の税金・社会保険料の影響
家族手当や通勤手当は給与に含まれるため、手当が増減すると、税金や社会保険料の計算に影響します。
【所得税・住民税への影響】
家族手当は給与所得として課税対象になります。通勤手当は、1か月あたり15万円までが非課税限度額とされており、それを超える部分は課税対象です。
そのため、手当が増えると課税所得が増え、結果として所得税や住民税の負担が大きくなる可能性があります。
【社会保険料への影響】
家族手当や通勤手当は「固定的賃金」にあたるため、標準報酬月額の算定対象に含まれます。
従業員の報酬が、手当増減などで大幅にかわった場合、随時改定(いわゆる月額変更届)の対象となることがあり、健康保険料や厚生年金保険料の額に反映されるため注意が必要です。
結婚に伴い手当が変更となった場合は、事業主が該当の報酬月額などを「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届」に記入し、すみやかに日本年金機構へ提出する必要があります。
随時改定を行う必要のある場合や手続き方法の参照は、日本年金機構のホームページ「随時改定(月額変更届)」をご確認ください。
配偶者を扶養に入れる場合の税務手続きと控除のポイント
従業員に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合は、本人と配偶者の合計所得金額に応じて「配偶者控除」または「配偶者特別控除」が適用されます。
これにより、従業員本人の所得から一定額が控除され、納める所得税と住民税の金額が少なくなります。
控除項目と控除額は以下のとおりです。
【控除項目と控除額】
| 控除項目 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|---|
| 配偶者控除 | 58万円以下 | 最大38万円 ※納税者本人の所得により変動 |
| 配偶者特別控除 | 58万円超~133万円以下 | 最大38万円 ※同上、段階的に減額される |
控除に関する税務手続きは、年末調整で行います。
適用を受ける場合、従業員は年末調整に関する書類の提出期限(多くの企業は11月中)までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」を会社へ提出します。会社はこれを取りまとめ、所轄の税務署へ提出します。
詳しい条件や控除額の算定方法は、国税庁のホームページ「配偶者控除」および「配偶者特別控除」をご確認ください。
従業員の結婚に関する社内制度・就業規則の確認ポイント

従業員が結婚した場合、社会保険や税務だけでなく、会社が定める社内制度や就業規則の取り扱いについても確認が必要です。
結婚に伴う特別休暇や慶弔見舞金の支給など、福利厚生のルールは企業ごとに異なるため、あらかじめ制度の内容や運用方法を整理しておきましょう。
結婚休暇・慶弔見舞金など福利厚生の確認
従業員の結婚に伴って利用されることの多い制度が「結婚休暇」と「慶弔見舞金」です。
これらは法律で義務づけられているものではなく、会社ごとに就業規則や福利厚生制度として独自に定めているものです。
実務担当者は以下のポイントを確認しておくと安心です。
【結婚休暇|確認ポイントの例】
- 設置の有無と日数(平均5日程度)
- 休暇の種類(有給か無給か)
- 申請方法と期限
【慶弔見舞金(結婚祝い金)|確認ポイントの例】
- 支給の有無と金額(一般的には2-3万円台)
- 申請書の提出方法と期限
結婚休暇や慶弔見舞金などの制度は従業員が知らないこともあるため、掲示板や人事システムを通じて周知しておくことが重要です。
制度運用ルールと人事マニュアルの整備
結婚休暇や慶弔見舞金などの福利厚生制度は、給与計算や経費精算と連動するため、人事・総務・経理間での人事マニュアルを明確にしておく必要があります。
また、明文化された運用ルールは対応のばらつきを防ぎ、従業員からの信頼や会社全体の透明性を高める効果もあります。
スムーズな制度運用のための整備ポイントは、以下のとおりです。
- 手続きフローを明確化する
就業規則や人事マニュアルに、結婚に関する手続き手順をフロー化して記載しておくことで、各部署が役割を把握しやすくなります。 - チェックリストやQ&Aを整備する
属人化を防ぐ仕組みを用意することで、担当者が交代しても同じ対応ができ、提出資料の抜け漏れを防げます。 - 対象範囲や制度内容を明文化・周知する
結婚休暇の日数や慶弔見舞金の金額・対象範囲を就業規則に明記し、従業員に周知します。 - 法的婚姻関係にないケースへの対応を定める
事実婚や内縁といった法的婚姻関係にないケースへの対応方針も事前にルール化しておくことで、適切な判断ができ、トラブルも未然に防げます。
担当者交代や制度改定にも対応できる仕組みを整えることが、長期的な安定運用につながります。
まとめ|従業員の結婚に伴う手続きに備えましょう
本記事では、従業員が結婚した際に会社が対応すべき手続きについて、社会保険・税務・扶養・社内制度まで幅広く解説しました。
結婚に伴う手続きは多岐にわたり、氏名や住所が変更になる場合は社会保険や雇用保険の変更手続き、配偶者を被扶養者とする場合は認定要件の確認や申請が必要です。さらに、税務上の控除や年末調整に伴う書類の更新、家族手当・通勤手当・結婚休暇など社内制度の適用確認も重要になります。
従業員にとって結婚は大切なライフイベントであり、会社が誠実かつ制度的に整った対応をすることは、信頼感や定着率の向上につながります。一方で、制度や法的要件は複雑であり、会社だけで対応しきれないケースも少なくありません。
社内の結婚に伴う業務負担を軽減し、正確な手続きを行うためには、早めに社労士などの専門家と連携することをおすすめします。
従業員が結婚した際の会社側の手続きについて社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めたうえで依頼しましょう。