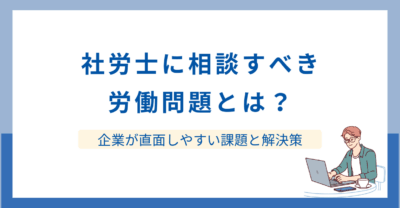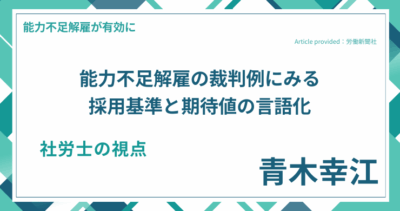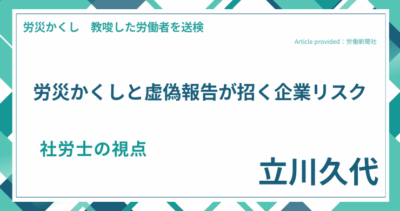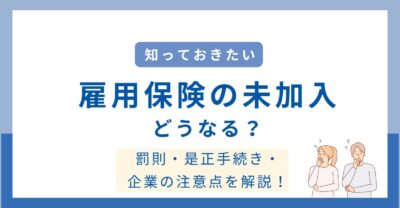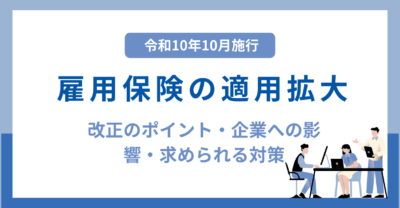セクハラとは? 定義・種類・最新法改正と企業対応を徹底解説
セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、企業規模や業種を問わず発生する恐れがあります。事案が起これば、職場の信頼関係が崩れ、損害賠償や企業イメージの失墜にもつながるリスクをはらんでいます。
2025年の法改正では、求職者等に対するセクシャルハラスメント(いわゆる就活ハラスメント)を防止するための措置が企業に義務づけられることとなり(改正法の施行は公布の日(2025年6月11日)から起算して1年6ヶ月以内)、企業には一層の対策が求められています。
本記事では、定義・種類・法的リスク・最新改正・防止策を解説し、中小企業の経営者・人事担当者が実務で役立つ対応と、社労士など専門家の活用法を紹介します。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
セクハラとは?基本の定義

職場のセクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)は、企業の信頼と職場環境を大きく損なうリスクを持つ行為です。被害者本人の人権侵害にとどまらず、職場全体の士気低下・離職・訴訟リスクにも直結します。
この章では、法的な定義・成立の要件・社会的背景を整理し、企業が取るべき理解と対応の基礎を解説します。
セクハラの法的定義(男女雇用機会均等法第11条)
男女雇用機会均等法では、セクハラを明確に「防止義務」の対象としています。
「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」 (男女雇用機会均等法第11条第1項)
この条文をもとに、厚生労働省は「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(厚生労働省告示第314号)」を公表しました。
たとえば、上司が「デートを断られた社員を降格させる」行為や、「会議中に容姿を揶揄する」発言もこれに該当します。
さらに、この指針では、行為者を上司・同僚に限らず、顧客や取引先など外部関係者も含むと明示しており、企業には第三者によるセクハラへの対応も求められています。
セクハラ成立の要件
セクハラの成立は、「行為者の意図」ではなく被害者の就業環境への影響で判断されます。
厚生労働省の指針では、以下の3要素を総合的に考慮するよう示されています。
- 職場に関連する場面であるか
自社オフィス内に限らず、出張先・懇親会・取引先のオフィス・オンライン会議など、業務に関連するあらゆる場所を含みます - 「性的な言動」に該当するか
性的な冗談・噂・執拗な誘い・身体への接触・性的画像の送信など、一度でも悪質な言動があった場合は成立します - 就業環境が害されたか
「平均的な労働者の感じ方」を基準に、看過できない程度に職場環境が悪化していれば該当します
「冗談のつもりだった」は通用しません。被害者が不快に感じ業務に支障があれば、セクハラと判断されます。
判断には、行為の態様・頻度・関係性・被害の程度などが総合的に考慮されます。企業には、発生前の「予防体制」と発覚後の「迅速な調査・対応体制」の両立が不可欠なのです。
セクハラの種類と典型的な具体例

職場におけるセクハラは、2つに分類されます。
- 対価型セクハラ
- 環境型セクハラ
上記の特徴・典型的な行為例を通して実務上どう捉えるべきか解説します。
対価型セクハラ
対価型セクハラとは、性的な言動に拒否・抵抗したことを契機に、昇進・昇給・契約更新・継続雇用など労働条件における不利益取扱いがなされるものを指します。
厚生労働省は、リーフレット「セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」(平成27年6月版)において、「職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動に対し、これを拒否・抵抗したことで当該労働者が労働条件に関して不利益を受けるもの」を「セクシュアルハラスメント(対価型)」と明記しています。
例えば、上司が「交際してくれたら昇進させる」と女性社員に発言し、断った後に昇給査定を下げたケースなどが典型です。
実務上は、評価・昇格・配置換え・契約更新・解雇などと性的言動との因果関係が疑われる場合に、対価型セクハラの可能性が出てきます。
企業としては、労働条件の決定プロセスを記録し説明可能な状態にしておくことが重要です。
環境型セクハラ
環境型セクハラとは、性的な言動そのものが被害者(または職場の労働者)にとって就業環境を不快なものとし、その結果、通常通りの業務遂行に看過できない支障をきたすものです。
厚生労働省の「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」にて、「職場において行われる労働者の意に反 する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重 大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること」という説明があります。
例えば、職場でわいせつな画像が常時掲示されていた、性的な冗談が繰り返されたことで被害者が職場に居づらくなった、という場合が該当します。
実務的に押さえるべきは、「頻度・態様・被害者の感じ方・職場の配慮状況」などが総合されて判断される点です。
企業としては、日常的な言動・職場文化・誘い・冗談等を軽視せず、環境悪化となる前段階からモニタリング・相談体制・予防研修を行うことが有効です。
取引先・顧客・他社従業員からのセクハラ
近年、セクハラ行為者として「社内の上司・同僚」に限らず、取引先・顧客・他社従業員などの外部関係者が該当するケースも明文化・実務上で頻出しています。
例えば、営業先で顧客が女性社員に対し性的発言・身体接触を行ったケース、あるいは取引先担当者が社内飲み会で不適切な発言・誘いを行ったケースなどです。
厚生労働省の「職場におけるハラスメントの防止のために」では、「事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者又はその家族、学校における生徒等もセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり…」
と明記されています。
この観点から、企業は自社従業員相互のみを対象としたセクハラ対策にとどまらず、「社外関係者を含めた言動管理」「取引先・顧客との接触場面の注意」「契約条項や取引先規程へのハラスメント防止要件反映」なども含めたハラスメント防止体制の構築が求められます。
典型的な具体例
下表は、「対価型」「環境型」という行政上のセクハラ類型に加えて、企業実務上特に留意すべき「社外関係者(取引先・顧客等)からの性的な言動」を整理したものです。
実務者が「自社で起きうるものかどうか」をチェックするための行動例として列挙しています。
| 分類 | 具体的行為例 |
|---|---|
| 対価型 | ・部長が「お付き合いしてくれたら昇進させる」と社員に発言し、拒否された後に昇給査定を下げる ・契約社員が顧客から性的関係を求められているが、会社から「断ったら契約更新をしないと」言われる |
| 環境型 | ・会議室に裸のポスターが掲示されていたり、社内で性的な冗談が常態化していたため、社員が不快に感じた ・飲み会で上司が部下の容姿を繰り返し話題にし、部下が退職を検討する程居づらいと感じた |
| 取引先/顧客等からのセクハラ | ・営業先の顧客が当社の社員に不適切に身体に触れたり、性的な話題を執拗に繰り返した ・取引先社員が社内懇親会で当社の社員を誘い出し、「応じなければ取引の解除を考える」とほのめかした |
これらの行為は、厚生労働省の指針にも「行為者が取引先・顧客等を含む」旨が記されており 厚生労働省・労働局による指導・裁判例でも確認されています。
企業としてはこうした構図が自社の規模・業種を問わず起こり得るという認識を持ち、就業規則・ハラスメント防止ポリシー・相談窓口・管理職研修・外部関係者対応等を整備することが重要です。
セクハラがもたらす法的リスク

セクハラは、加害者個人の問題にとどまらず、企業全体に民事・刑事・行政・労務上の責任をもたらす重大なリスクです。
被害者からの損害賠償請求や労働局による指導・企業名公表、さらに刑事事件化するケースも少なくありません。
企業が取るべき基本姿勢は3点です。
- 迅速な初動
- 公平な調査
- 再発防止の徹底
対応を怠ると、損害賠償請求や社会的信用の失墜につながります。
民事責任(損害賠償・慰謝料)
セクハラを行った本人は、民法第709条・710条に基づく不法行為責任を負い、被害者に対して損害賠償や慰謝料を支払う義務があります。
さらに、企業も行為が職務の範囲内で行われた場合には使用者責任(民法第715条)を問われる可能性があります。
また、セクハラ防止策や相談体制を整えていなかった場合、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)として、会社自体が損害賠償を命じられるケースもあります。
実際の裁判例でも、会社の調査遅延や放置が違法とされ、賠償額が増額された事例があります。
刑事責任(強制わいせつ・名誉毀損など)
セクハラの内容が身体的接触や脅迫を伴う場合、刑法第176条(不同意わいせつ)や第177条(不同意性交)により刑事罰の対象となります。
また、容姿や性的な話題を公然と口にして相手の尊厳を傷つけた場合には、名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(231条)が適用されることもあります。
特にSNSやオンライン会議上での発言も「職場内の行為」として扱われる場合があり、悪質なケースでは懲戒処分や刑事告訴に発展します。
企業は、通報・被害保全・警察相談への対応フローを社内規程として明確化しておくことが重要です。
行政指導・企業名公表のリスク
男女雇用機会均等法第11条は、事業主にセクハラ防止措置の実施を義務付けています。違反が認められると、都道府県労働局による助言・指導・勧告が行われ、それでも改善されない場合は企業名が公表(第30条)されます。
実際に、厚生労働省が企業名を公表した例もあり、社会的信用の失墜や採用・取引への影響は非常に大きいものです。
形式的な規程整備だけでなく、運用実態を伴った社内体制の構築が求められます。
企業の安全配慮義務違反による責任
労働契約法第5条は、企業に対し「労働者が生命・身体の安全を確保しつつ働けるよう必要な配慮をする義務」を定めています。
セクハラを放置したり、被害者保護を怠った場合には、この安全配慮義務に違反したとして債務不履行(民法第415条)または不法行為(709条)で損害賠償を命じられる可能性があります。
具体的には、相談体制の欠如・被害者と加害者を同一職場に置いたまま放置・再発防止策を取らないといった対応が違法とされやすいです。
企業は、研修・相談窓口・調査・是正・再発防止というPDCAサイクルを継続的に回すことが不可欠です。
参考元:内閣府男女共同参画局「性犯罪に関する法改正等(法務省刑事局)」
厚生労働省「職場におけるハラスメント防止」「均等法に基づく指導・勧告制度」
被害者が取るべき対応と相談先

セクハラの被害を受けたとき、最も重要なのは「一人で抱え込まないこと」と「冷静に事実を残すこと」です。感情的になってしまうのは当然ですが、時間が経つほど証拠は失われ、対応も難しくなります。
被害を受けたら、証拠を残す → 社内・外部に相談する → 必要に応じて専門家へという3段階の行動を意識しましょう。
この手順を踏むことで、被害者自身を守り、職場全体の改善にもつながります。
証拠の確保(記録・メール・録音)
最初に行うべきは、客観的な証拠をできるだけ多く残すことです。
厚生労働省は、「職場におけるハラスメント防止対策」の中で、被害者が冷静に事実を整理・記録することを推奨しています。
証拠として有効なのは、次のようなものです。
- 日付・場所・相手・状況を記したメモや日記
- メール・チャット・SNSなどのメッセージ履歴
- 録音データ(法的に許される範囲で)
- 目撃者・同席者の証言
- 心身の不調を証明する診断書
「一度だけだから」と思わず、事実を残すことが後の相談や調査の大きな助けになります。
社内相談窓口・上司への相談
次のステップは、社内の相談窓口や信頼できる上司に相談することです。
男女雇用機会均等法第11条では、企業に対してセクハラ防止措置と相談体制の整備が義務付けられています。
相談する際は次の点を意識しましょう。
- 被害の内容を時系列で整理し、具体的に伝える
- どのような対応を望むか(注意・配置転換など)を明確にする
- 相談した事実を自分でも記録しておく
加害者が上司や経営層の場合は、外部相談窓口を利用しても構いません。同じく男女雇用機会均等法第11条により事業主は、相談者に対する不利益取扱いを禁じられています。
公共機関(労働局・社会保険労務士会)の相談窓口
社内で解決が難しい場合は、公的な相談窓口を活用しましょう。厚生労働省では、都道府県労働局に「雇用環境・均等部(室)」や「総合労働相談コーナー」を設置しており、無料・匿名で相談が可能です。
また、各地の社会保険労務士会や法テラスでも、ハラスメント問題に関する専門相談が受けられます。
主な相談先
必要に応じて、行政による指導・あっせん(ADR)を通じた解決も可能です。
弁護士・社労士に相談すべき場面
社内・労働局への相談でも解決しない場合、法律や労務の専門家に相談することを検討しましょう。
弁護士
- 損害賠償請求
- 示談交渉
- 刑事告訴や労働審判の手続きなど
法的なサポートを行います。
社会保険労務士(社労士)
- 職場環境の改善指導
- 再発防止のための制度設計
- 従業員教育・相談体制づくりなど
など、企業と労働者の双方の立場から助言を行います。
「訴えるため」だけでなく、「トラブルを整理して穏やかに解決するため」にも、早めの相談が効果的です。早期対応が、精神的な負担を軽減し、企業の適切な対応や再発防止にもつながります。
加害者・企業の対応責任

セクハラが発覚した際、企業は「事実確認・是正措置・再発防止」を速やかに実施する法的責任を負います。対応を誤れば、被害者からの損害賠償請求や、労働局による行政指導・企業名公表のリスクに発展しかねません。
厚生労働省の指針では、企業に3段階の対応を求めています。
- 迅速・正確な事実確認
- 適切な措置
- 再発防止策
それぞれの具体的な対応を解説します。
加害者へのヒアリングと改善指導
加害者へのヒアリングは、公正な事実確認のための重要なプロセスです。
厚生労働省は「セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」において、被害者・加害者双方から事情を聴取し、事実関係を明らかにするよう求めています。
被害者の訴えのみで断定せず、発言の意図・頻度・職場での影響を丁寧に確認することが不可欠です。
ヒアリング後は、行為者の再教育・指導を含めた改善策を講じます。
- 就業規則に基づく制裁や被害者との引き離しを意図した配置転換
- 被害者との関係改善に向けた援助
- 行為者の謝罪等
などが挙げられます。再発防止の努力を記録として残すことが、後の紛争予防にもつながります。
企業の調査義務と懲戒処分
企業は、通報や相談を受けた時点で「調査義務」を負います。厚労省告示第314号では、事業主は「迅速かつ正確に事実確認を行い、被害者及び行為者に対して適正な措置を講じる」ことが求められています。
- 相談受付
- 被害者・加害者・目撃者へのヒアリング
- 調査報告書の作成
- 懲戒処分(譴責・減給・降格・出勤停止・解雇など)
上記のプロセスを明確にすることが重要です。また、就業規則に「セクハラ行為は懲戒処分の対象」と明記しておく必要があります。
迅速な対応を怠った場合の使用者責任
相談を放置したり、形式的に処理した場合、企業は使用者責任(民法第715条)や安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
裁判例でも、企業が適切な調査や保護を行わなかったとして損害賠償を命じられたケースがあります。
企業は以下の点を徹底すべきです。
- 通報後速やかに初動対応を開始
- 調査経過・処分内容・再発防止策を文書で保存
- 経営層が定期的にハラスメント防止体制を点検
対応の遅れや隠蔽は、結果的に「企業ぐるみの放置」と見なされ、社会的信用を大きく失うリスクがあります。
参照元:厚生労働省「ハラスメント対策指導事例」
企業に求められる防止策と専門家の活用

セクハラ防止は「発生後の対応」よりも「発生させない仕組みづくり」が何より大切です。厚生労働省の指針では、以下の4点を中心に取り組みを求めています。
- 方針の明確化
- 相談体制の整備
- 教育啓発
- 実態把握と改善
企業が実務で押さえておくべきポイントと、社労士など専門家の活用方法を整理します。
防止方針の策定と周知
防止方針は、企業の「ハラスメントを許さない姿勢」を社内外に示す基本方針です。方針には以下の3点を明示することが推奨されています。
- セクハラ行為を一切容認しない旨
- 行為者に対して懲戒処分を含む厳正な措置を行うこと
- 被害者に対する不利益取扱いの禁止
策定した方針は、就業規則や社内イントラネットへの掲載だけでなく、朝礼・研修・入社時説明会などで繰り返し周知し、経営トップのメッセージとして伝えることが重要です。
相談窓口の設置・外部相談員の活用
厚生労働省指針では、企業に「相談窓口の明確化と機能確保」を求めています。社内だけでなく、外部相談員や社労士を窓口に加えることで、相談しやすい環境を整えることができます。
外部窓口を導入するメリットは次の通りです。
- 相談者が社内での不利益を恐れずに相談できる
- 第三者の専門的視点で事実確認・助言を受けられる
- 企業対応の客観性・信頼性を高められる
中小企業では、都道府県労働局や社労士会の外部相談サービスを利用することも有効です。
従業員・管理職向け研修
防止体制を根付かせるには、「意識」と「行動」を変える教育が欠かせません。特に管理職は、職場文化の形成者としての責任が重く、定期的な管理職研修を実施することで、初動対応力と部下への配慮力を高められます。
研修では以下の内容を組み込みましょう。
- セクハラ・パワハラの定義と境界線
- 職場・SNS上での注意点
- 相談を受けた際の対応手順
- 再発防止とチームマネジメント
オンライン研修やeラーニングの活用により、全社員への継続的教育を行いやすくなります。
定期的なモニタリング・アンケート
ハラスメント対策は「一度整えれば終わり」ではありません。年1回程度の匿名アンケートや職場ヒアリングを実施します。
- 相談窓口が機能しているか
- 管理職の対応に偏りがないか
- 職場風土が健全に保たれているか
上記を確認することが重要です。
結果は経営層・人事部門で共有し、再教育や体制見直しにつなげることで、防止策の「形骸化」を防げます。
社労士への相談がもたらす安心と実効性
社会保険労務士は、ハラスメント防止措置の設計・運用を支援する専門家です。企業が社労士を活用することで、次のような実務的メリットがあります。
- 防止方針・就業規則の改訂支援(法令準拠)
- 相談窓口・研修制度の設計・運用アドバイス
- 行政対応・助成金申請支援
- トラブル発生時の第三者対応・調停サポート
特定社会保険労務士であれば、労働局の「あっせん手続代理」も可能で、企業と従業員の双方にとって、公正で早期の解決を実現できます。
参照元:厚生労働省「職場のセクシャルハラスメント対策はあなたの義務です!」
まとめ:セクハラ防止は「企業の責務」であり「専門家相談」が鍵
セクハラ防止は、企業の「法的義務」であり、同時に「信頼される組織づくり」の根幹です。厚生労働省の指針では、すべての企業に対して、方針の明確化・相談体制の整備・教育研修・実態把握の実施を求めています。
もし対応が遅れれば、損害賠償・行政指導・企業名公表など、深刻なリスクに発展しかねません。
また、社労士などの専門家に早期相談することで、法令遵守だけでなく、再発防止・就業規則の整備・外部対応までをトータルに支援してもらえます。
セクハラ防止は、経営層のリーダーシップと専門家の力を組み合わせることで、「誰もが安心して働ける職場」を実現する取り組みです。
セクハラ対策について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。