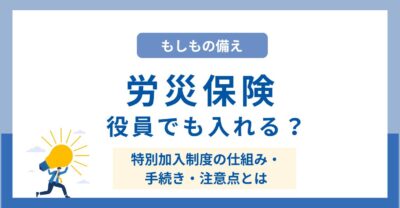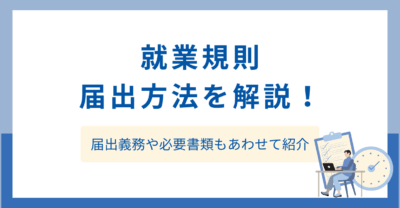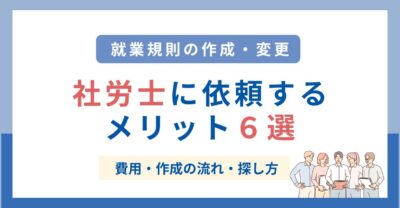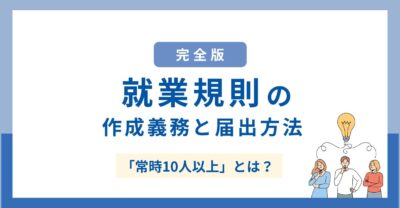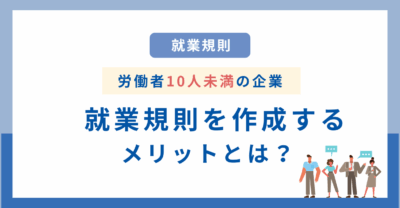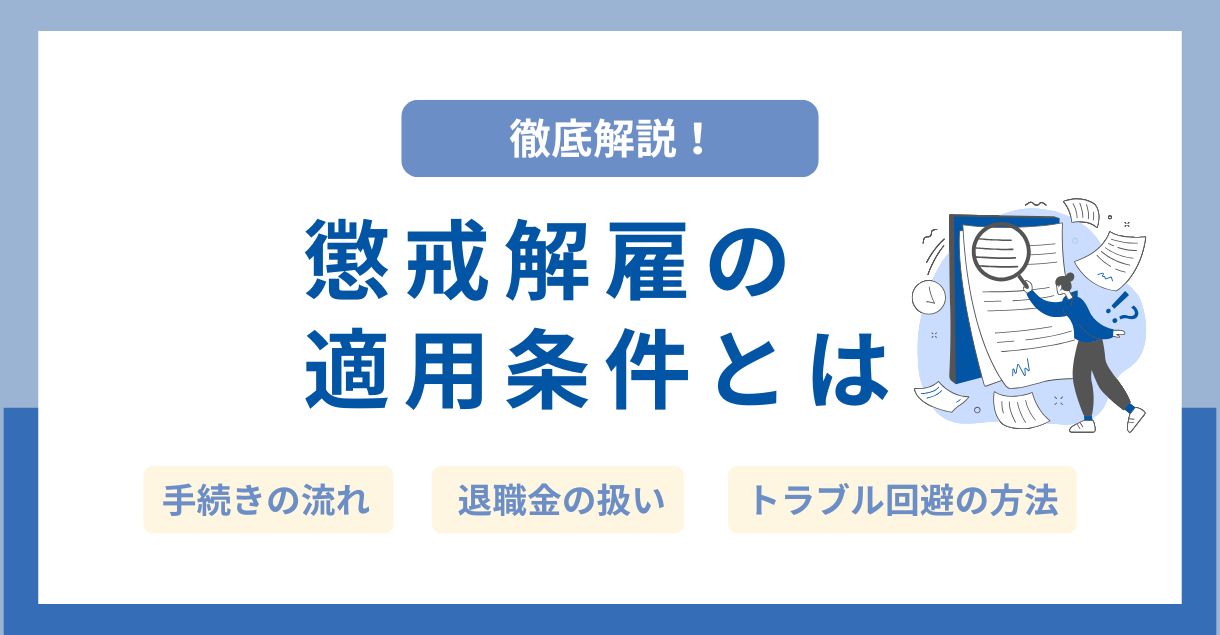
懲戒解雇とは?適用条件・手続き・退職金の扱いまで徹底解説!
懲戒解雇は、企業が従業員に対して行う最も重い処分です。
横領やハラスメントなど、重大な規律違反によって企業秩序を著しく乱す行為が対象であり、労働契約を一方的に終了させる強い法的効果を持ちます。
一方で、その適用を誤ると「不当解雇」と判断されるリスクがあり、退職金や雇用保険の基本手当(失業手当)の扱いをめぐるトラブルにも発展しかねません。
とくに中小企業では、「どの行為が懲戒解雇に該当するのか」「どのような手続きが必要か」といった判断に迷うケースも多く見受けられます。
本記事では、懲戒解雇の基本から適用条件、手続き、退職金の扱い、トラブル回避のポイントまでをわかりやすく解説します。
経営者や人事担当者の皆さまに向けて、リスクを抑えつつ、適切に対応するための実践的な知識をお届けします。
最後までご覧いただき、実務対応の参考としてご活用ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
懲戒解雇とは?普通解雇との違い
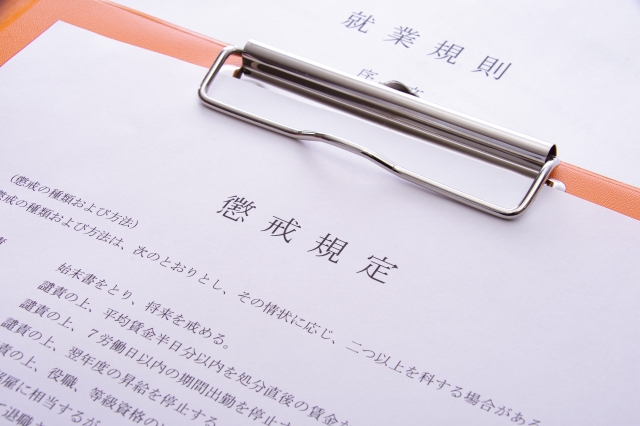
従業員による重大な違反行為に対し、企業が下す最も重い処分が「懲戒解雇」です。
横領や暴力行為などが対象となり、退職金の不支給や雇用保険の基本手当(失業手当)への影響など、従業員に強い不利益が伴います。
一方で、「普通解雇」や「諭旨解雇」と混同したまま処分を進めると、不当解雇と判断され、企業側に法的責任が及ぶ可能性もあります。
まずは、懲戒解雇の定義と他の解雇形態との違いを整理しましょう。
懲戒解雇の定義とは?
懲戒解雇とは、従業員の重大な規律違反などに対し、企業が懲戒処分として一方的に労働契約を解除する手続きです。
懲戒解雇が有効とされるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 就業規則に「懲戒解雇の定義」と「対象行為」が明記されている
- 規定に該当する違反行為が、事実として存在する
- 懲戒解雇が客観的に合理的で、社会通念上相当である
懲戒解雇の対象となる主な行為
- 横領や着服などの刑事事件
- 経歴詐称
- 長期の無断欠勤
- パワハラ、セクハラ など
ただし、これらに該当しても、手続きに不備があると無効とされる場合があります。
特に、「十分な事実関係の調査が無い」「対象となる従業員に弁明の機会を与えない」などの処分は、手続き的に不適切とされやすいため注意が必要です。
※上記の「主な行為」に該当する場合でも、事案によって判断が分かれることがありますのでご注意ください。
普通解雇・諭旨解雇との違い
懲戒解雇と混同されやすいのが「普通解雇」や「諭旨解雇」です。
処分の重さが大きく異なるため、企業側の理解が不可欠です。
| 解雇の種類 | 内容 | 主な理由 | 退職金 |
|---|---|---|---|
| 懲戒解雇 | 労働者が企業秩序を乱す行為等を行った場合、会社が一方的に雇用契約を終了 | 業務上の横領・暴力・重大な規律違反・背信行為など | 原則不支給 (一部不支給、全額不支給の場合あり) |
| 普通解雇 | やむを得ない事由があるときに、会社が労働契約を終了 | 能力不足、健康問題、経営悪化など | 支給される場合あり |
| 諭旨解雇 | 自主退職を促す (労働者が応じない場合は懲戒解雇となる) |
反省・情状等を考慮 | 支給される場合あり |
※退職金は企業の規定により異なります。
懲戒解雇は、企業秩序を守るうえで有効な手段ですが、慎重な運用が求められます。
普通解雇や諭旨解雇と違い、法的な扱いや退職後の対応も異なるため、就業規則の整備や証拠の確保、正当な手続きを徹底することが重要です。
就業規則の必要性については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:就業規則がないのは違法?10人未満でも作成する理由やリスクを解説)
懲戒解雇の適用条件

懲戒解雇は企業にとって極めて重い処分であるだけに、適用を誤れば「懲戒権の濫用」として無効となるリスクがあります。
裁判や労働審判に発展する可能性もあるため、どのような行為が懲戒解雇の対象となり得るのか、また、適用の際に注意すべきポイントは何かを把握しておくことが重要です。
ここでは、懲戒解雇に該当しうる行為の代表例と、無効と判断されるケースを解説します。
何をしたら懲戒解雇になるのか
懲戒解雇が成立するには、以下の2点を満たす必要があります。
- 就業規則に定められた懲戒事由に該当すること
- 社会通念上、懲戒解雇が妥当と認められること
懲戒解雇に該当する例として、以下の内容が挙げられます。
懲戒解雇に該当しうる行為の例
| 懲戒解雇に該当しうる行為 | 内容 |
|---|---|
| 経費の私的流用・横領 | 業務で扱う金銭を不正に使用・着服 |
| 無断欠勤の長期化 | 正当な理由なく、14日以上欠勤が続く |
| ハラスメント行為 | パワハラ・セクハラなど、職場秩序を乱す |
| 機密情報の漏洩 | 顧客情報や技術上の秘密を故意に第三者に開示 |
同じ行為でも、悪質性や経緯によって処分の重さは異なります。
懲戒解雇を判断する際は、事実関係を丁寧に確認し、就業規則と照らし合わせて慎重に進める必要があります。
懲戒解雇が無効と判断されるケース
懲戒権の濫用として、懲戒解雇が無効になるのは、手続きや処分の進め方に不備があるケースです。
懲戒解雇が無効と判断されるケース
- 就業規則に懲戒事由が定められていない
- 調査やヒアリングを行わず、一方的に処分した
- 社会通念上、懲戒解雇が重すぎる
- 労働者に弁明の機会を与えなかった
トラブル回避のために企業が取るべき対応は以下のとおりです。
- 客観的な証拠(記録・証言・書面など)を揃える
- 社内の懲戒委員会や第三者視点での判断体制を整える
- 弁明の機会を必ず設け、その記録も残す
後半部分の「懲戒解雇後のトラブルを防ぐための注意点」にて詳しく解説します。
懲戒解雇の流れと手続き
懲戒解雇を適切に行うには、明確な社内ルールの取り決めと、慎重な手続きが不可欠です。
労働契約法では「懲戒権の濫用」を禁じており、形式を欠いた処分は無効と判断される可能性があります。
ここでは、懲戒解雇に至るまでの実務的な手順を、4つに分けて解説します。
1.会社のルールを確認する
まず、自社の就業規則や懲戒処分に関する社内ルールを確認しましょう。
懲戒解雇が適正に成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 懲戒事由と処分の内容が就業規則に明記されている
- 就業規則を労働基準監督署に届け出済み
- 従業員に周知されている(社内掲示や社内ネットなど)
就業規則が未整備または周知不足だと、処分自体が認められず、企業の対応が不当と判断される可能性があります。
2.事実関係を調べ、本人に説明の機会を与える
次に、就業規則違反の事実があるかを調査します。
- 関係者へのヒアリング
- 関連書類や業務記録の精査
- 社内ルール・規程との照合
結果をもとに、対象従業員へ行為の内容と経緯を説明し、本人の主張や反論を聞く機会を設けます。
弁明の機会を与えない処分は、懲戒権の濫用とされる恐れがあるため注意が必要です。
3.社内で慎重に判断する
十分な調査と聴取を行い、処分の要否と内容を社内で協議します。
- 行為の悪質性や業務への影響
- 過去の類似事例との整合性
- 社会的常識との整合性
企業によっては、人事部門・コンプライアンス部門・社内弁護士等を交えた会議で判断する体制を整えています。
感情的・短絡的な判断を避け、公正な判断ができる体制を整えることが重要です。
4.正式な通知を出し、必要な手続きを行う
懲戒解雇が決定したら、2種類の書面を交付します。
解雇予告通知書(原則必要)
労働基準法第20条により、企業は30日前までに解雇を予告するか、または、即時解雇の場合は平均賃金30日分の「解雇予告手当」を支払う義務があります。
懲戒解雇であっても原則必要で、免除されるのは労働基準監督署の「解雇予告除外認定」を受けた場合に限ります。(解雇予告除外の例:横領や傷害行為など)。
懲戒解雇通知書(必須)
懲戒解雇の処分の内容を明示する正式書類です。以下のように記載します。
| 項目 | 記載内容 | 記載例 |
|---|---|---|
| 解雇理由 | 行為の事実・経緯 | 2025年6月5日、業務用クレジットカードを私的に使用したことが判明。 社内調査の結果、○○○万円の不正使用と認定。 |
| 根拠条文 | 該当する社内規定 | 就業規則第〇条第〇項(横領等の背信行為) |
| 解雇日 | 解雇の効力発生日 | 2025年7月15日付にて解雇とする |
| 処分の種類 | 「懲戒解雇」であること | 懲戒解雇とする |
| 通知日 | 通知書を交付した日 | 2025年6月5日 |
| 会社情報 | 社名、代表者名、押印など | 株式会社〇〇 代表取締役〇〇〇〇印 |
この2種類の書面は、処分の正当性を支える重要な証拠となるため、内容を正確に記載し、控えを保管することが大切です。
懲戒解雇になった場合、退職金はどうなる?
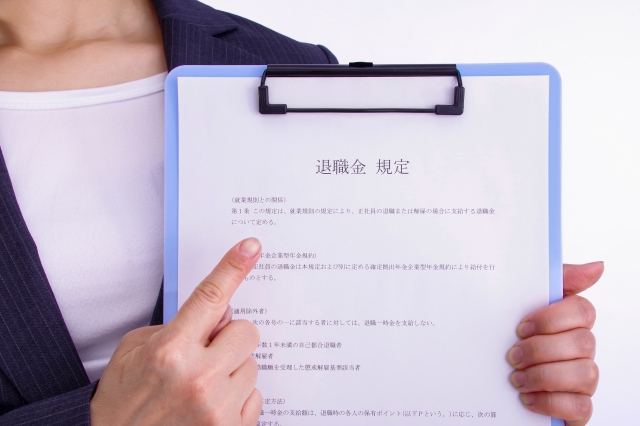
懲戒解雇でも、必ずしも退職金を全額不支給にできるわけではありません。
「懲戒解雇=退職金なし」と思われがちですが、実際には就業規則や状況によって異なり、不適切な対応は訴訟リスクや企業イメージの低下につながる可能性があるため、注意が必要です。
ここでは、不支給にできる条件と、企業がとるべき対応を整理して解説します。
就業規則で「退職金なし」とできる場合
退職金は法律で義務付けられている制度ではなく、就業規則や退職金規程に基づく社内制度です。
そのため、就業規則に以下のような記載があれば、懲戒解雇時に退職金を不支給にできます。
- 懲戒解雇の場合は退職金を支給しない」
- 「重大な背信行為があった場合、一部または全額を支給しない」
ただし、以下の2点を満たさなければ、のちに無効とされる可能性があります。
- 就業規則に退職金不支給の条件が明記されていること
- 内容が合理的であり、従業員に周知されていること
さらに、すべての懲戒解雇において無条件に退職金をゼロにできるわけではありません。従業員の功績や違反の内容によって、一部支給とする柔軟な対応が求められる場合もあります。
退職金をめぐるトラブルと企業のリスク
懲戒解雇において、特にトラブルが生じやすいのが「退職金の取り扱い」です。
「懲戒解雇だから支払わない」と企業が一方的に判断し、従業員から労働審判や訴訟を起こされ、一部支給が命じられたケースもあります。
たとえば、小田急電鉄事件(東京高裁・2003年)では、懲戒解雇は有効とされつつも、退職金の全額不支給は過剰と判断され、3割の支給が命じられました(出典:全基連/退職金請求控訴事件)。
これは、退職金が単なる「送別金」ではなく、以下のような社会的性格を持つためです。
- 長年の勤務に対する功労報酬(功労報償的性格)
- 将来の生活保障としての機能
たとえ不正行為があっても、それ以前の勤務状況や貢献を無視し、退職金を一律で不支給とする対応は「過剰処分」と判断される可能性があります。
企業がトラブルを回避するには、以下の対応が有効です。
- 不支給の条件や範囲を就業規則に明記する
- 違反の程度に応じた支給ルールを設ける
- 必要に応じて社労士や弁護士へ相談する
退職金の扱いひとつで、企業の法的責任や信用失墜に発展することもあります。感情的な判断は避け、制度と手続きの両面から冷静に対応することが重要です。
懲戒解雇後に必要な手続き
懲戒解雇後も、企業には法的・実務的な手続きが数多く求められます。
手続きが不備だと、不当解雇・雇用保険の基本手当(失業手当)の給付制限トラブル・行政からの指摘といったリスクに発展する可能性もあります。
特に、「離職票の記載」と「社会保険・雇用保険の資格喪失手続き」は、企業の信頼性にも関わるため、正確さが求められます。
離職票の記載方法-普通解雇とは異なるポイント
離職票(雇用保険被保険者離職票)には、退職理由を正確に記載する必要があります。
離職理由の項目では、普通解雇は「会社都合退職」と記載されるのが一般的ですが、懲戒解雇の場合は「重責解雇」と記載します。また、ハローワークでの雇用保険給付制限の扱いや具体的事実の記載も異なるため、確認しておきましょう。
| 項目 | 普通解雇 | 懲戒解雇 |
|---|---|---|
| 離職理由の記載 | 会社都合退職 | 重責解雇 |
| 雇用保険給付制限の扱い | 給付制限なし(7日間の待機期間の後、支給) | 原則、最大3ヶ月の給付制限あり(+7日間の待機期間) |
| 具体的事実の記載 | 記載がなくても認定されやすい | 客観的事実を記載する必要がある (例:「就業規則第○条に基づく処分」) |
「普通解雇と書けば穏便に済む」といった誤解から記載を誤るケースもありますが、これは行政上も不適切とされるため注意が必要です。
社会保険・雇用保険の資格喪失手続き
懲戒解雇であっても、一般退職と同様に資格喪失手続きは必須です。
| 手続き項目 | 提出期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険資格喪失届 | 解雇の日の翌日から5日以内 | 年金事務所 |
| 雇用保険資格喪失届・離職証明書 | 解雇の日の翌日から10日以内 | ハローワーク |
さらに、住民税の特別徴収分の精算・源泉徴収票の交付・企業からの貸与物(社員証・PCなど)の返却処理なども必要になります。
雇用保険の給付制限に関する注意点
離職票に「懲戒解雇」と記載されると、ハローワークでの判断により最大3ヶ月の給付制限が設けられる可能性があります。
この影響により、「処分は重すぎる」と従業員が反発し、トラブルに発展するケースも見られます。
違反内容が軽微な場合は、就業規則での処分区分(諭旨解雇・戒告など)を再検討し、表現や処分の妥当性を事実と照らし合わせて慎重に判断することが重要です。
懲戒解雇後のトラブルを防ぐための注意点

懲戒解雇は、企業・従業員の双方にとって、精神的・社会的な負担が大きい処分です。
特に、手続きミスや説明不足によって「不当解雇」や「名誉毀損」などのトラブルに発展すれば、企業の信用やブランドに深刻な影響を及ぼします。
ここでは、懲戒解雇後のトラブルを防ぐために、押さえるべき4つの実務ポイントを紹介します。
1.証拠と記録の管理
懲戒解雇が正当と認められるには、客観的な証拠と記録の保存が不可欠です。
- 行為の発覚日時・内容
- 関係者ヒアリング記録
- 適用する就業規則の条文・規定
- 社内審査(懲戒委員会など)の記録
感覚的・曖昧な対応では、労働審判や訴訟で不利になる可能性があるため、確実な記録管理が重要です。
2.処分理由の説明責任を果たす
「なぜ懲戒解雇に至ったのか」「何が違反だったのか」を本人に明確に説明し、反論の機会を設ける必要があります。
通知書の交付だけでなく、以下の内容を口頭や書面で伝えることが重要です。
- 違反行為とその経緯
- どの規則に反していたのか(就業規則の条文)
- 弁明の場を設けた記録
説明不足は、従業員側から「処分理由が不明確」とされ、不当解雇の主張につながるリスクがあります。
3.名誉とプライバシーへの配慮
懲戒解雇の事実が周囲に知れ渡ることで、従業員の社会的信用に影響が出るおそれがあります。情報共有の範囲や表現には十分な配慮が求められます。
- 社内報・朝礼での氏名公表は避ける
- 担当変更や引継ぎも、処分理由には触れない
- 社外対応は最小限・必要な範囲にとどめる
企業としては「処分の正当性」と「本人の名誉」のバランスを意識した対応が求められます。
4.専門家への早期相談
懲戒解雇は、法的な判断や書類作成に高い専門性が求められます。判断が難しい場面では、社労士や弁護士への早期相談が有効です。
- 曖昧な処分理由に関する調査対応
- 就業規則の表現見直し
- 離職票の記載相談 など
専門家の視点を取り入れることで、処分の妥当性やトラブルリスクが明確になり、より適正な対応が可能になります。
まとめ|懲戒解雇は慎重に!トラブル回避に備えよう
本記事では、懲戒解雇の定義や普通解雇との違い、適用条件や正しい手続きの流れ、退職金の扱い、そして懲戒解雇後の手続きと注意点までを詳しく解説しました。
懲戒解雇は、企業にとって最も重い処分であると同時に、対応を誤れば法的トラブルや信頼失墜につながるおそれがあります。
だからこそ、就業規則の整備や証拠の確保、適正な手続き、従業員への説明など、各ステップを丁寧に進めることが重要です。
特に中小企業では、法務・労務の専門部署がないことも多いため、判断に迷う場面では社労士や弁護士といった専門家に相談することが、リスクを未然に防ぐ有効な手段となります。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。