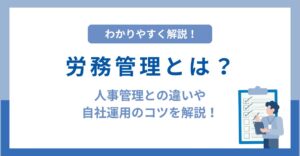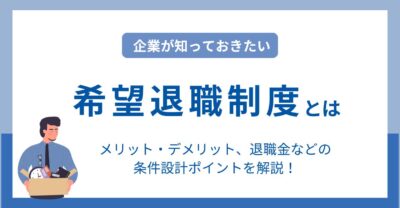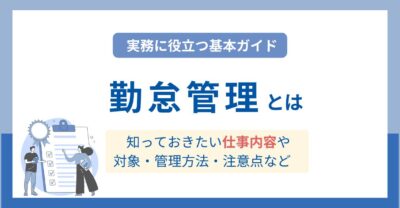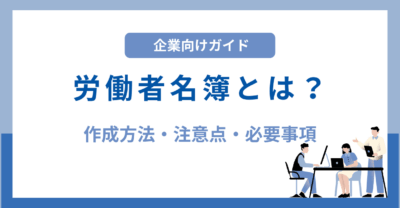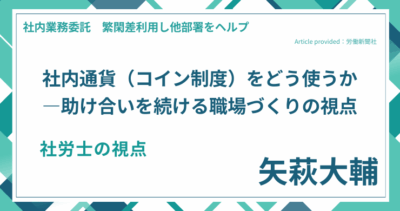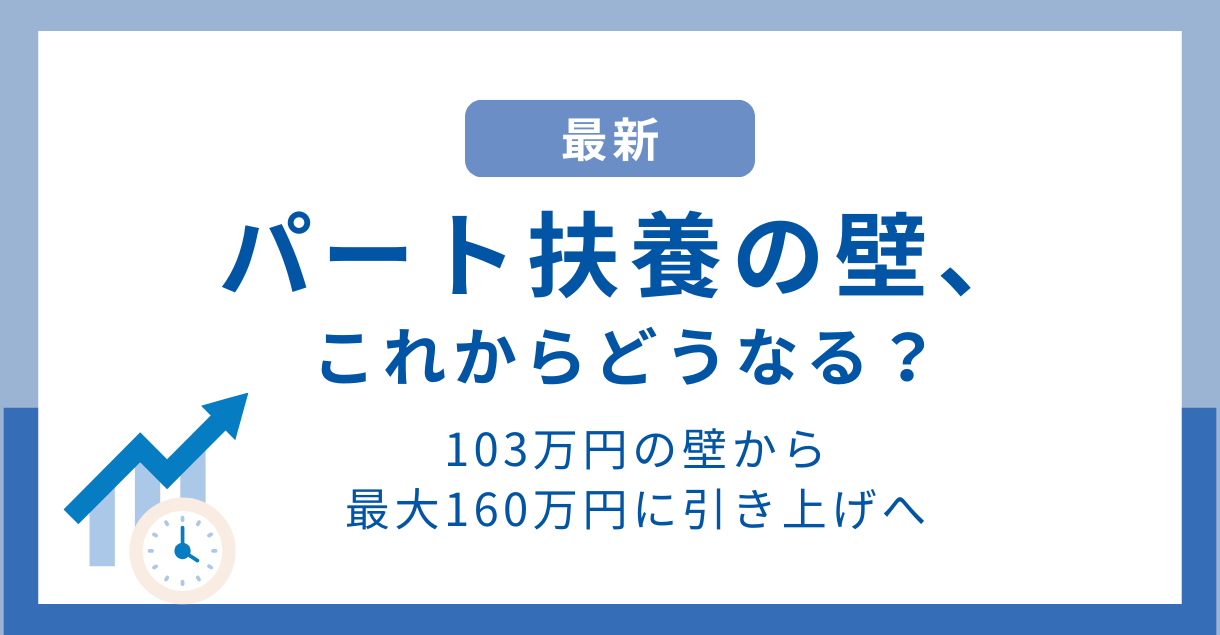
【最新】“パート扶養がなくなる”は誤解?年収の壁一覧とポイント整理
近年、税制や社会保険制度の見直しが進むなかで、「パート扶養がなくなるのではないか」といった不安の声が聞かれるようになってきました。
この背景には、年収によって税金や保険料の負担が発生する「年収の壁」に関する制度変更があります。
たとえば、2025年には、所得税に関し、給与所得控除と基礎控除の見直しにより、最大160万円まで非課税(年収200万円以下の場合)となる税制改正が決定しました。
さらに、2025年年金改正法が成立し、2025年6月20日から3年以内には、社会保険の「月収8.8万円以上」という加入要件(いわゆる 「106万円の壁」)が撤廃されることになり、働き方や雇用管理にも大きな影響が及ぶ可能性があります。
こうしたなか、特にパート労働者を多く雇用している中小企業では、これまで「扶養内」で働いていた労働者が今後もそのままの条件で働き続けられるのか、どの法改正が自社に影響するのかといった不安や疑問を抱える場面が増えているのではないでしょうか。
本記事では、「扶養制度がなくなる」という誤解されがちな情報の整理に加え、企業が押さえておくべき2025年の税制の変更点と、実務に役立つ対応策をわかりやすく解説します。
ぜひご一読いただき、今後の対応にお役立てください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
“パート扶養がなくなる”は誤解?2025年税制改正のポイントを整理

社会保険の適用要件の拡大により、「パート扶養がなくなるのでは?」という声も一部で聞かれていますが、扶養制度そのものが廃止されるわけではありません。
年収要件の見直しにより、“扶養内で働く”というこれまでの基準が変化する可能性がある、というのが正確な理解です。
実際に、2025年の税制改正により、所得税が課税される年収の基準が160万円まで引き上げられます。
以下、2025年に実施されるその改正と経緯について詳しく解説します。
一時検討された「103万円→123万円」案とは?
2024年の年末に発表された自民党・公明党の「令和7年度税制改正大綱」では、所得税が発生する年収基準を103万円から123万円へ引き上げる案が盛り込まれました。
これは、基礎控除、給与所得控除の金額をそれぞれ引き上げることで実現するもので、具体的には以下のような見直しが検討されていました。
〈123万円案〉
| 控除 | ~2024年 | 2025年以降(変更前との差) |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 48万円 | 58万円(+10万) |
| 給与所得控除 | 55万円 | 65万円(+10万) |
| 合計 (非課税枠) |
103万円 | 123万円 |
この2つの控除を合計すると、年収123万円まで所得税が課されないという仕組みになります。
そのため、「扶養控除を受けたいパート社員が調整するライン」が、これまでの103万円から123万円にシフトすると想定され、多くのメディアでも「103万円の壁が緩和される」と注目されました。
しかし、この123万円案は最終的に撤回され、より的確に低所得層の支援を厚くする新制度へと切り替えられました。
決定したのは「最大160万円まで非課税」の新制度
最終的に決定されたのは、年収に応じて基礎控除額を段階的に上乗せする「定額減税を含む新たな税制改正」です。
この改正により、年収200万円以下の場合、最大で160万円まで所得税が非課税となる仕組みが導入されました。
| 項目 | ~2024年 | 2025年以降(変更前との差) |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 48万円 | 95万円(+47万円)※ |
| 給与所得控除 (最低額) |
55万円 | 65万円(+10万円) |
| 合計 (課税最低限) |
103万円 | 160万円 |
※基礎控除95万円は、年収200万円以下に限り恒久措置として適用
また、年収200万超〜850万円以下の層にも、2年間限定(2025年・2026年)で基礎控除の上乗せ措置が適用されます。
〈新制度での年収に応じた控除額〉
| 年収 | 基礎控除(変更後) | 上乗せ額(適用期間) |
|---|---|---|
| ~200万円 | 95万円 | 37万円(恒久措置) |
| 200万超~475万円以下 | 88万円 | 30万円(2年間) |
| 475万超~665万円以下 | 68万円 | 10万円(2年間) |
| 665万超~850万円以下 | 63万円 | 5万円(2年間) |
このように、今回の改正では、「一律103万円→123万円」という単純な基準の引き上げではなく、年収層に応じて控除額を細かく設定する、より公平でターゲットを絞った支援が導入されています。
とくにパート社員にとっては、課税最低限が160万円に引き上げられたことにより、これまでのような就業調整の必要性が軽減される可能性があります。
企業の人事担当者としては、「103万円の壁」が見直された背景や制度変更のポイントをわかりやすく伝え、労働者が安心して働ける環境づくりにつなげることが大切です。
2025年以降どう変わる?年収の壁一覧表(103万・106万・130万など)

パート扶養の維持に大きな影響を与える収入ラインとして、以下の5つの壁が挙げられます。
以下の表では、これらの年収の壁がどの制度に関係し、どのような影響があるのか、そして改正の有無や時期をまとめています。
年収の壁と発生する影響まとめ
▼リンクをクリックすると、解説箇所にジャンプできます
| 年収の壁 | 発生する影響 | 【時期】現状と変更予定 |
|---|---|---|
| 103万円の壁→160万円へ | 所得税が発生するようになる | 【2025年~】課税最低限を160万円へ引き上げ(控除の増額による) |
| 106万円の壁 | 一定の要件(※1)を満たすと、社会保険の加入が義務となる | 【2024年10月~】対象企業が51人以上に拡大 【2025年6月20日~3年以内】月収要件(8.8万円以上)の撤廃 |
| 130万円の壁 | 扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要がある | 【現在】130万円未満でも、条件により社会保険加入が必要となるケースあり |
| 150万円の壁(※2) | 配偶者の税控除額が段階的に減少しはじめる | 変更なし |
| 201万円の壁 (※2) |
配偶者控除が受けられなくなる(完全に対象外) | 変更なし |
※2:配偶者特別控除(150万・201万円の壁)は、扶養されるパート本人ではなく、扶養する側の納税者の税額に関わる制度です。社会保険の扶養とは異なるため、混同には注意が必要です。
以下、それぞれ解説します。
103万円の壁の見直し|2025年から課税最低限が160万円に
「103万円の壁」とは、パート社員が扶養内で働く場合に意識される、所得税の課税対象とならない収入の上限です。
2025年度の税制改正により、給与所得控除・基礎控除の引き上げが決定しました。これにより、課税最低限が160万円となる新制度がスタートします。
| 項目 | ~2024年 | 2025年以降(変更前との差) |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 48万円 | 95万円(+47万円)※ |
| 給与所得控除 (最低額) |
55万円 | 65万円(+10万円) |
| 合計 (課税最低限) |
103万円 | 160万円 |
※年収により変動。基礎控除の上乗せは、年収200万超〜850万円以下の方を対象に2025年、2026年の2年間限定。
詳しくは、前半部分の『決定したのは「最大160万円まで非課税」の新制度』で解説しています。
今回の改正により、これまで就業調整をしていたパート社員も働き方の選択肢が広がる可能性があります。ただし、これは所得税の制度変更で、社会保険や住民税の要件は変わっていないため、他の壁にも注意が必要です。
106万円の壁:社会保険の適用拡大(2024年10月〜)
「106万円の壁」とは、一定条件を満たす短時間労働者に、社会保険の加入義務が発生する年収の目安です。
下記の条件すべてに該当した場合、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が必要です。
社会保険加入の条件(2024年10月以降)
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 企業規模 | 労働者数が51人以上(2024年10月以降) |
| 労働時間 | 週20時間以上 |
| 月収 | 月額8.8万円以上(年収換算:約106万円) |
| 雇用見込み | 2ヶ月超の見込みあり |
| 学生 | 原則、学生は対象外(例外:夜間・通信制等) |
さらに、2025年年金法改正では、「月収8.8万円以上」の要件を撤廃する方向で見直しが検討され、同法の公布日(2025年6月20日)から3年以内に月収要件は撤廃されることになっています。
また、2025年改正法では、企業規模要件についても、2027年10月以降、段階的に撤廃していくことが決まりました。これが実現すると、週20時間以上勤務するパート社員のほとんどが、社会保険の対象となる可能性があります。

引用:被用者保険の適用拡大及び第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応について②|厚生労働省
社会保険の加入対象を正しく見極めるためには、年収だけでなく、勤務時間や企業規模もあわせて確認しておくことが重要です。
社会保険については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:社会保険とは?概要から保険料の計算方法まで徹底解説!)
130万円の壁:扶養から外れる年収の上限
130万円の壁とは、 社会保険上で配偶者の扶養から外れるかどうかを左右する年収の上限です。
年収が130万円を超えると、社会保険上の扶養の対象外となるため、本人が自ら社会保険に加入し、保険料を負担する必要があります。
勤務先で社会保険に加入しない場合には、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
一方で、近年の社会保険の適用拡大により、年収130万円未満でも社会保険の加入対象となるケースが生じているため、注意が必要です。
■ 130万円未満でも社会保険の加入対象となるケース
たとえば、労働者数51人以上の企業に所属し、週20時間以上の勤務、月収が8.8万円(年収換算で約106万円)であれば、扶養から外れ、本人が社会保険の加入対象となります。(いわゆる「106万円の壁」)
企業としては、「130万円未満だから扶養内で問題ない」と安易に判断せず、勤務時間や雇用形態も含めて適切に確認することが求められます。
社会保険の加入義務については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:社会保険の加入義務とは?パートの適用拡大と企業の対応ポイントを解説)
150万円/201万円の壁:配偶者特別控除の制限
「150万円の壁」「201万円の壁」とは、パートなどで働く配偶者の年収に応じて、配偶者特別控除が変動する年収ラインです。
これは社会保険ではなく税制上の仕組みで、主に配偶者を扶養している側(例:夫)の所得税に影響します。
| 配偶者の年収 | 配偶者特別控除の扱い |
|---|---|
| 〜150万円 | 控除満額(38万円) |
| 150万円超〜201.6万円未満 | 控除額が段階的に減少 |
| 201.6万円以上 | 控除なし(対象外) |
この制度は、労働者の働き方や就業時間の調整にも影響しやすい要素のひとつです。企業としては、こうした制度背景を理解したうえで、希望に応じた柔軟な対応が重要となります。
「扶養から外れる」と何が変わる?企業とパート社員それぞれの影響

年収の増加や社会保険の適用範囲拡大により、配偶者の扶養から外れ、自ら社会保険に加入するパート社員が増えつつあります。
この変化は、本人の働き方や企業の人件費管理にも影響を及ぼすため、企業側の理解と備えが重要です。
ここでは、扶養から外れた場合(労働者が自身で社会保険に加入する場合)のメリット・デメリットを、企業と労働者の両面から整理します。
■企業側の視点
メリット
- 長期雇用の促進や、福利厚生面での信頼感向上につながる
- 正社員との待遇格差が縮まり、法令遵守・コンプライアンス面の強化になる
デメリット
- 社会保険料の事業主負担が増える
- 就業管理や説明対応など、労務管理対応の負担が増す
- 扶養内で働きたい」という希望が強い場合、離職やシフト調整が難航する可能性がある
制度変更への対応には一時的な負担もありますが、結果的には職場の安定や法的リスクの回避につながります。労働者との対話を重ね、信頼関係を築くことが大切です。
■パート社員の視点
メリット
- 将来の年金受給額が増える
- 医療保険の保障内容が充実する(扶養時より充実)
デメリット
- 社会保険料の自己負担が発生し、短期的に手取り額が減る可能性
- 制度が複雑で、自分がどの制度に該当するか不安になりやすい
扶養を外れることで、一時的な負担感がある一方で、将来への保障は強化される側面があります。そのため、労働者が制度を前向きに受け止められるよう、企業からの丁寧な説明やサポートが欠かせません。
人事・労務担当者がすべき実務対応とは?
企業として段階的に進む制度変更に対応していくためには、対象者の把握から社内体制の整備、必要に応じた外部連携までを計画的に進めることが重要です。
労働者への影響を最小限に抑えつつ、スムーズに対応をするために、以下の実務対応が有効です。
① 対象者のリストアップと影響の把握
週20時間以上・月収8.8万円以上に該当するパート・アルバイトを事前にリストアップし、社会保険加入の可能性や、手取りへの影響を整理しておきます。社内全体の把握を進めておくことで、制度変更時の混乱を防ぎやすくなります。
② 社内説明資料の整備と説明会の実施
対象者への説明は、制度の背景や加入後の変化をわかりやすく伝えることが大切です。説明会や個別面談を通じて、不安や疑問を解消したうえで導入できるようサポートします。
③ 就業規則・雇用契約書の見直し
労働時間や社会保険加入条件の変更にあわせて、就業規則や契約書の該当箇所(勤務条件や社会保険加入基準など)の確認が必要です。特に「社会保険未加入」を前提とした記述が残っていないかをチェックし、必要があれば明文化・修正を行いましょう。
④ 社労士など専門家との連携
最新の法改正情報や実務上の判断に迷った際は、社会保険・労務管理に精通した社労士に相談することが有効です。制度ごとの適用判断や、社内書類の見直し、労働者対応まで、外部の専門知識を活用することで対応の精度とスピードを高められます。
専門家との連携が安心|パート扶養問題の適切な対応をサポート

頻繁に見直される税制や社会保険制度に対応するためには、最新の制度に即した判断と正確な手続きが欠かせません。
税制は税理士へ、社会保険制度は社労士へ、専門家に相談するのがおすすめです。
特に以下のような場面で、その専門性が発揮されます。
- 社会保険の適用基準の判断(加入対象者の特定など)
- 制度変更に合わせた社内説明資料の作成や労働者説明のサポート
- 就業規則や雇用契約書の制度対応に伴う見直し・修正
- 行政機関への申請書類の作成、手続きのアドバイス・代行
特に中小企業では、人員や体制の面から、法改正への対応を社内だけで完結させるのが難しいこともあります。
そうした場合でも、専門家と連携することで、制度変更への対応を確実かつスムーズに進めることが可能です。
まとめ|今後の変化に備えて早めの対応を!
「パート扶養がなくなる」という言葉が注目を集めていますが、実際に変わるのは制度の廃止ではなく、その前提となる社会保険・税制のルールです。
とくに2024年から2028年にかけては、「年収の壁」に関する制度改正が段階的に進行し、企業側にも正確な対応が求められる場面が増えていきます。
保険料負担や労務管理、社内説明の準備など、現場対応は一時的に負荷となるかもしれません。しかし、それを制度への理解を深め、労働者との信頼関係を築くチャンスと捉えることで、より持続可能な組織づくりにつながります。
こうした変化への備えとして、専門家との連携は非常に有効な手段のひとつです。専門家のサポートを受けながら、自社にとって最適な対応を見つけていきましょう。