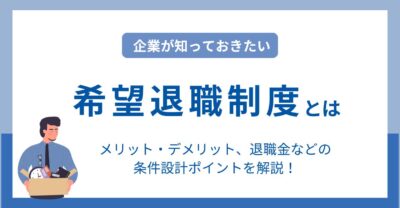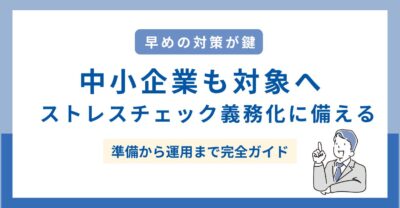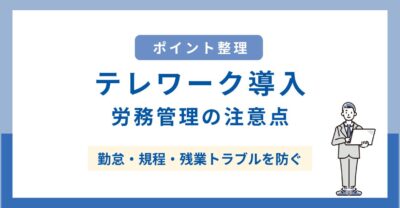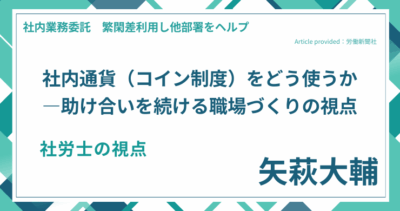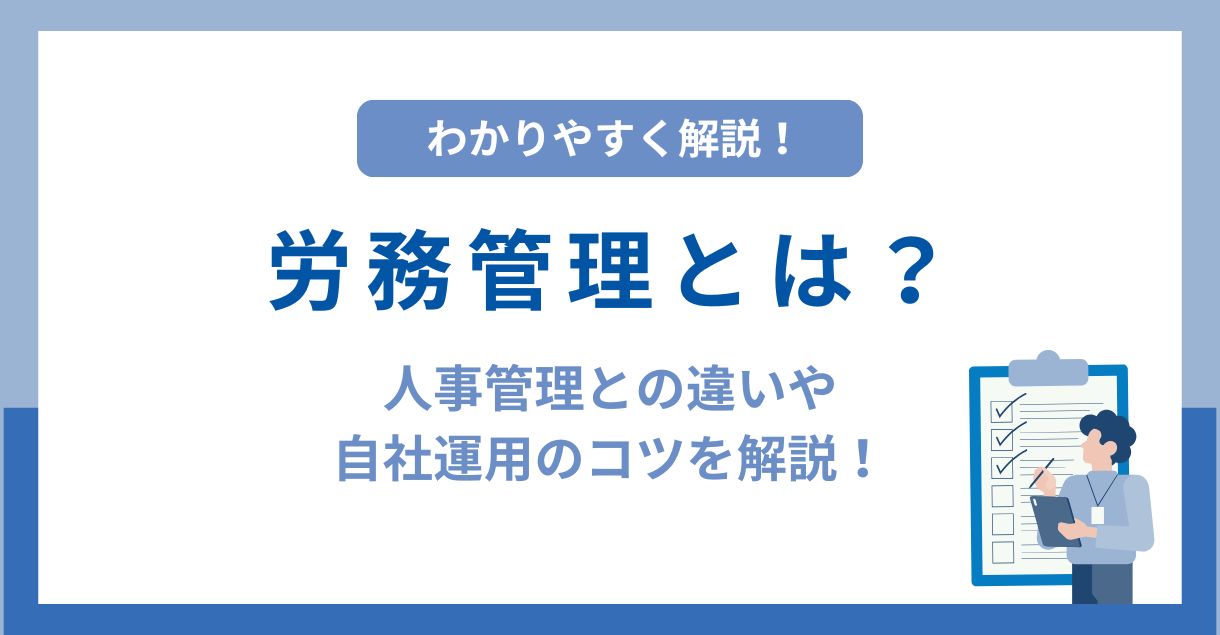
労務管理とは?人事管理との違いから自社運用のコツまでわかりやすく解説
労務管理とは、労働者の労働条件や勤務環境を、企業が法令に基づいて整備・運用することを指します。
単なる事務作業ではなく、企業が守るべき義務であり、信頼される職場づくりのためにも重要な業務です。
労働時間の管理、給与や社会保険の手続き、職場の安全対策まで対応範囲は多岐にわたり、正しく行わなければ法令違反や労使トラブルといったリスクに直結します。安定経営のためには、適切な体制整備が大切です。
本記事では、労務管理の基本的な定義から、主な業務内容、人事管理との違い、さらに注意すべきポイントや自社運用のコツまで、実務に直結する内容をわかりやすく解説します。
労務管理の見直しを検討する企業担当者の方にとって、実践的なヒントとなる内容です。ぜひご活用ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
労務管理の定義と目的

労務管理は、企業が労働関係の法令に沿って労働者の労働条件や職場環境を整え、円滑な労使関係を築くために行う業務のことです。
労働時間・休日・賃金・福利厚生・安全衛生などを適切に管理します。一見すると事務的な作業に見えるかもしれませんが、労務管理は企業経営の基盤として、企業の信頼性の確保や生産性の向上にも直結します。
主な目的は次のとおりです。
- 労働関係法令を守り、企業としての信頼を高める
- 働きやすい職場環境を整え、労働者の定着やモチベーションを向上させる
- 労使トラブルを未然に防ぎ、生産性や職場の安定を守る
このように労務管理は、法令遵守にとどまらず、企業のリスク管理や人材マネジメントの基盤となる役割を担っています。
労務管理の主な業務内容

労務管理は、労働者が安心して働ける環境を整え、企業として労働関係法令を適切に運用するための多様な業務が含まれます。
労務管理の実務は、給与や勤怠などの基本業務に直結しており、正確な運用が企業と労働者の信頼関係につながります。
代表的な業務とその概要
| 業務名 | 内容の概要 |
|---|---|
| 労働契約管理 | 労働条件通知書・雇用契約書の作成・保管・更新 |
| 就業規則の整備 | 社内ルール(就業時間・服務規律など)の作成・改定 |
| 勤怠管理 | 出退勤・残業・休暇など、労働時間に関する記録・管理 |
| 給与計算 | 勤怠データに基づく給与額の算出・支給 |
| 社会保険手続き | 健康保険・厚生年金・雇用保険などの加入・喪失・変更の処理 |
| 安全衛生管理 | 健康診断、ストレスチェック、災害防止策の実施 |
| 福利厚生の運用 | 住宅手当、育児支援、社内イベントなど任意制度の整備 |
以下、それぞれの業務について詳しく説明します。
労働契約管理
目的:
労働条件を明確にし、労使トラブルを未然に防ぎながら、企業と労働者の信頼関係を構築する。
主な対応内容:
- 「労働条件通知書」や「労働(雇用)契約書」の作成・保管・更新
- 契約内容の定期的な見直し
注意点:
労働基準法第15条では、労働条件の明示が義務付けられています。特にパート社員や契約社員など雇用形態が多様化している企業では、管理が属人化しやすく、運用が不統一になりがちです。
契約内容や更新スケジュールを明確にし、共通の運用ルールを整備しておくと、実務対応のばらつきを防ぐことができます。
就業規則の整備
目的:
職場内のルールを文章で明確にし、企業と労働者が共通理解をもって働ける環境を整備する。
主な対応内容:
- 就業時間、休暇、服務規律、懲戒規定などを記載した就業規則の作成・改定・周知
- 労働者が常時10人以上いる事業所では、労働基準監督署への届出が義務(労働基準法第89条)
注意点:
実態とかけ離れた規則や、法改正に未対応の就業規則を運用していると、トラブル時に企業側が不利になる可能性があります。就業規則は、作成後の定期的な見直しと、社内通知(掲示・配布など)を通じた運用が重要です。
就業規則については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:就業規則の届出方法を解説!届出義務や必要書類もあわせて紹介)
勤怠管理
目的:
労働時間を正確に把握し、法令を遵守しながら、労働者の健康管理と職場環境の維持を図る。
主な対応内容:
- 勤怠(出退勤、残業、深夜・休日労働、有給休暇などの勤務時間)をまとめて記録・管理
- 時間外労働がある場合は、36協定の締結および所轄労働基準監督署への届出が必要(労働基準法第36条)。
注意点:
打刻と実際の勤務時間にズレがあると、残業代の未払いや過重労働のリスクが高まります。協定内容(36協定)が現場で適切に反映されているか、定期的に確認する必要があります。
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)の詳細については、下記の記事もあわせてご覧ください。
>「企業が知るべき「36協定」とは?特別条項・届出方法・違反リスクまで徹底解説」
給与計算
目的:
労働関係法令に則り、給与を正しく支給することで、労働者との信頼関係を築く。
主な対応内容:
- 勤怠情報・手当・控除(社会保険料・所得税など)に基づいた給与額の算出・支給
- 年末調整や住民税の管理を含む関連業務の実施
注意点:
勤怠管理との連携が不十分な場合、支給ミスや過少・過大控除などのトラブルが生じる可能性があります。また、社会保険料率や税制改正など制度変更にも適時対応する必要があります。
社会保険手続き
目的:
労働者が必要な社会保障を受けられるよう、法令遵守の体制を構築する。
主な対応内容:
- 健康保険、厚生年金、雇用保険に関する加入・喪失・変更の申請および届出
- 労働災害時の治療や休業などに関する給付申請
- 育児休業や介護休業時の給付金申請など、ライフステージに応じた対応
注意点:
入退社や扶養変更、育児・介護休業など、個別の事情に応じた正確な対応が求められます。手続きの誤りや遅延があると、給付漏れや保険料の過徴収、行政指導の対象となる恐れがあります。制度内容や手続きフローを理解し、スムーズに対応できる体制を整えることが重要です。
社会保険の詳細や具体的な手続きの流れについては、こちらの記事もぜひご参照ください。
>「社会保険とは?企業が知っておくべき加入条件や必要書類を解説!」
安全衛生管理
目的:
労働者の心身の健康と安全を守り、安心して働ける職場環境を維持・向上する。
主な対応内容:
- 定期健康診断、ストレスチェックの実施
- 災害防止策の整備、衛生管理者・産業医の選任など(労働者50人以上の事業場では義務)
注意点:
労働安全衛生法に基づく体制整備は、法令遵守にとどまらず、労働者の健康保持・安全配慮義務の履行としても企業責任に関わります。制度の形骸化を防ぐため、定期的に見直しを行い実効性のある運用と改善を意識しましょう。
福利厚生の運用
目的:
労働者の働きやすさや満足度を高め、人材の定着率の向上や企業の魅力アップにつなげる。
主な対応内容:
- 法定外福利厚生※の設計・運用(住宅手当・通勤手当・健康診断補助・育児支援・社内イベントなど)
- 利用条件や申請方法の明文化と社内周知
※法定外福利厚生とは:法律で義務づけられていない任意制度のこと(例:住宅手当や社内イベントなど)。一方、健康保険や厚生年金などは「法定福利厚生」と呼ばれます。
注意点:
福利厚生制度は導入義務のない任意の取り組みである一方で、運用が不公平な場合や、内容が周知されていない場合は、労働者の不満や不信感につながることがあります。
全労働者が安心して利用できるよう、制度の整備や情報発信を行いましょう。
労務管理と人事管理の違い

企業において、「労務管理」と「人事管理」はどちらも欠かせない業務ですが、それぞれの目的や管理対象には明確な違いがあります。
労務管理は、労働時間・給与・社会保険・安全衛生といった職場の基盤を支える運用業務です。労働関係法令を遵守しつつ、働きやすい環境を整えることを目的とします。
一方、人事管理は、採用・育成・配置・評価などを通じて、将来を見据えた人材活用の分野を担います。
労務管理と人事管理の違い
| 比較項目 | 労務管理 | 人事管理 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 労働環境全体の最適化とリスク管理 | 組織力の向上、人材の最適配置 |
| 担当領域 | 労働契約、勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、安全衛生管理など | 採用・評価・配置・研修・人材戦略 |
| 管理の視点 | 運用中心(制度・手続き) | 戦略中心(人材開発・組織成長) |
中小企業ではこれらの業務を一人の担当者が兼務していることも多いため、目的や領域を正しく把握し、必要に応じて業務を切り分けることが、効率化や組織強化につながります。
労務管理と勤怠管理の違い

労務管理と勤怠管理は密接に関係していますが、主に対象業務の範囲と目的に明確な違いがあります。
労務管理は、労働条件・就業制度・社会保険・安全衛生などを整える制度設計・労働関係法令対応のための包括的な管理業務です。
一方で、勤怠管理は、労務管理の一部分として、労働時間・残業など日々の勤務状況を正確に記録・運用する業務を担います。
労務管理と勤怠管理の違い
| 比較項目 | 労務管理 | 勤怠管理 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 労働環境全体の最適化とリスク管理 | 労働時間の記録・日常的な勤怠の把握 |
| 担当領域 | 労働契約、勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、安全衛生管理など | 出退勤・残業・有給休暇の取得管理 |
| 管理範囲 | 包括的(職場環境・労務制度全体の整備)※勤怠管理も含む | 部分的(日常の勤怠記録・運用に特化) |
両者の違いを正しく理解し、制度設計(労務)と日常運用(勤怠)をバランスよく連携させることで、労務管理の精度が高まり、トラブル予防や効率化にもつながります。
「労務管理」における課題と注意すべきポイント

労務管理は、企業経営の土台を支える重要な業務です。とくに現場で注意すべき代表的な課題として、以下の5つが挙げられます。
- 法令遵守の徹底
- 長時間労働の是正
- 多様な働き方への対応
- トラブル対応の遅れ
- 管理体制の属人化
それぞれの課題について、順にわかりやすく解説していきます。
① 法令遵守の徹底
労務管理の基本は、労働関係法令の正確な理解と適切な運用です。
労働基準法や育児・介護休業法、労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止措置など、労務管理に関係する法令は年々改正され、制度は多岐にわたり複雑化しています。
一方で、現場では「忙しくて手が回らない」「どの改正が自社に関係あるか判断できない」などの理由から、対応が後回しになりがちです。
その結果、知らず知らずのうちに法令違反の状態となっていたケースも少なくありません。
対策:
法改正の動向を定期的にチェックし、就業規則や運用ルールを継続的に見直す体制を構築しましょう。
② 長時間労働の是正
長時間労働の常態化は、企業の生産性や信頼性に深刻な影響を及ぼします。
働き方改革関連法により、時間外労働の上限(月45時間・年360時間)は明確に定められています。
しかし、業務量の偏りや勤怠管理の不備により、過剰な労働時間が是正されないまま放置されている職場も少なくありません。
とくに管理職や少人数体制の部署では、慢性的な残業が常態化しやすく、労働者の健康リスクや労災リスクが高まる傾向にあります。
過重労働が健康被害につながった場合、企業の対応が問われ、信頼性にも影響を及ぼす可能性があります。
対策:
勤怠の正確な記録・分析と36協定の適正な運用を徹底し、長時間労働の兆しを早期に発見・是正する仕組みを構築しましょう。
③ 多様な働き方への対応
働き方の多様化に対応できるかどうかは、労務管理の柔軟性と制度設計力が問われる重要なポイントです。
テレワークや副業、フレックスタイムなど柔軟な働き方に対応する制度を導入する企業が増える一方で、社内ルールや実務面の整備が追いついていない例も見られます。
企業の「認めているつもり」と、労働者の「活用できていない」とのギャップが、不公平感や誤解となり、組織のストレスやトラブルにつながることもあります。
対策:
制度の内容や運用ルールを明文化し、就業規則などへの反映とあわせて、企業と労働者の双方が正しく理解できるよう、情報共有や説明の機会を設けることが大切です。
④ トラブル対応の遅れ
労働トラブルへの初動対応が遅れると、企業の信頼や組織の雰囲気に悪影響を及ぼすおそれがあります。
ハラスメントや不当解雇、労働条件への不満などは、早期対応で防げるケースは少なくありません。しかし、相談窓口が明確でなかったり、対応が曖昧だったりすると、問題の深刻化を招きやすくなります。
場合によっては、労働審判や訴訟といった法的トラブルに発展する可能性もあります。
対策:
社内相談窓口やガイドラインを整備し、労働者が安心して声を上げられる環境づくりを進めましょう。トラブルの芽を早期に察知し、防止するためには、組織内に「気づける仕組み」を整備することが必要です。
⑤ 管理体制の属人化
労務業務が特定の担当者に依存している状態は、企業にとって対応力の低下を招く要因になります。
担当者が退職や休職をした際に業務が滞ったり、業務知識や処理ノウハウが失われたりすることで、労務手続きに支障が出るケースも見られます。
特に中小企業では「詳しいのはあの人だけ」といった状態になりやすく、後任への引き継ぎがスムーズにいかないことも少なくありません。
対策:
業務マニュアルの整備や社内共有の仕組みを整え、「誰が担当しても同じ品質」での運用を目指しましょう。また、クラウド型の労務管理システムを活用することで、情報共有と業務の標準化が図れます。
労務管理|自社管理の範囲と社労士に任せた方がよい範囲

労務管理には、日常的な定型業務から法改正やトラブル対応といった専門性の高い対応まで、幅広い内容が含まれます。
すべての労務管理を社内で完結させるのは現実的ではなく、業務の性質やリスクの大きさをふまえた適切な役割分担が求められます。
企業の規模や体制に応じて、「どこまでを自社で担うか」「どこから専門家である社労士に相談するか」を見極め、体制を整えることが重要です。
自社で対応可能な業務:定型業務
以下のような手順が明確でマニュアル化しやすい業務は、社内対応も十分可能です。
- 毎月の勤怠データの入力・チェック
- 給与ソフトを使った計算と支給処理
- 福利厚生制度の社内運用(手当、社内イベントなど)
これらは業務内容が定型化されていれば、担当者が対応しやすく、業務効率化や属人化防止も図れます。特に勤怠管理や給与計算については、システムを導入することで作業の負担軽減や、ミスの防止にも役立ちます。
社労士に任せた方がよい業務:専門性が高い業務
一方、以下のように法的知識や実務経験が求められる業務は、社労士への相談・依頼が効果的です。
- 就業規則の作成・見直し
- 労使協定の締結・労働基準監督署への届出書類作成
- 解雇・ハラスメント対応に関する労務トラブルへの助言や対応
とくに、法改正に伴う規定整備や労使トラブルへの対応、労働基準監督署による調査や是正勧告への対応などには、社労士の専門知識と実務経験が大きな支えとなります。
社労士に依頼することで、法的リスクの軽減や対応の正確性向上が確保され、安心して労務体制を整備することができます。
就業規則や労使協定については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:就業規則の届出方法を解説!届出義務や必要書類もあわせて紹介)
(関連記事:労使協定とは?36協定などの種類と届出ルールを一覧表付きで徹底解説)
まとめ|労務管理は社労士との連携で安心・正確に
本記事では、労務管理の定義をはじめ、主な業務内容、人事管理・勤怠管理との違い、よくある課題、そして社労士との業務分担のポイントについて解説しました。
労務管理は、労働関係法令を遵守し、働きやすい職場環境を整えることで、企業の信頼性と安定経営を支える重要な取り組みです。
しかし、その対応範囲は広く、法改正やトラブルへの対応といった高度な専門知識が求められる場面も多く存在します。
日常的な勤怠管理や給与計算は社内で対応しつつ、制度整備やトラブル対応などの専門性の高い領域は、社労士と連携することで、労より正確かつ安心な体制を構築できます。
労務管理について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。