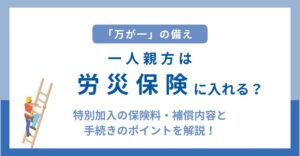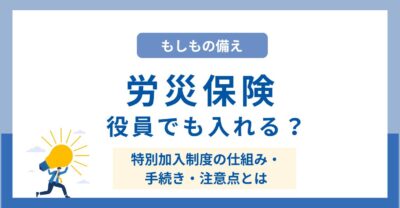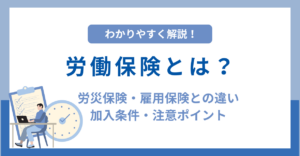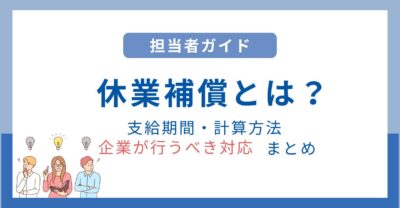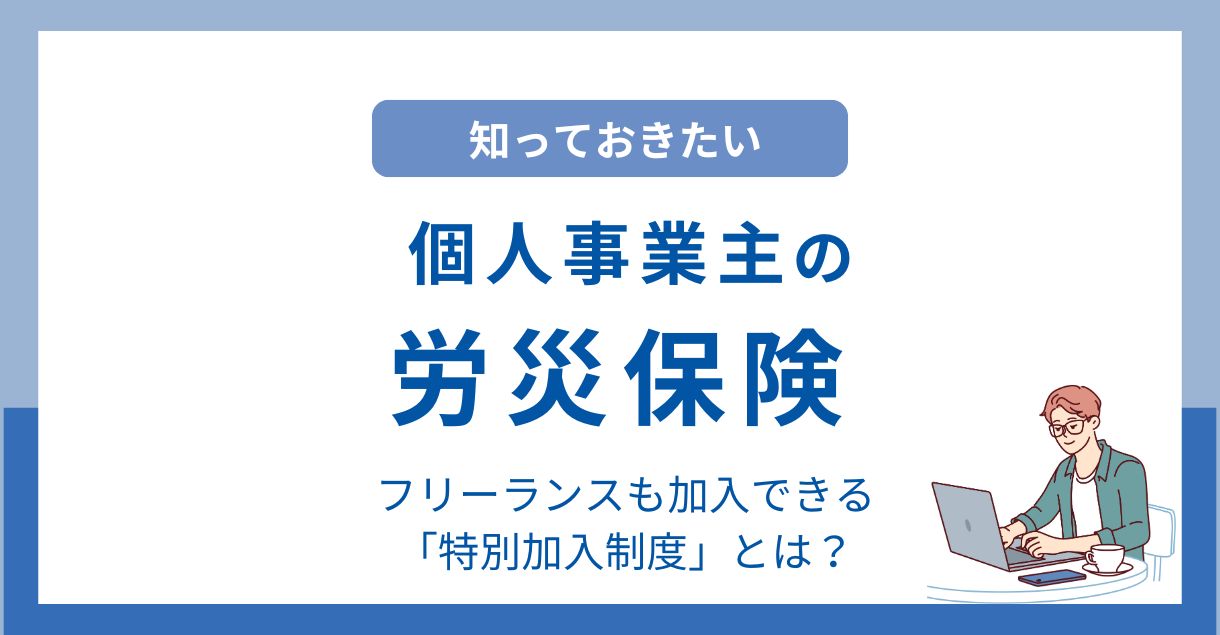
個人事業主の労災保険|フリーランスも加入できる特別加入制度をやさしく解説
個人事業主(以下、フリーランスを含む)として働くうえで、自由な働き方と同時に「万が一の備え」も欠かせません。
特に、業務中のケガや通勤中の事故といったリスクにどう備えるかは重要な課題です。
労働者が加入する労働者災害補償保険(以下、「労災保険」)は、政府管掌保険の一つで本来、事業主が保険料を全額負担し雇用されている人を対象としていますが、一定の条件を満たすことで、個人事業主(フリーランスを含む)でも加入できる「特別加入制度」があります。
この制度を知らずに個人事業主として働いていると、万が一の事故で補償を受けられず、治療費や収入減をすべて自己負担する事態にもなりかねません。
本記事では、労災保険の特別加入制度の仕組みや対象者、補償内容、保険料、手続き方法までを最新情報とともにわかりやすく解説します。
安心して仕事に取り組むために、ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
個人事業主でも労災保険に入れる!「特別加入制度」とは

労災保険の「特別加入制度」とは、国が定める事業と従業員数の基準に該当する、いわゆる中小事業主や、いわゆる一人親方等と呼ばれる企業に雇用されていない個人事業主(フリーランスを含む)、個人事業主の家族従業者、海外派遣者等の本来、労災保険に加入できない方が、労災保険に任意で加入できる仕組みです。
2024年11月1日から労災保険の特別加入制度のうち一人親方の要件が拡充され、労災保険に特別加入できる個人事業主の範囲が広がりました。
要件に該当し労災保険の特別加入を行った個人事業主であれば、委託契約に基づく業務を行う際や、業務の現場と自宅の往復中に起きたケガや病気に対して、労働災害や通勤災害として認められるようになり、労災保険の補償の対象者になりえます。
実際、厚生労働科学研究(2022年度)の調査では、フリーランスの約2割が業務中や通勤途上の災害を経験し、約6割が労災補償の支援を望んでいることが明らかになりました。こうした背景から、労災保険の特別加入制度の必要性は高まっています。
労働災害は働き方を問わず誰にでも起こり得ます。安心して事業を続けるためにも、個人事業主における労災保険への特別加入は重要な選択肢となるでしょう。
労災保険に特別加入できる個人事業主
2024年10月31日までは、一人親方やフリーランスとして働く方などのうち、特別加入ができるのは一定の事業に従事する場合に限られていました。
表1
|
特定フリーランス事業以外の特別加入の事業または作業 |
|
| 建設業の一人親方等 | 歯科技工士 |
| 個人タクシー業者 | 特定農作業従事者 |
| 個人貨物運送業者 | 介護作業従事者 |
| 漁船による自営漁業者 | 家事支援従事者 |
| 林業の一人親方等 | 芸能関係作業従事者 |
| 再生資源取扱業者 | アニメーション制作作業従事者 |
| 柔道整復師 | ITフリーランス |
| あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師 | |
など
2024年11月1日からは、それまで対象外であった事業のうち、企業またはフリーランス(以下、「企業等」といいます。)から業務委託を受けて行う事業(以下、「特定フリーランス事業」といいます。)に該当する場合も特別加入ができることとなりました。
表2
|
特定フリーランス事業 |
| 営業 |
| 講師、インストラクター |
| デザイン、コンテンツ制作 |
| 調査、研究、コンサルティング |
| 翻訳、通訳 |
| データ、文書入力 |
など
ここでは、労災保険の特別加入について、特定フリーランス事業を中心に具体的な条件や該当例を詳しく解説します。
特定フリーランス事業が労災保険の特別加入の対象となる条件とはまずは、労災保険の特別加入の対象となる場合、対象とならない場合について、見ていきましょう。
特別加入の対象となる場合
対象となる場合
※いずれも、他に特別加入可能な事業または作業(表1参照)を除きます。 |
<対象となる場合の具体例>
例えば、スポーツジムのインストラクターであるフリーランスが、企業から業務委託を受けて事業を行う場合や、同じ事業を個人から直接委託を受けて(パーソナルトレーナーなどとして)行う場合に特別加入の対象となります。

特別加入の対象とならない場合
対象とならない場合
|
<対象とならない場合の具体例>
例えば、以下のような場合、特定フリーランス事業の対象にはなりません。
- スポーツジムを経営する企業からインストラクターの業務委託は受けていないが、個人向けにインストラクター(パーソナルトレーナー)を事業として行っている場合
- 出版社から編集の業務委託を受けているが(インストラクターの業務委託は受けておらず)、個人向けにインストラクター(パーソナルトレーナー)として事業を行っている場合

個人事業主(フリーランスを含む)に労災保険が必要な理由

企業に雇用されていない個人事業主(フリーランスを含む)は、業務委託先で働いていたとしても、事故やトラブルが起きた際に企業や加入している健康保険・国民健康保険から補償を受けられるわけではありません。
そのため、自らを守る手段として労災保険の特別加入が重要です。
ここでは、個人事業主に労災保険が必要とされる代表的なケースを紹介します。
1.通勤途中の交通事故に備えるため
業務委託先へ向かう途中に交通事故に遭った場合でも、個人事業主は企業から補償を受けられません。
たとえば、常駐先へ移動中に事故で骨折し長期入院となった場合、治療費も休業中の収入も自己負担になります。
労災保険に加入していれば、治療費や収入減が一定額補償され、安心して療養に専念できます。
2.在宅勤務中の健康障害やケガに対応するため
自宅での作業でも、長時間のデスクワークによる腱鞘炎や腰痛など、健康障害のリスクがあります。
たとえば、Webデザイナーが腰痛で業務ができなくなることも考えられます。
労災保険に加入していれば、治療費の補償に加え、休業補償も受けられるため安心です。
3.業務委託先での作業中に事故が起きた場合
撮影や研修などの現場で活動するフリーランスは、突発的な事故のリスクも抱えています。
たとえば、カメラマンが転倒し骨折した場合、収入が途絶えるだけでなく治療費も大きな負担となるでしょう。
労災保険に特別加入していれば、こうした事故による経済的損失に備えられます。
●留意点
- 個人事業主(フリーランスを含む)が労災保険の特別加入をするには、特別加入団体を通じて手続きを行う必要があります。特別加入団体は厚生労働省のホームページよりご覧になれます。(労災保険への特別加入|厚生労働省)
- 都道府県労働局長の承認があった時点で、労災保険の特別加入ができることとなります。
- 労災保険の給付を受けるためには、労働基準監督署長の認定が必要になります。
個人事業主の労災保険料はいくら?計算方法と年間保険料

個人事業主(フリーランスを含む)が労災保険の特別加入を検討する際、「どれくらいの保険料がかかるのか」「経費として処理できるのか」は特に気になるポイントです。
ここでは、保険料の決まり方や、給付基礎日額の選び方、年間保険料の目安についてわかりやすく解説します。
保険料は「給付基礎日額」によって決まる
労災保険の特別加入における保険料は、「給付基礎日額」と「保険料率」に基づいて決まります。
- 給付基礎日額:労災でケガや病気をした際に支給される補償額や、支払う保険料の計算の「もと」になる金額
- 保険料率:業務の危険度に応じて業種ごとに定められている割合
加入者は希望する日額を選び、特別加入団体を通じて申請します。その後、労働局長の承認を経て正式に決定されます。
選択できる日額は3,500円~25,000円の範囲(16段階)で、自身の年収や生活状況を踏まえて設定するのが一般的です。
年間保険料の目安(営業コンサルタントとしてフリーランスで働く方の場合)
年間保険料は、「給付基礎日額×365日×保険料率」で計算されます。
保険料率は、業務の危険度に応じて厚生労働省が業種ごとに定めています(特別加入保険料率)。自身の業種に該当する保険料率は、最新の情報を確認しましょう。
例として、特別加入対象となった「特定フリーランス事業」のうち、「営業」に従事する個人事業主(例:フリーランスの経営コンサルタントなど)を想定し、2025年4月時点の保険料率3/1,000をもとに試算しています。
【給付基礎日額と年間保険料の目安】
| 給付基礎日額(円)
A |
年間保険料算定基礎額(円)
B=A×365日 |
年間保険料(円)
B×3/1000(保険料率) |
|
25,000 |
9,125,000 | 27,375 |
| 24,000 | 8,760,000 | 26,280 |
| 22,000 | 8,030,000 |
24,090 |
| 20,000 | 7,300,000 |
21,900 |
| 18,000 | 6,570,000 |
19,710 |
| 16,000 | 5,840,000 |
17,520 |
|
14,000 |
5,110,000 | 15,330 |
|
12,000 |
4,380,000 | 13,140 |
| 10,000 | 3,650,000 |
10,950 |
| 9,000 | 3,285,000 |
9,855 |
|
8,000 |
2,920,000 | 8,760 |
| 7,000 | 2,555,000 | 7,665 |
| 6,000 | 2,190,000 |
6,570 |
|
5,000 |
1,825,000 | 5,475 |
|
4,000 |
1,460,000 | 4,380 |
| 3,500 | 1,277,500 |
3,833 |
参考:フリーランス(特定受託事業に従事する方)の皆さまへ|厚生労働省
たとえば「給付基礎日額10,000円」を選んだ場合、保険料算定基礎額は3,650,000円、保険料は年額で10,950円となります。
保険料自体は全国一律ですが、加入する団体によっては、保険料とは別に入会金や年会費がかかる場合もあります。そのため、費用やサポート内容をしっかり比較して選びましょう。
その他にかかる費用
労災保険の特別加入の手続きには、保険料とは別に次のような費用がかかる場合があります。
- 入会金:1,000円〜10,000円程度
- 会費(年会議または月会費):月額500円〜3,000円程度
- 手続き事務手数料
これらの費用は加入先によって異なるため、費用面だけでなく、サポート体制や対応の丁寧さも比較し、信頼できる団体を選びましょう。
特別加入の手続き先
労災保険の特別加入の手続きは、行う事業の種類によって申し込み先が異なります。
| 事業の種類 | 手続き先 |
【特定フリーランス事業に該当する場合】※企業等から業務委託を受けるフリーランス |
特別加入団体業種により、手続き先の団体が異なります。 詳しくは厚生労働省のホームページ「労災保険への特別加入」をご参照ください。 (ページ中段「特別加入団体一覧表」) |
【特定フリーランス事業以外】※従来から特別加入対象の業種 |
業種の詳細については、「労災保険に特別加入できる個人事業主」の表1、表2をご参照ください。
ご自身がどちらに該当するか不明な場合は、特別加入団体や最寄りの労働基準監督署等に問い合わせましょう。
給付基礎日額の選び方と注意点
給付基礎日額は、補償内容と保険料の金額を左右する非常に重要な項目です。
高めに設定すれば手厚い補償を受けることができますが、当然ながら保険料の負担も増えます。
一方で、保険料を抑えるために日額を低くしすぎると、万が一のときに生活費や医療費を十分にカバーできず、経済的に困る可能性があります。
特に個人事業主(フリーランスを含む)は収入が不安定になりやすい側面があるため、「最低限必要な補償額」から逆算して給付基礎日額を設定することがポイントです。
【給付基礎日額を選ぶ際のポイント】
| 年収・生活費を基準に設定する | 月々の生活費、家賃、ローン支払いなどから必要な補償額を計算し、日額を設定しましょう。 |
| 家族構成や扶養の有無を考慮する | 扶養家族がいる場合、収入が減少しても生活を維持できるかを確認しましょう。 |
なお、給付基礎日額は年度単位でしか変更できません。事故や災害が起きたあとに変更することはできないため、加入時点で適切に設定する必要があります。
給付基礎日額の設定に不安がある場合は、労災保険に詳しい社労士に相談し、自身の働き方や家計状況に合った日額を検討することをおすすめします。
個人事業主の労災保険で補償される内容とは?給付の種類

個人事業主(フリーランスを含む)が労災保険に特別加入することで受けられる補償は、基本的に企業に雇用されている労働者と同様の内容です。
仕事中や通勤中に発生したケガや病気に対し、公的な保険制度として各種給付が支給されます。
労災保険の特別加入によって受けられる代表的な補償内容は以下の通りです。
【個人事業主の特別加入で受けられる主な補償内容(2025年4月時点)】
| 給付の種類 | 内容 | 支給条件・金額 |
| 療養(補償)等給付 | 業務中・通勤中のケガや病気に対する治療費を全額補償 | 指定医療機関での治療は自己負担なし。指定外の場合は後日支給 |
| 休業(補償)等給付 | 働けない期間中、給付基礎日額の80%を支給 | 休業4日目以降が対象(最初の3日間は待機期間) |
| 障害(補償)等給付 | 後遺障害が残った場合、障害等級に応じて一時金または年金を支給 | 一時金:第8〜14級、年金:第1〜7級 |
| 傷病(補償)等年金 | 1年6か月以上治らず、障害等級に該当する場合に支給 | 「症状が固定していない」かつ「障害等級に該当すること」が条件 |
| 遺族(補償)等給付 | 労災死亡時、遺族に一時金または年金を支給 | 年金:遺族人数で日数が異なる/一時金:最大基礎日額の1,000日分(一定条件あり) |
| 葬祭料(葬祭給付) | 葬儀費用として葬祭料を支給 | 「31万5千円+基礎日額30日分」または「基礎日額60日分」のいずれか高い方を支給 |
参考:フリーランスの皆さまも、特別加入により労災保険の補償を受けられます!|厚労省
個人事業主が労災保険に特別加入することで、業務中や通勤中に発生したケガや病気、万が一の死亡事故に対して、補償を受けられるようになります。
個人事業主が労災保険に加入するための手順と必要書類
個人事業主(フリーランスを含む)が労災保険の特別加入を希望する場合、行っている事業の種類によって手続き先が異なります。
手続きは、事業の種類ごとの「特別加入団体」へ申請を行います。
ここでは、一般的な申請の流れを紹介します。
| 手順 | 内容 |
| ①特別加入団体に相談する | 加入条件や費用を確認し、必要書類を案内してもらいましょう。 |
| ②必要書類を提出する | 加入申込書、業務委託契約書、本人確認書類などを準備して提出します。 |
| ③保険料と組合費を納付する | 給付基礎日額に応じた年間保険料、入会費・年会費を支払います。 |
| ④労働局の承認を経て加入完了 | 手続きが受理され、労働局長の承認が下りると正式に加入となります。 |
【主な提出書類】
|
加入の可否や詳細な手続きは、加入を希望する特別加入団体によって異なります。
不安がある場合やスムーズに進めたい場合は、労災保険の手続きに詳しい社労士に相談するのも有効です。
労災保険の特別加入に関するよくある質問

Q1|申請から補償までどれくらいかかりますか?
労災保険の特別加入の申請手続きは1~2週間程度、補償の対象となる(労働局長の承認が下りる)までには1〜2か月程度が目安です。
※特別加入団体の手続き状況等により前後することがあります。
Q2|保険料は経費計上できますか?
労災保険の特別加入で支払った労災保険料は、確定申告時に「社会保険料控除」として処理できます。また、特別加入団体に支払った入会金や年会費は、必要経費(諸会費)として計上可能です。
申告の際には、支払ったことがわかる領収書などを保管しておきましょう。
まとめ|個人事業主の「万が一」に備えるなら労災保険の活用を

本記事では、個人事業主(フリーランスを含む)が労災保険に特別加入できる仕組みについて、対象者、補償内容、加入手続き、保険料の目安まで、最新の制度改正を踏まえて解説しました。
労災保険の特別加入は、万が一の業務中・通勤中の事故や病気に備え、個人事業主(とくにフリーランス)が自ら公的な補償を確保するための有効な手段です。
一方で、特別加入の制度自体は知っていても、書類の準備や団体選びなど、実際に手続きを進めるには時間と手間がかかるため、後回しにしてしまうケースも少なくありません。
「労災保険への特別加入を検討しているけれど、どこから始めればいいかわからない」
「自分の仕事内容や生活状況に応じて、適切な補償額をどう設定すればよいか悩んでいる」
そのような方は、労災保険の特別加入制度に詳しい社労士に相談するのがおすすめです。
個人事業主(フリーランス)の労災保険について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。