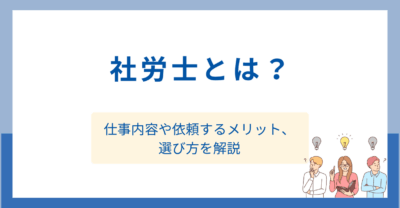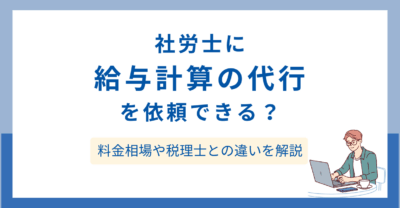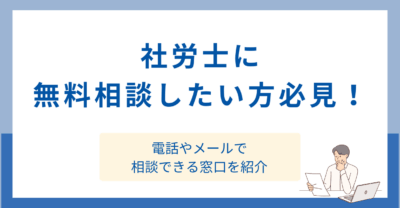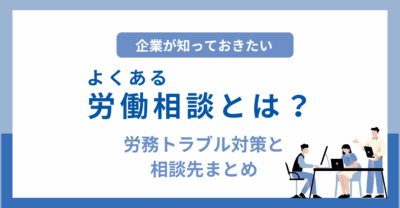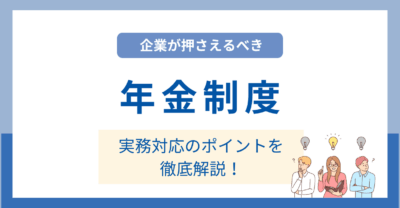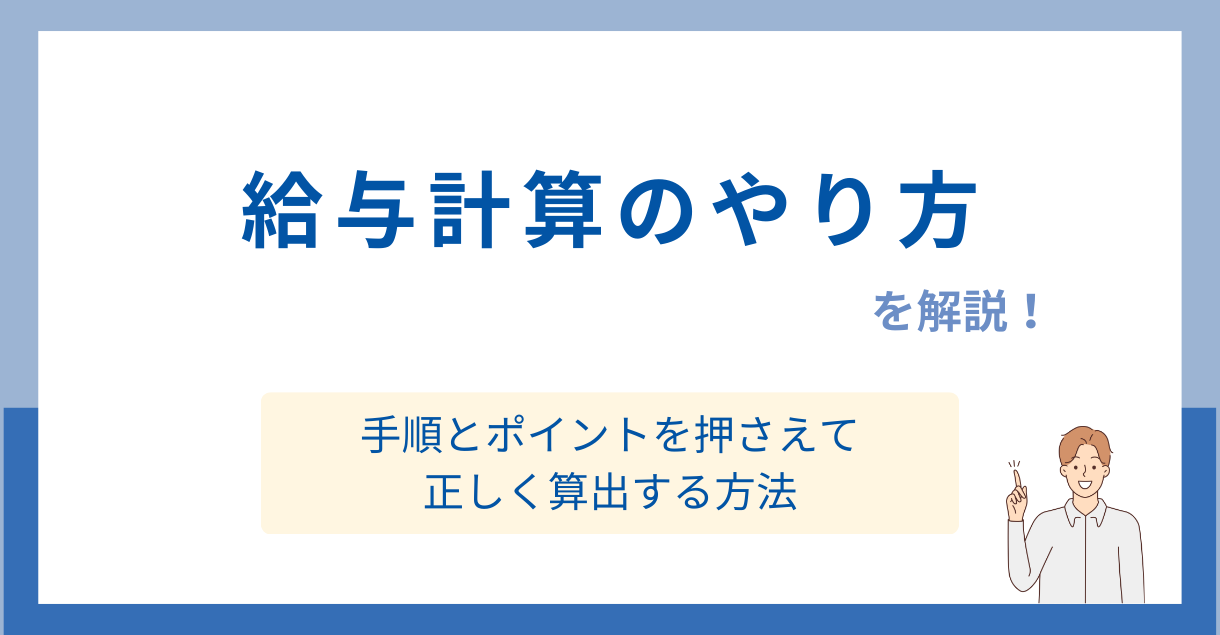
給与計算のやり方を解説!手順とポイントを押さえて正しく算出する方法
給与計算、どう進めればいいのかわからないという悩みを抱えている経営者や経理・総務・人事担当者の方も多いのではないでしょうか。誤った処理をしてしまうと、法令違反として罰則の対象になったり、従業員からの信頼を損ねたりするリスクもあります。
本記事では、給与計算の基本的な流れを段階的に整理しながら、注意すべきポイントを解説します。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
日本最大級の社労士検索サイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
給与計算のやり方・手順
給与計算は、一連の作業を段階的に行うことで正確性が保たれます。ここでは、実務の現場で必要となる基本ステップを順に整理して解説します。
- 勤怠集計
- 基本給・割増賃金を計算
- 手当を加算
- 総支給額の算出
- 社会保険料・所得税・控除項目を計算
- 差引支給額(手取り)を確定
1. 勤怠集計
最初に行うのは当月分の勤怠データを確定することです。具体的には、出勤日数、欠勤日数、残業や深夜勤務、休日出勤、有給休暇の取得状況などを締め日までにまとめ、記録ミスや打刻の誤りがないかを確認します。
この時点で、時間外労働の上限を定めた36協定の範囲内に収まっているかもチェックしておくことが重要です。上限を超過すると、行政指導(行政手続法第32条)の対象となり、是正命令に従わない場合には罰則が科されるリスクがあります。※厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
また、欠勤控除の算出方法(所定労働日数を月毎にするか年平均にするか)や、欠勤控除の対象となる手当といったルールを就業規則に明示しておくことで、後工程の混乱を防げます。
2. 基本給・割増賃金を計算
基本給を時間単価に換算し、時間外・深夜・法定休日労働の割増賃金額を求めます。
時間単価の計算
- 月給制:月給÷月の所定労働時間
- 日給制:日給÷1日の所定労働時間
- 時給制:時給をそのまま使用
割増賃金の計算
| 労働の名称 | 対象時間 | 割増率 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 時間外労働 | 1日8時間(または1週40時間) を超える分 |
+25% | 8:00~19:00(うち1時間休憩) 勤務だと残業2時間 |
| 深夜労働 | 22:00〜翌5:00の労働 | +25% | 22:00〜翌5:00の勤務など |
| 法定休日労働 | 週1日(または4週4日) の法定休日に行う労働 |
+35% | 日曜出勤8hなど |
時間外労働が月60時間を超えた部分については、2023年4月以降、企業規模を問わず割増率50%以上が義務付けられています。※厚生労働省「Ⅱ 法定割増賃金率の引上げ関係」
また、基本給の欠勤控除がある場合にはこの段階で計算してください。
こうして算出した割増賃金額とあれば欠勤控除額、次の工程で計算する各種手当を加えると総支給額になります。
3. 手当を加算
次に、手当ごとに支給対象者・支給額を計算・確認します。
給与の手当は、勤怠状況などによって変動する「変動手当」・金額が固定的な「固定手当」・通勤手当や実費精算の交通費などの「非課税手当」・大入り手当やお祝い金などの「臨時的・一時的な手当」の4つに分類できます。それぞれ、源泉所得税の課税可否や割増賃金の算定基礎額への算入、社会保険料の標準報酬に含めるかといった扱いが異なるため、各手当の設定を事前に正しく確認する必要があります。
| 分類 | 源泉所得税 | 割増賃金の算定基礎額への算入 | 社会保険料の標準報酬対象 |
|---|---|---|---|
| 変動手当(皆勤手当・インセンティブ手当など) | 課税対象 | 含める | 対象 |
| 固定手当(住宅手当・固定残業代など) | 課税対象 | 手当により異なる※1 | 対象 |
| 非課税手当(通勤手当など) | 非課税 | 含めない | 対象※2 |
| 臨時的・一時的な手当(慶弔見舞金・大入手当など) | 社会通念上相当額まで非課税※3 | 含めない | 対象外 |
※2 交通機関等を利用する人に支給する通勤手当は所得税法上、月15万円までは非課税ですが、健康保険・厚生年金の標準報酬月額には含まれます。また、業務上の出張旅費や交際費などの実費精算は標準報酬の対象外となります。
※3 国税庁「13 源泉所得税の取扱い」
詳しい手当の取扱いは、下記の公的資料で確認できます。
- 所得税に関して 国税庁「令和7年版 源泉徴収のしかたp5「給与所得の範囲」」
- 割増賃金の算定基礎額に関して 厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」
- 標準報酬の対象に関して 日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブックp3|2.用語の説明(1)報酬とは」
手当の設定を誤ると、給与の再計算が必要になるおそれがあります。就業規則で手当を明示し、毎年見直すことでミスを防ぎましょう。
4. 総支給額の算出
ここまでの各項目を合計すると、従業員に支払う「総支給額」が導き出されます。このうち、非課税手当を除いた金額が「課税支給額」となり、そこから社会保険料や所得税、住民税、控除項目を差し引いた金額が「差引支給額(手取り)」です。
総支給額を確定する前に、扶養家族の増減、住所の変更、介護保険の該当有無など、従業員の状況変化がシステムに反映されているかを必ずチェックしてください。
5. 社会保険料・所得税・控除項目を計算
総支給額が確定したら、まず社会保険料を計算します。
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料を最新の料率表金額を用いて算出しましょう。次に源泉所得税・住民税、社宅家賃や財形貯蓄など控除項目も加算し、当月の控除合計を確定させます。
6. 差引支給額(手取り)を確定
控除合計を総支給額から差し引くと手取り額が算出されます。
前月の金額と比較して明らかにおかしい点がないか、口座情報に変更がある従業員はいなかったかなどを最終確認します。
金額に大きな増減があったり社会保険料標準報酬月額の変更があったりした従業員には事前の説明や案内文を配布すると、誤解が生まれずスムーズに給与支給日を迎えられるでしょう。
正確な給与支払いのための準備とポイント
給与計算をミスなく行うには、事前の準備が大切になります。法令順守を土台に、制度の理解やデータ整備を怠らないことが、トラブルを未然に防ぐポイントを紹介します。
- 賃金支払いの5原則を厳守する
- 社会保険・雇用保険の加入要件を確認する
- 従業員データを最新状態に保つ
- 最低賃金を把握する
- 年間スケジュールを確認する
賃金支払いの5原則を厳守する
労働基準法第24条では、賃金支払いに関する「5つの原則」が明文化されています。
- 賃金は通貨で支払うこと(通貨払の原則)
- 賃金は直接労働者に支払うこと(直接払の原則)
- 賃金は全額支払うこと(全額払の原則)
- 賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこと(毎月1回以上、一定期日払の原則)
※引用元:厚生労働省兵庫労働局「賃金」
例外として、銀行振込やデジタルマネーなどを用いた支払いが可能ですが、その際には労使協定と本人の同意が必要です。給与支払いの形式を変更する際は、必ず計画を立てて手続きをしましょう。
社会保険・雇用保険の加入要件を確認する
従業員が社会保険や雇用保険に加入するかどうかは、週の所定労働時間や月の報酬額などで判断されます。
例えば、常時51人以上の事業所で、週20時間以上かつ月額報酬8万8,000円以上あり、雇用について2カ月を超える見込みがある場合は、学生を除いて、厚生年金・健康保険の適用対象となります。※厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
雇用保険は、週20時間以上の所定労働時間があり、31日以上の雇用見込みがある労働者(学生を除く)が加入対象です。2028年10月1日からは所定労働時間が20時間以上から10時間以上へと適用拡大される点も留意しておきましょう。
「資格取得届」や「喪失届」などの提出時期を入社・退職のフローに組み込んでおくことで、手続き漏れを防げます。
従業員データを最新状態に保つ
給与計算の正確性を保つには、従業員に関する情報が常に最新であることが前提です。扶養親族の変更、住所の移転、40歳から64歳まで義務付けられている介護保険料の控除など、従業員データの変更がそのまま給与計算に影響します。
とくに注意したいのが40歳の誕生日です。介護保険料の控除は誕生日の前日が属する月の分(9月11日が誕生日の場合は9月分から発生します。)から開始されるため、忘れがちなポイントです。労働者ごとの40歳の誕生日を管理し、対応漏れを防ぎましょう。
最低賃金を把握する
最低賃金は都道府県ごとに異なり、毎年10月頃に変更されます。複数の拠点がある企業では、就労実態のある地域の最低賃金を適用する必要があるため注意が必要です。
時給制の場合はもちろん、月給制でも労働時間で割った際に最低賃金を下回るのは違法です。
なお、テレワークの場合は、就業場所に関わらず、テレワークを行う労働者の属する事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。
また、特定(産業別)最低賃金が設定されている業種もあります。例えば、鉄鋼業、電子部品・デバイス製造業、自動車関連、百貨店・総合スーパーなどが該当し、地域別最低賃金より高い額が定められています。該当するかどうかは、厚生労働省「特定(産業別)最低賃金 全国一覧」で確認してください。
年間スケジュールを確認する
給与計算では「いつ・何を準備するか」をカレンダーで押さえておくと、担当者が替わっても手続き漏れが起きません。以下は多くの企業で発生する主なタスク例です。
| 時期 | 主な準備内容 |
|---|---|
| 新入社員 入社時 |
雇用契約書で賃金・手当を確認 扶養控除申告書・通勤経路届を回収 社会保険・雇用保険の資格取得届提出 |
| 毎月 | 源泉所得税の納付 社会保険料の納付 |
| 3月 | 健康保険・介護保険料率改定を設定 |
| 4月 | 昇給・人事異動の反映 雇用保険料率を更新 |
| 6月 | 住民税特別徴収額を新年度分へ切替え |
| 7月 | 労働保険料の年度更新・算定基礎届を提出 |
| 9月 | 新しい標準報酬月額を適用 |
| 11月 | 年末調整の書類の案内・配布・回収 |
この一覧を年間カレンダーやタスク管理ツールに落とし込み、担当者と期日を明確にしておくことが、計算ミス防止の近道です。
給与計算を行う際の注意点
給与計算には多くの要素が絡むため、細かなミスが思わぬトラブルを招くこともあります。以下のポイントを意識しておくことで、ミスや法令違反を未然に防げます。
- 賃金台帳の備付けと給与明細の交付義務を守る
- 個人情報流出リスクを防ぐ
- 転記・計算ミスを防ぐ
- 月額変更届の提出漏れに注意
賃金台帳の備付けと給与明細の交付義務を守る
労働基準法第109条により、事業者には賃金台帳の作成・保存が義務付けられており、その保存期間は原則5年間です(当分の間は3年とされています)。※e-Gov法令検索「労働基準法第109条」電子保存も可能ですが、その場合は改ざん防止や検索性の確保が求められます。
給与明細は紙での交付だけでなく、従業員が同意すれば電子明細でも問題ありません。賃金台帳を備え付けなかった場合は労働基準法120条により30万円以下の罰金、給与支払明細書を交付しなかった場合は所得税法242条7号により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。
個人情報流出リスクを防ぐ
マイナンバーや銀行口座など機微情報を扱うため、個人情報流出への対策は欠かせません。
アクセス権を部署単位で制限し、暗号化ストレージを用いて保管するなど、セキュリティ対策をすることでリスクを防ぎます。
転記・計算ミスを防ぐ
担当者が総支給額・控除合計・差引支給額を算出した後、別の担当者がそれぞれの金額を二段階で確認するダブルチェックを行いましょう。
毎月、前年同月と前月の支給額を確認し、金額の急増減がないかチェックすると、設定漏れや入力ミスを早期に発見できます。
(例:2025年6月給与を計算する場合は、2024年6月・2025年5月の給与と照合して差異を確認)
給与支給後に誤りが判明したときは、正しい金額を再計算し、速やかに対象の従業員へ経緯と対応を説明しましょう。対応としては、社会保険料は翌月の給与で差額を調整し、源泉所得税は年末調整で調整されることが多いです。
月額変更届の提出漏れに注意
基本給や通勤手当などの固定的賃金が変動した場合には「月額変更届」の提出が必要な場合があります。提出漏れが発生すると、社会保険料や所得税額にずれが生じ、訂正届提出のほか、これらの保険料や所得税額を後から徴収しなければならない場合もあります。昇給や従業員の引越により通勤手当に変更があった場合などには月額変更の対象かどうかを必ず確認しましょう。
給与計算は社労士への依頼がおすすめ
給与計算は毎月繰り返される業務ですが、その中には最新の法律や制度への対応、従業員ごとの個別対応など、高度な知識と注意力が求められます。
一度やり方を覚えたとしても、制度の改正や保険料率・税率の変更は毎年のように発生します。また、従業員の扶養変更、介護保険加入、住民税の反映など、情報更新の必要性も絶えず続きます。これらをすべて自社内で対応するには、相応の時間と体制が必要です。
こうした背景から、給与計算を社労士にアウトソーシングする企業が増えています。社労士であれば、毎月の計算はもちろん、社会保険・労働保険の手続きや法改正への対応までワンストップで任せることが可能です。結果として、経営者や管理部門は本業に集中できるようになり、コンプライアンスと人件費管理を両立できます。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。