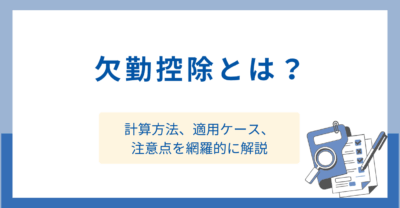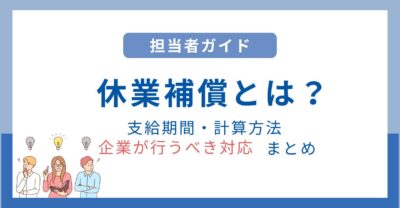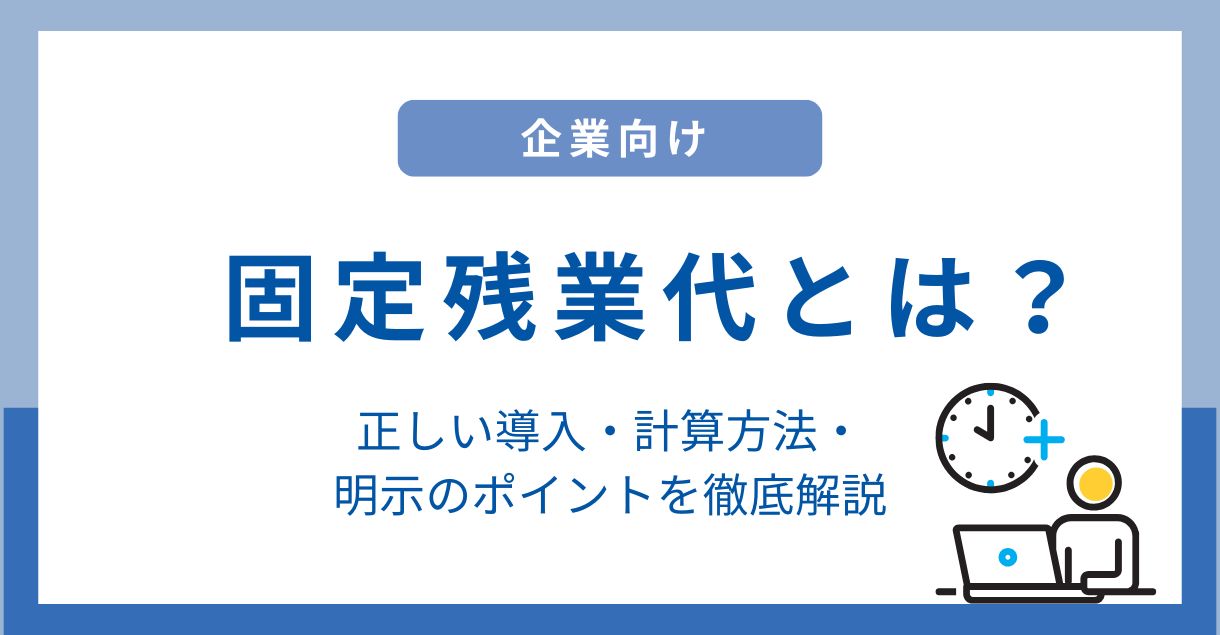
【企業向け】固定残業代とは?正しい導入・計算方法・明示のポイントを徹底解説
固定残業代制は、労働者の一定時間分の時間外労働に対する割増賃金をあらかじめ一定額として支給する制度です。固定残業代制の導入により、計算業務の効率化や人件費の平準化といったメリットがあります。しかし一方で、制度設計や運用を誤ると「違法な未払い残業代」として指摘されるリスクもあります。
本記事では、固定残業代制の概要から、メリット・デメリット、適法な記載例、計算方法、制度導入時の注意点までをわかりやすく解説します。
特に、「すでに制度を導入しているが、このままで問題ないか不安」という企業担当者にとっても、自社制度を見直す視点が得られる内容です。
ぜひ最後までご覧いただき、安心して運用できる固定残業代制の理解と整備にお役立てください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
日本最大級の社労士検索サイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
固定残業代とは?

固定残業代制とは、あらかじめ定めた一定時間分の時間外労働・休日労働・深夜労働に対して、定額で割増賃金を支給する制度です。
これは、実際の残業に対して支払う割増賃金を前もって定額の手当や基本給の一部として支給する仕組みであり、「みなし残業制」、「定額残業制」などと呼ばれることもあります。 固定残業代制は、割増賃金が発生する労働時間の手当ごとに個別に導入するのが一般的です。後述するように、固定残業代制はいくつかの要件を満たす必要があるため、時間外手当・休日手当・深夜手当をそれぞれの内訳も示さずに一括でまとめて固定残業代とすることはできません。
※固定残業代制が無効となる可能性がある場合の例。
- 月給30万円(固定残業代含む)
- 営業手当8万円(固定残業代含む)
いずれも、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分(固定残業代)とを判別していないため無効となる可能性があります。
【割増賃金が発生する手当の種類】
| 種類(手当) | 支払う条件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 時間外 (時間外手当、残業代など) |
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 25%以上 |
| 時間外労働が限度時間(1か月45時間、1年360時間など)を超えたとき | 25%以上 (※1) |
|
| 時間外労働が1か月60時間を超えたとき | 50%以上 (※2) |
|
| 休日(休日手当) | 法定休日(週1日)に勤務させたとき | 35%以上 |
| 深夜(深夜手当) | 午後10時から午前5時までの間に勤務させたとき | 25%以上 |
※1:限度時間超えについては、労使協定により25%を超える割増率とする努力義務があります。
※2:中小企業にも2023年4月から適用されています。
出典:東京労働局「しっかりマスター労働基準法「割増賃金編」」
たとえば、固定残業代を「時間外手当」にだけ導入している場合は、固定残業時間として支払われるのは時間外労働(残業)だけです。
一方、労働者が休日や深夜の時間帯に働いた場合には、その分は固定残業代の対象外となり、別途、休日手当や深夜手当を追加で支払う必要があります。
具体的な固定残業代の金額計算については、「固定残業代の計算方法と計算例」の章でわかりやすいモデルケースを交えてご紹介します。
なお、本記事では、「時間外手当に対して固定残業代を支払う場合」を前提に解説します。
企業が固定残業代制を導入するメリット

固定残業代制度は、単なる給与体系の一種ではなく、企業の業務効率やコスト管理にも関わる重要な仕組みです。
以下、企業が固定残業代制度を導入する2つのメリットをご紹介します。
残業代の計算を簡素化できる
固定残業代制度を導入することで、毎月の残業時間に応じて都度計算する必要がなくなり、残業代の算出作業が大幅に効率化されます。
給与計算においても、定額処理が可能になるため、月々の処理が標準化され、経理や人事部門の負担を軽減できるのが大きな利点です。
特に、従業員数が限られており、業務効率が重要となる中小企業では、固定残業代制度の導入によって月次の給与処理業務の精度とスピードが向上するという効果が期待できます。
労働者の時間意識や業務効率が向上する
固定残業代制度では、あらかじめ「月〇時間分の残業代を含めて支給する」と明示されているため、労働者はその時間内で業務を終える意識を持ちやすくなります。
このような時間意識の変化に伴い、非効率な働き方や“なんとなくの残業”を抑制する効果があります。結果として、企業全体の業務効率や生産性にも良い影響を与えるでしょう。
制度を適切に設計・運用すれば、企業にとってはコスト管理や業務改善の手段となり、労働者にとっても無理のない働き方の促進となるため、双方にとって有益な制度といえるでしょう。
企業が固定残業代制を導入するデメリット

固定残業代制は便利な一方で、運用を誤ると法令違反やトラブルの原因になることもあります。
ここでは、企業が押さえておくべき固定残業代制度の主なデメリットを3つ解説します。
残業時間に満たなくても支給義務がある
固定残業代制は、設定した時間分に達しなかった場合でも全額を支給しなければならない制度です。たとえば、「月30時間分の固定残業代」を設定していて、実際の残業が10時間だったとしても、30時間分すべての支払い義務が発生します。
そのため、「実際に働いた分だけ支払う」という仕組みと比べると、人件費が高くなる可能性があることに注意が必要です。
制度を導入する際は、過去の残業実績をもとに固定残業時間を設定することや、事前にシミュレーションを行うことが重要です。
勤怠管理の実態把握が不可欠
「固定で払っているから記録は不要」という誤解が多いですが、実際の残業時間は適切に記録しなければなりません。
「使用者は、労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。」
引用:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドライン」
労働基準監督署の調査が入った場合、企業には客観的な勤怠記録の提示が求められます。実態と記録に乖離がある場合は、是正勧告や未払い賃金の支払い指導を受ける可能性があるため注意が必要です。
関連記事:【実務に役立つ】勤怠管理とは?仕事内容から対象・管理方法まで徹底解説!
超過分の残業代支給漏れリスクがある
固定残業時間を超えて労働が発生した場合、超過分に対しては別途残業代の支払いが必要です。
たとえば、月30時間分の固定残業代を支給していて、実際の残業が40時間だった場合、超過10時間分は追加支払いの対象です。
この超過分に対して未払いが発生すると、違法状態となり、未払い残業代の請求や法的トラブルに発展するリスクがあります。未払い賃金があった場合、労働者は支払い日から5年間(本記事の執筆時点では経過措置の期間中で、当分の間は「支払日から3年間」です)までさかのぼって請求できることが労働基準法で定められています。
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあっ た時から五年以内にしなければならない。
引用:e-Gov「労働基準法第114条」
したがって、固定残業代制度を導入していても、実際の労働時間はしっかり集計・確認することが欠かせません。
固定残業時間を超えて働いた場合には、その超過分の残業代も忘れずに支給するようにしましょう。
固定残業時間の上限

固定残業代制は、法律に明文規定はありません。そのため、固定残業時間の上限も明確なものはありませんが、「月45時間」を基準に設定されることが多いです。この「月45時間」は、36(サブロク)協定による時間外労働時間の原則的な上限時間に基づいています。
36協定とは、労働基準法第36条に基づき、企業が労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合に必要となる労使間の協定です。
企業と労働者の代表が協議のうえで協定を結び、所轄の労働基準監督署へ届け出ることで、はじめて時間外労働が可能になります。
この36協定では、原則として「1か月45時間・1年360時間」の上限が定められているため、固定残業時間も36協定の上限時間をふまえて、月45時間以下で設定するのが一般的です。
関連記事:企業が知るべき「36協定」とは?特別条項・届出方法・違反リスクまで徹底解説
固定残業代の2種類|「組込型」と「手当型」

固定残業代制の計算方法には2種類あります。
- 組込型
- 手当型
以下、それぞれ解説します。
組込型の固定残業代
組込型の固定残業代とは、基本給の中に固定残業代を含める方式です。
一見すると基本給が高く見えるため、求職者にとって魅力的に映る場合もありますが、実際には賃金の内訳が不明確になりやすいという課題があります。
そのため、組込型の固定残業代を採用する場合は、賃金構成が誤解されないように明確に記載する必要があります。
記載例:
基本給:300,000円(うち時間外労働の有無にかかわらず、月40時間分の固定残業代 92,000円を含む)
※40時間を超える時間外労働分については、別途割増賃金にて支給します。
このように、通常の基本給と時間外労働に対する割増賃金をはっきりと区別して記載することで、労使間の認識のズレを防ぎ、法的にも適切な形で制度を運用できます。
手当型の固定残業代
手当型の固定残業代は、基本給とは別に「固定残業手当」として明示して支給する方式です。
記載例:
月給:300,000円
・基本給:208,000円
・固定残業手当:92,000円(時間外労働の有無にかかわらず、月40時間分の時間外労働に対する手当として支給)※40時間を超える時間外労働分については、別途割増賃金にて支給します。
給与明細や契約書上で「固定残業手当 〇〇円(〇時間分)」と項目を分けて記載するため、賃金構成が明確になりやすいのが特徴です。
固定残業代の計算方法と計算例

ここからは、企業担当者向けに、固定残業代の計算方法と計算例を解説します。これから固定残業代制を導入したいとお考えの方や、自社の固定残業代制を見直したい方は、ぜひ参考にしてください。
固定残業代の計算式
固定残業代を設定する際には、時間外労働に対する割増賃金(時間外労働は1.25倍以上)を含めて支給する必要があります。そのため、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働に対しては、以下の計算式を用いて金額を算出します。
【計算方法】
固定残業代=1時間あたりの賃金 × 固定残業時間 × 1.25
1時間あたりの賃金は以下の式で求められます。なお、1時間当たりの賃金を計算するときは、原則として諸手当も含めて計算しなければなりませんが、家族手当や住宅手当、通勤手当、残業代など法令で定められた一定のものは、計算から除外することができます。
参照:東京労働局「しっかりマスター労働基準法「割増賃金編」」
1時間あたりの賃金=(基本給 +諸手当)/ 月平均所定労働時間
月平均所定労働時間の計算式は以下のとおりです。
月平均所定労働時間=
(365日-年間休日日数)/ 12か月×1日の所定労働時間数
固定残業代の計算例
たとえば、以下の条件で固定残業代を算出するケースを見てみましょう。
- 基本給:320,000円
- 年間休日日数125日
- 固定残業時間:40時間(時間外労働)
- 1日の所定労働時間:8時間
この条件をもとにした固定残業代の計算方法は、以下のとおりです。
【固定残業代の計算例】
- 月平均所定労働時間=(365-125)/ 12か月×8時間=160時間
- 1時間あたりの賃金=320,000円 / 160時間=2,000円
- 固定残業代=2,000円×1.25×40時間=100,000円
したがって、40時間分の固定残業代は100,000円となります。
なお、実際の残業時間が40時間に満たない場合でも、固定残業代は満額支給しなければなりません。
たとえば、実際の残業が10時間だった場合でも、40時間分(この例では100,000円)を支払う必要があります。固定残業代の一部を減額することはできないため、運用時には注意が必要です。
また、固定残業時間を超えて労働が発生した場合には、その超過分に対して別途残業代を追加で支給する必要があります。
制度の正しい理解と運用により、労使双方が納得できる給与体系を実現しましょう。
固定残業代制の明示義務と無効リスク

固定残業代制を採用する場合は、労働者に支払う給与のうち、通常の労働に対する「基本給」と割増賃金に対する「固定残業代」が明確に区別できるよう、明示しなければなりません。
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
引用:e-Gov「労働基準法第15条」
したがって、「基本給」と「固定残業代」が、書面上で明示されていない場合は、固定残業代が「無効」と判断され、過去5年(当面の間は3年)まで遡って未払い残業代を請求される可能性もあります。
以下の書面では、必ず「基本給」と「固定残業代」をそれぞれ明示しましょう。
■固定残業代の明示が必要な書面
- 募集要項
- 雇用契約書(労働条件通知書)
- 就業規則
固定残業代制を採用する場合は、以下の3点を書面に必ず明記することが求められます。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 固定残業時間数・金額・計算方法
- 固定残業時間を超える労働については、別途割増賃金を支給する旨
【記載例】時間外労働について固定残業代制を採用する場合
- 基本給:320,000円 (以下の手当を除く金額)
- 固定残業手当:100,000円(時間外労働の有無にかかわらず、月40時間分の時間外手当として支給)
- 40時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
このように、制度の適正運用と労使間のトラブル防止のためには、「誰が見てもわかる形での明示」が不可欠です。
導入前・導入後を問わず、記載内容のチェックと見直しを定期的に行うことをおすすめします。
固定残業代制の導入に必要な3つのステップ

固定残業代制を適切に導入・運用するには、事前の準備と明確な手続きが欠かせません。ここでは、固定残業制導入に必要なステップを3つに分けて解説します。
1.残業時間の把握と妥当性の検討
まずは、実際の労働者の残業時間を把握することが重要です。
もし、設定した固定残業時間が実態とかけ離れていると、「過少支給」によるトラブルや、「人件費の無駄な増加」といった問題が生じる可能性があります。特に、「固定残業代を導入しているから大丈夫」として実際の労働時間の集計や確認を行っていないと、多額の未払い残業代が発生するおそれもあります。
制度を適正に運用し、トラブルを防ぐためにも、実態に即した妥当な固定残業時間の設定が必要です。
2.契約書・就業規則への明記と労使合意
前述のとおり、固定残業代制を導入する際には、以下の項目を契約書や就業規則などに明確に記載することが必須です。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 固定残業時間数・金額・計算方法
- 固定残業時間を超える残業については、別途割増賃金を支給する旨
これらの項目は、労働者が固定残業制の内容を正しく理解するためにも、文書で具体的かつ明示的に記載することが求められます。
また、単に書面に記載するだけでなく、労使間で合意して初めて固定残業代が有効になります。特に、基本給を減額して固定残業代制を導入するなど労働者に不利益が伴う場合は、書面で合意を得ても無効となるリスクがありますので、十分な説明を行うなど労働者の納得を得ることが大切です。
3.労働者への説明・同意取得
新たに固定残業代制を導入する場合や、既存制度の内容を変更する場合には、労働者に対して制度の内容を丁寧に説明し、書面で同意を取得することが必要です。(労働契約法8条)
企業が一方的に制度を導入・変更した場合、それが無効と判断されるリスクもあるため、十分な合意形成が不可欠です。
説明の際には、固定残業時間・支給金額・超過分の取り扱いなど、誤解が生じやすいポイントを中心に、わかりやすく説明することが求められます。
制度を導入した後は、契約書や就業規則への明示とあわせて、労働者に制度内容をしっかり周知し、法令に基づく手続きを確実に進めましょう。
まとめ|固定残業代は明示・管理が重要です。制度設計は専門家と連携を
本記事では、固定残業代制の仕組みから導入時のメリットやデメリット、計算方法や適切な記載例、導入時に必要な3つのステップまでを詳しく解説しました。
固定残業代の導入は、業務効率の向上や、労働者の給与額の安定化に役立ちます。その一方で、制度の設計や運用に不備があると、「無効」と判断され未払い残業代の請求やトラブルに発展するリスクがあります。
とくに、明示義務・勤怠管理・超過分の支払いなどの実務面は、法令との整合性が求められるため、固定残業代制の設計および運用には、社労士などの専門家によるアドバイスやチェックが欠かせません。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。