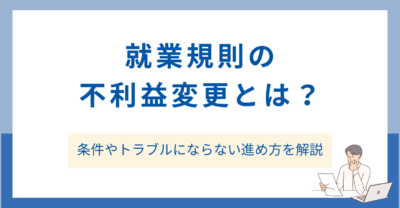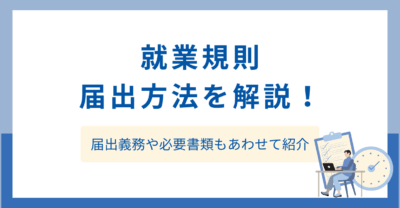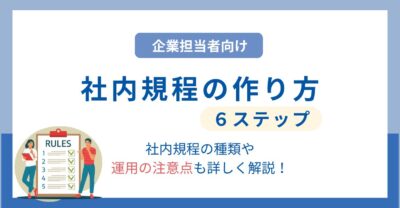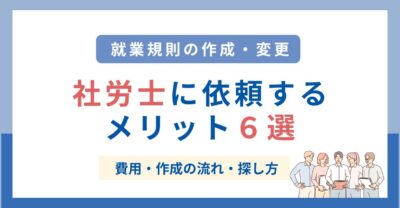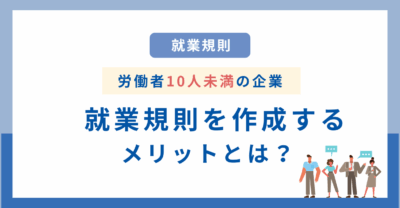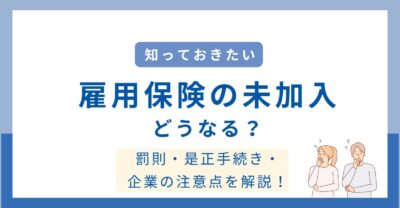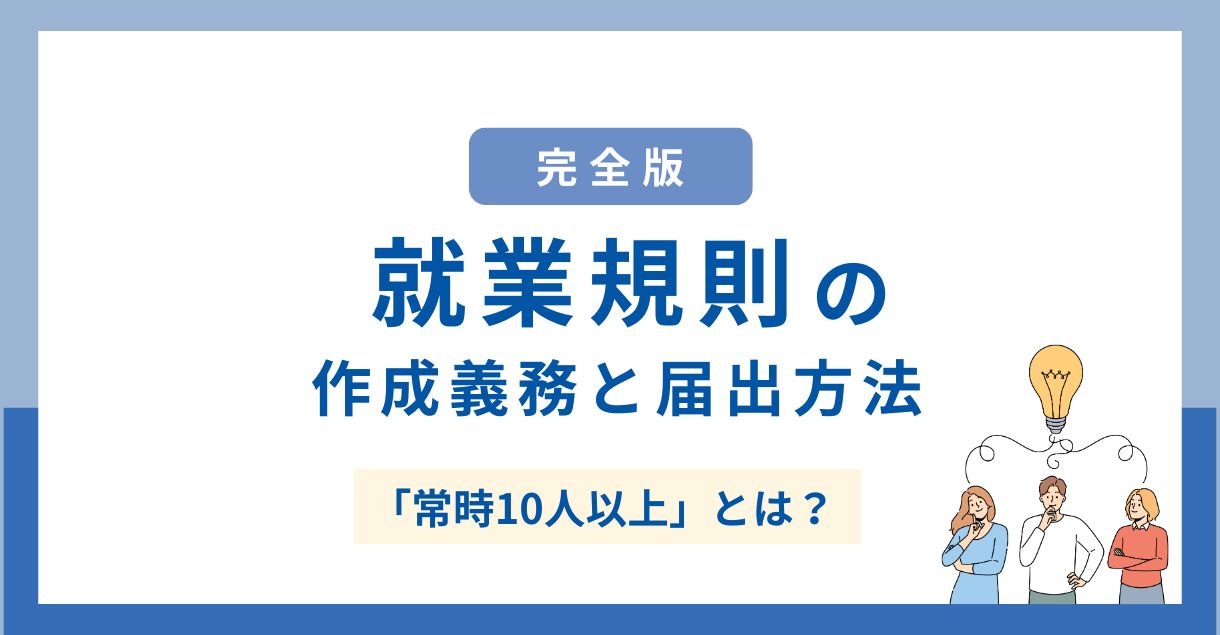
【完全版】就業規則の作成義務と届出方法|「常時10人以上」とは?
「常時10人以上の労働者」を雇用する事業場では、労働基準法第89条により就業規則の作成と所轄の労働基準監督署長への届出が義務付けられています。
しかし、実務では「常時10人以上」にパートタイム労働者などの非正規労働者を含めるのか、一部変更時の届出には何が必要なのかなど、疑問や不安を抱く企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、就業規則の作成義務のポイント、「常時10人以上」の数え方、届出と変更の手続き方法や周知方法まで、実務で押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。
本記事を読めば、企業担当者として、就業規則の作成から管理方法を具体的に理解できるようになります。
ぜひ最後までご覧いただき、自社の労務管理にお役立てください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
企業における就業規則の作成と届出の義務とは

就業規則とは、労働基準法第89条に基づき、労働時間、休憩、休日、賃金、退職、服務規律など、労働者の労働条件や職場の規律に関する事項を定めた規則です。
就業規則を作成し、労使双方がこれを遵守することで、労働者は安心して働くことができ、職場内の労使トラブルの未然防止にもつながります。
そのため、企業において就業規則は非常に重要です。
ここでは、どのような企業が就業規則の作成と届出の義務があるのか、その対象と労働者のカウント方法について解説します。
就業規則の作成義務とは
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成と所轄の労働基準監督署長への届出が義務付けられています。
なお、就業規則を変更する際にも、同様に届出が必要です。
就業規則の作成と届出の義務を怠った場合は、労働基準法120条により、罰則として30万円以下の罰金を科せられることがあります。
また、就業規則の内容は、法令や労働協約に反してはならないとされています(労働基準法第92条)。
事業場単位で作成する義務
就業規則の作成と届出は、「企業単位」ではなく「事業場単位」で作成し、届け出なければならないという点に注意が必要です。
例えば、1つの企業が複数の営業所や店舗を運営している場合、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則の作成義務が発生します。
事業場の規模別でみる就業規則の作成義務(例)
| 事業場の規模 | 就業規則の作成義務 |
| 本社80名 | 義務あり |
| 支店20名 | 義務あり |
| 営業所8名 | 義務なし |
このように、企業全体の労働者数を合計するのではなく、各営業所や店舗等をそれぞれ1つの事業場として就業規則を作成する義務があります。
ただし、複数の営業所・店舗の就業規則が本社のものと同一の内容である場合に限り、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して一括して届出を行うことも可能です。
この場合は、一括届出で手続きを簡略化できますが、変更前の就業規則の内容も同一であることが条件となります。
「常時10人以上の労働者」の範囲
「常時10人以上の労働者を使用する使用者」とは、雇用形態や勤務形態を問わず、雇用(所属)している労働者が常態として10人以上いることを指します。
この「常時10人以上の労働者」には、正社員だけでなく、パートタイム労働者やアルバイト等、自社と雇用契約のあるすべての労働者が含まれます。
「常時10人以上の労働者」の範囲について、以下のポイントを押さえておきましょう。
|
常時10人未満の労働者を使用している場合は、法令上の就業規則の作成義務はありませんが、実際には10人未満でも就業規則をつくることは少なくありません。
その目的は、労務のトラブル防止のほか助成金申請のため、などがあります。
法令上の就業規則の作成義務の有無にかかわらず、企業には、労働者の労働条件や職場のルールを定めた就業規則を作成することが望まれます。
就業規則に記載義務のある内容

就業規則に記載しなければならない事項は、労働基準法第89条に基づき、大きく次の2種類に分けられます。
| ・すべての事業場で必ず定めなければならない事項(以下「絶対的必要記載事項」といいます。)
・事業場でルールを設ける場合に記載が求められる事項(以下「相対的必要記載事項」といいます。) |
以下、それぞれ解説します。
絶対的必要記載事項
絶対的必要事項は、次のとおりです。
1.労働時間関係始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 2.賃金関係賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期並びに昇給に関する事項 3. 退職関係退職に関する事項(解雇の事由を含みます。) |
これらは労働条件の基本であり、労働者の権利保護の観点からも必須の項目です。
相対的必要記載事項
各事業場内でルールを定める際に記載が必要な事項として、以下のものがあります。
1.退職手当関係適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 2.臨時の賃金・最低賃金額関係臨時の賃金等(退職手当を除きます。)および最低賃金額に関する事項 3.費用負担関係労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項 4.安全衛生関係安全および衛生に関する事項 5.職業訓練関係職業訓練に関する事項 6.災害補償・業務外の傷病扶助関係災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項 7.表彰・制裁関係表彰および制裁の種類および程度に関する事項 8.その他事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項 |
なお、これら以外の事項についても、内容が法令や労働協約に反しないものであれば、就業規則に任意で記載できます(任意記載事項)。
また、育児・介護休業法など労働基準法以外の法令で導入が義務付けられている制度については、就業規則に規定する必要があります。
育児・介護休業法の詳しい内容については、以下をご覧ください。
(関連記事:【一覧表つき】育児・介護休業法の2025年改正内容と企業対応ポイントまとめ)
就業規則の作成の変更と届出の流れ

ここでは、就業規則の作成から届出、周知までの流れを、担当者が取り組みやすいようにステップごとに解説します。
1. 就業規則(案)の作成
まずは、現在の職場の労働条件や職場規律などを整理し、就業規則(案)の作成に取りかかります。
| (1)現在の職場の労働条件や職場規律を箇条書きで整理する (2) 整理した内容の中から、労働基準法第89条に基づく「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」に該当するものを選定する (3)労働条件や職場規律の具体的な内容を十分に検討し、必要に応じて専門家(社労士等)に相談する (4) 章別に分類し、条文化して体系的にまとめる (5)条文ごとの見出しを設定し、整理する |
就業規則の各条文についての解説や就業規則の例は、厚生労働省の「モデル就業規則」から閲覧・ダウンロードできます。
2. 労働者代表からの意見聴取
就業規則(案)ができたら、労働基準法第90条に基づいて労働者の代表の意見を聴き、意見書を作成しなければいけません。
労働者の代表とは、以下の2つのどちらかに当てはまります。
| (1)労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
(2)労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が労働者の過半数を占めていない場合には、労働者の過半数を代表する者 |
労働者の過半数を代表する者とは、労働基準法施行規則第6条の2により、次のいずれにも該当する必要があります。
| (1)管理監督者でないこと (2)使用者が選出手続を明示したうえで投票や挙手などの方法で選出された者であること |
例えば、投票を行い、過半数の労働者の支持を得た者を「過半数を代表する者」として選出する方法などがあります。使用者が一方的に指名する選出方法は認められないため、注意が必要です。
就業規則の意見書※に労働者代表の意見を記載し、労働者代表の記名または署名をしてもらいます。
※就業規則(変更)届と意見書の様式は、厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーからダウンロードできます。
3. 意見を踏まえた内容の検討
労働者代表からの意見を参考に、必要に応じて内容の修正・補足を行います。
4. 労働基準監督署長へ届出
完成した就業規則は、所轄の労働基準監督署長へ届出を行います(労基法第89条、90条)。
届出の提出書類は以下のとおりです。
| ■就業規則の作成・変更の届出に必要な書類 ・就業規則(変更)届 ・意見書 ・該当する就業規則(別規程として作成したものも含む) ※変更の場合は、新旧対照表による届でも可能です。詳しくは次の「就業規則の変更時の届出方法」の章で解説しています。■提出先 所轄の労働基準監督署 |
届出は、電子申請(e-Gov電子申請)でも対応可能ですので、企業の状況に応じて活用しましょう。
5. 労働者への周知
作成または変更した就業規則は、労働者に周知することが義務付けられています(労働基準法第106条)。
具体的な周知方法は、以下が挙げられます。
| (1)常時事業場内の見やすい場所に掲示する (2)書面で労働者に配布する (3)電子メールでの配信や電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにする |
このように、労働者がいつでも確認できる方法で周知を行いましょう。
特に、新たに就業規則を作成したり、その内容を変更したりした場合には、すべての労働者に対してその内容が確実かつ迅速に周知されるようにしなければなりません。
就業規則の変更時の届出方法

就業規則は、一度作成すれば終わりではなく、法改正や職場環境の変化などに応じて変更や届出が必要となります。
ここでは、特に「一部変更の場合」と「別冊・分冊規程の取り扱い」について、実務で役立つポイントを解説します。
一部変更の場合の届出書類の作成方法
就業規則の一部を変更した場合でも、労働基準監督署への届出は必要です。
この際、就業規則全体を届け出る必要はありませんが、変更箇所や変更内容がわかる書類を必ず添付しましょう。
具体的には、以下のような資料が推奨されます。
| ■就業規則の一部変更の際に必要な届出書類
・意見書 ・新旧条文対照表(変更前と変更後を並べて比較した表) ・該当ページの新旧の写し(変更したページのみ) |
このように変更点を明確にすることで、届出手続きがスムーズに進みます。
別冊・分冊での規程の取り扱い
賃金規程や育児介護休業規程などのように就業規則の一部として、別冊・分冊で就業規則を作成している場合も、本体の就業規則と一体のものとして扱われます。
そのため、これらの別冊・分冊規程を変更した場合も、就業規則の一部変更として必ず届出が必要です。
届出を見落としてしまうと、未届扱いとなり、就業規則の届出義務違反とみなされる可能性がありますので注意しましょう。
就業規則の法的効力と注意点

就業規則は、企業にとって労働条件や職場のルールを明文化した大切な規則であり、法的効力を持ちます。
ただし、その内容が法令や労働協約に反している場合は、その部分が無効となるため注意が必要です(労働基準法第92条)。
ここでは、「いつから就業規則の効力が発生するのか」「どのような場合に就業規則が無効となるのか」など、企業担当者が押さえておきたいポイントを解説します。
就業規則の効力が発生する時期
就業規則は、単に作成し、労働者代表の意見を聴取しただけでは効力は発生しません。労働者に周知しなければ効力は発生しないとされています。
そのため、就業規則の効力が実際に発生する時期は、次のとおりです。
|
適切なタイミングで労働者に周知しなければ、就業規則が法的効力を持たない可能性があります。
運用にあたっては、周知のタイミングにも十分注意を払いましょう。
就業規則が法的効力をもたないケース
以下の場合、就業規則の全部または一部が法的効力を持たないので注意が必要です。
|
これらの場合には、就業規則が本来の役割を果たさず、労使トラブルや法的リスクが生じる恐れがあります。
適切に就業規則を整備し、法令や協約を遵守しながら労働者に周知することが大切です。
就業規則の義務についてよくある質問

就業規則に関するよくある質問をまとめました。疑問点をクリアにし、安心して運用できるようにしましょう。
Q1|「常時10人以上」の判断基準は?
「常時10人以上」とは、正社員だけでなくパートタイム労働者、アルバイト、契約社員など、雇用形態を問わず、事業場に常態として雇用(所属)している労働者の数で判断します。
一時的に出勤している人数ではなく、実際に雇用契約を結んでいるかどうかがポイントです。
例えば、期間の定めのある労働者を一時的に雇って10人を超えても、その契約が終了すれば人数が減るため、その場合は常態としての人数には含まれないこともあります。
「常時10人以上」に該当するかどうかの判断に迷う場合は、社労士などの専門家に相談することをおすすめします。
Q2|数年に1回まとめて届出しても大丈夫?
就業規則の変更が生じた際は、その都度、遅滞なく届出を行う義務があります。
したがって、一定期間分まとめて届出することは認められていません。
変更があれば速やかに届出を行いましょう。
Q3|パートタイム労働者などの非正社員を適用除外とすることは可能?
1つの就業規則の適用範囲を「正社員のみ」とし、パートタイム労働者などの非正社員を適用除外とすること自体は問題ありません。
ただし、その場合には、非正社員用の就業規則を別途作成する必要があります。
もし、正社員の就業規則で非正社員を適用除外としておきながら、その非正社員に適用される就業規則の作成を怠った場合は、就業規則の作成義務違反となるため注意が必要です。
Q4|就業規則の義務違反をした場合どうなる?
就業規則を作成・届出しない、または内容が不適切な場合、企業は罰則の対象となることもあります。
就業規則の作成・届出義務に違反すると、労働基準法120条により「30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
また、労働基準監督署から是正勧告を受けた際には、速やかに対応しましょう。
これを怠ると、企業の信頼性を損ねるだけでなく、労働者とのトラブルや訴訟リスクが起こる可能性があります。
実態に合った就業規則を整備し、適正に運用することが望まれます。
まとめ|就業規則の作成と届出義務への対応は社労士との連携が安心です
本記事では、企業における就業規則の作成・変更義務について、「常時10人以上」の判断基準や、記載すべき事項、作成・変更時の届出手続き、周知の方法など、実務で押さえておくべきポイントを詳しく解説しました。
就業規則の整備は、法令遵守だけでなく、職場のルールを明確にし、労働者との信頼関係を築くうえでも非常に重要です。
ただし、就業規則は一度作成すれば終わりではありません。
法改正や職場の実態に応じて適切に見直し、常に最新の状態を保つことが求められます。さらに、就業規則の内容を労働者に確実に周知して初めて、法的効力を持つ点にも注意が必要です。
これらの対応には専門的な知識が求められるため、社労士などの専門家と連携しながら進めることをおすすめします。
就業規則の作成と届出義務について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。