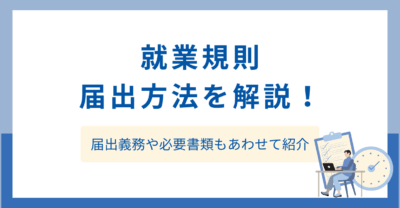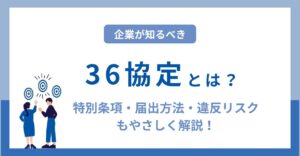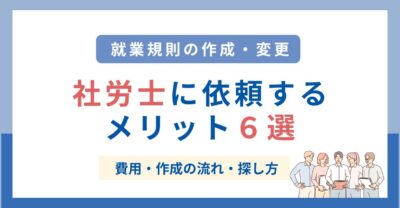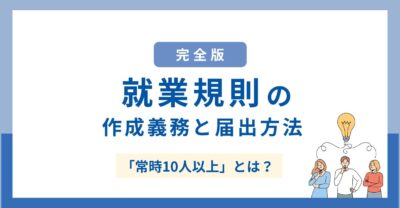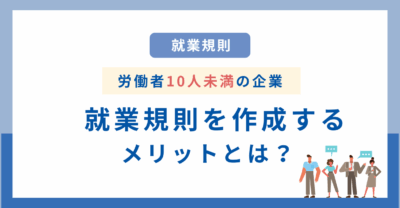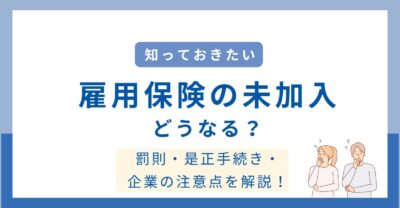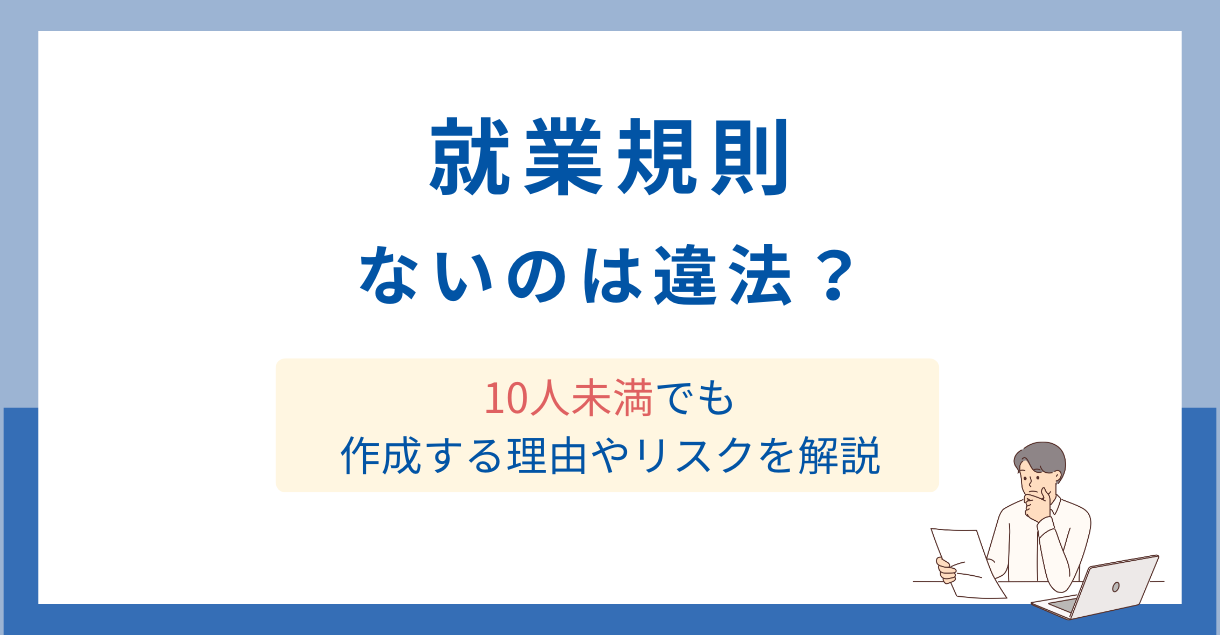
就業規則がないのは違法?10人未満でも作成する理由やリスクを解説
労働基準法では、常時10人以上の従業員を雇用する企業には就業規則の作成・届出が義務付けられています。一方、10人未満の企業では義務がないため、作成していないケースも少なくありません。
しかし、就業規則がないと、労務トラブルの発生や休職制度の不明確化、懲戒処分の適用が難しくなるなど、経営上のリスクが生じます。本記事では、就業規則がない場合のリスクや、10人未満の企業でも作成すべき理由を詳しく解説します。
適切な労務管理を行い、従業員と会社の双方にとって安心できる職場環境を整えるための参考にしてください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
就業規則がない会社の違法性
就業規則がない会社の違法性は、会社の状況や条件により異なります。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。(中略)※参考:労働基準法 第89条
就業規則がない会社の違法性は、2つのケースに分けられます。
- 違法になるケース:常時10人以上の従業員がいる事業場がある会社
- 違法にならないケース:常時10人未満の事業場のみの会社
常時10人以上の従業員がいる事業場がある会社は、就業規則がないと違法になる可能性があります。一方、常時10人未満の小規模な会社には作成義務はありません。
しかし、就業規則の作成は違法性の有無だけで判断せず、経営を円滑にするためにも作成をおすすめします。ここでは、就業規則の作成が必須とされる常時10人以上の数え方や、10人未満でも作成すべき理由について解説します。
常時10人以上の数え方
常時10人以上の数え方で注意するのは、主に以下の2つです。
- 事業場ごとに数える
- 非正規の労働者も含めて数える
事業場ごととは、1つの会社単位で数えるのではなく、各店舗や営業所、事務所などで数える意味です。そのため、各事業場で常時10人以上の従業員が労働する場合には、就業規則の作成が必要となります。
なお、本社には常時9人、支店には常時6人のような場合は、「常時10人以上の事業場」にそれぞれ該当しないので、就業規則の作成義務は発生しません。さらに、会長や社長などの経営者は労働者数に含まれないため、正社員9人と社長がいる事業場であれば常時9人の事業場となります。
また、非正規の労働者も人数に含めて数えるため、パートや契約社員も対象です。ただし、派遣社員は派遣先の労働者に含まれないため、混同しないよう注意しましょう。
就業規則は10人未満の会社でも作成がおすすめ
常時10人未満の会社は、就業規則の作成が義務付けられていません。しかし、義務ではなくとも就業規則はあるほうがよいといえます。
なぜなら、就業規則がないことによるリスクが大きいためです。作成する手間はかかるものの、就業規則があることでリスクを回避できます。
就業規則がない会社のリスク
就業規則がない会社のリスクは、次のとおりです。
- 服務規律が定まらない
- 病気休職者に適切な対応ができない
- 定年制の運用が不明確になりやすい
- 懲戒解雇・減給ができない場合がある
- 副業のルールが曖昧になる
- テレワークの管理が難しい
それぞれについて、具体的に見ていきましょう。
服務規律が定まらない
服務規律には以下のような内容を含むことが一般的です。定めていない場合はリスクにつながります。
- 営業秘密や個人情報を正しく取り扱うこと
- 取引先からキックバックを受け取ることを禁止する
- タイムカードは正しく打刻し、第三者が打刻することを禁止する
- セクハラ、パワハラに該当することをしてはならない
- 通勤時に車両を使用する場合は会社に申し出ること
- 就業時の身だしなみについて
当たり前のことでも、ルールとして明確にしていない会社では、従業員が違反した際に口頭で注意するのみに留まるケースが多くなります。従業員一人ひとりの行動基準が曖昧になり、会社の秩序や風紀を乱さないためにも、事業場の人数にかかわらず、就業規則で定めておくことが大切です。
病気休職者に適切な対応ができない
就業規則がない会社は、病気休職者に対して適切な対応ができません。適切な対応を取るためには、就業規則にて以下の内容にルールを設けましょう。
- 休職期間
- 休職期間中の給与
- 復職条件
- 退職条件
定年制の運用が不明確になりやすい
定年制を導入する場合にもルールを明確に定めることが重要です。
労働基準法では定年制の導入が義務付けられているわけではありませんが、退職に関する事項は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則に記載することが義務付けられています。※労働基準法 第89条
就業規則がない場合でも、個別の労働契約で定年を定めることは可能ですが、統一的な基準がないと従業員ごとに対応が異なり、不公平感が生じる可能性があります。また、定年の取り扱いが曖昧なままだと、労働者が「定年制が存在しない」と解釈し、無期限の雇用継続を求めるケースが発生する可能性もあります。
こうしたトラブルを防ぎ、会社としてのルールを明確にするためにも、就業規則を作成し、定年制の有無や条件を明確に定めることが重要です。
懲戒解雇・減給ができない場合がある
就業規則がない場合、懲戒解雇や減給の適用が不当と判断される可能性があります。懲戒処分は、合理的な理由と適正な手続きが求められるので、就業規則に明記されていないと不当とされる可能性があるためです。
就業規則に記載する場合は、以下の内容が必要になるため、把握しておきましょう。
- 懲戒種別:懲戒処分の種類・内容
- 懲戒事由:懲戒処分の対象になる内容
懲戒処分の内容を明確に定めることで、従業員もどのような行為が懲戒処分の対象になるのかを理解できます。会社側も公平かつ客観的な基準から懲戒処分を適正に行えるため、規律の維持が可能です。
また、解雇処分以外にも従業員の成績が悪い場合、減給処分を下すことが考えられます。就業規則に定めがあれば適正に実施できますが、過去の判例では、就業規則にもとづく減給措置でも不当と判断されたケースがあり、正しく規定しなければなりません。※出典:厚生労働省「8-1労働条件の引き下げ」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性」
懲戒解雇や減給については、就業規則がない場合でも、労働契約や労働協約の規定に基づいて行うことは可能です。しかし、基準が曖昧だとトラブルにつながる可能性が高くなります。会社のルールを明確にし、従業員とのトラブルを防ぐためにも、就業規則の作成が望ましいです。
懲戒解雇については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:懲戒解雇とは?適用条件・手続き・退職金の扱いまで徹底解説!)
副業のルールが曖昧になる
就業規則がない場合、副業のルールが曖昧になり会社が従業員の副業に対して言及できなくなります。
副業は、社員のスキルアップや自主性を高めるなどのメリットがある一方で、副業のルールが曖昧だと以下のリスクにつながることもあるため注意が必要です。
- 本業がおろそかになりやすい
- 自社の情報が漏えいする可能性がある
- 転職や独立に利用されることがある
- 長時間労働による体調不良などのリスクが高まる
副業を認める場合でも、会社の不利益にならないようルールを整備することが重要です。
テレワークの管理が難しい
コロナ禍をきっかけにテレワークを導入する企業が増えましたが、就業規則がないとテレワーク中の労働時間の管理や、テレワークに伴う費用の負担が明確化できません。そのため、テレワークの管理がおろそかになり、トラブルになる可能性もあります。
ただし、会社と従業員の合意でテレワークを行う場合は、就業規則に記載がなくとも法令違反にはなりません。法律を遵守するために作成するというよりも、ルールを明確化して働きやすい環境作りのために、就業規則で定めておくことがおすすめです。
就業規則がない会社が就業規則を作る手順・流れ
就業規則を作る手順は、次のとおりです。
- 現在のルールを確認する
- ひな形から作る
- 自社の就業規則に仕上げる
- 従業員の代表者から意見を聞く
- 労働基準監督署に届け出~社内周知
手順ごとに内容の詳細を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
1.現在のルールを確認する
まずは、現在のルールがどうなっているのかを確認しましょう。就業規則の根幹となる部分であるため、内容をよく確認することが必要です。
- 始業時刻
- 終業時刻
- 休憩時間
- 休日
- など
所定労働時間が法定労働時間を超えていないかも確認しましょう。ただし、変形労働時間制や特例措置対象事業場の場合は取り扱いが異なるため、自社の労働時間制をよく確認してください。※労働基準法 第32条
2.ひな形から作る
現在のルールを確認したら、就業規則を作成しましょう。ひな形を用いると作成作業を簡略化できるため、厚生労働省が公表するモデル就業規則などを活用してください。※厚生労働省「モデル就業規則(令和5年7月)」
作成する際は、モデル就業規則をそのまま使用しないよう注意が必要です。内容を精査しないと、自社のルールと異なるものになってしまいます。
また、他社の就業規則の使用はおすすめできません。自社と業種が同じでも会社ごとの細かなルールは異なるためです。
3.自社の就業規則に仕上げる
ひな形に記載されている項目は、全て目を通して修正および追加を行い、自社の就業規則に仕上げましょう。ただし、内容を修正する際は注意が必要です。
モデル就業規則の中には、法律上義務付けられている部分が記載されている場合もあり、修正すると違法な就業規則となる場合があります。法律を下回るような変更をしてはいけない例として、以下の内容が挙げられます。
- 有給休暇の付与
- 労災補償
- 解雇予告
ほかにもモデル就業規則の内容を修正する際は、細心の注意が必要です。
4.従業員の代表者から意見を聞く
就業規則が作成できたら、従業員の過半数代表からの意見聴取を実施します。作成した就業規則に目を通してもらい、意見書をもらわなければなりません。
過半数代表からの意見聴取結果も踏まえて話し合いを経て、会社の一方的な就業規則にしないよう努めましょう。従業員の代表者から意見がある際は、話し合いの場を設けて双方が納得できる形に仕上げることが大切です。
就業規則の意見書については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:就業規則の意見書とは?記入例や作成時のポイントや注意点を解説)
5.労働基準監督署に届け出~社内周知
最後に、作成した就業規則を労働基準監督署に届け出て、社内に周知すれば完了です。
就業規則の届出については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:就業規則の届出方法を解説!届出義務や必要書類もあわせて紹介)
手順解説では5つのステップとなりますが、実際に作成するには、時間と労力がかかります。とくに就業規則の内容を作成する際は、法律に関する専門知識が必要となるため、本業をこなしながらの作成は困難です。
そのため、就業規則の作成は専門家である社労士への依頼がおすすめです。本記事で解説した1~3までのステップを専門家の目線で作成してもらえます。
作成に割く時間と労力が不要になるほか、従業員の代表者に意見聴取を行う際も、修正や変更が少なく済むでしょう。また、双方が納得しやすい内容で作成してもらえる点も、社労士に依頼するメリットです。
就業規則がない会社の従業員からのよくある質問
最後に、就業規則がない会社の従業員からのよくある質問に回答します。
- 有給休暇はもらえますか?
- 退職金はありますか?
- 退職の手続きはどうすればよいですか?
- 休日はいつになりますか?
就業規則がない会社では、従業員がさまざまな不安や疑問を抱えるため、内容を確認して就業規則を作成する際の参考にしてください。
有給休暇はもらえますか?
条件を満たしていれば、必ず与えられるものです。就業規則がない会社でも従業員が条件を満たしている場合、会社は有給休暇を認めなければなりません。
有給休暇については、就業規則がある場合に必ず定めなければならない項目のひとつです。
退職金はありますか?
会社により異なるため、自社の取り扱いについて経営者等に確認しましょう。
退職の手続きはどうすればよいですか?
就業規則がない場合は民法上のルールに従い、正社員ならいつでも退職の申し出が可能です。申し出後、会社が退職を承認したとき、または退職の申し出から2週間が経過すると退職が認められることとなります。
休日はいつになりますか?
基本的には、法定休日が認められます。法定休日とは労働基準法に基づき、会社が従業員に与えなければならない休日です。また、法定外休日がある場合も休日として認められます。法定外休日とは、会社が独自に定めた休日です。
それぞれ同じ休日であるものの、出勤した際の違いがあります。法定休日に就業した場合は、休日割増賃金(35%以上)、法定外休日の就業では時間外割増賃金(25%以上)を支払わなければなりません。
就業規則を作成して社内を整えよう
就業規則は、企業のルールを明確にし、安定した経営を実現するために不可欠です。10人未満の企業では作成義務がないものの、服務規律や労働条件を明文化しておくことで、従業員とのトラブルを未然に防ぎ、より働きやすい環境を整えられます。
また、休職制度の明確化や懲戒処分の適正な運用を可能にするためにも有用です。ただし、就業規則の作成には法律の理解が不可欠で、不備があると逆にトラブルの原因になりかねません。そのため、専門家である社労士に相談し、適切な就業規則を整備することが重要です。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。