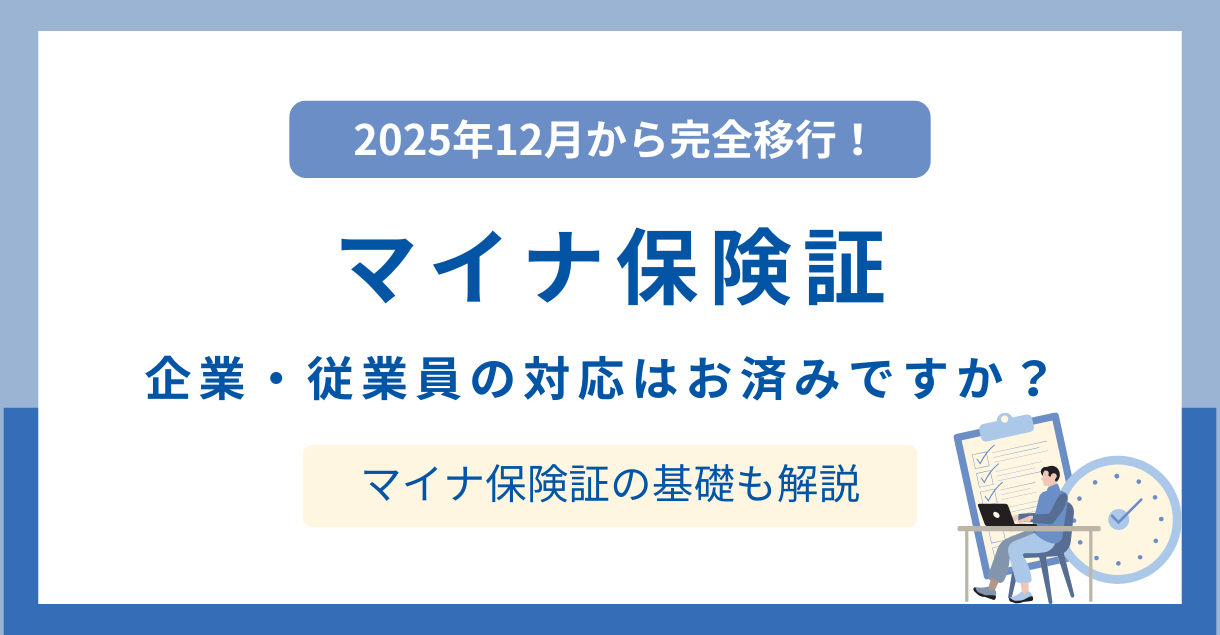
2025年12月から完全移行!企業・従業員の準備対応はお済みですか?マイナ保険証の基礎も解説。
2025年12月2日より紙の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードが「マイナ保険証」として完全に一本化されました。
「マイナ保険証とは何か?」
「従業員が登録していないとどうなるのか?」
「会社は何をすべきか?」
このような悩みを抱える企業担当者も多いことでしょう。対応が遅れていると従業員が医療機関で受診できないなど、トラブルにつながる可能性があります。
本記事では、厚生労働省など公的情報をもとに、マイナ保険証の仕組みと、2025年12月の完全移行に際して企業が取るべき実務対応をわかりやすく解説します。
※12月2日以降も2026年3月末まで健康保険証が使える旨の報道がありますが、これは暫定的な措置です。受診時にはマイナ保険証か資格確認書をご持参ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
2025年12月2日から「マイナ保険証」に完全移行

引用元:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
2025年12月2日より、これまで当たり前だった紙の健康保険証が廃止され、マイナンバーカードが健康保険証として使える「マイナ保険証」に完全移行しました。
病院や薬局では、カードをかざすだけで本人確認と健康保険資格の確認が、一度に行えるようになります。この仕組みは単なるカードの変更ではなく、国が進める「医療DX(デジタルトランスフォーメーション)」の中心的な施策です。
厚生労働省とデジタル庁は、医療情報をオンラインで安全かつ効率的に共有できる仕組みづくりを目指しています。マイナ保険証は、その第一歩として導入される制度です。
マイナ保険証導入の背景と目的
| 背景 | 目的 |
|---|---|
| 紙の保険証では事務手続きに時間がかかる | 医療機関・行政・保険者の情報をオンラインで連携 |
| 転職や引越しのたびに保険証の切替が必要 | 転入届等の情報を自動反映し手続きの手間を削減 |
| 健診・薬剤情報が医療機関間で共有されていない | 医療データを共有し、重複診療を防止。最大5年間の診療・薬剤情報を自身のマイナポータルで確認可能 |
| 不正利用やなりすましリスク | 顔認証や暗証番号による本人確認で安全性を向上 |
| 医療費が高額になった場合、限度額適用認定証の発行申請が必要 | 医療機関の窓口で限度額適用認定証の申請ができ、限度額を超える支払の免除が受けられる |
マイナ保険証は「医療の効率化」と「国民の利便性向上」を両立させるための仕組みです。病院側の事務負担が軽減されるだけでなく、利用者にとっても引越しや転職後の手続きがスムーズになるうえマイナポータルで過去の薬剤情報を確認することができます。
なぜ企業の人事担当者も準備が必要なのか
マイナ保険証は個人の制度でありながら、企業の労務管理にも直接関係します。なぜなら、従来の健康保険証や後ほど解説する資格確認書の発行は、入退社時の社会保険手続きと密接に連動しているからです。
中小企業や人事担当者に求められる対応は、次のとおりです。
- 従業員のマイナンバーカード取得・マイナ保険証の登録状況の把握
- 登録手順や利用方法を社内で周知
- 入社・退職時の社会保険手続きを確認
- マイナンバーカードを持たない社員への「資格確認書」案内
これらの対応を怠ると、「従来の保険証が使えない」「医療費が10割負担になる」など、従業員トラブルに発展する恐れもあります。
マイナ保険証の仕組みを正しく理解し、従業員が混乱しないよう早めの準備を進めることが重要です。
また、具体的な社内対応や手続き方法に不安がある場合は、社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談することで、確実かつスムーズに対応できます。
「マイナ保険証」とは?基本仕組みと従来保険証の違い

「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードに健康保険証としての機能を持たせたものです。これまでのように紙の保険証を持ち歩かなくても、マイナンバーカード1枚で医療機関を受診できるようになります。
受付ではカードをかざし、顔認証または暗証番号入力で本人確認と健康保険資格の確認が同時に完了します。従来の紙の保険証と比べると、事務の効率化・情報の正確性・安全性が格段に向上しています。
この仕組みは厚生労働省とデジタル庁が推進する「医療DX(デジタル化)」であり、行政・医療機関・保険者のデータをオンラインで安全にやり取りできるよう設計されています。
マイナンバーカードが“保険証”になる仕組み
マイナ保険証の仕組みはとてもシンプルです。マイナンバーカードに健康保険の資格情報をひもづけ、医療機関の「オンライン資格確認システム」を通じて、保険者や行政がその情報をリアルタイムで確認します。
医療機関での利用の流れは次の通りです。
- 病院や薬局でマイナンバーカードを専用リーダーにかざす
- 顔認証または暗証番号で本人確認
- オンラインで保険資格を即時照合
- 医療機関側の端末に保険情報が自動反映
保険証を提出して受付で目視確認する手間や、転職・引越し時の健康保険資格変更手続きを待つ時間が大幅に減ります。また、カード内には診療情報そのものが保存されるわけではなく、必要なときにのみ安全に照会できる仕組みです。
通信は暗号化され、厚生労働省とデジタル庁が厳重に管理しているため、セキュリティ面でも安心です。
マイナ保険証の特徴
マイナ保険証の最大の特徴は、利便性と安全性の両立です。従業員・企業・医療機関それぞれにメリットがあります。
主な特徴は次の3点です。
- 転職・引越し時の手続きがスムーズ
健康保険の資格変更情報がオンラインで即時反映されるため、紙の再発行を待つ必要がありません。 - 薬剤・健診情報の共有が可能
診療時に同意することで医師や薬剤師が過去の服薬履歴や健診結果を確認でき、重複投薬や不要な診察を防げます。また、最大で過去5年分の診療・薬剤情報がマイナポータルで閲覧可能です。 - 不正利用を防止
顔認証等による本人確認が導入されることで、他人の保険証を使う「なりすまし受診」のリスクが大幅に減ります。
マイナ保険証は「便利」なだけでなく、医療の信頼性と安全性を高めるための仕組みでもあります。医療機関と行政の間で情報が正確に共有されることで、国民全体の医療体験がよりスマートになります。
紙の保険証との違い
| 項目 | 紙の保険証 | マイナ保険証 |
|---|---|---|
| 資格確認 | 医療機関での目視確認 | オンラインで自動照合 |
| 住所・勤務先変更 | 会社が手続きをして保険証に裏書または発行 | 会社が手続きした内容を元にオンラインで即時反映 |
| 医療情報の共有 | 不可 | 薬剤・健診情報を医療機関で共有(同意制) |
| 本人確認 | 保険証+身分証明書 | マイナカード1枚(顔認証対応) |
マイナ保険証は「スピード・安全・利便性」のすべてを高めた新しい医療インフラです。企業にとっても、従業員の保険証切り替え手続きや住所変更対応がスムーズになり、結果的に労務担当者の事務負担を大きく軽減できます。
2025年12月の制度完全移行に向けて、今後はマイナ保険証を利用することがスタンダードになります。企業としても、この新しい仕組みを理解し、従業員がスムーズに登録・利用できるよう支援体制を整えておくことが求められます。
マイナ保険証を使うための登録・利用方法

マイナ保険証を使うには、まずマイナンバーカードを健康保険証として登録する手続きが必要です。登録といっても難しいものではなく、スマホやコンビニ端末、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーから数分で完了します。
登録の方法・医療機関での使い方・確認方法の3ステップで紹介します。
マイナ保険証の登録は、「マイナポータル」や「セブン銀行ATM」などからオンラインで簡単に行えます。一度登録すれば、転職や引越しのたびに再登録する必要はありません。
登録に必要なもの
- マイナンバーカード(ICチップ付き)
- 利用者証明用電子証明書パスワード(4桁)
多くの場合、申込み完了後すぐに利用できるようになります。
登録の手順
- マイナポータル(公式サイト)にアクセス
- 「健康保険証としての利用申込み」を選択
トップページまたはメニューから進みます。 - マイナンバーカードを読み取る
スマートフォン(マイナンバーカード対応機種)またはカードリーダーを使用します。 - 暗証番号を入力して認証
利用者証明用パスワード(4桁)を入力し、本人確認を行います。 - 申込み完了
手続きは数分で完了し、即時に利用可能となる場合がほとんどです。
(※一部の保険組合では、反映までに時間がかかる場合があります)
セブン銀行ATMでも登録可能
自宅にカードリーダーがない方は、全国のセブン銀行ATMからも登録が可能です。ATM画面で「マイナンバーカードの健康保険証利用申込み」を選び、案内に従ってカードをかざすだけで手続きが完了します。
医療機関・薬局でも登録可能
顔認証付きカードリーダーがある医療機関・薬局でも健康保険証利用の申込みができます。カードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証または暗証番号で本人確認をしてからカードリーダーの画面より申込・登録が完了します。
医療機関での利用手順
登録が済んだら、病院や薬局でマイナンバーカードを保険証として提示できます。利用手順はとてもシンプルです。
- 受付で「マイナ保険証を使います」と伝える
- 専用カードリーダーにマイナンバーカードをかざす
- 顔認証または暗証番号(4桁)で本人確認
- 保険資格がオンラインで即時確認され受付完了
この流れにより、従来のように保険証を提示して目視で確認してもらう必要はありません。また、資格の切り替えが遅れて「窓口で10割負担になった」というトラブルも防げます。
登録状況の確認方法
マイナ保険証の登録が完了しているかは、「マイナポータル」または「マイナポータルアプリ」からすぐに確認できます。
登録済みかどうかを自分で確かめておくことで、医療機関・薬局窓口でスムーズに受付をすることができます。
確認手順
- マイナポータルにログイン
パソコンまたはスマートフォンからアクセスします。 - トップページの「登録状況の確認」または「健康保険証」アイコンを選択
画面上の「健康保険証」メニューをクリックします。 - 「登録状況を確認」ボタンを押す
表示画面で「健康保険証としての利用登録状況」を確認できます。 - 「登録済」と表示されていれば手続き完了
この表示が出ていれば、マイナンバーカードが保険証として利用できる状態になっています。
スマートフォンから確認する場合
スマートフォンで確認する場合は、「マイナポータルアプリ」を利用します。アプリを開き、マイナンバーカードをスマホにかざしてログインすれば、同様に「健康保険証の登録状況」を確認できます。
企業に求められる対応
2025年12月2日以降は健康保険証が利用できなくなり、企業に問い合わせをする従業員が出てくる事もあります。まだ、マイナ保険証の登録が済んでいない従業員のために、下記案内をおこなうと良いでしょう。
- 登録方法を案内する社内マニュアルの整備
- 登録状況の確認依頼
マイナ保険証を持たない人のための「資格確認書」とは

マイナンバーカードを持っていない人や、利用登録をしていない人も医療機関で困らないように、「資格確認書」という健康保険資格の証明書があります。
マイナ保険証を利用できない人のために発行される暫定的な健康保険資格の証明書で、誰もが安心して医療を受けられるようにするための救済措置です。
資格確認書の概要
「資格確認書」は、マイナンバーカードを保険証として登録していない人に対して、
各保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)が発行する健康保険資格の証明書です。
資格確認書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | マイナンバーカードを持たない人 健康保険証利用登録をしていない人 |
| 発行元 | 各健康保険組合 全国健康保険協会(協会けんぽ) |
| 有効期限 | 最大5年(発行元により異なる) |
| 利用範囲 | 全国の医療機関・薬局で使用可能(マイナ保険証と同様) |
| 交付費用 | 無料(申請手続きが必要) |
利用方法と注意点
医療機関での使い方
資格確認書は、医療機関や薬局でマイナ保険証と同じように提示して利用します。受付で資格確認書を見せるだけで、これまで通り保険診療を受けることができます。
窓口での負担割合(3割負担など)も従来と変わりません。
利用時の注意点
- 有効期限が設けられています(最大5年)。期限切れになると更新手続きや再申請が必要です
- 紛失・破損した場合は再交付手続きを行います。紛失・破損の連絡が従業員よりあった場合にはすぐに保険者(協会けんぽ・健康保険組合)へ連絡しましょう。
- マイナンバーカード申請中の人も対象です。カードが届くまでの間、資格確認書で受診できます。
外国人労働者への対応
外国人労働者も資格確認書を申請できます。企業は在留カードと合わせてマイナ保険証の有無や資格確認書を確認しましょう。マイナ保険証については厚生労働省より在日外国人向けの各言語の資料が公開されているので、日本語が不得意な方に対しては厚生労働省の資料を案内すると良いでしょう。
資格確認書は、マイナ保険証への移行期間におけるセーフティネット(安全網)です。マイナンバーカードを持たない人でも安心して受診できるよう設けられた仕組みであり、「医療にアクセスできない人を出さない」ための制度的配慮といえます。
企業が取るべき「マイナ保険証」対応の実務ポイント

厚生労働省・デジタル庁の発表内容をもとに、会社が取るべき5つの実務対応ポイントを解説します。
① 従業員のカード取得状況を把握する
まずは、従業員がどの程度マイナンバーカードを取得しているかを確認することが出発点です。カードを持っていない従業員は「資格確認書」で対応する必要があり、事前の把握が欠かせません。
実務ポイント
- 社員名簿やアンケートでカード取得状況を把握
- 未取得者には申請サポート(申請書配布・役所案内・同行支援など)
- 外国籍従業員やパート社員なども対象に含めて確認
デジタル庁が令和6年度にインターネット上でおこなった調査によると、マイナンバーカード取得率は約87%です。依然として一定数の未取得者が存在し、企業の支援が重要です。
② 登録支援・社内周知の仕組みを整える
マイナンバーカードを持っていても、「健康保険証としての利用登録」をしていなければマイナ保険証として使えません。企業は登録方法や確認手順を分かりやすく案内する仕組みを整えることが大切です。
実務ポイント
- 登録手順ガイドを社内向けに作成
- 社員説明会・メール配信・掲示などで登録を促進
- イントラネットにFAQページを設置して問い合わせ対応を簡略化
③ 社会保険手続きを的確にすすめる
マイナ保険証制度は、社会保険の資格取得・喪失情報とオンラインで連動します。入退社手続きとの整合性を保つため、人事・社労士・システム担当者の連携が重要です。
実務ポイント
- 入社時:マイナンバーカードの有無を確認する
無い場合:資格取得届の提出と資格確認書の申請をおこなう
有る場合:資格取得届の提出
マイナ保険証登録がまだの場合:マイナ保険証登録を案内 - 退職時:資格確認書交付の有無
無い場合:資格喪失届の提出
有る場合:資格確認書を回収して資格喪失届に添付して提出 - 社会保険システム担当・社労士との情報共有会を定期開催
保険資格の更新が遅れると、医療機関で「無効扱い」となるリスクがあります。
④ 資格確認書対象者への対応フローを整備する
マイナンバーカードを持たない従業員に対しては、「資格確認書」の利用を案内する必要があります。資格確認書は暫定的なマイナ保険証として機能し、医療機関でマイナ保険証と同様に利用できます。
実務ポイント
- 未取得者をリスト化する
- 申請方法・必要書類を社内共有する
- 資格確認書の有効期限を把握し、時期が来たら更新を促す
⑤ トラブル防止と社内広報を徹底する
制度移行期には、全国的に「保険証が使えない」「登録が反映されていない」といった混乱が起きる可能性があります。社内で情報共有と相談体制を整えておくことが大切です。
実務ポイント
- 「2025年12月2日以降、従来の健康保険証は使えません」と繰り返し周知
- マイナ保険証に関する窓口(厚生労働省等の公的サイト・人事・社労士)を明示
- 外国人従業員向けに多言語案内(英・中・ベトナム語など)を用意
- 利用トラブル発生時の社内報告ルールを整備
マイナ保険証の完全移行は、企業にも従業員からの問い合わせが発生する重要な制度改正です。
対応に不安がある場合は、社会保険労務士(社労士)に相談することで、最新の法令・運用に基づいた実務サポートを受けられます。
トラブル防止Q&A|現場でよくある質問まとめ

マイナ保険証の利用が始まるり、「カードを忘れた」「登録できていない」など、現場での混乱が起こりがちです。よくある質問と実務的な対応策をまとめました。
Q:医療機関・薬局でマイナ保険証を忘れた場合は?
A:従来の健康保険証でも2026年3月末までは健康保険資格の確認ができれば保険診療を受けられるケースがあります。健康保険証も持っていない場合は窓口に伝え、後日提出が認められない場合は一旦自費診療となります。
ポイント
- 資格確認書を持っている場合は、それを提示すればOK
- 自費診療になったとしても後から保険者より保険適用分の払い戻しがされます
従業員向けに「マイナ保険証を忘れたときの対応フロー」を社内掲示・メールで共有しておくと安心です。
Q:マイナ保険証を紛失したら?
A:市区町村窓口で再発行できます。マイナンバーカードを紛失した場合は、市区町村の窓口で再発行の申請を行います。不正利用を防ぐため、すぐにマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ連絡して利用を一時停止してください。
再発行の流れ
- 紛失・盗難の連絡(上記フリーダイヤル)
- 市区町村役場で再発行申請(本人確認書類を持参)
- 数日以内に新カードが発行
- 新カードにも保険証機能が自動で引き継がれる
以前と同じように「健康保険証としての登録」について再申請は不要です。マイナポータルにログインすれば、登録状況がそのまま確認できます。
Q:外国人労働者もマイナ保険証を使える?
A:利用可能です。外国人労働者も、日本に住民登録している(住民票がある)場合はマイナンバーカードを取得できます。
マイナンバーカードに健康保険情報を紐づければ、日本人と同じようにマイナ保険証を利用可能です。
対応ポイント
- マイナンバーカードを持たない場合は資格確認書の発行を申請する
- 外国籍社員には英語・中国語・ベトナム語などの社内案内資料を用意
外国人労働者の在留期間や資格の更新時に、マイナ保険証登録の有効性も合わせて確認しておくと安心です。
Q:医療機関がマイナ保険証に対応していない場合は?
A:資格確認書または従来の資格確認で受診可能です。2025年末までに全国すべての医療機関がオンライン資格確認に対応する予定ですが、一部では導入が遅れている施設もあります。
その場合は、以下の方法で問題なく受診できます。
対応方法
- 資格確認書を提示する
- 保険者番号・被保険者番号を伝えてオンライン資格確認してもらう
医療機関が非対応でも、保険診療が受けられないわけではありません。医療機関側の対応状況は「厚労省・医療機関検索システム」で確認可能です。
まとめ:早めの準備でスムーズに「マイナ保険証」へ移行
2025年12月2日に健康保険証は廃止され、マイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されました。
登録は任意とされていますが、今後は医療機関での本人確認が「マイナ保険証」前提になるなど、実質的な義務化が進んでいます。
企業にとっても、従業員がスムーズに受診できる体制を整えることは、労務管理・福利厚生の一環として欠かせません。そのため、今のうちから社内での準備を進めておくことが重要です。
企業向けチェックリスト
- 従業員のマイナンバーカード取得状況を把握した
- マイナ保険証の利用登録方法や確認手順を社内で周知した
- 資格確認書の対象者を把握し、対応フローを整えた
- 社会保険労務士(社労士)など、相談できる専門家を確保した
マイナ保険証は「医療DX」の一環として導入が進む大きな制度改革です。
社労士など相談できる専門家と連携し、今後の制度改正をウォッチしておくと安心です。
マイナ保険証について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。














