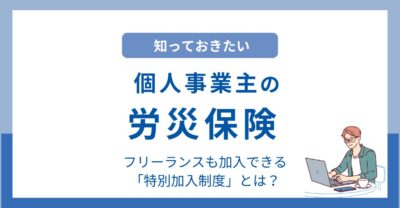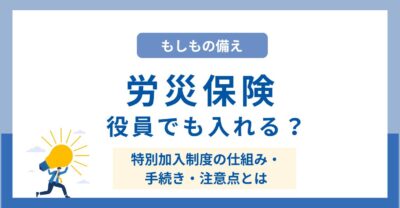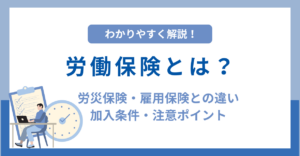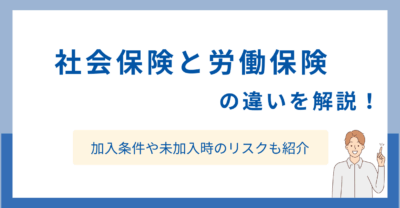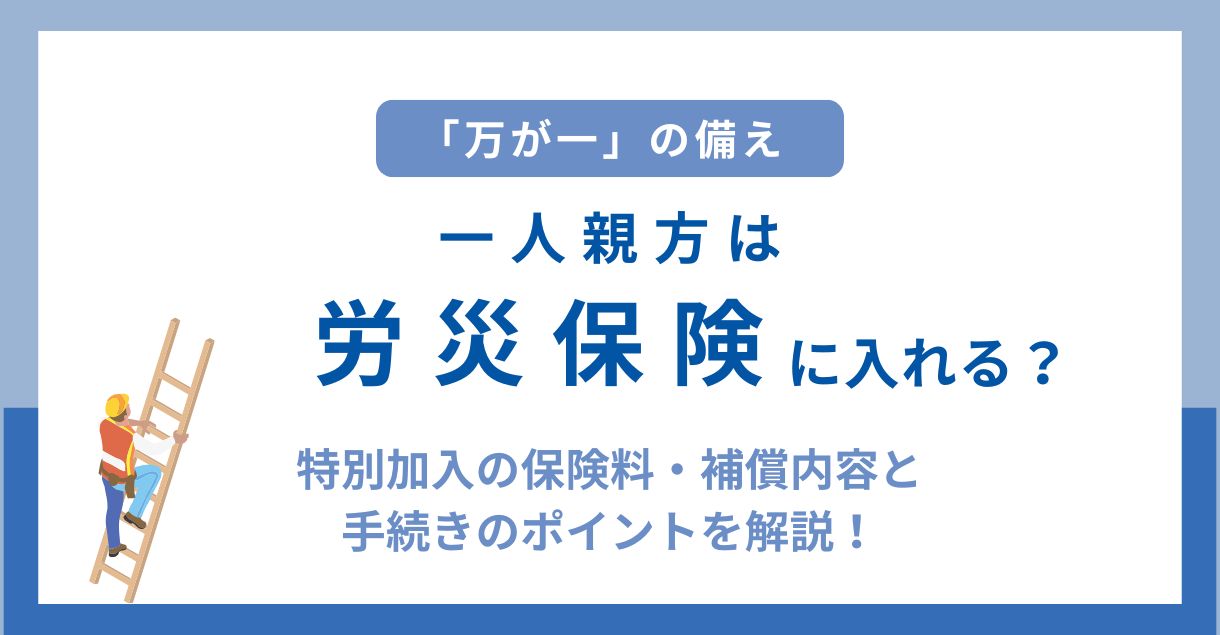
一人親方は労災保険に入れる?特別加入制度と保険料・補償内容をわかりやすく解説
建設や運送などの現場で働く一人親方は、自らが事業主の立場にあるため、原則として労災保険加入の対象外です。
しかし、一人親方であっても現場での作業内容や環境は、雇用されている労働者とほとんど変わりません。業務中に災害が発生するリスクも、労働者同様に存在します。こうした実態を受け、国が認めているのが、一人親方への労災保険の「特別加入」です。
この制度に未加入のままだと、ケガや事故が起きた際に補償を一切受けられず、治療費や休業中の生活費をすべて自己負担しなければならない可能性があります。
近年では、元請から「労災保険に入っていなければ現場に入れない」と加入を求められるケースも少なくありません。
本記事では、一人親方が労災保険に加入するための「特別加入制度」の仕組み、補償内容、保険料、手続き方法、注意点まで詳しく解説します。
一人親方として安心して働くために、労災保険の特別加入でどのような備えができるのかを理解できますので、ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
なぜ一人親方は通常の労災保険に加入できないのか?

一人親方は自営業者という立場にあるため、原則として労災保険の適用対象外となります。
労災保険は、以下のとおり「雇用されている労働者」を対象とした制度です。
■ 労災保険制度とは
・労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
・労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
たとえば、大工や左官などが請負契約で現場に入る場合、「雇われている」状態ではなく「自らの責任で作業する」ことになり、法律上は「労働者」として扱われません。
このような立場では、たとえ作業中に事故が起きたとしても、労災保険の適用対象外とされ、補償を受けることができません。
一人親方が加入できる労災保険とは?

労働者ではない一人親方などであっても、作業実態や災害リスクの高さから、「労働者と同様に保護すべき」と判断される場合には、例外的に労災保険への加入が認められています。
ここでは、一人親方が実際に労災保険に加入できる「特別加入制度」の概要について詳しく解説します。
一人親方の特別加入制度とは
特別加入制度とは、労災保険の適用対象ではない一人親方などが、一定の要件を満たすことで労災保険に「任意加入」できる制度です。
これは、労働災害リスクの高い業務に従事する自営業者の保護を目的に設けられた制度で、厚生労働省が所管しています。
特別加入により、通常の労働者と同様に以下のような補償を受けられるようになります。
- 治療費の全額補償
- 休業補償給付(最大80%)
- 障害補償、遺族補償、介護補償など
この特別加入制度に加入しておくことで、被災時における経済的なリスクを最小限に抑えられます。
補償内容は原則的に労働者と同じですが、加入者自身が申請し、加入にかかる費用は全額自己負担となります。
特別加入団体への所属が必要
一人親方の特別加入制度は、個人が直接労働基準監督署に申し込むことはできません。
都道府県の労働局長が承認した「特別加入団体」に所属し、その団体を通じて手続きを行う仕組みになっています。
承認を受けた特別加入団体は、厚生労働省のページの特別加入団体一覧表で確認することができます。
以下、一人親方が労災保険に特別加入する際のそれぞれの役割を示した表です。
| 立場・機関 | 主な役割・内容 | 関連する手続き |
|---|---|---|
| 一人親方等 | 労災保険の特別加入を希望する一人親方および家族従事者。保険料負担・日額選択・書類提供などを行う。 | 特別加入団体に対して、加入・脱退・業務内容の変更などを申し出る。 |
| 特別加入団体 | 一人親方の代行で手続きや保険料の徴収・納付を行う。 | 労働局長(労働基準監督署)へ変更届などを提出する。 |
特別加入団体は、特別加入に関して以下のような変更が生じた場合、労働基準監督署へ変更届を提出します。
変更届の提出が必要な場合
- 特別加入者の氏名、業務内容などに変更があった場合
- 新たに一人親方として特別加入を希望する人がいる場合
- 特別加入者としての要件にあてはまらなくなった場合(加入団体を脱退する場合)
また、特別加入団体に所属するには、労災保険料に加えて団体の会費を支払う必要があります。
団体によって会費や必要書類、サービス内容が異なるため、複数の団体を比較検討するとよいでしょう。
一人親方の労災保険料はいくら?計算方法と年間保険料

労災保険の特別加入制度を利用するにあたり、多くの一人親方が気になるのが「いくらかかるのか」「経費にできるのか」という点です。
ここでは、労災保険料の決定方法や目安の保険料、経理上の扱いについて解説します。
保険料は「給付基礎日額」で決まる
一人親方の特別加入保険料は「給付基礎日額」と職種・業種に基づいて決定されます。
給付基礎日額とは、休業補償などの給付額や保険料の算出基準となる額で、一人親方が希望額を選択し、特別加入団体が選択された額に基づき届出、労働局長が決定します。
加入者は、自身の年収や生活状況を踏まえて、3,500円〜25,000円までの範囲から給付基礎日額を選択できます。
保険料の計算方法
一人親方の特別加入の年間保険料は「給付基礎日額 × 365日 × 保険料率」で計算されます。
保険料率は職種・業種によって定められていますので、自身の保険料率については、厚生労働省が定める最新の特別加入保険料率を確認しましょう。
例として建設業に従事する一人親方の場合を見てみます。
建設業の一人親方は、保険料率が17/1000と定められており、給付基礎日額と保険料額は以下のとおりとなります。(2025年4月時点)
■ 給付基礎日額と年間保険料の目安 ※建設業の一人親方向け
| 給付基礎日額(円) A |
年間保険料算定基礎額(円) B=A×365日 |
年間保険料(円) 保険料率17/1000 |
|---|---|---|
| 25,000 | 9,125,000 | 155,125 |
| 24,000 | 8,760,000 | 148,920 |
| 22,000 | 8,030,000 | 136,510 |
| 20,000 | 7,300,000 | 124,100 |
| 18,000 | 6,570,000 | 111,690 |
| 16,000 | 5,840,000 | 99,280 |
| 14,000 | 5,110,000 | 86,870 |
| 12,000 | 4,380,000 | 74,460 |
| 10,000 | 3,650,000 | 62,050 |
| 9,000 | 3,285,000 | 55,845 |
| 8,000 | 2,920,000 | 49,640 |
| 7,000 | 2,555,000 | 43,435 |
| 6,000 | 2,190,000 | 37,230 |
| 5,000 | 1,825,000 | 31,025 |
| 4,000 | 1,460,000 | 24,820 |
| 3,500 | 1,277,500 | 21,709 |
給付基礎日額10,000円を選んだ場合、保険料算定基礎額は3,650,000円、保険料は年額62,050円となります。
なお、労災保険料率や給付基礎日額に基づく保険料は全国一律で、どの特別加入団体に加入しても変わりはありません
しかし、特別加入団体の会費や、サポート内容が異なりますので、比較検討のうえ、ご自身に合った特別団体を選びましょう。
労災保険の日額の選び方と注意点
給付基礎日額は補償額と保険料を決める非常に重要な基準です。
高い給付基礎日額を選択すれば補償内容も手厚くなりますが、当然ながらその分、保険料の負担も高額になります。
一方、保険料を抑えるために給付基礎日額を低く設定しすぎると、十分な補償が受けられないリスクがあります。実際に労働災害が発生した場合に、生活費や医療費などをどの程度カバーする必要があるのかを事前に想定して、給付基礎日額を検討しましょう。
■ 給付基礎日額を選ぶ際のポイント
| 年収・生活費を基準に補償額を逆算する | 月々の生活費や住宅ローンなどを踏まえ、「最低限必要な補償額」を意識しましょう。 |
| 家族構成や扶養状況を考慮する | 扶養家族がいる方は、収入減でも家族の生活が維持できるように、補償額が十分か確認しましょう。 |
給付基礎日額を変更するには「年度単位」と制限があり、災害発生後には変更できません。
したがって、最初に選ぶ日額が非常に重要になります。
一人親方に関する労災保険の特別加入団体や給付基礎日額の選び方に不安がある場合は、社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談するのがおすすめです。
必要に応じて、社労士に相談し、ご自身に合った日額設定を行いましょう。
一人親方の労災保険料は経費になる?
特別加入にかかる保険料は、「必要経費」として確定申告で経費計上が可能です。
青色申告・白色申告どちらの場合でも、必要経費として処理できます。
節税効果も期待できるため、領収書や納付明細をきちんと保管しておきましょう。
加入時には必ず「証憑(しょうひょう)」を受け取り、税務書類と一緒に管理しておくことが大切です。
一人親方の労災保険で受けられる補償
特別加入のメリットは、一人親方が労災事故に遭った際にも、労働者と同等の補償を受けられるという点です。
通常の労働者と同等の補償を、自営業者である一人親方でも受けることができます。一人で働く立場だからこそ、万が一に備える意識が重要です。
以下は、一人親方が業務または通勤時に被災した際に受けられる主な補償内容です。
| 補償の種類 | 内容概要 |
|---|---|
| 療養補償給付 | 業務・通勤中のケガや病気の治療費が 給付基礎日額に関係なく無料で受けられます。 ※労災指定病院等で治療を受けた場合。 ※労災指定病院等以外で治療を受けた場合は、治療に要した費用が支給されます。 |
| 休業補償給付 | 労働災害により働けない場合、 休業4日目以降、休業1日につき 給付基礎日額の80%が支給されます。 |
| 障害補償給付 | 障害が残った場合、 障害の等級に応じて一時金または年金が支給されます。 |
| 遺族補償給付 | 万が一死亡した場合、遺族に対して 一時金または年金が支給されます。 |
| 葬祭料 | 葬儀を行う際に、一定額の葬祭料が支給されます。 |
| 介護補償給付 | 常時または随時介護が必要になった場合、介護に対する費用が支給されます。 |
このように、一人親方が特別加入制度を活用することで、万が一のときにも労働者と同等の補償を受けることができます。
特に家計の担い手となっている一人親方にとっては、特別加入制度は生活の安定と安心を確保するうえで、重要な備えとなります。
一人親方の労災保険加入時に注意すべき点
特別加入は心強い制度ですが、特定の条件下では、事故や災害が補償の対象外となる場合もあります。
補償を確実に受けるためには、制度の仕組みを事前に理解しておくことが重要です。
補償対象外となる主なケース
労災保険では、「業務中に起きた不可抗力の事故」でないと労災とは認められません。
飲酒や故意による事故、就業時間外の私的行動中の事故などは、補償対象外となりますので注意が必要です。
補償対象外となる主なケース
- 故意に起こした事故
- 飲酒や違法薬物使用による事故
- 就業時間外の私的行動中の事故
- 他人への加害行為に起因する事故
制度の恩恵を確実に受けるためにも、補償対象外となるリスクをあらかじめ把握しておくことが安心につながります。
一人親方が労災保険に加入するための手続きと必要書類

ここでは、一人親方が特別加入制度を利用して労災保険に加入する際の手続きの流れと、準備すべき書類について解説します。
これから特別加入したいとお考えの方は、確認しておきましょう。
特別加入の手続きの流れ
- 特別加入団体を選ぶ
地域や業種に応じて加入可能な団体を探します。 - 申込書類を提出する
特別加入団体が求めている加入についての申請書・本人確認書類などを提出します。 - 保険料の納付
自分で選んだ給付基礎日額に応じて計算された保険料などを支払います。 - 加入証明書の発行
審査・登録完了後、労災保険加入証明書が発行されます。
「粉じん作業を行う業務・振動工具使用の業務・鉛業務・有機溶剤業務」に一定期間従事したことがある場合には、特定の健康診断の受診と結果の提出が必要な場合もあります。
また、建設業の場合、加入証明書は元請業者から提示を求められることもあるため、大切に保管しましょう。
申請に必要な書類
特別加入に必要な主な書類は以下のとおりです。
書類の様式や提出手順は特別加入団体によって異なるため、申し込み前にあらかじめ当該団体に確認を取りましょう。
特別加入の申請に必要な書類
- 本人確認書類のコピー(運転免許証など)
- 特別加入申請書(各特別加入団体の規定による)
- その他添付書類など
申請書類や添付書類の不備や遅れは、加入日が遅れ、労災補償が受けられない期間が生じる恐れがありますので、注意しましょう。
「元請が保険に入っているから大丈夫」は本当?よくある誤解と落とし穴

建設業の一人親方の方がよく誤解されるのが、「元請が労災保険に加入していれば、自分もその保険で補償される」という認識です。しかしながら、元請の労災保険は、自社および下請の「労働者」しか補償しません。
請負契約で働く一人親方は「労働者」には該当せず、元請が加入している労災保険の補償対象にはなりません。
そのため、「元請が労災保険に入っているから自分も大丈夫」と思い込んでいると、万が一の事故の際に補償が受けられず、治療費や休業中の生活費を全額自己負担する事態にもなりかねません。
労災事故への備えは、元請任せではなく一人親方自身が特別加入によって備える必要があると考えることが大切です。
まとめ|一人親方も労災保険に加入できる!万が一に備えよう
本記事では、一人親方が通常の労災保険に加入できない理由から、特別加入制度の仕組み・補償内容・加入手続き・注意点までを詳しく解説しました。
労災保険の特別加入は、万が一の事故やけがに備えて、法的な補償を自ら確保する有効な手段です。
一方で、特別加入制度自体を把握しているものの、自分で調べて進めるには時間も労力もかかるため、加入を後回しにする方も少なくありません。
「特別加入を検討しているが、団体選びや手続きがわからない」
「自分の仕事内容や収入に対してどのくらいの補償があれば安心なのか判断がつかない」
そのような方は、特別加入制度についての専門家である社労士に相談するのが安心です。
一人親方の労災保険について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。