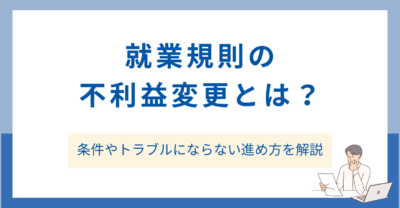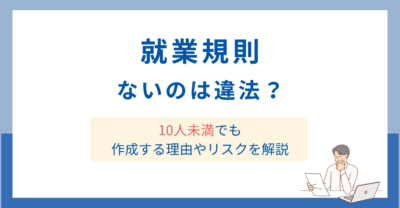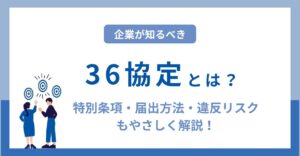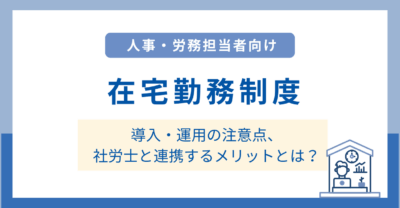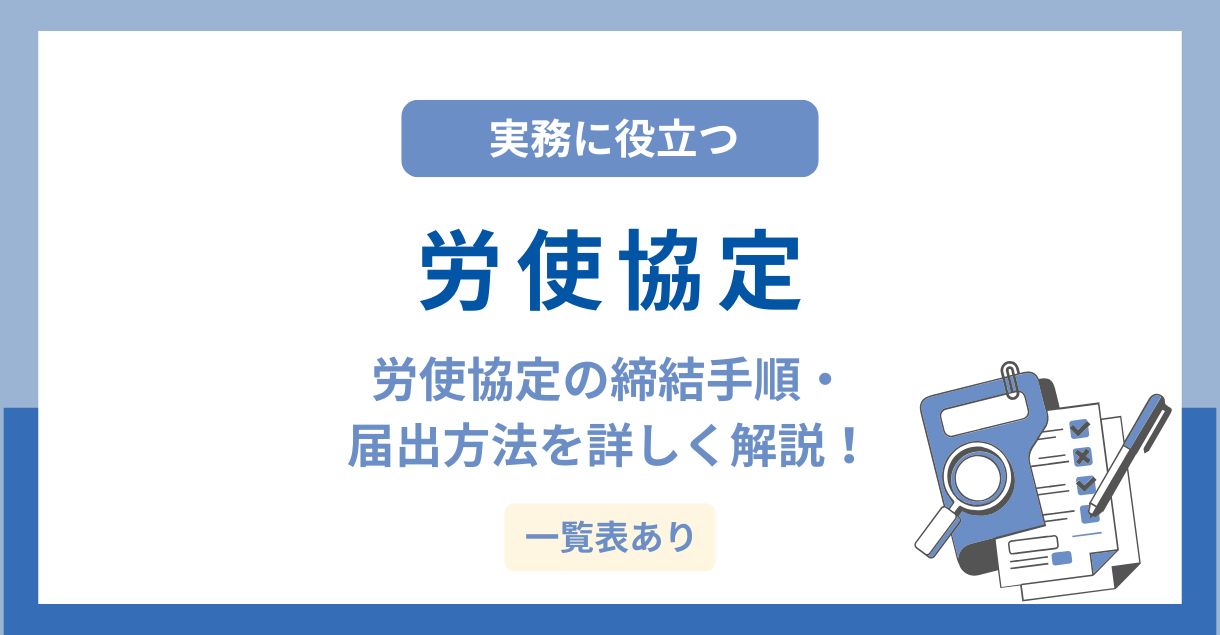
労使協定とは?36協定などの種類と届出ルールを一覧表付きで徹底解説
企業が労働者に残業や休日出勤をさせる場合や、フレックスタイム制を導入する場合には、法律に基づいた「労使協定」の締結が必要です。
労使間での明確な取り決めがないまま、時間外労働や特定の勤務制度を導入してしまうと、労働基準法違反に該当する可能性があります。
その結果、是正勧告や罰則、さらには未払い賃金の請求といったリスクが発生する恐れもあります。
本記事では、「労使協定」の基本的な仕組みから種類ごとの特徴、そして届出が必要な協定・不要な協定の違いまで、わかりやすく解説します。さらに後半部分では、労使協定の締結手順や労働基準監督署への届出方法もまとめています。
どの制度にどの協定が必要かを理解し、実務に役立てたい経営者や人事担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
労使協定とは

労使協定とは、使用者(企業)と労働者の間で合意される書面の取り決めのことを指します。労働基準法に定められた一定の事項について、例外を設ける場合や、特定の制度を導入する場合に必要とされます。
最もよく知られている労使協定が、「36協定(サブロク協定)」です。
これは、原則として「1日8時間・週40時間まで」と決められている法定労働時間を超えて、時間外労働や休日労働をさせるときに必要になるものです。
この協定がなければ、たとえ本人が同意していても時間外労働や休日労働は違法となります。
このように、企業が様々な働き方や制度を導入するためには、労使協定を正しく理解し、適切に締結・管理することが欠かせません。
「労働者の過半数を代表する者」とは?
労使協定を結ぶ際には、労働者側の代表と取り決める必要があります。
この代表には2つのパターンがあります。
労働者の代表の決定方法
- 事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合がある場合(パートやアルバイトも含む) → その労働組合が代表となる。
- 上記の労働組合がない場合
→ 事業場の全労働者から、過半数の支持を受けた「過半数代表者」を選ぶ必要がある。
なお、過半数代表者を選ぶ際は、使用者(会社側)が指名するのではなく、労働者の自主的な手続きによって選出されなければならないというルールがあります。
例えば、立候補者を募って投票で選ぶなど、公正な方法で決めることが求められています。
また、管理監督者(労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者)を過半数代表者とすることもできません。
上記2パターンのうちどちらも満たしていない、適正でないと判断された場合は、労使協定は無効となるため注意が必要です。
労使協定と労働協約の違い
労使協定と似た言葉に「労働協約」があります。
それぞれの違いを正確に理解しておきましょう。
労使協定と労働協約の違い
| 区分 | 労使協定 | 労働協約 |
|---|---|---|
| 相手方 | 過半数労働組合、または、過半数代表者 | 労働組合 |
| 主な目的 | 法の例外を可能にする | 労働条件の基準を定める |
| 有効範囲 | 労働者全体 | 組合員(場合によっては非組合員にも及ぶ) |
| 具体例 | 36協定、賃金控除協定など | 賃金水準、退職金、昇給基準など |
労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合(または労働者の過半数を代表する者)と、企業(使用者)との間で結ばれる書面による取り決めです。
これは、法律で定められた労働条件のルールに“例外”を設けるために活用されます。
例えば「36協定(サブロク協定)」はその代表例で、労使協定が結ばれていなければ、残業や休日出勤を命じることは原則できません。
また、給与からの控除(社宅費や昼食代など)を行う場合にも、「賃金控除に関する労使協定」が必要です。
一方、労働協約は、労働組合と使用者の間で締結される合意文書で、労働条件そのものの基準を定めるものです。
賃金・昇給・賞与・労働時間・退職金・福利厚生など、幅広い内容が含まれます。
例えば、ある企業で「正社員の基本給は月給25万円以上」と労働協約で取り決めた場合、会社はそれを下回る金額で雇うことはできません。
協約で定めた条件は、原則として労働組合の組合員に対して適用されます。さらに、一定の条件を満たせば非組合員にも適用されることがあります。
労使協定と36協定の関係
36協定は、労使協定の中の一種で、「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。
労働基準法第36条に基づいて締結されていることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。
36協定は、労使協定の中でも特に重要で届出義務がある協定です。未提出のまま残業をさせると、法違反になります。
多くの企業で活用されており、企業が最初に整えるべき労使協定ともいえます。
36協定については、「企業が知るべき「36協定」とは?特別条項・届出方法・違反リスクまで徹底解説」をご覧ください。
労使協定の種類一覧と概要
以下は、主要な労使協定の一覧です。
協定ごとに届出義務の有無が異なるため、まず全体像を把握しておきましょう。
| 協定内容 | 内容 | 届出の有無 |
|---|---|---|
| 時間外労働・休日労働(36協定) | 法定労働時間を超える労働や休日労働の許可 | 必要 |
| 変形労働時間制 (1週間・1ヶ月・1年) |
労働時間の柔軟な設定 | 必要 |
| フレックスタイム制 | 始業・終業時間を労働者に委ねる制度 | 必要 (清算期間が1か月を超えない場合は不要) |
| 賃金控除 | 給与から控除を行う際の取り決め | 不要 |
| 年次有給休暇の計画的付与 | 年休を会社が計画的に指定する | 不要 |
| 代替休暇の取得 | 割増賃金の代替として休暇を与える | 不要 |
| 育児・介護休業等の対象除外 | 育児・介護休業等の対象除外となる者定める | 不要 |
| 休憩時間の一斉付与の例外 | 休憩時間の一斉付与の適用を除外する | 不要 |
以下、それぞれの協定を届出義務のある協定・義務がない協定に分けて解説します。
届出が必要な労使協定とは
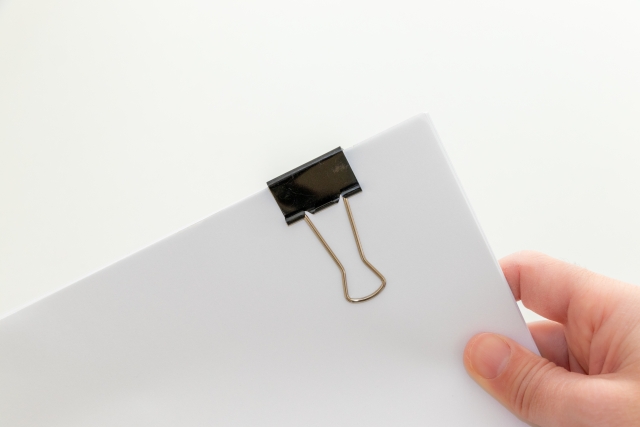
ここでは、労働基準監督署への届出が義務付けられている協定をご紹介します。
これらは法的に提出が必要なため、抜け漏れがないよう注意が必要です。
時間外・休日労働に関する協定(36協定)
法定労働時間(1日に8時間、1週間に40時間)を超える残業や休日労働を行う場合、36協定の締結と36協定届を労働基準監督署に提出する必要があります。
これを怠ると違法状態となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰則や、是正勧告を受ける可能性があります。
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定
労働者30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、条件を満たせば日ごとの労働時間を柔軟に調整できます。
条件
- 1日の労働時間を10時間以内
- 1週間の労働時間を40時間以内
勤務予定の通知や週労働時間の上限設定など、条件が厳密に定められており、要件を満たした協定の締結と届出が必要です。
1か月単位の変形労働時間制に関する協定
1か月の中で繁忙期と閑散期に応じて、1日の労働時間を調整できるようにするための協定です。
1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が原則40時間以内であれば、1日8時間を超える労働時間の設定が可能になります。
労働者に不利益が出ないよう、労使での明確な取り決めが必要です。
1年単位の変形労働時間制に関する協定
年間を通じて業務の波がある場合、労働時間を調整できるようにするための協定です。
1か月を超えて1年以内の一定期間で、1週間の平均労働時間が40時間以内であれば、1日や1週間の法定労働時間を超えて労働させることが可能になります。
この制度を導入するには、対象期間、所定労働時間の総枠、労働日および各日の労働時間等を協定書に定める必要があります。
フレックスタイム制に関する協定(清算期間1か月以上の場合)
フレックスタイム制に関する協定は、労働者が出勤や退勤の時間を自分で決められるようにする制度を導入するための取り決めです。
労働者が労働するべき時間を定める清算期間を3か月以内の範囲で設定でき、清算期間が1か月を超える場合は、労使協定の届出が必要です。
ただし、清算期間を1か月以内に設定することで労使協定の届出は不要になります。
総労働時間や標準時間を明記した協定が必要で、フレックスタイム制では、清算期間を平均して1週あたりの労働時間が40時間以内であれば、1日8時間を超える勤務も可能です。
つまり、1日8時間という上限は必ずしも適用されません。
ただし、清算期間全体で法定労働時間を超えた場合や、1か月ごとの労働時間が週平均50時間を超えた場合は、その超過分が時間外労働として扱われます。
また、法定労働時間を超えて時間外労働を行う場合は、フレックスタイム制に関する協定に加えて36協定の締結と届出が必要です。
参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定
事業場外で業務遂行に必要な時間が法定労働時間を超える場合、労使協定でその時間を定め、労働基準監督署への届出をする必要があります。
ただし、労働時間が法定労働時間を超えなければ、届出は不要です。
参考:「事業場外労働のみなし労働時間制」の適正な運用のために|東京労働局
届出が不要な労使協定とは

労働基準監督署に届出が不要な労使協定には、以下のようなものがあります。
届出義務はありませんが、書面作成と社内での保管が必要です。
賃金控除に関する協定
労働基準法第24条では、賃金は全額支払うことが原則ですが、所得税・住民税や社会保険料等の法定控除とされるもの以外に、社宅費や食事代などを給与から控除する場合、労使協定の締結が必要です。
労働者本人の同意だけでは不十分で、賃金控除に関する協定書に基づく運用が求められます。
年次有給休暇の計画的付与に関する協定
労働基準法第39条では、年次有給休暇のうち個人が自由に取得できる5日を超える日数について、労使協定を締結することで計画的に付与することが可能です。
対象者、付与日数、付与方法等を明記した協定が必要で、届出は不要です。
代替休暇の取得に関する協定
月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金の代わりに、休暇を与えられるようにするための協定です。
代替休暇を与えられる期間は、「時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内」とされています。
参考:代替休暇制度を導入するための労使協定を締結する場合のポイント|厚生労働省
育児・介護休業等に関する協定
育児・介護休業や短時間勤務などの制度は、基本的に労働者の希望により利用できますが、労使協定を結ぶことで、一定の労働者を対象から除外することが可能です。
例えば、「入社1年未満」「週2日以下勤務」「1年以内に雇用契約が終了予定」の労働者を、協定により制度の対象外にできます(育児・介護休業法に基づく)。
なお、休業等の制度によって対象外にできる労働者が異なりますので、ご注意ください。
育児・介護休業法については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:【一覧表つき】育児・介護休業法の2025年改正内容と企業対応ポイントまとめ)
休憩時間の一斉付与の例外に関する協定
労働基準法第34条では、休憩時間は労働者に対して一斉に与えることが原則です。
しかし、交替制勤務など一斉付与が困難な場合、労使協定を締結することで、個別に休憩時間を設定し交替で与えられます。
労使協定の締結手順と届出時の注意点
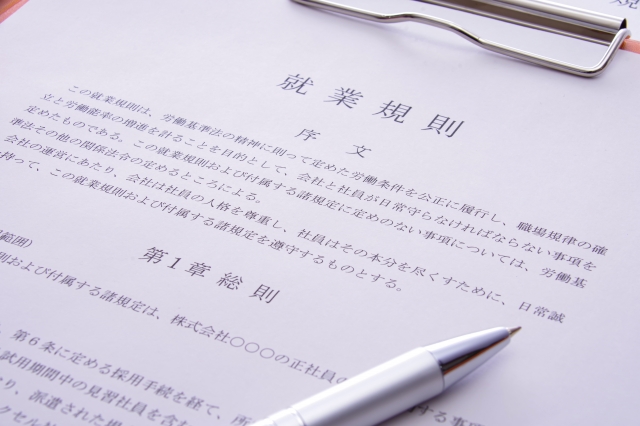
労使協定は、ただ作成すればよいというものではありません。
適切な手順を踏まなければ、無効とされるリスクもあるため、以下の流れをしっかり押さえておくことが大切です。
労使協定の締結手順6ステップ
以下、労使協定の流れを6ステップで解説します。
STEP 1|労働者代表の選出
労使協定を結ぶ前には、まず「労働者代表」を適切に選出する必要があります。
労働者代表の選出方法は、前述の『「労働者の過半数を代表する者」とは?』をご参考ください。
STEP 2|協定内容の作成とすり合わせ
まずは、企業側で協定内容のたたき台を作成します。
結ぶ協定の種類によって必要な記載項目が異なるため、法令や厚生労働省のガイドラインを確認しながら進めましょう。
とくに、労働基準監督署への届出が必要な協定は、必要事項が漏れていると「無効」と判断されるおそれがあります。
この段階で、労働組合や過半数代表者との協議・交渉を行い、内容を調整しましょう。
STEP 3|労働者代表と協定を正式に締結
内容が固まったら、使用者(会社)と労働者代表との間で正式に協定を締結します。
協定書には、締結日の記載と、両者の記名が必要になります。
STEP 4|就業規則の内容と整合性を取る
労使協定で取り決めた内容は、就業規則と関連することが多いため、必要に応じて就業規則を改定します。
就業規則に記載されている労働条件と矛盾がある場合、トラブルのもとになるため注意が必要です。
改定は、取締役会など社内の決裁手続きを経て、労使協定の発効日に合わせて行いましょう。
STEP 5|労働者に周知する
協定を結んだあとは、全労働者に内容をきちんと伝える(周知)義務があります。
社内の掲示板に貼り出すほか、社内ポータルサイト・共有ドライブなどで誰でも確認できる状態にしておきましょう。
STEP 6|労働基準監督署へ届出(必要な場合)
36協定など、届出が義務づけられている協定については、締結後、原則として発効日の前日までに労働基準監督署に届出ます。
届出が受理されてはじめて、協定は法的に効力を持ちます。
届出方法と注意点
労使協定は以下の方法で届出が可能です。
届出方法
- 労働基準監督署に持参
- 郵送による提出
- 電子申請(e-Gov)
ただし、届出時には以下の点に注意が必要です。
届出時の注意点
- 協定書は2部作成(1部は控えとして返却されます)
※労働基準監督署に持参・郵送の場合 - 労働者代表の選出手続きが適正であること
- 有効期間や対象範囲などの必要事項の記載漏れがないこと
- 協定内容が就業規則と矛盾しないこと
これらのポイントを事前に確認しておくことで、監督署からの指摘や差し戻しを防ぐことができます。
労使協定の作成と提出は、必要に応じて社労士などの専門家に相談をしながら、慎重かつ確実に進めましょう。
労使協定を結ばないとどうなる?
労使協定を結ばずに、時間外労働等の労使協定の締結が必要な制度を運用した場合、労働基準法違反となり、行政指導や罰則を受ける可能性があります。
特に36協定を提出せずに残業をさせた場合、以下のリスクがあります。
- 労働基準法違反で罰則(30万円以下の罰金など)
- 是正勧告や送検の可能性
- 労働者から未払い残業代の請求
- 労使トラブルが裁判に発展するおそれ
企業の信頼性や雇用関係に大きな影響を及ぼすため、適切な協定の締結と運用が不可欠です。
まとめ|労使協定の作成は社労士との連携が安心です
本記事では、労使協定の種類や届出義務の有無、労使協定の締結手順まで詳しく解説しました。
労使協定は、企業が法令を守りつつ柔軟な働き方を導入するために欠かせない仕組みです。
特に、届出が必要な協定は、労働基準監督署に提出して初めて効力が発生するため、提出漏れには注意が必要です。
ただし、協定の内容や進め方、書類作成には専門知識が求められるため、不安を感じる方も多いでしょう。
労使協定の作成・届出・労働者への周知など、一連の手続きを確実に行うためには社会保険労務士(社労士)への相談が安心です。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。