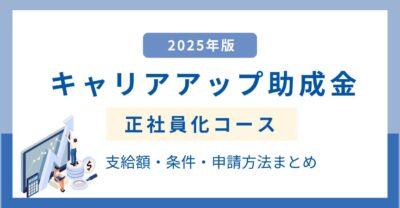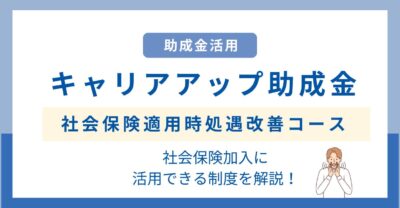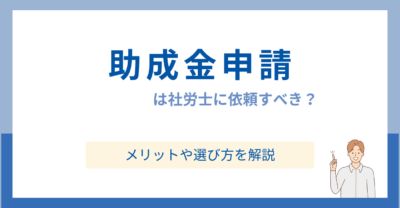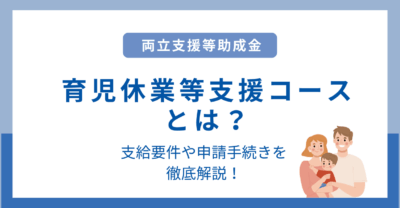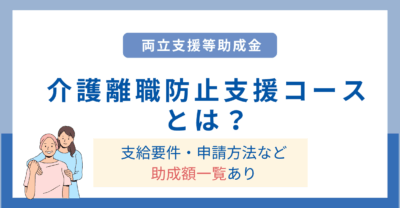キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)とは?共通化の具体例や注意点を解説!
キャリアアップ助成金の一つである「賃金規定等共通化コース」は、正規雇用労働者と有期雇用労働者等に共通の賃金規定や評価制度を適用した企業に対し、国が助成金を支給する制度です。
処遇格差の是正、労働者の意欲向上、公正な人事制度の整備など、企業・労働者双方にとってメリットが大きい支援策として注目されています。
一方で、制度の導入には、等級制度・賃金テーブルの整備・合理的な適用条件の設定など実務面で対応すべき項目が多く、不安を感じる担当者も少なくありません。
書類の不備や提出期日の誤認があると、助成金が支給されないケースもあるため正確な制度理解が不可欠です。
本記事では、キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の具体的な定義や支給要件、申請の流れ、導入時の注意点まで、具体例を交えてわかりやすく解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、自社の制度整備やスムーズな助成金申請にお役立てください。
キャリアアップ助成金の全体像について知りたい方はこちらをご覧ください。
>キャリアアップ助成金とは?対象企業・支給額・申請手続きまで徹底解説【2025年最新】
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)とは

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)は、企業で働く有期雇用労働者等※の処遇改善を支援する制度の一つです。
※「有期雇用労働者等」とは、有期雇用労働者および無期雇用労働者を指します。
- 有期雇用労働者:雇用契約の期間が決まっている労働者
- 無期雇用労働者:雇用契約期間の定めがない労働者のうち、正社員と同様の労働条件が適用されていない労働者
ここでは、キャリアアップ助成金の概要と、本記事のテーマである「賃金規定等共通化コース」について紹介します。
キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組む企業に対して、国が助成金を支給する制度です。
※「非正規雇用労働者」とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などを指します。
制度は「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2区分に分かれ、全6コースから自社の取り組みに合わせて選択・申請可能です。
企業内で非正規雇用労働者のキャリアアップを促進することで、人材の定着や生産性向上にもつながる制度として注目されています。
賃金規定等共通化コースとは
賃金規定等共通化コースは、キャリアアップ助成金のうち「処遇改善支援」に分類される制度です。
企業が雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の等級制度・賃金表・評価制度などを整備し適用した場合、国から最大60万円の助成金が支給されます。
助成金の申請は、共通化した賃金規定に基づき、対象労働者に6か月間の賃金を支給した日の翌日から2か月以内に行う必要があります。就業規則等への明記や、時給換算の比較など、制度要件に沿った事前準備が欠かせません。
後述では、共通化の定義や実施内容について詳しく解説しています。まずは、この制度の対象となる企業・労働者の要件を確認していきましょう。
賃金規定等共通化コースの対象となる事業主(企業)

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の支給を受けるには、申請する企業が、「全コース共通の要件」と「コース特有の要件」の両方をすべて満たしている必要があります。
ここでは、支給対象となるための要件について詳しく解説します。
全コース共通の支給要件
キャリアアップ助成金において、すべてのコースで共通して求められる基本的な要件は以下のとおりです。
- 雇用保険適用事業所であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者(キャリアアップに関する知識や経験をもつ者)を配置していること
※他の事業所や労働者代表との兼任はできません。 - 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ計画を作成し、管轄の労働局長に提出済みであること
- 実施するコースの対象労働者について、労働条件・勤務状況・賃金支払い状況を確認できる書類を備えており、賃金の計算根拠が明示できること
- キャリアアップ計画に基づいて、計画期間内に正社員化や処遇改善の取り組みを行い、申請時点ですべての支給要件を満たしていること
出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度)P4
全コースに共通する支給要件については、こちらの記事に詳しく解説しています。
>キャリアアップ助成金とは?対象企業・支給額・申請手続きまで徹底解説【2025年最新】
賃金規定等共通化コースの支給要件
賃金規定等共通化コースでは、就業規則の整備状況や賃金制度の適用範囲など、細かい基準が設定されています。
企業が助成金を受け取るには、全コース共通の支給要件を満たした上で、さらに以下①~⑧の要件をすべて満たしている必要があります。
- 就業規則または労働協約により、有期雇用労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、区分ごとに基本給等の待遇を定めていること
- 有期雇用労働者等の賃金規定等を作成するにあたり、その基準となる正規雇用労働者の賃金規定等が、同時またはそれ以前に導入されていること
- 正規雇用労働者と有期雇用労働者等に、それぞれ3区分以上の等級を設定し、両者を同じ等級にあてはめたうえで、有期雇用労働者等がその等級と同等またはそれ以上の等級に格付けされていること
- 上記③の同等またはそれ以上の区分において、有期雇用労働者等の基本給など職務内容に応じた賃金の時間当たりの額が、正規雇用労働者の同等区分における額と同額以上であること
- 賃金規定等が適用されるための合理的な条件を、就業規則または労働協約に明示していること
- 賃金規定等を、すべての有期雇用労働者等および正規雇用労働者に適用していること
- 賃金規定等を6か月以上運用していること
- 賃金規定等の適用により、すべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者の基本給および定額の諸手当※を減額していないこと
(※名称にかかわらず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動が見込まれるものも含みます。)
出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度)P42
制度活用を検討している企業は、自社の就業規則・等級制度・運用実績を改めて確認し、要件を満たしているかを慎重にチェックしましょう。
賃金規定等共通化コースの対象となる労働者

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)を活用するためには、企業側の支給要件を満たすだけでなく、対象となる労働者も一定の要件を満たしている必要があります。
労働者側が満たすべき要件は、以下のとおりです。
- 賃金規定等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前から、共通化後の6か月以上継続して雇用されている有期雇用労働者等であること
※「賃金規定等」とは、賃金に関する規定や賃金テーブル等を指します - 正規雇用労働者と同等、またはそれ以上の共通化された区分に格付けされていること
※「区分」とは、等級や号俸などを指します。有期・正規それぞれ3区分以上設けられ、うち2区分以上が共通である必要があります。 - 賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、雇用保険の被保険者であること
- 賃金規定等を新たに作成・適用した事業所の、事業主や取締役の3親等以内の親族でないこと
- 支給申請日時点で離職※していないこと
※自己都合退職、重大な理由による解雇、天災等による事業継続困難を除く
出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度)P42
上記のとおり、対象となる労働者の条件は、雇用形態だけでなく雇用期間や親族関係なども含まれるため、実情の確認が欠かせません。
賃金規定等共通化コースの支給額

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)では、適切に制度を導入・運用している企業に対して、企業規模に応じた助成金が支給されます。
企業規模別の支給額は、以下のとおりです。
| 企業規模 | 支給額 |
|---|---|
| 中小企業 | 60万円 |
| 大企業 | 45万円 |
支給は1事業所につき1回のみで、有期雇用労働者等の人数によって増減することはありません。複数名に共通化を適用していても、支給額は変わらないため注意が必要です。
企業規模「中小企業」の該当条件については、こちらの記事で詳しく解説しています。
>キャリアアップ助成金とは?対象企業・支給額・申請手続きまで徹底解説【2025年最新】
賃金規定等の共通化の定義と実施内容

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)を申請するには、正規雇用労働者と有期雇用労働者等に共通する賃金規定が整備され、合理的な条件のもとで運用されていることが求められます。
ここでは、制度上の「共通化」の定義・格付けや賃金の比較方法・共通化の適用条件・就業規則や労働協約への記載例まで、4つの観点で詳しく解説します。
賃金規定等の共通化とは
「賃金規定等の共通化」とは、有期雇用労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の職務区分や等級に応じた賃金体系を新たに設けることを指します。
賃金規定等の共通化における格付けと賃金設定のイメージは、以下のとおりです。
【賃金テーブル等共通化のイメージ】
| 6等級 | 月給××万円 | ― |
| 5等級 | 月給×▲万円 | ― |
| 4等級 | 月給■■万円 | 時給◯◯円 |
| 3等級 | 月給▲▲万円 | 時給□△円 |
| 2等級 | ― | 時給×○円 |
| 1等級 | ― | 時給△円 |
| 区分 | 正規雇用労働者 | 有期雇用労働者等 |
|---|
出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度)P44
上記の例では、正規雇用労働者と有期雇用労働者等の共通区分は3等級と4等級です。
この場合、共通区分(3等級・4等級)に格付けされた有期雇用労働者等の時給は、正規雇用労働者の月給を時給換算した金額と同額、もしくはそれ以上であることが求められます。
時給の計算方法
賃金規定等の共通化に必要な、正規雇用労働者の時給の計算方法は以下のとおりです。
| 正規雇用労働者の月給÷正規雇用労働者の月の労働時間数※
※月の労働時間数:1日の所定労働時間×月平均労働日数(週の所定労働日数×52÷12) |
具体的な計算例:
【月給30万円、1日8時間×週5日勤務の正規雇用労働者の場合】
- 月平均労働日数:5(日)× 52(週)÷ 12(か月)= 1か月あたり約21.7日
- 月の労働時間数:8時間 × 21.7日 ≒ 173.6時間
- 時給換算:30万円 ÷ 173.6時間 ≒ 1,728円
このとき、同じ等級に格付けされた有期雇用労働者等の時給が1,800円であれば、「正規の時給:1,728円<有期の時給:1,800円」となり、制度上「共通化している」といえます。
賃金テーブルを設計する際は、正規雇用労働者の給与水準を基準に、有期雇用労働者等の時給が同等以上の水準になるよう調整しましょう。
合理的な適用条件とは
合理的な適用条件とは、客観的かつ一貫した基準に基づいて設定されている、「誰にどの等級を適用するか」という格付けルールを指します。
以下の例は、合理的な適用条件を具体的に提示した一覧表です。
【賃金テーブル等が適用されるための合理的な条件】
| 区分 | 正規雇用労働者の例 | 有期雇用労働者等の例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6等級 | 企画 監督 |
業務に関する高度な専門知識・技能を有し、係の中・規則書等の遂行を図るとともに、部下の指導・教育を行い、その意欲を向上させることができる。 | ― | |
| 5等級 | 判断 指導 |
業務に関する一般的な専門知識・技能を有し、グループ構成員の業務を遂行できるとともに、下位構成員の指導ができる。 | ― | |
| 4等級 | 判断 | 業務に関する高度な業務知識・技能を有し、判断を要する業務を遂行できるとともに、下位構成員の業務を助言・指導できる。 | 判断 | 業務に関する高度な業務知識・技能を有し、判断を要する業務を遂行できるとともに、下位構成員の業務を助言・指導できる。 |
| 3等級 | 定型 熟練 |
業務に関する一般的な業務知識・技能を有し、ある程度判断力を要する業務を、確実に遂行できる。 |
定型 |
業務に関する一般的な業務知識・技能を有し、ある程度判断力を要する業務を、確実に遂行できる。 |
| 2等級 | ― |
一般 |
業務に関する基礎的な業務知識・技能を有し、主として定型的な業務を、正確に遂行できる。 | |
| 1等級 | ― |
定型 |
特別な業務知識・技能を必要としない日常の反復作業的な業務であり、細部的な指示を受けながら、正確に遂行できる。 | |
出典:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度)P44
上記の例では、3等級と4等級が正規雇用労働者と有期雇用労働者等の共通区分で、内容も同じです。このように、賃金規定等共通化コースでは、雇用形態にかかわらず同一の等級・内容が適用されていることが求められます。
共通化実施の就業規則等の規定例
共通化した賃金規定を制度として運用するには、就業規則や労働協約に、等級の適用条件や昇格ルールなどを具体的に記載しておく必要があります。
この記載が不十分だと、賃金規定等共通化コースの支給要件⑤を満たせず、助成金が支給されないケースもあるため注意が必要です。
※賃金規定等共通化コースの支給要件⑤:賃金規定等が適用されるための合理的な条件を、就業規則または労働協約に明示していること
厚生労働省の資料では、こうした合理的な条件の記載方法として、正規雇用労働者・有期雇用労働者等の両者に対する賃金表や等級構造の記載例が紹介されています。

引用元:厚生労働省|キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度)P45
就業規則等の規定が正しく設計され明示されているかは、助成金の支給可否に直結する重要なポイントです。
自社で就業規則を整備する際は、上記の記載例を参考に、明確で矛盾のないルールを構築しましょう。
賃金規定等共通化コースの申請に必要な書類

出典:厚生労働省|賃金規定等共通化コース内訳(様式第3号・別添様式4)
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)を申請するには、厚生労働省指定の様式による申請書類に加え、助成金の支給要件を満たしていることを示す添付書類の提出が必要です。
【申請書類】
- キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号)
- 賃金規定等共通化コース内訳(様式第3号・別添様式4)
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 支払方法・受取人住所届(初回・変更時のみ)
各様式は、厚生労働省ホームページ「申請様式ダウンロード(キャリアアップ助成金)」からダウンロード可能です。
※申請書類の様式は年度ごとに変更される場合があるため、必ず最新版を使用してください。
【添付書類】いずれも(写)
- 受理済みのキャリアアップ計画書
- 共通化前後の就業規則または労働協約
- 正規雇用労働者と有期雇用労働者等の両方に共通の賃金規定を適用していることを示す労働者名簿など
- 共通化対象となる正規雇用労働者1名・有期雇用労働者等1名の共通化前後の雇用契約書または労働条件通知書
- 同上2名分の、共通化前後の賃金台帳など
- 賃金台帳等に関する確認書
このほか、条件に応じて、委任状や事業所確認票が必要になるケースもあります。詳しくは厚生労働省のパンフレット「令和7年度版キャリアアップ助成金のご案内」(P.45)をご確認ください。
なお、記入漏れや記載不備があると、助成金が受給できない場合があります。
提出前には各様式の記載ルール・添付要件を確認し、不安な場合は社労士などの専門家への相談もおすすめです。
賃金規定等共通化コース申請の流れ

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の申請から受給決定までの流れは、以下のとおりです。
1.キャリアアップ計画の作成・提出
まず、企業はキャリア管理者を配置し、労働組合などの意見を聴取のうえ「キャリアアップ計画」を作成します。
キャリアアップ計画書とは:
有期雇用労働者のキャリアアップを効果的に進めるために、対象者・目標・期間・実施内容などの全体像を事前にまとめた行動プランです。企業が取り組む方向性やステップを明確にし、計画的に制度を活用するための指針となります。
完成したキャリアアップ計画書は、賃金規定等共通化コースの実施の前日までに、所轄の労働局またはハローワークへ提出(窓口・郵送・電子申請)します。
キャリアアップ計画書の作成方法はこちらの記事をご確認ください。
>キャリアアップ助成金とは?対象企業・支給額・申請手続きまで徹底解説【2025年最新】
2.賃金規定等の共通化の整備・実施
正規雇用労働者・有期雇用労働者等に共通する賃金規定等を整備し、就業規則や雇用契約書に明示のうえ適用します。規定の内容が支給要件をすべて満たしていることが重要です。
3.6か月分の賃金支払いと支給申請
共通化を適用した有期雇用労働者等に対し、整備後の賃金規定に基づき、6か月分※賃金を支払います(時間外手当や通勤手当などを含む)。
※出勤日数が11日未満の月は、賃金を支給した月数に含まれません。ただし、有給休暇などで賃金が全額支給されている日は出勤扱いとして計算します。
6か月分の賃金支給後、翌日から起算して2か月以内に、必要書類を揃えて受給申請を行います。
4.支給決定
提出された書類に基づいて労働局が内容を審査し、要件をすべて満たしていると判断された場合、助成金の支給が決定されます。
賃金規定等共通化コース申請時の注意点

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)を申請する際は、実施のタイミングと正確な手続きが重要です。
受給に必要な要件を満たしていても、書類の提出時期を誤ると助成金が受け取れないケースもあります。
ここでは、申請手続きにおける重要な注意点を3つに絞って解説します。
キャリアアップ計画書は必ず共通化実施前に提出
賃金規定の共通化を実施する前に、「キャリアアップ計画書」を所轄の労働局またはハローワークへ提出しておく必要があります。提出期限は共通化実施日の前日までと定められており、これを過ぎると申請そのものが無効になります。
手続きの遅れや不備による不支給を防ぐため、厚生労働省は「少なくとも実施の1か月以上前の提出」を推奨しています。早めの準備とスケジュール管理を徹底しましょう。
申請期間は「6か月分支給後の2か月以内」を厳守
賃金規定共通化コースを適用したあと、その規定に基づいて「6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内」に助成金の申請を行う必要があります。
この申請期限は厳格に定められており、1日でも期限を過ぎた申請は受理されません。不測の事態や申請期間の誤認があっても認められないため、申請期間は正確に把握しておきましょう。
スケジュールに不安がある場合は、事前に管轄の都道府県労働局に確認すると安心です。
共通化区分に「正規雇用労働者」と「有期雇用労働者等」が在籍していること
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)は、「正規雇用労働者に適用している賃金規定等を、有期雇用労働者等にも適用する」ことを目的とした制度です。
そのため、共通化した等級や職務区分に正規雇用労働者が不在の場合は、助成対象となりません。
また、正規雇用労働者が在籍していても、共通化後にその労働者に賃金支給実績がない場合(例:産休・育休などで無給が続くケース)も支給対象外となります。
制度の適用を進める際には、正規雇用労働者の配置と就業状況の確認を確実に行いましょう。
まとめ|賃金規定等の整備と助成金申請には専門家との連携が有効です
本記事では、キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の制度概要や対象要件、申請手続き、実務上の注意点まで詳しく解説しました。
賃金規定等共通化コースは、有期雇用労働者等に正規雇用労働者と共通の賃金規定等を整備・適用することで、有期雇用労働者等の処遇改善と企業の人材活用・定着を支援する仕組みです。
一方で、キャリアアップ計画の提出タイミング、就業規則の整備内容、申請書類の準備や提出期限管理など、制度の活用には細かな要件を正確に理解し、対応することが求められます。
不備があると助成金を受給できないケースもあるため、注意が必要です。
こうしたリスクを避け、助成金制度を確実に活用するためにも、社会保険労務士などの専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めたうえで依頼しましょう。