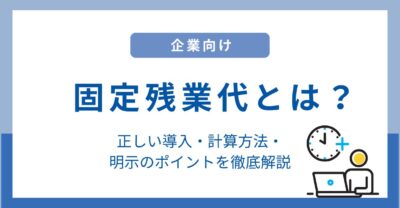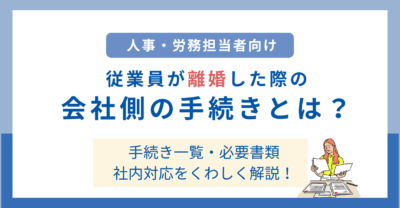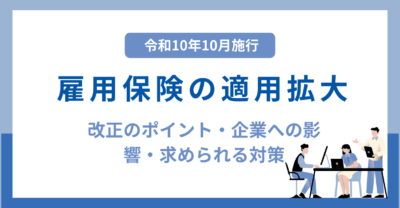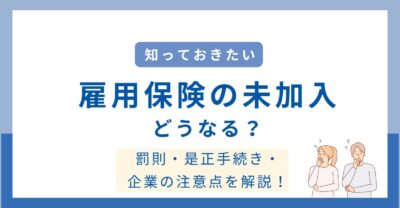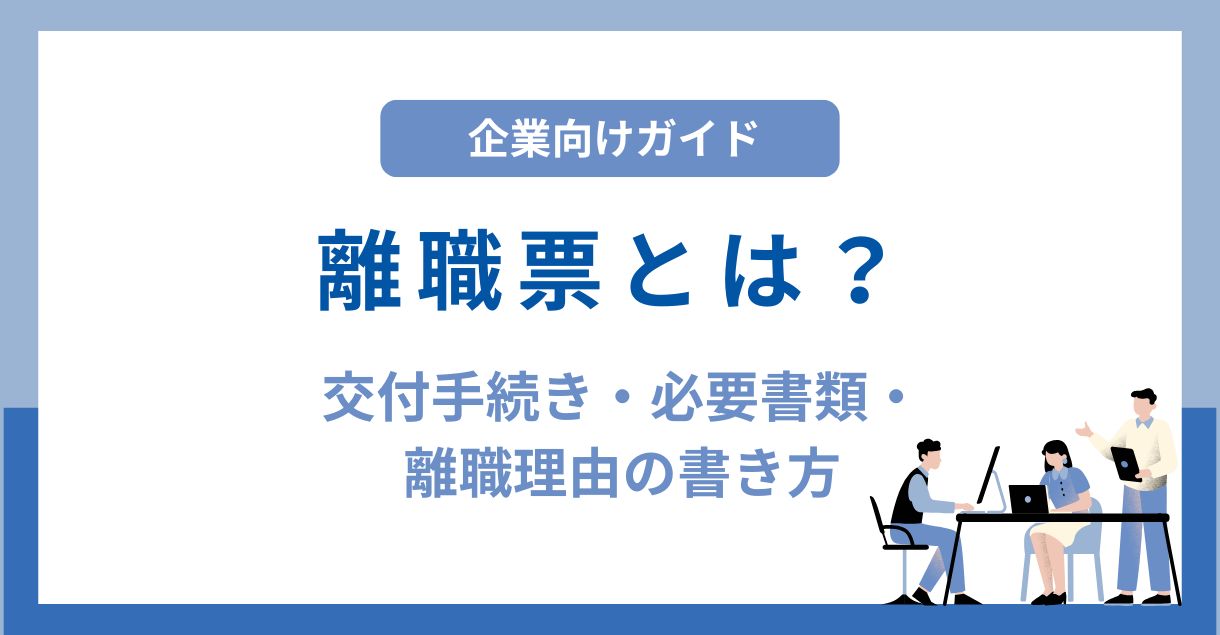
【企業向け】離職票とは?交付手続き・必要書類・記載ルールをわかりやすく解説
離職票の交付手続きは、退職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等。いわゆる「失業給付」)などを受けるうえで欠かせない、企業の重要な労務対応のひとつです。
書類への記載ミスや交付の遅れは、退職者の失業給付申請に支障をきたすだけでなく、退職者からの信頼を損なうほか企業の労務管理体制に対する評価にも影響しかねません。
さらに、2025年1月からはマイナポータルを通じた電子交付制度も始まっており、実務担当者にはこうした新たな選択肢についての理解も求められます。
本記事では、離職票の基本から交付対象・必要書類・記載時の注意点・電子交付のポイントまで、企業が押さえておきたい実務情報をわかりやすく解説します。
ぜひ最後までご覧いただき、自社の労務対応にお役立てください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
離職票とは

離職票とは、労働者が離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です。離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」といいます。
離職票は、雇用保険に加入していた労働者が離職した際、企業側が申請し、ハローワークから交付されます。
離職票の交付に必要な書類と手続き
離職票の交付に必要な書類と提出先は、以下のとおりです。
【必要な書類】
- 雇用保険被保険者資格喪失届(※マイナンバーの記載が必要)
- 雇用保険被保険者離職証明書(※3枚複写のためダウンロード不可)
- 記載した期間の給与・出勤状況が確認できる書類
(賃金台帳や給与明細、出勤簿やタイムカードなど) - 離職理由が確認できる資料
(労働者名簿、退職願、就業規則、雇用契約書など)
| なお、離職理由を確認する書類は、離職の理由(定年・契約終了・自己都合・解雇など)によって異なります。
厚生労働省の資料内にて、【持参いただく資料】の欄から参照できます。迷う場合は、所轄のハローワークまたは社労士などの専門家に確認すると安心です。 |
【提出先】
所轄のハローワーク
【提出期限】
労働者が離職した日の翌々日から10日以内
この提出書類をもとに、ハローワークが離職票(離職票-1・2)を発行し、企業に返送します。受け取り後、企業から離職者へ送付する流れが基本です。
離職票の種類
離職票には「離職票-1」「離職票-2」の2種類があり、それぞれ記載内容が異なります。
【雇用保険被保険者離職票-1】
- 作成:ハローワーク
- 記載内容:給付金の対象離職者の情報など
> 記入見本
【雇用保険被保険者離職票-2】
- 作成:ハローワーク(企業が記載・提出した離職証明書をもとに作成)
- 記載内容:賃金情報や離職理由など
> 記入見本
給付金の申請では、これら2枚の離職票の情報をもとに給付金額や期間が決定されます。
離職票と退職証明書の違い
離職票と退職証明書は、いずれも労働者の離職後に発行される書類ですが、目的や提出先、法的な性格が異なるため、混同しやすい書類です。
手続き内容に応じて正しく使い分けることで、申請や証明がスムーズに進みます。使用目的を踏まえたうえで、それぞれの書類の性質や記載内容を整理しておきましょう。
離職票と退職証明書の違いを以下にまとめました。
【離職票と退職証明書の違い】
| 項目 | 離職票 | 退職証明書 |
| 内容 | 基本手当等(いわゆる失業給付)のための公的書類 | 離職の事実を証明する私文書 |
| 主な用途 | 失業給付の申請 | 就職活動や各種手続きの証明 |
| 提出先 | ハローワーク | 転職先、保険会社、銀行など |
| 法律上の扱い | 雇用保険法に基づく | 労働基準法第22条に基づく |
| 発行義務 | 労働者が交付を希望しない場合を除き交付(離職理由を問わず) | 労働者から請求があれば必ず発行 |
| 発行者 | ハローワーク | 企業(社印付きが望ましい) |
| 様式 | ハローワーク指定様式(離職票-1・2) | 自由形式が多い(社内書式または任意書式) |
それぞれの役割や法的位置づけを正しく理解し、労働者からの希望に応じて適切に発行対応することが大切です。
離職票の交付が必要となるケース

離職票の交付手続きが必要となるのは、労働者からの希望がある場合(はっきり希望していなくても、交付を希望しないことが明確でない場合は交付が必要です。)や、特定の年齢条件に該当する場合です。
以下、交付が必要なケースについて確認しておきましょう。
労働者が離職するとき(交付希望の場合)
労働者から離職票の交付を希望された場合、企業には対応の義務があります。
なお、離職者の中には、直近の勤務先での被保険者期間が短い場合でも、過去の勤務先で発行された離職票と通算して、失業給付の受給資格を満たすケースがあります。
このようなケースに備え、離職者から特に希望の意思が確認できない場合であっても、離職票を交付することが必要とされています。
59歳以上の労働者が離職するとき
59歳以上の労働者が離職する場合は、本人の希望の有無にかかわらず、離職票の交付が必要です。
これは、60歳到達後に再就職して「高年齢雇用継続給付」の申請をする際、前職の離職票が必要になるケースがあるためです。
※高年齢雇用継続給付とは60歳到達時点より賃金が75%未満に下がった状態で働き続ける場合、差額の一部を支給する制度です。給付対象となるには、雇用保険の被保険者期間など一定の要件を満たす必要があります。 |
離職票はいつ届く?離職票の申請から発行までの流れ

離職票を申請してから届くまでの期間について、明確な規定はありませんが、おおよそ2週間が目安とされています。
ここでは、現在行われている主な離職票の発行までの流れと、2025年1月に導入されたマイナポータルでの受け取りについて解説します。
離職票の申請から発行までの流れ
離職票の申請には、企業が以下の順で手続きを行います。
流れ①|離職者に離職票が必要かどうかを確認する
離職者本人に離職票の交付希望があるかを確認します。なお、59歳以上の離職者には希望の有無に関わらず交付が必要です。
流れ②|企業が必要書類を準備し、ハローワークへ申請する
労働者が離職した日の翌々日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」や「雇用保険被保険者離職証明書」などの書類を所轄のハローワークへ提出します。
流れ③|ハローワークから企業に離職票が返送される
申請が正しく受理されると離職票-1、離職票-2が交付され、企業に返送されます。
流れ④|離職者へ離職票を送付する
企業に届いた離職票は、離職者本人へ手渡しまたは郵送で、すみやかに交付することが重要です。
離職者が求職者給付(基本手当等)を受給するには、本人が住居管轄のハローワークへ、離職票1・2、マイナンバーカード、写真2枚、預金通帳などを提出する必要があります。離職票の交付時に、申請方法の案内もあわせて伝えるよう務めましょう。
マイナポータルでも受け取り可能に

2025年1月20日から、希望する離職者はマイナポータルで離職票を受け取れるようになりました。
従来は、離職票(離職票-1・2)はハローワークから企業に返送され、企業が離職者へ送付する作業が必要でした(図左側③)。
しかし今回の制度変更により、企業が電子申請で手続きを行った離職票は、ハローワークから離職者のマイナポータルに直接送付されます(図右側③)。
これにより、企業の実務はハローワークへの届出(電子申請)だけとなり、離職者も企業からの離職票の到着を待たずにスムーズな受給手続きが可能になります(図右側④)。
ただし、このマイナポータルでの受け取りが利用できる対象は、一定の条件を満たす場合のみです。
利用の対象となる条件は以下のとおりです。
- マイナンバーと被保険者番号が正しく結びついていること
- 離職者本人によって、マイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定が済んでいること
- 企業が電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていること
条件を満たさない場合は、これまでどおり企業を経由して紙の離職票を受け取る必要があるため、事前に確認しておくと安心です。
雇用保険被保険者資格喪失届の書き方

出典:ハローワークインターネットサービス|雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者資格喪失届は、労働者が被保険者資格の要件を満たさなくなった場合、企業が用意してハローワークへ提出する書類です。
様式はハローワークインターネットサービスよりダウンロード可能で、手続きは電子申請にも対応しています。
提出期限は、離職した日の翌々日より10日以内です。漏れのないスムーズな手続きを心がけましょう。
以下に、雇用保険被保険者資格喪失届の書き方で気をつけるポイントを解説します。
1.「個人番号」
離職者のマイナンバーを記入します。
5.「離職等年月日」
離職した場合は、離職年月日を記入します。
例)令和7年6月30日→5-070630(※最初の5は元号、3:昭和、4:平成、5:令和)
6.「喪失原因」
以下の区分で、該当する数字を記入します。
|
7.「離職票交付希望」
離職票の交付を希望する場合は「1」、希望しない場合は「2」を記入します。
9.「補充採用予定の有無」
この届出に関連して、離職者の補充採用を予定している場合は「1」を記入します。ハローワークの紹介やその他の方法による採用を予定していない場合は、空欄のままで構いません。
雇用保険被保険者離職証明書の書き方

出典:厚生労働省|第5 被保険者についての諸手続|雇用保険被保険者離職証明書の様式例(P.8)
雇用保険被保険者離職証明書は、基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格・給付金額・給付日数の基礎となる重要な書類のため、正確な情報の記入が求められます。
なお、離職者が離職票の交付を希望しない場合は、離職証明書を提出する必要はありません。
様式は3枚複写式ですが、2枚目(安定所提出用)に、離職者の記名押印または自筆署名が必要な箇所が2箇所あります。書類作成の際には注意しましょう。
離職の日以前の賃金支払状況等
雇用保険被保険者離職証明書には、離職の日以前の賃金支払い状況等を記載する項目があります。
賃金支払状況の記入方法は、以下のとおりです。
⑧「被保険者期間算定対象期間」A 一般被保険者・・・一般被保険者 または高年齢被保険者ア 「離職日の翌日」欄には、「離職の翌日」を記入してください。 B 短期雇用特例被保険者離職した月から順次さかのぼって暦月を記入してください。 |
⑨「⑧の期間における賃金支払基礎日数」
|
⑩「賃金支払対象期間」
|
⑪「⑩の基礎日数」
|
⑫「賃金額」
|
⑭「賃金に関する特記事項」
|
引用:厚生労働省|第5 被保険者についての諸手続 |雇用保険被保険者離職証明書(用紙左側部分)の記入例(P11)
出勤記録や賃金台帳などの資料と照合しながら、正確に記入することが大切です。
離職理由の内容

出典:厚労省|第5 被保険者についての諸手続|雇用保険被保険者離職証明書の様式例(P.9)
雇用保険被保険者離職証明書用紙の右側には、離職理由を記載する項目があります。
離職理由の確認は、必ず対象の労働者が離職する日までに行いましょう。
記入する際のポイントは以下のとおりです。
- 企業が、離職者の主な離職理由に該当する箇所の□に○を付ける
- 離職者本人は、企業の○を付けた離職理由に対して「異議有り」「異議無し」のいずれかに○を付け、2枚目(安定所提出用)に署名をする
| 離職理由の各項目の内容や「具体的事情記載欄への主な離職理由」の書き方については、厚生労働省の資料から参照できます。 |
定年退職・再雇用時の離職票対応と記載ルール

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄は、定年退職と再雇用終了では記載区分が異なります。そのため、企業の実務担当者は正しい理解と対応が求められます。
以下では、定年・再雇用に伴って離職票が求められる場面と、離職理由欄の記載ルールを整理して解説します。
定年退職・再雇用終了後に離職票が求められる場面
定年退職や再雇用契約の終了による離職では、労働者の年齢や申請する制度に応じて、離職票が必要となる場面があります。
【離職後に必要となるケース】
- 60歳~65歳未満:通常の「基本手当(いわゆる失業給付)」を申請する場合に必要
- 65歳以上:「高年齢求職者給付金」を申請する場合に必要
【再雇用後に必要となるケース】
- 60歳~65歳未満:「高年齢雇用継続給付」を申請する場合に必要
59歳以上の労働者が離職する場合は、本人の希望にかかわらず離職票の交付手続きが必要となる点を踏まえて対応しましょう。
65歳以上の雇用保険についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
>雇用保険の加入は何歳まで?65歳以上の加入要件や再雇用時の手続きを徹底解説!
離職理由欄の記載方法
定年退職や再雇用契約の終了に際しては、雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄にチェックすべき理由区分がそれぞれ異なります。
定年による離職は、理由区分2の「定年によるもの」の欄に○を付けます。
定年後の有期契約で再雇用され、再雇用後の契約期間が終了して離職する場合は、理由区分3の(1)「採用または定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」または3の(2)の「労働契約期間満了による離職」に該当します。
| 離職理由の各項目の内容や「具体的事情記載欄への主な離職理由」の書き方については、厚生労働省の資料から参照できます。 |
離職票に関する注意点

離職票は、離職者が基本給付や各種制度の申請を行ううえで重要な書類です。不備があると手続きの遅れやトラブルにつながるため、以下の点に注意しましょう。
①離職者の希望有無を確認する
雇用保険法上、離職票は交付が原則です。交付を希望しないことが明確な場合は交付する必要はありません。ただし、59歳以上の離職者については、希望の有無に関係なく交付が必要です。
②離職理由の記載は慎重に
離職証明書には、企業側が離職理由に○をつけ、離職者はそれに対して異議の「有り・無し」のいずれかに○をつけて署名します。誤った理由を記載すると給付制限やトラブルの原因になるため、事実に基づいた記載を心がけましょう。
③記載期間・賃金に関する情報は正確に
離職前6か月〜12か月の賃金支払状況や出勤日数は、給付額に影響します。「11日以上働いた月」「対象期間の上限(原則2年、65歳以上は1年)」など、記載ルールに基づいた正しい記載が必要です。
④提出期限に注意
離職票の交付申請は、離職日の翌々日から10日以内にハローワークへ提出する必要があります。
提出の遅れは、離職者の受給手続きに支障が出るため厳守しましょう。
⑤電子交付を希望する場合は要件を確認
2025年1月20日から、一定の条件を満たす離職者は、マイナポータルで離職票を直接受け取れるようになりました。ただし、電子申請での手続きが必要なため、事前に対応状況を確認しましょう。
まとめ|離職票の対応は社労士と連携することで安心・正確に行えます
本記事では、離職票の役割や種類、取得までの流れ、記載時の注意点などについて詳しく解説しました。
離職票は、離職者が失業給付や各種制度を利用する際に欠かせない重要な書類です。記載内容は給付額や支給要件に直接影響するため、記入方法にも明確なルールが定められています。
また、交付時期や記載内容に不備があると、離職者が失業給付を受け取れない・手続きが大幅に遅れるなどのトラブルの原因になることもあります。
確実かつスムーズに対応するには、社労士と連携しながら制度に即した適切な運用を行うことが安心・正確な対応につながります。
離職票について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。