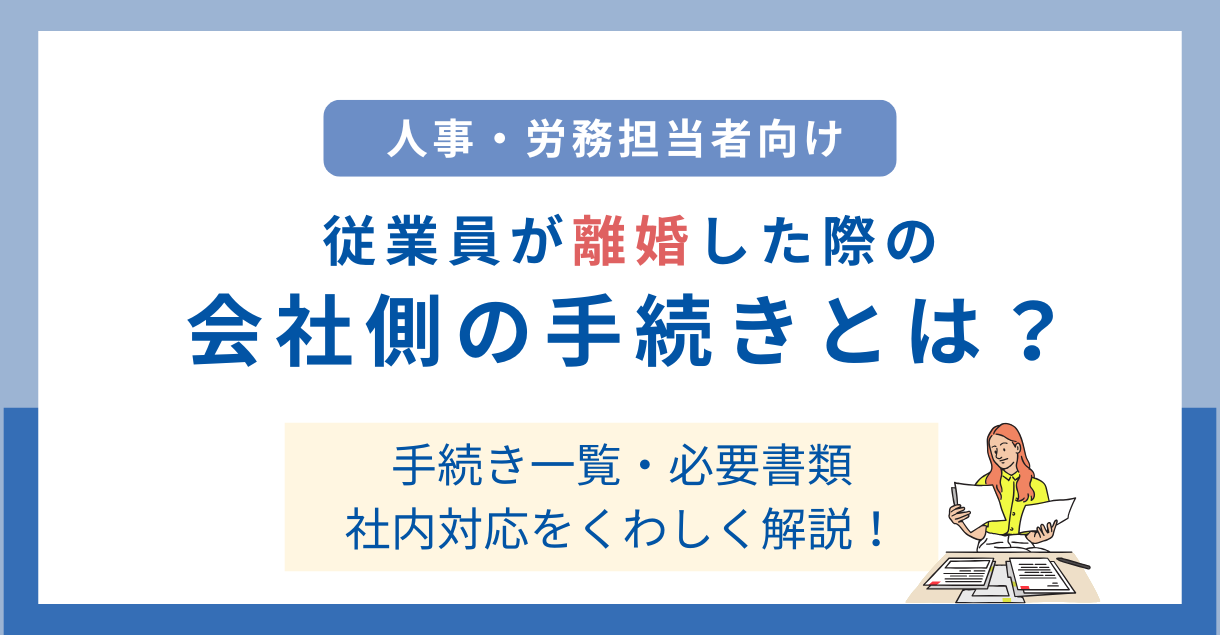
従業員が離婚した際に会社側が行う手続きとは?手続き一覧・必要書類・社内対応を徹底解説!
従業員が離婚した場合、企業の人事・労務担当者には、社会保険や税務上の変更手続きに加えて、社内制度に基づく手当の見直しや緊急連絡先の更新など、幅広い対応が求められます。
対応が遅れたり漏れたりすると、社会保険料や所得税の計算ミスが生じ、従業員への不利益、さらには不正受給やトラブルに発展する可能性もあります。
一方で、家族手当や住宅手当などの支給条件を明確にし、迅速かつ正確に対応することは、従業員の安心感と企業の信頼性を向上させるうえで欠かせません。
本記事では、従業員の離婚時に会社が行うべき手続きを一覧で整理し、社会保険・雇用保険・税務・社内制度の観点から詳しく解説します。
従業員から離婚の報告を受けた際にスムーズな実務対応ができるよう、必要書類や確認事項もあわせて紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
従業員が離婚した際に会社側が行う手続きとは?

従業員が離婚した場合、氏名や住所、扶養の有無などの変更に伴い、会社が対応すべき手続きは多岐にわたります。
まずは手続きの全体像を把握し、従業員に事前確認すべき情報や、提出してもらう書類を整理しておきましょう。
必要な手続き一覧
離婚に伴い、会社が行う主な手続きは大きく分けて、法令に基づくものと社内制度に基づくものがあります。
【法令に基づく手続き】
- 健康保険および厚生年金保険に関する氏名・住所変更の届出
- 雇用保険の氏名変更届出
- 配偶者が被扶養者から外れる場合の削除手続き
※従業員本人が被扶養者だった場合は、自社での社会保険加入や国民健康保険への加入案内 - 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出(年末調整対応)
【会社独自の社内制度に基づく対応】
- 家族手当・住宅手当の確認
- 緊急連絡先・福利厚生の見直し
社会保険や税務上の申告には期限が設けられているものもあるため、確認と準備を早めに行うことが大切です。
従業員に確認しておくべき事項
従業員から離婚の報告を受けた場合、会社が最初に確認すべき事項は次のとおりです。
- 離婚届を提出した日
- 姓の変更はあるか
- 住所の変更はあるか
- 扶養している配偶者や子どもがいるか
- 通勤手当の追加など、給与の変更はあるか
確認不足のまま処理を進めると、後から差し戻しや再提出が必要となります。従業員・会社双方に余計な負担がかかる恐れがあるため、最初に確認しておきましょう。
従業員に提出してもらう書類
提出書類は、確認内容を裏付ける証拠となり、会社が正しく手続きを行うために欠かせません。健康保険や税務の届出では添付が必要になることもあるため、不備のない準備が重要です。
離婚後に従業員から提出してもらう主な書類は以下のとおりです。
【法令に基づく手続き用(被扶養者がいる場合)】
- 戸籍謄本や住民票の写し
- (被保険者の住所に変更がある場合)被保険者の健康保険被保険者証
- 被扶養者の健康保険被保険者証、資格確認書など
【社内手続き用】
- 氏名・住所変更届
- 家族手当・住宅手当などの変更申請書
- 緊急連絡先の更新届など
一般的に、離婚届などの公的証明書を会社に提出させる義務はありません。
ただし、健康保険の被扶養者削除など一部の手続きでは確認書類として必要になる場合があります。従業員のプライバシーに十分配慮し、必要最低限の書類に限定して提出を求めることが望ましいでしょう。
従業員が離婚した際の社会保険の手続きと必要書類

離婚による社会保険の手続きは、「氏名や住所の変更」と「被扶養者の削除(非該当)に関する届出」が必要です。
ここではそれぞれの手続きについて整理します。
氏名変更と住所変更の手続き(協会けんぽの場合)
協会けんぽに加入している従業員は、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合、原則として氏名・住所変更の届出は不要です。
ただし、次のいずれかに該当する従業員の方は手続きが必要なため、書類や提出先を確認しておきましょう。
【手続きが必要になるケース】
- マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
- 健康保険(全国健康保険協会管掌)のみに加入している方
- マイナンバーを有していない海外居住者
- 短期在留外国人
- (住所変更時のみ)住民票住所以外の居所を登録する方
【必要書類】
・氏名変更:健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届
※添付書類:資格確認書および健康保険被保険者証が必要です。
なお、健康保険被保険者証は令和7年12月2日以降、原則廃止となるため使用できなくなります。必要添付書類については、日本年金機構の最新の情報をご確認ください。
・住所変更:健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届(国民年金第3号被保険者住所変更届)
※添付書類なし
【提出時期(氏名変更・住所変更ともに)】
氏名が変更になったらすみやかに
【提出先(氏名変更・住所変更ともに)】
提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
【提出方法】
電子申請(※氏名変更のみ)・郵送・窓口
協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合は、必要な届出や手続きが異なる可能性があります。加入先の健康保険組合へ直接お問い合わせください。
配偶者が被扶養者から外れる場合の手続き(協会けんぽの場合)
離婚により配偶者や子どもなどが被扶養者から外れる場合、被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。
申請に必要な書類や添付資料、提出の流れは以下のとおりです。
【提出書類】
・健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
・離婚の事実を確認する書類(被扶養者の戸籍謄本や住民票の写しなど)
・交付されている資格確認書または健康保険証(配偶者分)
※紛失等により回収ができない場合は、健康保険 資格確認書回収不能届」または「健康保険 被保険者証回収不能届を添付
【提出時期】
事実発生からその都度
【提出先】
事務センターまたは管轄の年金事務所
【提出方法】
電子申請・郵送・窓口
なお、従業員本人が配偶者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被扶養者だった場合、離婚後は扶養から外れるため、自らの加入先を選ぶ必要があります。
会社で厚生年金保険等に加入する場合は、被保険者資格取得届を提出します。加入しない場合は国民年金第1号被保険者としての加入手続きを行うよう案内しましょう。
従業員が離婚した際の雇用保険の手続きと必要書類

雇用保険については、従業員の氏名に変更が生じた場合に限り、所轄のハローワークで手続きが必要です。
従来は「雇用保険被保険者氏名変更届」による届出が必要でしたが、2020(令和2)年1月に制度が改正され、この届出は廃止されました。
現在は、以下のような他の届出を行う際に、あわせて氏名変更を届け出る仕組みとなっています。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用継続交流採用終了届
- 雇用保険被保険者転勤届
- 個人番号登録・変更届
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
- 高年齢再就職給付金の支給申請
- 育児休業給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
- 介護休業給付
なお、雇用保険では住所情報を登録していないため、氏名変更以外の理由での住所変更に関する手続きは不要です。
社会保険の変更手続きとは扱いが異なるため、混同しないように注意しましょう。
従業員の離婚に伴う給与・手当の変更と社会保険料・税務手続き

離婚により家族構成や住所に変更が生じると、家族手当や通勤手当などの社内手当が見直されるケースが多く、給与・税務・社会保険料計算上の影響が生じます。
また、配偶者控除が適用されていた家庭では、離婚によって控除が受けられなくなるため、税額や手取りが変わるケースが一般的です。
ここでは、離婚後に発生しやすい給与・税務・社会保険料計算上の影響と、それに伴う手続きについて整理します。
家族手当・通勤手当等の変更がある場合
家族手当や通勤手当は給与に含まれるため、手当が増減すると、税金や社会保険料の計算に影響します。
特に、家族手当や通勤手当などの手当は「固定的賃金」にあたるため、標準報酬月額の算定対象に含まれます。
従業員の報酬が、手当増減などで大幅にかわった場合は、随時改定(いわゆる月額変更届)の対象となることがあり、健康保険料や厚生年金保険料の額に反映されるため注意が必要です。
離婚に伴い手当が変更となった場合は、事業主が該当の報酬月額などを「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届」に記入し、すみやかに日本年金機構や健康保険組合へ提出する必要があります。
随時改定を行うべきシーンや手続き方法については、日本年金機構のホームページ「随時改定(月額変更届)」をご確認ください。
配偶者や子どもが被扶養者から外れる場合
離婚によって配偶者が被扶養者から外れると、それまでの「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が適用できなくなります。その結果、課税所得が増えるため所得税・住民税の負担が増加し、手取り額が減少するケースもあります。また、子どもが被扶養者から外れると、「扶養控除」が非該当になるため、配偶者同様に税負担が増加します。
控除の変更に伴い、従業員は以下の申告が必要となります。
【提出書類】
【提出期限】
- 年末調整書類の提出期限(おおむね11月頃)まで
【提出先・提出方法】
- 従業員が申告書に該当する変更事項などを記載し、給与の支払者へ提出
※基本的に給与支払者が保管し、税務署や市区町村から求められた場合のみ提出します
離婚後も配偶者控除や配偶者特別控除を誤って適用したままでいると、税額計算にズレが生じ、追徴課税や修正申告が必要になる恐れがあります。
また、控除が外れることで実質的な手取り額が減るケースもあるため、会社としては従業員に事前に説明を行い、変更内容を正しく理解してもらうことが重要です。
詳しい申請方法については、国税庁|A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告をご確認ください。
従業員の離婚に関する社内制度・就業規則の確認ポイント

従業員の離婚に関しては、社会保険や税務の手続きだけでなく、社内制度や就業規則に基づく確認も欠かせません。
離婚によって手当や福利厚生の対象条件が変わると、支給の過不足や不正受給につながるおそれがあるため、早めに見直しておく必要があります。
ここでは、手当の条件確認と、連絡先・福利厚生情報の見直しという2つの観点から解説します。
家族手当・住宅手当の条件を確認
家族手当や住宅手当など、一般的に家族を対象とする社内制度は、離婚後に要件を満たさなくなる場合があります。就業規則や社内規程をもとに、以下の点を確認しましょう。
- 家族手当:支給対象が配偶者であるか、子どもが扶養に残る場合は対象となるか、対象となる場合はその範囲や手当額など
- 住宅手当:「配偶者の有無」や「扶養人数」を条件としている場合、離婚後も要件を満たすかどうかなど
あらかじめ就業規則や社内規程で運用ルールを明確にしておくことで、不正受給を防ぎ、公平で一貫した支給が可能になります。
緊急連絡先・福利厚生情報の見直し
離婚後は、緊急連絡先や福利厚生の利用条件についても見直しが必要です。対応を怠ると、緊急時の連絡や社内制度利用時にトラブルを招く可能性があります。
- 緊急連絡先:配偶者を登録している場合は、親族や子ども、信頼できる第三者など新たな連絡先を提出してもらい、速やかに社内システムへ反映する。
- 福利厚生:保養施設や慶弔見舞金など、配偶者を対象とする制度が離婚後も利用できるかを整理し、必要に応じて見直しを行う。
離婚は従業員にとって非常にデリケートな出来事です。必要最低限の情報と書類のみを求め、就業規則や社内規程に沿った公平な対応を徹底することが望まれます。
会社の信頼性を高めるためにも、属人的な判断を避け、ルールをもとに運用していきましょう。
まとめ|従業員の離婚に伴う整備は社労士と連携すると安心です
本記事では、従業員が離婚した際に会社側が行う手続きについて、社会保険・税務・扶養・社内制度まで幅広く解説しました。
離婚に伴う手続きは、氏名や住所の変更、配偶者や子どもの扶養削除、年末調整における扶養控除の見直しなど、法令に基づく対応が中心です。加えて、家族手当・住宅手当などの社内制度の適用範囲や、緊急連絡先・福利厚生情報の更新も欠かせません。
一方で、離婚は従業員にとって非常にデリケートな問題です。会社は必要最低限の情報と書類にとどめ、プライバシーに十分配慮しながら進めることが求められます。
こうした複雑な法的要件や制度運用を正確かつ公平に進め、従業員との信頼関係を保つためには、社労士などの専門家と連携が安心です。
従業員が離婚した際の会社側の手続きについて社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めたうえで依頼しましょう。














