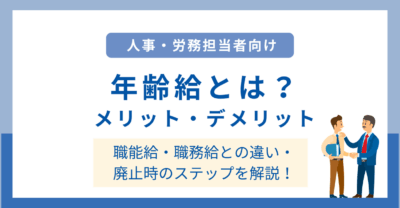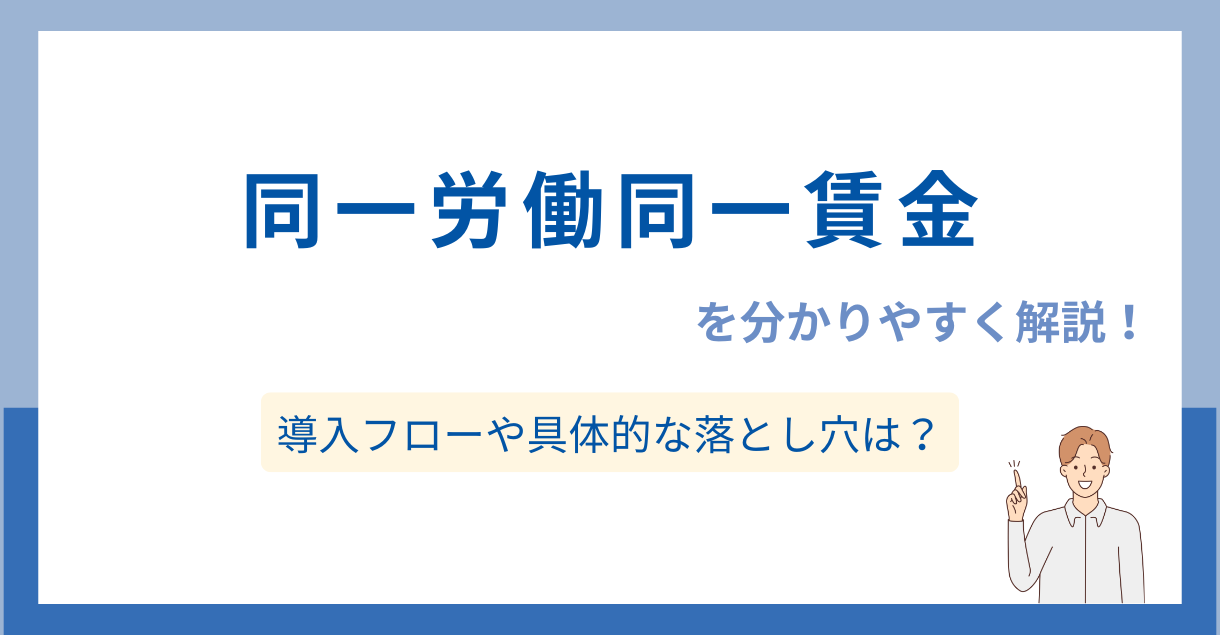
「同一労働同一賃金」の内容を分かりやすく解説!導入フローや具体的な落とし穴は?
2020年4月から「同一労働同一賃金」が施行され、2021年4月からは中小企業にも適用され全面施行となりました。
文字通り「同じ内容の労働や同程度の責任がある人であれば同じ賃金を支払うべきである」という考え方に基づく制度であり、正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差を解消する効果に期待が集まっています。
ただし、「施行から年数が経っているが自社で徹底できているか不安」「何から手をつければよいのか分からないまま放置されている」という企業は少なくありません。
本記事では、同一労働同一賃金の基本的な仕組みを分かりやすく解説していきます。
企業がスムーズに制度を導入するための具体的な導入フローにも触れているので、社員の満足度向上や職場の定着率アップにお役立てください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
同一労働同一賃金とは

厚生労働省では、同一労働同一賃金について「同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」と定義しています。
(※)引用:同一労働同一賃金特集ページ |厚生労働省
ただし、「同一労働同一賃金法」という法律が存在するわけではありません。
同一労働同一賃金はあくまでも考え方や目指す方向性を示す言葉であり、同一労働同一賃金に伴って改正された法律の多くは「パートタイム・有期雇用労働法」にあります。
以下で、同一労働同一賃金の概要を詳しく解説します。
パートタイム・有期雇用労働法上の位置づけ
パートタイム・有期雇用労働法では、同一労働同一賃金について以下2つの義務を企業に課しています。
- 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
- 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
改正により、正社員と非正規社員(パートタイム・契約社員など)が同じ仕事をする場合、賃金・手当・福利厚生などで不合理な差を設けてはいけないと明確に定められました。
例えば、
「正当な理由なく正社員だけに賞与を支給する」
「正当な理由なく正社員だけに住宅手当の支給や特別休暇を付与する」
「同じ仕事なのに非正規社員だけ極端に時給や手当が低い」
などの待遇にすることは禁止されています。
また、正社員と非正規社員(パートタイム・契約社員など)間で待遇差が生じる場合、会社側に説明する義務があります。
「同一労働同一賃金」では待遇差の解消に焦点が当てられがちですが、待遇差が生じる場合には説明することも義務になっているので注意しましょう。
同一労働同一賃金で問われる待遇項目
同一労働同一賃金では、主に以下の待遇について差がないかが問われます。
- 賃金
- 休暇
- 福利厚生制度
- 教育制度
「賃金」には、通勤手当や資格手当を含む各種手当も含まれます。その他、賞与・退職金など不定期に発生する金額や、昇給・昇格なども含むので注意しましょう。
ただし、正社員と非正規社員とで完全に同じ待遇を求めるものではありません。
同一労働同一賃金はあくまでも「不合理な」差を設けてはいけないと規定するものであり、合理的な差までも是正を求めるものではありません。
【合理的な待遇差の一例】
- 求められる役割や仕事内容が異なるときに手当を調整する
- 勤務時間に応じて賃金を按分する
- 将来の期待値や能力・経験・責任、職務や配置の変更範囲に応じた昇給制度を用意する
【不合理な待遇差の一例】
- 正社員は社員食堂を利用できるが、パート・アルバイトは利用できない
- 正社員は研修費用を補助されるが、パート・アルバイトは自費での参加を求める
- 昇進・昇格の機会を正社員にのみ与え、非正規社員は一切対象外とする
つまり、職務内容や配置等の変更の範囲、責任が同程度でありながら「非正規社員」や「有期雇用契約社員」など契約期間の長さや雇用形態の名称の違いだけで待遇差を設けることは差別的取扱いとなり、禁止されています。
一方で、「仕事内容や責任の違いなど合理的な理由がある場合」は合理的な差と考えるとわかりやすくなります。
同一労働同一賃金に関する罰則規定
結論からお伝えすると、同一労働同一賃金に関する罰則規定はありません。
「この条件を満たさない企業には刑事罰や罰金が課せられる」などの規定はなく、同一労働同一賃金対策の義務だけが課せられています。
とはいえ、「罰則がない=対策不要」と考えるのは危険です。
不合理な待遇差について訴えられ、労働審判や裁判に発展した場合、企業は損害賠償や慰謝料を求められる可能性があります。また、公的機関からの指導や企業イメージの悪化が続くなど、企業経営に与えるダメージも少なくありません。
同時に、待遇の不公平が職場に浸透したことが原因で労働者のモチベーション低下や離職が生じることもあります。
「ノウハウのある社員がどんどん離職してしまう」「求人を出しても人が集まらない」などの経営リスクを避けるためにも、同一労働同一賃金対策は急務です。
同一労働同一賃金が必要になった背景

ここでは、同一労働同一賃金が必要になった背景について解説します。
- 非正規雇用労働者数が増大している
- 多様な働き方のニーズが増大した
- 少子高齢化に伴って労働人口が減少した
以下でひとつずつ解説しますので、時代背景も合わせてチェックしてみましょう。
非正規雇用労働者数が増大している

(※)引用:「非正規雇用」の現状と課題
厚生労働省の調査によると、非正規雇用労働者の数は2015年に8年ぶりにプラスに転じ、10年連続で増加しているとわかりました。特に2022年以降は増加の一途を辿っており、正社員と比べて待遇が低いことが問題視されるようになっています。
国は65歳までの雇用確保措置を企業に義務付けており、60歳で定年したあとは見直された賃金で働く再雇用で働く人が増えました。再雇用者は、高年齢継続雇用として低い賃金で働くことが多いことも関係しています。
非正規社員の待遇改善は、人材確保・定着の観点からも重要です。「同一労働同一賃金」により可能な限り待遇差をなくすことができれば、労働者間の公平性を確保しやすくなります。
働き方のニーズが多様化した
近年、働き方のニーズが多様化し、ニーズに合った雇用形態やワークライフバランスの取り方に注目が集まるようになりました。
| 働き方のニーズ | 対応する雇用形態 | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| フルタイムで安定的に働きたい | 正社員 | 無期契約・フルタイム勤務。昇給・賞与・退職金などが用意されていることが多い |
| 短時間で働きたい 家事・育児・介護を重視したい |
パートタイム アルバイト |
勤務時間が短く、フレキシブルに勤務可能 |
| 契約期間を限定して働きたい プロジェクト単位で働きたい |
有期契約社員(契約社員) | 契約期間が決まっている。特定の業務やスキルに特化 |
| 転勤をしたくないが正社員として働きたい 家事・育児・介護と仕事を両立させたい |
多様な正社員 | 正社員でありながら配置転換や転勤、仕事内容や勤務時間などの範囲が限定されている |
| 専門スキルを活かして自身の裁量できたい | フリーランス・業務委託 | 雇用契約ではなく業務の受注という形になる。業務量・成果に応じて報酬が支払われる |
これまでオフィス出勤型の正社員が「当たり前」とされてきましたが、近年は多様な働き方を取り入れる人が増え、正社員以外の選択肢も増えています。スポットアルバイトや副業などのニュースが増えていることからも、時代の移り変わりを感じられるでしょう。
働き方が多様化するからこそ、待遇や労働条件などを見直しながら不合理な差が無いよう整備する必要があります。
同一労働同一賃金は、柔軟な働き方を容認しつつ、待遇の公平性を確保する仕組みとして重要です。
少子高齢化に伴って労働人口が減少した
急速に進行する少子高齢化に伴い、労働人口が減少していることも課題となっています。
少子化により若者の数が減り、同時に高齢者の定年退職者が増えたことで、企業の人材確保が難しくなりました。慢性的な人手不足に悩む企業が多く、労働力不足を補うためパート・アルバイト・契約社員などを雇うケースも増えています。
正社員と非正規社員で待遇差が大きいと優秀な人材が定着せず、労働力不足がさらに深刻化するので注意しましょう。
「同一労働同一賃金」により、仕事内容・責任が同じ場合は雇用形態に関わらず待遇を公平にできれば、人材確保もしやすくなる可能性があります。国全体で働き方改革が進められている今だからこそ、同一労働同一賃金を人材獲得のチャンスにしていくことが求められます。
同一労働同一賃金を開始する際によくある落とし穴

同一労働同一賃金を開始する際には、以下のような「落とし穴」があるので注意が必要です。
- コストだけで施策内容を判断する
- 従業員に十分な説明をせずに導入する
- 曖昧な改善計画で進める
- 評価・昇給・昇格の反映が不十分
思わぬトラブルやミスマッチを防ぐためにも、これらを避けて施策を打ち出すことが大切です。
コストだけで施策内容を判断する
同一労働同一賃金は、これまでの雇用条件や待遇の見直しが発生するため少なからずコストが発生します。
コストをなるべく避けたい気持ちはどの企業にも共通するものですが、コストだけで施策内容を判断するのは避けましょう。金銭的な負担を理由に最低限の改善しか行わないと、同一労働同一賃金の制度が形骸化し、企業の法令遵守や人材戦略上の目的を達成できません。
また、同じ業務をしているにもかかわらず待遇差を残すと、不公平感が生まれます。
従業員のモチベーション低下や信頼関係の悪化が、結果的に生産性の低下や離職率増加という形で企業に跳ね返ることも珍しくありません。従業員の納得感・モチベーション・定着率・採用力など、非金銭的要素の価値も含めて意思決定するのがポイントです。
従業員に十分な説明をせずに導入する
同一労働同一賃金を導入する際、制度や待遇の変更内容を従業員に十分説明せずに運用を開始するのは危険です。導入のスピードを優先するあまり、説明不足になっていると不満や不感を招く原因になります。
具体的には、以下のような不満が出やすくなるので注意しましょう。
- 「なぜ自分だけ差があるのか分からない」
同じ業務をしているのに給与や手当、福利厚生に差がある理由が説明されていない場合 - 「会社は公平に評価していないのではないか」
昇給・昇格や評価制度の運用が不透明で、努力や成果が正当に反映されていないと感じる - 「正社員だけ優遇されている」
賞与や研修、福利厚生などで正社員と非正規社員の差が大きく、納得感が得られない - 「自分の働きが軽視されている」
同じ業務量や責任を負っているにもかかわらず待遇差が残ることで、自分の貢献が認められていないと感じる
説明不足による不満は、給与だけでなく信頼感やモチベーションに直結します。導入前に明確な説明の場を設けることと、質問対応もすることが成功のカギとなります。
曖昧な改善計画で進める
不合理な待遇差を是正する改善計画を具体的に定めず、漠然とした内容のまま進めてしまうことも少なくありません。企業側に改善の意思はあるとしても、従業員にとっては「何がどう変わるのか分からない」という状態になりやすく、制度導入の目的が十分に達成されません。
特に、以下のような問題が発生しやすくなります。
- 従業員の納得感が得られない
「いつどの差を縮めるのか」「どの程度改善されるのか」が不明確なため、従業員は公平性を実感できません。 - 制度が形骸化するリスク
曖昧な計画では改善の優先順位や実施時期が曖昧になり、結果的に改善がほとんど進まないケースがあります。 - 法令リスクの増加
同一労働同一賃金は義務規定であるため、改善計画が具体的でないと、後に「不合理な待遇差が残っている」と指摘される可能性があります。
対象者の絞り込みや改善内容のリストアップなど、まずはひとつずつ丁寧に進めましょう。全社員に一度に適用できない場合でも、ステップごとに改善内容を明示するなど工夫して納得感を与えることが大切です。
評価・昇給・昇格の反映が不十分
給与や手当の改善だけに注力し、評価制度・昇給・昇格の運用が正社員中心のままになっている状態だといずれ制度運用に問題が生じます。評価・昇給・昇格が反映されないと公平性が損なわれ、制度導入の本来の目的が達成できません。
- 従業員の不公平感が増す
成果や能力に応じた昇給や昇格が非正規社員に適用されないと、「自分の働きが正当に評価されていない」と感じやすい - モチベーション低下
努力や成果が報われない状況では、業務への意欲や責任感が低下し、生産性の低下につながる - 優秀な人材の流出リスク
評価・昇給が反映されない場合、能力の高い非正規社員がより条件の良い企業へ転職する可能性がある - 制度の形骸化
給与差の是正だけで評価制度を改善しないと、同一労働同一賃金の導入が表面的な対応に留まり、従業員の信頼を得られない
同一労働同一賃金では、給与だけでなく評価制度も含めた包括的な公平性が求められます。理由が説明できる評価・昇給・昇格の仕組みを設計して、従業員の納得感・定着率・モチベーション向上につなげていきましょう。
同一労働同一賃金の導入フロー

同一労働同一賃金が自社で適切に運用できているか点検する際は、以下のステップで進めましょう。
- 現行の雇用条件や待遇をリストアップする
- 不合理な待遇差が起きている部分を可視化する
- 待遇の違いについて理由を説明できるか検討する
- 待遇差の改善に向けて案を作る
- 改善・効果測定
以下で詳しく解説します。
1.現行の雇用条件や待遇をリストアップする
まずは自社における現行の雇用条件・待遇を正確にリストアップしましょう。
正社員と非正規社員の待遇差を把握するための基礎となる部分であり、最新の情報でリストアップすることが欠かせません。就業規則・賃金規程・労働契約書・過去の給与台帳などを参照するのが近道です。
具体的には、以下の情報を集めると比較しやすくなります。
- 給与体系
- 手当・賞与・退職金の有無
- 勤務時間・シフト
- 福利厚生(休暇制度、施設利用など)
- 昇給・昇格制度
- 具体的な業務内容
特に注意したいのは、単に給与額をリストアップするだけでなく、業務内容や責任範囲に応じた手当・賞与・昇給の適用状況を確認する点にあります。
同じ「営業」をしている人員でも、支店全体の売上や業績を管理しながら営業活動をするマネージャーと、テレアポ営業のみを行うアルバイトとでは当然責任の範囲も異なります。業務内容だけを見るとどちらも「営業」ですが、責任範囲や求められる役割が違えば同一労働同一賃金の対象にはなりません。
2.不合理な待遇差が起きている部分を可視化する
現行の雇用条件や待遇をリストアップした後は、どの部分で不合理な待遇差が発生しているかを明確にする作業に移ります。待遇差が不合理であるか否かは最終的には裁判において判断されますが、まずは事業主が法の趣旨に沿って判断することが必要です。
正社員と非正規社員が同じ仕事や責任を負っているにもかかわらず、給与・手当・福利厚生・賞与などの待遇に差がある箇所を洗い出しましょう。
例えば、以下のように整理するとわかりやすくなります。
| 項目 | 正社員 | 非正規社員 | 不合理か合理か | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 基本給 | 月額30万円 | 時給1,500円 (フルタイム換算27万円) |
合理的 | 勤務時間が異なるため差は合理的 |
| 賞与 | 年2回支給 (基本給1か月分) |
支給なし | 不合理 | 同じ業務や責任が同程度であれば、差は不合理 |
| 退職金 | 支給あり | 支給なし | 不合理 | 勤続年数に応じた退職金は、同一業務なら差が問題となる可能性 |
| 通勤手当 | 上限3万円/月 | 上限2万円/月 | 不合理 | 差額の根拠が明確でない場合、不合理扱い |
| 研修参加 | 正社員対象 | 非正規社員対象外 | 不合理 | 業務に必要な研修なら非正規社員も参加可能にすべき |
| 福利厚生 (健康診断) |
年1回実施 | 年1回実施 | 合理的 | 同一内容であれば差はなし |
「不合理か合理か」の判断は、仕事内容・責任・勤務時間の差を考慮するのが近道です。上記表は一例ですが可視化できる表を作ることで、後の改善案作成や従業員への説明がスムーズになるのでご活用ください。
3.待遇の違いについて理由を説明できるか検討する
待遇差が可視化できたら、次に該当する待遇差について合理的な説明ができるかを検討します。
合理的な理由が示せない差は、後のトラブルや裁判リスクにつながる可能性があるので注意しましょう。また、従業員にも説明できるよう書面や規程で理由を整理しておくことが望ましいとされています。
【特にチェックしたいポイント】
- 業務内容・責任の程度:職務内容が同じであっても職務内容や配置の変更範囲はどうか、責任の程度はどうかなどを確認。
- 勤務時間・勤務形態の違い:フルタイム正社員と短時間勤務のパートで給与や手当で差をつける場合、時間換算や役割に基づく合理性を確認。
- 経験・資格・スキルの違い:同じ職務でも必要な資格や経験年数の差によって待遇差を設ける場合、その基準が明確かどうか。
同一労働同一賃金では、業務内容や責任が異なれば待遇差があっても合理的な差とされています。
4.待遇差の改善に向けて案を作る
不合理な待遇差が可視化されたら、次に具体的な改善案を作成します。従業員に納得してもらえる形で待遇差を是正する方法を検討し、実施計画を策定しましょう。
改善案の例として、以下が挙げられます。
| 改善対象 | 現状の差 | 改善案 | コメント |
|---|---|---|---|
| 基本給 | 正社員:月額30万円 非正規社員:フルタイム換算27万円 |
非正規社員の基本給を28.5万円に引き上げ | 時間換算や業務内容に基づき、合理的な差に調整 |
| 賞与 | 正社員:年2回1か月分 非正規社員:支給なし |
非正規社員も年1回0.5か月分支給 | 業務内容が同等の場合、部分的支給で公平性を確保 |
| 退職金 | 正社員:支給あり 非正規社員:支給なし |
勤続3年以上の非正規社員にも一部支給 | 勤続年数や契約期間に応じて段階的に適用 |
| 研修参加 | 正社員のみ参加可能 | 必要な研修は非正規社員も参加可能にする | スキルアップと業務能力向上の観点で公平性確保 |
| 健康診断 | 正社員:年1回 非正規社員:対象外 |
非正規社員も年1回健康診断を実施 | 法令対応と従業員満足度向上のため実施 |
| 通勤手当 | 正社員:上限3万円/月 非正規社員:上限2万円/月 |
非正規社員も上限3万円に統一 | 差額の合理的理由がない場合、統一することで納得感向上 |
改善案を作成する際は、コスト面・社内制度との整合性や従業員への影響を総合的に考慮する必要があります。改善内容は明文化して社内で共有し、従業員に説明できる状態にして反応を見るなど、慎重に進めましょう。
5.改善・効果測定
同一労働同一賃金は不合理な待遇差をなくす目的で導入する制度であり、改善後の効果測定をする必要があります。制度導入後、「実際に改善が効果的に機能しているか」の視点で自社を見直すのがおすすめです。
代表的な効果測定方法として、以下が挙げられます。
| 項目 | 測定内容 | 方法 | 目的・ポイント |
|---|---|---|---|
| 賃金・手当の運用状況 | 改善後の給与・手当が正しく支給されているか | 給与台帳や支給記録の確認 | 制度が正確に運用されているかを確認 |
| 福利厚生・研修制度の適用 | 非正規社員も対象の福利厚生・研修が実施されているか | 参加記録・利用状況の確認 | 公平性が担保されているかをチェック |
| 従業員満足度 | 改善後の待遇に対する納得感 | アンケート、ヒアリング | 従業員の理解度・納得感を把握 |
| 離職率・定着率 | 制度導入後の離職者数や定着率の変化 | 人事データ分析 | 人材定着への影響を定量的に評価 |
| 採用応募数・採用効果 | 制度導入後の応募数や選考通過率 | 採用管理システムのデータ分析 | 採用力向上への効果を測定 |
| 評価・昇給・昇格の反映 | 非正規社員も能力や成果に応じて評価されているか | 評価シート・昇給記録の確認 | 公平な評価制度が運用されているか確認 |
いわゆる「やった気になっただけの施策」「同一労働同一賃金の形骸化」を防ぐため、定期的に効果測定することも欠かせません。制度運用の透明性と従業員の納得感を高め、反感や不信感を持たれないようにする工夫も必要です。
また、労働環境や法律が変わったときは都度待遇も見直し、時代に合わせてアップデートしていきましょう。
まとめ
同一労働同一賃金とは、正社員・非正規社員などの雇用形態にかかわらず、同じ仕事をしている場合は同等の待遇を受けるための制度です。
法令遵守だけを目的にするのではなく、従業員の納得感や公平性を高め、モチベーション向上や人材定着を促進しながら進めましょう。
また、同一労働同一賃金は「一度導入すれば終わり」という制度ではありません。現状分析→改善策策定→実施→効果測定→改善のサイクルを回しながら、企業と従業員双方にとってメリットのある制度にすることがポイントです。
解雇の要件について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。