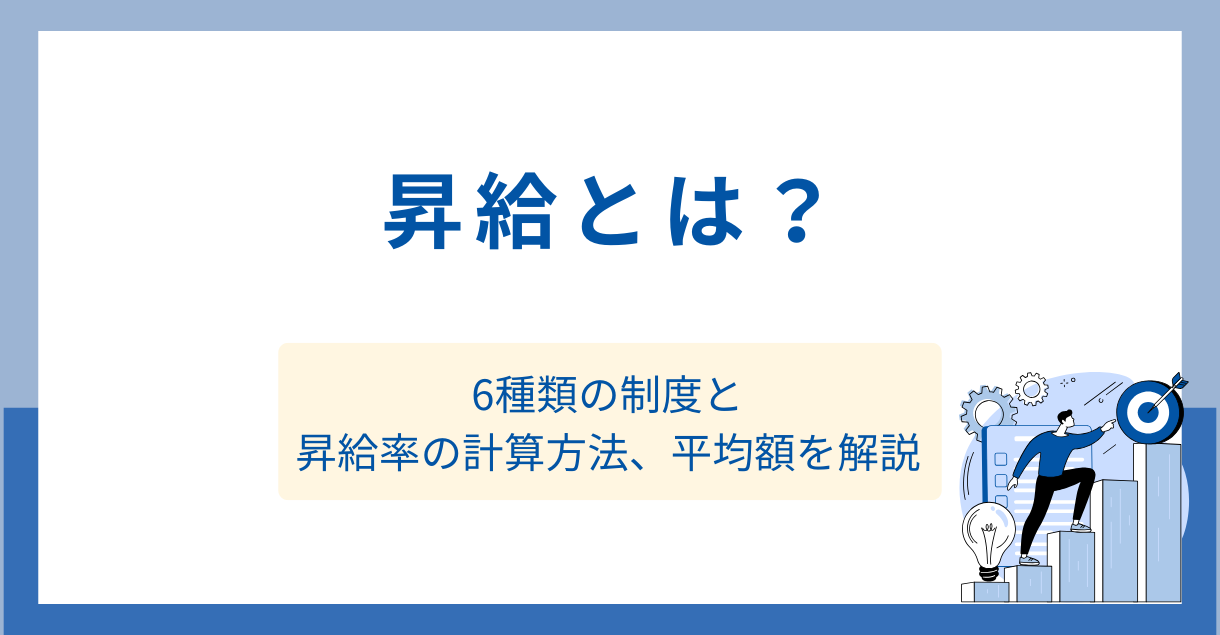
昇給とは?6種類の制度と昇給率の計算方法、平均額を解説
「昇給」は、企業にとって従業員のモチベーション向上や人材確保のために欠かせない制度であり、従業員にとってもキャリア形成や生活の安定に直結する重要な仕組みです。昇給制度を効果的に活用するためには、企業の目的に沿った適切な設計と運用、定期的な見直しが大切です。
本記事では、昇給制度の種類や目的、課題に加え、昇給率の計算方法や昇給平均額について解説します。最新の動向を踏まえ、自社の昇給制度を見直す際の参考にしてください。
昇給制度について社労士に相談する
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
昇給とは、勤続年数や業績に応じた基本給の引き上げのこと
昇給とは、従業員の勤続年数や個人・企業の業績に応じて、ボーナスを除いた基本給が引き上げられる制度です。企業の就業規則にもとづいて行われるため、その条件は企業によって異なります。中には、就業規則に昇給がない旨を明記し、昇給を実施していない企業もあります。
一方で、日本では毎年定期的に昇給する「定期昇給」を導入している企業が少なくありません。厚生労働省の「令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、一般職に対して「定期昇給制度あり」と答えた企業の割合は86.3%、実際に定期昇給を「行った・行う」と答えた企業の割合は83.4%に上ります。
※厚生労働省「令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査_概況」
昇給が行われるのはいつ?
昇給の時期には、法律で定められた決まりはありません。一般的には、年に1度なら4月、年に2度なら4月と10月に昇給を実施する企業が多いでしょう。
ただし、昇給は毎年必ず行われるとは限りません。企業によっては、業績が良い年だけ昇給を行うなど、実施のタイミングが異なります。
昇給制度の種類
昇給制度は、実施のタイミングや基準によって大きく6種類に分けられます。ここからはそれぞれの一般的な概要について解説します。
定期昇給
定期昇給は、企業が定めたタイミングで定期的に給与が上がる制度です。日本企業における主流の昇給制度であり、多くの場合、年1回または2回実施されます。
企業によっては、毎年必ず定期昇給を行うわけではなく、業績に応じて実施するか否かを決めることもあります。また、従業員が一定の年齢に到達すると定期昇給を停止する企業も少なくありません。
臨時昇給
臨時昇給は、時期や対象者を定めず、臨時で昇給を行うものです。一般的には、企業の業績が好調なときなどに実施します。定期昇給のように時期が定められているわけではなく、企業の判断によって柔軟に決定されるのが特徴です。
自動昇給
自動昇給は、特定の基準が満たされると、自動的に給与が上がる制度です。実績やスキルに関係なく、基準を満たした全従業員が一律に対象となります。昇給の基準は、勤続年数や年齢などです。定期昇給の一環として、自動昇給の仕組みを取り入れている企業もあります。
考課昇給
考課昇給は、仕事の実績に対する評価を基準に昇給を行う制度で、査定昇給ともいいます。定期昇給と同じタイミングで、考課昇給の査定が行われる場合もあります。上司からの評価や目標の達成度、顧客の満足度などを総合的に判断して行われるため、査定には時間や手間を要することが少なくありません。
普通昇給
普通昇給は、技能や職務遂行能力の向上を評価し、昇給を行う制度です。資格取得や社内研修の修了、社内試験の合格などを理由とするケースもあります。スキルアップに関して企業が設定した基準をクリアすれば、昇給が決まります。
特別昇給
特別昇給は、特殊な職務への従事や大きな功績など、特別な理由にもとづいて昇給を行う制度です。通常の普通昇給では対応できないケースに適用され、社内表彰や重要プロジェクトへの貢献などが理由となることもあります。企業の裁量による部分が大きく、特定の従業員に対して個別に実施されます。
定期昇給とベースアップの違い
定期昇給と混同されやすい制度として「ベースアップ(ベア)」という仕組みがあります。ベースアップとは、従業員全体の給与の基本額(ベース)を一律に引き上げる制度で、企業の賃金水準の底上げを目的としています。一方、定期昇給は、企業の規定にもとづき、勤続年数や評価などに応じて個人の給与を上げる仕組みです。つまり、定期昇給とベースアップの違いは、昇給が個人ごとに行われるか、企業全体で実施されるかという点です。
ベースアップの実施は、主に労働組合と雇用主の賃上げ交渉によって決定されます。特に、大手企業の労働組合を中心に毎年2~3月に行われる「春季生活闘争(春闘)」の結果、国の経済状況や物価上昇を反映して実施されるケースが多く見られます。
近年、労働組合に加入する労働者の割合は減少傾向にありますが、春闘で妥結した賃上げ額が社会に与える影響は依然として大きく、それを参考に賃金改訂を行う企業が少なくありません。ただし、一度引き上げた給与を下げるのは難しいため、多くの企業はベースアップの実施に慎重な姿勢をとっています。
昇給と昇格・昇進の違い
昇給と似た言葉として「昇格」や「昇進」がありますが、これらはそれぞれ意味が異なります。昇給は給与が上がることを指すのに対して、昇格は社内での等級が上がること、昇進は役職が上がることを指します。
昇給と昇格・昇進は必ずしも連動しませんが、昇格や昇進に伴って昇給することが一般的です。
昇給制度の目的
企業が昇給制度を導入する主な目的は、従業員の成長を促し、働きがいのある職場環境を維持することです。また、昇給制度は、企業から従業員に向けた意思表示の手段ともいえます。昇給制度を通して、従業員の幸福を実現し、安定した生活を支えたいというメッセージを伝える役割も担っているのです。ここからは、企業が昇給制度を導入する目的について紹介します。
勤続年数やスキル向上に伴う給与調整
昇給制度は、勤続年数や業務遂行スキルが上がった従業員に対して、それに見合った給与を支払う調整機能を果たします。個人の成長を適切に報酬に反映させることで、従業員のスキルアップを促し、企業全体の生産性向上にもつなげられます。
従業員のモチベーション向上
昇給制度の目的として、従業員のモチベーション向上も挙げられます。考課昇給や特別昇給など、個人の努力や成果を評価する制度があれば、従業員がさらに意欲的に働けるようになるでしょう。その結果、人材の定着や獲得につながることが期待できます。
長期的なキャリア形成の促進
従業員の長期的なキャリア形成を促進することも、昇給制度の目的といえます。昇給がスキル向上や業績貢献の評価と連動することで、従業員は自身の成長の方向性を明確にし、企業におけるキャリアプランを具体的に描きやすくなります。
従業員の生活水準の維持
従業員の生活水準の維持も、昇給制度の重要な目的です。物価上昇やライフステージの変化に応じて昇給を行うことで、従業員は結婚や子育て、住宅取得などのライフイベントに対応しつつ、経済的な安定を確保できます。
企業の成長性や安定性の提示
昇給制度には、計画的に給与を増額させることで企業の成長性や安定性を示し、従業員に安心感を与える役割もあります。さらに、昇給を通じて従業員の労働意欲や定着率が向上することで、組織運営の安定にも寄与します。結果的に求職者や取引先にも企業の健全な経営状況を印象づけられるでしょう。
人件費の計画的な管理
昇給制度を導入することで、人件費の増加を事前に見込み、計画的な資金管理が可能となります。特に定期昇給を採用している企業では、毎年の昇給額を予測しながら事業計画を立てることができるため、無理のないコスト管理につなげられます。
昇給制度の課題
昇給制度は、その設計に問題があると、想定した効果を得られない場合もあります。昇給制度を効果的に活用するためには、適切な対策や定期的な見直しが必要です。ここからは、昇給制度の課題を解説します。
評価基準の明確性や透明性の欠如
昇給制度の評価基準が明確でなく、プロセスが不透明な場合、従業員の不満が生じる原因になります。評価基準は明確かつ公平に設定し、制度の導入後も定期的に見直すことが重要です。また、評価の一貫性を保つため、評価基準や運用方法を従業員に周知し、評価者には適切な研修を実施することで、不公平な運用を防ぐことができます。
職種や業績に応じた柔軟性の不足
昇給制度が職種や役割、業績の違いを考慮せず一律に運用されていると、個人の活躍に応じた昇給が難しくなり、従業員が不公平感を抱きやすくなります。例えば、職種に応じて昇給制度を柔軟に設計したり、業績に応じて昇給のタイミングを調整できる仕組みを導入したりするなど、運用方法の検討が必要です。
インフレや物価上昇など市場動向への対応
昇給制度がインフレや物価上昇に対応していない場合、従業員の実質的な給与水準が低下する可能性もあります。制度導入後も定期的に昇給制度の見直しを行い、インフレ率や市場の賃金水準も考慮しながら、昇給率を適切に調整することが重要です。
能力開発やスキル向上との連携不足
昇給制度が、能力開発やスキル向上と結びついていない場合、どのように成長すれば評価につながるのかが不明瞭となり、従業員の意欲低下を招く可能性があります。
そのため、昇給制度は能力開発やスキル評価と明確に連動させることが重要です。例えば、資格取得や研修修了を昇給要件に組み込んだり、専門スキルの向上などを評価する昇給モデルを導入したりすることが求められます。また、年功序列と成果主義のバランスを見直し、個人の成長が正当に評価される仕組みを整備することも大切な取り組みです。
自社の昇給制度の課題について社労士に相談する
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
昇給額と昇給率の計算方法
ここからは、昇給額や昇給率の計算方法について見ていきましょう。まず「昇給額」は以下の計算式で求めます。
<昇給額の計算式>
昇給額=昇給後の給与額-昇給前の給与額
さらに、昇給前の給与と比較して昇給後の給与が何パーセントアップしたのかを示したものを「昇給率」といいます。昇給率の計算式は以下のとおりです。
<昇給率の計算式>
昇給率(%)=昇給額÷昇給前の給与額×100
例えば、昇給前の基本給が30万円で、昇給後の基本給が30万9,000円の場合、昇給率は9,000円÷30万円×100%=3%となります。
企業規模別の昇給の平均額
昇給額や昇給率は企業によって異なりますが、近年日本の昇給の平均額は増加傾向にあります。ここからは、日本経済団体連合会が公表する、ベースアップと定期昇給を含めた賃上げのデータを見てみましょう。
中小企業における昇給の平均額
中小企業の昇給の平均額は、企業規模によって差が見られます。まず、2024年の中小企業全体の総平均妥結額(ベースアップと定期昇給を足した賃上げ額)は10,712円、前年に対するアップ率(賃上げ率)は+4.01%でした。2023年の8,012円、+3.00%に比べて大幅に増額しています。
企業規模別では以下のとおりで、企業規模が大きいほどアップ率も大きくなっています。
■ 2024年 中小企業の妥結額・アップ率
| 企業規模 | 妥結額 | アップ率 |
|---|---|---|
| 従業員100人未満の企業 | 9,188円 | 3.59% |
| 従業員100~300人未満の企業 | 9,778円 | 3.67% |
| 従業員300~500人未満の企業 | 11,974円 | 4.43% |
※(一社)日本経済団体連合会「2024年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(加重平均)」
大企業における昇給の平均額
一方、大企業では、2024年の全業種の総平均妥結額は19,210円、アップ率は+5.58%です。2023年の総平均妥結額は13,362円、アップ率は+3.99%と、こちらも前年に比べて大きな増額です。アップ率が+5%を超えたのは1991年以来33年ぶりで、これほど大幅に上昇した背景には、物価高や人手不足の深刻化などがあります。
2024年の業種別データを見ると、以下のとおりで、製造業のアップ率の方がやや高くなっています。
■ 2024年 大企業の妥結額・アップ率
| 業種 | 妥結額 | アップ率 |
|---|---|---|
| 製造業 | 19,636円 | 5.79% |
| 非製造業 | 17,969円 | 5.01% |
※(一社)日本経済団体連合会「2024年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果(加重平均)」
2025年の昇給に関する動向は?
上記のとおり名目賃金は上昇しているものの、物価高の影響で実質賃金は減少しており、2025年も賃上げの要求・実施は続くと予想されます。
実際、日本労働組合総連合会はすでに、2025年春闘における賃上げ要求の方針を固めています。具体的には、ベースアップ相当分として3%以上、定期昇給分を含めて5%以上、中小企業ではさらに1%上乗せして6%以上の賃上げを要求する予定です。
企業側も賃上げに前向きで、経済同友会の「景気定点観測アンケート調査結果」では、経営者の68.3%が2025年に賃上げの実施意向を示しています。さらに現在、政府も「賃上げ促進税制」により、給与の増額分の最大35%~45%を税額控除対象とする制度を設け、企業の賃上げを支援しています。
また、最低賃金の引き上げも進む見込みです。政府は、2020年代に全国平均1,500円を最低賃金の目標とする考えを示しています。最低賃金の上昇により、パート・アルバイトの賃金が引き上げられることで、正社員の給与が引き上げられる可能性もあるでしょう。
ただし、正社員の給与が据え置かれ、パート・アルバイトの時給のみ引き上げられた場合、正社員と非正規社員の賃金格差が縮小します。その結果、正社員の給与面での優位性が小さくなり、「責任の重い仕事を担っていても、給与の差がほとんどない」と不満を感じる人が増えるおそれもあります。
こうしたモチベーション低下を防ぐため、企業は正社員のスキルアップ支援や福利厚生の充実、柔軟な働き方の導入を進め、成長機会を増やしながら、働きがいを高めることが重要です。
※経済同友会「2024年9月(第150回)景気定点観測アンケート調査結果」(2024年10月10日)
※経済産業省「賃上げ促進税制」
時代の変化に応じて見直される昇給制度
厚生労働省の「令和5年版 労働経済の分析」では、賃金を決める要素として、従来の「年齢・勤続給」の占める割合を減らし、「成果・業績給」や「役割・職責給」を増やす企業が多いことが指摘されています。近年、日本の昇給制度においては、従来の終身雇用・年功序列型の制度の見直しが進んでおり、今後もこの傾向は続くと予測されます。
こうした動向を踏まえ、まずは自社の昇給制度の方針を明確にすることが大切です。その上で、その方針をどのように制度化し、どのように継続運用するのかを検討しましょう。
※厚生労働省「令和5年版 労働経済の分析 第3章 持続的な賃上げに向けて」
昇給制度の見直しは人事労務のプロに相談を
昇給は、従業員のモチベーションの向上や人材の定着・獲得に直結する重要な制度です。適切な効果を得るには、公平かつ一貫性を保ちつつ、柔軟に運用できる制度設計が求められます。
しかし、適切な昇給制度の設計には、評価基準の明確化や企業の成長戦略との整合性など、さまざまな要素を考慮する必要があります。こうした課題に対応するためには、人事労務の専門家である社会保険労務士(社労士)のサポートを活用するのが有効です。社労士は、企業の課題やニーズをヒアリングし、それに応じた昇給制度の設計や運用について適切なアドバイスができます。企業と従業員の双方にとって有益な昇給制度の構築につながるでしょう。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。














