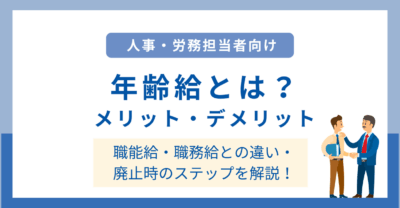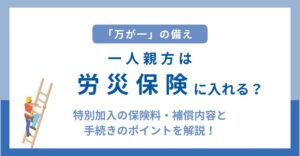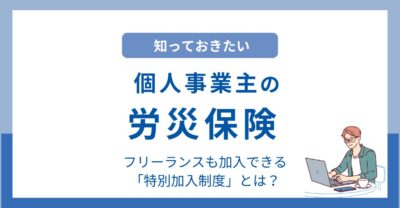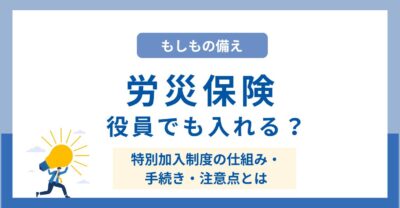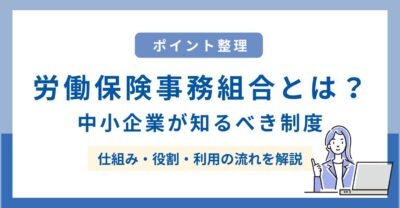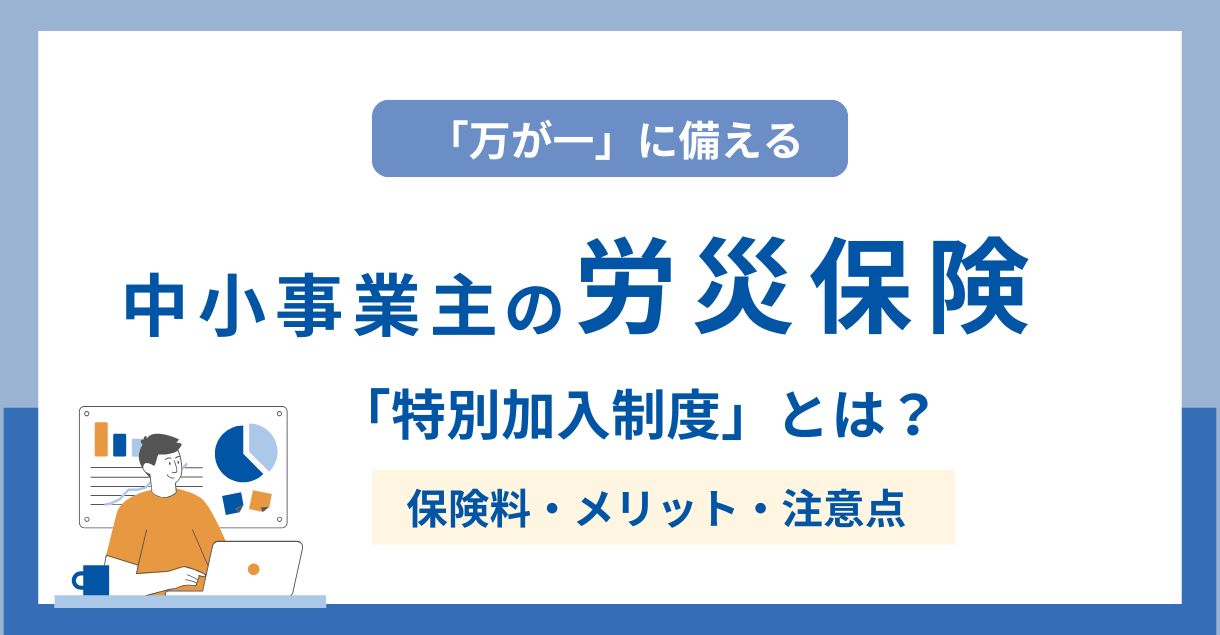
中小事業主も入れる労災保険「特別加入制度」とは?保険料・メリット・注意点まで完全解説
労災保険は、原則として労働者を対象とした制度であり、業務中や通勤中にケガの事故にあった場合等に補償を受けることができます。
その一方で、労働者ではない立場の方、たとえば事業主自身や一人親方、家族従業者、海外派遣者などは、通常この補償の対象外とされています。
しかし、中小企業では、事業主自身が労働者と同様に作業を行うケースも多く、事故やケガのリスクは決して他人事ではありません。
こうした状況に備える手段として設けられているのが、「労災保険の特別加入制度」です。
この制度は、一定の要件を満たす方が任意で労災保険に加入し、業務災害や通勤災害に対する補償を受けられる仕組みです。
本記事では、その中でも「中小事業主の労災保険特別加入」について、制度の概要、対象要件、保険料の計算方法、メリット、注意点、申請の流れまでをわかりやすく解説しています。
「保険料はいくらになるのか」「手続きの流れや注意点は?」といった疑問をお持ちの方にも役立つ内容です。
ぜひ最後までご覧いただき、万が一に備えた制度としての活用をご検討ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
中小事業主が労災保険に加入する方法「特別加入制度」とは?

従業員の労災リスクには注意を払っていても、「自分は事業主だから労災保険の対象外」と思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、中小企業では、現場での作業や営業活動など事業主自身が直接業務に関わるケースも珍しくありません。そのため、事業主自身も労災リスクと無縁とはいえないのが実情です。
そうした背景を踏まえて設けられているのが、「労災保険の特別加入制度」です。
この制度を利用するには、一定の要件を満たす必要があります。特別加入できる中小事業主の条件について、次章で詳しく解説します。
「一人親方」の労災保険については、こちらの記事をご覧ください。
(関連記事:一人親方は労災保険に入れる?特別加入制度と保険料・補償内容をわかりやすく解説)
「個人事業主/フリーランス」の労災保険については、こちらの記事で解説しています。
(関連記事:個人事業主の労災保険|フリーランスも加入できる特別加入制度をやさしく解説)
中小事業主が労災保険の特別加入対象になるための要件とは?
中小事業主が労災保険の特別加入制度を利用するには、厚生労働省が定める「中小事業主等」に該当していることが前提です。
以下、中小事業主における労災保険の特別加入者の範囲や特別加入の要件を詳しく解説します。
特別加入の対象となる中小事業主の基準
「中小事業主等」とは、次のいずれかに該当する方を指します。
| 1.下の表1に定める数の労働者を常時使用している事業主(法人の場合は代表者)
2.上記1の事業主の事業に従事している労働者以外の方(例:家族従事者、法人役員など) |
表1.中小事業主等と認められる企業規模
|
業種 |
労働者数 |
| 金融業
保険業 不動産業 小売業 |
50人以下 |
| 卸売業
サービス業 |
100人以下 |
| その他の業種(建設業・製造業など) |
300人以下 |
出典:労災保険特別加入制度のしおり|P3.表1_中小事業主等と認められる企業規模|労働基準監督署
※労働者を通年雇用しない場合でも、1年間に100日以上労働者を使用している場合は「常時使用している」と見なされます。
※1つの企業に複数の支店や工場などがある場合には、それぞれで常時使用される労働者を合計した数で考えます。
上記2の「事業に従事している労働者以外の方」については、事業主本人だけでなく、その企業で働く家族や役員なども条件を満たせば労災保険の補償対象となる仕組みです。
繁忙期のみパートやアルバイトを雇用しているケースでも該当する可能性があります。判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署に確認すると安心です。
労災保険の特別加入に必要な2つの要件
中小事業主等が初めて特別加入をする場合、一般的には次の2つの要件を満たしている必要があります。
| 1.雇用する労働者について保険関係が成立していること
2.労働保険の事務処理を労働保険組合に委託していること |
出典:労災保険特別加入制度のしおり|P4.特別加入の手続き|労働基準監督署
1の「保険関係が成立していること」については、労働者を1人でも雇用している場合、法律上、当然に労災保険の保険関係が成立します。特別加入をするには、この保険関係がすでに成立していることが必要です。
また、2の「労働保険事務組合」とは、中小事業主等に代わって、労働保険に関する事務手続きを行うことを厚生労働大臣から認められている団体です。
中小事業主等の特別加入の申請は、労働保険事務組合を通じて行うことが義務づけられています。
中小事業主等の特別加入にかかる保険料の計算方法と年間保険料の目安

中小事業主等の労災保険特別加入にかかる保険料は、業種や設定する給付基礎日額によって大きく変動します。
この章では、労災保険特別加入にかかる保険料の基本的な計算方法や業種別の保険料率、さらに年間保険料の目安について、具体例を交えながら解説します。
中小事業主等の特別加入にかかる保険料の基本的な計算方法
中小事業主等の特別加入にかかる保険料は、以下の計算式によって算出されます。
| 保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)×業種別保険料率=年間保険料 |
給付基礎日額は、3,500円から25,000円の範囲(1,000~2,000円刻み、16段階)で選択可能です。
■特別加入保険料給付基礎日額一覧
| 給付基礎日額(円) | 保険料 算定基礎額(円) |
給付基礎日額 (円) |
保険料 算定基礎額(円) |
| 25,000 | 9,125,000 | 10,000 | 3,650,000 |
| 24,000 | 8,760,000 | 9,000 | 3,285,000 |
| 22,000 | 8,030,000 | 8,000 | 2,920,000 |
| 20,000 | 7,300,000 | 7,000 | 2,555,000 |
| 18,000 | 6,570,000 | 6,000 | 2,190,000 |
| 16,000 | 5,840,000 | 5,000 | 1,825,000 |
| 14,000 | 5,110,000 | 4,000 | 1,460,000 |
| 12,000 | 4,380,000 | 3,500 | 1,277,500 |
出典:労災保険特別加入制度のしおり|P8.表3給付基礎日額・保険料一覧表|労働基準監督署
給付基礎日額が高いほど、保険料は高くなりますが、万が一の際の補償額も増加します。
加えて、年間保険料に影響するもう一つの要素が、業種ごとに定められている保険料率です。次に、代表的な業種における保険料率の例を見てみましょう。
業種別保険料率の例(2025年度)
業種ごとに設定されている労災保険料率は、労働災害のリスクの高さによって異なります。
以下は2025年度における代表的な事業の一例です。
| 事業の種類 | 2025年度の保険料率(例) |
| 建設事業(既設建築物設備工事業を除く) | 9.5/1,000 |
| 食料品製造業 | 5.5/1,000 |
| 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 8.5/1,000 |
| 卸売業・小売業・飲食店・宿泊業 | 3/1,000 |
| その他の各種事業(広告業、クリーニング業、理容・美容業、レンタル業、教育業、医療業、福祉業、幼稚園・保育園、情報サービス業など) | 3/1,000 |
実際の保険料率は事業内容によって細かく分かれています。令和7年度の労災保険率等については、厚労省|令和7令和7年度の労災保険率等|労災保険率表(令和6年度〜)をご確認下さい。
年間保険料の例
具体的な年間保険料は、選択した「給付基礎日額」と、「業種別保険料率」によって決まります。
以下に例を示します。
【例1|建設事業(既設建築物設備工事業を除く)の場合】
|
【例2|飲食店の場合】
|
このように、同じ給付基礎日額を設定していても、業種により負担額は大きく異なります。
補償内容と費用のバランスを踏まえ、無理のない範囲で適切な給付基礎日額を選ぶことが重要です。
中小事業主等が労災保険に特別加入するメリットとは

中小事業主等の労災保険の特別加入制度は、中小企業の事業主自身や家族従業者、法人役員の業務災害リスクに備えるための、有効かつ実用的な仕組みです。
現場作業をともなう業種や、家族や役員が中心となって経営を行っている中小企業では、加入することで得られる安心感は特に大きいといえるでしょう。
ここでは、労災保険の特別加入によって得られる、主なメリットを3つご紹介します。
①業務中や通勤中の事故でも労災給付が受けられる
中小事業主等が労災保険に特別加入することで、一般の労働者と同じように、業務や通勤時の事故に備えることができます(一定の要件あり)。
被災した場合には、所定(療養・休業・障害・遺族など)の保険給付に加え、要件により特別給付金も支給されます。
こうした制度により、業務や通勤時の突発的なケガや災害による経済的な不安を軽減できるのは、大きな安心材料といえるでしょう。
詳しい給付の内容や条件については、厚生労働省|労災保険特別加入制度のしおりをご参照ください。
②家族従事者や法人役員も条件次第で補償対象にできる
特別加入制度では、事業主本人だけでなく、配偶者や子どもなどの家族従事者や法人役員も補償対象に含めることができます。
原則として、業務に従事している対象者全員をまとめて申請する「包括加入」が求められます。ただし、高齢や病気療養などを理由に実際に働いていない方は除外可能です。
中小企業では、家族従事者や法人役員が現場作業や営業を支えているケースが少なくありません。労働者だけでなく、家族や役員の安全を守ることも、企業のリスク管理につながります。
申請時は、自身だけでなく一緒に働く家族や役員の状況もあわせて確認しておきましょう。
③給付基礎日額の設定は柔軟に対応可能
労災保険の特別加入では、給付基礎日額を3,500円〜25,000円の間で収入に見合った適正な額を選択します。この金額は、補償の基準になると同時に、保険料の算出にも使われます。
業務のリスクや収入状況に応じて柔軟に設定できるのは、大きな利点です。
「保険料負担は抑えたいが、一定の補償は確保したい」といったニーズにも対応しやすく、無理のないリスクマネジメントが可能になります。
現場作業の多い職種や家族経営の企業にとっては、実情に合った選択ができるため安心です。
中小事業主等が労災保険に特別加入するための申請手続き

ここでは、初めて特別加入を検討している方向けに、申請手続きの基本的な流れをご紹介します。
(※すでに企業として特別加入している方がいらっしゃる場合は、新規申請ではなく、加入者の追加・変更手続きで対応可能です。)
申請の流れ(はじめて特別加入制度に申請する場合)
1.労働保険事務組合を選定し、事務委託契約を結ぶ
事務委託契約を結ぶには、選定した労働保険事務組合に「労働保険事務等委託書」を提出します。
労働保険事務組合は全国にあり、業種や地域等によって組合ごとに対応先を定めています。企業の業種や所在地に合った組合を選びましょう。
また、委託には手数料や年会費がかかる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
2.必要に応じて健康診断を受ける
粉じん作業や振動工具の使用、鉛、有機溶剤を扱う業務に一定期間従事している(していた)場合は、加入時健康診断が必要な場合があります。
診断の有無は、労働保険事務組合を通じて監督署長に提出された申出内容に基づき判断されます。必要な場合は、労働局長が委託した診断実施機関で受診します。
3.労働局による審査・承認をうける
加入を希望する事業主は「特別加入申請書(中小事業主等)」を作成し、委託契約を結んだ労働保険事務組合へ提出するのが原則です。
申請書は、組合から所轄の労働基準監督署長を経由し労働局長に提出され、審査が行われます。
特別加入の申請が受理されると、申請の翌日から30日以内の範囲で、申請者が希望した日が「加入の開始日」として承認されます。
労災保険による補償の対象となるのは、この加入開始日以降に発生した災害です。
申請に必要な書類一覧
中小事業主等の特別加入手続きの申請に必要な書類は以下のとおりです。
【初めての場合】
- 特別加入申請書(中小事業主等)※希望する給付基礎日額もここで記入
【健康診断が必要とされた場合】
- 特別加入時健康診断申出書
- 特別加入時健康診断指示書 ※監督署長より交付
- 特別加入時健康診断実施依頼書 ※監督署長より交付
- 健康診断証明書(特別加入用)※申請書に添付
【加入内容を変更する場合】
特別加入制度に関する手続きは書類の種類や判断条件が細かいため、事務を委託する労働保険事務組合へ確認しましょう。
知っておくべき中小事業主等が労災保険に特別加入する際の注意点

労災保険に特別加入していても、すべての事故が補償対象になるわけではありません。
なぜなら、業務災害として補償されるには、「特別加入申請書に記載された業務を、労働者と同じ立場・時間帯で行っていたこと」が原則となるからです。
以下のようなケースでは、労災として認定されない可能性があるため注意が必要です。
|
一方で、労働者と同様の勤務時間・勤務内容で発生した災害であれば、原則として補償の対象です。また、通勤中の災害については労働者と同様に補償されます。
このように、補償の対象となるかどうかは「申請内容」と「実際の働き方」が一致しているかがポイントです。加入時には、労働者に即した業務内容や勤務時間を正確に申請することが重要です。
万が一に備え、民間の災害補償保険を併用する中小事業主も少なくありません。特別加入制度の補償範囲を正しく理解し、必要に応じて民間保険の活用なども含めたリスク対策を検討しましょう。
まとめ|中小事業主等の特別加入は万が一への備えとして有効です
本記事では、中小事業主等が労災保険に特別加入する方法について、制度の概要から要件、保険料、メリット、手続き、注意点まで解説しました。
中小事業主等の労災保険の特別加入制度は、現場で働く中小事業主等の安全と、企業経営の継続性を支える仕組みです。
制度を正しく理解し、条件に合った形で加入することで、万が一の事故にも安心して備えることができます。
ただし、制度の適用可否や、委託先となる労働保険事務組合の選定など、実際に検討や手続きを進めるうえでは専門的な判断が必要となる場面もあります。
こうした場面では、労災保険の特別加入制度に詳しい社労士に相談することで安心して手続きを進めることができるでしょう。
労災保険の特別加入制度について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。