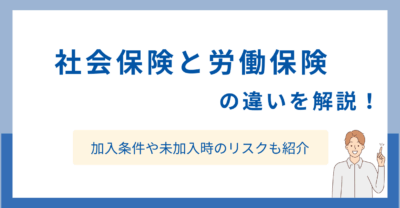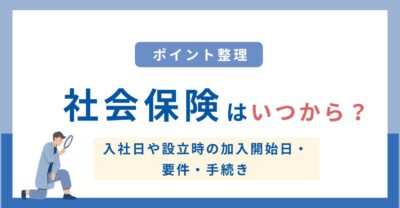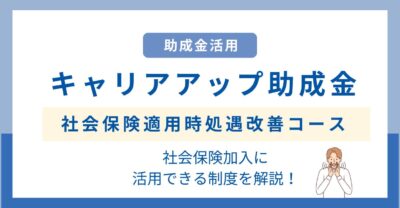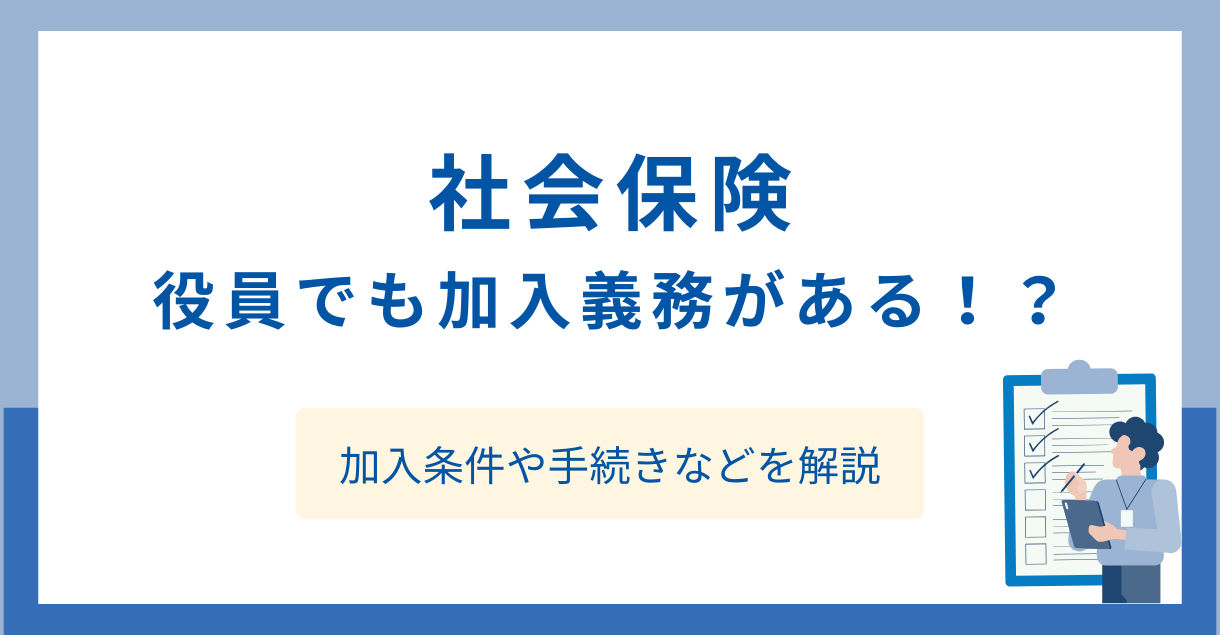
社会保険は役員でも加入義務がある!?加入条件や手続きなどを解説
法人の場合は社員だけではなく、役員にも社会保険の加入義務があります。ただし、役員報酬を受け取っていない場合など、条件によっては加入の必要がないケースもあるため注意が必要です。
なお、本記事でいう「社会保険」は、会社の被用者を対象とする健康保険・厚生年金保険を指しています。国民健康保険や国民年金も社会保険に含まれる制度ですが、加入対象や仕組みが大きく異なるため、本記事では別の制度として整理しています。
また、法人役員と個人事業主では、社会保険の加入義務や保険給付の内容も異なります。本記事では、役員の社会保険の加入義務や適用されるタイミング、加入手続きの方法についても紹介しています。ぜひ参考にしてください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
社会保険は役員でも加入義務がある
法人の役員は、原則として社会保険への加入義務があります。ただし、加入の有無は法令に定められた要件をすべて満たしているかどうかによって異なります。ここでは、役員の社会保険への加入義務について、以下の内容を解説します。
- 役員に社会保険への加入義務が発生する条件
- 社会保険適用における役員と社員の違い
- 非常勤役員なら社会保険への加入義務はない?
それぞれの内容について、確認してみましょう。
役員に社会保険への加入義務が発生する条件
役員が社会保険に加入しなければならないのは、以下の3つの条件をすべて満たしている場合です。
- 会社が社会保険の強制適用事業所に該当していること
- 役員報酬を受け取っていること
- 実質的に業務に従事していること
役員報酬を受け取っていない場合には、社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入義務が生じない可能性がありますが、国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。
日本では医療保険および年金制度への加入が義務付けられており、たとえ厚生年金などに加入していなくても、国民健康保険・国民年金への加入義務が生じます。
社会保険適用における役員と社員の違い
正社員であれば社会保険への加入条件を満たしているため、役員と異なり特別な加入条件はありません。
しかし、パート・アルバイト社員の場合は、1週間の所定労働時間や1ヶ月の所定労働日数が、同事業所内における正社員の4分の3以上になると社会保険の加入対象に該当します。
また、従業員数が常時51人以上の企業に勤務している場合は、所定労働時間が正社員の4分の3未満であっても、以下の4つの条件をすべて満たすと社会保険の加入対象になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 継続して2ヶ月以上の雇用が見込まれている
- 月額賃金が8万8,000円以上(通勤手当を含む)
- 学生ではない
役員と正社員、パート・アルバイト社員では、加入条件が異なる点を把握しましょう。
従業員の社会保険の加入義務については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:社会保険の加入義務とは?パートの適用拡大と企業の対応ポイントを解説)
非常勤役員なら社会保険への加入義務はない?
非常勤役員なら、社会保険の加入義務はありません。ほかに常勤の会社がある場合は、常勤の会社で社会保険に加入します。すべての事業所において非常勤の役員である場合には、社会保険に加入する必要はありません。
ただし、「非常勤」の形式にかかわらず、実態として継続的かつ恒常的に勤務していると判断される場合には、社会保険の加入義務が発生する可能性があります。加入についての判断が難しい場合には、専門家である社労士へ相談すると良いでしょう。
社労士に聞けば、これまで経験した事例や判断基準に基づいて、適切なアドバイスを受けることができます。
社会保険における法人役員と個人事業主の違い
法人役員と個人事業主では、社会保険に関する扱いが大きく異なります。主な違いは以下の2点です。
- 個人事業主は従業員数や業種で判断
- 加入する保険で給付内容が異なる
個人事業主には法人役員とは異なる制度が適用されるため、保険の加入条件や給付内容を事前にしっかり確認しておくことが大切です。
個人事業主は従業員数や業種で判断
法人ではない個人事業主は、従業員が5人以上であれば原則として社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用義務があります。
ただし、個人事業主の場合は、すべての事業所が社会保険の強制適用事業所になるわけではありません。従業員が5人未満の場合や、一部の業種(非適用業種)については社会保険の適用除外となります。
■社会保険の適用事業所に該当しない例
- 従業員数5人未満の個人事業
- 農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業、洗濯・理美容・浴場業、娯楽業、デザイン業、警備業、ビルメンテナンス業、政治・経済・文化団体、就業等の個人事業(従業員数を問わず)
なお、社会保険に加入しない場合は、国民健康保険や国民年金に自ら加入する必要があります。
加入する保険で給付内容が異なる
社会保険に加入した場合と国民健康保険・国民年金に加入した場合とでは、保険給付内容が異なります。
例えば国民健康保険には、健康保険と異なり、傷病手当金や出産手当金などの所得補償制度がありません。また、厚生年金と国民年金では将来的な年金受給額に大きな差が生じることもあります。
そもそも社会保険や会社役員とは?
ここまで、役員の社会保険への加入義務や社会保険適用における役員と社員の違いなどについて解説しましたが、そもそも社会保険や会社役員とは、どのようなものなのかを解説します。
社会保険の各制度の概要をおさらいし、会社役員に該当する人物像について紹介しますので、確認しましょう。
社会保険の各制度の概要をおさらい
社会保険とは、健康保険や介護保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険といった保険制度の総称です。国が提供する公的な保険制度で、医療費や年金、失業時の生活支援などが受けられます。
以下は、その中でも被用者向けの社会保険の種類と特徴をまとめた一覧表です。
■社会保険の種類と特徴
| 制度名 | 対象者 | 保険料負担 | 主な給付・補償 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会保険 | 健康保険(医療保険) | 従業員とその扶養家族 | 企業と従業員で折半 |
|
| 介護保険 | 40歳以上の健康保険加入者 | 企業と従業員で折半 (40歳以上のみ) |
|
|
| 厚生年金保険 | 企業の従業員 (一定の条件を満たすパート・アルバイト含む) |
企業と従業員で折半 |
|
社会保険については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
(関連記事:社会保険とは?企業が知っておくべき加入条件や必要書類を解説)
会社役員に該当する人物像
一般的に「会社役員」とされるのは、会社法などの法律に基づいて設置される取締役など、法人の意思決定や経営に関与する立場の人を指します。
役員は労働者ではないため、賃金ではなく「役員報酬」という形で報酬を受け取ります。
社会保険に役員が加入するタイミング
役員が社会保険に加入するタイミングとしては、新たに役員へ就任したときや、それまで無報酬だった役員に報酬が支払われるようになったときが挙げられます。この場合、社会保険の加入手続きが必要になるため、あらかじめ確認しておきましょう。
役員に就任した人がいるとき
外部から新しく役員として就任した人がいるときは、社会保険の加入手続きが必要です。これまで社員だった方が役員となる場合には、すでに社会保険に加入しているはずであり、加入に関する手続きは必要ありません。
無報酬から役員報酬が支払われることに変更されたとき
無報酬だった役員に対して、報酬を支払うことになった場合は、社会保険への加入義務が発生します。社会保険の適用事業所で報酬を受け取る役員は、原則として社会保険への加入が義務付けられています。
非常勤役員などのケースでも、業務の実態によって加入義務が発生する可能性があります。詳細は前述の「非常勤役員なら社会保険への加入義務はない?」で解説していますので、参考にしてください。
個別の状況によっては判断が難しい場合もあるため、社会保険の実務に精通した社労士に相談することで、正確な対応が可能となるでしょう。
役員に関する社会保険の手続き
役員に関する社会保険の手続きは、就任や退任、報酬変更などの状況に応じて異なります。
- 従業員が役員に就任する場合
- 外部から役員に就任する場合
- 役員を退任する場合
それぞれのケースで必要な書類や提出先、期限などを正しく把握することが重要です。
従業員が役員に就任する場合
役員就任により報酬が増え、標準報酬月額に2等級以上の差が生じる場合は「標準報酬月額変更届」を、所轄の年金事務所に提出しなければなりません。
標準報酬月額変更届(随時改定)は、報酬変更後の3ヶ月間の実績平均をもとに算出され、原則としてその翌月に提出します。
外部から役員に就任する場合
外部から役員に就任する場合は、社会保険の加入手続きが必要です。
加入手続き方法は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を所轄の年金事務所に提出するのみです。役員に就任した人(被保険者)に扶養者がいる場合は「被扶養者(異動)届」も提出が必要になるため、注意しましょう。
社会保険の加入手続きが適正に行われないと、適切な年金受給を受けられなくなるほか、高額な医療費を個人が負担しなければならなくなるため、速やかに手続きを進めましょう。
役員を退任する場合
役員を退任する場合には、社会保険に関する手続きが必要になるケースがあります。
役員を退任し、同時に会社を退職する場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を所轄の年金事務所に提出します。
退任から5日以内に提出しなければならないため、決定した段階で書類を準備しましょう。
社会保険に役員を加入する手続きを円滑にするために
社会保険の適用事業所では、社員だけではなく役員も条件により加入義務が生じます。法人設立とともに役員に就任する際は、社会保険の手続きが必要です。
手続きを進めるには、役員報酬を証明する株主総会議事録や就任承諾書などの書類が必要となるため、正確な情報の整備が不可欠です。自身で手続きが困難な場合には、社労士への依頼を検討しましょう。
社労士は、社会保険の制度や手続きに精通しており、状況に応じた正確な対応が可能です。社会保険関連の書類作成や提出を代行できる唯一の国家資格者であり、法改正への対応や行政とのやりとりもスムーズに進められます。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。