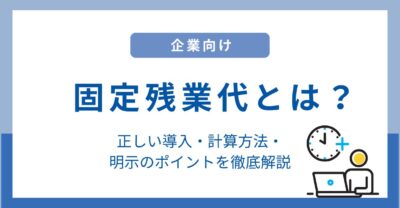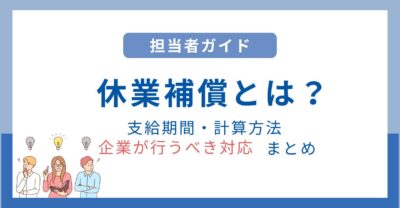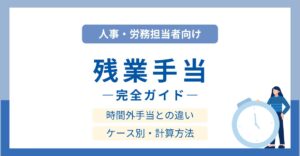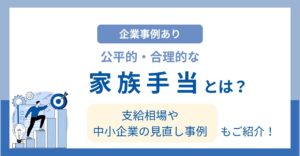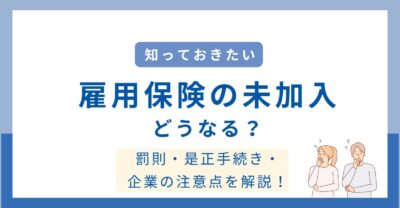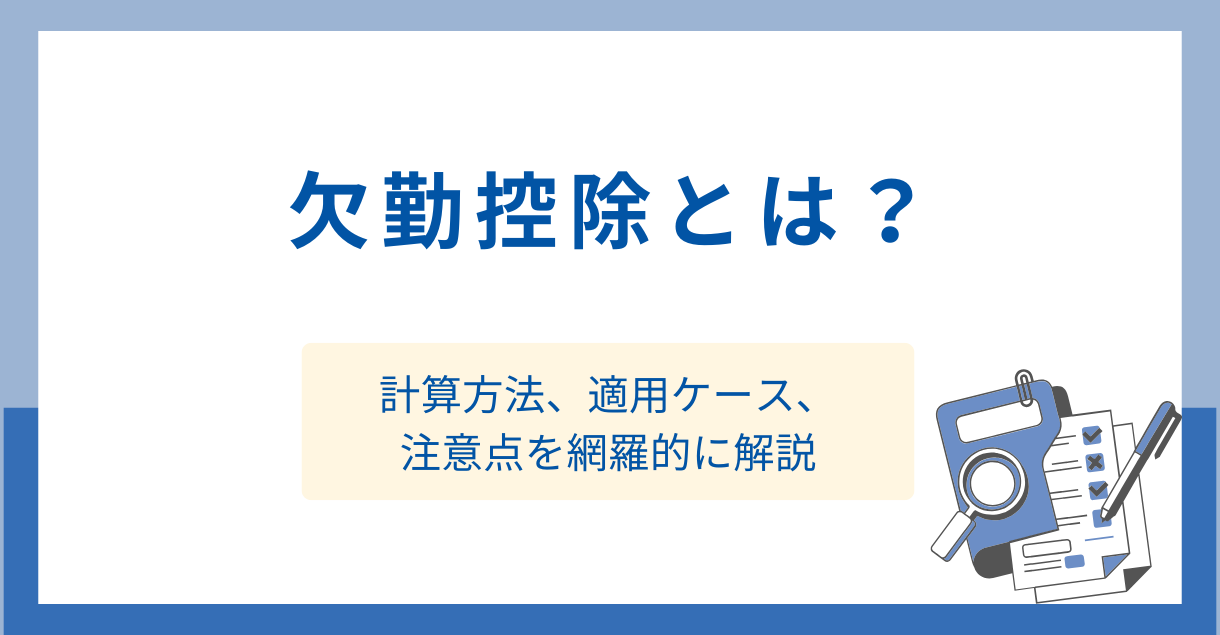
欠勤控除とは?計算方法、適用ケース、注意点を網羅的に解説
企業が適切に給与を管理するには、「欠勤控除」の正しい理解が欠かせません。欠勤控除は、従業員が勤務しなかった分の賃金を差し引く仕組みですが、その適用には細かなルールがあり、誤った処理をすると従業員とのトラブルや労働基準法違反のリスクを招く可能性があります。そのため、企業担当者は、欠勤控除について正しく理解することが必要です。
本記事では、欠勤控除の計算方法に加え、適用ケース、注意点などを詳しく解説します。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
日本最大級の社労士検索サイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
欠勤控除とは、従業員が欠勤した分の賃金を給与から差し引くこと
欠勤控除とは、従業員に支払う給与から、欠勤した分の賃金を差し引くことです。ここでいう「欠勤」とは、従業員が本来勤務すべき日に、有給休暇を取得せずに自己都合で休むことを指します。
欠勤控除は、働かなければ賃金は発生しないという「ノーワーク・ノーペイの原則」にもとづき行われます。
なお、労働基準法には欠勤控除に関する明確な規定はありません。ただし、正社員が日給月給制で給与を支給されている場合、欠勤日数に応じて給与を控除するのが一般的です。
一方、控除額の計算方法や適用ルールは、企業ごとに異なります。労使トラブルを防ぐためにも、企業は就業規則や給与規程に欠勤控除について明記し、従業員に周知することが重要です。
就業規則については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:就業規則がないのは違法?10人未満でも作成する理由やリスクを解説)
欠勤控除と減給の違い
給与から控除が行われるケースとして、欠勤控除のほかにも「減給」があります。しかし両者は、目的や法的な扱いが異なります。
減給とは、従業員の規則違反に対する懲戒処分として給与を減額することです。例えば、無断欠勤や遅刻を繰り返したり、職場の備品を勝手に持ち出したりするなど、企業のルールに違反した場合にペナルティとして科されます。減給は制裁としての性質を持つため、労働基準法により、減額の上限が定められ、従業員に対して過度な不利益を課すことができないよう制限されています。
一方、欠勤控除は、あくまで働いていない分の賃金を差し引くものであり、減給のように制裁的な意味合いはありません。法律上、直接的な上限規制は設けられていませんが、就業規則などにもとづき、適切に実施することが求められます。企業担当者は、両者の違いを正しく理解しておきましょう。
欠勤控除が適用されるケース
欠勤控除は、有給休暇の取得状況などによって適用の可否が決まります。ここでは、欠勤控除が適用される具体的なケースを解説します。
有給休暇を取得せずに休んだ場合
従業員が有給休暇を取得せずに自己都合で休んだ場合は、欠勤控除の対象となります。例えば、有給休暇を使いきった後に休む場合や、突発的な病気で有給休暇を取得せずに休む場合などが該当します。ただし、就業規則で有給休暇の事後申請が可能とされている場合は、後日申請すれば欠勤扱いにならず、欠勤控除の対象にもなりません。
遅刻・早退をした場合
体調不良や子供の迎えなどの自己都合で、従業員が遅刻・早退した場合は、欠勤控除の対象となります。ただし、就業規則で時間単位の有給休暇の取得が可能とされている場合は、手続きをすれば欠勤扱いにならず、欠勤控除の対象にもなりません。
また、小学校3年生修了までの子供の病気やケガ、入園(入学)式や卒園式などで、従業員が遅刻・早退をしたり仕事を休んだりする場合、一定の条件を満たせば、育児・介護休業法で定められた「子の看護等休暇」の取得が認められます。この場合も、欠勤控除の対象になりません。
欠勤控除が適用されないケース
従業員が勤務しなかった場合であっても、常に欠勤控除が行われるとは限りません。ここからは、欠勤控除が適用されない具体的なケースについて解説します。
有給休暇を使う場合
従業員が有給休暇を取得して休んだ場合、欠勤扱いとはならず、欠勤控除は適用されません。これは、労働基準法により有給休暇中の賃金が保障されているためです。また、企業が独自に設けている慶弔休暇やリフレッシュ休暇などの特別休暇を利用した場合も同様に、欠勤控除の対象とはなりません。
会社都合で休ませた場合
感染症の拡大防止や自然災害の影響、設備の故障などにより、企業側の判断で従業員に出勤停止命令を出した場合は、企業の都合による休業のため、欠勤扱いになりません。この場合、労働基準法第26条にもとづき、企業は従業員に対して平均賃金の60%以上を「休業手当」として支給する必要があります。
ただし、行政命令や自然災害などの不可抗力によって事業継続が困難な場合は、休業手当の支払い義務が生じないこともあるため、慎重に判断しましょう。
休職・休業期間中の場合
休職や育児・介護休業中の従業員には就業義務がないため、欠勤控除の対象にはなりません。休職は、病気療養や私的な理由で長期間勤務できない場合に、会社の規定にもとづいて認められるものです。一方、育児・介護休業は法律で定められた制度として、一定の条件を満たせば取得できます。いずれの場合も、休職・休業期間中の給与に関する支給の有無は企業の就業規則によって異なります。
欠勤控除の計算方法と特徴
欠勤控除の計算方法は企業ごとに異なります。適用する際は、自社の就業規則や給与規程を確認し、必要に応じて社労士などの専門家に相談しましょう。ここからは、月の所定勤務日数から計算する場合をはじめ、代表的な欠勤控除の計算方法とそれぞれのメリット・デメリットを解説します。
月の所定勤務日数から計算する場合
従業員が欠勤した月の所定勤務日数を用いて、以下のとおり欠勤控除額を算出します。
<計算式>
欠勤控除額=月の給料÷月の所定勤務日数×欠勤日
この計算方法のメリットは、各月の勤務日数の実態に合った欠勤控除額を算出できるため、公平性を確保しやすいことです。
一方、デメリットは、月ごとに所定勤務日数が変動するため、控除額が一定ではなく、計算が複雑になることです。例えば、ゴールデンウィークや年末年始などで所定勤務日数が少ない月は、他の月に比べて1日あたりの欠勤控除額が大きくなるため注意する必要があります。
月の平均所定勤務日数から計算する場合
月の平均所定勤務日数を用いて、以下のとおり欠勤控除額を算出します。
<計算式>
欠勤控除額=月の給料÷月の平均所定勤務日数(年間の所定勤務日数÷12)×欠勤日
この計算方法のメリットは、どの月であっても欠勤した1日あたりの控除額が変わらないため、計算がシンプルでわかりやすいことです。例えば、ゴールデンウィークや年末年始などで所定勤務日数が少ない月でも、欠勤控除額が増減しないため、毎月の給与計算が安定します。
一方、デメリットとして、実際の勤務日数と計算上の勤務日数が一致しない可能性もあるため、月によっては実際よりも控除額が多くなったり、少なくなったりすることがあります。
月の暦日数から計算する場合
従業員が欠勤した月の暦日数を用いて、以下のとおり欠勤控除額を算出します。
<計算式>
欠勤控除額=月の給料÷該当月の暦日数×欠勤日
この計算方法のメリットは、月給をその月の日数(28日~31日)で割るため、平日・土日祝日を問わず、1日あたりの欠勤控除額が均等になることです。つまり、どの日に欠勤しても、同じ月内であれば控除額は変わりません。
一方、デメリットとして、毎月の暦日数が異なるため、月ごとに計算式を変える必要があり、給与計算がやや複雑になる点が挙げられます。
遅刻・早退による控除額を計算する場合
遅刻・早退による欠勤控除額を算出する場合は、以下のとおり計算します。
<計算式>
欠勤控除額=月の給料÷月の所定勤務時間×欠勤時間
例えば、月の所定勤務日数が22日、1日の所定勤務時間が8時間の場合、1ヵ月の所定勤務時間は22日×8時間=176時間です。さらに、1ヵ月の給与が30万円で、遅刻・早退による欠勤が5時間だった場合、欠勤控除額=30万円÷176時間×5時間=約8,522円になります。
この計算方法は、時間単位で正確に控除できますが、計算が細かくなるため、給与計算の手間が増える可能性はあります。
欠勤控除について社労士に相談する
日本最大級の社労士検索サイト「社労士ナビ」は地域、得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
欠勤控除における注意点
欠勤控除の誤った適用は、従業員の不満やモチベーション低下を招く可能性があります。こうしたリスクを防ぐために、企業担当者は以下の点に注意しましょう。
就業規則に欠勤控除の取り扱いを明記する
欠勤控除は労働基準法で定められたものではないため、各企業が規則を設けて実施する必要があります。行政通達や判例による一定のルールを踏まえた上で、適用対象となるケースや控除額の計算方法を決め、就業規則や給与規程に明記することが重要です。
また、欠勤控除の実施は従業員との信頼関係にも直結するため、管理職に向けて制度を周知し、適切な対応ができるよう教育することも欠かせません。企業担当者は、就業規則・給与規程の作成や改訂に加え、社内周知や管理職向けの研修を実施しましょう。なお、就業規則の作成・改訂をした場合は、労働基準監督署への届け出を行う必要があります。
就業規則の届出方法については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:就業規則の届出方法を解説!届出義務や必要書類もあわせて紹介)
控除後の給料が最低賃金を下回らないようにする
欠勤控除を行う際は、控除後の賃金が最低賃金を下回らないよう注意が必要です。特に、所定労働日数が多い月に数日だけ出勤し、残りを欠勤した場合、通常の計算では時給換算で最低賃金を下回る可能性があります。企業は、最低賃金を下回らないよう、時間単位のチェックも行い、法令に沿った処理をする必要があります。
また、給与計算方法を変更する場合は、従業員との合意を前提に、給与規程への明記や労働契約との整合性を十分に考慮しなければなりません。
なお、最低賃金は地域ごとに異なり、毎年改定されるため、給与計算システムの更新を定期的に確認しましょう。
残業代の取り扱いを明らかにしておく
固定残業代(みなし残業)を支払っている場合は、欠勤控除との関係に注意が必要です。固定残業代は「所定労働時間を超えた労働」に対する手当のため、欠勤に応じて控除するには、就業規則や給与規程に明記しなければなりません。
規程があり、実際の労働時間と対応していれば、固定残業代も控除の対象となる場合があります。ただし、計算が煩雑になりやすいため、企業は控除のルールを明確にし、適正に運用することが重要です。
税金や社会保険の取り扱いを明らかにしておく
欠勤控除を適用する場合は、給与から控除額を差し引いた後に税金を計算します。所得税や住民税は所得額に応じて決まるため、給与が減れば源泉徴収される税額も少なくなるのが一般的です。
また、欠勤による給与の減額は、社会保険料の算定にも影響を与えます。長期間の欠勤や大幅な給与の減少で、3ヵ月間の平均報酬が2等級以上変動した場合は、標準報酬月額の変更(随時改定)や社会保険料の再計算が必要になることがあります。特に、給与の変動が一定の基準を超えると、事業者は「月額変更届」を提出しなければなりません。
なお、業務外の病気やケガで長期休業し、給与が支給されない場合、従業員は社会保険制度の一環として傷病手当金を受給できる場合があります。企業担当者は、社労士などの専門家と連携しながら、必要に応じて申請手続きを適切にサポートしましょう。
欠勤控除額の端数処理に気をつける
欠勤控除の計算で1円未満の端数が生じた場合、切り上げると実際より多く控除され、従業員に不利益を与える可能性があります。そのため、一般的には「切り捨て」で処理するのが適切です。企業の担当者は、端数の処理ルールを給与規程に明記し、給与計算が適正に行われているか確認しましょう。
欠勤控除について社労士に相談する
日本最大級の社労士検索サイト「社労士ナビ」は地域、得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
欠勤控除で違法に該当する場合
欠勤控除で差し引けるのは、業務に従事していない時間分のみです。例えば、半日の欠勤にもかかわらず1日分を控除するなど、実際の欠勤時間より多く差し引くと、労働基準法違反にあたるため注意が必要です。計算ミスや就業規則の不整備があると、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性もあります。
また、欠勤控除ではなく懲戒処分として「減給」を行う場合は、労働基準法91条により以下の制限があるため注意してください。
- 1回の減給額は、平均賃金の半額を超えてはならない
- 総額は、賃金支払期の給与の1/10を超えてはならない
労使トラブルを防ぐためにも、法令を遵守し、社労士などの専門家と連携しながら、就業規則や給与規程を適正に整備・運用しましょう。
欠勤控除の適用ルールを正しく理解し、適正な給与管理を
欠勤控除の誤った運用は、従業員とのトラブルや労働基準法違反のリスクを招きます。就業規則や給与規程に明確なルールを定め、適切な計算方法で管理することが重要です。また、最低賃金や税金への影響も考慮しましょう。
就業規則の整備や適切な賃金計算については、社労士のサポートが有効です。社労士は労務管理の見直しを支援し、リスク管理や適正な運用をアドバイスすることで、法令遵守の徹底、人事トラブルの防止、そして健全な職場環境の維持に貢献します。
社労士を探す際には、全国の依頼可能な社労士の20%に当たる、全国6,000以上の事務所の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この日本最大級の社労士検索サイトでは、地域や会社規模、得意分野などを指定して社労士を検索できるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。社労士への初回の相談は無料なので、ぜひご活用ください。