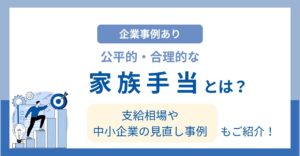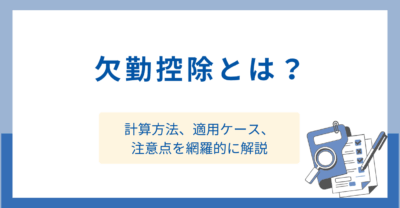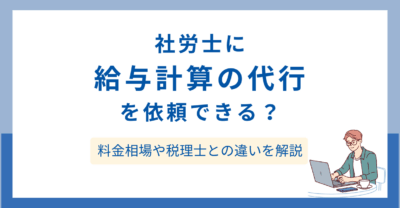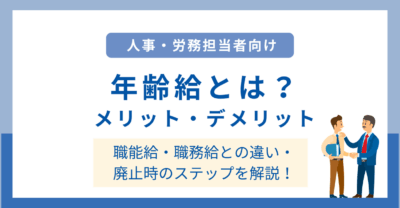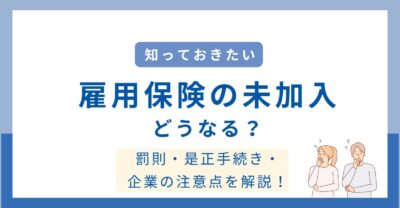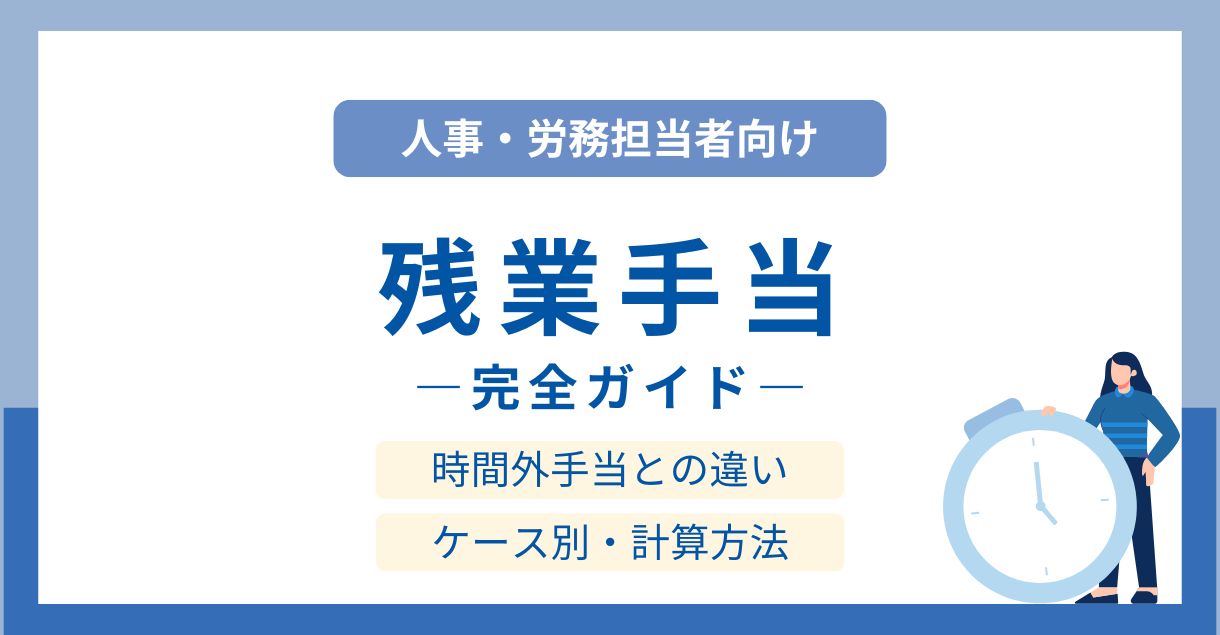
【完全ガイド】残業手当とは?時間外手当との違い・計算方法まで徹底解説
企業にとって、残業手当の適切な支給と管理は、法令遵守にとどまらず、労働者との信頼関係を築くうえでも重要です。
しかし、働き方が多様化し、固定残業代の導入や変形労働時間制の運用などが進んでいる現在、「残業手当をどのように算出すべきか悩んでいる」という人事・労務担当者の方も少なくありません。
本記事では、残業手当の法的な位置づけから時間外手当との違い、給与形態ごとの計算方法、そして制度運用時の注意点まで、実務に役立つ情報を網羅的に解説します。
本記事を読めば、残業手当の正しい計算方法や、制度運用で押さえておくべきポイントが明確になります。
ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
日本最大級の社労士検索サイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
残業手当とは|法定労働時間と割増賃金の基本ルール

残業手当とは、所定労働時間(企業で決められている労働時間)を超えて働いた労働者に対して、企業が支給する追加の賃金を指します。
一般的には、法定労働時間の1日8時間・週40時間(商業、接客娯楽業などで、労働者が常時10人未満の場合は週44時間)を超えた「時間外労働」への支払いを指します。
しかし、企業によっては法定時間内の残業にも残業手当として支給するケースがあります。
本記事では、労働基準法における「割増賃金」のルールを中心に、残業手当の定義や支給対象、計算方法などをわかりやすく解説します。
労働基準法における残業手当の定義
労働基準法第37条では、法定労働時間を超える労働(いわゆる時間外労働)に対し、通常の賃金よりも高い割増賃金(残業手当)を支払う義務が企業に課せられています。
具体的には、基礎賃金に対して25%以上の割増率で支払う必要があります。この「25%以上」とは企業がそれを下回らない範囲で、より高い割増率を設定してもよいことを意味しています。
また、1か月に時間外労働が60時間を超えた部分については、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
残業には法定内残業と法定外残業がある
残業には、大きく以下の2種類があります。
● 法定内残業:
所定労働時間を超えて働いたものの、法定労働時間(1日8時間・週40時間)内に収まっている労働時間のことです。この場合、通常の賃金が支払われますが、割増賃金の対象にはなりません。
● 法定外残業:
法定労働時間を超える労働で、企業は25%以上の割増賃金を支払う義務があります (労働基準法37条)。
【具体例:所定労働時間が9時~17時(休憩1時間)で、18時まで残業をした場合と19時まで残業をした場合】
| 実働時間 | 残業区分 | 支給される賃金 |
|---|---|---|
| 9時〜18時(実働8時間) | 17時〜18時=法定内残業 | 通常賃金(割増なし) |
| 9時〜19時(実働9時間) | 17時〜18時=法定内残業 18時〜19時=法定外残業 |
1時間は通常賃金、1時間は割増賃金 (25%以上) |
※補足:2019年4月(中小企業は2020年4月)施行の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」により、法定外残業には月45時間・年360時間という上限が設けられました。
なお、大前提として、労働者に法定外残業をさせる場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の締結・労働基準監督署への届け出が不可欠となります。
また、一時的に上記の上限時間を超える場合は、特別条項付き36協定の締結が必要で、年間720時間・複数月平均80時間・1か月100時間未満(休日労働含む)といった、追加上限も適用されます。
36協定の届出方法や注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。
>「企業が知るべき「36協定」とは?特別条項・届出方法・違反リスクまで徹底解説」
残業手当の適用範囲と適用されないケースとは?
残業手当は、企業に雇用されている正社員・契約社員・パート社員などの労働者に広く適用されます。
所定労働時間を超えて勤務した場合、雇用契約の内容に応じて、原則として残業手当の支給が必要です。
一方で、次のような方には、法律上、残業手当の支給義務がないケースもあります。
● 管理監督者
労働時間、休憩、休日の制限を受けない、一定の裁量を持つ労働者が該当します。
このような労働者には、時間外・休日労働に関する割増賃金の支払い義務が免除されます(労働基準法第41条)。ただし、深夜労働は割増賃金の対象です。
なお、「課長」などの肩書きがあっても、出退勤の自由がなく、人事・賃金の決定に関与していない場合などは、管理監督者とは認められません。役職名だけでなく、業務の実態に基づいて判断されます。
● 裁量労働制※の対象業務に従事する労働者(成果評価型の労働者)
業務の遂行方法や時間配分を労働者に委ねる、成果評価型の労働者を指します。
※裁量労働制は「専門業務型」と「企画業務型」の2種類があり、対象業務は法律で限定されています。
裁量労働制では、あらかじめ労使協定で定めた時間を「みなし労働時間」として扱い、原則として時間外労働に対する割増賃金の支払いルールは適用されません。
ただし、みなし労働時間が法定労働時間を超える場合には割増賃金が必要になります。また、休日労働や深夜労働を行った場合にも割増賃金が必要です。
● 業務委託契約の個人事業主
雇用契約ではなく、事業者同士の契約(請負や委任など)にあたるため、労働基準法の適用外となります。そのため、残業手当や割増賃金の支払い義務も発生しません。
残業手当の対象かどうかは、「雇用関係の有無」「職務内容の実態」によって判断されます。
企業側は制度の運用にあたり、慎重な確認が求められます。
残業手当と時間外手当の違い

「残業手当」と「時間外手当」は混同されがちですが、法的な定義や支払い条件が異なる言葉です。
時間外手当とは、法律で定められた「法定労働時間(1日8時間・週40時間)」を超えて働いた場合に、企業に支給が義務づけられている割増賃金です(労働基準法第37条)。
この制度は、長時間労働による過重な負担を抑え、労働者の健康保護を目的としています。
なお、残業手当は法律用語ではなく、一般的に幅広く使われる用語です。法定時間内の労働も対象とするケースがあるため、時間外手当とは厳密に意味が異なります。
残業手当(時間外手当)などの割増賃金と割増率
法定労働時間を超える労働に対して支給される「割増賃金」において、その割増率や対象となる条件にはいくつかのパターンがあります。
特に、深夜・休日や長時間の残業には、高い割増率が定められているため注意が必要です。
割増賃金の種類と支給条件は、以下のとおりです。
| 種類(手当) | 支払う条件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 時間外 (時間外手当) |
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 25%以上 |
| 時間外労働が限度時間 (1か月45時間、1年360時間など)を超えたとき |
25%以上 (※1) |
|
| 時間外労働が1か月60時間を超えたとき | 50%以上 (※2) |
|
| 休日(休日手当) | 法定休日(週1日)に勤務させたとき | 35%以上 |
| 深夜(深夜手当) | 午後10時から午前5時までの間に勤務させたとき | 25%以上 |
※1:限度時間超えについては、労使協定により25%を超える割増率とする努力義務があります。
※2:中小企業にも2023年4月から適用されています。
出典:しっかりマスター労働基準法「割増賃金編」|東京労働局
時間外労働と深夜労働が重なる場合は、それぞれの割増率(各25%)を合算し、通常賃金の1.5倍(50%増)の残業手当を支給します。
【加算の具体例】
月給制の労働者が午後10時~午後11まで1時間の残業をした場合:
この1時間に対しては、時間外手当と深夜手当の両方を加算しなければなりません。計算イメージ:
⚫︎ 時間単価:2,000円
⚫︎ 割増率:25%(時間外手当)+25%(深夜手当)=50%
⚫︎ 支給額:2,000円✕1.5=3,000円
近年の働き方改革関連法の影響により、特に中小企業においても、割増率の適用範囲が強化されるなど、制度の運用にはより慎重な対応が求められています。
就業規則や給与計算システムに正しく反映し、実務に即した制度設計と定期的な見直しを行うことが重要です。
残業手当(時間外手当)の計算方法|ケース別で解説

残業手当(時間外手当)の計算方法は、給与体系や就業形態によって異なります。
誤った計算は、企業にとって金銭的な損失だけでなく、法令違反や労使トラブルのリスクにもつながるため、注意が必要です。
ここでは、代表的な3つのケースの時間外手当の計算ルールと注意点を整理して解説します。
- 時給制・月給制(一般的)
- 変形労働時間制(1か月単位、1年単位等)
- 固定残業代(みなし残業代)
以下、それぞれ解説します。
ケース1|時給制・月給制(一般的)
時間外手当の基本的な計算方法は、時給制と月給制で異なります。どちらも、法定時間外労働に対して通常賃金の25%以上を加えた金額を支給するのが基本です。
時給制の場合
- 計算式:時給×1.25×残業時間数=残業手当
- 例:時給1,200円×1.25×10時間=15,000円
月給制の場合
- 計算式:月給÷1か月の平均所定労働時間×1.25×残業時間数=残業手当
- 例:月給300,000円÷160時間×1.25×10時間≒23,437円
※月給制の場合、1時間あたりの賃金は、月給を平均所定労働時間で割って算出します。なお、詳細な算出方法は就業規則や給与規定によって異なる場合があります。
【割増賃金の計算から除外される賃金項目】
以下の賃金は労働の対価としての性質が薄いものとされているため、基本的に割増賃金の算定基礎から除外するよう定められています(労働基準法施行規則第21条)。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金(例:慶弔見舞金など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与など)
ただし、一律支給されている場合や、実費精算でない場合には、算定基礎に含める必要があるため、注意が必要です。
家族手当については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:家族手当とは?支給条件・相場と見直し事例をくわしく解説)
ケース2|変形労働時間制(1か月単位、1年単位等)
変形労働時間制とは、労働時間の配分に変動をもたせる働き方の制度で、繁忙期と閑散期の差がある業種で活用されています。
この制度では、1日や1週間の労働時間が一時的に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えても、期間全体の合計時間が法定の枠内であれば、時間外労働とはなりません。
ただし、その期間内の労働時間が法定の総枠を超えた場合には、超過分に対して割増賃金(25%以上)を支払う必要があります。
変形労働時間制の場合(例:1か月単位の変形労働時間制)
- 法定労働時間枠:40時間×4週=160時間
- 実働が176時間だった場合:
176時間-160時間=「16時間分」が時間外労働(割増賃金の対象)
変形労働時間制を導入するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 労使協定の締結・労基署への届出(※)
- 就業規則または労使協定への制度明記
- 対象期間・労働時間・休日の具体的な定め
※導入する制度によって異なりますのでご注意ください(参考:厚生労働省「変形労働時間制の概要」)。
制度設計を誤ると違法な時間外労働とみなされるリスクがあるため、導入前の設計と運用ルールの整備が重要です。
ケース3|固定残業代(みなし残業代)
固定残業代制度(みなし残業代)とは、あらかじめ定めた一定時間分の残業手当を、基本給とは別に定額で支給する制度です。
実際の残業時間に関わらず、定められた時間分までは毎月定額で支給されるのが特徴です。ただし、設定時間を超えた分については、別途割増賃金を支払う必要があります。
固定残業代の場合
(例:月20時間分の固定残業代=30,000円設定)
- 残業が10時間(設定時間未満):30,000円(満額支給)
- 残業が25時間(設定時間超過):
30,000円+超過した5時間分の残業手当(25%以上の割増賃金)
この制度は、給与計算を簡素化する一方で、誤った運用によるトラブルも多いため、適切な導入と管理が不可欠です。
詳細な要件については、後述の「注意点③」を参照してください。
なお、上記のいずれの計算例においても、時間外労働が休日や深夜に及んだ場合には、その分の割増率を加算する必要がありますので、ご注意ください。
残業手当(時間外手当)を支給する際の注意点

残業手当(時間外手当)の支給方法を誤ると、未払い賃金や法令違反などの重大なトラブルに発展する可能性があります。
ここでは、実務上とくに注意すべき3つのポイントを整理して解説します。
① 残業時間の記録管理と保存義務
2020年の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」に基づく法改正の一環で、労働時間の記録や賃金台帳の5年間の保存が義務化されました。
対象となる主な記録媒体の例:
- タイムカード:打刻による出退勤時間の記録
- 勤怠管理システムのログ:ICカードやクラウド型などの自動記録データ
- 労働日報・業務報告書:手書き・デジタル問わず、業務内容や時間の記録
② 時間外手当と課税対象としての取扱い
時間外手当は「労働の対価」として給与所得に含まれるため、企業には正しい税務処理が求められます。
実務上の注意点:
- 時間外手当は給与所得として課税対象
時間外手当は通常の給与と同様、所得税が課されます。 - 支給時は源泉徴収を実施
支給時に企業が源泉徴収を行う必要があります。 - 未払い分は支給年に課税
過去の残業代をまとめて支払う場合、その支払年の所得として扱われ、課税対象となります。 - 年末調整後の支給には事前の案内を
年末調整後に残業代を支給すると、労働者に修正申告が必要になる場合もあるため、事前に説明しておくと安心です。
③ 固定残業代制度の適正な運用方法
固定残業代制度(みなし残業代制度)を正しく運用するためには、関連法令や厚生労働省のガイドライン等で示されている要件を満たす必要があります。
具体的には、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 契約書への明記:
固定残業代の対象時間数・金額・超過分の取扱いについて、雇用契約書や労働条件通知書に記載する。 - 就業規則への記載:
制度の概要や支給基準を、就業規則または賃金規程に明記する。 - 給与明細での内訳表示:
基本給と固定残業代を明確に区分し、それぞれの金額を記載する。 - 超過分の精算:
設定時間を超えた分は、必ず別途で割増賃金を支払う。
これらの1つでも欠けると「名ばかり固定残業代」とみなされ、制度が無効になる可能性があります。
過去に遡って未払い残業代を支払うこととなった事例もあるため、制度設計・契約書・就業規則の整備は社労士と連携して行うことが重要です。
まとめ|社労士との連携で残業手当の管理をスムーズに

本記事では、残業手当と時間外手当の違い、計算方法、支給時の注意点や固定残業代制度の扱い方まで、幅広く解説しました。
残業手当(時間外手当)の整備は、企業にとって法令遵守の要であると同時に、労働者との信頼関係を築く基盤としても重要です。
ただし、制度の適用範囲や計算方法は、働き方や給与形態によって大きく異なるため、実務では判断に迷う場面も少なくありません。
時間外手当の運用や労働時間制度の見直しを進める際には、法令と現場の両方に精通した社労士との連携が有効です。
時間外手当について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。