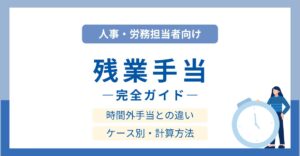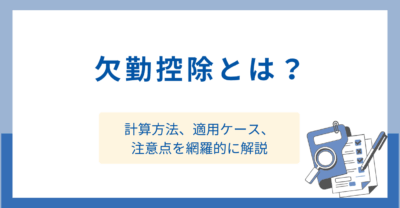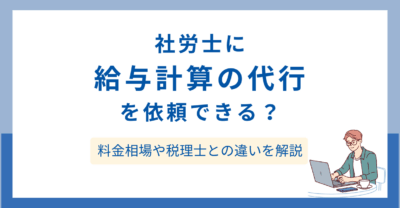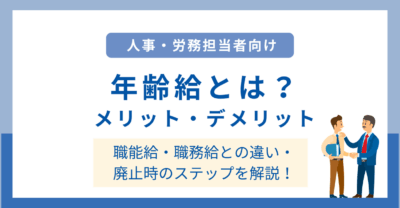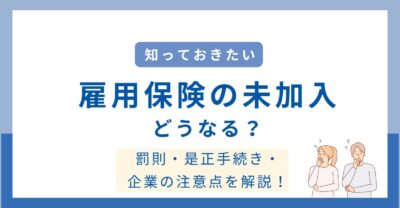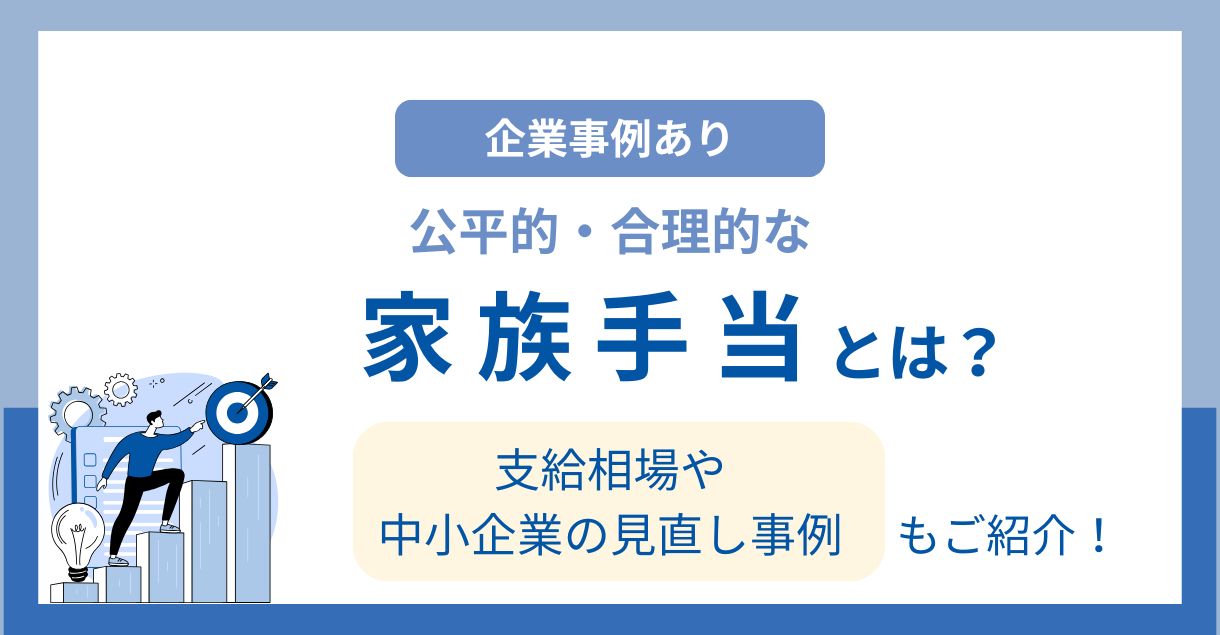
家族手当とは?支給条件・相場と見直し事例をくわしく解説
家族手当は、家族がいる従業員の生活を支援する目的で、多くの企業が導入してきた制度です。 しかし近年では、家族手当の制度の在り方を見直す企業が増えています。
その背景にあるのが、「成果主義の推進」や「非正規社員と正規社員との待遇差是正」といった公平性・合理性の課題です。制度の設計が曖昧なままでは、支給対象や金額に不公平感が生まれ、従業員の納得感を損ねる可能性があります。
本記事では、家族手当の支給条件や扶養手当との違い、支給額の相場などを詳しく解説しています。さらに、家族手当の見直しを実施した中小企業の事例も紹介します。
自社の処遇制度における家族手当について検討したい方、見直したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
日本最大級の社労士検索サイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
家族手当とは?

家族手当とは、配偶者や子どもなど家族がいる従業員に対して、企業が独自に支給する手当のことです。
生活費や子育て費用など、家族を持つことによる経済的負担を少しでも軽減し、従業員が安心して働き続けられるようにすることが主な目的です。
この手当は、法律で定められた義務ではなく、企業が任意で導入できる「法定外福利厚生」に分類されます。
そのため、家族手当の有無や、支給対象となる家族の範囲、支給条件、金額などは企業ごとに大きく異なります。
家族手当の支給条件と対象家族
家族手当は、法的な支給義務はないため、制度の有無や内容、支給条件は企業が自由に設計できる点が特徴です。
企業ごとに異なりますが、一般的には以下のような支給条件が設けられています。
家族手当の支給条件の例
- 扶養している配偶者や子どもがいる
- 子どもは18歳未満、または22歳未満の学生の場合に対象
- 両親は60歳以上かつ扶養義務がある場合に限る
- 同居しており、同一生計内で生活している
- 配偶者の年収が103万円または130万円未満である
多くの企業では、一定以上の収入がある家族は支給対象外とする運用が一般的です。また、支給対象の家族が複数いる場合には、人数に応じて手当額が加算されるケースもあります。
このように、家族手当は企業ごとに独自に設定されており、対象や金額、支給基準には大きな違いが見られます。
制度設計の際は、他社事例や従業員構成も考慮しながら、自社に合ったルールを定めることが重要です。
「家族手当」と「扶養手当」との違い
家族手当と扶養手当は、どちらも家族に関する支援を目的とした手当ですが、その支給要件には違いがあります。
家族手当は、「配偶者や子どもなどの家族がいること」を前提に支給されるのが一般的です。
一方、扶養手当は、「実際に扶養している家族がいること」が支給の条件とされていることが多いです。
ただし、企業によっては、家族手当の支給条件を「扶養している家族がいること」としているケースもあります。こうした場合、実質的には「扶養手当」として運用していても、制度名として「家族手当」と表記していることがあります。
さらに、企業によっては「配偶者手当」「子ども手当」など、家族構成ごとに手当の名称を分けて設けていることもあります。
企業によって名称が異なる場合があるため、自社で手当を設ける場合には、就業規則で運用ルールや支給条件を明確に定義しておくことが重要です。
家族手当を導入している企業の割合
人事院の令和6年職種別民間給与実態調査によると、家族手当の制度を導入している企業の割合は全体で74.5%にのぼります。
以下は、企業規模別に見た家族手当導入率の比較です。
| 企業規模(従業員数) | 家族手当制度の導入率 |
|---|---|
| 500人以上 | 74.1% |
| 100人以上500人未満 | 76.5% |
| 50人以上100人未満 | 69.9% |
中堅・中小企業でも7割前後の企業が家族手当を導入しており、依然として高い普及率を保っています。
また、配偶者がいる場合に家族手当を支給する企業は53.5%とも発表されており、制度導入企業の中でも配偶者手当の占める比率が高いことが伺えます。
企業規模にかかわらず、多くの職場で家族手当が導入されている一方で、実際の支給額や支給対象の範囲には企業ごとの違いが大きく見られます。
次に、平均的な支給額の水準について確認していきましょう。
家族手当の相場(平均支給額)はいくら?

家族手当の支給額は、企業規模や制度の設計によって大きく異なります。
厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査」によると、企業規模別の従業員1人あたり平均支給額は以下のようになっています。
| 企業規模(従業員数) | 平均支給額(月額) |
|---|---|
| 1,000人以上 | 22,200円 |
| 300~999人 | 16,000円 |
| 100~299人 | 15,300円 |
| 30~99人 | 12,800円 |
上記からもわかるように、大企業ほど家族手当の支給額が高い傾向にあります。
一方で、家族構成に応じて加算される「加算型」の家族手当制度を導入している企業も少なくありません。この場合、扶養する家族の人数によっては、平均支給額よりも手当の総額が大きくなる可能性があります。
東京都産業労働局の「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」によると、家族構成ごとに加算される家族手当の平均額は次の通りです。
| 家族構成 | 平均支給額(月額) |
|---|---|
| 配偶者 | 10,356円 |
| 第一子 | 5,255円 |
| 第二子 | 4,858円 |
| 第三子以降 | 4,859円 |
扶養家族が配偶者と子ども2人である従業員の場合、以下の合計金額が支給されることになります。
10,356円(配偶者)+5,255円(第1子)+4,858円(第2子)=20,469円/月
家族手当の支給方式が家族構成に応じた加算型である場合、家族の人数が多いほど従業員一人当たり月額の支給額も増加する仕組みです。
一律支給と比べて柔軟性は高いものの、企業側の財政的負担も大きくなるため、制度設計にはバランスが求められます。
家族手当に関する税金や社会保険の注意点

家族手当は、法律上「給与の一部」として扱われるため、支給にあたっては税金や社会保険料算定の対象になる点に注意が必要です。
まず、家族手当は所得税や住民税の課税対象です。
通勤手当のような一定額まで非課税とされる手当とは異なり、家族手当は原則すべて課税所得として扱われ、年末調整や源泉徴収にも含まれます。
また、家族手当は、社会保険制度上「報酬」に該当するため、標準報酬月額の算定対象となります。
標準報酬月額とは
社会保険の被保険者が受け取る毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したものです。この標準報酬をもとに、保険料や保険給付の額が計算されます。
標準報酬には、基本給、家族手当、通勤手当、残業手当等、労働の対償として支給されるものが含まれます。
社会保険については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:社会保険とは?概要から保険料の計算方法まで徹底解説!)
家族手当の見直しが進む理由とは?企業が直面する3つの課題
家族手当は多くの企業で支給されている福利厚生のひとつですが、家族手当の導入を見直す企業が年々増えています。
ここ30年で、家族手当を導入している企業の割合は以下のように推移しています。
家族手当の普及率の推移(平成6年~令和6年)
| 年 | 導入企業の割合 |
|---|---|
| 平成6年(1994年) | 91.7% |
| 平成16年(2004年) | 83.0% |
| 平成26年(2014年) | 76.8% |
| 令和6年(2024年) | 74.5% |
出典:配偶者手当を取り巻く現状|厚生労働省
令和6年職種別民間給与実態調査の結果|人事院
この30年間でおよそ17%の減少となっており、長期的に家族手当の見直し・廃止が進んでいる実態が明らかです。
家族手当を見直し・廃止する企業が増えている主な理由には、主に次の3つの要因が挙げられます。
1.成果主義・職務給とのミスマッチ
昭和の高度経済成長期には、「男性が働き、女性が家庭を守る」といったモデルが一般的でした。そのような中で家族手当は、家族を養う従業員への重要な福利厚生のひとつとされてきました。
しかし現在は、共働きや単身世帯の増加、働き方の多様化により、処遇制度も価値観も大きく変化しています。
近年の人事制度では、年齢や家族構成ではなく、業務内容や成果に応じて処遇を決める「成果主義」「職務給」の導入が進んでいます。
そのため、家族構成に基づいて支給される家族手当は、「個人の貢献度を正当に反映した給与体系と一致しないのでは?」との疑問の声が上がっているのが実状です。
このように、「公正な評価に基づいて処遇を行いたい」と考える企業にとって、家族手当は制度設計上の障壁となりやすく、見直しや廃止の対象となっています。
2.非正規社員との待遇差の是正(同一労働同一賃金)
働き方改革の一環として推進されている「同一労働同一賃金」の原則も、家族手当の見直しに影響を与えています。
たとえば、家族手当を正社員にのみ支給する場合です。
パート社員や契約社員を支給対象から除外する場合、その取り扱いに合理的な理由がなければ、不合理な待遇差と判断されるリスクがあります。
実際に、「同じ仕事をしているのに家族手当が支給されないのは不公平だ」といった制度への不満が、従業員間の不信感につながるケースも少なくありません。
このようなリスクを避けるため、企業の間では雇用形態を問わず、公平な処遇を実現しようとする動きが広がっています。
3.配偶者手当による女性の就業抑制の問題
家族手当の一種である「配偶者手当」は、配偶者の年収が一定以下(例:103万円または130万円未満など)であることを支給条件としているケースが一般的です。
こうした条件が、「年収の壁」として、女性パートタイム従業員による就業抑制(いわゆる就業調整)を招く要因のひとつとされています。
実際に、女性パートタイム従業員が就業調整を行う理由としては、以下のような回答が挙げられています(複数回答)。
就業調整をする理由
| 就業調整をする理由 | 割合 (複数回答) |
|---|---|
| 一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから | 57.3% |
| 自分の所得税の非課税限度額(103万円)を超えると税金を支払わなければならないから | 49.6% |
| 一定額を超えると配偶者の税制上の配偶者控除が無くなり、配偶者特別控除が少なくなるから | 36.4% |
| 一定額を超えると配偶者の企業の配偶者手当がもらえなくなるから | 15.4% |
厚生労働省は、こうした就業抑制の構造的要因を問題視しており、女性の就労促進やキャリア形成を妨げるものとして、企業に配偶者手当の在り方の見直しを促す方針を打ち出しています。
家族手当を見直した中小企業の事例

以下では、実際に制度変更を行った中小企業の事例をご紹介します。
自社の家族手当の見直しを検討する際の参考としてご覧ください。
事例1|能力に応じた手当に再構成した事例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 企業規模 | 50~99人 |
| 業種 | 卸売業 |
| 見直し前 | 扶養人数に応じた家族手当(例:配偶者+子で23,500円/月) |
| 見直し後 | 能力に応じた3種の基礎能力手当を新設 それぞれ6段階で評価 ①PC /IT能力手当(最大20,000円/月) ②対人・態度能力手当(最大20,000円/月) ③道具としての英語力手当(最大25,000円/月) |
参考:配偶者を対象とした手当に関する見直しが実施・検討された事例等|厚生労働省
この企業では、年齢や家族構成に左右されない公正な処遇を目指して、家族手当や住宅手当を廃止しました。
そのうえで、これらの手当の原資を活用し、「基礎能力手当」を新たに創設しています。
この手当は、PCスキル・対人態度・英語力の3分野を対象に、それぞれ6段階で評価する仕組みで従業員の成果や能力を反映した賃金制度へ、段階的に移行する狙いです。
事例2|各種手当を廃止し、基本給に統合した事例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 企業規模 | 50~99人 |
| 業種 | サービス業 |
| 見直し前 | 配偶者手当を含む多様な手当を支給 |
| 見直し後 | 各種手当を廃止し、5年間で段階的に基本給へ統合 |
参考:配偶者を対象とした手当に関する見直しが実施・検討された事例等|厚生労働省
この企業では、公平性と公正性の観点から、家族手当を含むすべての手当制度の見直しを行いました。
急な廃止による従業員への影響を避けるため、5年間の経過措置を設け、段階的に手当の原資を基本給へ再配分しています。
5年後には、各種手当を完全に廃止する制度へと移行しました。
その結果、特に若手社員のモチベーション向上につながったと報告されています。
家族手当に代わる支援制度例

制度の見直しや廃止を検討する際には、代替となる支援制度の導入が重要です。
以下、家族手当に代わる新たな手当や制度の一部をご紹介します。
ライフサポート手当
家族構成や扶養の有無に関係なく、全従業員に一定額を支給する制度です。たとえば、毎月5,000円~10,000円を一律支給とすることで公平性が確保できます。使途を限定せず、医療・育児・介護・自己啓発など従業員自身のニーズに応じた使い方ができます。
カフェテリアプラン(選択型福利厚生)
企業が用意した福利厚生メニューの中から、従業員がポイント制で自由に選べる制度です。ライフステージや価値観に応じて、育児・介護支援、健康維持、旅行・レジャーなどさまざまな支援が可能となります。
まとめ|公平性・合理性のある家族手当に向けて整備しよう
本記事では、家族手当の基本的な内容から、支給対象や支給額の相場、見直しが進む理由やそして他社の実例の紹介まで、制度運用のポイントを幅広く解説しました。
家族手当は、従業員の生活支援という目的がある一方で、現代の多様な働き方や人事制度に即した柔軟で公平な制度設計が求められています。
制度の設計次第では、反対に従業員間の不公平感やモチベーション低下を生むリスクもあります。
そのため、家族手当の導入や見直しを行う際には、社労士など専門家のアドバイスを受けながら、自社の人事方針や経営戦略に合った制度設計を行うことが重要です。
家族手当を含めた諸手当について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。