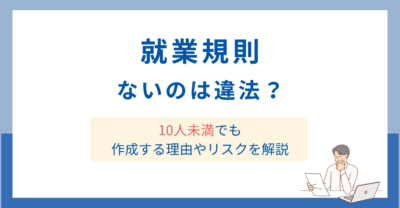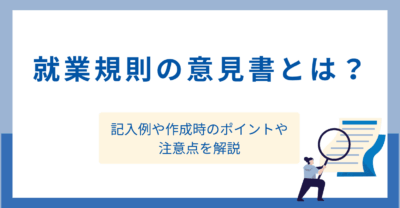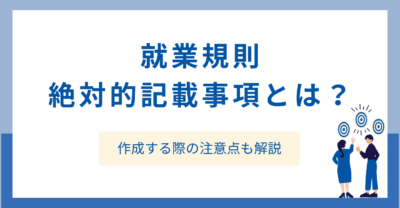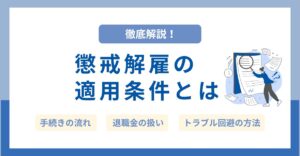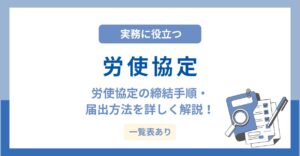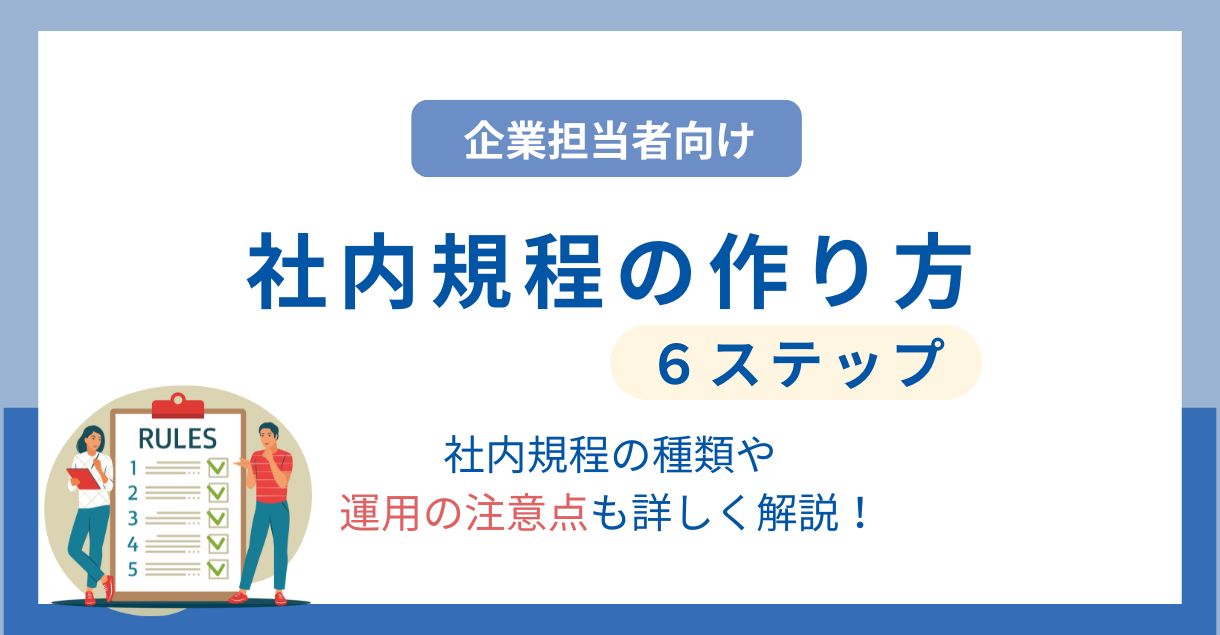
【企業担当者向け】社内規程の作り方とは?種類や運用の注意点も詳しく解説!
社内規程は、企業が独自に定める社内ルールや行動基準で、業務の標準化や労働トラブルの未然防止に役立ちます。
その一方で、内容が曖昧だったり、法改正に対応できていなかったりするとかえってリスクを招く恐れがあります。
また、就業規則を整備している企業でも、個別の社内規定が不足していたり、実態に合っていなかったりするケースは少なくありません。
本記事では、企業担当者の方に向けて、社内規程の基本的な考え方から、具体的な作成手順、運用上の注意点、見直しのタイミングまでを詳しく解説します。
自社のルール整備を見直すきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
社内規程とは

社内規程とは、企業が労働者に求める行動基準や業務ルール等を明文化したもので、企業組織における秩序の維持や業務効率の向上を目的に定められるものです。
企業が独自に定める内部ルールであるため、その内容は企業の規模や業種、業務の特性、企業方針などによって様々です。
一般的に整備されている社内規程の例として、以下のようなものがあります。
【例】
- 勤務態度や服装、遅刻・早退・欠勤など、日常業務に関する基本的な行動規範
- 始業・終業時刻、所定労働時間、休憩、残業、深夜労働などに関する労働時間のルール
- 賃金体系、各種手当、支給日、割増賃金の算出方法、昇給・賞与など賃金に関する規定
これらは、法令を遵守するための基盤となるだけでなく、企業の価値観や方針を社内に浸透させ、労使トラブルの未然防止や組織運営の安定にもつながります。
企業は自社の実態や課題に応じて、必要な社内規程を整備・見直していくことが求められます。
「社内規程」と「社内規定」の違い
- 「規定」:条文など個別のルールのこと 例)時間外労働に関する規定。
- 「規程」:個々の規定をまとめた文書全体のこと 例)賃金規程。
たとえば賃金規程には、支給方法や計算方法などの個別ルール(=規定)が複数含まれています。こうした各種の規程を総合的にまとめた社内ルール全体のことを「社内規程」といいます。
社内規程の目的
社内規程は、企業組織を円滑に運営するうえで重要な役割を果たします。
具体的には、次のような目的があります。
- 業務を標準化して組織全体の運用を円滑にする
- 社内トラブルを未然に防ぐ
- 労働者の働きやすい環境を整える
以下では、これらの目的について詳しく解説します。
業務の標準化
社内規程を整備することで、社内の対応に一貫性が生まれ、部署や担当者による判断のばらつきを防げます。
たとえば、遅刻や服装のルールなど、社内で統一したいルールを明文化しておくことで、対応基準の違いによる混乱や不公平感を避けられます。
また、各種手続きの手順や業務ルールを文書化することも重要です。これにより、誰が担当しても同じ基準で業務を進められるようになり、引き継ぎや教育の負担も軽減されます。
このように、社内ルールを明確に整備しておくことは、業務の再現性を高め、組織全体で統一された効率的な運用体制を築くうえで不可欠といえます。
社内トラブルの未然防止
社内規程を整備することは、労働者とのトラブルを未然に防ぐうえでも有効です。
たとえば、「言った・言わない」や「どこまで許容されるのか」といった曖昧な状況があると、処分や対応をめぐって労働者との間に誤解や不満が生じやすくなります。
事前にルールを明示し、誰もが確認できる状態にしておくことで、不要な摩擦や対立を回避できます。
労働者の働きやすい環境づくり
社内規程は、秩序維持やリスク対策の観点だけでなく、労働者が安心して働ける環境づくりにも大きく貢献します。
就業条件や業務ルールが明確に定められていれば、「自分がどう行動すべきか」「どのような制度が利用できるのか」が分かりやすくなり、日々の業務にも落ち着いて取り組めます。
こうした制度設計は、働きやすさや安心感の向上に寄与し、結果として職場定着率の改善やエンゲージメントの強化にもつながるでしょう。
社内規程と就業規則との違い

「就業規則とその他の社内規程の違いがわかりにくい」と感じる方も少なくありません。
以下、2つの違いを詳しく解説します。
- 就業規則:労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を雇用する企業に作成義務がある、法的根拠のある企業ルールです。必ず記載しなければいけない項目には、労働時間(始業及び終業の時刻、休憩時間など)、休日、賃金、退職に関する事項などがあります。
(参考:1 就業規則に記載する事項 2 就業規則の効力 |労働基準監督署)就業規則は、労使トラブルが発生した際にも判断基準となります。そのため、法令に基づいて作成し、労働基準監督署への届け出も必要です。 - 社内規程:就業規則を補足・具体化するために企業が任意で作成するルールです。
企業独自の方針や業務上の細かい運用ルールを定めるものであり、法的義務はありません。
しかし、企業実務においては、就業規則ではカバーしきれない詳細事項を明文化するうえで不可欠です。※就業規則で定めなければならない事項(絶対的必要記載事項)である、労働時間、賃金、退職等を「社内規程」として整備する場合には法的義務が生じますので、ご注意下さい。
■両者の関係と使い分け
たとえば、就業規則で「懲戒処分を行うことがある」と記載していても、どのような行為が対象となるのか、処分の種類や手続きの流れまでは就業規則に詳細に記されていないケースがあります。
そのような場合に、「懲戒規程」や「服務規律規程」などを別途整備することで、運用ルールを明確化し、現場対応のばらつきを防ぐことができます。
社内規程の主な種類と内容
社内規程には、労働者の就業に関するものから、組織運営や業務管理、近年の働き方や社会的要請に対応したものまで、幅広い種類があります。
ここでは、代表的な社内規定を6つの分野に分けて紹介します。
1.経営・ガバナンスに関する規程
企業理念や企業運営の基本方針、意思決定機関の運営方法など、企業の根幹を成す規程です。
企業の法的枠組みや価値観、取締役会・株主総会の運営ルールなどを明文化し、経営の透明性と統制を確保します。
主な規程と内容例
- 定款:企業の基本ルール
- 企業理念・社訓:企業の存在意義・価値観・行動指針
- 取締役会規程/役員規程:取締役・役員の職務、責任、会議の運営方法
- 株主総会議事運営規程:株主総会の招集、議事進行、議決方法など
- 諸会議規程:経営会議などの構成、開催要件、議決方法など
2.組織体制・職務権限に関する規程
社内組織の構造や各役職・部門における責任と権限、意思決定の流れを明確にするための規程です。
組織運営の効率化と責任の所在の明確化に役立ちます。
主な規程と内容例
- 職務権限規程:役職や部門ごとの決裁・承認などの権限範囲
- 業務分掌規程:部門や担当ごとの業務分担・責任範囲
- 稟議規程:社内の承認フローや決裁ルール
- 倫理規程:法令遵守や企業倫理に基づいた行動規範
3.人事・労務管理に関する規程
就業ルールや賃金制度、福利厚生など、労働者の働き方に直接関わる規程です。
法定義務を含むため、労働基準法など関連法令に基づいた整備が求められます。
主な規程と内容例
- 賃金規程/賞与規程/退職金規程:給与・賞与・退職金の支給基準や計算方法
- 出張旅費規程/転勤旅費規程:出張・転勤時の費用精算や支給条件
- 人事評価(考課)規程:昇給・昇格・賞与などに関わる評価基準と運用方法
4.機密事項や社内資産の取り扱いに関する規程
社内資産や設備、文書等の管理方法を定めるとともに、労働者の安全と健康を守るための体制を規定します。
これらは、日常的な管理業務の効率化と安全な職場環境の整備に寄与します。
主な規程と内容例
- 文書取扱規程:社内文書の保存・管理・廃棄に関するルール
- 社宅管理規程/備品管理規程:社宅や業務用備品の使用・貸与・返却等のルール
- 安全衛生管理規程(労災・防火対策含む):従業員の安全確保と健康保持のための管理体制
5.業務運営・管理に関する規程
業務の円滑な遂行や内部統制の強化を目的に、経理・財務・購買などの業務運用ルールを定めた規程です。
業務運用ルールを明文化することで、組織全体での統一的な対応が可能となり、内部統制の仕組みとしても機能します。
主な規程と内容例
- 経理規程:会計処理・出納・経費精算などの基本ルール
- 予算管理規程:予算の編成・配分・執行・管理に関するルール
- 在庫管理規程:在庫の棚卸・記録・管理の適正化に関するルール
- 購買規程:仕入れの手続き、承認フロー、業者選定などの運用基準
- 債権管理規程/与信管理規程: 取引先の信用調査、与信枠の設定、売掛金管理
- 内部監査規程: 監査の対象範囲、実施手順、結果の報告・是正措置の流れ
6.その他、近年必要性が高まる社内規程
近年は、ハラスメント対策やSNSの利用ルールなど、社会環境や働き方の多様化に対応した社内規程の整備が求められるようになっています。
これらの規程は、企業のコンプライアンス体制強化やリスク管理、労働者の安心・安全な労働環境の整備を目的としており、企業イメージや法令遵守体制にも関わります。
主な規程と内容例
- テレワーク規程:在宅勤務時の労働時間管理、業務指示方法、通信費補助、情報セキュリティ対策など
- 副業・兼業規程:副業の許可基準、申請・承認フロー、競業避止義務の扱い
- ハラスメント防止規程:パワハラ・セクハラ等の定義、相談窓口、調査・対応手順
- 個人情報保護規程: 顧客情報・従業員情報等の収集・利用・管理に関するルール
- ソーシャルメディア利用規程:SNS発信時の注意点、企業名・業務内容に関する投稿の制限など
社内規程に法的拘束力はある?

一定の条件を満たす場合には、社内規程にも労働者に対する法的拘束力が認められる場合があります。具体的には以下のようなケースが該当します。
- 労働契約に「社内規程を遵守する義務」が明記されている場合
- 就業規則に社内規程の適用根拠が明示され、適切な手続きのもとで規程が策定・変更されている場合
運用に当たっては、「労働者に対して十分に周知されたもの」「社会通念上、合理的と判断されるもの」であることを確認することが重要です。
社内規程の作成方法6ステップ
社内規程を整備するには、目的に応じた内容の明確化と関係者との調整を経て、実効性のあるルールとして定着させることが重要です。
以下、社内規程の作成から社内導入までの基本ステップを6つに分けて解説します。
ステップ1:必要な規程の洗い出し
まず初めに行うべきは、「自社に必要な社内規程は何か」を整理することです。
既に規定されている内容と重複や矛盾を避けつつ、以下のような視点で必要項目をリストアップしましょう。
- 過去に発生したトラブルや、従業員から寄せられた相談内容
- 現場からのヒアリング(非効率な業務や曖昧なルールはないかなど)
- 法改正や社会的要請
現場との乖離を防ぐためにも、担当者は総務・人事・現場責任者などから幅広く意見を集めることも重要です。
ステップ2:関連法令の確認と遵守
社内規程は企業が独自に定める内部ルールですが、当然ながら労働関連法令を遵守することが求められます。
規定しておくべき内容やそれに関連する法令を事前に確認しておきましょう。
内容に不安がある場合や制度設計が複雑な場合は、社会保険労務士(社労士)や弁護士などの専門家の助言を得ることで、法的リスクを回避できます。
ステップ3:社内規程案の作成
洗い出した項目と法的要件をもとに、社内規程の原案を作成します。このとき意識すべきポイントは、「具体的かつ実態に即していること」です。
抽象的な表現は解釈のブレを生み、現場で混乱を招く原因になります。
【例:避けたい表現】
×「適切な服装を心がけること」
〇「スーツまたはオフィスカジュアル(Tシャツ・ジーンズ不可)とする」
ステップ4:専門家や関係部署、労働者代表に確認してもらう
社内規程案を作成したら、弁護士や社労士などの専門家に確認してもらうと安心です。
法令違反がないか、リスク回避の観点から不足がないかを確認し、必要に応じて修正を加えます。
また、各部署からの実務的な観点でのフィードバックを受けることで、実態に即した内容へとブラッシュアップできます。
さらに労働者の代表者(または労働組合)からの意見を求めることも、実効性や納得感を高めるうえで有効です。
ステップ5:経営陣の承認を得る
最終案が完成したら、経営者や役員会の承認を得ましょう。
社内稟議や取締役会など、正式な決裁プロセスを経ることで、社内での位置づけが明確になります。
また、このタイミングで以下のような文書管理の整備も行っておくとよいでしょう。
- 制定日や施行日
- 担当部署・管理責任者の明記
- 改訂履歴の記録方法の設定
これにより、後の見直しや社内周知の際にもスムーズな運用が可能になります。
ステップ6:労働者への周知と説明
最終的な規程を決定したら、労働者にしっかり周知します。
周知方法としては、紙による配布だけでなく、社内ポータルへの掲載、説明会や動画配信、メール通知など、複数の方法を併用することが望まれます。
社内規程が労働契約の一部として効力を持つためには、「労働者がいつでも確認できる状態にあること(知り得る状態)」が法的要件となります。そのため、単なる掲示だけにとどまらず、内容の趣旨や適用範囲についての説明責任を果たすことが重要です。
また、Q&A形式の補足資料や、管理職向けの解説資料も併せて用意するとより効果的です。
社内規程の運用における注意点

社内規程は、作成して終わりではなく、実際に現場で活用されることが重要です。形骸化を防ぎ、労使トラブルや法的リスクを回避するためには、以下のような視点で運用と改善を行う必要があります。
1.定期的に見直して更新する
社内規程は時間とともに実態とずれていくことがあります。また、法改正・制度変更・トラブル発生時なども見直しが必要です。
年1回の点検をルール化し、見直しの主導部門(人事部・総務部・法務部など)が主体となって棚卸しする体制を整えましょう。
2.法律違反がないか確認する
社内規程を作成する際は、会社法、労働基準法、個人情報保護法などの関連法令に反しないようにしなければなりません。
社内独自のルールであっても、法令に反する内容を含んでいる場合は、社内規程自体が効力を持たず、行政指導や是正勧告の対象となるおそれもあります。
法的観点に不安がある場合は、弁護士や社労士などの専門家に確認してもらうと安心です。
3.労働者への周知を徹底する
規程の効力は、労働者に内容が伝わっていることが前提です。
社内ポータルへの掲載、研修、変更点の案内資料配布などで継続的な周知と理解促進に努めましょう。
まとめ|社内規程の整備は企業の信頼性向上とリスク管理につながる
本記事では、社内規程の基本的な役割から、作成手順、運用・見直しのポイントまでを詳しく解説しました。
社内規程は、企業運営の効率化や秩序の維持に加え、労働者との信頼関係の構築や、労務リスクの予防にも大きく貢献する重要な基盤です。
ただし、法改正や働き方の多様化等、変化に対応できていない規定は、逆にリスク要因となるおそれもあります。そのため、規定が現行法や社内実態に合致しているか定期的に見直 さなければなりません。
社内だけで判断が難しい場合や法的観点に不安がある場合には、弁護士や社労士など専門家に確認してもらうこともおすすめです。
社内規定の整備について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めたうえで依頼しましょう。