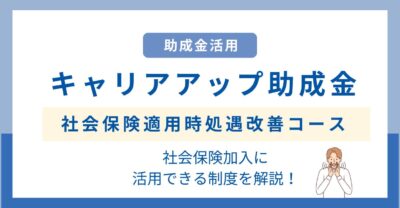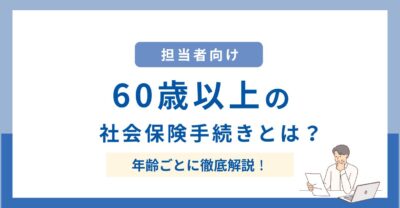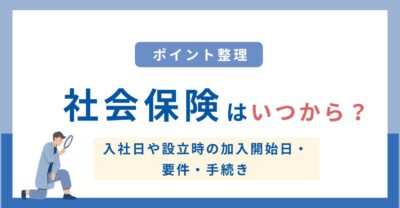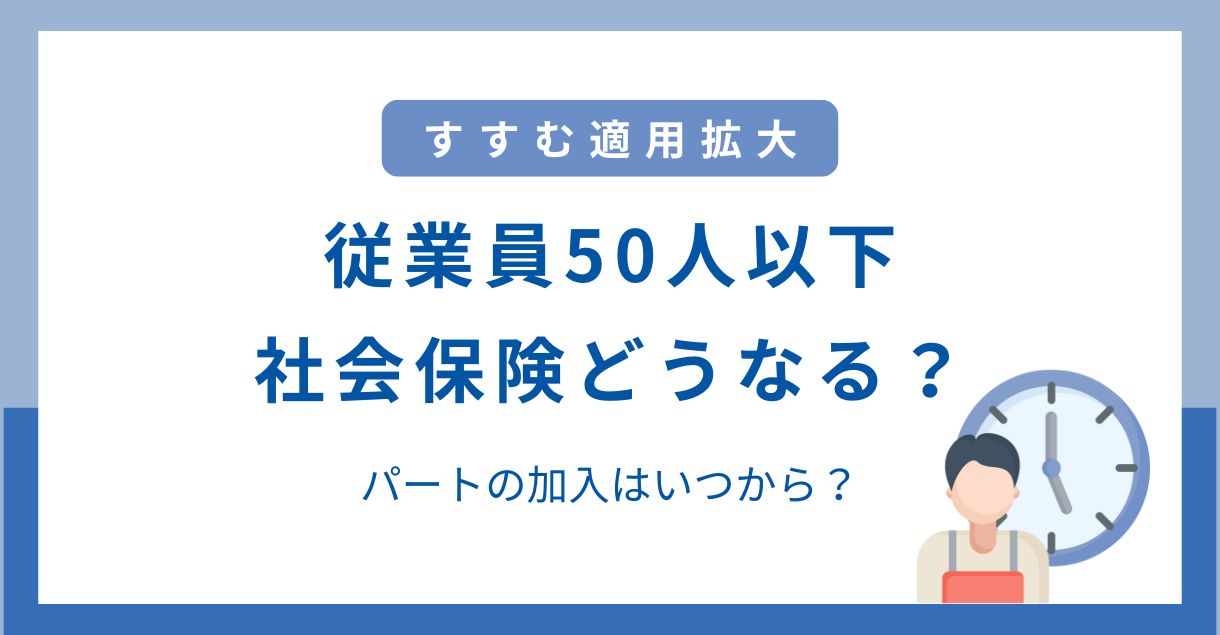
50人以下企業のパートの社会保険はどうなる?最新ルールと加入条件を解説!
2022年・2024年の法改正を経て、社会保険の適用範囲は今後さらに広がっていく見通しです。
なかでも注目されているのが、2027年10月から段階的に実施される「社会保険の適用拡大」です。これにより、従業員が50人以下(厚生年金保険の被保険者数でカウントします)の企業でも、パートタイム従業員への社会保険加入が義務化されることになります。
「うちは小規模企業だから関係ない」と思っていた経営者や人事担当者も、制度改正の影響を避けて通ることはできません。
本記事では、2025年10月現在の制度に基づき、小規模企業における社会保険の加入要件や扶養の扱い、未加入によるリスク、そして2027年10月以降に向けた備え方までを網羅的に解説します。
「自社はいつ、どのように対応すべきか?」その疑問に答えを出したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
【2025年最新】社会保険の加入条件とは

社会保険(健康保険・厚生年金)は、企業と従業員の条件によって、加入が義務づけられる制度です。
まず、企業が「適用事業所」に該当するかどうかが判断され、そのうえで、各従業員が「被保険者」となる基準を満たしているかどうかで適用がきまります。
ここでは、2024年10月の法改正を踏まえた、2025年時点の最新ルールを整理します。
| ※本記事では、企業規模を説明する際の「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数(社会保険に加入している正社員や条件を満たすパート社員など)を指します。単なる在籍人数とは異なりますので、ご注意ください。 |
【2025年最新(企業・従業員別)|社会保険の加入条件まとめ】
| 区分 | 条件 |
| 企業の加入義務 |
|
| ▼▼▼ 企業に加入義務が「ある」と判断された場合 ▼▼▼ | |
| パートタイム従業員への適用 | 以下の条件をすべて満たす従業員は加入の必要がある
|
※社会保険の非適用業種:飲食業、理美容業、農林水産業、旅館業など
なお、この非適用業種については、2029年10月から廃止されることになっています。
社会保険の概要や種類、企業に求められる役割については、「社会保険とは?概要から保険料の計算方法まで徹底解説!」の記事でわかりやすく解説しています。
社会保険の従業員数の詳しいカウント方法については、以下の記事をご参考ください。
(関連記事:社会保険の加入義務とは?パートの適用拡大と企業の対応ポイントを解説)
では、従業員が50人以下の企業ではどうなるのでしょうか?
次章では、そうした中小企業における社会保険の対応ルールをわかりやすく解説します。
50人以下の企業で働く場合、社会保険はどうなる?

社会保険は、従業員の勤務実態に応じて加入の可否が判断される制度です。
従業員数が50人以下の企業は従来どおり、個人の働き方や雇用形態によっては加入対象か否かが判断されます。
【社会保険に加入が必要になるケース ※企業規模は問わない】
- 雇用形態が正社員である
- パートタイム従業員で、所定労働時間・労働日数ともに、正社員の4分の3以上である
【原則、加入義務がないケース】
- パートタイム従業員で、所定労働時間・労働日数が、正社員の4分の3未満である
なお、2026年10月からは制度が段階的に見直され、パートタイム従業員への社会保険適用が拡大されていくことになっています。
最新の情報を確認し、自社の体制や雇用状況に応じた準備を進めておくことが求められます。
従業員50名以下の企業でも社会保険に加入できるケース

従業員が50人以下の企業においては、原則として、所定労働時間・労働日数が正社員の4分の3未満であるパートタイム従業員の社会保険の加入義務はありません。
ただし、労使合意の上、一定の手続きを経て社会保険への加入が可能です。
具体的には、事業主が「任意適用事業所」または「任意特定適用事業所」として厚生労働省へ申請し、認可を受ける必要があります。
この2つの事業所の違いは以下の通りです。
- 任意適用事業所:加入義務のない個人事業所が、事業所全体で社会保険に加入できる制度
- 任意特定適用事業所:従業員数が50人以下の事業所が、一定の要件を満たすパートタイム従業員に社会保険を適用できる制度
ここでは、中小企業でも導入を検討するケースが増えている「任意特定適用事業所」について詳しく解説します。
「任意特定適用事業所」とは
「任意特定適用事業所」とは、従業員数50人以下の企業であっても、一定基準を満たすパートタイム従業員に社会保険を適用できる制度です。
この制度を活用することで、企業規模にかかわらず、以下の一定の条件を満たすパート社員などにも、健康保険・厚生年金が適用されるようになります。
【パートタイム従業員の適用要件】
- 所定労働時間が週20時間以上
- 雇用期間が2か月を超える見込み
- 月額報酬が8万8,000円以上(基本給+固定手当)
- 学生でない
非正規雇用の待遇改善や人材確保の面でも注目されており、導入を検討する中小企業が増えています。
「任意特定適用事業所」になる条件
企業が「任意特定適用事業所」として認定を受けるには、以下の条件を満たし、所定の手続きを行う必要があります。
【申請に必要な条件】
- 社会保険に加入している従業員の過半数から同意書を得ること
- 所轄の年金事務所へ任意特定適用事業所申出書を提出すること
制度を導入する際は、対象従業員を正確に把握し、労使間で丁寧に協議して合意を得ることが大切です。
社内の体制や契約内容の整理とあわせて、計画的に検討を進めましょう。
従業員が社会保険の扶養の範囲内で働くには

中小企業の現場では、パートやアルバイトから「扶養の範囲内で働きたい」「社会保険への加入は避けたい」といった相談を受けることも多いのではないでしょうか。
特に人手不足の中、希望に応じた雇用条件をどう整えるかは、労務管理上の大きな課題となります。
従業員が扶養内で働くためには、被扶養者と認定されることに加え、勤務時間や報酬などにも一定の上限があります。
【被扶養者の認定条件(一般的な目安※1)】
- 被保険者に生計を維持されている
- 年間収入※2が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満の場合は150万円未満)である
- 被保険者本人の収入の2分の1未満である
(被保険者との関係によって、同居が条件となる場合もあり)
【労働条件】
- 勤務時間が週20時間未満であること
- 月額報酬が8万8,000円以下であること
- 勤務先が「任意特定適用事業所」として認可を受けていないこと
※1:他にも細かい要件がありますので、詳しくは加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合)に確認してください。
※2:ここでの収入判定基準は、「税法上の扶養(103万円・150万円など)」とは異なり、社会保険制度に基づいて適用されます
企業側は、制度の誤解を防ぐためにも、従業員に対して社会保険の適用条件を正確に説明・共有することが重要です。
扶養内に関する改正内容や、年収の壁について詳しく知りたい方は、「【2025年最新】“パート扶養がなくなる”は誤解?年収の壁一覧とポイント整理」の記事もあわせてご覧ください。
社会保険の適用拡大で50人以下の企業で働くパートタイム従業員も対象に!いつから?

現在、パートタイム従業員に対する社会保険の適用拡大は、従業員が「常時51人以上」の企業に限られています。
しかし、2025年6月に成立した改正年金法により、この企業規模の要件を段階的に引き下げ、2035年10月以降にはすべての企業が対象となることが決まっています。
確定した見直しのスケジュールは以下の通りです。
【適用開始スケジュール】
| 適用開始時期 | 対象企業規模(厚生年金の被保険者数) |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 企業規模要件を撤廃(すべての企業が対象) |
出典:厚生年金加入の企業規模要件撤廃 2035年10月に見直す案 厚労省|NHK NEWS WEB
この改正により、小規模な企業でも、一定の条件を満たすパートタイム従業員が社会保険の対象となります。
月額報酬の条件は、2028年6月20日から3年以内に撤廃されることが決まっています。さらに2035年10年以降は、社会保険適用条件が「労働時間」のみになることが検討されています。こうした制度の見直しにより、企業は人件費の増加や労務体制の見直しといった課題に直面することが想定されます。
一方で従業員は、傷病手当金や出産手当金、老齢厚生年金などの保障を受けられるようになり、将来への安心感が得られるでしょう。
特に中小企業においては、制度の段階的な拡大を見据え、早めに社内体制を整備しておくことが重要です。
パートタイム従業員の社会保険加入を怠った場合の企業リスク

企業が、本来対象となるパート従業員を社会保険に加入させていない場合、重大な法的・経営的リスクが発生します。
以下、パートタイム従業員への社会保険加入を怠った場合の企業へのリスクを3つ解説します。
保険料を2年前までさかのぼって支払う必要がある
本来、社会保険の適用対象であったパートタイム従業員を加入させていなかった場合、最大で2年間まで未納保険料を遡って徴収されることになります。
本来であれば従業員が負担する保険料を、事業者が立て替えるケースもあります。
さらに、既に退職した労働者が対象であった場合は、企業が労使折半分を含めた保険料を全額負担するケースもあるなど、経営的負担が大きくなるため注意が必要です。
未納保険料には追徴金が加算される
社会保険の加入義務があるパートタイム従業員を未加入のままにしていた場合、保険料の未納分に加えて追徴金(加算金)として未納額の10%を支払う義務が生じます。
未加入期間が長くなるほど支払わなければいけない保険料の総額は増加し、対象となる従業員の人数が多いほど企業の負担も大きくなります。
今後、社会保険の適用範囲はさらに広がり、対象となるパートタイム従業員も増える見込みです。
企業には、対象となる労働者を正確に把握し、漏れなく加入手続きを行うことが求められます。
こうした経営リスクや実務負担を未然に防ぐためにも、早めに社内体制を整え、スムーズに対応できる仕組みを構築しておきましょう。
6か月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金を受ける
社会保険の加入義務があるパートタイム従業員に対して正当な理由もなく加入させなかった場合、刑事罰の対象となることがあります。
具体的には、下記のような場合に6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
- 日本年金機構などからの調査に対し、必要な書類や資料の提出を拒否した場合
- 職員の質問に対して正当な理由なく答えなかった場合
- 調査の場で虚偽の説明をした場合
- 検査を拒否、妨害、または意図的に避けた場合
(参考:厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取組|日本年金機構)
こうした行為は単なる手続き漏れではなく、厚生年金保険法第100条に基づき「悪質な違反」と見なされます。
企業が調査への協力を怠ったとみなされた場合には、行政指導だけでなく刑事罰の対象となることもありますので、速やかに対応できる体制を整えておきましょう。
まとめ|50人以下の企業もパート従業員の加入準備を
本記事では、2025年時点の社会保険(健康保険・厚生年金)制度や、今後予定されている適用拡大について解説しました。
現在、パートタイム従業員への社会保険の適用は、常時従業員51人以上の企業が対象とされていますが、2027年10月以降は50人以下の企業も段階的に対象に含まれることとなります。
これにより、小規模事業者にも一定の労働時間や賃金要件を満たすパートタイム従業員には、社会保険への加入義務が発生する可能性があります。
もし加入させるべき従業員を見落としていた場合、保険料の遡及徴収や追徴課税、刑事罰のリスクに加え、企業イメージの低下や採用難につながるおそれもあります。
適用拡大を見据え、今のうちから就業実態を確認し、加入対象となるパート従業員の把握と社内対応の準備を進めることが重要です。
制度対応や社内整備に不安がある場合は、専門家である社労士に相談し、正確で効率的な管理体制の構築を図りましょう。
パートタイム従業員の社会保険について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めたうえで依頼しましょう。