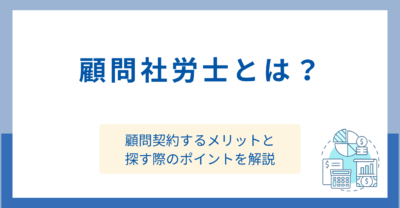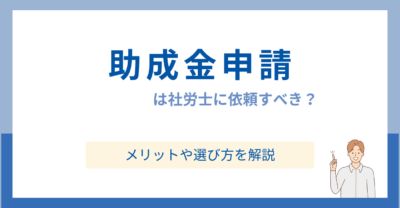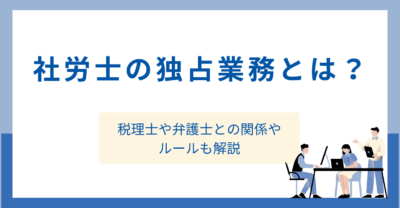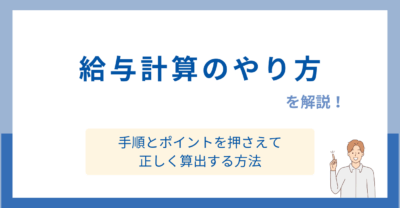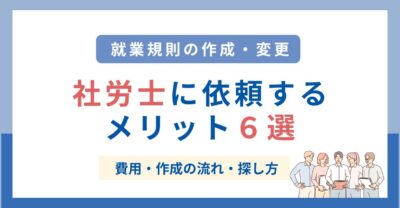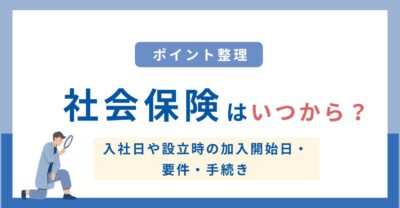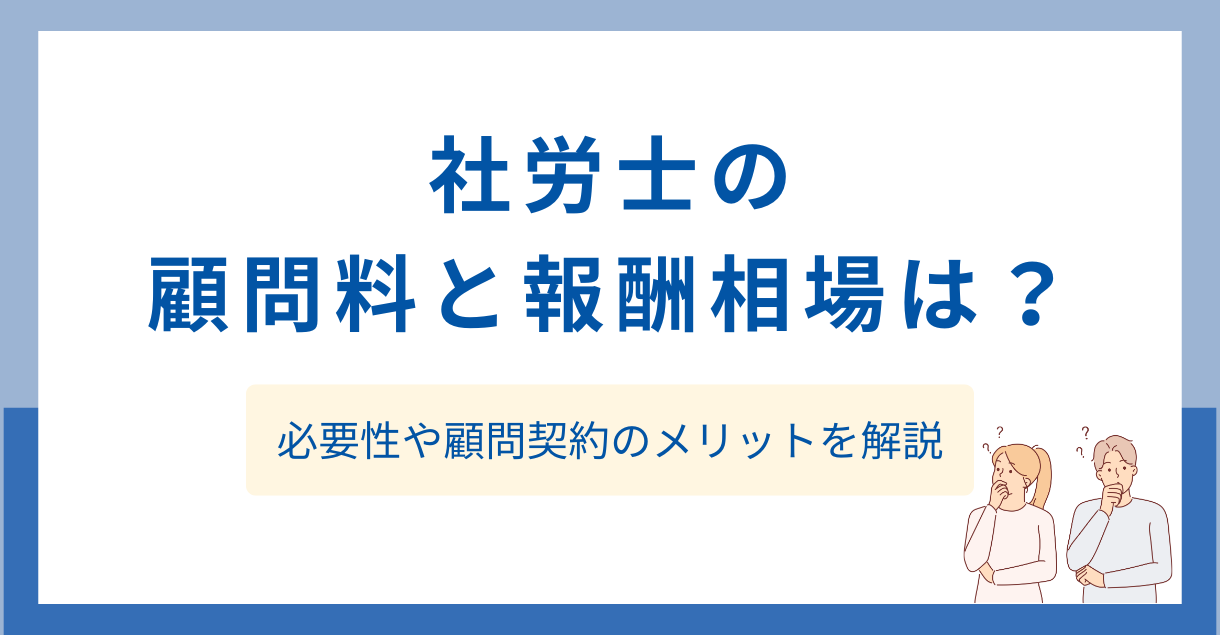
社労士の顧問料と報酬相場は?必要性や顧問契約のメリットを解説
社労士は、労務管理や社会保険の手続きといった複雑な業務をサポートしてくれる専門家です。存在は知っていても、顧問契約で依頼できる業務内容や顧問料の相場を把握している方は少ないのではないでしょうか。
本記事では、社労士の顧問料の相場を紹介するとともに、社労士の必要性や顧問契約のメリット、デメリットについて解説するので、ぜひ参考にしてください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
日本最大級の社労士検索サイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
社労士の顧問料の相場
社労士の顧問料の相場は、主に下記の要素で異なります。
- 従業員数
- 契約に含まれる業務内容
- スポット契約料金
ここでは、従業員数により顧問料が変動する理由や、業務内容ごとの料金の相場を解説します。
従業員数による顧問料の相場
従業員数による顧問料の相場は、2万円~8万円程度です。労働・社会保険に関する基本的な手続きや相談を依頼するのみであれば、こちらの料金が該当します。従業員数別の顧問料の相場を表にまとめました。
| 従業員数 | 顧問料の相場 |
|---|---|
| 4名以下 | 2万円程度 |
| 5~9名 | 3万円程度 |
| 10~19名 | 4万円程度 |
| 20~29名 | 5万円程度 |
| 30~49名 | 6万円程度 |
| 50名以上 | 8万円程度 |
※金額は一般的な顧問料の相場であり、社労士事務所によって異なります。
社労士事務所によっては従業員1人あたりの単価を定めている場合もあるため、依頼する社労士を探す際は料金体系について必ず確認しましょう。
業務内容ごとの顧問料の相場
業務内容ごとの顧問料の相場を表にまとめました。
| 業務内容 | 顧問料相場(月額) |
|---|---|
| 相談のみ | 従業員数4名以下:1万円~1万5,000円 従業員数5名~9名:1万5,000円~2万円 従業員数10~19名:2万5,000円~3万円 従業員数20~29名:3万5,000円~4万円 従業員数30~49名:4万5,000円~6万円従業員数50名以上:6万円~8万円 |
| 給与計算 | 従業員数4名以下:1万円~3万円 従業員数5名~9名:1万5,000円~3万5,000円 従業員数10~19名:3万円~5万円 従業員数20~29名:4万円~6万5,000円 従業員数30~49名:6万円~10万円従業員数50名以上:別途相談 |
※金額は一般的な顧問料の相場であり、社労士事務所によって異なります。
従業員数が増加すると対応に手間がかかることから、顧問料も増加します。さらに、対応にかかる手間や時間を含めた実工数による変動もあるでしょう。
スポット契約料金の相場
顧問料のほかにも、スポット契約料金の相場も紹介します。スポット契約とは、社労士に単発で依頼する契約のことです。一度作成するのみで完結する業務内容が多くあります。スポット契約料金の相場を表にまとめました。
| 業務内容 | 料金相場 |
|---|---|
| 就業規則の作成 | 5万円~20万円程度 |
| 就業規則の修正 | 2万円~5万円程度 |
| 賃金規程などの作成 | 3万円~10万円程度 |
| 36協定の作成 | 3万円程度 |
| 労働・社会保険の手続き代行 | 従業員5名以下の場合で5万円~8万円程度 |
| 労務管理に関する相談 | 1万円程度/1時間 |
| 助成金の申請 | 着手金:3万円~15万円程度 報酬金:助成額の15~25% |
| ADR(紛争解決代理業務) ※特定社会保険労務士のみ |
着手金:5万円程度 報酬金:解決金額の10~20% |
※金額は一般的な顧問料の相場であり、社労士事務所によって異なります。
まずは社労士への無料相談を活用して、必要な費用の確認や社労士活用のイメージをもっていただくと良いでしょう。社労士への無料相談については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:社労士に無料相談したい方必見!電話やメールで相談できる窓口を紹介)
社労士の業務内容
社労士の業務は大きく「1号業務」「2号業務」「3号業務」の3つに分けられます。社労士に依頼できる業務内容は、下記のように分けられています。
都道府県の自治体をはじめとする、厚生労働省以外が支給する助成金や奨励金などの場合は社労士以外でも委託できます。しかし、厚生労働省の助成金は、社労士のみ代理申請が可能です。
社労士の業務内容については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:社労士に無料相談したい方必見!電話やメールで相談できる窓口を紹介)
社労士との顧問契約の必要性
社労士との顧問契約の必要性は、会社の状況により異なります。スポット契約で済む場合もあれば、顧問契約したほうがよい場合もあるため、自社の状況を確認してみてください。
表では、社労士との顧問契約の必要性について具体的な企業の課題と、社労士による解決策の一例をまとめました。
| 企業の課題 | 社労士による解決策の一例 |
|---|---|
| 人手不足に陥っている | 働き方改革を通じて雇用環境を整え、離職率を改善 助成金を活用した採用活動を提案 |
| 事務作業のミスが目立つ | 社労士による給与計算・社会保険手続き代行でミス削減 システム導入や業務フロー改善の提案 チェック体制の構築で効率化 |
| 従業員数が10人以上で就業規則が必要 | 就業規則の作成・労働基準監督署への届出を代行 会社のルールを明確化し、従業員の安心感を向上 トラブル予防で職場環境を改善 |
| 事業拡大に伴い労務管理が複雑化 | 規模拡大に伴う労務管理の複雑化に対応 新たな法令や制度適用に備える 従業員の多様な働き方に対応する労働環境を提案 |
社労士と顧問契約すれば、さまざまな課題を解決できる可能性が高いため、表に当てはまる方は、ぜひ相談してみてください。
顧問社労士については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:顧問社労士とは?顧問契約するメリットと探す際のポイントを解説)
社労士と顧問契約を結ぶメリット
健全な会社運営や業務の効率化など、社労士との顧問契約には多くのメリットがあります。内容を把握して社労士との顧問契約を検討しましょう。
- 法改正などの動向に素早く対応できる
- 労使間のトラブルを予防できる
- 助成金に関する相談ができる
- 仕事を効率化できる
- 専任の担当者を採用する場合より安価なケースがある
法改正などの動向に素早く対応できる
社労士と顧問契約を結ぶと、定期的に最新の法改正情報を提供してもらえるため、法改正の動向に素早く対応できることがメリットです。
人事労務に関する法律や制度は複雑、かつ頻繁に法改正が行われることから無自覚なまま法律違反を犯してしまうケースも少なくありません。しかし、社労士と顧問契約を結んでいれば、法的リスクの軽減を期待できます。
顧問社労士は、法改正の情報を提供してくれるほか、会社側で必要な対応や情報をわかりやすく教えてくれます。そのため、経営者や担当者が自ら法改正情報を調べる手間がかかりません。
労使間のトラブルを予防できる
社労士と顧問契約を締結すると、従業員とトラブルになりそうな点を見つけ出してくれるため、トラブルを未然に防げます。トラブルになりやすい主な原因は、就業規則や賃金規程、雇用契約書の未整備をはじめ、運用がそれぞれ定められているものと合っていないことなどです。
例えば、会社の賃金規程があいまいな場合、多額の未払い残業代が発生し、従業員から請求されるリスクがあります。賃金規程を正しく作成しなければ、労働基準法に抵触する可能性もあるため、注意が必要です。
しかし、社労士と顧問契約していれば例のような不備を徹底的に洗い出してくれるため、トラブルを未然に防げるほか、従業員も安心して働けます。
助成金に関する相談ができる
社労士と顧問契約すると助成金に関する相談ができることもあるため、新たな施策を導入しやすくなるメリットがあります。企業が利用できる助成金は種類が多いことから、自社に合った制度を選べない場合も少なくありません。
しかし、社労士と顧問契約を締結すれば、自社に合った助成金の最新情報を提供してくれるので、見逃すことなく制度を活用できます。また、顧問社労士に申請手続きの代行を依頼し、会社側が行う手続きの負担を軽減できることも特徴です。
社労士への助成金申請の依頼については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:助成金申請は社労士に依頼すべき?メリットや選び方を解説)
仕事を効率化できる
社労士と顧問契約を締結すると、顧問社労士に一部の業務を一任できるため、仕事を効率化できます。社労士に社会保険や労働保険などの手続きを一任すれば、経営者がバックオフィス業務にかける時間の軽減が可能です。
また、コンサルティングを依頼すれば、人事制度の導入方法や労務管理におけるシステムの導入に関してアドバイスを受けられます。そのため、アドバイスをもとに企業の業務効率を高める基盤や、体制の構築も可能です。
専任の担当者を採用する場合より安価なケースがある
社労士と顧問契約を締結すると、専任の担当者を採用するより安価な場合があるため、コストを抑えられます。人事・労務に関する手続きは、社労士に外注するほうが、コスト削減につながる可能性があるので、検討してみてください。
自社で従業員に人事や労務に関する手続きや処理を担当させる場合、採用コストのみではなくマネジメントや教育のコストが発生します。人事・労務の専門家である社労士なら、マネジメントや教育は不要です。
また、従業員数が増加すると社会保険の手続きや給与計算などの事務作業が増え、業務量が増加すると、従業員を増員しなければなりません。社労士に外注した方が経費を削減できるケースが多いため、コスト面からも社労士との顧問契約を検討しましょう。
社労士と顧問契約を結ぶデメリット
社労士と顧問契約を結ぶ際は、デメリットについても把握しましょう。
- 顧問料が発生する
- 社会保険関係の業務に携わる従業員のスキルアップが必要
顧問料が発生する
社労士と顧問契約をすると顧問料が発生するため、ランニングコストがかかる点がデメリットです。
社労士の顧問料は、依頼する業務内容や従業員数により異なります。そのため、顧問料が会社経営の予算内で適正なのかどうか慎重に見極めなければなりません。
社労士と顧問契約を締結する際は、契約前に料金と業務範囲を確認した上で、費用対効果を見極めましょう。
社会保険関係の業務に携わる従業員のスキルアップが必要
社労士と顧問契約をして業務を委託することで、社会保険や労務管理に関する手続きの負担を軽減できます。しかし、業務を完全に社労士へ任せられるわけではなく、自社側にも一定の知識を持つ担当者が必要です。場合によってはスキルアップのための研修や教育が求められ、追加の費用や時間がかかる可能性があります。
例えば、社会保険業務を社労士に委託した場合、自社で社会保険関連の業務を行う負担は軽減されるものの、自社担当者と連携できていなければ業務がスムーズに行われないケースもあります。
それを防ぐためには、社労士と顧問契約を締結する前に、担当者の配置やスキルアップの計画を立てておくことが重要です。
社会保険業務については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:社会保険とは?概要から保険料の計算方法まで徹底解説!)
社労士に顧問を依頼する際のポイント
最後に、社労士に顧問を依頼する際のポイントを解説します。ポイントを把握してから依頼すれば、納得できる形で顧問社労士を雇用できます。
- 契約前に社労士の実績や評判をチェックする
- 契約内容を明確化する
- 個人情報の漏えいリスクと対策を確認する
- 社労士とのコミュニケーション手段を確認する
- スポット契約にかかる費用を確認する
契約前に社労士の実績や評判をチェックする
社労士と顧問契約する際は、契約前に社労士の実績や評判をチェックしましょう。実績や評判には、信頼性や信用性を確認できる内容が含まれているため、入念なリサーチが必要です。チェックすべき項目として、以下の内容を参考にしてみてください。
- 得意な領域
- これまでの実績
- 実務経験年数
- 評判・口コミ
契約内容を明確化する
社労士に顧問を依頼する際、契約内容を事前に明確化しないまま顧問契約すると後々のトラブルにつながる可能性があります。明確化したほうがよい契約内容は、以下のとおりです。
- 料金
- サービス内容
- 契約期間
- 契約解除の条件
個人情報の漏えいリスクと対策を確認する
個人情報の漏えいリスクに対して、社労士がどのような対策をしているのかを確認しましょう。
社会保険手続きは給与情報やマイナンバーなど、従業員の個人情報を取り扱います。依頼する社労士はもとより、社労士事務所全体のセキュリティ対策も重要です。具体的には、社労士によるヒューマンエラーやサイバー攻撃を受けた場合などについて、どのような対策をしているのかを確認してみてください。
また、プライバシーマークなどの第三者機関認証の有無、契約後に定期的な監査を実施できるかなども確認しましょう。
社労士とのコミュニケーション手段を確認する
社労士に顧問を依頼する際は、自社と社労士の双方が利用しているコミュニケーションツールやアプリを契約前に確認しましょう。事前の確認が不足すると、契約後にコミュニケーション手段の種類が限定される場合があるため注意が必要です。
例えば、メールでやり取りする場合、社労士から返答をもらえるまで数日かかるケースもあります。対処法として、いつでも内容を確認できる連絡手段の設定がおすすめです。
スポット契約にかかる費用を確認する
社労士と顧問契約した場合でも、別途スポット契約にかかる費用を確認しましょう。契約外の業務を依頼する際は、スポット契約の費用が顧問料とは別に発生することが一般的です。
そのため、社労士に顧問を依頼する際は業務内容の確認に加えて、顧問契約中のスポット契約業務についても確認が必要です。また、顧問契約しないとスポット契約業務を受けてもらえないケースもあるため注意しましょう。
社労士を活用してさらなる事業の成長を目指そう
今回は、社労士の顧問料の相場や社労士と顧問契約する際のメリットやデメリット、依頼する際のポイントなどを解説しました。
社労士と顧問契約することで、業務負担の軽減や労使間トラブルを防げるメリットがあります。顧問料として固定費が発生するものの、いつでも相談できる人事・労務の専門家がいると安心です。
さまざまな助成金も活用しやすくなるため、社労士と顧問契約して事業の成長を目指してみてください。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この日本最大級の社労士検索サイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談は無料の場合も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。