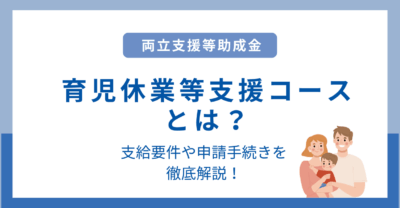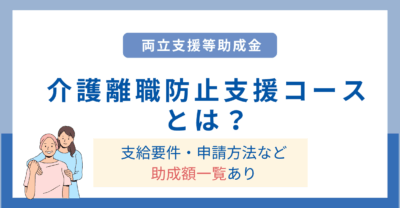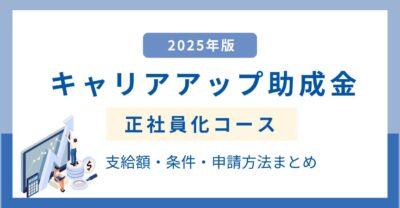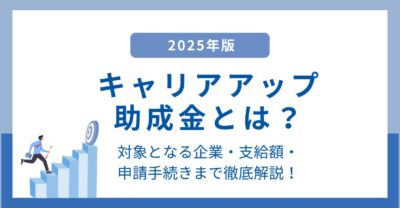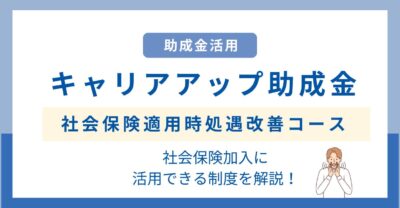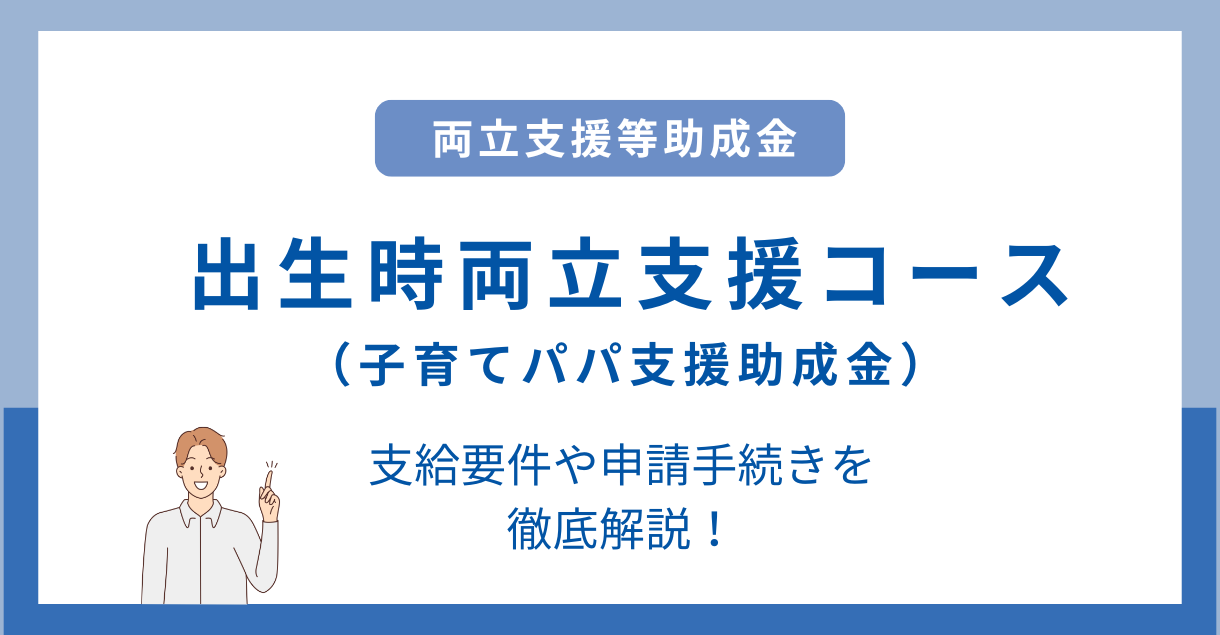
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは?支給要件や申請手続きを徹底解説|両立支援等助成金
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は、男性労働者の育児休業取得を支援する取り組みを行う企業に対して、国から助成金が支給される制度です。
男性育休の取得促進は、労働者のワークライフバランスの向上や職場の働きやすさ改善に加え、優秀な人材の確保や企業イメージの向上にもつながります。
一方で、制度の導入や申請には、就業規則の見直しや書類の準備など、実務面での細やかな対応が求められます。申請内容に不備があると助成金を受給できないケースもあるため、正確な制度理解が欠かせません。
本記事では、出生時両立支援コースの概要、第1種と第2種の違いや支給要件を解説します。また、助成金額一覧や申請の流れ、注意点まで、実務担当者に役立つポイントをわかりやすく整理しています。
ぜひ最後までお読みいただき、自社での制度活用や円滑な助成金申請の参考としてお役立てください。
※本記事は令和7(2025)年度の制度内容を元に作成しています。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは?|両立支援等助成金

「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」(以下、出生時両立支援コース)は、男性労働者の育児休業取得を支援する、中小企業を対象とした助成制度です。
この制度は厚生労働省が実施する「両立支援等助成金※」の一環として、男性労働者が育児休業を取得しやすい環境を整えることで、育児休業取得率を向上させることが目的です。
※両立支援等助成金とは、仕事と家庭の両立を推進する職場環境整備に取り組む企業を支援する制度です。2025年現在、6コースの支援制度があり、労働者が働き続けやすい環境を整えることで、離職防止や人材の安定確保につなげることを目的としています。
両立支援等助成金の全体像や各コースの概要については、こちらの記事で詳しく解説しています。
>【一覧表あり】両立支援等助成金とは?中小企業が知っておきたい6つのコースと申請方法
2024年度の制度見直しを経て、2025年度からは出生時両立支援コースの助成金額や支給要件に一部変更が加えられました。
主な変更点は次の2点です。
- 「第2種」は、「第1種」受給の有無に関わらず申請可能に
- 「第2種」の要件緩和
これにより、企業にとって活用しやすく、男性労働者の育児休業促進につながる仕組みに強化されています。第1種と第2種の内容については次の「助成金の種類」で解説します。
助成金の種類
出生時両立支援コースには、第1種と第2種の助成金に加えて、「育児休業等に関する情報公表加算」が設けられています。
1.第1種:男性労働者の育児休業取得
企業が「雇用環境整備」や「業務体制整備」に取り組み、そのうえで男性労働者が子の出生後8週間以内に育児休業を開始し、連続5日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。
2.第2種:男性の育児休業取得率の上昇等
事業年度(=事業主の会計年度)あたりの男性労働者の育児休業取得率※の値が、以下のいずれかを達成した場合に支給されます。
- 1事業年度で30ポイント以上上昇し、50%以上を越えた
(例えば、もともと40%であり、70%以上になった場合) - 2事業年度で連続70%以上となった
※育児休業取得率は以下の計算式で求められます。
育児休業取得率(%:小数第1位以下切り捨て)=
一事業年度中に育児休業を取得した男性労働者数/一事業年度中に配偶者が出産した男性労働者数
3.育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業制度や取得状況を、支給申請日までに厚生労働省が運営する「両立支援のひろば|一般事業主行動計画公表サイト」で公表した場合に、加算支給されます。
情報公表加算の申請方法と注意点は後述の「育児休業等に関する情報公表加算の申請方法と注意点」で解説しています。
対象となる企業は中小企業のみ
出生時両立支援コースは、中小企業のみが対象の助成制度です。
両立支援等助成金制度における「中小企業」とは、業種ごとに資本金(出資金)または常時雇用する労働者のいずれかが、下記基準以下である企業を指します。
| 業種 | 資本金または出資金 | 常時雇用する労働者数※ | |
|---|---|---|---|
| 小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
| その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
出典:厚生労働省|2025(令和7)年度両立支援等助成金のご案内(P.4)
※常時雇用する労働者とは、以下の両方を満たす者を指します。
- 2か月を超えて連続雇用される者(期間の定めがなく雇用される者、2か月を超える契約期間で雇用される者を含む)
- 週の所定労働時間が当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同じである者
申請を検討する際には、まず自社がこの中小企業の定義に該当するかを確認しておきましょう。
出生時両立支援コースの助成金額一覧

出生時両立支援コースの助成金額は、以下のとおりです。
【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の助成金額一覧】
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 第1種:男性労働者の育児休業取得 | 1人目:20万円 ※雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合:30万円 2・3人目:各10万円 |
| 第2種:男性の育児休業取得率の上昇等 | 育児休業取得率が、申請年度の前年度を基準として30ポイント以上上昇し、50%以上になった(もしくは事業主の会計年度において2年連続で70%以上となった)場合:60万円 ※プラチナくるみん認定事業主の場合(申請時):15万円加算 |
| 育児休業等に関する情報公表加算:2万円 ※第1種(1~3人目のいずれか)または第2種の、いずれか1回限り |
|
【注意事項】
- 同一事業主について、第1種は3人目まで、第2種は1回限りです。
- 第2種の受給後に第1種の申請はできません。
- 令和3年度以前に旧制度(男性労働者の育児休業・育児目的休暇)を受給している事業主であっても、新たに支給要件を満たせば申請が可能です。
出典:厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)|出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
出生時両立支援コースは、区分や条件によって金額は異なりますが、最大77万円(プラチナくるみん認定事業主+第2種+情報公表加算の場合)の助成金が支給されます。
申請可能な区分や加算要件を確認し、自社にとって最適な形で制度を活用していきましょう。
出生時両立支援コースの支給要件

「第1種」と「第2種」のそれぞれの支給要件は、以下のとおりです。
第1種の支給要件
①「育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置※」のうち、定められた数の対策を社内で実施していること
▼実施が必要な雇用環境整備措置の数
| 助成金の対象人数 | 出生時育児休業(産後パパ育休)申出期限が2週間前まで | 出生時育児休業(産後パパ育休)申出期限が2週間前より長い |
|---|---|---|
| 1人目 | 2つ以上 | 3つ以上 |
| 2人目 | 3つ以上 | 4つ以上 |
| 3人目 | 4つ以上 | 5つ(全て) |
②育児休業を取得する従業員の業務について、代替者の業務内容を見直すための社内ルールを整備し、そのルールに基づいた業務体制の整備をしていること
③男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を連続で取得していること
▼要件となる育児休業歴日数と育児休業期間中の所定労働日数
| 助成金の対象人数 | 育児休業の歴日数 | 育休中の所定労働日数 |
|---|---|---|
| 1人目 | 連続5日以上 | 4日以上 |
| 2人目 | 連続10日以上 | 8日以上 |
| 3人目 | 連続14日以上 | 11日以上 |
④育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届けていること
⑥対象の男性労働者を育休開始から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
第2種の支給要件
①「育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置※」のうち、複数社内で実施していること(出生時育児休業(産後パパ育休)の申出期限を2週間前より長く設けていた場合は3つ以上)
②育児休業を取得する従業員の業務について、代替者の業務内容を見直すための社内ルールを整備し、そのルールに基づいた体制づくりが行われていること
③男性労働者の育児休業取得率が、申請年度の前事業年度(Bの場合は前々年度も含む)と比較して、以下のいずれかを達成していること
- 事業年度で育児休業取得率が30ポイント上昇し、50%以上となった
※例えば、前事業年度の育児休業取得率が30%であった場合、申請年度の取得率が60%以上になれば、要件を満たします。 - 2年連続で育児休業取得率70%以上となった
※さらに、2事業年度前に、配偶者が出産した育休対象の男性労働者(雇用保険加入者)が5人未満でなければなりません。
④育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること
⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届けていること
⑥育休開始から申請日まで、対象の男性労働者を継続して雇用していること
「育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置」とは、次の5項目を指します。
※「育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置」
- 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
- 育児休業に関する相談体制の整備
- 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
- 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
- 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
出典:厚生労働省|両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)|P.5
出生時両立支援コースに申請する際は、必ず厚労省の「両立支援等助成金のご案内」ページにて取組が該当する年度の支給要件をご確認ください。
出生時両立支援コース申請時の必要書類と手続きの流れ

助成金を受け取るためには、申請の流れや期限を把握し、必要書類を正しく提出する必要があります。
ここでは、「第1種」と「第2種」それぞれの申請に必要な書類、申請期限、申請の流れを整理しています。
※実際の申請の際は、必ず厚生労働省の「両立支援等助成金のご案内」ページ内にある該当年度の『両立支援等助成金支給申請の手引き』で詳細をご確認ください。
第1種の申請手続き
必要書類
- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース(第1種))支給申請書(様式第1号①②)
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 育児休業制度や育児のための短時間勤務制度を規定するもの(労働協約・就業規則・労使協定など)
- 雇用環境整備措置の実施内容(措置分)と実施日が分かる書類
- 業務体制整備に関する規定(育休取得者の業務代替に関するもの等)
- 対象の男性労働者の育児休業申出書
- 対象の男性労働者の就業実績(育児休業前1か月分)および休業状況が確認できる書類(出勤簿・タイムカード及び賃金台帳など)
- 対象の男性労働者の雇用契約期間・育休期間の所定労働時間・所定労働日が確認できる書類(就業規則・労働条件通知書、勤務シフト表など)
- 子の出生を証明する書類(母子手帳・住民票など)
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(プラチナくるみん認定事業主は不要)
- (過去に申請ありの場合)提出を省略する書類についての確認書(様式第4号)
※2・3人目の申請で内容に変更がない場合、省略できる書類は、3.、4.、5.および10.です。 - (始めて申請する場合)支払方法・受取人住所届及び支払口座が確認できる通帳等の写し
申請期限
- 対象男性労働者の育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内
- 育児休業(産後パパ育休を含む)を複数回に分割して取得した場合も、最初の休業で支給要件を満たしていれば、その育児休業終了日の翌日から2か月以内
※申請期限は、すべての育児休業が終了終わってからではなく、要件を満たした最初の休業終了後です。
第2種の申請手続き
必要書類
- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース(第2種))支給申請書(様式第1号①②③④)
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 育児休業制度や育児のための短時間勤務制度を規定しているもの(労働協約・就業規則・労使協定など)
- 雇用環境整備措置の実施内容(措置分)と実施日が分かる書類
- 業務体制整備に関する規定(育休取得者の業務代替など)
- 育児休業取得率を算出した男性労働者の育児休業申出書
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(プラチナくるみん認定事業主は不要)
- (過去に申請ありの場合)提出を省略する書類についての確認書(様式第4号)
※省略できる書類は、3.、4.、5.、7.です。 - (始めて申請する場合)支払方法・受取人住所届及び支払口座が確認できる通帳等の写し
申請期限
- 申請に係る事業年度(育児休業取得率が上昇等した事業年度)の翌事業年度の開始日から起算して6か月以内
手続きの流れ
出生時両立支援コースの申請手続きは、以下のとおりです。
- 制度利用が要件を満たしているか確認する
- 支給申請書類(支給申請書・添付書類一式)を準備する
- 管轄の都道府県労働局または労働基準監督署に期限内必着で提出する
- 審査を経て、支給決定後に助成金が振り込まれる
申請前に「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」を策定し、労働局へ届け出ておく必要があります。忘れずに行いましょう。
申請先と申請方法
申請先は、事業主の人事労務管理の機能を有する部署の所在地を管轄する、労働局雇用環境・均等部(室)です。
申請方法は、郵送のほか、以下の条件に当てはまる場合は電子申請も利用できます。
- 第1種:令和5年4月1日以降に対象労働者の育児休業が開始した場合
- 第2種:令和5年4月1日以降に支給要件を満たした場合
なお、郵送の場合は、消印有効ではなく期限内に必着である点に注意してください。郵送事故を防止するため、配達記録が残る方法(簡易書留など)で送付すると安心です。
申請に必要な書類は厚生労働省|両立支援等助成金のご案内からダウンロードできます。
育児休業等に関する情報公表加算の申請方法と注意点

育児休業等に関する情報公表加算(以下、情報公表加算)は、第1種(1~3人目のいずれか)または第2種の、1回限りで申請が可能です。
申請方法と注意点は以下のとおりです。
【申請方法】
情報公表加算の申請を行うためには、支給申請日までに、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば|一般事業主行動計画公表サイト」で以下の①~③の情報をすべて公表する必要があります。
- 雇用する男性労働者の育児休業等の取得割合
- 雇用する女性労働者の育児休業の取得割合
- 雇用する労働者(男女別)の育児休業の平均取得日数
公表後、申請書(育児休業等に関する情報公表加算(様式第3号))を用意し、第1種または第2種の申請とあわせて提出します。
【注意点】
- 情報公表加算のみを単独で申請することはできません。
- 自社ホームページなど、厚生労働省の運営サイト以外での公表は対象外となります。
情報公表加算の申請方法や、申請に必要な公表すべき内容の詳細は、厚労省の「両立支援等助成金のご案内」ページにある最新手引き内の『育児休業等に関する情報公表加算について 』からご参照いただけます。
まとめ|出生時両立支援コースの必要事項を理解し、確実に申請を進めましょう
本記事では、「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」について、助成金の種類(第1種・第2種)や制度概要、助成金額、支給要件、申請の流れや注意点まで詳しく解説しました。
出生時両立支援コースは、男性労働者の育児休業取得を後押しするために、中小企業を対象として整備された助成制度です。子育てに理解ある企業姿勢を社内外に示すことで、人材定着や採用力向上にもつながるメリットが期待できます。
一方で、就業規則の整備や環境整備の証明、複数の書類準備など、申請には細かな要件を正確に満たす必要があります。特に、書類不備や申請期限の遅れは受給不可につながる可能性もあるため注意が必要です。
こうしたリスクを避け、制度を確実に活用するためには、社労士など専門家に相談しながら準備を進めると安心です。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。