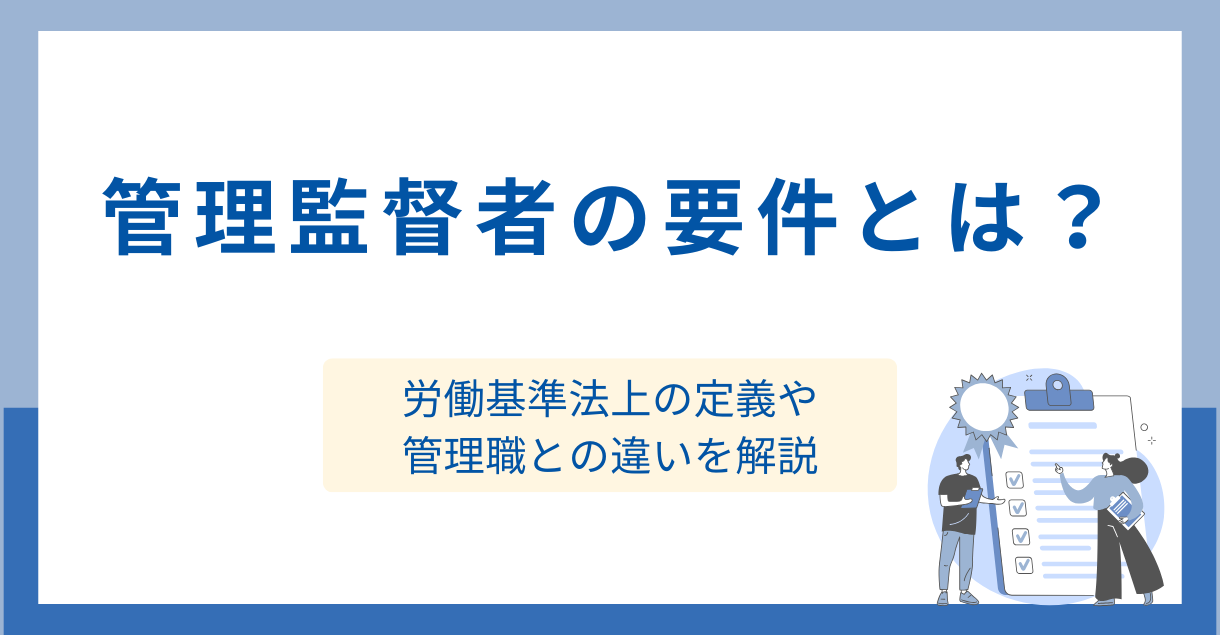
「管理監督者」の要件とは?労働基準法上の定義や管理職との違いを解説
企業における「管理監督者」と「管理職」という言葉は似ているようで、実は労働基準法上の取扱いでは大きな違いがあります。「管理監督者」に該当する場合、は労働時間や休日に関する規制の一部が適用除外となる点に注意しましょう。
一方、「管理職」は、企業がそれぞれの基準で部下を監督する立場である部長や課長などの役職者を「管理職」と呼ぶことにしているにすぎません。したがって、労働基準法の適用除外を受けるかどうかは、あくまで労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかです。
本記事では、労働基準法における「管理監督者」の定義や要件を整理し、一般的な管理職との違いをわかりやすく解説します。「管理監督者」の扱いを理解しておきたい企業の方は、ぜひご参考ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
管理監督者とは
33337726_s.jpg)
労働基準法第41条2号の管理監督者とは、「労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と定義されています。(※)
具体的な要件は、以下の通りです。以下に該当する人は管理監督者である、と判断できるということになりますが、その判断は慎重さが求められます。
- 職務内容:経営方針決定等に関与する、又はこれに準ずる経営者と一体的な立場にあること
- 責任・権限:一般社員にはできない責任・権限を有していること
- 勤務態様:労働時間管理を受けず、自律的に勤務時間を決定できること
- 待遇:その職務と責任に見合う処遇がなされていること(賃金水準が一般社員に比して相応に高いこと)
また、管理監督者は労働基準法で定められた労働時間・休憩・休日の制限を受けないのが特徴です。労働基準法第41条2号でも「事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者」については、第4章(労働時間、休憩、休日)の規定を適用しないとされています。したがって、法定労働時間を超えて労働させた場合の残業代や法定休日に労働させた場合の休日出勤手当であっても、割増賃金を支払う必要がありません。
ただし、制限を受けないのは労働時間・休憩・休日等に限られており、深夜労働に関する割増賃金(法第37条第4項)は除外されない点に注意が必要です。
【管理監督者の取り扱い】
| 休日出勤手当 | なし |
| 深夜手当 | あり |
| 年次有給休暇 | あり |
| 遅刻・欠勤への欠勤控除 | なし |
| 出勤しないときの欠勤控除 | あり |
| 勤怠管理 | あり |
| 健康診断・面接指導 | あり |
| 残業代 | なし |
(※)参考:日本労働組合総連合会:労働基準法の「管理監督者」
以下で、1つずつの要件について詳しく解説します。
管理監督者と判断される4つの要件
33527481_s.jpg)
ここでは、前述した管理監督者と判断される要件について、それぞれ詳しく解説します。「この人は管理監督者なのか?」と迷ったときは、以下の要件に当てはまるかチェックしてみましょう。
職務内容
厚生労働省では、管理監督者の職務内容について「労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること」という要件を定めています。(※)
要件における「重要な職務内容」とは、例えば以下のような職務を指します。
- 部署や事業の運営について経営上の意思決定に関与すること
- 労務管理や人事評価など重要事項を決定すること
- 上司の細かい指示を受けなくても自律的に業務を遂行すること
- 単なる業務リーダーや現場監督ではなく経営者側の視点で判断・行動すること
必然的に経営会議の参加や経営戦略の立案に携わることも多くなります。
(※)引用:厚生労働省:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
責任・権限
厚生労働省では、管理監督者の責任・権限について「労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること」という要件を定めています。(※)
つまり、一般社員にはできない以下のような責任・権限を持っていることがポイントとなります。
- 採用・解雇・人事考課などに関する権限を有していること
- 部下の勤務割や働き方を決定する権限を有していること
- 経営者不在時に企業運営ができること
上司の決裁を仰がずに判断できる場合や、上司の命令なく動ける場合は管理監督者に当たる要素があると考えてよいでしょう。
(※)引用:厚生労働省:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
勤務態様
厚生労働省では、管理監督者の勤務態様について「現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること」という要件を定めています。(※)
つまり、以下のような働き方をしていることがポイントとなります。
- 所定労働時間に拘束されずに勤務していること
- 遅刻・早退があっても欠勤控除されることがないこと
- 厳格な時間管理や労働時間に基づくマイナス評価がされないこと
とはいえ、「裁量労働制で働く社員=管理監督者」とは限りません。
裁量労働制も実際の労働時間に関わらず報酬を支払う働き方ですが、労使協定や労使委員会の決議を前提に導入する制度である点に注意しましょう。労働時間は「みなし労働時間」としてカウントされ、休日労働についての割増賃金も必要です。
(※)引用:厚生労働省:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
待遇
厚生労働省では、管理監督者の待遇について「賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること」という要件を定めています。(※)
管理監督者は経営者と一体的な立場で経営方針に関与できる立場であり、その責任に見合う待遇・報酬が必要です。
「管理監督者だが一般社員と比べて賃金にほぼ差がない」「管理監督者になる前の収入と変わらない」という場合、管理監督者として認められないケースがあるので注意しましょう。労働基準法における「管理監督者」はかなり要件が厳しく設定されており、「名ばかり管理監督者」にならないよう注意が必要です。
(※)引用:厚生労働省:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために
管理監督者と管理職との違い
31990819_s.jpg)
管理監督者について考える際、混同しやすい存在が「管理職」です。
「管理職」は企業内でよく使われる用語で「管理監督者」と非常に似通っているように感じられますが、定義や取扱いが異なるので違いを理解しておきましょう。
【管理監督者と管理職の違い】
| 項目 | 管理監督者(労基法上) | 管理職 |
|---|---|---|
| 定義 | 労働基準法第41条で定められた「労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されない」立場 | 企業内で部下を統率し、組織運営を担う役職全般 |
| 判断基準 | 実態で判断される(職務内容、権限、待遇など) | 会社の役職・肩書によって決まる |
| 労働時間規制 | 労働時間・残業・休日規定の適用除外(ただし深夜労働割増は必要) | 「管理監督者」に該当しない限り労働時間・残業・休日規定が適用される |
| 権限 | 経営者と一体的な立場で経営方針に関与できる程度の権限 | 部下の人事評価や業務指示などを行う場合もあるが様々 |
| 待遇 | 職務と責任に見合った相応の待遇(給与や役員並みの手当など)が必要 | 一般社員より高めだが様々 |
| 判定のポイント | 実態で総合的に判断(名ばかり管理職は認められない) | 会社の人事制度・役職名 |
問題になるのは、「労働時間規制」です。
管理監督者が労働時間・残業・休日規定の適用除外を受けるのに対し、管理職は労働基準法上の「管理監督者」に該当しない限り、適用除外にはなりません。つまり、管理職であっても残業代や休日出勤手当の支払いが必要な場合があるわけです。
「管理職=必ず残業代が出ない」わけではなく、法律上の「管理監督者」にあてはまる場合だけ労働時間のルールから外れる、と理解しておきましょう。
また、労働時間規制以外にも権限や待遇が異なります。
労働基準法上の管理監督者と認められるためには「経営者と一体的な立場にある者」としてより高い権限が必要とされるのに対し、管理職は会社が決めた範囲で部署・業務・チームなどの統括を任される立場です。従って、待遇も会社が決めたものでよいわけです。
管理監督者によくあるトラブル・注意点
33548989_s.jpg)
従業員を管理監督者として取り扱うことにはメリットがある一方で、トラブルや注意点があることも事実です。
- 「名ばかり管理監督者」問題
- 待遇水準の不一致
- 労働時間管理の不徹底
- 深夜労働の割増未払い
ここでは代表的なトラブル・注意点を紹介します。以下の点に十分注意し、法律面順守も従業員のモチベーション向上も意識した運用にしてください。
「名ばかり管理監督者」問題
「名ばかり管理監督者」とは、「肩書きや役職名は管理監督者になっているものの実態は管理監督者として認められない」状態のことを指します。
例えば、以下のようなケースでは「名ばかり管理監督者」といえます。
- 肩書きは管理監督者でも、上司の指示に従って働いている
- 経営企画の立案に携わらず、業務の管理や作業進捗のチェックのみを担当している
- 労働時間の裁量がなく、出勤・退勤時間が明確に決められている
- 部下の採用・昇進・評価・処分権限がなく、実務上は現場リーダーになっている
- 過重労働が常態化しているが管理監督者であることを理由に残業代が支払われない
例えば、「残業代を支払わなくてよいなら管理監督者にしようという誤った認識で任命するのは、法的リスクが高いです。管理監督者として取り扱う以上、管理監督者の要件を満たす働き方や報酬にする必要がある点に注意しましょう。
管理監督者として取り扱っていながら実態は「名ばかり管理監督者」になっていた場合、法的リスクが発生するだけでなく、労務トラブルや紛争の原因になることも。従業員からの信頼を損ない、労働組合や労基署からの是正勧告・調査につながるなど、思わぬトラブルも生じます。
待遇水準の不一致
管理監督者として扱う場合、責任や権限に見合った待遇(給与・手当)が伴う必要があります。待遇水準の不一致が発生している場合、「名ばかり管理監督者」となる他、未払い残業代や休日出勤・深夜労働の割増賃金がまとめて請求されるなど、コスト面でのリスクも生じます。
待遇水準の不一致の代表例として、以下が挙げられます。
- 権限や裁量が大きいので管理監督者として取り扱っているにも関わらず、一般社員とほとんど同じ給与水準である
- 一般社員から管理職に昇進し管理監督者として取り扱われるようになったにも関わらず、給与が上がらない
- 店舗や部門の成果責任を負うにもかかわらず、責任手当や役職手当が十分に支給されていない
- 労働時間の自由度や裁量権はあるが評価制度が成果に連動しておらず、報酬が固定的で不透明
組織内での公平性が損なわれ、他従業員からの不満や労使トラブルにつながるリスクも生じます。
労働時間管理の不徹底
管理監督者の場合、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものである必要があるため、一般社員のような厳格な遅刻早退による不就労時間分の賃金控除や残業申請の管理をすることは適当ではありません。
しかし、「労働時間管理が一切不要」「勤務時間や業務量の実態を把握しなくてよい」ということではない点に注意しましょう。管理監督者であっても、労働安全衛生法により、タイムカードなどにより労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったかを把握する必要があります。長時間労働が常態化すると、過労やメンタル不調が起きるなど従業員の健康被害に直結します。
名ばかり管理職としての法的リスク(裁判や労基署調査)と重なると、企業責任が問われることも少なくありません。
深夜労働の割増未払い
管理監督者の労務管理で間違えやすいのが、「管理監督者にも深夜労働の割増賃金を支払う必要がある」という点です。
深夜労働(22時~翌5時)に対する割増賃金(25%以上) は、労働基準法上必ず支払わなければなりません。「管理監督者だから残業代も深夜手当も不要」と誤解したり、意図的に支払わなかったりする場合、企業側の責任が問われます。
結果、従業員は「ただ働きさせられている」と不満を強め、未払い賃金の請求や労働基準監督署への申告などの法的トラブルに発展するリスクがあります。社会的に「ブラック企業」と報じられるなど、企業イメージに与えるダメージも甚大です。
管理監督者のリスク回避チェックリスト
23362176_s.jpg)
管理監督者は正しく運用されていれば会社にとっても従業員にとってもメリットのあるポジションである一方、誤った労務管理や制度運用によるリスクも見逃せません。
ここでは、管理監督者のリスク回避チェックリストを紹介します。以下のチェックリストを使って社内確認を進め、名ばかり管理監督者の発生リスクを未然に防ぎましょう。
1. 職務内容の確認
- 経営者と一体的な立場で意思決定に関与しているか
- 部署や店舗の運営において、自律的に業務を遂行できるか
- 単なる業務指示や作業管理だけにとどまっていないか
2. 責任・権限の確認
- 部下の採用・昇進・評価・処分に関する権限があるか
- 部門の労務管理や業務配分を裁量で決定できるか
- 部署や事業の成果に対して最終的な責任を負う立場か
3. 勤務態様の確認
- 労働時間の裁量を持っているか
- 突発的な業務や休日出勤・深夜勤務に柔軟に対応できるか
- 上司の細かい指示で勤務時間が制約されていないか
4. 待遇の確認
- 権限や責任に見合った給与・手当が支給されているか
- 他の一般社員と比べて、責任に応じた待遇差があるか
- 成果や業績に応じた評価制度が整備されているか
5. 文書化・規定整備
- 管理監督者の取り扱いを就業規則に明記しているか
- 権限・責任・裁量・待遇の実態を社内で文書化しているか
- 定期的に実態と規程の乖離がないか確認しているか
また、管理監督者として取り扱っている従業員がいる場合、チェックリストを使った定期的な運用状況の確認が求められます。「現場で労働基準法違反が発生していたのに本社が気づけなかった」「いつの間にか当初想定していた形とは違う働き方をしている」という事態にならないよう注意しましょう。
管理監督者の要件に関する「よくある質問」
最後に、管理監督者の要件に関する「よくある質問」を紹介します。気になる項目や間違えやすい項目を中心にピックアップしているのでご参考ください。
Q:管理職=管理監督者ですか?
いいえ。役職名が「管理職」であっても、自動的に労基法上の「管理監督者」に該当するわけではありません。権限や待遇などの実態に基づき、要件を満たすかどうかで判断されます。
一般的に「管理職」と呼ばれる人が、必ずしも労働基準法上の「管理監督者」にあたるわけではない点に注意が必要です。
Q:管理職を管理監督者にできますか?
可能ですが、必ずしもすべての管理職が管理監督者になるわけではありません。「管理職=管理監督者」と一律に決めることはできず、労働基準法上の要件を満たしているかどうかで判断されます。
管理職を管理監督者にする場合、昇進に伴う待遇の見直しも必要です。
Q:裁量労働制と管理監督者は同じ制度ですか?
いいえ、全く別の制度です。裁量労働制は「みなし労働時間制」の一種で、実際の労働時間に関わらずあらかじめ決められた時間を働いたものとみなす制度です。
どちらも従業員の裁量により労働時間等を決められる点で同一ですが、裁量労働制は「仕事の性質や労使協定」で判断されます。一方、管理監督者は「経営に近い立場かどうか」で判断されるのがポイントです
Q:誰を管理監督者に指定するかは会社の自由ですか?
会社が「あなたを管理監督者とする」として取り扱っても、労基法上の要件を満たさなければ「管理監督者」とは認められません。労働基準法で定められた実態要件(職務内容・責任と権限・勤務態様・待遇)を満たしていなければ、法的には管理監督者として扱えないので注意が必要です。
Q:管理監督者にしたら労働時間の記録は不要ですか?
いいえ、労働時間の記録は引き続き必要です。管理監督者は労基法上労働時間・休憩・休日の規制が適用されませんが、だからといって労働時間を全く把握しなくてよいわけではありません。
過労死防止や健康管理の観点からも労務管理が重要であり、「会社が労働実態を全く把握していない」というのは責任問題になるケースもあります。
まとめ|管理監督者の要件と制度運用に要注意!
本記事では、管理監督者の要件を中心に、管理職との違いやトラブル事例を解説しました。
管理監督者制度は、人材の裁量を広げ、柔軟な組織運営を実現するなどメリットが多いことで知られています。
一方、要件を満たさないまま「名ばかり管理監督者」として制度を運用してしまうと労働基準法違反となり、未払い賃金請求・訴訟・企業イメージの失墜など大きなリスクを招きかねません。役職や名称だけで判断せず、職務内容・権限・待遇などの実態を丁寧に確認し、制度を適切に運用することが不可欠です。
健全な労務管理を行うことで従業員の納得感やモチベーションを高め、組織全体の信頼性と生産性向上にもつながる制度にしていきましょう。
管理監督者について不安がある場合には、社労士との連携が安心です。
社会保険の加入について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。














