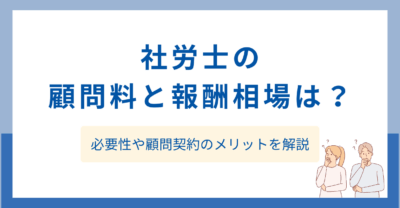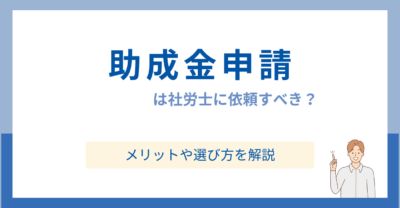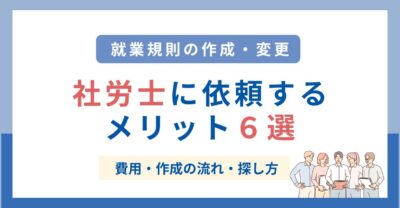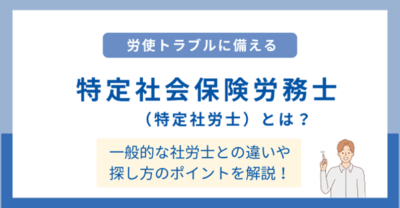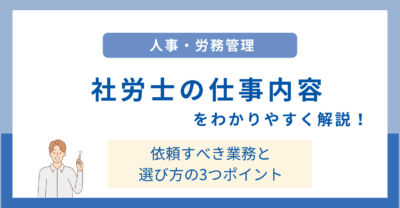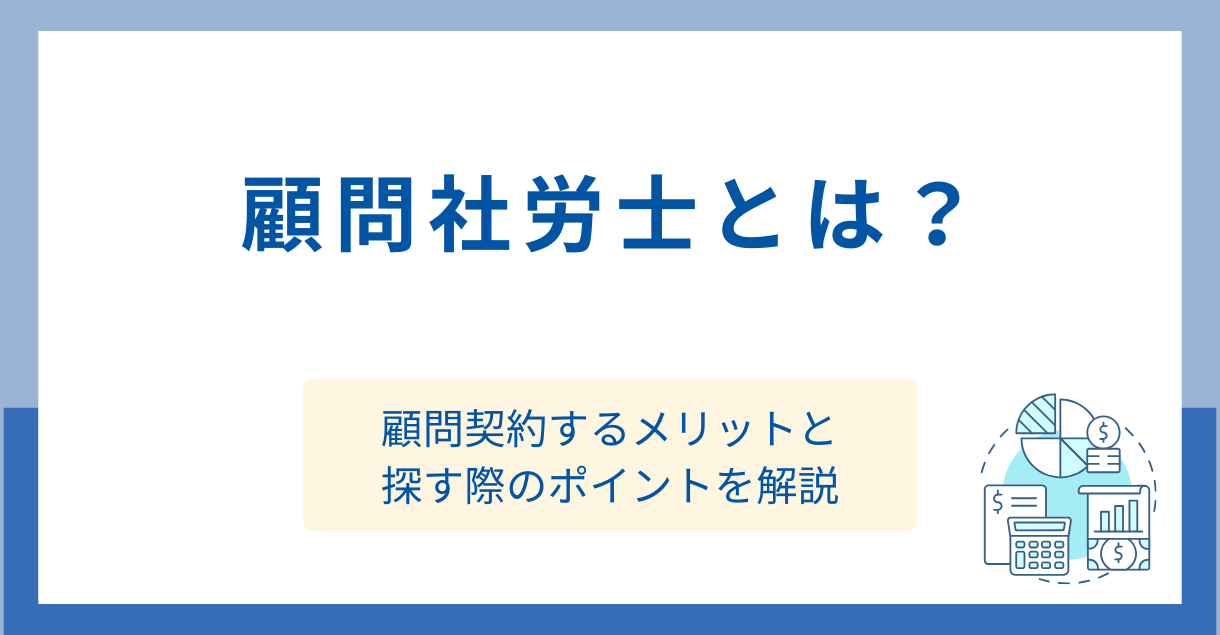
顧問社労士とは?顧問契約するメリットと探す際のポイントを解説
顧問社労士とは、企業と顧問契約を締結し、社会保険・雇用保険など各種手続きの代行や、人事・労務に関する相談対応、就業規則や労務管理体制の整備を継続的に支援する社労士(社会保険労務士)のことです。社労士は、国家資格を持つ人事・労務管理の専門家で、前述のような各種手続きの代行や、労務トラブルに関する相談対応を担います。
本記事では、顧問社労士の必要性や社労士と顧問契約するメリットとデメリットについて解説します。自社にあった顧問社労士を探すポイントも併せて紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
日本最大級の社労士検索サイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
顧問社労士とは
顧問社労士とは、企業と顧問契約を結んだ社労士を指します。社労士を一言で表すと「企業における人事・労務管理の専門家」です。労働・社会保険などの専門的な業務について、手続きの代行や相談、コンサルティングなどが主な業務となります。
社労士が担っている具体的な業務内容は、下記のとおりです。
- 社会保険や労働保険の手続きの代行
- 給与計算
- 労働時間・残業管理の改善コンサルティング
- 労務管理・労務相談
- 就業規則の作成・改定
- 採用・退職時の労務手続きサポート
- 育児休業・介護休業などの制度設計と手続き
- 助成金の申請
- 人事・賃金制度の策定
- ハラスメント防止体制の構築支援
- 教育研修の提案
- 福利厚生の相談
- 労働紛争の調停・仲裁(※特定社会保険労務士のみ)
このように企業の人事・労務にまつわる様々なことに幅広く対応しています。また、このなかでも「労働社会保険諸法令にもとづく帳簿書類の作成」や「社会保険の手続き書類の作成・提出の代行業務」は、社労士の独占業務です。
顧問契約に含まれる業務内容は社労士によって異なるため、契約前に確認しましょう。
社労士の業務内容については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:社労士とは?仕事内容や依頼するメリット、選び方を解説)
顧問社労士の必要性
顧問社労士は、労務関係の書類作成やコンサルティング業務を通じて、企業の発展に貢献できます。少ない労働力で多くの成果を上げるためには、人事・労務の専門家である社労士への依頼が最適です。
企業のさまざまな課題と状況において、社労士により解決した以下のような例があります。
| 課題 | 状況 | 社労士による解決例 |
|---|---|---|
| 法改正への対応 | 労働、社会保険関係の法改正が頻繁にあり、対応方法がわからない | 最新の法改正に精通した社労士が、自社に適した対応策を提案 |
| 労務管理システムの運用 | 自社で法律や就業規則に合わせた設定ができていない | 社労士が専門的な観点からや運用をサポートし、トラブルのリスクを軽減 |
| 事務作業の内製化 | 総務、経理担当者が労務手続きや給与計算を担当し、業務が属人化している | 社労士が業務を担当することで、担当者の負担軽減と業務の標準化が可能 |
| 助成金の申請 | どんな助成金があるかわからない 助成金の申請手続きが複雑で時間がかかる | 社労士が相談から申請までをサポートし、時間と労力を大幅に削減 |
上記のように、社労士に依頼すれば解決できる課題は多くあるといえます。日常的に必要性が少ないと感じる企業でも、すぐに相談できる社労士と顧問契約を結んでおくことが大切です。
社労士と顧問契約するメリット
社労士は、企業のさまざまな問題を解決してくれますが、顧問契約することでさらに多くのメリットを得られる可能性があります。
- トラブル時にも迅速に対応できる
- 経営上の課題を相談できる
- 従業員が安心感を持って働ける
- 業務をスポット契約する場合よりお得なケースが多い
- 助成金の申請に関するサポートを受けられる
トラブル時にも迅速に対応できる
社労士と顧問契約するメリットは、トラブル発生時に迅速に対応できる点です。顧問契約していない場合は、依頼する社労士を探すところから始めなければなりません。そのため、対応が遅れてしまい、損失を被る可能性もあります。
顧問社労士がいれば、労使トラブルが起きた際でも適切に対応できるほか、事前に労務環境の適正化を図れるため未然に防ぐことも可能です。労使トラブルが表面化すると企業は社会的信用を失うリスクもあります。
また、人事労務に関する制度や法律は複雑かつ頻繁に改正されることから、知らないうちに法律違反となる場合も少なくありません。社労士と顧問契約を結び、日頃から労務に関するトラブルを未然に防ぐような取り組みが重要です。
経営上の課題を相談できる
顧問社労士がいる会社は、経営上の課題を相談できます。経営者や人事担当者の多くが直面する課題は決して安易なものではありません。常に相談できる専門家がいると考えれば、安心して経営や業務に取り組めます。
ほかにも、複雑な労働管理や法的な課題について、顧問社労士からアドバイスを受けることも可能です。例えば、賃金規程や就業規則が不明確で従業員とトラブルが懸念される場合でも、法律にもとづいたアドバイスを受けて解決できます。
また、人事や労務に関する業務が一部の担当者に集中している場合に、顧問社労士に業務の一部を依頼して、社内リソースを効率的に活用できる点もメリットです。
従業員が安心感を持って働ける
顧問社労士がいることで、従業員が安心感を持って働ける会社になれる点もメリットです。顧問社労士がいれば、労使トラブルが発生しないよう事前に対策を立てられます。
また、顧問社労士が従業員の相談に応じてくれる場合もあり、より働きやすい職場環境の実現にもつながります。ほかにも、従業員からの休暇や休業申請に対し、就業規則にもとづいたスムーズな対応が可能です。
結果として従業員の満足度が向上し、離職率の低下にも期待できます。
業務をスポット契約するケースよりお得なことが多い
社労士と顧問契約することで、業務をスポット契約する場合よりもお得になるケースが多くなっています。
契約内容によるものの、顧問契約に含まれている各種諸手続きや相談、指導業務なら、頻度にかかわらず定額でサービスを受けられることも少なくありません。毎回費用をかけて社労士に依頼・相談するよりも十分お得になります。
顧問契約に含まれていない業務が発生した場合は、スポット契約での業務を依頼しなければなりません。しかし、すでに顧問契約を結んでいる場合、スポット契約の金額が抑えられることも多く、コスト削減につながります。
助成金の申請に関するサポートを受けられる
社労士と顧問契約すると、助成金の申請に関するサポートを受けられるメリットもあります。助成金の制度は要件が頻繁に変更されるため、利用するためには最新情報の把握が必要です。
しかし、本業を行いながら助成金の最新情報を毎回調べることは現実的ではありません。顧問社労士なら、依頼すれば助成金の最新情報を迅速に調べ上げてくれるため、すぐに知りたい情報を取得できます。
ただし、顧問契約していないと助成金申請のサポートに関しては費用が割高になるケースや業務を受けてもらえないケースがあるため、事前の確認が必要です。
社労士への助成金申請の依頼については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:助成金申請は社労士に依頼すべき?メリットや選び方を解説)
社労士と顧問契約するデメリット
社労士と顧問契約する際はメリットのみで判断せず、デメリットも確認しましょう。
- 顧問料が発生する
- 社労士では対応できない業務がある
- 社労士によってスキルや相性に差がある
顧問料が発生する
社労士を顧問契約すると必然的に顧問料が発生します。単発の業務ではないことから月額で支払うことが一般的です。
顧問料は依頼する業務内容や頻度により異なるため一概にはいえないものの、小規模企業の場合は顧問料が負担になる場合もあります。そのため、費用対効果を確認してから決めましょう。
社労士の顧問料については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:社労士の顧問料と報酬相場は?必要性や顧問契約のメリットを解説)
社労士では対応できない業務がある
社労士を顧問契約するデメリットとして、社労士では対応できない業務がある点も挙げられます。社労士は労務管理関連の専門家ですが、全ての業務を包括的にカバーできるわけではありません。
例を挙げると、法務の専門的な分野には弁護士や司法書士などほかの専門家の協力も必要です。社労士に依頼可能な業務内容を事前に確認していない場合、希望する実務を依頼できなくなる可能性もあります。
社労士によってスキルや相性に差がある
社労士と顧問契約する際、社労士によってスキルや相性に差がある点もデメリットにつながります。どちらも顧問契約を結ぶ前に確認すれば、未然に防げる内容です。
社労士は国家資格であることから、知識や専門性については一定の品質が担保されています。ただし、実務経験や得意分野については個々に差があるため、サービス品質には違いがあります。
また、業務を円滑に進めるためには顧問社労士との相性も重要です。スキルや相性は実際に社労士と話してみないとわからない部分も多いので、信頼できる社労士と顧問契約するためにも慎重に選定しましょう。
自社に合った顧問社労士を探すポイント
自社に合う信頼できる顧問社労士を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。以下の6つのポイントを意識して、探してみましょう。
- レスポンスが早くて対応が丁寧か
- 幅広い分野のアドバイスをしてもらえるか
- サービス内容とコスト面のバランスが良いか
- 社労士の業務領域がニーズに合っているか
- コミュニケーションが図りやすいか
- 顧問報酬と料金体系が明確化されているか
レスポンスが早くて対応が丁寧か
顧問社労士を探す際は、レスポンスが早くて対応が丁寧かどうかを確認しましょう。こちらからの連絡に対し、素早く丁寧なレスポンスが返ってくる社労士がおすすめです。
また、相談のしやすさもひとつのポイントになります。気になった点について気軽に相談できる雰囲気がある社労士や、自社担当者と相性のよい社労士を選ぶことで、円滑な業務連携が可能です。
ほかにも、対面での打ち合わせ以外にオンラインにも柔軟に対応できる社労士が増えています。そのため、メールだけではなくチャットツールを使ったやり取りも、業務をスムーズに進める上で重要です。
幅広い分野のアドバイスをしてもらえるか
幅広い分野のアドバイスをもらえるかどうかも、顧問社労士を探す際のポイントです。幅広い分野に精通した社労士なら、より多くのアドバイスをもらえる可能性が高くなります。
例を挙げると、「労務管理を効率化できるシステムの導入の提案」や「従業員のスキルアップをサポートする制度の構築」など、法的な面を超えた提案ができる社労士もいます。
以上のような社労士と顧問契約できれば、企業が成長するきっかけにもなるため、幅広い分野に精通する社労士を選びましょう。
サービス内容とコスト面のバランスが良いか
顧問社労士を探す際は、サービス内容とコスト面のバランスが良い社労士を選びましょう。社労士のサービス内容と料金設定は事務所ごとに異なるため、顧問契約の締結前に提供してもらえるサービスを確認してみてください。
サービス内容については、明確な業務を指定しなくても「労務管理が属人的になっている」や「採用支援をしてほしい」など、自社の課題を伝える方法もあります。自社に適した顧問社労士を選ぶには、まず課題を洗い出しましょう。
社労士の業務領域がニーズに合っているか
自社に合った顧問社労士を探すポイントとして、社労士の業務領域がニーズに合っているかどうかも重要です。社労士によって、受け付けている業務名が同じでも業務内容や業務の品質、対応力が異なります。
給与計算の代行業務を例に挙げると、以下のように内容が異なるため、注意が必要です。
- タイムカードを渡すだけで、月次の勤怠を集計してくれる給与計算業務
- 企業側でタイムカードを集計したデータを渡して給与を算出してくれる給与計算業務
顧問社労士を探す際は、どのような領域を社労士に外注したいのかを整理すると、納得できる社労士に出会える可能性が高くなります。
コミュニケーションが図りやすいか
顧問社労士を探す際は、コミュニケーションが図りやすいかどうかも重要です。社労士に依頼する労務管理や助成金申請などの業務は、期日厳守が求められるものが多くなっています。そのため、定期的にコミュニケーションが図れないと、手続き状況の確認に時間がかかります。
一方で、コミュニケーションが定期的に図れる顧問社労士なら、手続き状況の確認も迅速で、助成金や法改正に関する有益な情報を受け取りやすくなります。顧問社労士を探す際は、コミュニケーションが図りやすい社労士を選んでみてください。
顧問報酬と料金体系が明確化されているか
顧問社労士を探す際に押さえておきたい最後のポイントは、顧問報酬をはじめとする料金体系が明確化されているかどうかです。
社労士の業務は、大まかな相場はあるものの報酬に明確な基準がないため、事務所ごとに料金を設定しています。事務所によってはホームページに料金を記載していないケースも多くあります。
依頼する業務内容や業務範囲、企業の経営状況や従業員数など、さまざまな要素で料金が異なるため、ホームページに記載がない場合は見積りをとって詳細を確認しましょう。
自社に合った顧問社労士を見つけよう
今回は、社労士を顧問契約する必要性やメリット、デメリットについて解説しました。企業は労使問題をはじめ、さまざまな課題を抱えています。顧問社労士と契約すると、課題を最短で解決できる可能性があるため、企業にとって必要な存在です。
また、顧問契約していればトラブル時に迅速に対応できるほか、従業員が安心感を持って働けるメリットもあります。顧問料が発生するものの、依頼できる内容を精査して見積りをとれば、納得できる形で顧問契約を締結可能です。
本記事で解説した顧問社労士を探すポイントを押さえて、自社に合った顧問社労士を見つけてみてください。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。