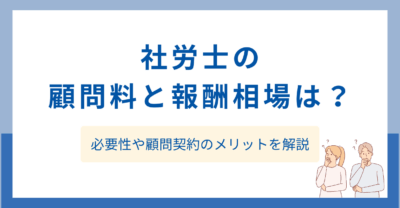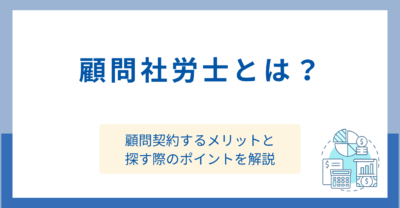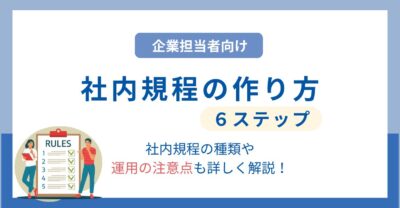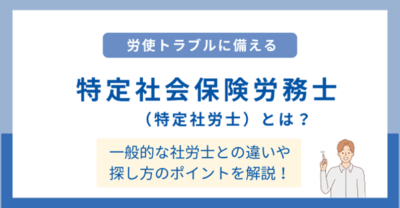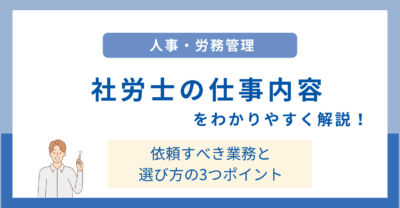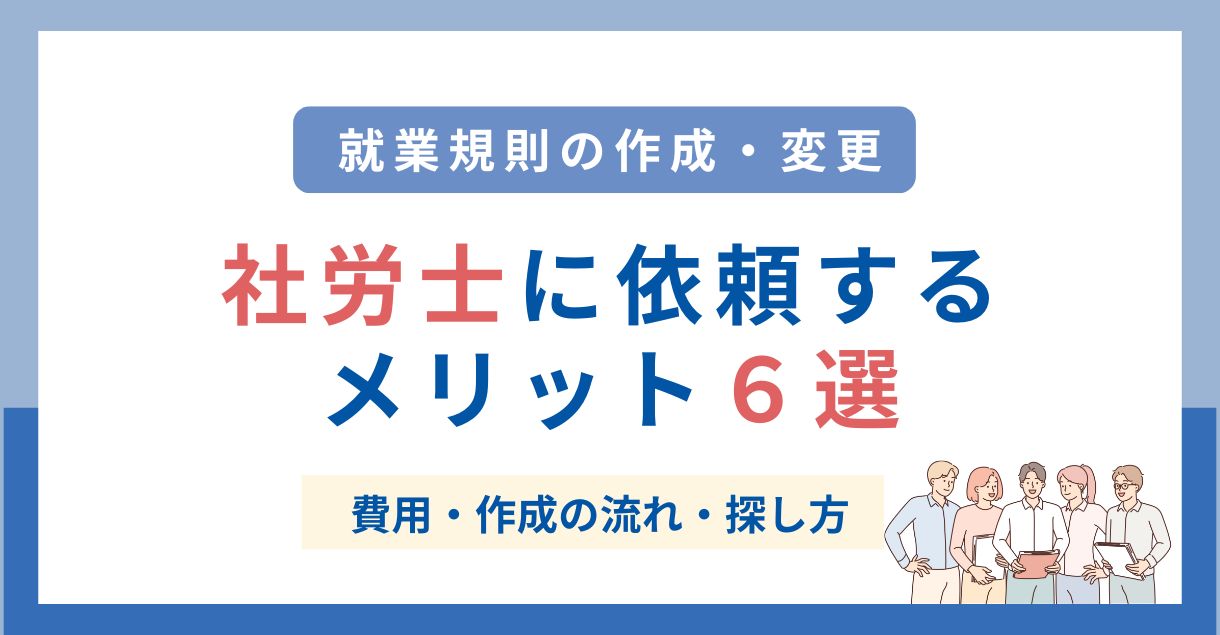
就業規則の作成時に社労士に依頼するメリット6選|費用・流れ・探し方を解説!
就業規則の整備は、企業が法令を順守するだけでなく、現場の働き方に即したルールを整備して労使トラブルを未然に防ぐためにも欠かせません。
しかし、「作成・届出・改定・運用・管理」までの一連の業務には多くの専門知識と労力が求められ、企業担当者にとって大きな負担となってしまうこともあります。
特に他業務と兼任している担当者は、書類の作成や法改正への対応、事業所ごとの運用調整などに追われ、本来の業務に集中しづらくなるケースも少なくありません。
そうした負担を軽減し、法令を順守しつつ労働者の理解と納得を得て、確実な周知・運用を実現するには、社会保険労務士(以降、社労士)に依頼するのが効果的です。
本記事では、就業規則の作成や変更を社労士に依頼するメリット、費用相場、依頼の流れや探し方までを丁寧に解説します。
「就業規則の作成・変更を社労士に依頼したい」とご検討中の企業担当者は、ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
| 企業の実務担当者が就業規則を作成する際の、掲載ルールや労働基準監督署への届出の流れなどは以下の記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。 |
そもそも就業規則とは

企業にとって、労働者とのトラブルを未然に防ぎ安定した職場環境を築くためには、就業規則の整備が欠かせません。
ここでは、就業規則の基本的な位置づけや重要性について整理していきましょう。
就業規則の役割と重要性
就業規則は、労働基準法第89条に基づき、労働時間・休日・賃金・服務規律など、労働条件や職場ルールを明文化した社内規則です。
常時10人以上の労働者を雇用する事業場(企業全体ではなく、支社、営業所、店舗などの単位で考えます。)は、就業規則の作成と所轄の労働基準監督署への届出が義務付けられています(労働基準法第89条)。
就業規則を変更する場合も同様の届出義務があり、これに違反した場合、30万円以下の罰金(労働基準法第120条)が科される可能性があります。
また、就業規則が未整備の状態では、以下のような実務リスクも発生するため注意が必要です。
- 労務トラブルの際、「規定がない」として従業員への処分が無効になる可能性
- 労働者から訴えられた場合、企業側が不利になる
- 労基署による行政指導や監査で、企業の信用が損なわれる
就業規則は法的義務を果たすと同時に、企業を守る防波堤でもあります。
手続きを怠ったことによる罰則はもちろん、実務リスクや経営的損失の方が深刻になる可能性があるため、就業規則の作成・届出は経営上の重要な責務といえるでしょう。
就業規則の作成・変更が発生するケース
就業規則は一度作成したら終わりではなく、社会の変化や企業の実態に応じて、定期的な見直しが求められます。
以下のようなケースでは、新たに規則を作成・変更し、労働基準監督署への届出が必要です。
【作成】
- 企業規模が大きくなり、事業場の労働者が常時10人以上になったとき
【変更】
- 法改正が行われたとき(例:育児・介護休業法、ハラスメント対策の強化など)
- 労働時間・賃金制度の変更を行うとき(例:フレックスタイム制の導入、有給休暇付与基準の見直しなど)
- 新たな制度や働き方を導入するとき(例:在宅勤務、副業制度、出産・育児支援制度など)
- トラブルや訴訟が発生したとき
- 組織再編や拠点拡大で、組織や拠点単位でルールの整備が必要になったとき
企業の実態と就業規則がかけ離れている状態は、リスクそのものです。見直しや変更のタイミングを逃さず、継続的なメンテナンスを行いましょう。
企業が就業規則を作成・変更する際の注意点

就業規則を整備する際には、法的手続きや実務運用の観点から、いくつかの重要なポイントが存在します。
ここでは、企業が見落としがちな注意点を、実務目線でわかりやすく整理します。
法令を順守して就業規則を作成する
就業規則は、労働基準法や関連法令に基づいて作成する必要があります。
内容が法律に反している場合、その部分の規則の条項は無効とされ、30万円以下の罰金や是正命令の対象となる恐れがあります。必ず法令を確認し、最新のルールを反映させましょう。
法改正に合わせて就業規則を見直す
法改正への対応を怠ると、労働基準監督署からの是正指導や行政処分の対象になる可能性があります。
年1回の就業規則点検や、社労士との連携による法改正情報の確認など、定期的な見直し体制の整備が推奨されています。
現場の実態に即した内容にする
厚生労働省のモデル就業規則をそのまま使うと、現場の運用と異なってしまう恐れがあるため注意しましょう。
特に支店や部署ごとに働き方(労働時間の制度など)が異なる場合は、実際の勤務形態や業務フローに即した内容にすることが重要です。
就業規則を作成・変更した場合は届出をする
就業規則を新たに作成・変更した場合は、所轄の労働基準監督署への届出が義務です(労働基準法第89条)。
届出を怠ると、罰則の対象となるだけでなく、トラブル発生時に企業側が不利になる可能性があります。
労働者へ確実に周知して運用する
就業規則は、届出を行っただけでは効力を持ちません。労働者に対して確実に周知することで効力が発生するとされており、周知することが義務付けられています(労働基準法第106条)。
社内掲示、書面配布、社内報への掲載など、複数の手段を併用し、確実な周知とその記録を残すことが望まれます。
就業規則の作成を社労士に依頼する6つのメリット

就業規則の作成や変更は、法令順守・制度設計・労務リスクへの対応など、多岐にわたる専門知識と労力が求められます。
特に、人事・総務業務と兼務している担当者にとっては、本来の業務を圧迫する原因となりやすく、対応に頭を悩ませる場面も少なくありません。
ここでは、社労士に就業規則の作成・見直しを依頼することで得られる、6つのメリットをご紹介します。
1.専門的な制度知識を活用できる
社労士の知見を活用すると、制度が複雑化する中でも要点を押さえた就業規則の整備が可能です。
たとえば、短時間労働者(パートタイマー)の適用範囲、在宅勤務制度またはテレワーク制度の設計、有給休暇の管理方法など、専門的判断が求められる分野も的確に対応できます。
2.法改正への対応が迅速かつ確実
法改正の施行に備え、情報収集から対応準備までを先回りして支援してくれるのが社労士の強みです。
自社で対応する場合に比べ、情報の見落としや対応の遅れを防ぎ、結果として法令違反のリスク回避につながります。
3.企業の実態に即した制度設計が可能
業種や事業規模、勤務形態に応じて必要な規定は異なります。
社労士に依頼することで、ヒアリングを通じて現場の状況を把握し、実際の業務に適した無理なく運用できる就業規則の構築が可能です。
4.労務トラブルの予防につながる
不明瞭な規定や不整合のあるルールは、労使トラブルの火種になりかねません。
社労士は過去の判例や実務経験に基づき、トラブルにつながるリスクを事前に洗い出し、予防につながる整備を行います。
5.手続きや届出がスムーズに進む
就業規則の変更には、労働者代表からの意見書や新旧対照表の作成、労働基準監督署への届出など多くの手続きが伴います。
これらの手続きを社労士に任せることで、正確かつ迅速な対応が可能となり、実務負担を大きく軽減できます。
6.労働者への説明支援まで一貫対応
就業規則は、見直した後の実際の運用段階で、労働者への説明と理解の促進が不可欠です。
社労士は説明資料の作成から就業規則説明会の運営補助まで対応可能で、規則の趣旨を正確に伝え、スムーズで実効性のある社内周知を実現します。
就業規則を社労士に依頼する場合の費用相場

就業規則の作成や見直しを社労士に依頼する場合、その費用は一律ではなく、企業の規模・依頼の程度・内容の密度によって大きく変動します。
一般的な費用相場
依頼内容ごとの費用目安は下記のとおりです。
| 依頼内容 | 費用相場 |
| 新規に就業規則を作成する場合 | 10万円~50万円 |
| 既存規則の一部改定 | 数万円~15万円 |
| アドバイスや確認のみ | 5万円~20万円 |
ただし、これはあくまでも目安であり、社労士にどこまでの対応を求めるかによって費用は異なります。
費用が高額になる要因と対策
社労士への報酬が高くなる要因としては、以下の点が挙げられます。
- 企業規模が大きい(労働者数が多いほど内容が複雑化し労使トラブルのリスクが高くなる)
- 事業内容に特有のリスクがある(製造業や医療、IT業など)
- 対応範囲が広い(法改正対応、労働基準監督署への届出代行、労働者への説明会の実施など)
- 綿密なヒアリングや提案を重視する(設計段階でのコミュニケーション量が多い)
このように、「時間・専門性・提案力」が求められる場合ほど、費用は高くなる傾向にあります。
費用を抑えるためには、依頼内容を絞る、できることは自社で行うなどの工夫が有効です。
費用と支援内容のバランスを見極め、自社に合った最適な依頼先を選びましょう。
就業規則作成を社労士に依頼する場合の流れ

就業規則の作成から変更、労働基準監督署への届出、労働者への周知までの一連のプロセスは、労働基準法に基づき必要な手続きが決まっています。
社労士と連携しながら進める場合の一般的な流れを、実務ベースで解説します。
1.初回相談と現状確認
初回相談では、自社の労務管理の現状(労働時間・休暇制度・服務規律など)や要望を正確に伝えていただき、曖昧な運用ルールやリスク、法令上の問題点について相談します。
会社の基本情報や、見直しを行う場合は現在の就業規則などの関連資料を事前に準備し、質問事項も整理しておくとスムーズです。
2.作成依頼とヒアリングの実施
社労士の専門性や費用に納得した段階で、就業規則の作成(もしくは見直し)を正式に依頼します。
依頼内容に沿って複数回にわたりヒアリングを実施し、課題の深掘りを行います。
企業の就業実態やトラブル傾向を具体的に伝え、必要な制度項目の洗い出し作業を進めましょう。
3.原案の作成と修正対応
社労士から、大体2週間ほどでヒアリング結果をもとにした「就業規則(案)」が提示されます。企業担当者は内容に誤りがないか、依頼の趣旨にマッチしているかを確認しましょう。
社労士はフィードバックされた修正点や追加項目を精査し、条文の構成や表現などを再調整しながら、最終案に近づけていきます。
4.労働者代表からの意見聴取
就業規則の作成・変更時には、労働者の代表の意見を聴取することが義務付けられています(労働基準法第90条)。
就業規則(最終案)を労働基準監督署へ届出するためには、労働者の代表の「意見と署名」が記載された意見書が必要です。
意見聴取の方法や意見書の書き方については社労士から具体的にアドバイスをもらい、形式不備によって不受理にならないよう努めましょう。
労働者の代表の選出方法については、以下の記事をご覧ください。
(関連記事:【完全版】就業規則の作成義務と届出方法|「常時10人以上」とは?)
5.労働基準監督署への届出
労働者代表の意見聴取が完了し、就業規則が完成した段階で、所轄の労働基準監督署へ提出します。
「就業規則(変更)届」「意見書」「就業規則原本または新旧対照表」など、届出に必要な書類は社労士が準備します。必要に応じて手続き代行も依頼可能です。
労働基準監督署への届出方法についても、以下の記事で詳しく解説しています。
(関連記事:【完全版】就業規則の作成義務と届出方法|「常時10人以上」とは?)
6.就業規則の納品と保管
届出が完了した社内規則は、社労士から正式文書として納品されます。
企業はこの文書を、法的効力をもつ正式文書として保管し、将来的な見直しにも対応できるよう努めましょう。
7.労働者への周知と運用開始
就業規則は、届出を行っただけでは効力を持たず、労働者に対して確実に周知することが法律で義務付けられています(労働基準法第106条)。
また、社労士へ労働者向けの説明会や研修資料の作成支援依頼も可能です。必要に応じて依頼を検討しましょう。
上記のような流れはあくまで一例ですが、「初回相談・詳細ヒアリング・原案作成・意見聴取・届出・納品・周知と運用」というステップで進むケースが一般的です。
初めての就業規則作成や法改正を受けた全面的な見直しなど、企業担当者の負荷の大きい場面では、専門家との協力が非常に心強い選択肢となるでしょう。
就業規則の作成を依頼する社労士の探し方

社労士を探す方法は、各都道府県の社会保険労務士会Webサイトや、「社労士ナビ」といった社労士検索サイト、知人・同業者からの紹介などが挙げられます。
ただし、社労士自身にも得意分野や対応スタイルの違いがあるため、単に探すだけでなく自社の業種や課題に合った信頼できるパートナーを見極めることが重要です。
ここでは、社労士を選ぶ際に注目したいポイントを紹介します。
得意分野・業種・規模で社労士を比較する
社労士には大企業の複雑な制度設計に慣れている方、建設業・医療・IT業界など特定業界に精通した方、助成金と制度設計の組み合わせを提案できる方など、得意な分野が異なります。
自社の課題や今後の展望に合った専門性や実績を持つ事務所を選ぶと、提案の質が高まり、導入後の効果も期待できるでしょう。
初回相談や対応の柔軟性を確認する
初回相談が無料かどうか、訪問対応やオンラインでの打ち合わせが可能かなど、相談のしやすさは社労士選びの重要なポイントです。
また、契約後の修正対応・アフターフォロー体制の有無など、どこまで柔軟に対応してくれるかも事務所ごとに異なります。
制度設計を成功させるには、専門性だけでなく「話しやすさ」や「要望のくみ取りやすさ」といった、コミュニケーションの相性も大切です。
全国の社労士から自社に合った社労士を探す
自社に合った社労士を探すなら、全国ネットワークから社労士検索ができる「社労士ナビ」がおすすめです。
社労士ナビは、社労士の全国6,000以上の事務所が登録する社労士ポータルサイトです。
地域、得意分野、初回相談の有無などから社労士の絞り込みが可能で、自社に合った専門家が見つかります。
初回無料の事務所も多いため、複数の候補と比較したうえで、対応スタンスや人柄を確認してから依頼できるのも大きな魅力です。
まとめ|就業規則の作成は全国の社労士から選べる「社労士ナビ」を活用しよう
本記事では、就業規則の重要性や作成・変更時の注意点、社労士に依頼するメリット、費用の相場、そして依頼の流れや探し方について解説しました。
就業規則は法令順守のためだけでなく、労使関係を円滑にし、企業の信頼性を高める重要なツールです。一方で、その整備・管理には専門性が求められ、企業内だけでの対応には限界もあります。
就業規則の整備・見直しを行う際には、社労士との連携が最も安心で確実な方法です。
就業規則の作成・変更について相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。