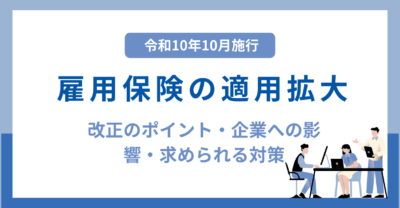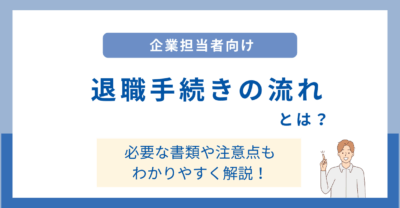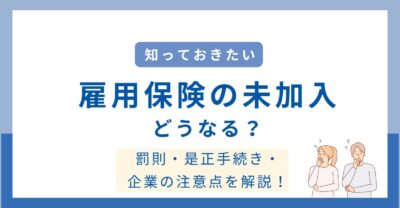雇用保険に未加入だとどうなる?罰則・是正手続きのポイント・企業の注意点を解説!
雇用保険の未加入は、企業にとって法令違反となるだけでなく、労働者が退職時に受け取る基本手当(いわゆる失業手当)の給付などにも影響する重要な問題です。
未加入のまま放置すると、罰則の適用や保険料の遡及徴収、給付金の不支給による信用低下といった、企業経営に大きなリスクが生じるおそれがあります。
この記事では、企業が知っておくべき雇用保険未加入による罰則や労働者への影響、未加入に陥りやすいケースと注意点をわかりやすく解説します。
未加入が発覚した場合の是正手続きについても詳しく解説していますので、万が一に備えた実務対応にぜひご活用下さい。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
雇用保険に未加入だとどうなる?企業への罰則とリスク

雇用保険に未加入であることは、企業にとって重大な法的リスクを伴います。
雇用保険法第7条では、適用基準を満たす労働者について、企業や労働者の意思に関係なく被保険者としたうえで、公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはならないと定められています。
つまり、対象となる労働者がいれば、企業は必ず雇用保険に加入させなければなりません。
ここでは、雇用保険に未加入の場合、企業が負う法的責任と罰則について詳しく解説します。
雇用保険に未加入だった場合の法的罰則とは
雇用保険制度は、失業や育児などで働けない期間の生活を支える公的な仕組みです。
1人でも加入要件を満たす労働者を雇用している企業は原則として加入が義務付けられています。
それにもかかわらず、企業が雇用保険加入の届出をせず未加入のままにしている場合や偽りの届出をした場合は、雇用保険法83条で「6か月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金」に処されると定められています。
企業が罰則を受けるまでの流れ
企業が雇用保険の加入手続きを怠っている場合、その事実は、労働者からの申告やハローワークへの確認などを通じて明らかになることがあります。
未加入が発覚すると、まず管轄のハローワークから加入手続きの指導があります。そして、再三にわたって加入指導等を行ったにも関わらず、加入手続きを行わない場合は労働局の職権による強制加入手続きにより、最大2年間遡った雇用保険料と追徴金(10%)が徴収されます。
また虚偽の報告・隠蔽などの悪質な対応を取る場合などには、雇用保険法に基づく罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があります。
罰則を避けるためには、雇用保険の加入要件を正しく理解し、適切に対応することが重要です。
雇用保険の加入要件とは

ここでは、企業と労働者それぞれに求められる加入要件について、厚生労働省の基準に基づいてわかりやすく解説します。
「誰が・いつから・どのような条件で」加入対象となるのか、あらためて確認しておきましょう。
企業側の加入要件
雇用保険は、以下の加入要件に該当する労働者を1人でも雇っている場合、企業に対して雇用保険への加入手続きが義務付けられています。
農林水産業の一部を除き、業種や事業規模にかかわらず、労働者を雇用するすべての企業が雇用保険の適用事業所として取り扱われるため、例外はほとんどありません。
雇用保険の加入要件に該当する労働者を雇用した場合は、所轄のハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
労働者側の加入要件
労働者が雇用保険に加入するには、以下のいずれの要件も満たす必要があります。
| 1.31日以上の雇用見込みがあること
「31日以上の雇用見込みがある」と判断される具体例:
※当初は31日未満の見込みであっても、後に31日以上の雇用が見込まれるようになった時点から、雇用保険の適用対象となります。 2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること |
雇用した労働者が雇用保険の対象になる場合、企業は「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークへ提出する必要があります。
提出期限は、被保険者となった月(=雇用開始日など)の翌月10日までです。
加入漏れは、企業・労働者それぞれにリスクをもたらします。企業には、要件の確認と正確な手続きが欠かせません。
雇用保険の未加入リスクと影響

雇用保険に加入していない状態が続くと、企業・労働者の双方に深刻なダメージが及ぶ可能性があります。
それぞれに及ぶ主なリスクと影響は以下のとおりです。
企業側のリスク
企業が雇用保険に加入していなかった場合、次のような重大なリスクが生じる可能性があります。
- 法的責任や罰則の対象となり、社会的信用を損なうことで企業イメージが悪化する
- 過去に遡って保険料を徴収され、企業の財政に影響が出る
- 労働者が給付を受けられず損害を被った場合、損害賠償請求につながる恐れがある
また、企業が雇用保険の加入義務を怠った場合、その影響は労働者にも及びます。
労働者への影響
雇用保険に未加入であることにより、労働者は本来受けられるはずの給付制度を受けられなくなります。
【受けられなくなる主な給付・支援】
(1)離職票が交付されないため申請できない給付
(基本手当、技能習得手当、傷病手当、高年齢求職者給付金など)
(再就職手当、就業促進定着手当など) (2)雇用保険に未加入のため、そもそも支給対象外となる給付
(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金)
(高年齢雇用継続給付、介護休業給付)
(出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金) |
雇用保険の未加入は、企業にとっては法的・財政的リスク、労働者にとっては生活支援の喪失という深刻な影響をもたらします。
こうしたリスクを回避するためにも、雇用保険の適正な加入と退職時の適切な事務処理が必要です。
雇用保険に未加入だった場合の是正手続き

万が一、雇用保険に未加入だったことが発覚しても、速やかに適切な是正手続きを行うことで、法的リスクや従業員への不利益を最小限に抑えられます。
企業と労働者それぞれの立場で必要な是正手続きの流れを、正しく理解しておきましょう。
企業が雇用保険に未加入だった場合
企業が雇用保険に未加入であるということは、事業所として「雇用保険適用事業所設置届」が提出されておらず、制度上の適用対象になっていない状態を意味します。
そのため、是正にあたっては雇用保険の適用事業所としての手続きから順を追って対応する必要があります。
【手続きの流れ(※農業・建設業を除く一般的な手順)】
| (1)労働基準監督署で「労災保険」の手続きをする
【提出書類】
※各様式は、労働基準監督署やハローワークの窓口で受け取るほか、郵送でも入手が可能です。 (2)ハローワークで「雇用保険」の手続きをする 【提出書類】
【確認書類】
①登記事項証明書、②事業計画書、③工事契約書、④不動産契約書、⑤源泉徴収票、⑥他の社会保険の適用関係書類
①労働者名簿(法令様式第19号)②賃金台帳 ③出勤簿またはタイムカード(雇い入れ日から提出日までの分 ④雇用契約書(有期契約労働者の場合) ※上記手続きの詳細、また農業・建築業に関する手続きは、引用元をご確認ください。 |
引用:厚労省|~雇用保険の手続きが初めての場合、まずこちらの手続きからお願いいたします~
事業所全体で保険関係成立届を未提出のまま、保険料も納めていない場合は、保険料の徴収時効である2年経過後でも納付できることになっています。
労働者が未加入だった場合
企業が雇用保険の届出を期限内(被保険者となった月の翌月10日まで)に行わず、労働者が未加入だったことが判明した場合、早急な是正対応が求められます。
手続きは所轄のハローワークで行い、未加入期間によって内容が異なります。
6か月以内の遅れの場合は「雇用保険被保険者資格取得届」の提出と、書類確認(労働者名簿、雇用契約書、タイムカードなど)のみで手続きが可能です。
6か月以上遅れた場合は、審査が慎重に行われることから、以下の書類を提出する必要があります。
上記以外に、労働者名簿および労働条件が確認できる書類(雇用契約書または労働条件通知書)の提出を求められる場合があります。 |
また、雇用保険料は原則として過去2年間に限り、さかのぼって納付が可能です。
ただし、給与から雇用保険料が控除されていた事実が確認できる場合は、2年を超えて遡及加入が認められることがあります。
なお、保険料は企業・労働者の双方で負担する仕組みのため、労働者本人にも納付内容を丁寧に説明し、トラブルの未然防止に努めましょう。
雇用保険未加入に陥りやすいケースと注意点

雇用保険は原則としてすべての労働者が対象ですが、現場では加入漏れが起きやすい場面がいくつかあります。
特にパートタイム労働者や高年齢者の雇用は雇用形態が多様になることが多く、注意が必要です。
以下に、未加入に陥りやすいケースとその回避ポイントについて解説します。
パートタイム労働者の雇用保険
パートタイム労働者のような短時間労働者であっても、以下の適用基準を満たしていれば、被保険者として雇用保険への加入が必要です。
【適用基準】
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
ただし、上記の適用基準を満たしていても、次のいずれかに該当する場合は雇用保険に加入することができません。
- 季節的に雇用される労働者(雇用期間が4か月以内、かつ労働時間が週30時間未満)
- 昼間の学生(夜間・通信・定時制を除く)
- 複数の企業で雇用されており、既に他社で雇用保険に加入している場合
パートタイム労働者は雇用や勤務の形態が多様であるため、個別に契約内容を確認することが重要です。
自社のパートタイム労働者が加入対象になるか、判断に迷う場合は、所轄のハローワークに相談すると安心です。
65歳以上の労働者の雇用保険
平成29年1月1日より、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となりました。
これにより、65歳以上の労働者で適用基準(31日以上の雇用見込み、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上)を満たす場合、雇用保険への加入が必要です。
65歳以上の雇用保険については、こちらの記事をご覧ください。
(関連記事:雇用保険の加入は何歳まで?65歳以上の加入要件や再雇用時の手続きを徹底解説!)
よくある質問

雇用保険の未加入が発覚した場合、「どこまで遡って加入できるのか?」は企業担当者が悩むポイントです。
ここでは、遡及可能な期間とその条件についてわかりやすく解説します。
Q.1|雇用保険に未加入だった場合、何年まで遡って加入できますか。
原則として、未加入が判明した日から2年前まで遡って加入が可能です。
(例:2025年4月1日に未加入が判明した場合→2023年4月1日まで遡及可能)
Q.2|雇用保険は2年を超えて遡って加入できますか。
原則は2年までですが、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明確な場合は、2年を超えて遡っての加入手続きができます。
この場合、企業は労働者負担分も含めて保険料全額をまとめて納付する必要があります。
手続き手順についてはこちらに詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
まとめ|雇用保険の未加入が発覚したら速やかに手続きを行うことが大切
本記事では、企業が雇用保険に未加入だった場合に生じる法的リスクや、企業・労働者それぞれへの影響、そして是正手続きの具体的な流れについて解説しました。
雇用保険の未加入は、罰則や信用低下、労働者への不利益につながる重大なリスクを伴います。特に、パートタイムや高年齢の労働者は加入要件の見落としが起きやすく、注意が必要です。
また、過去2年を超える期間であっても、条件によっては遡及加入が認められる場合があり、状況に応じた適切な判断が必要です。
手続きや要件判断に不安がある場合は、社労士などの専門家への相談も検討し、リスクを抑えた確実な手続きを進めていきましょう。
雇用保険の未加入について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。