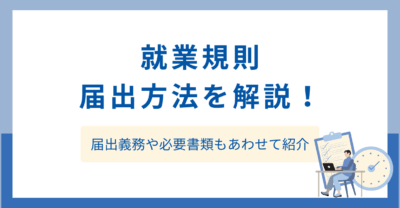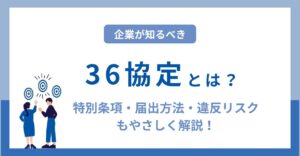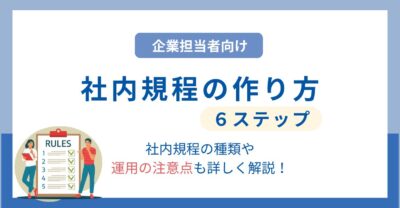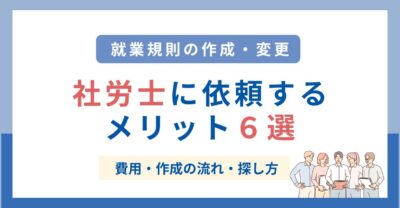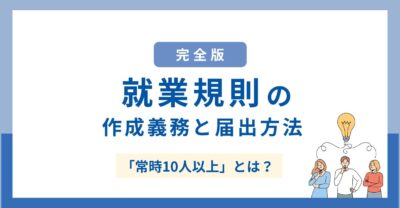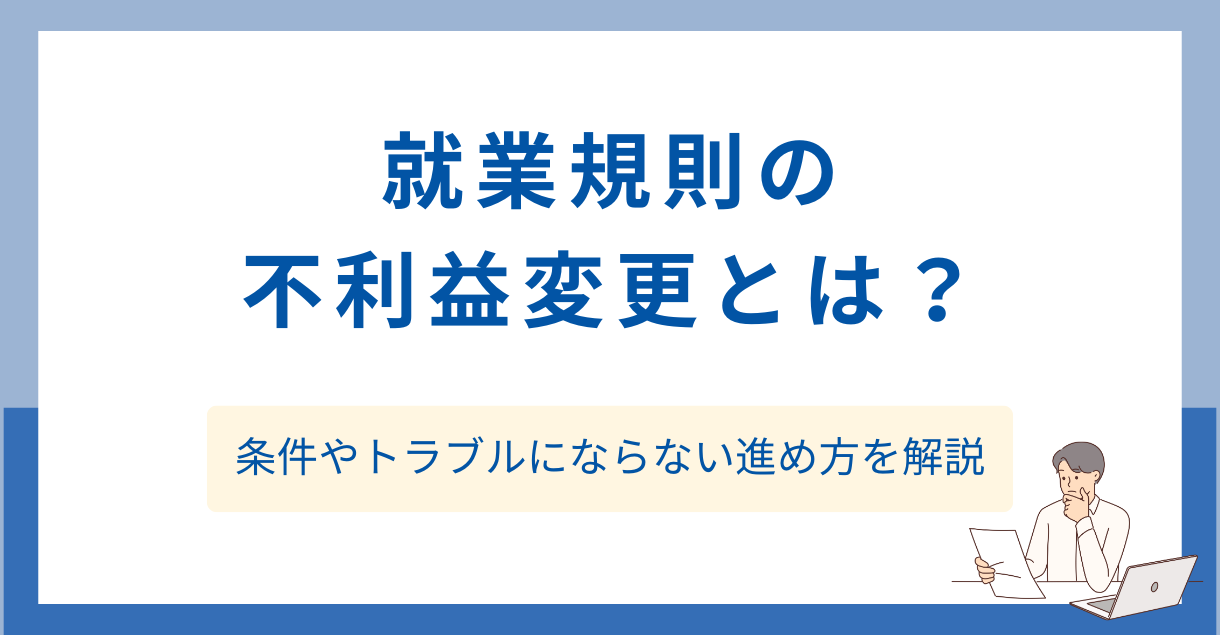
就業規則の不利益変更とは?条件やトラブルにならない進め方を解説
就業規則を見直す際、変更内容が不利益変更になるのかどうか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。不利益変更とは、従業員に不利益が生じる内容へ変更することを指します。
不利益変更は行わないことが望ましいものの、経営状況によっては実施を検討せざるを得ない場合もあります。本記事では、不利益変更となる条件や不利益変更に従業員が合意しない場合について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
就業規則・労働条件の不利益変更とは?
就業規則の不利益変更とは、従業員の労働条件を不利に変更することを指します。
不利益変更を行うためには、法律にもとづいたルールに則る必要があるため、実施する前の確認が重要になります。次にどのような内容が不利益変更に該当するか、具体例を挙げて解説しますので、参考にしてください。
就業規則・労働条件の不利益変更禁止の原則
労働条件は、原則的に会社の一方的な判断では変更できません。
すでに就業規則で定められている労働条件は、労使間で合意した内容で定められています。そのため、従業員の意思に反する内容とする不利益変更は、一方的に行えません。
不利益変更は従業員の収入や生活に大きな影響を与えるため、原則として従業員の合意を得た上で行うことが義務付けられています。※労働契約法 第9条
不利益変更の具体的な一例
不利益変更に該当する具体的な例を以下の表にまとめました。
| 賃金(手当、退職金) | ・基本給や手当の減額 ・定期昇給の廃止 ・基本給に固定残業代を含ませる |
| 休日や有給休暇 | ・年間の所定休日を減らす ・それまで休日だったお盆や年末年始を有給休暇扱いにする |
| 労働時間 | ・労働時間の延長(賃金は変わらない場合) ・シフト変更 |
| 雇用形態 | ・正社員からパート社員、無期パート社員から有期パート社員などに変更する |
| 異動・出向 | ・賃金が低い企業や休日が少ない企業に出向させる ・休みが不規則な部署へ異動させる |
| 懲戒解雇 | ・懲戒事由の追加や厳格化 |
不利益変更は原則として、従業員の合意がなければ行えません。しかし、不利益変更に該当するすべての内容が認められないわけではなく、一定の条件を満たせば変更が可能です。認められるケースは少ないものの、合理性が認められた場合には適法とされることがあります。
就業規則・労働条件の不利益変更が可能になる条件
就業規則および労働条件の不利益変更が可能になる条件は、以下のとおりです。
- 変更内容に合理性がある
- 就業規則を周知する
変更内容に合理性がある
変更する内容に合理性が認められる場合は、不利益変更が可能となります。合理性を判断する要素として、以下の4つが挙げられます。
- 従業員が受ける不利益の程度と会社の配慮
- 変更の必要性(会社の存続など)
- 変更後の就業規則が実態に合っているか
- 従業員代表や労働組合との交渉状況
また、従業員が受ける不利益に対して会社が十分な配慮を行う場合、将来的に不利益を緩和する措置を講じる場合には、合理性が認められる可能性があります。
さらに、不利益変更を行わなければならない明確な理由がある場合や、変更内容が業種や企業規模などの実態に合っている場合も、合理性が認められることがあります。
加えて、不利益変更に際して適正な協議を行い、法的手続きを踏んで従業員の意見を聴取した上で就業規則を変更する場合も、認められるケースがあります。
就業規則を周知する
不利益変更を適法に行うためには、変更後の就業規則の周知義務を確実に実施することが重要です。就業規則の周知は、常時見やすい場所への掲示や書面での交付、電子データにより各事業場で内容を常時閲覧できる状態にすることのいずれかで行ってください。
つまり、従業員が就業規則の内容を常に確認できる状態にしておくことが必要であり、この周知義務を怠った場合には、労働基準法違反となり罰金が科せられることもあります。
就業規則・労働条件の不利益変更を進める手順
就業規則および労働条件の不利益変更は、適正な手順を踏むことで法的に有効と認められる場合があります。ここで、不利益変更を進める際の適切な手順を確認しましょう。
- 従業員に対して適切な説明を行う
- 従業員の合意を個別に得る、または、労働協約を変更する
- 就業規則を変更する
従業員に対して適切な説明を行う
不利益変更を進めるにあたって、まずは従業員に対して丁寧に説明することが重要です。説明する際には、不利益変更の具体的な内容と変更が必要な理由を正確かつ分かりやすく伝えてください。不利益変更を適法に行うためには、従業員からの合意が必要となるケースがあるため、十分な理解を得ることが不可欠です。
また、従業員への不利益が大きい場合は代償措置を検討して、提示することが望まれます。従業員と誠実に協議することで、不利益変更に対する理解を得やすくなります。
なお、従業員に説明する際に、威圧的な態度や解雇をほのめかして合意させると不利益変更自体が無効と判断される可能性があります。不利益変更について合意を得られなかった場合には、無理に合意させてはなりません。従業員が納得できる代償措置を提案するなど、十分な協議を行うことが不可欠です。
従業員の合意を個別に得る、または、労働協約を変更する
不利益変更を行う場合には、原則として個別に従業員の合意を得ることが基本となります。就業規則の変更を行う際の手続きとは異なるため注意しましょう。
個別に合意を得る方法は任意とされているため、書面に残したり全従業員を集めて会議を行ったりする義務はありません。不利益変更の内容と必要性を個別に説明し、従業員が合意すれば成立します。
しかしながら、実務上は、変更内容やその必要性について文書で説明し、同意書に署名・押印をもらう方法が一般的です。全従業員を集めて会議を開く必要はありませんが、各従業員に対し丁寧に個別説明を行うことが重要です。
同意書は個別に合意を得た証明となるため、万が一の紛争に備えて保管しておきましょう。トラブルを未然に防ぐためには、個別説明の場面での録音や録画に基づき議事録を残しておくことも有効です。
なお、労働組合がある場合には、会社と労働組合が合意した労働協約の変更により、不利益変更が可能になります。ただし、労働協約の効力は組合員に限定されるため、非組合員にも不利益変更の内容を適用させる場合には、個別の合意を得る必要があります。
例外として、当該労働組合が事業場の従業員の4分の3以上で構成されている場合は、非組合員にも労働協約が適用されることもあります。
また、地位や年齢、性別などにより不利益の程度に大きな差が生じる場合は、労働協約による不利益変更が認められないこともあるため、注意が必要です。
合意を得る際のポイント
不利益変更について合意を得る際は、口頭ではなく書面で合意してもらうことが重要なポイントです。
口頭での合意では、後になって従業員から「説明を受けていない」「無理強いさせられた」などと主張された場合に、合意が無効となる可能性があるためです。また、口頭での説明だけでは、不利益変更の内容が正確に伝わらず、従業員の理解不足によるトラブルも生じるかもしれません。
そのため、合意の証拠として書面による「同意書」や「説明同意確認書」などを作成することが望ましいです。
合意書に必要な記載内容は以下のとおりです。
- 変更内容(どの労働条件が変わるのか)
- 不利益の程度(従業員にどのような影響が生じるのか)
- 変更理由(なぜ変更が必要なのか)
- 変更日(いつから変更されるのか)
なお、就業規則の変更は、労働基準監督署への届出に加えて、従業員に周知されることで効力が生じます。そのため、合意書などに記載する変更日については、あらかじめ「○月○日適用予定」などと予定日として記載しておくと、従業員との認識のずれを防ぐことができます。
従業員が合意しない場合
仮にすべての従業員が反対する場合は、変更内容が合理性に欠けている可能性があります。このような場合には、不利益変更の内容やその必要性について、改めて見直しを行い、従業員にとって納得しやすい形に再構成することが望ましいでしょう。
一方で、一部の従業員が反対している場合であっても、変更内容に合理性が認められれば不利益変更が認められるケースもあります。とはいえ、将来的なトラブルを防ぐためにも、できる限り全従業員の理解と合意を得られるように努めましょう。
もし労働紛争に発展してしまった場合でも、多くの従業員が不利益変更に合意している事実があれば、裁判等で合理性の有無を判断する際の有力な判断材料となる可能性があります。
就業規則を変更する
合意を得たあとは、就業規則を変更して所轄の労働基準監督署に届け出ましょう。この届出に際しては、不利益変更にあたって個別に従業員に合意を得る手続きとは別に、従業員代表の意見書を添付する必要があります。
事業場内のすべての従業員の中から、民主的な手続きにより従業員代表者を選出し、就業規則の変更についての意見書を記載してもらいます。
不利益変更の個別合意とは異なり、合意を求める手続きではなく、就業規則の変更内容に対して意見を聴く手続きとなります。
就業規則の意見書については、下記の記事で手続き方法やテンプレートを用いた書き方を紹介していますので、あわせてご覧ください。
(関連記事:就業規則の意見書とは?記入例や作成時のポイントや注意点を解説)
違法な不利益変更を行った際のリスク
違法な不利益変更を行った際のリスクとしては、訴訟による損害賠償請求などが挙げられます。
訴訟の結果、不利益変更の違法性が認められた場合、不利益変更は無効になります。無効になると、過去3年さかのぼって、変更前の労働条件に基づく賃金の支払いが発生するケースもあります。
不利益変更に関する問題は、変更直後ではなく、数年後になってから従業員とのトラブルに発展するケースもあります。
また、一人の従業員から訴えられた場合でも、その訴訟の結果として不利益変更が無効と認定されれば、ほかの従業員にも波及して、該当する全従業員へ賃金等の支払いを命じられる可能性があります。
違法な不利益変更に対する罰則はないものの、前述のような訴訟や労使トラブルのリスクを考慮すると、合理性に欠ける不利益変更は避けるべきです。
さらに、不利益変更が法律上有効であったとしても、従業員のモチベーションの低下や離職、生産性への悪影響や会社のイメージダウンなどにつながる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
不利益変更を行う際の注意点
不利益変更は、変更しようとする内容によって注意すべきポイントが異なります。ここでは、以下のケースを例に挙げて、不利益変更を行う際の注意点を解説します。
- 給与減額・手当の廃止の場合
- みなし残業代の廃止の場合
- 労働日数・休日の変更の場合
- 会社支給から従業員負担に変更の場合
給与減額・手当の廃止の場合
給与を減額する場合は、どの程度の減額となるのかを示しつつ、削減後の給与水準が同業他社や同規模企業と比べて、妥当であるかを説明できるようにしておくことが重要です。比較した他社と大きな差がないようであれば、不利益変更であっても合理性があると判断されやすくなります。
また、給与の削減計画を立てた後は、従業員に理解してもらえるよう十分に説明し、個別に合意書を取得することが望まれます。
みなし残業代の廃止の場合
みなし残業代制度は、あらかじめ一定時間分の残業代を固定で支払う制度であり、廃止すると従業員の受け取る賃金が少なくなる可能性があります。特に実際の残業時間がみなし時間に満たない従業員にとっては、廃止により手取り額が下がることになり、不利益変更に該当します。
ただし、本来残業代は実際に残業した時間に対して支払われるものであるため、従業員の合意が得られなかった場合でも、合理性が認められれば、不利益変更として有効とされる可能性があります。
また、みなし残業代制度の廃止により、従業員の給与が著しく低下することが見込まれる場合には、一定期間に限って手当を支給するような経過措置を設けることも有効です。
経過措置があることで、会社が従業員に対して十分な配慮をしていることが評価され、不利益変更の合理性が認められる可能性が高まります。
労働日数・休日の変更の場合
労働日数や休日を変更する場合は、給与計算の基礎となる各種単価への影響を具体的に示しましょう。
変更案には、時間単価や残業単価、休日出勤単価などを明記すると、単に労働日数が増減すること以外に、どのような影響があるのかを従業員に正しく伝えることができます。
また、固定残業代や時間控除単価などの見直しがある場合も、あわせて明記しておくことで、不利益の程度を明確に示すことが可能です。
会社支給から従業員負担に変更の場合
制服や作業服、作業用品などの購入費用を、会社負担から従業員負担に変更する場合、これらの費用が賃金に該当していない場合には、従業員の個別合意がなくても変更が認められるケースがあります。
しかし、就業規則上で会社が費用を負担すると定めているものを変更する場合には、合理性を確保するためにも、従業員の合意を取得する対応が求められます。
このように、不利益変更に該当するかどうかの判断はケースバイケースであるため、就業規則の変更のみで済む場合もあれば、個別に従業員の合意を得なければならない場合もあります。
不利益変更を行う際は専門家に相談しよう
不利益変更は、その性質上、労務トラブルにつながりやすいものであり、会社も従業員も可能な限り避けたいものです。しかし、会社の経営状況が悪化し、事業の継続や雇用の維持のために、やむを得ず不利益変更を行わざるを得ない状況もあります。
このような場合には、不利益変更を実施した先を見据えるビジョンを持つことが重要になります。
不利益変更を進める際には、従業員一人ひとりの理解と納得を得ることが必要であり、できる限り全従業員が納得した上で合意を得ることを目指しましょう。
そのためには、不利益変更の必要性や内容を丁寧に説明するとともに、不利益を緩和するための措置を検討・提示することが有効です。
不利益変更の合理性や合意手続きに不安がある場合には、専門家である社労士へ相談することをおすすめします。社労士に相談すれば、変更内容の妥当性や合理性、必要な手続きについて具体的にアドバイスを受けることができ、トラブルを未然に防ぐ一助となります。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。