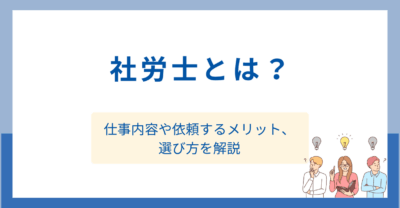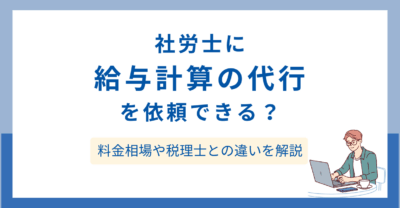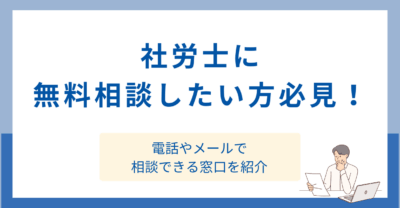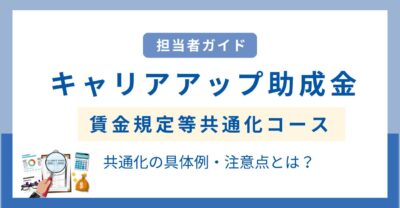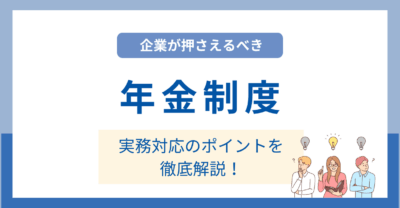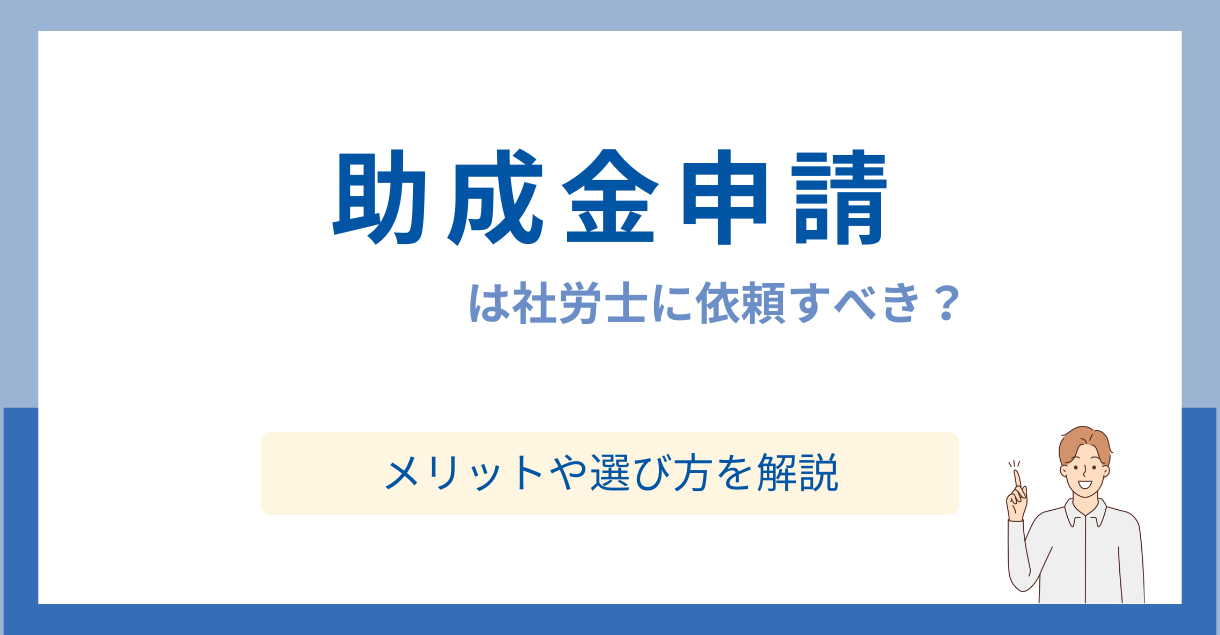
助成金申請は社労士に依頼すべき?メリットや選び方を解説
企業が助成金を申請して受け取るまでの過程は複雑であり、途中でつまずくことも少なくありません。助成金の申請を社労士に依頼し、つまずくことなくスムーズに進めたいという方も多いでしょう。
本記事では、社労士に助成金申請を依頼する際のメリットや、社労士の選び方を解説します。また、社労士に依頼したい助成金の種類もあわせて紹介しますので、申請を検討される方はぜひ参考にしてください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
助成金とは
助成金とは、国や自治体が推進する施策を行った企業や団体に対して支給される、財政支援を指します。例えば、厚生労働省の所管している助成金では、人材育成や働き方改革の推進など、雇用環境を改善すると受給できます。
補助金と混同されることも多いですが、補助金は申請後に審査が行われ、採択されなければ受給できません。対して助成金は、支給条件を満たせば受給可能です。
とはいえ、助成金の申請から受給に至るまでのプロセスは決して簡単ではありません。具体的には、助成金の選定や申請要件の確認、必要書類の準備といった多くの手間がかかります。この工程には細かな作業や専門的な対応が求められるため、自社で対応するには労力や専門知識が必要です。
厚生労働省の助成金申請を依頼できる社労士とは
厚生労働省の助成金申請を依頼できる社労士は、労働・社会保険に関する法律の専門家であり、企業の労務管理や社会保険手続きをサポートする国家資格の保持者です。
雇用環境の改善によって受給できる助成金にも精通しており、申請手続きを代行することもサポートできます。社労士の主な業務内容をまとめました。
- 労働社会保険の手続き代行(独占業務)
- 就業規則の作成・改定(独占業務)
- 助成金申請代行(独占業務)
- 労務相談
- 給与計算
厚生労働省の助成金申請の代行は、社労士の独占業務に含まれます。そのため、社労士以外が申請を代行することは違法です。助成金申請について、外部の専門家の協力を受ける際には社労士に依頼しましょう。
社労士に助成金の申請を依頼するメリット
助成金の申請を社労士に依頼することで、さまざまなメリットが得られます。主なメリットは以下のとおりです。
- 専門家の視点からアドバイスをもらえる
- 担当者の負担を軽減できる
- 不支給となる可能性を抑えられる
それぞれのメリットを確認して、助成金申請の依頼を検討しましょう。
専門家の視点からアドバイスをもらえる
社労士に助成金の申請を依頼すると、専門家の視点からアドバイスをもらえます。なぜなら、社労士は助成金制度の知識が豊富にあるためです。
新設された助成金や要件が変更された助成金についての最新情報も得られるため、申請の機会を逃しにくくなります。また、申請書類の作成も社労士が代行するため、手間をかけずに助成金を申請できます。
担当者の負担を軽減できる
社労士に助成金の申請を依頼すると、自社担当者の負担を軽減できます。日々の業務に加えて助成金の調査、申請準備、申請後の手続きなど、助成金の申請には時間と労力が必要です。
社労士に依頼すれば、助成金申請に関する書類作成や手続きを任せられるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。これにより、本来の業務をおろそかにせず、助成金も滞りなく申請可能です。
不支給となる可能性を抑えられる
助成金申請を社労士に依頼すれば、助成金が不支給となる可能性を抑えられます。社労士は、助成金を申請する際の必要書類や申請方法を熟知しており、事前申請の漏れや期限の徒過など防ぎます。
なお、助成金が不支給になる原因はさまざまですが、よくあるケースとして、以下の内容に注意しましょう。
- 労働関係法令の違反
- 申請期限切れ
- 解雇のタイミング
- 必要書類の不備
- 手順を間違えた
社労士なら上記の不支給となるケースも把握しており、事前に助成金を受給できるかどうかをある程度判断できます。助成金を受給できそうな場合は、社労士が手続きしてくれるので、安心して任せましょう。
社労士に助成金の申請を依頼する際に気を付けたいポイント
社労士に助成金の申請を依頼する際、気を付けたいポイントもあります。それぞれの内容を確認し、社労士に助成金申請を依頼するかどうかを判断しましょう。
- 依頼に際して発生する費用について把握しておく
- コストと受給額が見合うか確認する
依頼に際して発生する費用について把握しておく
基本的なことですが、社労士に依頼すると着手金や成功報酬などの費用が発生します。費用は社労士事務所や助成金の種類により異なるため注意しましょう。
単発の依頼ではなく、顧問契約をしていると着手金がかからない場合や顧問価格が適用される場合もあります。また、そもそも顧問契約をしていないと、助成金申請を依頼できないケースもあるため、注意が必要です。
社労士と顧問契約していれば、助成金申請で就業規則の変更が伴う場合に、会社の状況を把握してもらっている上で相談ができるため安心です。
顧問社労士については、以下の記事でわかりやすくまとめています。あわせてご覧ください。
(関連記事:顧問社労士とは?顧問契約するメリットと探す際のポイントを解説)
コストと受給額が見合うか確認する
社労士に助成金申請を依頼する際は、コストと受給額が見合うかどうかを確認しましょう。制度の導入にあたってコストが発生する場合もあり、助成金でカバーしきれないことも多くあります。
助成金申請や制度の導入などで発生するコストの例として、下記のものが挙げられます。
- 社労士への依頼費用
- 助成金申請の準備作業
- 労働環境改善など助成金の要件となる施策の導入・運用
- 教育訓練の費用
コストは基本的にかかるものであるため、助成金で全額をカバーしようとせず、予算を組んでおくことが大切です。また、費用を抑えようと施策を行ったことにするなどの不正受給を行うと助成金の返還や刑事告訴などのペナルティがあります。
社労士に依頼したい助成金の種類
助成金の種類は非常に豊富で、さまざまなものが挙げられます。なかでも、社労士に依頼したい雇用や労働環境改善に関する助成金の一部を紹介します。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| キャリアアップ助成金 | 非正規雇用労働者のキャリアアップを支援するための助成金 |
| 両立支援等助成金 | 仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主を支援する助成金 |
| 人材確保等支援助成金 | 人材の確保・定着に取り組む事業主を支援する助成金 |
| 65歳超雇用推進助成金 | 65歳以上への定年引き上げなどの取り組みを実施した事業主を支援する助成金 |
| 働き方改革推進支援助成金 | 時間外労働の削減や週休2日制の推進、労働時間の適正管理、勤務間インターバル制度の導入や有給休暇を取得しやすい環境整備をする事業主を支援するための5つのコースが設けられている助成金 |
※厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
記載した助成金は一部であり、ほかにもさまざまな種類があります。また、要件や受給額は変動するため、申請前に必ず最新の情報を確認しましょう。
助成金を依頼する社労士の選び方
助成金を受給するためには、助成金に強く申請の実績が豊富な社労士のサポートを受けることが重要です。ここでは、社労士を選ぶ際に押さえておきたい以下のポイントを解説します。
- 助成金申請の実績があるか
- 導入する施策に対して長けているか
- コミュニケーションは取りやすいか
助成金申請の実績があるか
助成金申請を依頼する社労士を選定する際には、これまで助成金申請の実績があるか確認しましょう。経験の浅い社労士よりも、過去に助成金申請手続きをこなしてきた豊富な経験を持つ社労士がおすすめです。
経験が豊富な社労士は、申請のノウハウを持っているほか、直近で同じ助成金の申請を行っている場合もあるため、スムーズに必要書類の作成や申請手続きを進められます。
ほかには、自社の業界に特化した社労士を選ぶことも有効でしょう。業界特有の課題に対応するための助成金や業界ごとの労働慣行にマッチした助成金を把握しており、助成金に対応する施策についても熟知していることから最適な提案を受けられることでしょう。
導入する施策に対して長けているか
労働環境の改善などといった助成金支給対象の施策や制度に対して長けているのかも、社労士を選ぶ際の重要なポイントです。助成金は、施策や制度を導入する際に受給できます。実施する施策が決定している場合は、施策自体を得意とする社労士かどうかを確認することがおすすめです。
例えば、労働環境の改善を目的としたテレワークの導入や、従業員のスキル向上を支援する研修制度の実施など、企業によって取り組む施策は異なります。それぞれの施策に適した助成金を申請するには、対象となる要件や制度を理解した上で、申請サポートができる社労士を選ぶことが大切です。
コミュニケーションは取りやすいか
社労士の実績や知識だけでなく、コミュニケーションのしやすさも重要な要素です。知識が豊富で実績があっても、相談しにくかったり対応が一方的であったりすると、円滑な連携が難しくなります。
助成金の申請は、企業の労務管理や経営方針にも関わるため、信頼関係をもってやり取りできることが求められます。こまめな連絡が取れるか、質問しやすい雰囲気があるかなども確認しながら、スムーズに相談できる社労士を選びましょう。
コミュニケーションの取りやすい社労士であれば、助成金の申請だけでなく、今後の労務管理や新たな制度の導入についても相談してみると良いつながりが生まれるのではないでしょうか。
社労士に助成金申請を依頼する流れ
最後に、社労士に助成金申請を依頼する基本的な流れを解説します。
- 依頼前の準備
・「全国社労士検索」などで社労士を検索
・社労士に相談して申請する助成金を決定 - 社労士との契約・申請準備
・契約内容の確認
・契約の締結 - 申請手続き
・申請書類やデータを用意
・申請書類の作成・提出
・審査・支給決定 - 審査・支給決定
・審査後のアフターフォロー
この助成金申請の流れは、助成金の種類や社労士事務所によって異なる場合があります。
なお、申請手続きに必要な書類やデータは自社で用意しなければならないものもあります。社労士に任せたら何もしなくても良いというわけではありませんので、その点は把握しておきましょう。
社労士に助成金を依頼してスムーズに申請を進めよう
社労士に助成金申請を依頼すれば、専門的なアドバイスがもらえるほか、滞りなく手続きを進められる点がメリットです。コストと受給額が見合うかどうかは要確認ですが、依頼後は社労士とコミュニケーションを取りながら、要所要所の気を付けたいポイントを把握しておけば、円滑に助成金を受給できるでしょう。
依頼する際は相談しやすく助成金申請の実務経験が豊富な社労士がおすすめです。これまで培ってきたノウハウをもとに、自社に合う助成金の提案についても期待できます。助成金申請を検討している方は、ぜひ社労士に相談してください。
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。この日本最大級の社労士検索サイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
社労士によって初回相談は無料の場合も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。