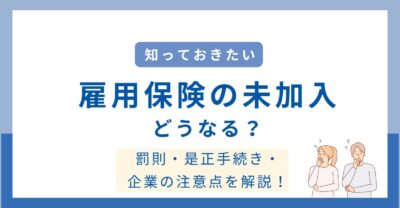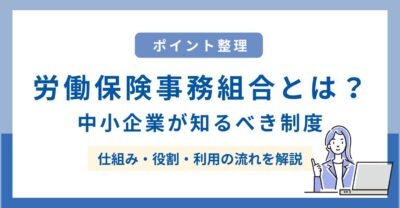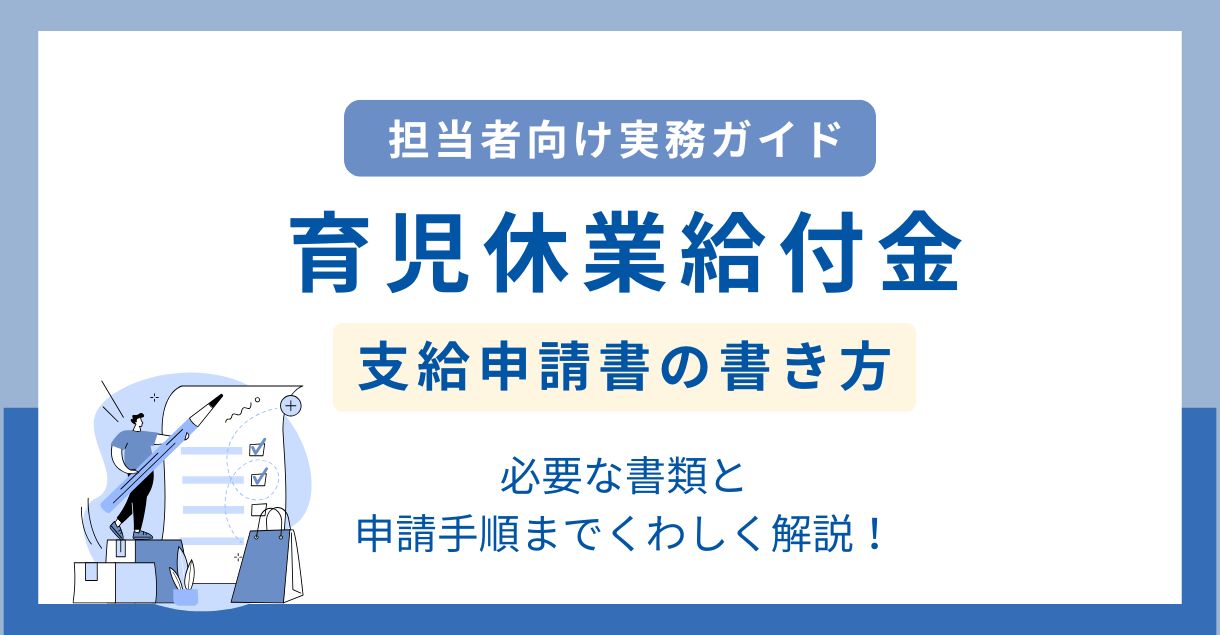
【実務ガイド】育児休業給付金 支給申請書の書き方と必要な書類・申請手順を詳しく解説!
育児休業給付金を適切に受給するためには、正確な申請手続きと必要書類の準備が欠かせません。
書類の不備や記入ミスがあると、支給の遅れや不支給につながる恐れもあるため、企業としても慎重な対応が求められます。
本記事では、「育児休業給付金とは何か」といった制度の基本から、申請に必要な書類の一覧、記入例付きの書き方解説、よくある質問までを網羅的に解説します。
育児と仕事の両立を支える制度運用は、企業の信頼や人材定着にも関わる重要な取り組みです。
制度を正しく理解し、実務に役立てていただくためにも、ぜひ最後までご覧ください。
※育児休業関連の給付金は、他にも出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金がありますが、本記事では、「育児休業給付金」に絞って解説しております。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
育児休業給付金とは

育児休業給付金は、雇用保険法(第六十一条の七)に基づき、実施されている公的な給付金です。
育児休業を取得した雇用保険の被保険者に対し、育児休業中の経済的負担を軽減し、職場復帰を支援することを目的に支給されます。
この給付金を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
【支給対象となる主な条件】
|
支給期間は原則、子が1歳に達するまでですが、「申込を行っているにもかかわらず、保育所等の利用ができない場合」などの理由がある場合は規定の書類を提出し認定を受けることで、1歳6か月または2歳まで延長できる場合があります。
なお、両親がともに育児休業を取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」の制度を利用することで、いずれか一方の育児休業を子が1歳2か月になるまで延長することが可能な場合もあります。(参考:育児休業等給付の内容と支給申請手続|厚生労働省)
育児休業給付金の申請手順

育児休業給付金の申請は、原則として、被保険者を雇用している企業(事業主)がおこないます。ただし、本人の希望があれば被保険者が直接提出することも可能です。
この章では、企業の担当者が押さえるべき初回・継続の申請フローを説明します。
申請手順の流れ
手順①|申請前の要件確認と社内対応の準備労働者から育児休業の申出があった場合には、支給対象の要件を満たしているか必ず確認しましょう。 確認すべきポイント:
手順②|必要情報の確認と申請書の作成支給対象と判断した場合、必要書類を準備します。 企業側で管理している情報(勤怠・賃金など)と、労働者本人から提出してもらう情報(母子手帳・給付金の受け取り口座など)を整理し、所定の様式へ記入します。 手順③|初回申請と受給資格確認の実施初回申請は育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の月末までに、必要書類をまとめて事業所管轄のハローワークへ提出します。 例:育児休業開始日が7月10日の場合→4か月を経過する日は11月9日、提出期限は11月30日までとなります。 基本的に、初回申請と受給資格確認は同時に行います。 ※初回申請に必要な書類については初回申請に必要な書類で詳しく説明しています。 手順④|2回目以降、継続申請(2か月ごと)の対応継続申請では、原則として2か月ごとに、育児休業を継続していることを確認するための書類を提出します。 ※2回目以降の継続申請に必要な書類については2回目以降(継続申請)に必要な書類で詳しく説明しています。 |
申請にはそれぞれ期限が明確に定められているため、企業と労働者の間でスケジュールを共有し、余裕を持って準備を進めましょう。
育児休業給付金の申請に必要な書類

育児休業給付金を遅滞なく受給するには、申請に必要な書類を漏れなく、正確に準備する必要があります。
この章では、初回申請と継続申請それぞれに必要な書類を詳しく解説します。
初回申請に必要な書類
初回申請では、「育児休業給付の受給資格申請」と「初回の支給申請」を1枚の書類で行います。
(書類は「出生後休業支援給付金支給申請書」も兼ねていますが、ここでは育児休業給付金の申請に絞って解説しております)
初回申請時に必要な書類は以下のとおりです。
【提出書類(両方必要)】※ハローワークインターネットサービスからダウンロード・電子申請が可能です。
※ハローワークのサイトからはダウンロードできません。企業所在地を管轄するハローワークの窓口、または郵送で受け取る必要があります。 【添付書類】・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取り扱い通知書など ※育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの。 ・母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など ※育児の事実、出産予定日および出生日を確認することができるもの(写し可) |
初回申請により受給資格が認定されると、ハローワークから「継続申請用の育児休業給付金支給申請書」が交付されます。
以降は、原則として2か月ごとに支給対象期間に応じた継続申請が必要です。
また、育児休業受給資格確認のみ先に済ませている場合には、交付されるこの様式が、初回からの支給申請書として使用されます。
2回目以降(継続申請)に必要な書類
継続申請では、支給対象期間中に育児休業を引き続き取得していることを証明するための書類を提出します。
継続申請時に必要な書類は以下のとおりです。
【提出書類】
【書類確認用資料(該当支給対象期間分)】・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなど。 ※育児休業給付金支給申請書の記載内容を確認できるもの。 |
育児休業給付金の申請書の書き方【記入例あり】

育児休業給付金の申請書類は、育児休業の期間や就労・賃金の有無など、給付の可否に関わる情報を正確に記入する必要があります。
ここでは、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」の書き方について詳しく解説します。
正しく記入するために、あらかじめ必要な情報や資料を手元に揃えておきましょう。
【記入時に必要となる書類】
|
以下、厚生労働省の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書記入例に基づいて、記入方法を一つずつ解説します。
注意事項:
◎印が付いている項目は、実際の申請で特にミスが起こりやすい部分です。
給付額の算出や受給の可否に影響するため、記入時は申請内容の確認・ダブルチェックを企業側で徹底しましょう。
基本情報の記入
1.被保険者番号/3.被保険者氏名:
雇用保険被保険者証に記入された番号(10桁、16桁の場合は下段10桁)・労働者本人の氏名を正確に記入します。
2.資格取得年月日:
雇用保険の資格取得年月日(通常は入社日)を、元号表記で記入します。
(例:令和5年4月1日→「5-050401」)
4.事業所番号:
11桁の雇用保険適用事業所番号を記入します(10桁の場合、左詰めで記入し最後の枠は空欄とします)。
◎5.育児休業開始年月日:
育児休業を開始した日を記入します(※出産日そのものではなく、育児休業の開始日)。ただし、女性の被保険者が労働基準法の規定による産後休業に引き続いて育児休業を取得した場合は記入の必要はありません。
6.出産年月日
育児休業の対象となる子どもの出産年月日を記入します。
7. 出産予定日
育児休業の対象となる子どもの出生日が出産予定日と異なる場合で、出生日前から育児休業を開始している場合に出産予定日を記入します。
9.個人番号
受給予定者本人の個人番号(マイナンバー)12桁を記入します。
10.郵便番号、11.住所/12.電話番号:
現住所、連絡先を正確に記入します。
就業・賃金関連
◎13・17.支給単位期間(その1・その2):
育児休業開始から1か月ごとの期間を「支給単位期間」とし、その1・その2にそれぞれ記入します。用紙1枚で2か月分の申請が可能です。
特記事項・延長・配偶者関連
21.最終支給単位期間:
今回が最終申請となる場合にのみ記入します。
なお、申請時点において、すでに育児休業が終了している場合は、最終支給単位期間を含む3か月分の申請が可能です。
14・18・22.就業日数/15・19・23.就業時間:
育児休業中に就労があった場合、就業日数を記入します。10日以上の場合は就業時間も併記が必要です。
◎16.20.24.支払われた賃金額:
該当する支給単位期間に実際に支払われた賃金総額(いわゆる額面)を正確に記入します。
- 原則含まれる:基本給・残業代・通勤手当・家族手当など
- 含まれない:賞与など臨時に支払われる賃金(通常3か月を超える期間ごとに支払われるもの)
25.職場復帰年月日:
支給申請時点で被保険者が育児休業を終えて復職している場合、その年月日を記入します。
26.支給対象となる期間の延長事由-期間:
保育所に入所できない等の理由で育児休業を延長した場合、理由と延長した期間を記入します。
◎28.配偶者の被保険者番号/29.配偶者の育児休業開始年月日:
「パパ・ママ育休プラス」制度を利用する際に記入します。必要に応じて、配偶者の育児休業開始日や証明書類の添付が求められます。
支給口座・同意欄
◎32.公金受取口座利用希望(払渡希望金融機関指定届):
育児休業給付金の振込先は、育児休業を取得する本人名義の普通預金口座を指定します。マイナポータルに登録された公金受取口座を使う場合は、「公金受取口座利用希望」欄に1と記載します(その場合、金融機関情報について記載の必要はありません)。
裏面.事業所証明欄:
事業所名・所在地・代表者氏名を正確に記入し、申請内容の正当性を企業として証明します。
◎裏面.申請者氏名欄:
原則、育児休業を取得する被保険者本人が記入します。企業が代理申請を行う場合は、「申請について同意済み」と記入します。
企業による代理提出時は、被保険者の同意書などの証明書を保存する必要があります。
各項目を正確に記入することはもちろん、申請時には様式や資料の不備がないか確認しましょう。
育児休業給付金の申請で注意すべき点
ここでは、育児休業給付金の申請において、特に注意すべき3つのポイントを解説します。
1.申請期限と様式の最新確認を徹底する
申請期限を過ぎると、給付が受けられなくなる可能性があります。
- 初回申請:育児休業開始日の翌日から4か月以内
- 継続申請:支給対象期間終了日の翌日から2か月以内
また、申請様式や制度の内容は年度ごとに更新されることがあります。提出前には、厚生労働省やハローワークで最新の情報・様式を必ず確認しましょう。
2.記入ミス・資料不整合を防ぐ
申請書の内容と添付資料の整合性が取れていない場合、差戻しや支給遅延の原因となります。
被保険者番号や育児休業開始日の誤記、就業日数・賃金額と出勤簿・賃金台帳の不一致はよくある記入ミスです。
記入後は必ず社内でダブルチェックを行い、確認資料と照合することが望ましいです。
3.労働者の同意取得と記録の適正管理
企業が申請を代行する場合でも、労働者本人の同意は必須です。
制度の内容を丁寧に説明したうえで、同意書や確認書類を取得し、社内で適切に保管しましょう。
こうした対応は、申請の信頼性を高めるとともに、後のトラブル防止にもつながります。
不明点があれば、早めにハローワークや社労士に相談し、安心して申請を進められる体制を整えましょう。
よくある質問

育児休業給付金の申請に関して、よくある質問を以下にまとめました。
Q1|育児休業給付金の申請書はどこで入手できますか?
以下の方法で取得できます。
【育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書】
ハローワークインターネットサービスからダウンロード可能です。また、事業所の所在地を管轄するハローワークの窓口、もしくは郵送でも取得できます。
【雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書】
ダウンロード不可のため、管轄のハローワーク窓口で直接受け取るか、郵送で取り寄せる必要があります。
詳しくは、本記事内の「育児休業給付金の申請に必要な書類」をご参考ください。
Q2|育児休業給付金の申請は、企業が対応する必要がありますか?
企業が労働者に代わって申請を行うケースが一般的ですが、法的義務ではありません。対応の有無や方法は企業判断に委ねられています。
申請の流れや提出スケジュールについては、事前に労働者本人と確認しておくことが重要です。
Q3|育児休業給付金の申請タイミングはいつですか?
育児休業給付金の申請タイミングは、初回申請と継続申請で異なります。
- 初回申請:育児休業開始日の翌日から4か月以内
- 継続申請:支給対象期間終了日の翌日から2か月以内
いずれも提出期限が明確に定められているため、申請スケジュールを把握し、遅れのないよう計画的に対応することが大切です。
Q4|育児休業中に出勤した場合、給付金はもらえますか?
育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。その場合、就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。
なお、支給単位期間(※1)中に就業した場合は申告が必要になります。就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるときは、育児休業給付金は支給されませんのでご注意ください。
また、育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額される場合等がありますので、ご注意ください。
※1:「支給単位期間」とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間のことです(育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間です。)。
(出典:厚生労働省|育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について)
申請に必要な書類は、支給の可否に直結します。内容や記載方法に不明点がある場合は、早めにハローワークへ確認しましょう。
まとめ|育児休業給付金の申請は企業による正確な記入が不可欠です

本記事では、育児休業給付金の概要から申請手順、必要書類、記入のポイント、注意点までを、人事担当者の視点で詳しく解説しました。
育児休業給付金は、労働者の収入を支える重要な制度であると同時に、企業にとっても信頼性やコンプライアンスの維持に関わる実務の一つです。
ただし、申請には細かな要件確認や書類の準備、制度の最新情報の把握が求められ、社内対応だけでは不安を感じる場面も少なくありません。
申請や運用に不明点がある場合は、ハローワークへの確認はもちろん、社労士など専門家と連携しながら進めることで、安心かつ確実な対応につながります。
育児休業給付金について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。