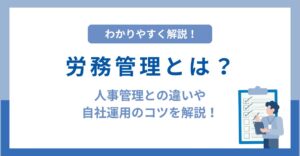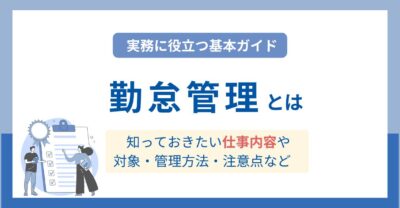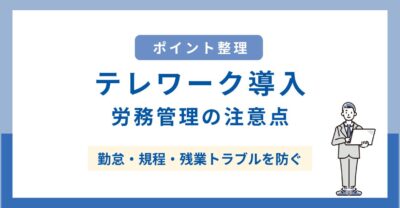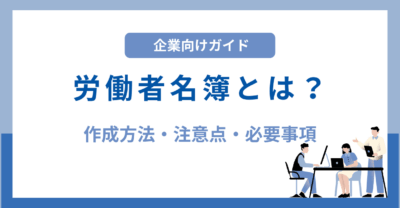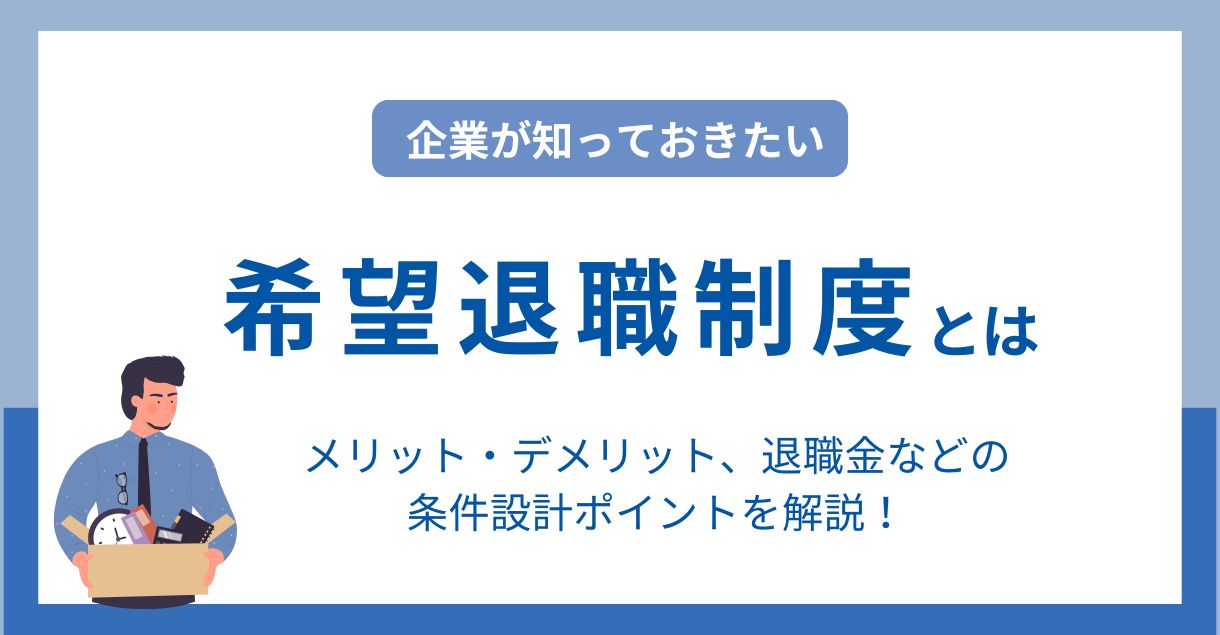
希望退職制度とは|企業が導入するメリット・デメリットと条件設計ポイント
経営環境の変化や将来の不確実性が高まる中、人員整理や組織再編を進める企業が増えています。
実際に、東京商工リサーチによると、2024年に早期・希望退職を実施した上場企業は前年比39.0%増の57社、募集人員は3倍の1万9人にのぼり、3年ぶりに1万人を超えました。
こうした背景のもと、「希望退職制度」は、従業員の納得を得ながら柔軟に人員整理を進められる手段として、注目を集めています。
一方で、制度設計や運用を誤ると、想定外の人材流出や法的トラブルにつながるおそれもあるため、慎重な準備が不可欠です。
本記事では、希望退職制度の仕組みから導入の流れ、割増退職金の設定や制度設計のポイントまで、人事・労務担当者や経営層の方向けに、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。
本記事を読めば、希望退職制度を安全かつ適正に導入するための実務知識と設計の考え方が整理できます。ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
希望退職制度とは

「希望退職制度」とは、経営環境の変化に伴い人員の見直しや事業再編を進める企業が活用する制度のひとつです。
企業が労働者に配慮しつつ、円滑に人員整理を進める手段として導入されるケースが多く見られます。
ここでは、希望退職制度の基本的な仕組みと、混同されがちな「早期退職制度」との違いについて解説します。
希望退職制度の仕組みと特徴
希望退職制度は、企業が通常よりも優遇された退職金などの条件を提示し、それに同意した労働者が自発的に退職を申し出る仕組みです。
応募は本人の自由意思によるもので、企業が労働者に強制することはできません。
なお、必要な人材の流出を防ぐため、企業が最終的に応募者の退職の可否を判断する「承認制」を導入することも可能です。
また、制度を導入する企業の多くは労働者からの応募を促す目的で、以下のような優遇措置を自主的に設けています。
【希望退職制度で導入される主な支援措置の例】
- 割増退職金(通常より多めに支給される退職金)
- 再就職支援サービス(外部機関によるキャリア相談・求人紹介)
- 有給休暇の買取(未消化分の現金清算)
このように、希望退職を募集する際に支援措置を整えておくことで労働者の不安や混乱を最小限に抑えながら、企業は人員整理をスムーズに進められます。
希望退職制度と早期退職制度の違い
希望退職制度と早期退職制度は、いずれも定年前の円満な退職を促す制度ですが、運用の形や導入の目的に違いがあります。
以下に、両者の主な違いを表にまとめました。
| 項目 | 希望退職制度 | 早期退職制度 |
| 運用の形 | 「一時的」な経営施策 | 「恒常的」に運用される社内制度 |
| 導入の目的 | 経営再建・人員整理など | 人員構成の最適化・高年齢層のキャリア支援 |
| 対象者 | 企業が定めた条件(年齢・勤続年数など)に該当する労働者 | 一定年齢以上の労働者(例:55歳以上など) |
| 募集期間 | 限定的(数週間~数か月程度) | 常時応募可能なケースが多い |
| 制度の主体 | 企業が制度として募集 | 労働者が制度を活用して申出 |
希望退職制度は経営課題への対応として一時的に実施されるケースが多く、早期退職制度はあらかじめ制度化された人員構成の最適化策であるという点が特徴です。
希望退職制度のメリット

では、希望退職制度は、企業にとってどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
ここでは、制度導入によって企業が得られる主なメリットを紹介します。
メリット1|希望退職制度による人件費の削減
中高年層の労働者は給与や退職金の水準が高く、企業にとって人件費の負担が大きくなりがちです。しかし、日本では法的に整理解雇のハードルが高いため、簡単には実施できません。
その点、希望退職制度は労働者の同意に基づいて退職を促す仕組みのため、スムーズかつ合法的に人件費を抑制できる手段として有効です。
メリット2|世代交代による組織の活性化と若手育成
希望退職制度によりベテラン層が退職し、管理職や専門職などのポストに空きが生まれると、若手社員に新たな役割やポジションを任せる機会が生まれます。これにより、キャリア形成や成長を促進する環境が整い、組織全体の活性化につながります。
近年では黒字経営の企業でも、将来を見据えた世代交代や人材構成の再設計を目的に制度を活用するケースが増えています。
メリット3|トラブルを避ける円満な退職誘導
希望退職はあくまでも労働者の意思に基づく応募制であり、企業からの一方的な解雇とは異なります。
このため、退職に対する納得感が得られやすく、退職後の労使トラブルを抑えることで、企業イメージの維持や社内外からの信頼確保にもつながります。
希望退職制度のデメリット
希望退職制度は企業にとって人員再編などのメリットをもたらす一方で、運用の仕方によっては思わぬリスクを招くこともあります。
ここでは、制度導入にあたって注意しておきたい代表的なデメリットを紹介します。
デメリット1|割増退職金などによる一時コストの負担
希望退職制度の実施にあたっては、割増退職金の支給や再就職支援サービスの導入など、短期的にまとまった支出が発生する可能性があります。
ただし、中長期的に見た場合、希望退職制度は将来的な人件費を抑える方法として有効です。
たとえば、希望退職者1人あたり月額給与の12か月分を割増退職金として支給した場合、一時的なコストはかかりますが、翌年からはその分の人件費が発生しなくなります。
このように、希望退職による人件費の削減効果と、退職金の支給額や応募人数を踏まえた費用シミュレーションが大切です。
デメリット2|優秀な人材の流出リスク
希望退職は自発的な応募によって成立するため、企業にとって必要な人材まで離職を希望するケースも考えられます。特に、管理職や専門職など中核人材の流出は事業継続に支障をきたす恐れがあります。
こうした事態を防ぐためには、応募者の選定に一定の裁量を持たせる「承認制」を取り入れることで、企業側の判断余地を確保する運用が可能になります。
希望退職制度の導入手順とスケジュールの目安

希望退職制度を円滑に導入するには、制度設計から社内通知、退職処理に至るまで、段階的な対応が求められます。
一般的な実施の流れは、以下のとおりです。
| ステップ | 内容 |
| ① 経営課題の整理 | 経営状況や人員構成の課題を洗い出し、制度導入の背景を明確化する |
| ② 制度設計 | 対象者、募集期間、退職金加算などの条件を社内で検討 |
| ③ 労使協議 | 労働組合や労働者代表と制度の方針について協議 |
| ④ 社内通知・説明 | 制度の目的・内容を説明会などで労働者へ丁寧に共有 |
| ⑤ 応募の受付開始 | 募集期間は、一般的に2週間〜1か月程度。期間設定は状況に応じて柔軟に調整 |
| ⑥ 個別面談と承諾判断 | 応募者と面談し、企業側が承認の可否を最終判断 |
| ⑦ 退職処理と支援 | 退職手続きの実施、退職金支給、再就職支援の開始 |
募集期間は、おおむね2週間〜1か月が目安とされ、労働者が家族と将来を話し合う時間として確保されます。
準備工程(ステップ①~③)には通常1〜2週間程度を要し、その後の募集期間や退職対応を含めると、全体で(ステップ①〜⑦)1か月前後のスケジュールを見込むのが現実的です。
募集期間が短すぎると検討時間が不十分になり、逆に長すぎると社内の不安や業務への支障が生じやすくなります。制度の目的や対象者の状況に合わせた、適切な期間を見極めることが大切です。
希望退職の条件の設計

希望退職制度は、法的リスクを避け、労働者の納得を得ながら進めるために、条件や支援内容を丁寧に設計することが重要です。
実務で検討すべき主な4つのポイントは以下の通りです。
- 希望退職の退職金(割増退職金)の相場と設定基準
- 再就職支援サービスと活用できる助成金制度
- 有給休暇の買取対応と労働者への説明方法
- 退職金の支払いタイミングと運用ルールの明確化
これらについて、順番に詳しく解説します。
希望退職の退職金(割増退職金)の相場と設定基準
希望退職では、就業規則や退職金規程に基づく通常の退職金に加え、企業が自主的に設定する「割増退職金」を上乗せするケースが一般的です。
| 希望退職時の退職金総額=「通常退職金」+「割増退職金」 |
この加算金は法的に義務づけられているものではなく、企業ごとに自由に設計できるのが特徴です。ただし、実務では、以下のような水準がひとつの目安として挙げられることがあります。
【割増退職金の支給水準(※一例)】
- 経営に余裕があり、制度への納得感と応募意欲を高めたい場合:
月額給与の12〜24か月分
- 業績悪化など財務的に制約がある場合:
月額給与の3~6か月分
【割増退職金を設計する際の主な考慮要素】
- 勤続年数:長期勤続者への優遇
- 年齢:再就職が難しい高年齢者への配慮
- 職種・役職:代替が可能な人材に対して応募を促すための上乗せ対応
- 財務状況:企業体力とのバランスを考慮した支給額の設定
また、過去に実施した希望退職の加算金水準が、将来の人事施策における前例となる可能性がある点にも注意が必要です。
明確な相場があるわけではないため、他社事例や過去の社内事例を参考にしつつ、社労士などの専門家と連携しながら慎重に検討すると安心です。
再就職支援サービスと活用できる助成金制度
希望退職に応じた労働者に対し、企業が再就職支援を行うことは重要な配慮とされています。
特に高年齢層の場合、再就職が難航することも多く、スムーズなキャリア移行をサポートする体制づくりが望まれます。
企業が実施する主な支援策には、以下のようなものがあります。
- グループ会社などへの再配置
- 専門の再就職支援会社(アウトプレースメント※)の活用
※アウトプレースメントとは、企業が外部の再就職支援会社に委託し、退職予定者に対してキャリア支援や求人紹介などを行うサービスのことです。
このサービスの利用には、1人あたり50万〜100万円程度の費用がかかるとされており、多くの場合、企業が全額を負担します。
こうした負担を軽減する手段として有効なのが、厚生労働省の「早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)」です。この制度では、一定の要件を満たした企業に対して、再就職支援にかかる費用の一部が国から補助されます。
責任ある人員整理を進めたい企業にとって、経済的負担を抑えながら支援体制を整備できる有効な制度といえるでしょう。
有給休暇の買取対応と労働者への説明方法

希望退職を実施する際には、未消化の有給休暇をどのように扱うかをあらかじめ明確にし、対象者に丁寧な説明を行うことが求められます。
有給休暇は、本来「取得して休むこと」を前提とした制度であり、在職中の買取は労働基準法第39条の趣旨に反するとされています。
ただし、退職により有給休暇を取得する機会(実際に休暇を取ること)が失われる場合には、労働基準法の趣旨に反しない限りで例外的に買取が認められており、企業の判断で対応が行われています。希望退職の場合、多くの企業が自主的に買取を実施しているのが実情です。
具体的には、以下のような対応が一般的です。
- 取得可能な日数は、できる限り退職までに取得を促す
- 取得できない分については、一部または全日数を買い取る
- 買取方針を事前に明示し、対象者に説明・同意を得る
買取金額を巡るトラブルを避けるためには、あらかじめ就業規則などで以下のような算定方法を定めておくと安心です。
- 1日あたりの平均賃金を基準とする方法
- 就業規則で定めた定額方式
いずれの方法を採用する場合でも、計算根拠を明確にし、個別対応ではなく公平性を確保する姿勢が必要です。
また、業務の引き継ぎなどで有給取得が難しい場合には、労働者の実情に応じて柔軟に対応する姿勢が、信頼関係の維持にもつながります。
退職金の支払いタイミングと運用ルールの明確化
退職金の支払い時期は、希望退職制度を円滑に運用するうえで、企業が特に配慮すべき重要なポイントのひとつです。
退職後の生活設計に直結する要素であるため、労働者が安心して制度に応募できるよう、企業は「いつ・どのように支払うか」をあらかじめ明確に示す必要があります。
法令上は退職金の支払期限に明確な規定はありませんが、実務では以下のような対応が一般的です。
- 退職日の翌月末までに振込する
- 退職日当日または翌営業日に支給する
また、退職金は「退職所得」として扱われるため、支払い時には所得税の源泉徴収を行う必要があり、あわせて退職者に源泉徴収票を交付することも義務付けられています。
なお、退職後すぐに再就職先が見つからないケースも考えられるため、できる限り速やかに支給することが、企業にとっても信頼性を高める対応といえるでしょう。
希望退職に関するよくある質問

希望退職制度を導入する際は、制度設計だけでなく、退職予定者の疑問や不安に丁寧に答えることも重要です。
ここでは、現場でよく寄せられる代表的な質問とその対応ポイントをまとめました。
Q1|希望退職は「自己都合退職」?それとも「会社都合退職」?
希望退職は、企業が制度として募集を行い、それに応募した労働者が退職する形で実施されます。
この場合、離職証明書には「事業主からの働きかけによる退職」と記載され、会社都合退職として取り扱われるのが一般的です。
その結果、失業給付の給付制限期間が免除され、給付開始が早くなるなど、労働者にとって有利な取り扱いになります。
Q2|希望退職者にも賞与は支給される?
賞与の支給可否は、就業規則や賞与支給規定に基づいて判断されます。
退職者であっても、算定期間に在籍していれば支給対象となる場合があります。
ただし、多くの企業では「賞与支給日に在籍していること」を支給要件としているため、賞与支給日の前に退職した場合は、賞与は支給されないケースが一般的です。
支給の有無については、自社の規定を確認するとともに、企業は誤解などが生じないように事前に労働者に対して丁寧な説明を行いましょう。
Q3|希望退職時に有給休暇の買取はしてもらえる?
退職日までに有給休暇の取得が難しい場合には、未消化分を買い取る対応は多く見られます。
原則としては、未消化の有給休暇は退職日までに取得を促すことが基本です。ただし、業務の引き継ぎなどにより取得が困難な場合には、一部または全日数を企業が買い取る形で対応するケースもあります。
買取対応の基準や金額の算定方法は企業ごとに異なるため、事前に方針を明示し、対象者に説明と同意を得ておくことが重要です。
※この内容は本記事内「有給休暇の買取措置と説明対応」で詳しく解説しています。
まとめ|希望退職制度は制度設計と適切な支援で円滑に

本記事では、希望退職制度の概要からメリット・デメリット、導入手順や割増退職金の相場、さらに有給休暇の対応や再就職支援まで、導入時に押さえるべきポイントを整理して解説しました。
希望退職制度は、法令に則った対応だけでなく、労働者の納得と信頼を得ながら、円滑な人員再構成を進められる、比較的リスクの少ない選択肢です。
一方で、制度の設計や運用にあたっては、法的な理解・支援制度の整備・社内調整など、慎重な判断が求められる場面も少なくありません。
特に、割増退職金の支給条件や、再就職支援の設計、離職手続きに関する対応などに迷う場合には、社労士など専門家と相談して決めることで円滑に進められるでしょう。
希望退職制度について社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めた上で依頼しましょう。