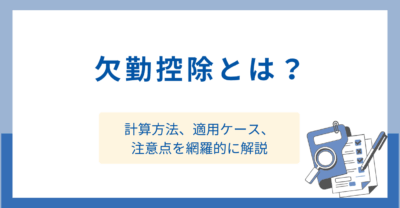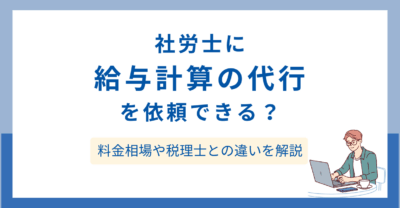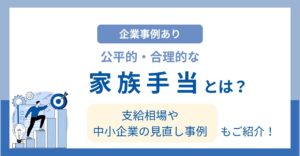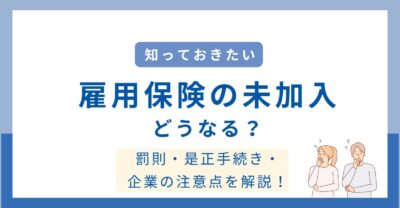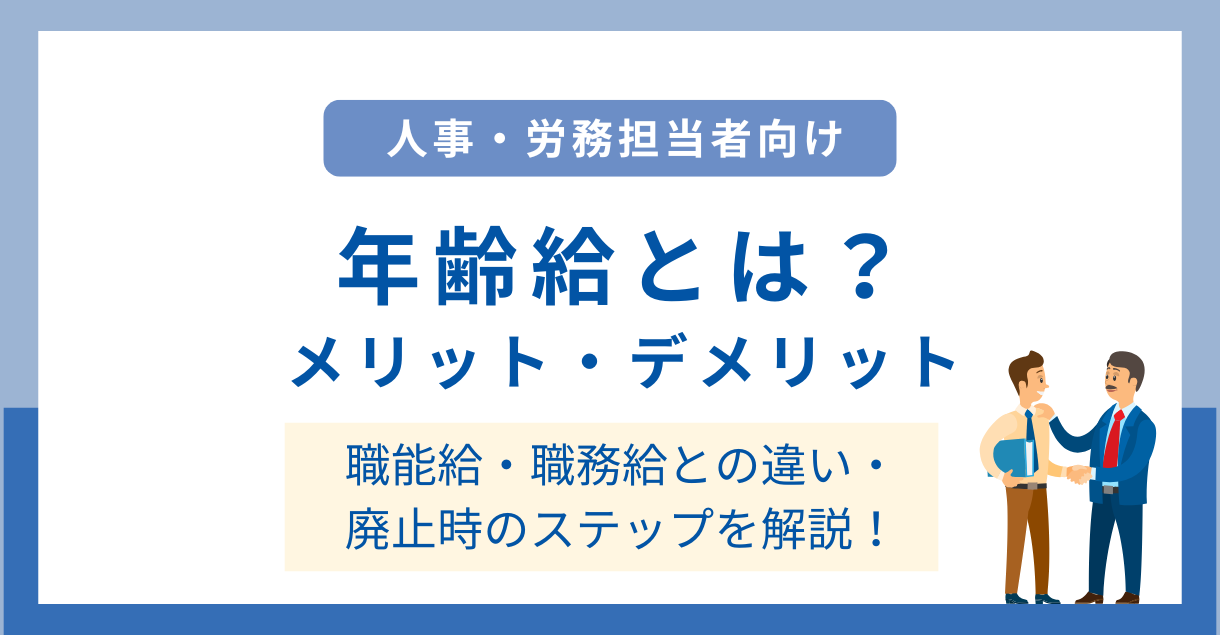
年齢給とは?メリット・デメリットや職能給・職務給との違いをわかりやすく解説!
年齢給とは、企業が労働者の年齢や勤続年数に応じて基本給を決定する社内の給与制度の一つです。法律で定められた制度ではありませんが、高度経済成長期には長期雇用を支える安定的な賃金体系として広く活用されてきました。
しかし近年は、人件費高騰や若手の離職を防ぐために成果主義や職務給への移行が進み、年齢給の見直しを検討する企業も少なくありません。
本記事では、年齢給の基本的な仕組みやメリット・デメリット、職能給・職務給・業績給との違いを解説します。さらに、人事・担当者向けに年齢給を廃止・変更する際の具体的なステップや注意点についてもわかりやすく整理しています。
自社の現状を見直し、将来に向けて最適な賃金制度を検討する際の参考として、ぜひ最後までご覧ください。
自社にぴったりの社労士が見つかる!
企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイト「社労士ナビ」は、地域や得意分野を指定して、自社のニーズに合った社労士を簡単に見つけられます。
年齢給とは?

年齢給とは、労働者の年齢・最終学歴の卒業年次・勤続年数などの属人的要素を基準に基本給を決定する賃金制度です。
つまり、年齢や勤続期間が長くなるほど自動的に昇給する仕組みです。
企業にとっては、長期雇用を前提とした給与設計がしやすく、労働者を計画的に育成・配置できるため、技術力の安定的な確保や人材の定着につながります。
また、労働者にとっても将来の収入が見通しやすくなります。年齢や勤続年数に応じて昇給する仕組みにより、結婚・住宅取得・子育てなどの生活設計を立てやすい点が特徴です。
年齢給が廃止・縮小傾向にある背景とは

年齢給は双方に利点がある賃金制度ですが、近年、年齢給を廃止または縮小する企業が増えています。
その背景には、以下のような理由が考えられます。
- バブル崩壊以降の企業業績の変動により、終身雇用を前提とした賃金体系が成り立ちづらくなったこと
- 労働市場の流動化に伴い若手社員の転職が一般化し、年齢を基準とした賃金体系では公平性を保ちにくくなったこと
- 同一労働同一賃金の考え方と、年齢や勤続年数で給与を決める年齢給の仕組みが一致しないこと
「同一労働同一賃金」とは、同じ仕事や責任の程度が同じなら、雇用形態にかかわらず同じ待遇を受けるべきという考え方です。一方、年齢給では年齢や勤続年数が基準となるため、仕事内容が同じでも給与に差が出やすいという構造的な問題があります。
また、政府は非正規を含むすべての労働者の生活を支えるため、最低賃金の引き上げや下請け価格への労務費反映など、社会全体で賃金の底上げを進めています。
こうした企業環境と社会の変化を受け、今後は「年齢」ではなく、職務内容や成果に応じた公正で説明可能な賃金制度が求められる傾向にあります。
年齢給のメリット・デメリット

年齢給は、労働者の長期勤続を促し、生活の安定を支える仕組みとして長く活用されてきました。一方で、働き方や評価の多様化が進むなか、従来の年齢給をそのまま維持するかどうかを見直す企業も増えています。
ここでは、年齢給の特徴を理解するために、そのメリットとデメリットを整理します。
年齢給のメリット
年齢給のメリットは以下のとおりです。
- 年齢を基準とするため、給与体系が分かりやすい
賃金テーブルが明確になり、労働者にも企業側にも理解しやすい仕組みです。 - 給与計算や人事管理が容易
年齢や勤続年数に基づくため、複雑な評価制度を設けなくても一定の整合性が保ちやすい特徴があります。 - ライフステージに応じた生活安定を支援できる
結婚・子育て・住宅取得などのタイミングで収入が増えるため、生活設計がしやすくなります。 - 労働者の長期勤続を促進する
勤続するほど給与が上がる仕組みは、定着率や忠誠心の向上につながります。 - 職務変更・配置転換が柔軟に行える
年齢が基準となるため、職務内容が変わっても賃金体系を大きく変更せずに運用しやすい点もポイントです。
年齢給は、「年齢とともに給与が上がる」シンプルな仕組みのため、制度設計や運用が容易で、労働者に安心感を与えやすい賃金制度です。
特に、長期雇用を前提とする企業においては、定着率の向上や人材の安定確保にもつながります。
年齢給のデメリット
一方で、現代の企業環境において、年齢給は以下のようなデメリットがあります。
- 仕事の内容と基本給が一致しない(同じ仕事内容でも年齢によって賃金が異なる)
若手の高スキル人材が正当に評価されにくく、年齢層によって処遇に差が生じる傾向があります。 - 業績や能力の向上と給与が結びつかない
成果主義ではないため、個人の努力や成果が給与に反映されづらい傾向にあります。 - 企業業績と無関係に人件費が増加する
高齢層が増えるにつれて給与総額が上昇し、企業の経営負担となる可能性があります。 - 平均年齢の上昇により人件費が膨らみ、若手層に不公平感が生じやすい
若手の昇給が抑制される構造となり、結果的に人材流出のリスクが高まります。 - 日本独自の制度であり、国際的な整合性が乏しい
成果・職務ベースの給与体系が主流の海外企業と比較し、グローバルな人事制度との整合性が取りづらい傾向があります。
このように、個人の成果や職務の内容にかかわらず賃金が決まるため、公平性を欠き、労働者のモチベーションを損なうリスクがあります。また、年齢構成の高齢化によって人件費が自動的に膨らみ、経営の柔軟性を損なう要因にもなりかねません。
このような背景から、多くの企業が「職能給」や「職務給」など、成果や職務内容に応じた柔軟な給与制度へ移行しつつあるのが現状です。
年齢給以外の「基本給」の給与制度とその違い

年齢給以外にも、基本給を決定する給与制度がいくつかあります。
ここでは、企業で広く採用されている 「職能給」「職務給」「業績給(成果主義型賃金)」 の特徴と、年齢給との主な違いを整理します。
職能給
職能給とは、労働者の「職務遂行能力(スキル・知識・経験など)」を基準に基本給を決定する給与制度です。
人事異動が行いやすく、労働者にさまざまな業務を経験させることでスキルの幅を広げやすい点が特徴です。その結果、複数の業務に対応できる人材を育成でき、企業の長期的な成長にもつながります。
ただし、勤続年数が長ければ職務遂行能力も高まると想定して設計されていることが多く、ポストが無くとも能力を元に基本給が決定されるため、高齢化によって人件費が膨らみやすく、結果的に年功的な運用になりやすいという課題があります。
年齢給との違いは、能力を基準にしている点です。運用次第で年齢給に似た課題が生じる点に注意が必要です。
職務給
職務給とは、労働者が担当する「職務の内容や責任の重さ」を基準に基本給を決定する給与制度です。
仕事の価値と基本給が一致しやすいのが特徴です。同様の職務経験を持つ人材を外部から採用しやすく、職務能力の向上コストがかからないメリットがあります。
一方で、職務内容が固定されるため他職種への人事異動が難しく、社内での能力開発や人材育成を促しにくいのがデメリットです。
年齢給に比べ職務内容と給与が連動しており、成果主義に近い考え方です。
業績給(成果主義型賃金)
業績給(成果主義型賃金)は、労働者が従事した「仕事の業績」を基準に基本給を決定する給与制度です。
仕事の成果と報酬が連動するため、労働者のモチベーション向上につながります。短期的には業績改善や生産性の向上が期待でき、企業全体の成果意識を高める効果があります。
一方で、チームでの協働や共同作業が必要な業務では成果の評価が難しく、個人間の競争が強まりすぎるリスクがあります。
年齢給と異なり、短期的な成果を評価する仕組みのため、安定よりも成果重視の企業に向いている給与制度です。
どの制度にも長所と短所があり、企業の規模・業種・評価方針によって適した形は異なります。年齢給から他の給与制度へ移行を検討する場合は、自社の人事戦略や育成方針、業務内容との整合性を見ながら、段階的な導入やハイブリッド型の制度設計を行うとよいでしょう。
年齢給を廃止・変更する際のステップ

年齢給は、給与規程として就業規則の一部に位置づけられる制度です。そのため、年齢給を廃止・変更する際には労働基準法に基づく正式な手続きを踏む必要があります。
特に、パート・アルバイトを含む労働者が常時10人以上いる事業場では、就業規則を作成または変更した場合に、労働基準監督署へ届出を行うことが義務づけられています(労働基準法第89条)。
また、給与制度など労働条件を変更する際には、変更後の労働条件を労働者に明示し書面で交付する必要があります。(労働基準法第15条、労働基準法施行規則5条)
ここでは、年齢給を見直す際の流れを4つのステップに分けて解説します。
ステップ1|年齢給の見直し方針と変更案を策定する
まずは、現在の年齢給制度の課題を整理し、見直しの目的と方向性を明確にします。
見直しを進める際は、以下の2点を特に意識して検討しましょう。
- 変更によって労働者に不利益が生じないか
- 最新の法改正や判例に対応しているか
これらを踏まえたうえで、職能給・職務給・業績給など、自社の方針や組織体制に合った給与制度案を具体的に検討していきます。
特に、労働者にとって不利益となる可能性がある場合には、「合理性のある理由」と「十分な説明・同意のプロセス」が求められます。裁判例においても、不利益変更に関しては厳しい判断が下される傾向があるため、慎重な対応が必要です。
ステップ2|労働者代表と協議し、意見書を作成する
賃金制度の変更は労働者の生活やモチベーションに大きく影響するため、十分な説明と協議が欠かせません。
一方的に制度を変更すると、不利益変更をめぐるトラブルや信頼関係の悪化につながるおそれがあります。そのため、年齢給の見直し案については、労働者代表や労働組合と協議を重ね、変更内容・目的・想定される影響を丁寧に共有することが重要です。
また、常時10人以上の労働者を使用する事業場が就業規則を変更して届ける際には、労働者代表の「意見書」の添付が義務づけられています(労働基準法第90条2項)。協議の内容や経緯は必ず記録に残し、申請にむけて適切に整理しておきましょう。
ステップ3|年齢給の変更を反映した就業規則を届け出る
年齢給の変更・廃止が決定した際は、企業はすみやかに所轄の労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
提出すべき書類は、以下の3点です。
- 就業規則(変更)届
- 労働者代表の意見書
- 変更後の就業規則の全文
「就業規則(変更)届」と「労働者代表の意見書」には、法定の統一様式は設けられていません。厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーなどで公開されている参考様式を活用すると便利です。
届出方法は、窓口・郵送・CD-ROMなどの電子媒体・電子申請(e-gov)のいずれにも対応しています。電子申請であれば24時間365日利用可能なため、忙しい担当者でも時間を選ばず手続きが可能です。
ステップ4|変更後の就業規則を労働者に周知する
就業規則の変更後は、労働者に対して内容を周知することが義務づけられています(労働基準法第106条)。
周知は、以下のいずれかの方法で行います。
- 常時、各作業場の見やすい場所に掲示または備え付ける
- 書面で交付する
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
単に掲示や交付をするだけでなく、労働者の理解を得ることが重要です。
制度変更の背景や目的を説明する場を設け、労働者の抱える疑問や不安を解消することで、労働者の理解と納得を得やすくなります。
賃金規定など、就業規則の変更に関する詳しい内容はこちらで詳しく解説しています。
>【完全版】就業規則の作成義務と届出方法|「常時10人以上」とは?
年齢給を廃止・変更する際のポイント

年齢給を廃止・変更する際は、給与計算の仕組みを変えるだけでなく、人事制度全体の見直しが必要です。
配慮や手続きを怠ると、労働者のモチベーション低下や法令違反などのリスクにつながるおそれがあります。
ここでは、実務担当者が押さえておくべき主な3つのポイントを整理します。
1、労働者への影響を把握し丁寧に説明する
年齢給を廃止すると、給与が下がる労働者が出る場合があります。
特に、年齢や勤続年数に応じて昇給している層には注意が必要です。不利益変更になる場合は、労働者の合意を得る必要があります(労働契約法第9条)。
変更による影響を事前にシミュレーションし、説明会や個別面談を通じて変更理由や新制度の狙いを丁寧に伝えましょう。仮に現行制度よりも賃金水準が下がる場合には、経過措置(例:一定期間の賃金維持など)を設けることで、労働者の不安を和らげることが可能です。
2、給与体系と評価制度の整合性を取る
新たな給与体系を導入する際は、評価の仕組みと賃金の決定方法を一致させることが重要です。
たとえば、「スキルや成長度を評価しているのに、給与は業績だけで決まる」ような不整合があると、労働者の納得感が得られにくい可能性があります。
評価基準・給与基準・昇給ルールを一体で設計し、職種や役割に応じた基準を明確にしておきましょう。
3、専門家と連携して法的リスクを抑える
給与制度変更には、就業規則の改定・労働基準監督署への届出・労働者への労働条件の明示など、複数の法的手続きが発生します。
届出内容に不備があると、是正勧告や不利益変更をめぐるトラブルに発展するリスクがあります。
法的リスクを最小限に抑えつつ、制度改定を正確に進められるほか、従業員説明資料の作成支援や、説明会対応に関する実務的なアドバイスも受けられます。
複雑な手続きを自社だけで抱え込まず、専門家のサポートを得ながら安心して制度変更を進めることが、最終的なトラブル防止と信頼構築につながります。
まとめ|年齢給の見直しには専門家の連携が安心です
本記事では、年齢給の仕組みやメリット・デメリット、職能給・職務給・業績給との違い、さらに廃止・変更のステップや変更時のポイントまでを解説しました。
年齢給を見直す際は、給与体系の再設計・労働者への説明・就業規則の改定など、慎重な対応が求められます。対応を誤ると、不利益変更をめぐるトラブルや労働者のモチベーション低下を招くおそれがあります。
こうしたリスクを回避し、公平性・柔軟性のある制度へスムーズに移行するためにも、制度設計の段階から社労士などの専門家との連携をおすすめします。
年齢給の見直しについて社労士に相談する
社労士を探す際には、全国6,000以上の事務所(全国の依頼可能な社労士の20%)の社労士が登録する、中小企業福祉事業団の「社労士ナビ」をご活用ください。
この企業と社労士をつなぐ日本最大級のポータルサイトでは、地域や得意分野などを指定して社労士を探せるので、自社のニーズに合った社労士が簡単に見つかります。
初回相談が無料の社労士も多いため、事務所のスタンスや人柄をしっかり見極めたうえで依頼しましょう。